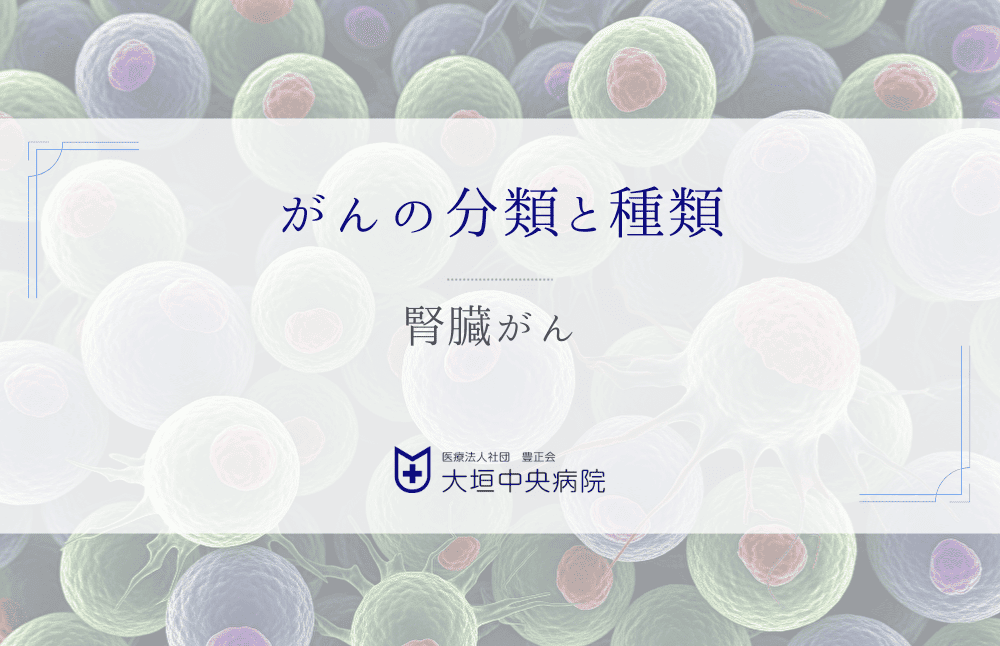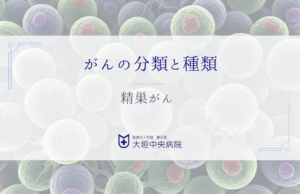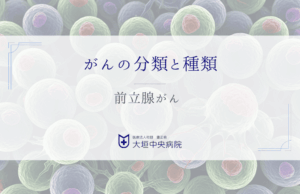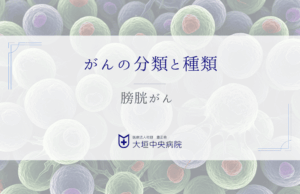腎臓がんと診断された方や、ご家族が腎臓がんの疑いがあると告げられた方々は、大きな不安の中にいることでしょう。
腎臓がんは初期の段階では自覚症状が乏しく、健康診断などで偶然発見されることも少なくありません。
しかし、病気について正しく理解し、ご自身の状況に合った適切な治療法を選択することが、より良い未来へとつながります。
この記事では、腎臓がんの基礎知識から、検査や診断、さまざまな治療法の選択肢、そして治療後の生活に至るまで、患者さんやご家族が知っておきたい大切な情報を網羅的に解説します。
腎臓がんの基本知識 – 発生の仕組みと特徴
私たちの体の健康を維持するために重要な役割を担う腎臓。ここに発生するがんは、どのような特徴を持つのでしょうか。まずは腎臓がんの基本的な事柄を理解することから始めましょう。
腎臓がんの大部分を占める「腎細胞がん」を中心に、その種類や発生の背景について解説します。
腎臓の働きとがんの発生
腎臓は、腰のやや上、背中側に左右一つずつある握りこぶしほどの大きさの臓器です。その主な働きは、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として体外に排泄することです。
その他にも、血圧を調整するホルモンや、赤血球を作るのを促すホルモンを分泌するなど、生命維持に欠かせない多様な機能を持っています。
腎臓がんは、この腎臓の細胞が何らかの原因でがん化し、無秩序に増殖することで発生します。
腎臓の主な機能
| 機能 | 説明 |
| 尿の生成 | 血液中の老廃物をこし取り、尿として排出する。 |
| 血圧の調整 | レニンというホルモンを分泌し、血圧をコントロールする。 |
| 赤血球産生の促進 | エリスロポエチンというホルモンを分泌し、骨髄に働きかけて赤血球の産生を促す。 |
腎細胞がんとは
腎臓にできるがんの約90%は、尿を作る細胞(尿細管上皮細胞)ががん化した「腎細胞がん」です。そのため、一般的に「腎臓がん」という場合、この腎細胞がんを指すことがほとんどです。
腎細胞がんは、がん細胞の見た目(組織型)によっていくつかの種類に分類され、それぞれ性質や進行の速さが異なります。
腎細胞がんの主な組織型
| 組織型 | 特徴 |
| 淡明細胞型腎細胞がん | 最も多く、全体の約70~80%を占める。血管が豊富で、薬物療法が比較的効きやすい。 |
| 乳頭状腎細胞がん | 全体の約10~15%を占める。比較的ゆっくり進行することが多い。 |
| 嫌色素性腎細胞がん | 全体の約5%を占める。他のタイプに比べて予後が良い傾向がある。 |
腎盂がんとの違い
腎臓には、腎細胞がんの他に「腎盂がん」という種類のがんも発生します。これは、腎臓で作られた尿が集まる「腎盂」という部分にできるがんです。
腎盂がんは、尿路上皮という細胞から発生するため、腎細胞がんとは性質が異なり、膀胱がんや尿管がんに近い仲間と位置づけられています。したがって、検査や治療の方針も腎細胞がんとは異なります。
腎臓がんの初期症状と発見のきっかけ
腎臓がんは「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」とも呼ばれるように、初期の段階では特有の症状がほとんど現れません。
がんがかなり進行してから症状が出ることが多いため、早期発見が難しいがんの一つです。ここでは、どのような症状に注意すべきか、そしてどのような経緯で発見されることが多いのかを解説します。
気づきにくい初期症状
がんが小さい初期の段階では、自覚できる症状はほぼありません。そのため、症状がないからといって安心はできません。
がんが進行して大きくなると、いくつかの特徴的な症状が現れることがあります。
腎臓がんの典型的な症状
- 血尿
- 腹部のしこり(腫瘤)
- わき腹や背中の痛み
これらの症状が3つともそろうことは比較的まれですが、いずれか一つでも気づいた場合は、速やかに泌尿器科を受診することが重要です。
特に血尿は、腎臓がんや膀胱がんなど、尿路系の病気における重要なサインとなります。
血尿は重要なサイン
血尿は、腎臓がんにおいて最も注意すべき症状の一つです。尿に血液が混じる状態で、目で見てわかる「肉眼的血尿」と、尿検査で初めてわかる「顕微鏡的血尿」があります。
血尿の種類と注意点
| 種類 | 特徴 |
| 肉眼的血尿 | 尿が赤や茶褐色に見える。痛みを伴わないことが多いのが特徴。 |
| 顕微鏡的血尿 | 見た目は正常だが、検査で赤血球が検出される。健康診断などで指摘されることが多い。 |
一度血尿が出ても、自然に止まってしまうことがあります。
しかし、それでがんが治ったわけではありません。症状が消えたからと安心せず、必ず専門医の診察を受けてください。
偶然見つかる「偶発がん」
近年、医療技術の進歩に伴い、腎臓がんは症状が出てから見つかるよりも、他の病気の検査や人間ドックなどで偶然発見される「偶発がん」の割合が増加しています。
腹部の超音波検査やCT検査を受けた際に、たまたま腎臓の異常が見つかるケースです。
このように偶然発見された腎臓がんは、比較的小さく、転移もない早期の段階であることが多いため、治療成績も良好な傾向にあります。定期的な健康診断がいかに大切かがわかります。
腎臓がんの検査方法と診断の流れ
腎臓にがんの疑いがある場合、正確な診断を下すためにいくつかの検査を行います。画像検査でがんの存在や広がりを確認し、最終的には病理診断で確定します。
ここでは、腎臓がんの診断に至るまでの一連の検査の流れを詳しく見ていきましょう。
診断の中心となる画像検査
腎臓がんの診断では、体の内部を画像化して調べる検査が中心的な役割を果たします。これらの検査によって、腫瘍の有無、大きさ、位置、そして他の臓器への転移の可能性などを評価します。
CT検査
CT検査は、X線を使って体の断面を撮影する検査で、腎臓がんの診断において最も重要な検査と位置づけられています。
多くの場合、造影剤という薬剤を腕の静脈から注射して撮影します。造影剤を使うことで、正常な腎臓の組織とがん組織との境界がより鮮明になり、腫瘍の血流の状態なども詳しくわかります。
これにより、腫瘍が良性か悪性(がん)かをおおよそ判断できます。また、肺や肝臓、リンパ節などへの転移の有無を調べる上でも、CT検査は非常に有用です。
超音波(エコー)検査
お腹の表面にゼリーを塗り、超音波を発する器具(プローブ)を当てて腎臓の状態を調べる、体に負担の少ない検査です。
健康診断などで最初に行われることが多く、腎臓の腫瘍の有無や、腫瘍の内部が液体(のう胞)か固形成分(固形腫瘍)かを見分けるのに役立ちます。
MRI検査
磁気と電波を使って体の内部を撮影する検査です。CT検査と同様に詳細な画像が得られます。
特に、CT検査で使う造影剤にアレルギーがある場合や、腎機能が低下している場合、あるいは腫瘍と周囲の血管との関係をより詳しく調べたい場合などに有用です。
腎臓がんの診断に用いられる主な検査
| 検査の種類 | 目的と特徴 |
| 超音波(エコー)検査 | 腫瘍の有無や性状(のう胞か固形か)を調べる。体に負担が少ない。 |
| CT検査 | 腫瘍の大きさ、位置、広がり、転移の有無を調べる。診断の中心的役割を担う。 |
| MRI検査 | CT検査を補完する目的や、造影剤が使えない場合に行う。 |
確定診断のための病理検査
画像検査で腎臓がんが強く疑われた場合でも、最終的な確定診断は、手術で摘出した腫瘍組織を顕微鏡で調べる「病理診断」によって下されます。
病理医ががん細胞の種類(組織型)や悪性度を詳しく調べることで、治療方針の決定や今後の見通しを立てる上で重要な情報が得られます。
多くの場合、手術によって腫瘍を摘出し、その組織を調べることで確定診断と治療を兼ねることになります。
病期(ステージ)分類と予後の関係
がんの診断がつくと、次に重要になるのが「病期(ステージ)」の決定です。
病期とは、がんがどのくらい進行しているかを示す指標のことで、治療方針を決定し、今後の見通し(予後)を予測する上で極めて重要です。
腎臓がんの病期分類と、それに関連する生存率について解説します。
がんの進行度を示すTNM分類
腎臓がんの病期は、国際的に用いられている「TNM分類」に基づいて決定します。これは、以下の3つの要素を組み合わせて評価する方法です。
- T因子(Tumor) 原発巣である腎臓の腫瘍の大きさや広がり
- N因子(Node) 周囲のリンパ節への転移の有無
- M因子(Metastasis) 他の臓器への遠隔転移の有無
これらのTNMの組み合わせによって、病期がステージⅠからステージⅣまでの4段階に分類されます。ステージの数字が大きくなるほど、がんが進行していることを意味します。
TNM分類の概要
| 因子 | 評価する内容 |
| T(原発腫瘍) | 腫瘍が腎臓内にとどまっているか、周囲の組織に広がっているか、その大きさはどれくらいか。 |
| N(所属リンパ節) | 腎臓の近くにあるリンパ節にがんが転移しているか。 |
| M(遠隔転移) | 肺、骨、肝臓など、腎臓から離れた臓器にがんが転移しているか。 |
ステージごとの状態
TNM分類を基にしたステージは、がんの進行度を具体的に示します。
- ステージⅠ がんが腎臓内にとどまっており、大きさが7cm以下。
- ステージⅡ がんが腎臓内にとどまっているが、大きさが7cmを超える。
- ステージⅢ がんが腎臓の近くの太い血管や周囲の脂肪組織に広がっている、または近くのリンパ節に転移がある。
- ステージⅣ がんが副腎など腎臓を包む膜を越えて広がっている、または肺や骨などの遠隔臓器に転移がある。
病期と生存率の関係
病期は、治療後の経過を予測するための重要な指標となります。一般的に、ステージが早い段階で発見され治療を開始するほど、生存率は高くなります。
生存率は、がんと診断されてから一定期間後(多くは5年後)に生存している人の割合を示すもので、「5年相対生存率」という指標がよく用いられます。
腎臓がんのステージ別5年相対生存率(目安)
| ステージ | 5年相対生存率 |
| Ⅰ | 95%以上 |
| Ⅱ | 約80-90% |
| Ⅲ | 約50-70% |
| Ⅳ | 約10-20% |
| 注:この数値はあくまで全国的な統計データに基づく目安であり、個々の患者さんの状態、治療法、年齢などによって大きく異なります。 |
大切なのは、これらの数字は過去のデータに基づく統計的な平均値であるということです。薬物療法の進歩などにより、治療成績は年々向上しています。
ご自身の詳しい見通しについては、担当医とよく話し合うことが重要です。
腎臓がんの治療選択肢 – 手術療法から薬物療法まで
腎臓がんの治療法は、がんのステージ、組織型、患者さんの全身状態や年齢、腎機能などを総合的に考慮して決定します。
転移のない限局性のがんであれば手術が治療の基本となり、転移がある進行がんでは薬物療法が中心となります。ここでは、主な治療法の選択肢について詳しく解説します。
治療の根幹をなす手術療法
転移のない限局性の腎臓がん(ステージⅠ~Ⅲ)に対しては、がんを完全に取り除くことを目指す手術療法が第一選択となります。
近年は、体への負担がより少ない低侵襲手術が主流になってきています。
腎部分切除術
がんが比較的小さく(主に4cm以下)、腎臓の端の方にある場合に検討される手術です。がんの部分だけを周囲の正常な組織を含めて切除し、できるだけ多くの腎臓の機能を温存することを目指します。
腎機能を温存することで、将来的な慢性腎臓病や心血管系の病気のリスクを低減させる効果が期待できます。
根治的腎摘除術
がんが大きい場合や、腎臓の中心近くにある場合など、部分切除が難しい場合に選択される手術です。がんのある側の腎臓を、副腎や周囲の脂肪組織、尿管の一部などと一緒にすべて摘出します。
片方の腎臓が正常であれば、残った腎臓が機能を補うため、日常生活に大きな支障が出ることは通常ありません。
手術の方法
手術には、お腹を大きく切開する「開腹手術」のほかに、お腹に数か所の小さな穴を開けてカメラや手術器具を挿入して行う「腹腔鏡手術」や、医師が3D画像を見ながらロボットアームを遠隔操作して行う「ロボット支援手術」があります。
後者二つは低侵襲手術と呼ばれ、傷が小さく、術後の痛みが少なく、回復が早いという利点があります。
主な手術方法の比較
| 手術方法 | 特徴 |
| 開腹手術 | 大きな傷で直接見て手術する。複雑な症例にも対応可能。 |
| 腹腔鏡手術 | 小さな傷で行う。術後の回復が早い。 |
| ロボット支援手術 | 精密な操作が可能で、特に腎部分切除術で有用性が高い。 |
進行がんに対する薬物療法
がんが発見された時点で既に他の臓器に転移している場合(ステージⅣ)や、手術後に再発・転移した場合、あるいは手術が困難な患者さんには、薬物療法が治療の中心となります。
腎細胞がんは、従来のがん化学療法(抗がん剤)や放射線治療が効きにくいという特徴がありましたが、近年、分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬の登場により、治療成績が飛躍的に向上しました。
分子標的薬
がん細胞の増殖や、がんが栄養を取り込むために作る新しい血管(血管新生)に関わる特定の分子(タンパク質や遺伝子)の働きをピンポイントで妨げる薬です。
正常な細胞への影響が比較的小さく、従来のがん化学療法に比べて副作用が少ないとされています。
免疫チェックポイント阻害薬
私たちの体には、がん細胞などの異物を攻撃する免疫機能が備わっています。がん細胞は、この免疫機能にブレーキをかけることで攻撃から逃れようとします。
免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞によってかけられた免疫のブレーキを解除し、患者さん自身が本来持っている免疫の力でがんを攻撃させる薬です。
薬物療法の種類と主な働き
| 薬物療法の種類 | 主な働き |
| 分子標的薬 | がんの増殖や血管新生に関わる分子を標的にして、がんの成長を抑える。 |
| 免疫チェックポイント阻害薬 | 免疫細胞のブレーキを外し、自身の免疫力でがんを攻撃する力を高める。 |
これらの薬は、単独で用いることもあれば、種類の違う薬を組み合わせて(併用療法)使うこともあります。
どの薬を選択するかは、がんの組織型やリスク分類、患者さんの全身状態などを基に慎重に判断します。
その他の局所療法
手術が困難な比較的小さな腎臓がんに対しては、ラジオ波やマイクロ波でがんを焼き切る「ラジオ波焼灼療法(RFA)」や、細い針を刺してがんを凍結させて死滅させる「凍結療法」といった、体に負担の少ない局所療法が選択されることもあります。
治療後の経過観察とフォローアップの重要性
腎臓がんの治療が終わった後も、安心して日常生活に戻るためには、定期的な経過観察(フォローアップ)がとても重要になります。
治療の効果を確認し、再発や転移を早期に発見するとともに、治療によって生じた可能性のある合併症や副作用に対応していくことが目的です。
なぜ定期的な検査が必要か
腎臓がんの治療、特に手術が無事に終了すると、ひとまずは安心ですが、残念ながら一定の確率で再発や転移が起こる可能性があります。
再発は、手術で取り除いた腎臓の周辺に再びがんが現れる「局所再発」と、肺や骨、肝臓など他の臓器にがんが現れる「遠隔転移」に分けられます。
再発したがんも、早期に発見できれば、薬物療法や場合によっては再度手術を行うなど、次の治療につなげることができます。
フォローアップで確認すること
- 再発・転移の有無
- 残った腎臓の機能
- 薬物療法の副作用の管理
- 全身状態のチェック
検査の頻度と内容
治療後のフォローアップで行う検査の内容や頻度は、がんのステージや組織型、行った治療法などによって異なりますが、一般的にはCT検査や超音波検査、胸部X線検査、血液検査などを定期的に組み合わせて行います。
治療後最初の数年間は、3か月から6か月に1回程度の頻度で検査を行い、その後は徐々に間隔をあけていくのが一般的です。
例えば、術後2年間は3~6か月ごと、3~5年目は6か月~1年ごと、それ以降は年1回といったスケジュールが組まれます。具体的な計画については、担当医と相談して決定します。
腎機能の維持と生活習慣
腎臓を一つ摘出した場合や、部分切除で腎臓の機能が低下した場合は、残った腎臓の機能を大切に維持していくことが重要です。
高血圧や糖尿病、脂質異常症などは腎機能に悪影響を与えるため、食事や運動など生活習慣を見直し、適切に管理していく必要があります。禁煙も腎機能保護の観点から非常に重要です。
日常生活で気をつけたいリスク要因
腎臓がんの発生原因は、まだ完全には解明されていません。しかし、これまでの多くの研究から、特定の生活習慣や病気が腎臓がんの発生リスクを高めることがわかってきています。
これらのリスク要因を知り、可能な範囲で避ける生活を心がけることが、予防の第一歩となります。
肥満との関連
複数の研究により、肥満が腎臓がんの明確なリスク要因であることが示されています。特に、ボディマス指数(BMI)が高いほど、リスクも高まる傾向にあります。
肥満は、ホルモンバランスの変化や慢性的な炎症を引き起こすことが、がんの発生に関与していると考えられています。
高血圧のリスク
高血圧も、腎臓がんの重要なリスク要因の一つです。長期間にわたって血圧が高い状態が続くと、腎臓の細い血管に負担がかかり、細胞が傷つくことでがん化につながる可能性が指摘されています。
高血圧の治療を適切に行うことが、リスクの低減につながります。
喫煙の危険性
喫煙は、肺がんだけでなく、腎臓がんを含む多くの種類のがんのリスクを高めることが確実視されています。
タバコの煙に含まれる多くの発がん性物質が、血液を介して全身を巡り、腎臓でろ過される際に腎臓の細胞を傷つけ、がんを引き起こすと考えられています。
喫煙量が多いほど、また喫煙期間が長いほどリスクは高まります。禁煙は、腎臓がんの予防において最も効果的な方法の一つです。
腎臓がんの主なリスク要因
- 肥満(高いBMI)
- 高血圧
- 喫煙
その他の要因
上記の他に、特定の鎮痛剤の長期的な乱用や、職業上で特定の化学物質(カドミウムやアスベストなど)にさらされること、透析を長期間受けていることなどもリスク要因として挙げられます。
また、ごく一部ですが、遺伝的な要因が強く関与する家族性の腎臓がんもあります。
腎臓がん患者さんが利用できる支援制度
がんの治療には、身体的、精神的な負担だけでなく、経済的な負担も伴います。治療に専念するためにも、利用できる社会的な支援制度について知っておくことは非常に大切です。
ここでは、腎臓がんの患者さんやご家族が活用できる可能性のある主な公的支援制度を紹介します。
経済的負担を軽減する制度
高額な医療費がかかった場合でも、自己負担額を一定限度額までに抑えることができる制度があります。
高額療養費制度
医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。上限額は、年齢や所得によって異なります。
事前に「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関の窓口に提示すれば、支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
傷病手当金
会社員や公務員などで健康保険に加入している方が、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
連続して3日間休んだ後の4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
その他の支援
治療や療養生活を支えるための様々な制度があります。
利用できる可能性のある公的支援制度の例
| 制度名 | 内容 |
| 障害年金 | 病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金。 |
| 介護保険サービス | 65歳以上の方、または40歳から64歳で特定疾病(がん末期など)の方が受けられる介護サービス。 |
| 医療費控除 | 1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に、確定申告を行うことで所得税が還付される制度。 |
相談窓口の活用
経済的な問題だけでなく、治療に関する不安や療養生活上の悩みなど、さまざまな相談に応じてもらえる窓口があります。
全国のがん診療連携拠点病院などに設置されている「がん相談支援センター」では、専門の相談員が患者さんやご家族からの相談に無料で対応しています。
一人で抱え込まず、こうした窓口を積極的に活用することが重要です。
よくある質問
腎臓がんについて、患者さんやご家族からよく寄せられる質問にお答えします。
- 腎臓を一つ摘出しても、日常生活に影響はありませんか?
-
はい、もう片方の腎臓の機能が正常であれば、日常生活に大きな影響が出ることはほとんどありません。残った腎臓が、摘出した腎臓の分まで働いて機能を補ってくれます。
これを「代償性肥大」と呼びます。ただし、残った腎臓に負担をかけないよう、高血圧や糖尿病の管理、塩分やタンパク質の過剰摂取を避けるといった生活上の注意は必要になります。
定期的に腎機能のチェックを受けることも大切です。
- 腎臓がんの治療中、食事で気をつけることはありますか?
-
治療法によって注意点が異なります。手術後は、体力の回復を助けるためにバランスの取れた食事を心がけることが基本です。
腎機能が低下している場合は、医師や管理栄養士の指導のもと、塩分やタンパク質の摂取量を調整することがあります。
薬物療法中は、副作用として吐き気や口内炎、下痢などが起こることがあるため、口当たりの良いものや消化しやすいものを選ぶなど、症状に合わせた工夫が必要です。
自己判断で極端な食事制限を行うことは避け、必ず医療スタッフに相談してください。
- 腎臓がんは遺伝しますか?
-
腎臓がんのほとんどは遺伝とは関係のない「散発性」のものです。しかし、ごく一部(全体の数%程度)に、遺伝的な要因が強く関与する「遺伝性(家族性)腎臓がん」が存在します。
フォン・ヒッペル・リンドウ(VHL)病などがその代表です。
若年で発症した場合や、両方の腎臓に多発性にがんができた場合、血縁者に腎臓がんの患者さんが複数いる場合などは、遺伝性腎臓がんの可能性も考えられるため、遺伝カウンセリングなどについて主治医に相談してみることをお勧めします。
この記事では腎臓がんについて解説しましたが、泌尿器系のがんには他にも注意すべき病気があります。
特に「膀胱がん」は、腎臓がんと同様に「痛みを伴わない肉眼的血尿」が最も多い初期症状として知られています。
尿を作る腎臓から、尿を溜める膀胱まで、尿の通り道(尿路)はつながっており、これらの臓器に発生するがんは共通の性質を持つこともあります。
腎臓がんについて理解を深めた今、同じく重要な泌尿器がんである膀胱がんについても知ることは、ご自身の健康を守る上で大変有意義です。
血尿という共通のサインを見逃さず、適切な対応をとるためにも、ぜひ膀胱がんに関する知識も深めておくことをお勧めします。
以上
参考文献
PEINEMANN, Frank, et al. Immunotherapy for metastatic renal cell carcinoma: A systematic review. Journal of Evidence‐Based Medicine, 2019, 12.4: 253-262.
COPPIN, Chris, et al. Targeted therapy for advanced renal cell cancer (RCC): a Cochrane systematic review of published randomised trials. BJU international, 2011, 108.10: 1556-1563.
WEI, Chao, et al. Efficacy of targeted therapy for advanced renal cell carcinoma: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. International braz j urol, 2018, 44.2: 219-237.
QUHAL, Fahad, et al. First-line immunotherapy-based combinations for metastatic renal cell carcinoma: a systematic review and network meta-analysis. European Urology Oncology, 2021, 4.5: 755-765.
POSADAS, Edwin M.; LIMVORASAK, Suwicha; FIGLIN, Robert A. Targeted therapies for renal cell carcinoma. Nature Reviews Nephrology, 2017, 13.8: 496-511.
LOMBARDI, Pasquale, et al. New first-line immunotherapy-based combinations for metastatic renal cell carcinoma: A systematic review and network meta-analysis. Cancer Treatment Reviews, 2022, 106: 102377.
LALANI, Aly-Khan A., et al. Systemic treatment of metastatic clear cell renal cell carcinoma in 2018: current paradigms, use of immunotherapy, and future directions. European urology, 2019, 75.1: 100-110.
MOTZER, Robert J.; BUKOWSKI, Ronald M. Targeted therapy for metastatic renal cell carcinoma. Journal of clinical oncology, 2006, 24.35: 5601-5608.
VERA-BADILLO, Francisco E., et al. Systemic therapy for non–clear cell renal cell carcinomas: a systematic review and meta-analysis. European urology, 2015, 67.4: 740-749.
KO, Jenny J., et al. The International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium model as a prognostic tool in patients with metastatic renal cell carcinoma previously treated with first-line targeted therapy: a population-based study. The lancet oncology, 2015, 16.3: 293-300.
泌尿生殖器系がんに戻る