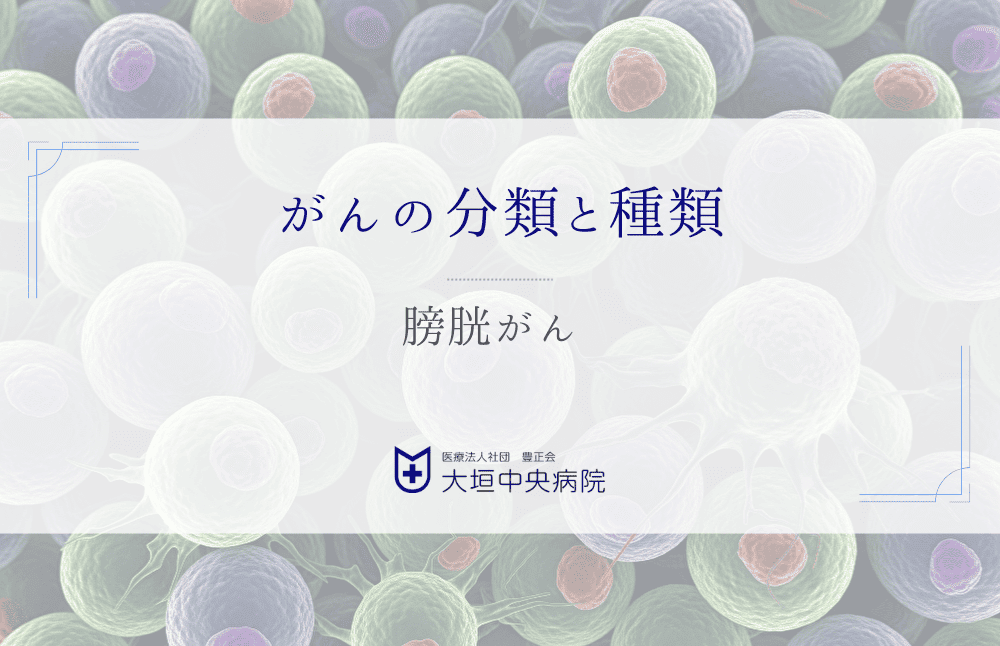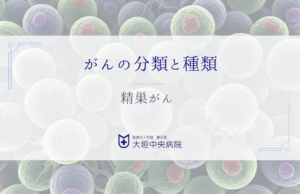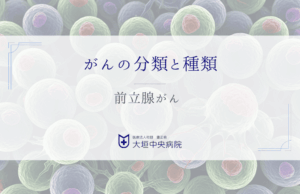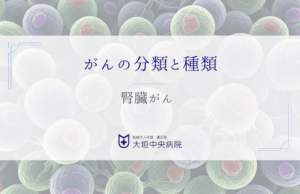ある日突然、尿に血が混じる「血尿」という症状に気づいたとき、多くの人が不安を感じるでしょう。血尿は、膀胱がんの最も重要なサインの一つです。
この記事では、膀胱がんという病気について、その症状や原因、検査、そして治療法に至るまで、患者さんやご家族が知っておくべき情報を詳しく解説します。
正しい知識を持つことは、病気と向き合い、納得のいく治療を選択するための第一歩です。ご自身の体からのメッセージを正しく理解し、治療への道筋を一緒に考えていきましょう。
膀胱がんの警告サイン – 血尿が教える重要なメッセージ
膀胱がんの発見のきっかけとして最も多いのが「血尿」です。
特に、痛みを伴わない血尿は、体が発する重要な警告サインと考え、決して軽視してはいけません。症状がないからといって放置せず、速やかに専門医の診察を受けることが、早期発見と治療成功の鍵を握ります。
ここでは、血尿の種類や、その他に注意すべき症状について詳しく見ていきます。
肉眼的血尿と顕微鏡的血尿
血尿には、目で見て明らかに色が赤いとわかる「肉眼的血尿」と、見た目ではわからないものの検査で初めて赤血球が発見される「顕微鏡的血尿」の2種類があります。
どちらも膀胱がんの可能性を示す重要な所見です。
見てわかる血尿の重要性
目で見てわかる肉眼的血尿は、膀胱がん患者さんの約85%が経験する初期症状です。尿の色は、鮮やかな赤色から、ピンク色、茶褐色まで様々です。特徴的なのは、痛みを伴わないことが多い点です。
また、血尿は一時的に止まることもありますが、自然に治ったわけではありません。一度でも肉眼的血尿を認めた場合は、症状が消えても必ず泌尿器科を受診してください。
健康診断で指摘される血尿
健康診断や人間ドックの尿検査で指摘されるのが顕微鏡的血尿です。自覚症状が全くないため、指摘されても実感が湧かないかもしれません。
しかし、症状がないからといって問題がないわけではありません。膀胱がんだけでなく、腎がんや尿管がんなど、他の泌尿器系の病気が隠れている可能性もあります。
精密検査を受けるよう指示があった場合は、必ず従いましょう。
血尿の種類と特徴
| 種類 | 特徴 | 考えられる原因 |
|---|---|---|
| 肉眼的血尿 | 目で見て尿の色が赤い、茶色いとわかる。痛みを伴わないことが多い。 | 膀胱がん、腎がん、尿路結石、膀胱炎など |
| 顕微鏡的血尿 | 見た目は正常だが、検査で尿中に赤血球が混じっている状態。 | 初期の膀胱がん、腎炎、前立腺の病気など |
血尿以外の膀胱がんの症状
血尿ほど多くはありませんが、膀胱がんが原因で他の症状が現れることもあります。これらの症状は膀胱炎など他の病気と似ているため、自己判断せずに専門医に相談することが重要です。
排尿時の痛みや頻尿
がんが膀胱の粘膜を刺激することで、排尿時の痛み、頻尿(トイレが近い)、残尿感(尿が残っている感じ)といった症状が出ることがあります。
これらの症状は急性膀胱炎とよく似ているため、特に女性では膀胱炎と診断され、抗生物質を処方されるケースも少なくありません。
薬を飲んでも症状が改善しない、または繰り返す場合は、膀胱がんの可能性も視野に入れた検査が必要です。
その他の注意すべき症状
がんが進行し、尿管の出口を塞いでしまうと、尿の流れが滞って腎臓が腫れる「水腎症」という状態になり、腰や背中に痛みを感じることがあります。
また、さらに進行して他の臓器への転移が起こると、転移した場所に応じた症状(例えば、骨転移による痛みや、リンパ節転移による足のむくみなど)が現れます。
これらの症状は、病気がかなり進行しているサインである可能性が高いです。
膀胱がんはなぜ起こるのか – 発生原因と危険因子
膀胱がんがなぜ発生するのか、その全てが解明されているわけではありません。しかし、長年の研究から、特定の生活習慣や環境が発症のリスクを高めることがわかっています。
これらの危険因子を知ることは、ご自身の状況を理解し、場合によってはリスクを減らす行動をとる助けになります。
膀胱がんの主な原因
膀胱がんの発生に強く関与していると考えられるのが、喫煙と化学物質への曝露です。
これらは、がんを引き起こす可能性のある物質が尿中に排泄され、膀胱の粘膜を長期間にわたって刺激することが原因と考えられています。
喫煙という最大のリスク
膀胱がんの危険因子の中で、最も確実で影響が大きいのが喫煙です。喫煙者は非喫煙者に比べて、膀胱がんになるリスクが2倍から4倍も高くなると報告されています。
タバコの煙に含まれる多くの発がん性物質が体内に吸収され、尿として排泄される際に膀胱の粘膜を傷つけ、がん細胞の発生を促します。
禁煙することで、そのリスクは時間とともに低下していきます。
職業上の化学物質への曝露
特定の化学物質を扱う職業に従事している、あるいは過去に従事していた人も、膀胱がんのリスクが高まることが知られています。
特に、染料や塗料、ゴム、皮革、化学薬品などを製造する工場で使われる「芳香族アミン」という物質は、強い発がん性を持つことがわかっています。
職業歴について医師に伝えることも、正確な診断のために重要です。
膀胱がんの主な危険因子
| 危険因子 | 内容 | リスクの目安 |
|---|---|---|
| 喫煙 | タバコの煙に含まれる発がん性物質が尿中に排泄される。 | 非喫煙者の2~4倍 |
| 化学物質 | 染料、塗料、ゴムなどに含まれる芳香族アミンへの職業的曝露。 | 曝露の程度による |
| 慢性的な刺激 | 繰り返す膀胱炎、尿路結石、カテーテルの長期留置など。 | リスクが上昇 |
その他の危険因子
喫煙や化学物質以外にも、膀胱がんの発症に関わるいくつかの因子が指摘されています。
年齢、性別、人種
膀胱がんは高齢者に多く、50歳代から増加し始め、70歳代でピークを迎えます。また、男性は女性に比べて約3倍かかりやすいとされています。
これは、男性に喫煙者が多いことや、職業性曝露の機会が多いことなどが一因と考えられています。人種的には、白人に多い傾向があります。
慢性的な膀胱の炎症や感染
長期間にわたって膀胱の粘膜が刺激にさらされることも、がんの発生につながる可能性があります。
具体的には、繰り返す細菌性の膀胱炎、膀胱結石、あるいは排尿障害のために尿道カテーテルを長期間留置している状態などが挙げられます。
これらの慢性的な炎症が、細胞の異常な増殖を引き起こす一因となるのです。
膀胱がんの種類と進行度による分類
膀胱がんと診断されたとき、治療方針を決めるために最も重要なのが、がんの「種類(組織型)」と「進行度(ステージ)」です。がんは一つの塊に見えても、その性質や広がり方は様々です。
これらを正確に評価することで、一人ひとりの患者さんに合った治療計画を立てることができます。
膀胱がんの組織型
膀胱がんは、がん細胞の見た目(顔つき)によっていくつかの種類に分類されます。これを組織型分類と呼びます。
最も多い尿路上皮がん
膀胱がんの90%以上を占めるのが「尿路上皮がん」です。これは、膀胱の内側を覆っている尿路上皮という粘膜から発生するがんです。
腎臓で作られた尿が通る道(腎盂、尿管、膀胱、尿道)はすべて尿路上皮で覆われているため、これらの場所に多発することもあります。
扁平上皮がんと腺がん
頻度は低いですが、尿路上皮がん以外にも「扁平上皮がん」や「腺がん」といった種類の膀胱がんがあります。扁平上皮がんは、慢性的な膀胱結石や感染による刺激が長期間続くことと関連が深いとされています。
腺がんは非常に稀ながんです。これらの特殊なタイプは、尿路上皮がんとは性質が異なり、治療法も変わることがあります。
がんの深達度による分類 – 筋層非浸潤がんと筋層浸潤がん
膀胱がんの治療を考える上で、組織型と同じくらい重要なのが、がんが膀胱の壁のどの深さまで達しているか(深達度)です。
膀胱の壁は、内側から粘膜、粘膜下層、筋層、漿膜(または脂肪組織)という層構造になっています。このうち、がんが筋層まで達しているかどうかで、治療法が大きく異なります。
筋層非浸潤性膀胱がん(表在性膀胱がん)
がんが膀胱の壁の浅い部分(粘膜または粘膜下層)にとどまっているものを「筋層非浸潤性膀胱がん」と呼びます。かつては「表在性膀胱がん」とも呼ばれていました。
膀胱がん全体の約70%がこのタイプで、転移の可能性は低いですが、膀胱内に再発しやすいという特徴があります。
筋層浸潤性膀胱がん
がんが膀胱の壁の深い部分にある筋層にまで達したものを「筋層浸潤性膀胱がん」と呼びます。このタイプは、がんが膀胱の外に広がりやすく、リンパ節や他の臓器へ転移する危険性が高くなります。
そのため、より強力な治療が必要になります。
膀胱がんの深達度による分類
| 分類 | がんの深さ | 特徴 |
|---|---|---|
| 筋層非浸潤がん | 粘膜、粘膜下層まで | 転移は稀だが、再発しやすい。 |
| 筋層浸潤がん | 筋層以上に達している | 転移のリスクが高く、強力な治療が必要。 |
膀胱がんのステージ分類と生存率
がんの進行度を客観的に示す指標が「ステージ」です。膀胱がんでは、国際的に用いられているTNM分類に基づいて決定します。
TNM分類によるステージ決定
TNM分類は、以下の3つの要素を組み合わせて総合的にステージを判断します。
- T因子: がんの深達度(膀胱の壁への広がり)
- N因子: 所属リンパ節(膀胱の近くにあるリンパ節)への転移の有無
- M因子: 遠隔転移(肺や肝臓、骨など離れた臓器への転移)の有無
これらの組み合わせにより、ステージは0期からⅣ期までに分類されます。ステージが上がるほど、がんが進行していることを意味します。
ステージごとの5年生存率の目安
生存率は、治療成績を示す指標の一つで、がんと診断されてから5年後に生存している人の割合を示します。
これはあくまで多くの患者さんのデータの平均値であり、個々の患者さんの余命を示すものではありません。治療法の進歩により、生存率は年々向上しています。
ご自身の詳しい状況については、主治医に確認することが大切です。
ステージ別5年生存率の目安
| ステージ | がんの状態 | 5年相対生存率(目安) |
|---|---|---|
| 0期、Ⅰ期 | がんが粘膜、粘膜下層にとどまる | 約90%以上 |
| Ⅱ期 | がんが筋層にとどまる | 約70% |
| Ⅲ期 | がんが膀胱壁を越えて広がる | 約50% |
| Ⅳ期 | リンパ節や他の臓器に転移がある | 約15% |
検査から診断まで – 膀胱鏡検査の役割と重要性
血尿などの症状で医療機関を受診すると、膀胱がんの可能性を調べるためにいくつかの検査を行います。
問診から始まり、尿検査、画像検査、そして最終的な診断を確定するための膀胱鏡検査へと進むのが一般的な流れです。ここでは、それぞれの検査がどのような目的で行われるのかを解説します。
膀胱がんが疑われた際の初期検査
まずは、体への負担が少ない検査から行い、がんの存在を示唆する所見がないかを確認します。
尿検査の重要性
尿検査は、最も基本的で重要な検査です。尿に血液が混じっていないか(尿潜血)を調べるだけでなく、「尿細胞診」という検査も行います。
これは、尿の中にがん細胞が剥がれ落ちていないかを顕微鏡で調べる検査です。悪性度の高い(顔つきの悪い)がんほど陽性になりやすい特徴があります。
超音波(エコー)検査
超音波検査は、お腹の表面からプローブという器具を当てて、膀胱や腎臓の内部を画像として映し出す検査です。痛みもなく、放射線被ばくの心配もありません。
膀胱内にできた腫瘍の大きさや形、腎臓が腫れていないか(水腎症の有無)などを確認することができます。
診断を確定する膀胱鏡検査
尿検査や超音波検査で膀胱がんが強く疑われた場合、診断を確定するために膀胱鏡検査を行います。これは、膀胱がんの診断において最も重要な検査です。
膀胱内を直接観察する
膀胱鏡検査は、尿道から細い内視鏡(膀胱鏡)を挿入し、膀胱の内部を直接モニターに映し出して観察する検査です。がんの有無、位置、大きさ、形、個数などを詳細に確認できます。
がんが疑われる部分があれば、その組織の一部を採取(生検)し、病理検査でがん細胞の有無や種類(組織型)、悪性度を確定診断します。
軟性膀胱鏡と硬性膀胱鏡
膀胱鏡には、胃カメラのように柔らかく曲がる「軟性膀胱鏡」と、硬い金属でできた「硬性膀胱鏡」があります。
外来での検査では、患者さんの苦痛が少ない軟性膀胱鏡を用いることが主流になっています。検査に伴う痛みや不快感を和らげるために、ゼリー状の麻酔薬を使用します。
膀胱がんの主な検査とその目的
| 検査名 | 検査方法 | 目的 |
|---|---|---|
| 尿検査(尿細胞診) | 尿を採取し、顕微鏡で調べる。 | 尿中の血液やがん細胞の有無を確認する。 |
| 超音波検査 | 腹部に超音波を当てて内部を観察する。 | 膀胱内の腫瘍や腎臓の状態を確認する。 |
| 膀胱鏡検査 | 尿道から内視鏡を挿入し、膀胱内を観察・生検する。 | がんを直接確認し、組織を採取して確定診断する。 |
| CT/MRI検査 | X線や磁気を使って体の断面を撮影する。 | がんの広がり(深達度)や転移の有無を評価する。 |
画像診断による進行度の評価
膀胱鏡検査で膀胱がんと診断が確定したら、次にがんの広がり(ステージ)を正確に評価するために、CT検査やMRI検査といった画像診断を行います。
これらの検査は、治療方針を決定する上で重要な情報をもたらします。
CT検査とMRI検査
CT検査はX線を、MRI検査は磁気を利用して体の断面を撮影する検査です。
がんが膀胱の壁のどの深さまで達しているか、膀胱の周囲の臓器へ広がっていないか、また肺や肝臓、リンパ節などへの遠隔転移がないかを詳細に調べることができます。
造影剤という薬を注射して撮影することで、より鮮明な画像を得ることができます。
膀胱がんの治療戦略 – 膀胱温存から全摘出まで
膀胱がんの治療法は、がんが筋層に達しているかどうか(筋層非浸潤性か筋層浸潤性か)によって大きく異なります。
また、がんの悪性度、個数、大きさ、そして患者さんご自身の年齢や全身状態、希望などを総合的に考慮して、最適な治療法を決定します。ここでは、主な治療戦略について解説します。
筋層非浸潤性膀胱がんの治療
がんが膀胱の壁の浅い部分にとどまっている筋層非浸潤性膀胱がんの治療の基本は、内視鏡を使った手術です。
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)は、尿道から電気メスが付いた内視鏡を挿入し、膀胱内の腫瘍を削り取る手術です。お腹を切る必要がなく、体への負担が少ないのが特徴です。
この手術は、がん組織を採取して正確な診断(深達度や悪性度)を確定するという「検査」の側面と、腫瘍を取り除くという「治療」の側面を併せ持っています。
多くの場合、この手術だけで治療が完了しますが、再発予防のために追加の治療が必要になることもあります。
筋層浸潤性膀胱がんの治療
がんが膀胱の筋層まで達している筋層浸潤性膀胱がんは、転移のリスクがあるため、より強力な治療が必要です。標準的な治療は、膀胱をすべて摘出する手術です。
膀胱全摘除術という選択
膀胱全摘除術は、がんを根治させる(完全に取り除く)ことを目的とした標準的な手術です。男性では膀胱と前立腺、精嚢を、女性では膀胱と子宮、膣の一部を摘出します。
また、転移の可能性があるため、骨盤内のリンパ節も同時に切除します(リンパ節郭清)。膀胱を摘出すると尿を溜める場所がなくなるため、尿の出口を新しく作る「尿路変更術」を同時に行います。
膀胱温存療法の可能性
患者さんの状態や希望によっては、膀胱を温存する(残す)治療法が選択できる場合もあります。これは、TURBTで可能な限り腫瘍を切除した上で、放射線治療と抗がん剤治療を組み合わせる方法です。
手術と同等の治療効果を目指しますが、すべての人に適応となるわけではありません。また、膀胱が残る一方で、再発のリスクや治療による副作用もあります。
どの治療法が良いかは、担当の医師と十分に話し合って決めることが重要です。
膀胱がんの進行度別治療法
| がんのタイプ | 主な治療法 | 治療の目的 |
|---|---|---|
| 筋層非浸潤がん | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 診断と治療、腫瘍の除去 |
| 筋層浸潤がん | 膀胱全摘除術 + 尿路変更術 | がんの根治 |
| 筋層浸潤がん | 膀胱温存療法(放射線+抗がん剤) | がんの根治と膀胱の温存 |
| 転移性膀胱がん | 薬物療法(抗がん剤、免疫チェックポイント阻害薬) | がんの進行を抑え、症状を和らげる |
進行・転移性膀胱がんの治療
診断時にすでに他の臓器への転移が見つかった場合や、手術後に再発・転移した場合は、全身に効果が及ぶ薬物療法が治療の中心となります。
全身に作用する薬物療法(抗がん剤治療)
抗がん剤を点滴で投与し、全身に散らばったがん細胞を攻撃します。複数の抗がん剤を組み合わせる多剤併用療法が一般的です。
近年では、従来の抗がん剤に加え、自身の免疫力を利用してがんと闘う「免疫チェックポイント阻害薬」や、特定のがん細胞の目印を狙い撃ちする「抗体薬物複合体」といった新しいタイプの薬も登場し、治療の選択肢が広がっています。
これらの薬物療法は、がんの進行を抑え、症状を和らげ、生存期間を延長させることを目的とします。
再発予防と膀胱内注入療法の実際
筋層非浸潤性膀胱がんは、TURBTで腫瘍をきれいに取り除いても、高い確率で膀胱内に再発することが知られています。そのため、TURBT後の再発予防が非常に重要になります。
その中心となるのが、膀胱内に直接薬剤を注入する「膀胱内注入療法」です。
なぜ再発予防が重要なのか
筋層非浸潤性膀胱がんは、その悪性度や個数によって異なりますが、治療後5年以内に40~70%の患者さんで再発すると言われています。
再発を繰り返すだけでなく、中には悪性度が高くなったり、筋層浸潤性がんへと進行したりするケースもあります。再発と進行を防ぎ、膀胱を守るために、リスクに応じた追加治療を行います。
膀胱内注入療法
TURBTで診断されたがんの悪性度や深達度に基づいて、再発リスクを低・中・高の3段階に分類し、リスクに応じた注入療法を検討します。
BCG(ウシ結核菌)注入療法
BCGは、もともと結核予防のワクチンとして使われている、毒性を弱めたウシ結核菌です。これを膀胱内に注入すると、体内の免疫細胞がBCGに反応して膀胱の壁に集まり、活性化します。
その結果、免疫の力でがん細胞を攻撃し、破壊するのです。特に再発リスクや進行リスクが高いタイプの筋層非浸潤性がんに対して、最も効果的な再発予防法とされています。
通常、週に1回、6~8週間にわたって行います。
BCG注入療法の主な副作用
- 頻尿、排尿時痛
- 血尿
- 発熱、倦怠感
- 関節痛
抗がん剤注入療法
抗がん剤を膀胱内に直接注入し、膀胱の粘膜に残っている可能性のある微小ながん細胞を死滅させる治療法です。BCG注入療法が適さない場合や、再発リスクが比較的低いと考えられる場合に選択されます。
TURBTの直後(24時間以内)に1回だけ行うこともあれば、BCGと同様に、週に1回の注入を数週間続けることもあります。BCGに比べて副作用は軽い傾向にあります。
治療後の生活の質を保つための工夫とケア
膀胱がんの治療を受けた後は、それまでとは体の状態が変化することがあります。特に膀胱をすべて摘出した場合は、排尿の方法が大きく変わります。
しかし、適切なケアや工夫によって、治療前と変わらない、あるいはそれ以上に充実した生活を送ることは十分に可能です。ここでは、生活の質(QOL)を保つためのポイントを解説します。
膀胱全摘除術後の生活
膀胱を摘出した後に行う尿路変更術には、いくつかの方法があります。どの方法を選択するかによって、その後の生活やケアの方法が異なります。
尿路変更(ストーマ)との付き合い方
最も一般的な尿路変更術は「回腸導管」です。これは、小腸の一部(回腸)を利用して尿の通り道を作り、お腹の表面に作った出口(ストーマ、またはウロストミー)から尿を排出する方法です。
ストーマにはパウチと呼ばれる袋を貼り付け、そこに溜まった尿を定期的に捨てます。ストーマのケアには専門的な知識が必要ですが、入院中に看護師から指導を受けます。
また、ストーマ外来や患者会など、退院後も相談できる窓口がたくさんあります。適切な装具を選び、正しいケアを身につければ、仕事や旅行、スポーツなども楽しめます。
新膀胱造設後の排尿管理
患者さんの状態によっては、「自排尿型新膀胱」という尿路変更術が可能な場合があります。これは、腸を使って新しい膀胱の形を作り、元々の尿道につなぎ直す方法です。
ストーマは必要なく、これまで通り尿道から排尿できるのが最大の利点です。ただし、尿意を感じなくなるため、時間を決めて腹圧をかけて排尿する訓練が必要です。
また、夜間の尿失禁や、尿が完全に出し切れずに残ってしまう(残尿)といった問題が起こることもあります。
主な尿路変更術の種類と特徴
| 尿路変更術 | 特徴 | 管理のポイント |
|---|---|---|
| 回腸導管(ストーマ) | 腹部にストーマを作成し、パウチに尿を溜める。最も標準的な方法。 | 装具の交換、皮膚のケア。 |
| 自排尿型新膀胱 | 腸で新しい膀胱を作り、尿道につなぐ。ストーマが不要。 | 定時排尿の習慣づけ、残尿管理。 |
治療後の食事と栄養管理
「がんに効く特別な食事」というものは、科学的には証明されていません。治療後の回復を促し、体力を維持するためには、特定の食品に偏ることなく、バランスの取れた食事を心がけることが基本です。
バランスの取れた食事の基本
主食・主菜・副菜をそろえ、様々な食材から栄養を摂ることが大切です。
抗がん剤治療の副作用で食欲がないときや、腸を使った尿路変更術の後は、消化の良いものを少量ずつ、回数を分けて食べるなどの工夫をしましょう。
水分を十分に摂ることも、尿路感染の予防などの観点から重要です。食事について不安なことがあれば、医師や看護師、管理栄養士に相談してください。
心のケアと情報収集
がんと診断されたことや、治療による体の変化は、大きな不安やストレスの原因となります。一人で抱え込まず、信頼できる人に気持ちを話したり、専門家の助けを借りたりすることが大切です。
不安との向き合い方と相談窓口
多くの病院には、がん患者さんやその家族の様々な相談に応じる「がん相談支援センター」が設置されています。
療養生活のこと、医療費のこと、仕事のことなど、誰に相談してよいかわからない悩みを、専門の相談員が一緒に考えてくれます。
また、同じ病気を経験した仲間と語り合う患者会も、心の支えになることがあります。
信頼できる情報の見つけ方
インターネット上には、闘病体験を綴ったブログなど、様々な情報が溢れています。同じ病気の人の体験談は励みになる一方で、中には科学的根拠のない情報や、特定の治療法を過度に推奨するものもあります。
情報はあくまで参考とし、ご自身の治療については、主治医とよく話し合って決めることが最も重要です。
いわゆる「名医」探しに固執するよりも、ご自身の状況をよく理解し、何でも相談できる信頼関係を築ける医師を見つけることが、納得のいく治療につながります。
定期検査が膀胱がん管理の鍵となる理由
膀胱がんの治療が無事に終了した後も、それで終わりではありません。
膀胱がんは、治療した場所に再発したり、あるいは膀胱内の別の場所に新しく発生したりすることがあるため、長期にわたる定期的な検査(フォローアップ)が極めて重要です。
これにより、万が一の再発を早期に発見し、速やかに対応することができます。
治療後のフォローアップ計画
治療後の定期検査のスケジュールや内容は、最初のがんのステージや悪性度、治療法によって異なります。主治医が、個々の患者さんのリスクに応じたフォローアップ計画を立てます。
定期検査のスケジュール
一般的に、治療後最初の2年間は3~6ヶ月ごと、その後3~5年目までは6ヶ月~1年ごと、5年目以降は年1回、といった間隔で検査を行います。
これはあくまで目安であり、再発リスクが高いと判断された場合は、より頻繁な検査が必要になることもあります。
検査内容とその目的
定期検査では、治療前に行った検査を繰り返し行います。尿検査(尿細胞診)で尿に異常がないかを確認し、膀胱鏡検査で膀胱内を直接観察して再発の有無をチェックします。
これがフォローアップの基本です。必要に応じて、CT検査などの画像検査を行い、膀胱以外の尿路(腎盂、尿管)や、他の臓器への転移がないかも確認します。
自己管理と体調変化への注意
定期検査と合わせて、患者さん自身の自己管理も大切です。日々の生活の中で、ご自身の体の変化に気を配ることが、再発の早期発見につながります。
日常生活で気をつけること
最も注意すべきサインは、やはり「血尿」です。治療後に再び肉眼的血尿が出た場合や、排尿時の痛み、頻尿などの症状が現れた場合は、次の予約を待たずに、すぐに医療機関に連絡してください。
また、禁煙を継続することも、再発リスクを下げるために非常に重要です。
医師との連携の重要性
治療後の長い期間、不安を感じることもあるでしょう。定期検査は、体の状態を確認するだけでなく、医師や看護師と会い、疑問や不安を相談する良い機会でもあります。
自己判断で通院をやめてしまうことなく、決められたスケジュールで検査を受け続けることが、長期的な安心につながります。
医師との信頼関係を保ち、二人三脚で病気を管理していくという意識が大切です。
よくある質問
- 膀胱がんの名医はどのように探せばよいですか?
-
「名医」の定義は人それぞれですが、一般的には経験豊富な専門医を指すことが多いでしょう。
病院のウェブサイトで医師の専門分野や実績(手術件数など)を確認したり、日本泌尿器科学会が認定する「泌尿器科専門医・指導医」であるかを参考にしたりする方法があります。
しかし、最も重要なのは、患者さん自身がその医師を信頼し、何でも相談できると感じられるかどうかです。
セカンドオピニオン制度を利用して、複数の医師の意見を聞いてみるのも良いでしょう。
- 治療中の食事で特に気をつけることはありますか?
-
膀胱がんの治療において、「これを食べれば治る」「これは食べてはいけない」といった特別な食品はありません。基本は、栄養バランスの取れた食事を心がけることです。
抗がん剤治療中は、副作用で吐き気や口内炎が起こり、食事が摂りにくくなることがあります。その際は、無理せず食べられるものを、消化の良い調理法で少量ずつ摂るように工夫しましょう。
水分摂取は、脱水や尿路感染の予防のために重要ですので、こまめに摂るようにしてください。
- 膀胱がんの患者さんのブログは参考にしても良いですか?
-
同じ病気を経験した方の闘病記やブログは、情報収集だけでなく、精神的な支えや共感を得る上で役立つことがあります。
しかし、治療の経過や副作用の出方、生活への影響は、がんのステージや個人の体力などによって千差万別です。他人の体験が必ずしも自分に当てはまるとは限りません。
あくまで一つの参考情報として捉え、治療方針など重要な事柄については、必ずご自身の主治医と相談して決定してください。
- 膀胱を全部取った後の生存率はどうなりますか?
-
膀胱全摘除術を受けた後の生存率は、手術を受けた時点でのがんのステージに大きく左右されます。
がんが膀胱の筋層にとどまっており、リンパ節や他の臓器への転移がない段階(ステージⅡなど)で手術を受ければ、根治(がんが完全になくなること)が期待でき、良好な長期生存率が見込めます。
一方で、すでに膀胱の壁を越えていたり、リンパ節転移があったりする(ステージⅢ以上)場合は、再発のリスクが高くなります。
生存率はあくまで統計データであり、個々の患者さんの見通しは異なりますので、主治医から直接説明を受けることが大切です。
膀胱がんと同じく、泌尿器科が扱う代表的ながんに「前立腺がん」があります。特に中高年の男性にとっては、いずれも注意が必要な病気です。
膀胱がんの主な初期症状が「血尿」であるのに対し、前立腺がんは初期には自覚症状がほとんどなく、進行すると排尿困難や頻尿といった症状が現れます。
検査方法も異なり、前立腺がんは血液検査(PSA検査)が発見のきっかけとなることが多いのが特徴です。
ご自身の健康状態をより深く理解するために、前立腺がんに関する情報もあわせてご覧になることをお勧めします。
以上
参考文献
THIEL, Tomas, et al. Intravesical BCG treatment causes a long-lasting reduction of recurrence and progression in patients with high-risk non-muscle-invasive bladder cancer. World journal of urology, 2019, 37.1: 155-163.
FRIEDRICH, Martin G., et al. Long-term intravesical adjuvant chemotherapy further reduces recurrence rate compared with short-term intravesical chemotherapy and short-term therapy with bacillus Calmette-Guérin (BCG) in patients with non–muscle-invasive bladder carcinoma. European urology, 2007, 52.4: 1123-1130.
BALASUBRAMANIAN, Adithya, et al. Adjuvant therapies for non-muscle-invasive bladder cancer: advances during BCG shortage. World Journal of Urology, 2022, 40.5: 1111-1124.
WEIZER, Alon Z.; TALLMAN, Christopher; MONTGOMERY, Jeffrey S. Long-term outcomes of intravesical therapy for non-muscle invasive bladder cancer. World journal of urology, 2011, 29.1: 59-71.
LAUKHTINA, Ekaterina, et al. Intravesical therapy in patients with intermediate-risk non–muscle-invasive bladder cancer: a systematic review and network meta-analysis of disease recurrence. European urology focus, 2022, 8.2: 447-456.
LIU, Zheng, et al. Thulium laser resection of bladder tumors vs. conventional transurethral resection of bladder tumors for intermediate and high risk non-muscle-invasive bladder cancer followed by intravesical BCG immunotherapy. Frontiers in Surgery, 2021, 8: 759487.
LAUDANO, Melissa A., et al. Long-term clinical outcomes of a phase I trial of intravesical docetaxel in the management of non–muscle-invasive bladder cancer refractory to standard intravesical therapy. Urology, 2010, 75.1: 134-137.
DEL GIUDICE, Francesco, et al. Compared efficacy of adjuvant intravesical BCG-TICE vs. BCG-RIVM for high-risk non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC): a propensity score matched analysis. Cancers, 2022, 14.4: 887.
CHOU, Roger, et al. Intravesical therapy for the treatment of nonmuscle invasive bladder cancer: a systematic review and meta-analysis. The Journal of urology, 2017, 197.5: 1189-1199.
泌尿生殖器系がんに戻る