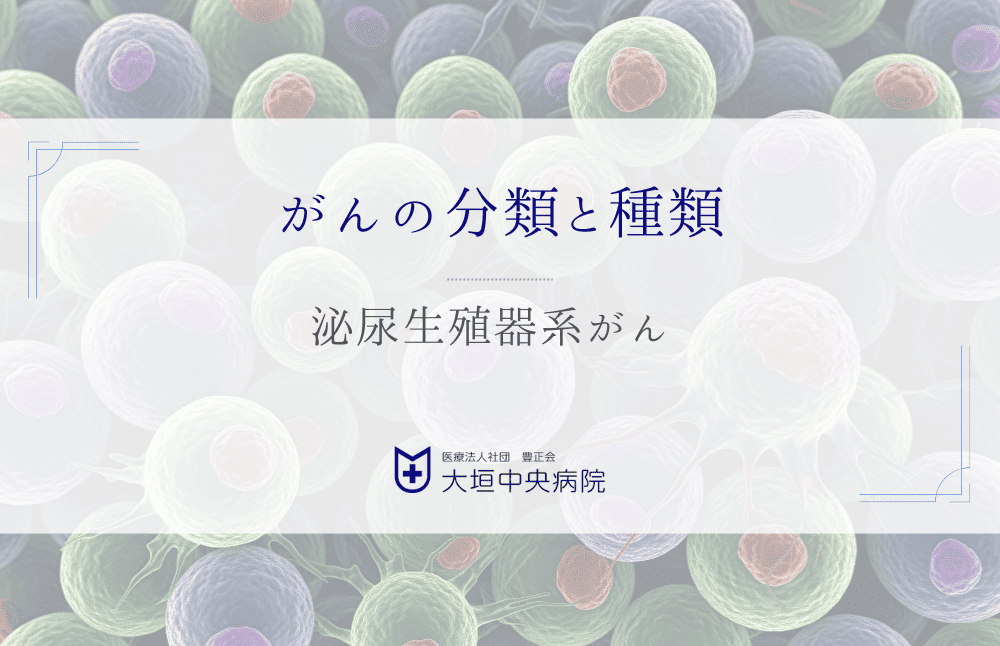泌尿生殖器系のがんは、尿を生成し排泄する臓器(腎臓、尿管、膀胱、尿道)や、男性の生殖に関わる臓器(前立腺、精巣)に発生する悪性腫瘍の総称です。
これらのがんは、発生する部位によって性質や症状、治療法が大きく異なります。高齢化に伴い、特に前立腺がんの患者数は増加傾向にあります。
一方で、精巣がんのように若い世代に多いがんも存在します。がんと向き合う上で、ご自身の体の状態を正しく知ることはとても重要です。
このページでは、代表的な泌尿生殖器系のがんである「腎がん」「膀胱がん」「前立腺がん」「精巣がん」について、それぞれの特徴や検査、治療の選択肢を分かりやすく解説します。
腎がん
腎臓は、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として体外に排出する重要な役割を担う臓器です。腎がんは、この腎臓の細胞ががん化したもので、多くは腎実質の尿細管という部分から発生します。
早期の段階では自覚症状がほとんどなく、健康診断や他の病気の検査で偶然見つかるケースが少なくありません。ここでは、腎がんの基本的な知識から検査、治療法までを詳しく見ていきます。
腎がんとは
腎がんは、腎臓に発生する悪性腫瘍です。かつては発見が難しいがんでしたが、近年は超音波(エコー)検査やCT検査などの画像診断技術の向上で、小さなうちに見つかることが増えました。
腎臓の働きとがんの発生
腎臓は背中側の腰の上あたりに左右一つずつある、そら豆のような形をした臓器です。
主な働きは、体内の水分バランスの調整、血液中の老廃物の除去、血圧のコントロール、赤血球を作るホルモンの分泌など、生命維持に欠かせない機能を持ちます。
腎がんの多くは、この腎臓の細胞が異常に増殖して発生します。喫煙や肥満、高血圧などが、発生のリスクを高める要因として知られています。
腎がんの種類
腎がんは、組織型によっていくつかの種類に分類されます。最も多いのが「淡明細胞型腎細胞がん」で、全体の70-80%を占めます。
その他、乳頭状腎細胞がん、嫌色素性腎細胞がんなどがあり、種類によってがんの性質や進行の速さが異なります。正確な組織型は、手術で摘出した組織を病理検査で調べることで確定します。
症状
腎がんは「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」とも呼ばれることがあるように、初期には特有の症状が現れにくいのが特徴です。
がんが大きくなるにつれて、様々なサインが現れるようになります。
初期症状
早期の腎がんでは、ほとんど症状がありません。そのため、人間ドックの腹部超音波検査などで偶然発見されることが、早期発見の重要なきっかけとなります。
症状がないからといって安心せず、定期的な健康診断を受けることが大切です。
進行した場合の症状
がんが進行すると、血尿、腹部のしこり、わき腹や背中の痛みが三大症状として現れることがあります。ただし、この三つの症状がすべてそろうケースは多くありません。
その他、原因不明の発熱、食欲不振、体重減少、貧血といった全身症状が見られることもあります。これらの症状に気づいた場合は、速やかに泌尿器科を受診してください。
検査と診断
腎がんが疑われる場合、いくつかの検査を組み合わせて診断を進めます。画像診断でがんの存在や広がりを確認し、最終的に病理診断で確定します。
画像診断
超音波(エコー)検査は、体に負担が少なく、腎臓の腫瘍の有無を手軽に調べられる検査です。ここで異常が見つかった場合、より詳しく調べるためにCT検査やMRI検査を行います。
これらの検査は、腫瘍の大きさや位置、性質、リンパ節や他の臓器への転移の有無を評価するために非常に有用な情報を提供します。
確定診断の方法
画像診断で腎がんが強く疑われる場合、多くは手術で腫瘍を摘出し、その組織を顕微鏡で調べる病理診断によって確定診断とします。
小さな腫瘍で診断が難しい場合などには、体の外から針を刺して組織の一部を採取する「生検」を行うこともあります。
腎がんの進行度
治療方針を決める上で、がんがどの程度進行しているかを正確に評価することが重要です。
進行度は、がんの大きさ(T)、リンパ節への転移(N)、他の臓器への遠隔転移(M)を組み合わせたTNM分類を用いて、ステージIからIVの4段階に分けます。
| ステージ | がんの状態 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| I | がんが腎臓内にとどまり、大きさが7cm以下 | 早期の段階で、転移は見られない。 |
| II | がんが腎臓内にとどまり、大きさが7cmを超える | がんは大きくなっているが、まだ腎臓内にある。 |
| III | がんが腎臓の主要な静脈や周囲の脂肪組織に及ぶ、または所属リンパ節に転移がある | がんが腎臓の周囲に広がり始めている状態。 |
| IV | がんが腎臓を越えて隣接する臓器に及ぶ、または遠隔転移がある | 肺や骨など、腎臓から離れた臓器に転移している。 |
治療法
腎がんの治療は、がんの進行度や種類、患者さんの全身状態を総合的に判断して決定します。主な治療法には手術、薬物療法、放射線治療があります。
手術療法
転移のない腎がんに対する基本的な治療は手術です。手術には、がんを含めて腎臓をすべて摘出する「根治的腎摘除術」と、がんの部分だけを切り取る「腎部分切除術(腎温存手術)」があります。
近年は、比較的小さながんに対しては、腎臓の機能をできるだけ温存するために腎部分切除術を積極的に行います。
手術の方法も、開腹手術のほか、体の負担が少ない腹腔鏡手術やロボット支援手術が広く普及しています。
薬物療法
手術で取りきれないほど進行した場合や、遠隔転移がある場合には薬物療法を選択します。腎がんの薬物療法は近年大きく進歩しました。
がん細胞の増殖に関わる分子を標的とする「分子標的薬」や、自身の免疫力を高めてがんを攻撃する「免疫チェックポイント阻害薬」が治療の中心です。
これらの薬剤を単独、あるいは組み合わせて使用します。
放射線治療
腎がんの原発巣(腎臓自体のがん)に対して放射線治療が効きにくい場合が多いため、主な治療法とはなりません。
しかし、骨や脳への転移による痛みを和らげる目的(緩和的治療)で放射線治療を行うことがあります。
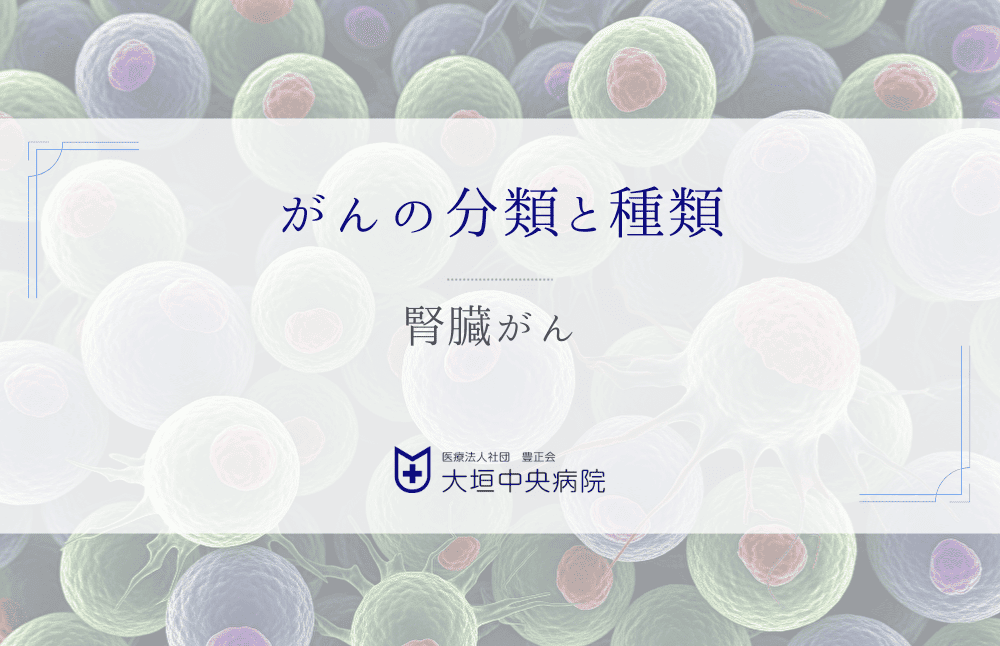
膀胱がん
膀胱は、腎臓で作られた尿を一時的に溜めておく袋状の臓器です。膀胱がんは、この膀胱の内側を覆う尿路上皮という粘膜から発生することがほとんどです。
初期症状として血尿が出ることが多く、比較的早期に発見されやすいがんの一つです。しかし、再発しやすいという特徴も持っています。ここでは膀胱がんの性質や検査、治療について解説します。
膀胱がんとは
膀胱がんは泌尿器系のがんの中では前立腺がんに次いで多く、特に高齢の男性に多い傾向があります。喫煙が最大の危険因子とされています。
膀胱の構造とがんの発生
膀胱は骨盤の中にあり、筋肉でできた伸縮性のある臓器です。内側は尿路上皮という粘膜で覆われています。膀胱がんの90%以上が、この尿路上皮から発生する「尿路上皮がん」です。
がんは膀胱の壁の内部へと深く進行していくことがあります。
膀胱がんの性質
膀胱がんは、がんが膀胱の壁のどの深さまで達しているかによって、大きく二つのタイプに分けられます。一つは、膀胱の表面の粘膜内にとどまっている「筋層非浸潤性膀胱がん」です。
もう一つは、粘膜を越えて膀胱の筋層まで達している「筋層浸潤性膀胱がん」です。この二つは進行度や治療法が大きく異なるため、正確な診断が重要です。
主な症状
膀胱がんの最も代表的な症状は血尿です。痛みなどを伴わないことが多いため、注意が必要です。
血尿
膀胱がんの初期症状として最も多いのが、痛みを伴わない「無症候性肉眼的血尿」です。これは、尿が赤や茶色になるなど、目で見て血液が混じっていると分かる状態を指します。
血尿は出たり出なかったりすることもあるため、一度でも血尿に気づいたら、すぐに泌尿器科を受診することが大切です。
排尿時の痛みや頻尿
がんが大きくなったり、膀胱炎を併発したりすると、排尿時の痛み、頻尿、残尿感といった症状が現れることがあります。
これらの症状は膀胱炎と似ているため、抗生物質を服用しても改善しない場合は、膀胱がんの可能性を考えて詳しい検査を行います。
検査と診断
血尿などの症状から膀胱がんが疑われた場合、尿検査や内視鏡検査で詳しく調べます。
尿検査
尿の中に血液が混じっていないか(尿潜血)、がん細胞が剥がれ落ちていないか(尿細胞診)を調べます。尿細胞診は、がんの有無を調べる上で有用な検査ですが、この検査だけで確定診断はできません。
膀胱鏡検査
診断を確定するために最も重要な検査が膀胱鏡検査(膀胱ファイバースコープ)です。尿道から細い内視鏡を挿入し、膀胱の内部を直接観察します。
がんの有無、位置、大きさ、形などを確認し、疑わしい部分があれば組織の一部を採取して病理検査に出します。
画像検査による進行度の評価
CT検査やMRI検査は、がんが膀胱の壁のどの深さまで達しているか、リンパ節や他の臓器への転移がないかを評価するために行います。
治療方針の決定に欠かせない情報となります。
膀胱がんの進行度
膀胱がんの治療方針は、がんの深達度(がんが膀胱の壁にどれだけ深く入り込んでいるか)と転移の有無によって決まります。
深達度はTa, Tis, T1(筋層非浸潤性)からT2, T3, T4(筋層浸潤性)に分類されます。
| 深達度 | がんの状態 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| Ta, Tis | がんが粘膜内にとどまっている | 最も早期の段階。Tisは上皮内がんと呼ばれる。 |
| T1 | がんが粘膜下層まで浸潤している | 筋層には達していないが、粘膜より深く進んでいる。 |
| T2-T4 | がんが筋層やさらに外側まで浸潤している | 進行した状態で、転移のリスクも高まる。 |
治療法
膀胱がんの治療は、筋層非浸潤性か筋層浸潤性かによって大きく異なります。
内視鏡手術
筋層非浸潤性膀胱がんの基本的な治療は、経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)です。これは、尿道から内視鏡を挿入し、電気メスでがんを削り取る手術です。
この手術は診断と治療を兼ねており、切除した組織を調べることで、がんの深達度や悪性度を正確に判断します。
膀胱内注入療法
TURBTの後、再発を予防する目的で、抗がん剤やBCG(ウシ型弱毒結核菌)を膀胱内に直接注入する治療を行うことがあります。
特に、悪性度の高いがんや上皮内がん(Tis)に対してBCG注入療法は有効な選択肢です。
膀胱全摘除術
筋層浸潤性膀胱がんに対しては、膀胱をすべて摘出する「膀胱全摘除術」が標準的な治療法です。男性では前立腺と精嚢、女性では子宮や卵巣なども同時に摘出することがあります。
膀胱を摘出した後は、尿の出口を新しく作る「尿路変向(再建)術」が必要です。
薬物療法と放射線治療
転移がある場合や、手術が難しい場合には、薬物療法(化学療法や免疫チェックポイント阻害薬)が中心となります。
また、膀胱の温存を希望する場合などには、化学療法と放射線治療を組み合わせる治療法を選択することもあります。
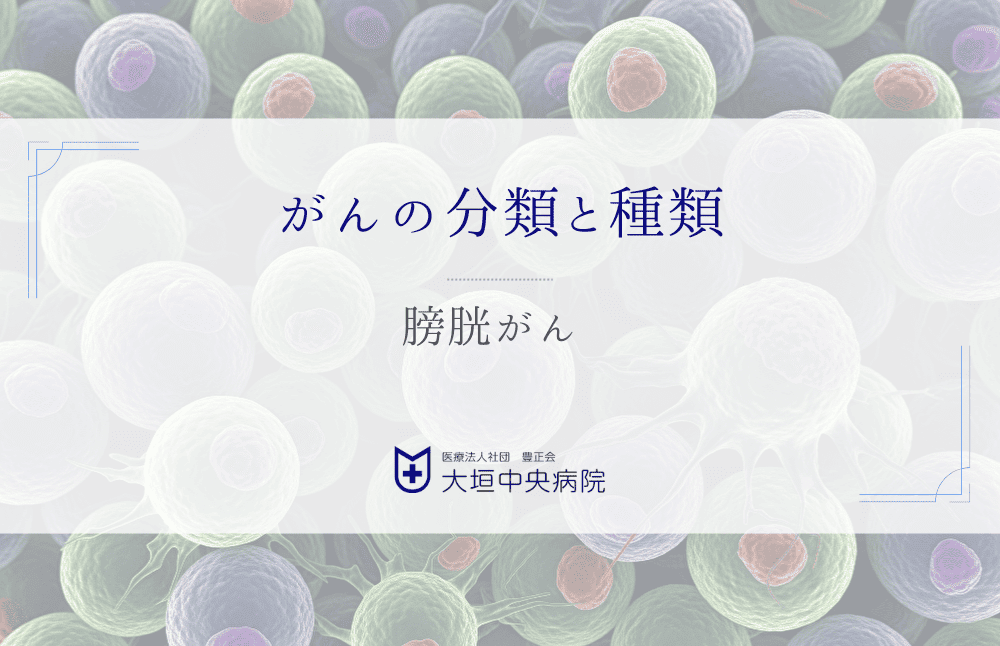
前立腺がん
前立腺は男性だけにある生殖器の一つで、前立腺がんはこの前立腺の細胞から発生します。他のがんと比べて進行が比較的ゆっくりであることが多く、早期に発見できれば根治を目指せる可能性が高いがんです。
近年、血液検査によるPSA検査の普及により、早期発見される方が増えています。ここでは、特に中高年の男性にとって関心の高い前立腺がんについて掘り下げていきます。
前立腺がんとは
前立腺がんは、日本の男性がかかるがんの中で最も多いものの一つです。特に50歳を過ぎた頃から増え始め、高齢になるほどかかる割合が高くなります。
前立腺の役割
前立腺は膀胱のすぐ下にあり、尿道を取り囲むように位置する、くるみ大の臓器です。精液の一部となる前立腺液を分泌する役割を担っています。
加齢とともに肥大しやすく、排尿障害を引き起こす前立腺肥大症とは異なる病気です。
がんの発生と特徴
前立腺がんの多くは、前立腺の外側に近い「辺縁領域」から発生します。そのため、初期の段階では排尿に関する症状が出にくいという特徴があります。
進行は比較的緩やかですが、進行すると骨やリンパ節に転移しやすい性質を持っています。
症状
前立腺がんは「静かなるがん」とも言われ、早期のうちは自覚症状がほとんどありません。症状が出たときには、ある程度進行している可能性があります。
初期には症状が出にくい
がんが前立腺の中にとどまっている早期の段階では、症状を感じることはまれです。そのため、症状がないからといって安心はできません。
50歳を過ぎたら、症状がなくても定期的にPSA検査を受けることが推奨されます。
進行に伴う症状
がんが大きくなって尿道を圧迫するようになると、尿が出にくい、排尿に時間がかかる、頻尿、残尿感といった、前立腺肥大症と似た症状が現れます。
さらに進行して骨に転移すると、腰や背中、肩などに痛みを感じることがあります。
検査と診断
前立腺がんの診断は、PSA検査をきっかけに行われることが大半です。いくつかの検査を組み合わせて、がんの有無や悪性度、広がりを調べます。
PSA検査
PSA(前立腺特異抗原)は、前立腺で作られるたんぱく質で、その一部が血液中に漏れ出します。前立腺がんになると、このPSAの値が高くなる傾向があります。
PSA検査は簡単な採血で済み、前立腺がんの早期発見に非常に有用です。
ただし、前立腺炎や前立腺肥大症でも数値が上がることがあるため、PSA値が高いことが直ちにがんを意味するわけではありません。
直腸診と生検
PSA値が高い場合や、医師が必要と判断した場合には、直腸診や生検を行います。直腸診は、肛門から指を挿入して直腸越しに前立腺を触診し、硬さやしこりの有無を調べます。
確定診断のためには、超音波で前立腺を観察しながら、細い針で組織を採取する「前立腺生検」が必要です。
採取した組織を病理医が顕微鏡で調べ、がん細胞の有無や悪性度(グリソンスコア)を評価します。
画像診断
生検でがんが確定したら、MRI検査でがんが前立腺内のどこに、どの程度広がっているかを詳しく調べます。また、CT検査や骨シンチグラフィ検査で、リンパ節や骨などへの転移がないかを確認します。
前立腺がんの進行度と悪性度
治療方針は、がんの進行度(TNM分類)、PSA値、そして生検で判明した悪性度(グリソンスコア)を基に、リスク分類を行って決定します。
リスクが低い場合は、すぐに治療を開始せず経過を観察することもあります。
| リスク分類 | PSA値・グリソンスコア・T分類 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| 低リスク | PSA < 10 かつ GS ≤ 6 かつ T1-T2a | がんがおとなしく、前立腺内にとどまっている可能性が高い。 |
| 中リスク | PSA 10-20 または GS = 7 または T2b | 低リスクと高リスクの中間の状態。 |
| 高リスク | PSA > 20 または GS ≥ 8 または T2c以上 | がんが進行性であるか、前立腺の外に広がっている可能性が高い。 |
治療法
前立腺がんの治療法は多岐にわたります。がんのリスク分類や患者さんの年齢、健康状態、そしてご自身の希望を考慮して、最適な治療法を選択します。
監視療法
低リスクの前立腺がんと診断された場合、すぐに治療を始めずに、定期的なPSA検査や生検で厳重に経過を観察する「監視療法」という選択肢があります。
治療に伴う体への負担や副作用を避け、生活の質を維持することを目的とします。
手術療法
がんが前立腺内にとどまっている場合、根治を目指す治療法として手術があります。前立腺と精嚢を摘出する「前立腺全摘除術」が標準です。
近年は、より精密な操作が可能で、術後の尿失禁や性機能障害といった合併症を軽減することが期待されるロボット支援手術が主流になっています。
放射線治療
手術と同様に、限局性前立腺がんの根治を目指す治療法です。体の外から放射線を照射する「外部照射」と、前立腺内に小さな放射線源を埋め込む「組織内照射(小線源治療)」があります。
高齢の方や合併症で手術が難しい方にも適した治療法です。
内分泌療法(ホルモン療法)
前立腺がんは、男性ホルモン(アンドロゲン)を養分として増殖する性質があります。この性質を利用し、男性ホルモンの分泌や働きを抑えることで、がんの増殖を抑制するのが内分泌療法です。
進行がんや転移がある場合の中心的な治療法ですが、放射線治療と組み合わせて行うこともあります。
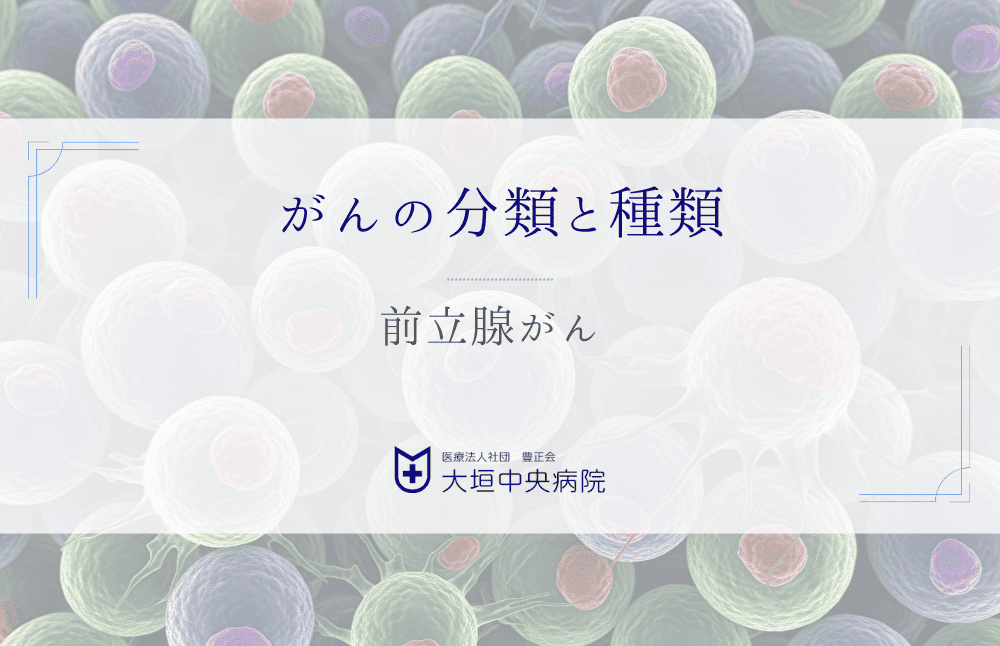
精巣がん
精巣がんは、男性の精巣(睾丸)に発生する悪性腫瘍です。他のがんと比べて発生頻度は低いものの、10代後半から30代の若い世代の男性に最も多く見られるという特徴があります。
幸い、早期に発見すれば化学療法(抗がん剤治療)などがよく効き、治癒率が非常に高いがんの一つです。
ご自身でしこりに気づくことが発見のきっかけとなることが多いので、日頃から関心を持つことが大切です。
精巣がんとは
精巣がんは、精子を作る精巣の細胞ががん化する病気です。比較的まれながんですが、若年層の男性にとっては最も重要な腫瘍の一つです。
若い世代に多いがん
精巣がんの発生のピークは20代後半から30代にあり、AYA世代(思春期・若年成人)のがんとして知られています。
停留精巣(精巣が陰嚢内に下降してこない状態)の既往がある人は、発生リスクが高いことが分かっています。
精巣がんの種類
精巣がんは、組織のタイプによって大きく「セミノーマ」と「非セミノーマ」に分けられます。
この分類は、治療方針を決める上で非常に重要です。セミノーマは進行が比較的緩やかで、放射線治療が効きやすい特徴があります。
一方、非セミノーマは複数の組織型が混在することが多く、進行が速い傾向がありますが、化学療法への感受性が高いです。
症状
精巣がんの最も一般的な初期症状は、痛みを感じない精巣のしこりや腫れです。
精巣のしこりや腫れ
入浴時などに、片方の精巣が硬くなったり、大きさが変わったり、しこりができたりすることで気づく場合がほとんどです。通常、痛みは伴いません。
左右の精巣の大きさが少し違うのは正常ですが、以前と比べて明らかな変化を感じた場合は注意が必要です。
その他の症状
がんが進行して転移すると、転移した場所に応じた症状が現れます。例えば、腹部のリンパ節に転移すると、お腹の不快感や腰痛が起こることがあります。
肺に転移すれば、咳や息切れ、血痰などが見られます。
検査と診断
精巣のしこりなどで受診した場合、触診や画像検査、血液検査などを通じて診断を進めます。
触診と超音波検査
まず医師が精巣を直接触って、しこりの硬さや大きさ、表面の状態などを確認します。
続いて、超音波(エコー)検査を行い、しこりが精巣内部にあるのか、液体のたまり(陰嚢水腫など)なのか、悪性を疑う所見はないかを詳しく調べます。
腫瘍マーカー
精巣がんでは、特定のたんぱく質が血液中で増加することがあり、これを「腫瘍マーカー」として診断や治療効果の判定に用います。
代表的なものにAFP、hCG、LDHがあり、特に非セミノーマで数値が高くなる傾向があります。
画像診断による転移の確認
精巣がんと診断されたら、CT検査で胸部、腹部、骨盤内を撮影し、リンパ節や肺、肝臓などへの転移がないかを調べます。
これにより、がんの進行度(ステージ)を決定します。
精巣がんの進行度
精巣がんの進行度は、転移の有無と腫瘍マーカーの値に基づいて、ステージIからIIIの3段階に分類します。このステージ分類が、手術後の追加治療の方針を決定する上で重要になります。
| ステージ | がんの状態 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| I期 | がんが精巣内にとどまっている | 転移はなく、腫瘍マーカーも正常化する。 |
| II期 | 腹部のリンパ節に転移がある | 横隔膜より下にあるリンパ節への転移。 |
| III期 | 遠隔転移がある(肺、肝臓など) | 横隔膜より上にあるリンパ節や、他の臓器への転移。 |
治療法
精巣がんの治療は、まず手術でがんのある精巣を摘出し、その後の病理結果や進行度に応じて追加の治療を検討します。
高位精巣摘除術
精巣がんが疑われる場合、診断と治療を目的として、まず手術を行います。足の付け根あたりを小さく切開し、がん細胞が散らばらないように精巣と精索(精管や血管の束)を一緒に摘出します。
これを「高位精巣摘除術」と呼びます。摘出した組織の病理検査で、がんの種類(セミノーマか非セミノーマか)と広がりを確定します。
追加の治療
手術後の治療方針は、病理結果とステージによって決まります。ステージIのセミノーマなど、再発リスクが低い場合は、手術のみで治療を終えて慎重に経過観察することが多いです。
一方、非セミノーマや進行したステージでは、再発を予防するために化学療法(抗がん剤治療)を追加します。
転移がある場合でも、シスプラチンという抗がん剤を中心とした多剤併用化学療法が非常によく効き、高い確率で治癒を目指せます。
化学療法で効果が不十分な場合や、残った腫瘍に対して、追加の手術や放射線治療を行うこともあります。

よくある質問
- 泌尿器系のがんは遺伝しますか?
-
ほとんどの泌尿器系がんは遺伝と直接関係なく発生しますが、一部には家族内で発症しやすい、いわゆる「家族性腫瘍」が存在します。
例えば、腎がんの中には特定の遺伝子の変異が原因で起こるものがあります。また、前立腺がんも、近親者に罹患者がいると発症リスクが少し高まると報告されています。
ご家族に同じがんの方がいるなど、遺伝に関してご心配な点があれば、主治医に相談してみてください。遺伝カウンセリングなどの情報を提供してもらえる場合があります。
- 治療後の生活で気をつけることは何ですか?
-
治療内容によって注意点は異なりますが、共通して大切なのは、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙など、規則正しい生活習慣を心がけることです。
また、治療後も定期的な通院と検査は欠かせません。再発や転移のチェックだけでなく、治療による長期的な影響(副作用)を管理するためにも、医師の指示に従って受診を続けてください。
不安なことや体の変化があれば、一人で抱え込まずに医療スタッフに相談することが重要です。
- セカンドオピニオンはどのように受ければよいですか?
-
セカンドオピニオンは、現在の主治医以外の医師に、診断や治療方針について意見を求めることです。患者さんの権利として認められており、納得して治療を受けるために役立ちます。
まずは主治医にセカンドオピニオンを希望する旨を伝え、紹介状(診療情報提供書)や検査データ(CT画像など)を用意してもらいます。
その資料を持って、他の専門病院を受診します。どの病院が良いか分からない場合は、がん診療連携拠点病院などに設置されている「がん相談支援センター」で相談することもできます。
- 治療費はどのくらいかかりますか?
-
治療費は、がんの種類、進行度、行う治療法(手術、放射線、薬物療法など)、入院期間によって大きく異なります。
日本の公的医療保険制度では、医療費の自己負担は原則1割から3割です。
さらに、医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
この制度を利用することで、経済的な負担を大きく軽減できます。
具体的な金額については、病院の相談窓口やソーシャルワーカー、がん相談支援センターなどで確認することをおすすめします。
以上
参考文献
AMIN, Mahul B.; TICKOO, Satish K. Diagnostic Pathology: Genitourinary E-Book: Diagnostic Pathology: Genitourinary E-Book. Elsevier Health Sciences, 2022.
MOCHA, Holger, et al. The 2016 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs—Part A: Renal, Penile, and Testicular Tumours. Eur urol, 2016, 70.1: 93-105.
MOCH, Holger, et al. The 2016 WHO classification of tumours of the urinary system and male genital organs—part A: renal, penile, and testicular tumours. European urology, 2016, 70.1: 93-105.
STEPHENSON, Andrew, et al. Diagnosis and treatment of early stage testicular cancer: AUA guideline. The Journal of urology, 2019, 202.2: 272-281.
CORNEJO, Kristine M.; RICE-STITT, Travis; WU, Chin-Lee. Updates in staging and reporting of genitourinary malignancies. Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 2020, 144.3: 305-319.
RIDDLE, Nicole, et al. Recent Advances in Genitourinary Tumors: Updates From the 5th Edition of the World Health Organization Blue Book Series. Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 2024, 148.8: 952-964.
CRUNK, April K. A Basic Overview of Genitourinary Cancers. Physician Assistant Clinics, 2025, 10.3: 541-563.
KHAJURIA, Atul; KUSHTE, Shilpa S. Genitourinary cancer: a perspective review. Santosh University Journal of Health Sciences, 2022, 8.2: 111-115.
MAZZUCCHELLI, Roberta, et al. Neuroendocrine tumours of the urinary system and male genital organs: clinical significance. BJU international, 2009, 103.11: 1464-1470.
JIA, Liwei, et al. Common diagnostic challenges and pitfalls in genitourinary organs, with emphasis on immunohistochemical and molecular updates. Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 2021, 145.11: 1387-1404.