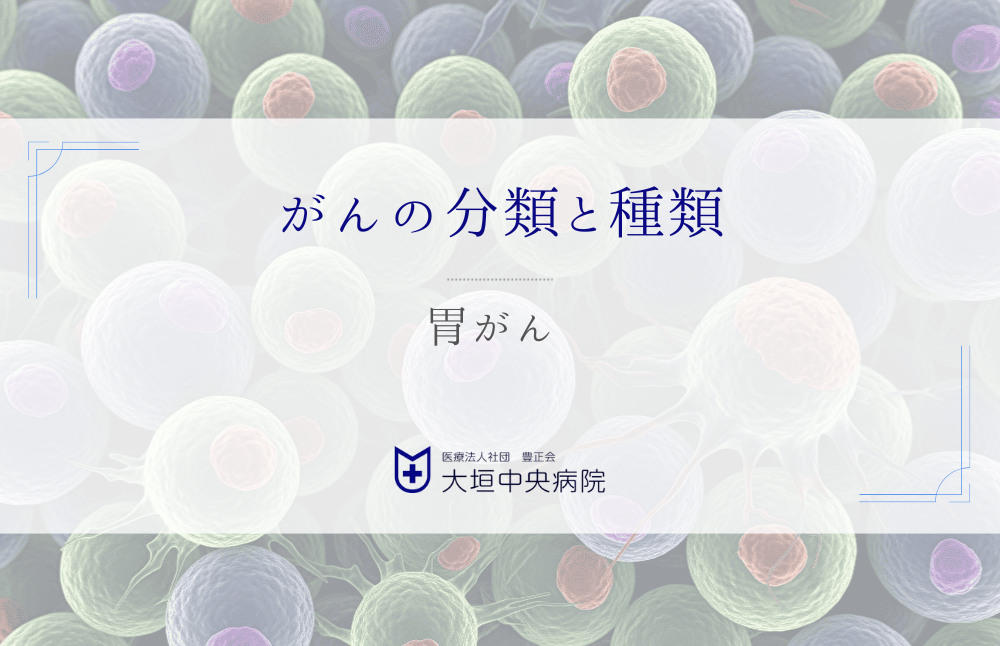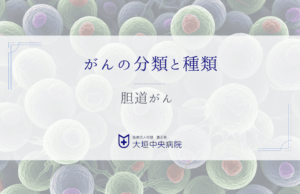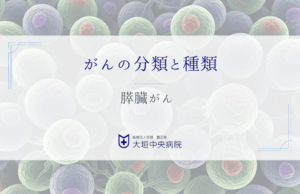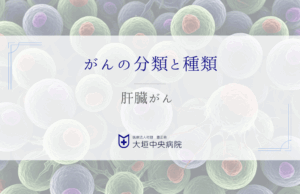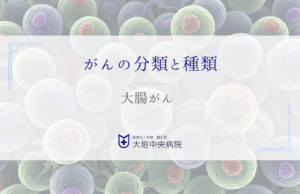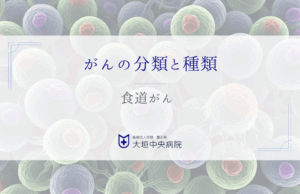胃がんは、かつて日本で最も死亡数の多いがんでしたが、医療の進歩によりその状況は変化しつつあります。しかし、今なお多くの人が罹患し、私たちの生活に大きな影響を与えています。
この記事では、胃がんという病気について、その発生の仕組みから、症状、検査、そして治療法に至るまで、基本的な知識を網羅的に解説します。
ご自身や大切な人の健康を守るため、正しい情報を知り、適切な行動に繋げることが重要です。本記事が、その一助となることを願っています。
胃がんとは何か – 日本人に多いがんの実態
胃がんは、胃の壁の内側を覆う粘膜の細胞が、何らかの原因でがん細胞に変化し、無秩序に増え続けていく病気です。
日本人のがんの中でも罹患数が多く、私たちの健康にとって依然として大きな脅威の一つです。その実態を正しく理解することが、向き合うための第一歩となります。
日本における胃がんの現状データ
日本では、長年にわたり胃がんががんによる死亡原因の上位を占めてきました。
食生活の欧米化やピロリ菌の除菌治療の普及などにより死亡率は減少傾向にありますが、高齢化社会の進展に伴い、罹患する人の総数は依然として多い状況です。
特に50歳を過ぎると罹患率が上昇する傾向が見られます。
統計データが示す社会的な課題
国立がん研究センターが公開する統計データを見ると、胃がんは男性に多く、死亡数は肺がん、大腸がんに次いで第3位となっています。
このデータは、胃がんが個人の問題だけでなく、日本の医療や社会保障制度全体で取り組むべき課題であることを示しています。早期発見・早期治療の体制を社会全体で支えることが重要です。
膨大な臨床データを解析し、より効果的な予防策や治療法を模索する研究が続けられています。
胃がんのリスク要因
| リスク要因 | 関連性 | 対策 |
|---|---|---|
| ヘリコバクター・ピロリ菌 | 最大の原因。感染者の胃に慢性的な炎症を引き起こす。 | 検査と除菌治療 |
| 食生活 | 高塩分食品の過剰摂取、野菜・果物不足。 | 減塩、バランスの取れた食事 |
| 喫煙 | 胃粘膜の血流を悪化させ、発がん物質にさらされる。 | 禁煙 |
胃がんの定義と種類
胃がんは、組織学的特徴、つまり顕微鏡で見たときの細胞の顔つきによって、いくつかの種類に分類されます。
この分類は、がんの性質や進行の速さ、治療方針の決定に影響を与えるため、とても重要です。
分化型と未分化型という細胞の顔つき
胃がんは大きく「分化型」と「未分化型」に分けられます。分化型は、がん細胞が胃の正常な粘膜細胞に近い形を保っており、比較的ゆっくりと増殖する傾向があります。
一方、未分化型は正常な細胞の形を失っており、増殖が速く、転移しやすい性質を持つことが知られています。内視鏡で採取した組織の画像診断によって、これらの型を判断します。
スキルス胃がんという特殊なタイプ
未分化型がんの一種に「スキルス胃がん」があります。このタイプは、粘膜の表面にあまり変化を起こさず、胃の壁の中を硬く厚くさせながら広がっていく特徴があります。
そのため発見が難しく、診断されたときにはすでに進行していることも少なくありません。このがんの性質の解明と新しい治療法の開発が、急務となっています。
胃の中で何が起きているのか – がん発生の成り立ち
私たちの胃の中で、どのようにしてがん細胞は生まれるのでしょうか。正常だった細胞ががん化し、増殖していく過程には、遺伝子の傷や慢性的な炎症が深く関わっています。
その一連の流れを理解することで、予防や早期発見の重要性が見えてきます。
正常な胃粘膜からがん細胞の生成へ
胃の粘膜は、強力な胃酸から自らを守るために、常に新しい細胞に入れ替わっています。しかし、ピロリ菌感染などによって慢性的な炎症が続くと、細胞が新しくなる過程で遺伝子に傷がつきやすくなります。
この傷が修復されずに積み重なることで、細胞の設計図に異常が生じ、がん細胞が生成されると考えられています。
繰り返す炎症が招く細胞の異常
ピロリ菌が引き起こす慢性胃炎は、胃粘膜の萎縮(萎縮性胃炎)や、腸の粘膜に似た細胞に置き換わる「腸上皮化生」という状態を引き起こします。このような環境は、がんが発生しやすい土壌となります。
炎症が続くことで、細胞の増殖をコントロールする仕組みが壊れ、がん化への道筋が作られてしまうのです。
がん細胞の進化と増殖
一度生まれたがん細胞は、正常な細胞のルールに従いません。自律的に増殖を続け、周囲の組織に染み込むように広がっていきます(浸潤)。
さらに、がん細胞は増殖の過程で次々と新たな遺伝子変異を獲得し、より悪性度の高い性質へと進化していくことがあります。
遺伝子の変異と無秩序な増殖
がんの発生には、がん遺伝子(アクセル役)の活性化と、がん抑制遺伝子(ブレーキ役)の機能不全が関与します。
これらの遺伝子に複数の変異が重なることで、細胞は増殖のコントロールを完全に失い、無限に増え続ける能力を獲得します。
このがん細胞の振る舞いを理解するための研究が、新しい治療薬の開発に繋がっています。
がんの進行度(ステージ)と主な状態
| ステージ | がんの広がり | 主な状態 |
|---|---|---|
| I期(早期) | 粘膜または粘膜下層に留まる | 自覚症状はほとんどない。内視鏡治療の対象となる場合がある。 |
| II期・III期(進行) | 固有筋層より深く浸潤、リンパ節転移 | 手術や化学療法が中心。症状が現れることがある。 |
| IV期(進行) | 遠隔臓器への転移 | 化学療法が中心。症状緩和も重要な治療目標となる。 |
見逃してはいけない症状 – 胃がんの初期サイン
多くの人が「がん=特有の症状」というイメージを持っていますが、胃がんの場合、その考えは当てはまりません。
特に、治癒率が高い早期の段階では、症状がほとんどないか、あっても非常に軽微です。この事実を知ることが、早期発見への意識を高める上で重要です。
初期段階では症状が出にくいという事実
胃がんの最も厄介な特徴の一つは、早期の段階では自覚症状がほとんどないことです。がんが胃の粘膜の表面に留まっている間は、痛みや不快感を感じることは稀です。
この「静かな進行」が、発見を遅らせる大きな原因となっています。
人間が自覚しにくい静かな進行
人間の体は非常にうまくできていますが、胃の粘膜には痛みを感じる神経がありません。
そのため、表面にがんができても痛みとして感知することができないのです。
症状がないからといって安心せず、リスクが高まる年齢になったら定期的に検診を受けるという能動的な姿勢が、自分の未来を守ることに繋がります。
注意すべき身体の変化
がんが少し進行してくると、何らかの症状が現れることがあります。しかし、それらは胃炎や胃潰瘍など、他の一般的な胃の病気と非常によく似ているため、自己判断は禁物です。
胃炎や潰瘍と似た症状
以下のような症状が続く場合は、専門医に相談することを推奨します。
これらの症状は胃がん特有のものではありませんが、体が発しているサインである可能性を認識することが大切です。
- みぞおちの痛み、不快感
- 胸やけ、げっぷ
- 食欲不振、吐き気
- 食事がつかえる感じ
進行した場合に現れる症状
がんがさらに進行し、大きくなったり、出血したりすると、よりはっきりとした症状が現れます。これらのサインに気づいた場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。
体重減少や黒色便という危険信号
がんからの出血が続くと、便が黒くなる「黒色便(タール便)」が見られることがあります。また、食事が十分に摂れなくなったり、がんが体の栄養を消費したりすることで、意図しない体重減少が起こります。
これらは進行がんのサインであり、迅速な検査と治療が求められます。
早期発見の重要性 – 検査方法と受診のタイミング
症状が出にくい胃がんだからこそ、症状がないうちに見つけ出す「早期発見」が極めて重要です。現在の医療技術は、非常に小さながんを発見することを可能にしています。
どのような検査があり、いつ受けるべきかを知っておきましょう。
なぜ早期発見が重要なのか
胃がんの治療成績は、発見されたときの進行度(ステージ)に大きく左右されます。
早期の段階で発見できれば、体への負担が少ない治療で根治を目指すことができ、その後の生活の質(QOL)も高く保つことができます。
治療成績を大きく左右する発見時期
| 発見ステージ | 主な治療法 | 5年相対生存率の目安 |
|---|---|---|
| ステージI | 内視鏡治療、手術 | 90%以上 |
| ステージIV | 化学療法など | 10%未満 |
このデータが示すように、発見が早いほど生存率は劇的に高まります。早期発見は、単に病気を治すだけでなく、その後の人生設計そのものを守ることに繋がるのです。
主な検査技術の種類と特徴
胃がんの検診や精密検査には、主に「胃部X線検査」と「内視鏡検査」という二つの技術が用いられます。それぞれに長所と短所があり、目的によって使い分けます。
胃部X線検査(バリウム検査)
発泡剤で胃を膨らませ、造影剤であるバリウムを飲んでレントゲン撮影を行う検査です。胃全体の形や粘膜の凹凸を観察し、大きな病変を見つけるのに役立ちます。
多くの人を対象とする住民検診や職場検診で広く活用されてきました。
内視鏡検査(胃カメラ)の技術的進化
先端に小型カメラが付いた細いスコープを口または鼻から挿入し、胃の内部を直接観察する検査です。
技術の進化は目覚ましく、ハイビジョン画質での観察や、特殊な光を用いて微細な血管や粘膜模様を強調する機能(NBIなど)も登場しています。
これにより、ごく初期の小さながんの発見率が飛躍的に向上しました。
内視鏡で見る詳細な画像情報
内視鏡検査の最大の利点は、胃の粘膜を直接、高精細なカラー画像で観察できることです。
医師はモニターに映し出されるリアルタイムの映像から、粘膜の色の変化やわずかな凹凸といった、がんのサインを読み取ります。
画像診断技術の活用と未来
近年では、AI(人工知能)を活用した画像診断支援システムの開発も進んでいます。過去の膨大な内視鏡画像をAIに学習させ、医師が見落とす可能性のある微小な病変を検知する技術です。
これにより、診断の精度がさらに向上し、医師の負担軽減にも繋がることが期待されています。未来の検診では、このような先進技術がより広く活用されることになるでしょう。
ピロリ菌と胃がんの関係 – 除菌治療の意義
近年の研究で、胃がんの発生に「ヘリコバクター・ピロリ菌」という細菌が極めて深く関わっていることが明らかになりました。この発見は、胃がん予防の考え方を大きく変えました。
ピロリ菌について正しく理解し、除菌治療の意義を知ることは、胃がんリスクを管理する上で非常に重要です。
ピロリ菌感染が胃がんの主因であるという根拠
ピロリ菌は、胃の強い酸性環境の中でも生きられる特殊な細菌です。感染すると胃の粘膜に住み着き、慢性的な炎症を引き起こします。
この慢性胃炎が長期間続くことが、胃がん発生の温床となるのです。
長年の研究データが示す関連性
世界保健機関(WHO)は、ピロリ菌を「確実な発がん因子」として認定しています。日本の胃がん患者の9割以上がピロリ菌に感染しているというデータもあり、その関連性は疑いようがありません。
ピロリ菌に感染していない人が胃がんになることは、極めて稀です。
ピロリ菌感染の有無による胃がん発生率
| ピロリ菌感染状態 | 胃がんの年間発生率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 感染者 | 約0.5% | 感染期間が長いほどリスクは上昇する。 |
| 非感染者 | ほぼ0% | 胃がんになるリスクは極めて低い。 |
除菌治療という予防的アプローチ
ピロリ菌感染が胃がんの大きな原因であるならば、その菌を取り除く「除菌治療」が有効な予防策となります。これは、胃がん予防における画期的な進歩です。
除菌治療の具体的な方法と流れ
除菌治療は、2種類の抗生物質と胃酸の分泌を抑える薬の3剤を、1週間服用するのが一般的です。服用終了後、一定期間をあけてから検査を行い、菌がいなくなったかを確認します。
1回目の治療(一次除菌)の成功率は約90%程度とされています。
治療法の開発と社会への貢献
除菌治療の確立は、多くの研究者や製薬企業の努力の賜物です。より効果的で副作用の少ない治療法の開発が続けられており、これは公衆衛生の向上という形で社会に大きく貢献しています。
除菌治療の普及は、将来の胃がん患者を減らすための重要な国家戦略とも言えます。
除菌後の注意点と倫理的な配慮
除菌治療が成功すれば、胃がんの発生リスクは大幅に低下します。しかし、リスクがゼロになるわけではありません。除菌後も油断せず、適切な健康管理を続けることが大切です。
ゼロにはならないリスクと定期検診の必要性
特に、長期間にわたる感染で胃の粘膜の萎縮が進んでしまった後に除菌した場合、すでにある程度がん化のリスクが高まっている可能性があります。
そのため、除菌に成功した人でも、定期的な内視鏡検査を受けることが強く推奨されます。
個人の遺伝情報や生活習慣といったデータを基に、より個別化された検診計画を立てるという考え方にも、倫理的な配慮と共に注目が集まっています。
病期別の治療方針 – 手術から薬物療法まで
胃がんの治療法は、がんの進行度である「ステージ(病期)」に基づいて決定します。
早期がんであれば体への負担が少ない治療も可能ですが、進行するにつれて、複数の治療法を組み合わせる「集学的治療」が必要になります。
ここでは、ステージごとの標準的な治療方針を解説します。
治療方針を決めるステージ(病期)分類
ステージは、がんの深さ(T因子)、リンパ節への転移の有無と範囲(N因子)、他の臓器への遠隔転移の有無(M因子)の3つの要素を組み合わせて、総合的に判断します。
TNM分類の要素
| 因子 | 評価項目 | 意味 |
|---|---|---|
| T因子(深達度) | がんが胃壁のどの深さまで達しているか | 数字が大きいほど深く浸潤している。 |
| N因子(リンパ節転移) | 転移しているリンパ節の個数 | 数字が大きいほど転移が多い。 |
| M因子(遠隔転移) | 肝臓や肺など離れた臓器への転移の有無 | 転移があればM1、なければM0。 |
臨床データに基づく生存率の学習
ステージ分類は、過去の膨大な臨床データを基に作られています。医師はこれらのデータを学習し、目の前の患者さんにとって最も効果が期待できる治療法を選択します。
患者さん自身も、自分のステージと治療方針について正しく理解することが、納得して治療に臨むために重要です。
不明な点は、AIを活用したチャットボットで予備知識を得ることもできますが、最終的には主治医とよく話し合うことが大切です。
早期がん(ステージI)の治療
リンパ節転移の可能性が極めて低く、がんが粘膜内に留まっているようなごく早期のがんは、内視鏡を使った治療の対象となります。
内視鏡治療という低侵襲技術
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)などの技術を用いて、お腹を切ることなく、口から入れた内視鏡でがんを粘膜ごと剥ぎ取ります。
この治療法は、体への負担が非常に少なく、入院期間も短くて済みます。胃が温存されるため、治療後の食事への影響もほとんどありません。
進行がん(ステージII・III)の治療
がんが胃壁の深くに進んでいたり、リンパ節への転移があったりする場合には、手術が治療の基本となります。
手術を中心とした集学的治療
手術では、がんのある部分を含む胃と、転移の可能性がある周囲のリンパ節を切除(郭清)します。
がんの場所によって、胃の出口側3分の2を切除する「幽門側胃切除術」や、胃をすべて切除する「胃全摘術」などが行われます。
再発リスクを減らすために、手術の前後に化学療法(抗がん剤治療)を組み合わせることもあります。
手術技術の進化と仕事復帰への配慮
近年では、お腹に小さな穴をいくつか開けて行う「腹腔鏡手術」や、ロボット支援下手術といった、より精密で体への負担が少ない手術技術も普及しています。
これらの低侵襲手術は、術後の回復を早め、患者さんの早期の仕事復帰や社会復帰を後押しします。
遠隔転移がある場合(ステージIV)の治療
発見時にすでに肝臓や肺、腹膜などに遠隔転移がある場合や、手術後に再発した場合は、全身に効果が及ぶ薬物療法が治療の中心となります。
薬物療法による未来への挑戦
薬物療法には、がん細胞を直接攻撃する「化学療法」、がんの増殖に関わる特定の分子を狙う「分子標的薬」、人間が本来持つ免疫の力を利用してがんと戦う「免疫チェックポイント阻害薬」などがあります。
新しい薬の開発は日進月歩で進んでおり、治療の選択肢は年々増えています。これらの治療は、がんの進行を抑え、症状を和らげ、QOLを維持しながらがんと共存することを目指します。
主な薬物療法の種類
| 治療法 | 作用 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 化学療法(抗がん剤) | 細胞分裂が活発な細胞(がん細胞)を攻撃する。 | 多くの胃がん |
| 分子標的薬 | がん細胞の増殖に関わる特定の分子の働きを妨げる。 | 特定の遺伝子変異を持つがん |
| 免疫療法 | 免疫ががんにかけるブレーキを解除し、攻撃力を高める。 | 特定の条件を満たすがん |
治療後の食生活 – 胃切除後の栄養管理
胃を切除する手術を受けた後は、食べ物を溜めておいたり、消化したりする胃の機能が変化します。そのため、以前と同じような食生活を送ることは難しくなります。
治療後の体を支え、回復を促すためには、食事の仕方を工夫することがとても重要です。
胃の機能変化と身体への影響
胃を切除すると、一度にたくさんの量を食べられなくなったり、食べたものが速く腸に流れることで様々な症状(ダンピング症候群など)が起きたりします。
人間の体は時間と共にある程度この変化に適応していきますが、慣れるまでは工夫が必要です。
胃切除後の主な身体の変化
- 一度に食べられる量が減る
- 食べ物が腸へ速く流れ込む(ダンピング症候群)
- 栄養素(特に鉄分、ビタミンB12)の吸収が悪くなる
食事の基本原則と工夫
術後の食事で最も大切なのは、「ゆっくり、よく噛んで、少しずつ」です。消化の良いものを中心に、1日の食事回数を5〜6回に分けて、1回あたりの量を減らす「少量頻回食」を心がけます。
食事の工夫のポイント
| ポイント | 具体的な方法 | 目的 |
|---|---|---|
| 少量頻回食 | 1日5〜6回に分けて食べる | 胃の負担を減らし、必要な栄養を確保する |
| よく噛む | 一口30回以上を目安にする | 唾液による消化を助け、満腹感を得やすくする |
| 消化の良い食品を選ぶ | 脂っこいもの、硬いもの、食物繊維の多いものを避ける | 胃腸への負担を軽減する |
栄養データを活用した食事計画
術後は体重が減少しやすいため、タンパク質やエネルギーを意識して摂取することが大切です。しかし、自己流の食事管理では栄養が偏ってしまうこともあります。
管理栄養士という仕事との連携
多くの病院では、管理栄養士が患者さん一人ひとりの状態に合わせて、具体的な食事内容や調理法の指導を行っています。
専門家は、栄養に関する豊富な知識とデータを活用し、退院後の生活を見据えた食事計画を立ててくれます。食事に関する悩みや不安は、遠慮なく管理栄養士という仕事のプロに相談しましょう。
定期検診の大切さ – 早期発見で変わる治療成績
胃がんの治療を終えた後も、あるいは胃がんのリスクを抱えている場合も、定期的な検診を受け続けることは非常に大切です。
検診は、万が一の再発や新たながんを早期に発見し、未来の健康を守るための重要な投資と言えます。
検診がもたらす未来への投資
症状がないからといって検診を怠ると、気づいたときには病状が進行している可能性があります。
定期的に自分の体の状態をチェックすることは、長期的な視点で見たときに、時間的にも経済的にも、そして何より精神的にも大きな利益をもたらします。
自分と家族のための健康管理
健康は、自分自身だけでなく、家族や大切な人にとってもかけがえのない財産です。定期検診を受けるという行動は、自分を大切にすると同時に、周りの人々を安心させることにも繋がります。
健康な体を維持することは、充実した人生を送るための基盤となります。
自治体や企業の検診制度の活用
日本では、多くの自治体で住民を対象とした胃がん検診が実施されています。また、企業に勤めている場合は、職場の健康診断の一環として検診を受ける機会があります。
これらの制度を積極的に活用することが、健康管理の第一歩です。
社会インフラとしての検診制度
これらの検診制度は、国民の健康を守るための重要な社会インフラです。一部では、検診の受診率向上がビジネス上の課題と捉えられ、受診勧奨のための様々なサービスが提供されています。
自分にどのような選択肢があるかを確認し、積極的に活用しましょう。
AIチャットボットなどを活用した情報収集
検診の重要性は分かっていても、具体的な方法や費用について疑問を持つこともあるでしょう。
近年では、医療機関のウェブサイトなどで、よくある質問に自動で回答するAIチャタットボットが導入されていることがあります。
正しい知識を得るためのツール
これらのツールを活用すれば、24時間いつでも気軽に初期的な情報を得ることができます。
ただし、生成される情報はあくまで一般的なものであり、最終的な判断は必ず専門医に相談することが重要です。テクノロジーを賢く活用し、正しい知識を得るための補助として役立てましょう。
よくある質問
- 胃がんは遺伝しますか?
-
胃がんそのものが直接的に遺伝することは稀ですが、「家族性胃がん」と呼ばれる、特定の遺伝子の変異により胃がんになりやすい家系が存在することは事実です。
また、ピロリ菌の感染しやすさや、塩分を好むといった食生活が家族内で似ることで、結果的に家族に胃がん患者が多くなる傾向が見られることもあります。
血縁者に胃がんになった人がいる場合は、より早期からの定期的な検診を検討することが重要です。個人の遺伝子データをどう扱うかについては、倫理的な側面も含む慎重な議論が必要です。
- ピロリ菌の除菌に失敗したらどうなりますか?
-
1回目の除菌治療(一次除菌)で菌が除去できなかった場合でも、薬の種類を変更して2回目の治療(二次除菌)を行うことができます。
二次除菌まで含めると、95%以上の人で除菌が成功するとされています。諦めずに主治医と相談し、治療を続けることが大切です。
新しい除菌療法の開発も進められており、治療の選択肢は進化し続けています。
- 治療と仕事の両立は可能ですか?
-
可能です。治療法や体の回復度合いによりますが、多くの人が治療を受けながら仕事を続けています。
特に内視鏡治療や腹腔鏡手術など、体への負担が少ない治療法の普及により、早期の職場復帰がしやすくなっています。
治療中の働き方については、会社の制度(病気休暇、時差出勤、在宅勤務など)を確認し、上司や同僚、産業医などと相談することが大切です。
がんと共に働く人々を支える社会的な支援体制も整いつつあります。
胃がんと同様に、消化器系のがんとして注意が必要なのが「大腸がん」です。
大腸がんもまた、食生活の欧米化に伴い日本で増加傾向にあり、早期発見が治療の鍵を握るという点で胃がんと共通しています。
症状が出にくい初期段階で見つけるためには、定期的な検診が欠かせません。
大腸がんの具体的な症状、リスク要因、そして内視鏡検査をはじめとする検査方法や最新の治療法について知ることは、ご自身の健康を多角的に守る上で非常に有益です。
以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。
参考文献
SUGIMOTO, Mitsushige; MURATA, Masaki; YAMAOKA, Yoshio. Chemoprevention of gastric cancer development after Helicobacter pylori eradication therapy in an East Asian population: Meta-analysis. World Journal of Gastroenterology, 2020, 26.15: 1820.
CHIANG, Tsung-Hsien, et al. Mass eradication of Helicobacter pylori to reduce gastric cancer incidence and mortality: a long-term cohort study on Matsu Islands. Gut, 2021, 70.2: 243-250.
SUGANO, Kentaro. Effect of Helicobacter pylori eradication on the incidence of gastric cancer: a systematic review and meta-analysis. Gastric cancer, 2019, 22.3: 435-445.
FORD, Alexander Charles; YUAN, Yuhong; MOAYYEDI, Paul. Helicobacter pylori eradication therapy to prevent gastric cancer: systematic review and meta-analysis. Gut, 2020, 69.12: 2113-2121.
LEE, Yi-Chia, et al. Association between Helicobacter pylori eradication and gastric cancer incidence: a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology, 2016, 150.5: 1113-1124. e5.
FORD, Alexander C.; YUAN, Yuhong; MOAYYEDI, Paul. Long-term impact of Helicobacter pylori eradication therapy on gastric cancer incidence and mortality in healthy infected individuals: a meta-analysis beyond 10 years of follow-up. Gastroenterology, 2022, 163.3: 754-756. e1.
TSUKAMOTO, Tetsuya, et al. Prevention of gastric cancer: eradication of Helicobacter pylori and beyond. International Journal of Molecular Sciences, 2017, 18.8: 1699.
LIOU, Jyh-Ming, et al. Screening and eradication of Helicobacter pylori for gastric cancer prevention: the Taipei global consensus. Gut, 2020, 69.12: 2093-2112.
LEE, Yi-Chia, et al. Mass eradication of Helicobacter pylori to prevent gastric cancer: theoretical and practical considerations. Gut and Liver, 2016, 10.1: 12.
SHIN, Wing Sum, et al. Updated epidemiology of gastric cancer in Asia: decreased incidence but still a big challenge. Cancers, 2023, 15.9: 2639.
消化器系がんに戻る