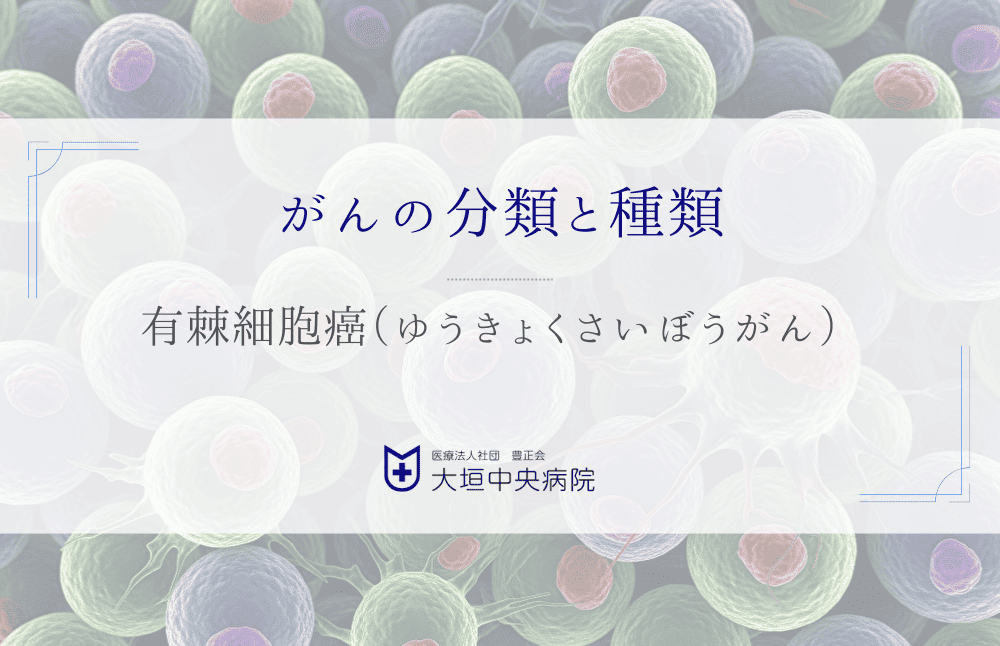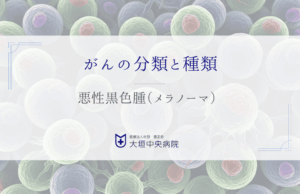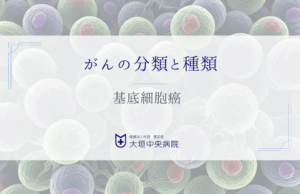有棘細胞癌(ゆうきょくさいぼうがん)は、私たちの体を覆う皮膚や、口の中、食道などの粘膜に発生する皮膚がんの一種です。
皮膚がんの中では基底細胞癌に次いで発生頻度が高く、早期発見と適切な治療が重要になります。
この記事では、有棘細胞癌がどのような病気なのか、その原因、症状の見た目、検査や治療法、そして他の皮膚がんとの見分け方まで、がんという病気に直面する患者さんやご家族が抱える疑問に答える形で、分かりやすく解説を進めます。
ご自身の症状と照らし合わせ、正しい知識を得るための一助としてください。
有棘細胞癌とは何か
まず、有棘細胞癌という病気の全体像を理解しましょう。このがんは、私たちの皮膚を構成する細胞の一つである「有棘細胞」が、がん化することによって発生します。
皮膚の表面に近い部分で起こるため、体の外から変化に気づきやすいという特徴があります。ここでは、その基本的な性質や特徴について掘り下げていきます。
皮膚の構造と有棘細胞の役割
私たちの皮膚は、外側から「表皮」「真皮」「皮下組織」の3層で構成されています。有棘細胞癌は、この最も外側にある表皮から発生します。
表皮はさらに4つの層に分かれており、有棘細胞は、表皮の大部分を占める「有棘層」を形成する細胞です。この細胞は、皮膚の構造を維持し、外部の刺激から体を守るバリア機能の一端を担っています。
この重要な役割を持つ細胞が、何らかの原因で異常に増殖を始めるのが有棘細胞癌です。
有棘細胞癌の基本的な特徴
| 項目 | 説明 | 重要度 |
|---|---|---|
| 発生母地 | 表皮の有棘細胞 | 高 |
| 主な原因 | 長年の紫外線曝露、慢性的な刺激、放射線など | 高 |
| 進行の特徴 | ゆっくりと進行するが、放置すると転移の可能性がある | 中 |
「がん」としての性質と進行
有棘細胞癌は悪性腫瘍であり、増殖して周囲の組織を破壊する性質を持ちます。初期の段階では皮膚の表面にとどまっていますが、進行すると皮膚の深い部分へと浸潤していきます。
さらに進行すると、リンパ管や血管に入り込み、リンパ節や他の臓器へ転移する可能性も出てきます。そのため、早期に発見し、がんが広がる前に治療を開始することが極めて大切です。
転移のリスクは、がんの大きさや発生した部位、がん細胞の悪性度によって異なります。
皮膚がんの中での有棘細胞癌の位置づけ
皮膚がんは、いくつかの種類に分類されます。その中で有棘細胞癌がどのような位置にあるのかを知ることは、病気の理解を深める上で役立ちます。
ここでは、代表的な皮膚がんとの比較を通じて、有棘細胞癌の相対的な特徴を明らかにします。
代表的な皮膚がんの種類
皮膚がんには主に3つの代表的な種類があります。それは「基底細胞癌」「有棘細胞癌」「悪性黒色腫(メラノーマ)」です。
このうち、有棘細胞癌と基底細胞癌は、悪性黒色腫に比べて発生頻度が高く、合わせて「非黒色腫皮膚がん」とも呼ばれます。それぞれの発生頻度や悪性度には違いがあります。
皮膚がんの種類別比較
| 種類 | 発生頻度 | 転移のしやすさ |
|---|---|---|
| 基底細胞癌 | 最も高い | まれ |
| 有棘細胞癌 | 2番目に高い | 可能性がある |
| 悪性黒色腫 | 比較的まれ | 高い |
有棘細胞癌の発生頻度と傾向
日本における有棘細胞癌の発生率は、高齢者を中心に増加傾向にあります。これは、主な原因である紫外線の影響が、長年の蓄積によって現れるためと考えられます。
特に、農業や漁業など、屋外での活動時間が長かった方に多く見られます。また、性別では男性にやや多く、発生部位は顔や頭部、手足など日光に当たりやすい場所が中心です。
これらの傾向を知っておくことで、リスクを意識した生活を送ることにつながります。
発生しやすい部位と初期に見られる変化
有棘細胞癌は体のどこにでも発生する可能性がありますが、特にできやすい部位が存在します。また、どのような見た目の変化として現れるのか、その初期症状を知ることは早期発見の第一歩です。
ここでは、具体的な発生部位と症状について、画像などをイメージしながら確認していきましょう。
日光にさらされやすい場所のリスク
有棘細胞癌の最大の原因は紫外線であるため、日光を浴びやすい部位に最も多く発生します。具体的には、顔(特に鼻、耳、唇)、頭部(特に毛髪の薄い部分)、首、そして手の甲や腕などです。
これらの部位は日常的に紫外線にさらされるため、皮膚の細胞がダメージを受けやすく、がん化のリスクが高まります。
特に注意すべき発生部位
- 顔面(鼻、耳、唇、まぶた)
- 頭部
- 首の後ろ
- 手の甲、前腕
初期症状の見た目と特徴
有棘細胞癌の初期症状は多様で、一つの決まった見た目があるわけではありません。多くの場合、赤みがかったしこりや、表面がカサカサして盛り上がった部分として現れます。
時には、治りにくいびらんや潰瘍(かいよう)の形をとることもあります。
ほくろとは異なり、いびつな形をしていることが多く、出血しやすかったり、かさぶたができてもすぐに剥がれてしまったりする特徴があります。
痛みやかゆみは伴わないことも多く、症状だけで判断するのは困難です。
初期症状の主な見た目
| 症状のタイプ | 見た目の特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 結節・腫瘤型 | 赤みを帯びた硬いしこり。表面がカリフラワー状になることも。 | 徐々に大きくなる。 |
| 潰瘍型 | 治りにくい傷やただれ。じくじくして出血しやすい。 | 数ヶ月以上治らない。 |
| 局面型 | 赤くカサカサした湿疹のような見た目。境界が不明瞭なことも。 | かゆみがない場合が多い。 |
有棘細胞癌の原因と関与するリスク要因
なぜ有棘細胞癌が発生するのでしょうか。その原因を理解することは、予防策を考える上で非常に重要です。
最も大きな原因は紫外線ですが、それ以外にもいくつかのリスク要因が関与していることがわかっています。
ここでは、がんを引き起こす可能性のある要因を詳しく見ていきます。
最大の原因である紫外線
長年にわたって紫外線を浴び続けることは、有棘細胞癌の最も重要な原因です。紫外線は皮膚の細胞のDNAにダメージを与え、これが修復されないまま蓄積すると、細胞ががん化する引き金となります。
特に、子供の頃から紫外線を多く浴びてきた人ほど、高齢になってから発症するリスクが高まります。日焼けを繰り返すことは、皮膚にとって大きな負担となります。
紫外線対策のポイント
- 日差しの強い時間帯(午前10時~午後2時)の外出を避ける
- 日焼け止めをこまめに塗り直す
- 帽子、日傘、長袖の衣服を活用する
その他のリスク要因
紫外線の他にも、有棘細胞癌の発生に関わる要因がいくつかあります。これらが単独、あるいは複合的に作用して発症につながると考えられています。
紫外線以外の主なリスク要因
| リスク要因 | 具体例 | 解説 |
|---|---|---|
| 慢性的な刺激や損傷 | 治らないやけどの痕、褥瘡(床ずれ)、放射線皮膚炎 | 長期間にわたる炎症が細胞のがん化を促すことがある。 |
| 特定の化学物質 | ヒ素、タール | 過去に職業などでこれらの物質に触れる機会があった場合。 |
| 免疫力の低下 | 臓器移植後の免疫抑制剤の使用、HIV感染症 | 体の防御機能が低下し、がん細胞の増殖を抑えきれなくなる。 |
| ヒトパピローマウイルス(HPV) | 特定の型のHPV感染 | 特に外陰部や肛門周囲に発生する癌との関連が指摘されている。 |
がんの進行と転移の特徴
有棘細胞癌がどのように進行し、体の他の部分に広がっていく(転移する)のかを理解することは、治療方針を決める上で大切です。
早期の段階では局所にとどまっていますが、進行すると周囲の組織や遠くの臓器に影響を及ぼす可能性があります。
局所での進行(浸潤)
発生した有棘細胞癌は、まずその場で大きくなり、皮膚の深い層へと根を伸ばすように広がっていきます。これを「浸潤」と呼びます。
がんが真皮や皮下組織にまで達すると、その下にある筋肉や骨にまで影響が及ぶこともあります。浸潤が深くなるほど、治療が複雑になり、体への負担も大きくなります。
リンパ節や他の臓器への転移
がん細胞がリンパ管や血管に入り込むと、血液やリンパの流れに乗って体の他の場所へと運ばれます。そして、別の場所で再び増殖を始めます。これが「転移」です。
有棘細胞癌が最初に転移しやすい場所は、がんが発生した部位の近くにあるリンパ節です。例えば、顔にできたがんの場合は首のリンパ節に転移することが多いです。
さらに進行すると、肺や肝臓、骨などの遠隔臓器に転移することもあります。転移が起こると、治療はより全身的なアプローチが必要になります。
進行度(ステージ)による分類
| ステージ | がんの状態 | 転移の有無 |
|---|---|---|
| 早期(0期~I期) | がんが小さい、または表皮内にとどまっている。 | なし |
| 中期(II期~III期) | がんが大きくなっている、または所属リンパ節に転移している。 | 所属リンパ節転移あり |
| 進行期(IV期) | 遠隔臓器に転移している。 | 遠隔転移あり |
有棘細胞癌のステージ別5年生存率(目安)
(日本皮膚悪性腫瘍学会などのデータを参考にした目安)
ステージI(2cm以下): 約95%以上
※早期に切除すれば、完治する可能性が非常に高いです。
ステージII(2cm超): 約80〜90%
ステージIII(リンパ節転移あり): 約50〜60%
※リンパ節に転移すると生存率が下がるため、早期発見が重要です。
ステージIV(遠隔転移あり): 30%未満
診断に用いられる検査と確認の流れ
皮膚に気になる変化を見つけた場合、それが有棘細胞癌かどうかを正確に判断するためには、専門医による診察と検査が必要です。診断は、主に皮膚科で行います。
ここでは、診断を確定させるためにどのような検査が行われるのか、その流れを解説します。
専門医による視診とダーモスコピー検査
まず、皮膚科医が病変部を直接目で見て、その形、色、大きさ、硬さなどを詳しく観察します(視診)。このとき、ダーモスコピーという特殊な拡大鏡を用いた検査を行うことが一般的です。
ダーモスコピー検査では、皮膚の表面の光の反射を抑え、皮膚の内部の色素や血管の状態を詳しく観察することができます。これにより、良性のほくろや他の皮膚疾患との見分け方の一助となります。
確定診断のための皮膚生検
視診やダーモスコピー検査で有棘細胞癌が疑われた場合、診断を確定するために皮膚生検を行います。
これは、病変部の一部または全部を局所麻酔下に小さく切り取り、その組織を顕微鏡で詳しく調べる病理組織検査です。この検査によって、がん細胞の有無や種類、悪性度などを正確に判断することができます。
有棘細胞癌の確定診断には、この皮膚生検が不可欠です。
診断までの主な流れ
- 皮膚科受診・問診
- 視診・触診
- ダーモスコピー検査
- 皮膚生検(病理組織検査)
- 確定診断
進行度を調べるための画像検査
皮膚生検で有棘細胞癌と診断が確定し、転移の可能性があると判断された場合には、がんの広がり具合を調べるための画像検査を追加で行います。
これにより、リンパ節や他の臓器への転移がないかを確認し、正確な進行度(ステージ)を決定します。この結果は、最適な治療法を選択する上で重要な情報となります。
広がりを調べる主な画像検査
| 検査の種類 | 調べる内容 |
|---|---|
| 超音波(エコー)検査 | 所属リンパ節への転移の有無 |
| CT検査 | リンパ節や肺、肝臓などへの転移の有無 |
| MRI検査 | がんの深さや周囲の組織への広がり |
| PET-CT検査 | 全身の遠隔転移の有無 |
治療法の種類と考え方
有棘細胞癌の治療は、がんの進行度、発生した部位、大きさ、患者さんの年齢や全身の状態などを総合的に考慮して決定します。治療の基本は、がんを完全に取り除くことです。
ここでは、主に行われる治療法について、それぞれの特徴を解説します。
第一選択となる外科的治療(手術)
有棘細胞癌の治療で最も基本となり、根治を目指せる可能性が高いのが手術による切除です。手術では、がん細胞の取り残しがないように、病変部から少し離れた正常な皮膚を含めて切除します。
切除した部分は、大きさや部位に応じて、縫い合わせたり、体の他の部分から皮膚を移植(皮弁形成や植皮)したりして閉じます。
切除した組織は、再度病理検査を行い、がんが完全に取りきれているか(断端陰性)を確認します。
手術が難しい場合の放射線治療
高齢であったり、他の病気を持っていたりするために手術が難しい場合や、手術で重要な機能(例えば顔の表情など)が損なわれるリスクが高い場合には、放射線治療を選択することがあります。
放射線治療は、高エネルギーのX線をがんに照射して、がん細胞を破壊する治療法です。また、手術後に再発のリスクが高いと判断された場合に、補助的な治療として行うこともあります。
進行した場合の薬物療法(化学療法)
がんがリンパ節や他の臓器に転移しており、手術や放射線治療だけでは治療が困難な進行期の場合には、薬物療法を行います。
抗がん剤を用いた化学療法や、近年進歩が著しい免疫チェックポイント阻害薬などが用いられます。これらの治療は、がんの増殖を抑え、症状を和らげることを目的として行います。
主な治療法の選択
| 治療法 | 主な対象 | 目的 |
|---|---|---|
| 外科的治療(手術) | 転移のない早期のがん | 根治(がんを完全に取り除く) |
| 放射線治療 | 手術が困難な場合、手術後の補助療法 | がんの制御、再発予防 |
| 薬物療法 | 転移・再発した進行がん | がんの進行抑制、症状緩和 |
治療後の経過観察と再発予防
治療が無事に終了した後も、定期的な通院による経過観察が重要です。これは、治療した場所にがんが再発していないか、あるいは別の場所に新しいがんが発生していないかを確認するためです。
また、日常生活においては、再発予防のために紫外線対策を徹底することが大切になります。
定期的な通院と検査
治療後は、医師の指示に従って定期的に皮膚科を受診します。診察では、治療した部位の視診や触診のほか、必要に応じてリンパ節のエコー検査などを行います。
通院の頻度は、がんの進行度や再発のリスクに応じて異なりますが、通常は治療後5年間程度は経過を観察します。何か気になる変化があれば、次の予約を待たずに早めに相談することが大切です。
セルフチェックの重要性
日頃からご自身の皮膚の状態に関心を持ち、セルフチェックを行う習慣をつけましょう。
特に、治療した部位の周りや、日光に当たりやすい部位を注意深く観察します。鏡を使って、背中や頭部など見えにくい場所も確認することが重要です。
セルフチェックで確認するポイント
- 以前治療した場所に新しいしこりや赤みがないか
- 治りにくい傷やただれができていないか
- ほくろの形や色が変化していないか
- 首や脇の下、足の付け根のリンパ節が腫れていないか
再発予防のための紫外線対策
有棘細胞癌の最大の原因である紫外線を避けることは、再発予防だけでなく、新しい皮膚がんの発生を防ぐためにも極めて重要です。治療後も、生涯を通じて紫外線対策を継続していく必要があります。
これは、一度皮膚がんになった方は、別のがんが発生するリスクが一般の人より高いと考えられているためです。
よくある質問
有棘細胞癌と診断されたり、その疑いがあると指摘されたりした際に、多くの患者さんが抱く疑問についてお答えします。
- 有棘細胞癌に痛みやかゆみはありますか?
-
初期段階では、痛みやかゆみといった自覚症状がないことがほとんどです。そのため、見た目の変化に気づいても放置してしまうケースが少なくありません。
がんが進行して大きくなったり、潰瘍を形成したりすると、痛みや出血を伴うことがあります。症状がないからといって安心せず、気になる変化があれば専門医の診察を受けることが重要です。
- ほくろやシミとの見分け方を教えてください。
-
一般の方がほくろやシミと有棘細胞癌を正確に見分けることは非常に困難です。有棘細胞癌は、一般的なほくろのように黒褐色ではなく、赤みを帯びた皮膚の色に近いことが多いです。
また、表面がカサカサしていたり、硬いしこりとして触れたり、形がいびつであったりする点が特徴です。しかし、見た目だけでの自己判断は危険です。
急に大きくなってきた、形が変わった、出血するようになったなどの変化があれば、皮膚科を受診してください。
- 治療にかかる期間はどのくらいですか?
-
治療期間は、選択される治療法やがんの進行度によって大きく異なります。早期がんで、単純な手術による切除で済む場合は、日帰り手術や数日の入院で完了することが多いです。
皮膚移植などが必要な大きな手術や、放射線治療、薬物療法を行う場合は、数週間から数ヶ月にわたる治療が必要となります。
具体的な期間については、ご自身の状況に合わせて主治医から説明があります。
- 転移や再発の可能性はどのくらいありますか?
-
転移や再発のリスクは、がんの大きさ、深さ(浸潤の程度)、発生部位、細胞の悪性度などによって変わります。
一般的に、早期に発見され、腫瘍が小さく浅い段階で適切に治療された場合の再発率は低いとされています。
しかし、発見が遅れたり、がんが大きかったり、神経の周りに浸潤していたりするようなケースでは、転移・再発のリスクが高くなります。そのため、治療後の定期的な経過観察が非常に重要になるのです。
有棘細胞癌について解説してきましたが、皮膚がんには他にも注意すべき種類があります。
特に、進行が速く転移しやすい性質を持つ「悪性黒色腫(メラノーマ)」は、有棘細胞癌や基底細胞癌とは異なる特徴を持ち、早期発見がさらに重要になるがんです。
悪性黒色腫は、ほくろによく似た見た目をしていることが多く、「ほくろのがん」とも呼ばれます。足の裏や爪など、普段あまり意識しない場所に発生することもあります。
有棘細胞癌との違いを理解し、皮膚がん全般についての知識を深めるために、ぜひ「悪性黒色腫(メラノーマ)」に関する記事もあわせてお読みください。
参考文献
HUSSEIN, Mahmoud R. Ultraviolet radiation and skin cancer: molecular mechanisms. Journal of cutaneous pathology, 2005, 32.3: 191-205.
COZMA, Elena-Codruta, et al. Update on the molecular pathology of cutaneous squamous cell carcinoma. International Journal of Molecular Sciences, 2023, 24.7: 6646.
ANDREASSI, Lucio. UV exposure as a risk factor for skin cancer. Expert Review of Dermatology, 2011, 6.5: 445-454.
SCHMITT, J., et al. Occupational ultraviolet light exposure increases the risk for the development of cutaneous squamous cell carcinoma: a systematic review and meta‐analysis. British Journal of Dermatology, 2011, 164.2: 291-307.
LAZO DE LA VEGA, Lorena, et al. Invasive squamous cell carcinomas and precursor lesions on UV-exposed epithelia demonstrate concordant genomic complexity in driver genes. Modern Pathology, 2020, 33.11: 2280-2294.
YAN, Guorong, et al. Single-cell transcriptomic analysis reveals the critical molecular pattern of UV-induced cutaneous squamous cell carcinoma. Cell Death & Disease, 2021, 13.1: 23.
MOLHO-PESSACH, Vered; LOTEM, Michal. Ultraviolet radiation and cutaneous carcinogenesis. CURRENT PROBLEMS IN DERMATOLOGY-BASEL-, 2007, 35: 14.
CIĄŻYŃSKA, Magdalena, et al. Ultraviolet radiation and chronic inflammation—Molecules and mechanisms involved in skin carcinogenesis: A narrative review. Life, 2021, 11.4: 326.
GREEN, Adèle C.; OLSEN, C. M. Cutaneous squamous cell carcinoma: an epidemiological review. British Journal of Dermatology, 2017, 177.2: 373-381.
WUNDERLICH, K., et al. Risk factors and innovations in risk assessment for melanoma, basal cell carcinoma, and squamous cell carcinoma. Cancers, 2024, 16.5: 1016.
皮膚がんに戻る