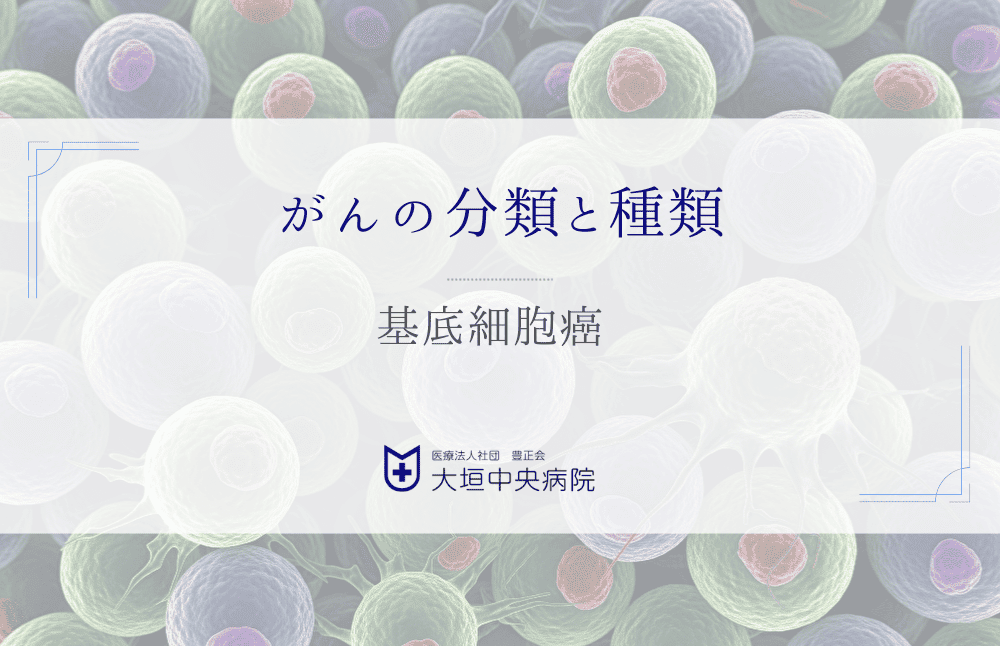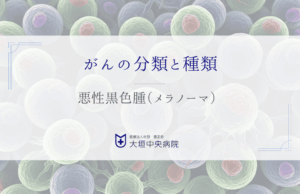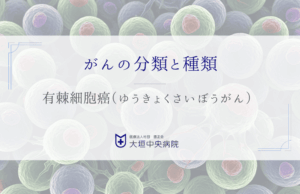「皮膚に、いつの間にか新しいほくろのようなものができた」「治りにくい傷やかさぶたがある」と感じていませんか。
それは、最も頻度の高い皮膚がんである「基底細胞癌」のサインかもしれません。このがんは進行が非常にゆっくりで、転移することは極めてまれですが、放置すると周囲の組織を破壊する性質を持ちます。
特に顔や鼻など、日光に当たりやすい部位に発生することが多いのが特徴です。
この記事では、基底細胞癌の基本的な知識から、症状の見分け方、原因、診断、そして治療法に至るまで、専門的な情報を分かりやすく解説します。
基底細胞癌とは何か
私たちの体の一番外側を覆う皮膚は、さまざまな細胞から成り立っています。基底細胞癌は、その皮膚を構成する細胞の一つが、がん化することで発生します。
数ある皮膚がんの中でも、最も発生頻度が高いがんであり、その性質を正しく知ることが早期発見と適切な対応につながります。
最も一般的な皮膚がん
基底細胞癌は、世界的に見ても最も一般的な皮膚がんです。白色人種で特に多く見られますが、日本人を含む有色人種でも決して珍しい病気ではありません。
高齢者に多く発生する傾向があり、年齢を重ねるにつれてそのリスクは高まります。幸いなことに、他のがんと比べて性質がおとなしく、早期に発見して治療すれば、多くの場合、完全に治すことが可能です。
表皮の基底細胞から発生
皮膚は外側から「表皮」「真皮」「皮下組織」の三層構造になっています。基底細胞癌は、この一番外側にある表皮の最も深い層、基底層を構成する「基底細胞」またはそれに類似した細胞から発生します。
基底細胞は、新しい表皮細胞を生み出す役割を担っており、常に分裂を繰り返しています。この細胞の遺伝子に異常が生じることが、がん発生の始まりと考えられています。
基底細胞の役割
基底細胞は、皮膚の新陳代謝、いわゆるターンオーバーの源となる重要な細胞です。
この細胞が分裂し、新しい細胞が上へ上へと押し上げられていくことで、私たちの皮膚は常に新しく生まれ変わり、バリア機能や保湿機能を維持しています。
この重要な役割を担う細胞ががん化するため、その性質を理解することが大切です。
皮膚がんの中での基底細胞癌の特徴
基底細胞癌は「がん」という名前がついていますが、胃がんや肺がんなど、一般的に知られる内臓のがんとは大きく異なる特徴を持っています。
その最大の特徴は、進行が非常にゆっくりであることと、転移の可能性が極めて低い点にあります。この性質を理解することで、過度に恐れることなく、冷静に対処できます。
進行が非常にゆっくり
基底細胞癌の成長速度は非常に遅く、数年をかけて少しずつ大きくなるのが一般的です。そのため、初期の段階では本人も気づかないことが少なくありません。
例えば、小さなほくろやシミのように見え、何年も変化がないように感じられることもあります。しかし、ゆっくりではあっても確実に成長し、放置すれば周囲の組織に影響を及ぼします。
他の皮膚がんとの進行速度比較
| 皮膚がんの種類 | 主な特徴 | 進行速度の目安 |
|---|---|---|
| 基底細胞癌 | 最も頻度が高い。転移はまれ。 | 非常にゆっくり(年単位) |
| 有棘細胞癌 | 転移の可能性がある。 | 比較的ゆっくり(月〜年単位) |
| メラノーマ | 悪性度が高い。早期から転移しやすい。 | 速い(週〜月単位) |
転移の可能性は極めて低い
基底細胞癌のもう一つの大きな特徴は、血液やリンパの流れに乗って他の臓器へ広がる「転移」が極めてまれである点です。
転移の確率は0.1%以下ともいわれ、皮膚がんの中でも特におとなしい性質を持つがんといえます。このため、生命に直接的な危険を及ぼすことはほとんどありません。
局所破壊性という性質
転移はまれですが、基底細胞癌には「局所破壊性」という無視できない性質があります。
これは、がんがその場で深く、そして広く浸潤し、周囲の正常な皮膚や、さらには軟骨や骨といった深部の組織まで破壊しながら進行していく性質のことです。
特に顔面に発生した場合、目や鼻、耳などの重要な器官を破壊し、機能的、整容的に大きな問題を引き起こす可能性があります。早期治療が重要なのは、この局所破壊を防ぐためです。
基底細胞癌の予後と治療成績(目安)
(日本皮膚悪性腫瘍学会ガイドライン等を参考)
5年生存率: ほぼ100%
※転移することは極めて稀(0.1%以下)なため、早期に発見して切除すれば、命に関わることはほとんどありません。
手術による根治率: 95%以上
※適切な手術で完全に取り切れば、再発することも稀です。ただし、顔面などでギリギリの切除になった場合は再発に注意が必要です。
発生しやすい部位と見た目の特徴
基底細胞癌がどこにできやすいのか、そしてどのような見た目をしているのかを知ることは、早期発見のための第一歩です。
多くの場合、特徴的な部位と見た目があり、セルフチェックの際の重要な手がかりとなります。
日光に当たりやすい部位
基底細胞癌は、長年の紫外線の影響が主な原因と考えられているため、日光に当たりやすい体の部位に発生する傾向があります。これを「光線露出部」と呼びます。
具体的には、顔、頭部、首、手の甲などが挙げられます。
顔や鼻、頭部が好発部位
特に顔は、基底細胞癌の80%以上が発生する最も多い部位です。中でも、鼻、まぶた、耳は好発部位として知られています。
日本人では、欧米人と比較してまぶた、特に内側の部分(内眼角)に発生する頻度が高いという特徴があります。これらの部位に治りにくいできものや傷ができた場合は、注意が必要です。
発生しやすい部位
| 順位 | 部位 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1位 | 鼻 | 顔の中でも最も突出し、紫外線を浴びやすいため。 |
| 2位 | まぶた | 特に目頭(内眼角)に多い傾向がある。 |
| 3位 | 顔のその他の部位 | 頬、額、耳など、日光が当たる場所全般。 |
初期症状と見分け方
基底細胞癌の初期症状は非常に多様で、一見するとがんだとは分かりにくいことが多いです。最も一般的なのは、少し盛り上がった黒色や肌色の結節(しこり)です。
表面はろうそくの「ろう」のような光沢を帯びていることがあり、よく見ると細い血管が浮き出て見えることもあります。
ほくろとの違い
特に黒色のものは、ほくろ(母斑細胞母斑)との見分け方が重要になります。
一般的なほくろは形が左右対称に近く、境界がはっきりしているのに対し、基底細胞癌は形が非対称であったり、境界が不鮮明であったりすることがあります。
また、中心部が潰瘍になってへこんだり、簡単に出血してかさぶたができたりする点も、ほくろにはあまり見られない特徴です。
ほくろと基底細胞癌の見た目の違い
| 項目 | ほくろ(良性) | 基底細胞癌(悪性) |
|---|---|---|
| 色 | 均一な黒色や茶色 | 黒色、まだらな色調、ろう様の光沢 |
| 形 | 円形や楕円形で左右対称に近い | いびつな形で左右非対称 |
| 表面 | なめらか | 潰瘍、出血、かさぶたを伴うことがある |
典型的な見た目の種類
基底細胞癌は、その見た目からいくつかのタイプ(病型)に分類されます。これを知っておくと、より深く理解できます。
- 結節型:最も多く、黒色でドーム状に盛り上がる。
- 表在型:赤みがかった平坦な病変で、湿疹に似る。
- 斑状強皮症型:白く硬い瘢痕(きずあと)のように見える。
基底細胞癌の原因と関わるリスク要因
基底細胞癌がなぜ発生するのか、その原因を知ることは予防につながります。最大の原因は紫外線ですが、それ以外にもいくつかのリスク要因が関わっていることが分かっています。
最大の原因は紫外線
基底細胞癌の発生における最大の原因は、太陽光に含まれる紫外線(UV)です。特に、子供の頃から長年にわたって紫外線を浴び続けたことによる「生涯紫外線曝露量」が大きく関わっています。
紫外線は皮膚細胞のDNAにダメージを与え、これが修復されないまま蓄積することで、細胞のがん化を引き起こすと考えられています。
長年の紫外線曝露の蓄積
若い頃に浴びた紫外線が、何十年も経ってから基底細胞癌として現れることも少なくありません。そのため、高齢者にこのがんが多いのは、長年の紫外線ダメージが蓄積した結果といえます。
日焼けを繰り返してきた人や、屋外での活動時間が長かった人は、特に注意が必要です。
紫外線対策のポイント
| 対策 | 具体的な方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 日焼け止め | SPF30、PA++以上のものをこまめに塗り直す | 汗をかいたら2〜3時間おきに |
| 衣類 | 帽子、サングラス、長袖の服を着用する | UVカット機能のある素材を選ぶ |
| 時間帯 | 紫外線が強い午前10時から午後2時の外出を避ける | 日陰を利用する |
その他のリスク要因
紫外線の他にも、いくつかの要因が基底細胞癌のリスクを高めることが知られています。肌の色が白い人、そばかすができやすい人は、紫外線に対する感受性が高いため、リスクが高いとされています。
また、過去に放射線治療を受けた部位や、治りにくい傷、やけどの痕から発生することもあります。
その他、免疫抑制剤を使用している人や、特定の遺伝性疾患を持つ人もリスクが高まることが報告されています。
がんの進行と転移の可能性
基底細胞癌はゆっくりと進行し、転移はまれですが、放置すれば局所で大きな問題を引き起こす可能性があります。
がんがどのように広がり、どのような影響を及ぼすのかを理解しておくことが大切です。
局所での進行
基底細胞癌は、発生した場所でゆっくりと、しかし着実に大きくなっていきます。最初は表皮内にとどまっていますが、時間が経つにつれて下の層である真皮、さらに深い皮下組織へと浸潤していきます。
この広がり方は、アリが巣を広げるように、不規則な形で周囲に伸びていくことが多いです。そのため、表面に見えている大きさよりも、実際にはがんが広がっている範囲が広いことがあります。
深部組織への浸潤
さらに進行すると、がん細胞は筋肉や軟骨、骨といった深部の組織にまで達し、これらを破壊します。
例えば、鼻にできた基底細胞癌を放置すると、鼻の軟骨を破壊して変形させたり、目の近くにできた場合は眼球に影響を及ぼしたりする可能性があります。
これが「局所破壊性」と呼ばれる、基底細胞癌の最も警戒すべき特徴です。
まれな転移のリスク
前述の通り、基底細胞癌の転移は極めてまれです。しかし、ゼロではありません。
特に、非常に大きくなった腫瘍(長径が数cm以上)、治療後に何度も再発を繰り返す腫瘍、あるいは免疫力が低下している患者さんでは、転移のリスクがわずかに高まるとされています。
転移先としては、所属リンパ節(がんの近くにあるリンパ節)や肺、骨などが報告されていますが、その頻度は極めて低いです。
診断の流れと確認に用いられる検査
皮膚に疑わしい病変を見つけた場合、正確な診断を下すためには専門医による診察と検査が必要です。診断は通常、いくつかの段階を経て確定します。
ここでは、皮膚科で行われる一般的な診断の流れを紹介します。
皮膚科での視診とダーモスコピー検査
まず、皮膚科専門医が病変を直接目で見て、その色や形、大きさ、表面の状態などを詳しく観察します(視診)。このとき、基底細胞癌に特徴的な所見がないかを確認します。
次に、ダーモスコピーという特殊な拡大鏡を用いて、病変をさらに詳しく観察します。この検査は痛みもなく、その場ですぐに行えます。
ダーモスコピーで見る特徴的な所見
ダーモスコピー検査では、肉眼では見えない皮膚の内部構造や血管のパターンを観察できます。
基底細胞癌の場合、「樹枝状血管」と呼ばれる木の枝のように分岐する血管や、「葉状構造」と呼ばれる葉っぱのような色素沈着など、診断の手がかりとなる特徴的な所見が認められることがあります。
これにより、ほくろや他の皮膚疾患との見分けがある程度可能になります。
診断の流れ
| 段階 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 問診・視診 | いつからあるか、症状などを聞き、目で観察する | 病変の全体像を把握する |
| ダーモスコピー検査 | 特殊な拡大鏡で詳細に観察する | 良性か悪性かの判断材料を得る |
| 皮膚生検 | 病変の一部を採取し、顕微鏡で調べる | がん細胞の有無を確認し、診断を確定する |
確定診断のための皮膚生検
視診やダーモスコピー検査で基底細胞癌が強く疑われた場合、診断を確定するために皮膚生検を行います。
これは、局所麻酔をした上で、病変の一部(または小さいものであれば全体)をメスや特殊な器具で切り取り、それを病理組織検査に提出するものです。
病理専門医が顕微鏡で組織を詳しく観察し、がん細胞の有無や種類を最終的に判断します。この結果をもって、基底細胞癌であるという確定診断が下されます。
治療の選択肢と考え方
基底細胞癌の診断が確定したら、次に治療方針を決定します。治療の第一の目的は、がん細胞を完全に取り除くことです。
治療法はいくつかありますが、がんの大きさや場所、患者さんの状態などを総合的に考慮して、最も適した方法を選択します。
第一選択となる外科的治療
基底細胞癌の治療において、最も標準的で確実な方法は、がん細胞を外科的に切除することです。がんの周囲にある正常な皮膚をわずかに含めて(安全マージン)、病変を完全に切り取ります。
切除した組織は病理検査で詳しく調べ、がんが完全に取りきれているか(断端陰性)を確認します。
単純切除術
比較的小さな基底細胞癌に対して行われる最も一般的な手術です。
病変の周囲に数ミリの安全マージンをつけて紡錘形に切除し、傷を縫い合わせます。多くの場合、局所麻酔による日帰り手術が可能です。
モース手術(Mohs手術)
顔面などの重要な部位にできた場合や、再発した場合、境界が不鮮明な場合などに行われる特殊な手術です。
この手術では、切除した組織をその場ですぐに顕微鏡で調べ、がん細胞が残っていないかを確認しながら、最小限の範囲で切除を進めます。正常な組織を最大限温存できるという利点があります。
主な治療法の比較
| 治療法 | 対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| 外科的切除 | ほとんどの基底細胞癌 | 根治性が最も高い標準治療。 |
| 放射線治療 | 高齢者、手術が困難な部位 | 傷跡が残りにくいが、治療期間が長い。 |
| 凍結療法 | ごく初期の小さな病変 | 液体窒素でがん細胞を凍結壊死させる。 |
手術以外の治療法
手術が困難な場合や、患者さんが手術を希望しない場合には、他の治療法を選択することもあります。
ただし、これらの治療法は外科的切除に比べて再発率がやや高い傾向があるため、適応を慎重に判断する必要があります。
放射線治療
高齢であったり、合併症のために手術が難しい場合や、手術で大きな変形が予想される部位(まぶたや唇など)に有効な治療法です。
高エネルギーのX線をがんに照射して、がん細胞を破壊します。治療には数週間の通院が必要です。
凍結療法や外用薬
ごく初期の小さな病変(特に体の表面の表在型)に対しては、液体窒素でがん細胞を凍結させて破壊する凍結療法や、免疫に働きかける塗り薬(イミキモドクリーム)などが用いられることもあります。
これらの治療は体への負担が少ないという利点があります。
治療後の経過観察と生活上の注意点
治療が無事に終了した後も、再発や新たな皮膚がんの発生に注意するため、定期的な経過観察が重要です。また、日常生活においても、皮膚がんのリスクを減らすための心がけが大切になります。
定期的な皮膚科の受診
治療後は、医師の指示に従って定期的に皮膚科を受診し、専門医によるチェックを受ける必要があります。
受診の頻度は、がんの進行度や治療法によって異なりますが、通常は治療後数年間は数ヶ月に一度、その後は年に一度程度の経過観察を行います。
再発のモニタリング
基底細胞癌は、適切に治療すれば再発率は低いですが、ゼロではありません。特に治療した部位の周辺に再発することがあります。
定期的な診察では、治療した部位の傷跡の状態や、その周辺に新しい病変ができていないかを注意深く観察します。
また、基底細胞癌になった人は、体の別の場所に新たな皮膚がん(基底細胞癌を含む)が発生するリスクが一般の人より高いことが知られているため、全身の皮膚をチェックすることも重要です。
セルフチェックの重要性
定期的な受診と合わせて、月に一度は自分自身で全身の皮膚をチェックする習慣をつけましょう。鏡を使って、背中や頭皮など、見えにくい場所も忘れずに確認することが大切です。
セルフチェックのポイント
- 新しくできたほくろやシミはないか
- 以前からあるほくろの形や色に変化はないか
- 治りにくい傷や、繰り返し出血するかさぶたはないか
- 赤みやただれが続いている部分はないか
紫外線対策の徹底
基底細胞癌の最大の原因は紫外線であるため、治療後も紫外線対策を徹底することが、再発や新たな皮膚がんの予防に非常に重要です。
日常生活の中で、日焼け止めを塗る、帽子や長袖の衣服を着用するなど、基本的な対策を継続しましょう。
基底細胞癌に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、基底細胞癌について患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。疑問や不安の解消にお役立てください。
- 痛みや痒みなどの症状はありますか?
-
基底細胞癌は、初期の段階では痛みや痒みといった自覚症状がほとんどないのが特徴です。そのため、本人が気づかないうちに進行していることがあります。
がんが大きくなり、中心部が崩れて潰瘍になると、出血しやすくなったり、軽い痛みを感じたりすることがあります。
症状がないからといって安心せず、見た目の変化に注意することが大切です。
- 放置するとどうなりますか?
-
進行は非常にゆっくりですが、放置すれば局所で大きくなり、周囲の正常な組織を破壊していきます。
特に顔面にできた場合、目、鼻、耳などの機能に障害をきたしたり、外見上の大きな変形を引き起こしたりする可能性があります。
転移はまれですが、命に関わらないからと軽視せず、早期に治療を受けることが重要です。
- 治療後の傷跡は残りますか?
-
外科的な切除を行う場合、傷跡はどうしても残ります。
しかし、皮膚科や形成外科の医師は、皮膚のしわの方向に沿って切開したり、特殊な縫合法を用いたりするなど、傷跡ができるだけ目立たなくなるように工夫します。
治療後の傷跡の見た目は、がんの大きさや場所、個人の体質によって異なります。傷跡が気になる場合は、担当医に相談してください。
- メラノーマとの違いは何ですか?
-
基底細胞癌とメラノーマは、どちらも黒く見えることがあるため混同されがちですが、全く異なる種類の皮膚がんです。
基底細胞癌は進行が遅く転移がまれなのに対し、メラノーマは進行が速く転移しやすいため、早期発見・早期治療が極めて重要です。見分け方としては、ダーモスコピー検査が非常に有用です。
自己判断は危険ですので、気になるほくろやシミがあれば、必ず皮膚科を受診してください。
基底細胞癌の次に多い皮膚がんとして「有棘細胞癌」があります。有棘細胞癌も紫外線が主な原因ですが、基底細胞癌とは異なり、転移を起こす可能性があります。
見た目も、赤く盛り上がったしこりや、表面が崩れて潰瘍になるなど、特徴が異なります。
皮膚がんについての理解をさらに深めるために、有棘細胞癌に関する情報もあわせてご覧になることをお勧めします。
二つのがんの違いを知ることで、ご自身の皮膚の状態をより正確に把握し、適切な行動をとる助けとなります。
参考文献
WOJTOWICZ, Irena; ŻYCHOWSKA, Magdalena. Dermoscopy of basal cell carcinoma part 3: differential diagnosis, treatment monitoring and novel technologies. Cancers, 2025, 17.6: 1025.
ALTAMURA, Davide, et al. Dermatoscopy of basal cell carcinoma: morphologic variability of global and local features and accuracy of diagnosis. Journal of the American Academy of Dermatology, 2010, 62.1: 67-75.
KARAMPINIS, Emmanouil, et al. Clinical and dermoscopic patterns of basal cell carcinoma and its mimickers in skin of color: a practical summary. Medicina, 2024, 60.9: 1386.
TRIGONI, A., et al. Dermoscopic features in the diagnosis of different types of basal cell carcinoma: a prospective analysis. Hippokratia, 2012, 16.1: 29.
LALLAS, Aimilios, et al. Dermoscopy in the diagnosis and management of basal cell carcinoma. Future Oncology, 2015, 11.22: 2975-2984.
LALLAS, A., et al. Dermoscopy uncovers clinically undetectable pigmentation in basal cell carcinoma. British Journal of Dermatology, 2014, 170.1: 192-195.
WOJTOWICZ, Irena; ŻYCHOWSKA, Magdalena. Dermoscopy of basal cell carcinoma part 1: dermoscopic findings and diagnostic accuracy—a systematic literature review. Cancers, 2025, 17.3: 493.
REITER, Ofer, et al. The diagnostic accuracy of dermoscopy for basal cell carcinoma: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Dermatology, 2019, 80.5: 1380-1388.
SERRANO, Carmen, et al. Clinically inspired skin lesion classification through the detection of dermoscopic criteria for basal cell carcinoma. Journal of Imaging, 2022, 8.7: 197.
ÜRÜN, Yıldız Gürsel, et al. Clinical, dermoscopic and histopathological evaluation of basal cell carcinoma. Dermatology Practical & Conceptual, 2023, 13.1: e2023004.
皮膚がんに戻る