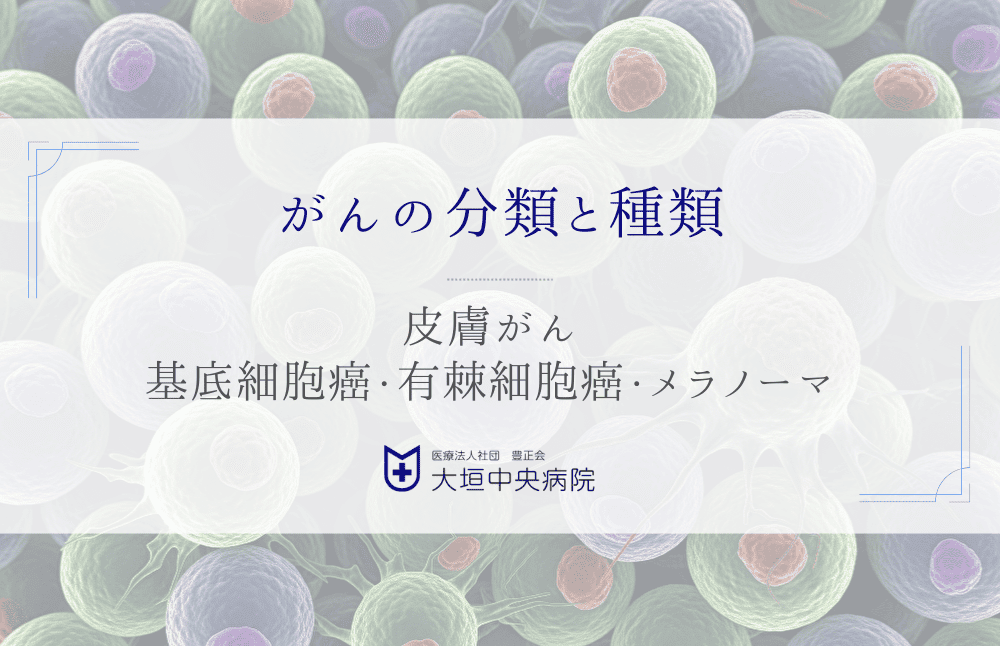皮膚がんは、私たちの体を覆う皮膚に発生する悪性腫瘍の総称です。皮膚は常に外部の刺激にさらされており、特に紫外線の影響を大きく受けます。
多くの場合、皮膚がんの初期症状はしみやほくろ、治りにくい傷などと似ているため、見過ごされることも少なくありません。しかし、早期に発見し、適切な治療を開始することが非常に重要です。
この記事では、代表的な皮膚がんである「基底細胞癌」「有棘細胞癌」「悪性黒色腫(メラノーマ)」の3種類を中心に、それぞれの特徴、症状、原因、治療法について詳しく解説します。
基底細胞癌 - 皮膚にできる最も多い皮膚がん
基底細胞癌は、皮膚がんの中で最も発生頻度が高いがんです。皮膚の最も外側にある表皮の最下層、基底層の細胞や、毛根を包む組織から発生します。
進行は非常に緩やかで、他の臓器に転移することは極めてまれですが、局所での破壊性が高いため、早期の治療が大切です。特に顔面に好発するため、美容的な観点からも注意が必要です。
基底細胞癌とは
このがんは、表皮の基底細胞に似た性質を持つ細胞が増殖して発生します。主に高齢者の顔面、特に鼻、まぶた、耳の周辺など、長年にわたり日光を浴びてきた部位によく見られます。
ゆっくりと大きくなるため、初期段階では痛みやかゆみなどの自覚症状がほとんどありません。そのため、小さなほくろやできものだと思い、放置してしまうケースも多いのが特徴です。
主な症状と特徴
基底細胞癌の見た目は多様ですが、いくつかの典型的なパターンがあります。早期の段階でこれらの特徴を知っておくことが、早期発見につながります。
見た目の特徴
最も一般的なのは、わずかに盛り上がった黒色または半透明のできものです。表面はろうそくの蝋のような光沢を持ち、よく見ると細い血管が浮き出て見えることがあります。
中央部がへこんで潰瘍のようになり、簡単に出血したり、かさぶたができたりすることを繰り返す場合もあります。色は黒いことが多いため、ほくろと見分けるのが難しいこともあります。
発生しやすい部位
基底細胞癌の約80%は、頭部や顔面に発生します。これは、生涯を通じて紫外線にさらされる量が最も多い部位であることと深く関係しています。特に、鼻、まぶた、耳介、額、頬などが好発部位です。
まれに、日光にあまり当たらない体幹や手足に発生することもあります。
原因とリスク要因
基底細胞癌の発生には、複数の要因が関与していますが、最大の危険因子は紫外線です。長期間にわたる紫外線の蓄積が、皮膚細胞の遺伝子にダメージを与え、がん化を引き起こすと考えられています。
紫外線
紫外線B波(UVB)が主な原因とされています。子供の頃から屋外で過ごす時間が長かった人や、色白で日光にあたると赤くなりやすい肌タイプ(スキンタイプⅠ、Ⅱ)の人は、特に注意が必要です。
紫外線対策を怠ってきた場合、高齢になってから発症するリスクが高まります。
その他の要因
紫外線以外にも、やけどの痕や外傷の痕、放射線治療を受けた部位から発生することがあります。また、免疫抑制剤を使用している人や、特定の遺伝性疾患を持つ人も発症しやすい傾向があります。
検査と診断
皮膚に疑わしいできものを見つけた場合、皮膚科専門医による診察を受けます。診断は、視診とダーモスコピー検査、そして確定診断のための皮膚生検によって行います。
ダーモスコピー検査
ダーモスコピーは、特殊な拡大鏡を用いて皮膚の表面を詳しく観察する検査です。
光の乱反射を抑えることで、皮膚の内部の色素や血管のパターンを詳細に見ることができ、悪性か良性かの判断に役立ちます。患者さんへの負担が少ない非常に有用な検査です。
皮膚生検
確定診断のためには、病変の一部または全部を切り取り、顕微鏡で調べる病理組織検査が必要です。これを皮膚生検と呼びます。局所麻酔下で行うため、痛みはほとんどありません。
この検査によって、がんの種類や悪性度を正確に判断します。
治療法
基底細胞癌の治療は、がんを完全に取り除くことを目的とします。治療法は、がんの大きさ、場所、種類、患者さんの状態などを総合的に考慮して決定します。
外科的切除
最も標準的な治療法は、がんの周囲の正常な皮膚を数ミリ含めて切除する外科手術です。切除した組織を病理検査で詳しく調べ、がんが完全に取りきれているか(断端陰性)を確認します。
顔面など、整容性が重要な部位では、できるだけ傷跡が目立たないように工夫します。
その他の治療選択肢
手術が難しい場合や、非常に初期のがんに対しては、液体窒素でがん細胞を凍結させる凍結療法、特殊な光に反応する薬剤を用いる光線力学療法、放射線治療、抗がん剤の塗り薬などが選択されることもあります。
基底細胞癌の主な治療法の比較
| 治療法 | 特徴 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 外科的切除 | がんを完全に取り除くことを目指す標準的な治療。切除範囲の確認が可能。 | ほとんどの基底細胞癌。 |
| 放射線治療 | 手術が困難な部位や高齢者に適用。治療期間が長くなることがある。 | まぶた、鼻、唇など手術が難しい部位。 |
| 凍結療法 | 液体窒素でがん細胞を破壊する。傷跡が残ることがある。 | 小さく、表面的ながん。 |
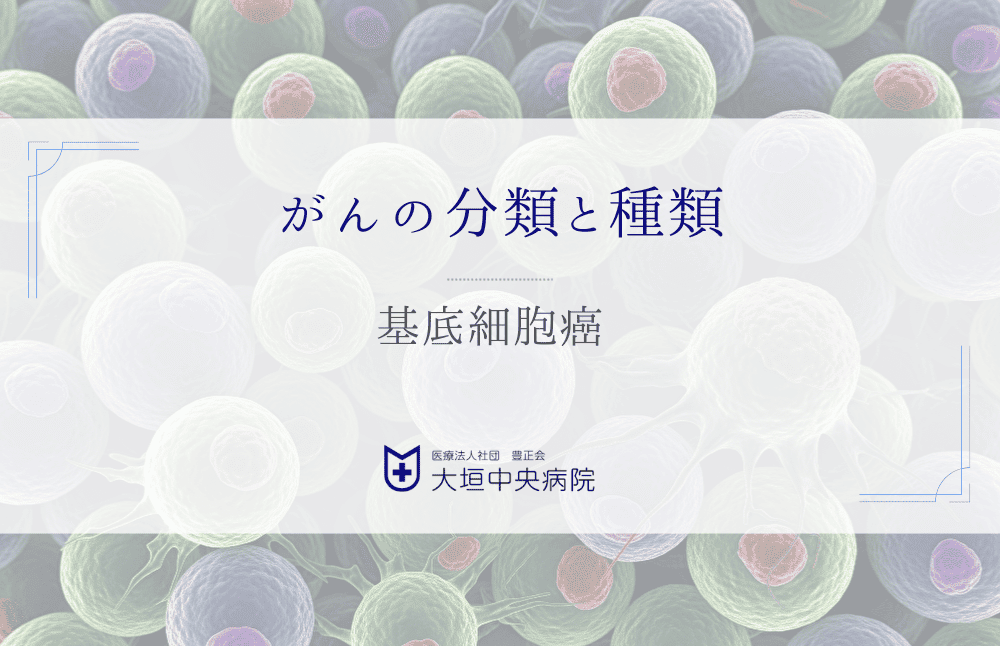
有棘細胞癌 - 皮膚や粘膜に発生する代表的な皮膚がん
有棘細胞癌は、基底細胞癌に次いで発生頻度の高い皮膚がんです。表皮の中層にある有棘細胞から発生します。
基底細胞癌とは異なり、進行するとリンパ節や他の臓器に転移する可能性があるため、より注意深い経過観察と確実な治療が必要です。
皮膚だけでなく、口の中や外陰部などの粘膜にも発生することがあります。
有棘細胞癌とは
このがんは、皮膚の細胞が異常に増殖してできる塊(腫瘍)です。初期は赤みを帯びた硬いしこりや、じくじくしたびらんとして現れることが多く、表面が崩れて潰瘍になることもあります。
痛みやかゆみなどの症状は初期には乏しいですが、進行すると出血しやすくなったり、悪臭を伴ったりすることがあります。
症状と進行
有棘細胞癌の症状は、発生した場所や進行度によって異なります。早期の段階では見分けがつきにくいこともありますが、進行すると特徴的な見た目になります。
初期症状
初期には、赤く盛り上がった硬いしこりや、治りにくいびらん、かさぶたのようなものができます。いぼのように見えることもあり、表面がカサカサしているのが特徴です。
日光角化症などの前がん病変から発生することも多く、その場合は徐々に大きくなり、硬さを増していきます。
進行した場合
がんが進行すると、腫瘍はさらに大きくなり、カリフラワーのような形になることがあります。中央部が崩れて深い潰瘍を形成し、出血や感染を起こしやすくなります。
周囲の組織を破壊しながら深部へと浸潤し、近くのリンパ節や、肺、肝臓などの遠隔臓器に転移する危険性があります。
原因と前駆症状
有棘細胞癌の最大の原因も、基底細胞癌と同様に長年の紫外線曝露です。その他、やけどの痕、放射線皮膚炎、慢性的な皮膚の炎症などもリスク要因となります。
また、がんになる前の段階である「前がん病変」から発生することが多いのも特徴です。
日光角化症
日光角化症は、長年にわたり紫外線を浴び続けた顔や手の甲などにできる、赤みがかったシミのような病変です。表面はザラザラしており、かさぶたが付着しています。
これは非常に早期の有棘細胞癌(表皮内癌)と考えられており、放置すると一部が浸潤性の有棘細胞癌に進行します。
ボーエン病
ボーエン病も表皮内癌の一種で、境界がはっきりした赤みのある斑点として現れます。表面にはかさぶたや鱗屑(りんせつ、皮膚の粉)が付着し、湿疹や乾癬と間違われることがあります。
これも放置すると浸潤がんへと進行する可能性があります。
診断方法
診断は、皮膚科専門医による視診や触診から始まり、確定診断のためには皮膚生検を行います。転移の可能性を調べるために、追加の画像検査が必要になることもあります。
視診と触診
医師が病変の大きさ、形、色、硬さなどを詳しく観察します。周囲のリンパ節が腫れていないかも触って確認します。ダーモスコピーも補助的な診断手段として有用です。
画像検査
がんが深く浸潤している疑いや、リンパ節への転移が疑われる場合には、超音波(エコー)検査、CT検査、MRI検査、PET検査などの画像検査を行い、病気の広がりを評価します。
治療の選択肢
治療は、がんの進行度(ステージ)に基づいて決定します。転移のない早期のがんであれば、手術が中心となります。
進行している場合は、手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせた集学的治療を行います。
手術療法
最も一般的な治療法は、外科的切除です。がんの周囲の正常組織を含めて切除し、病理検査で断端を確認します。
リンパ節への転移が認められる場合は、リンパ節も一緒に切除するリンパ節郭清を行います。
放射線治療
手術が困難な場合や、手術後の再発予防を目的として放射線治療を行うことがあります。高エネルギーのX線をがんに照射し、がん細胞を破壊します。
薬物療法
手術で取りきれないほど進行したがんや、遠隔転移がある場合には、薬物療法を選択します。
従来の細胞障害性抗がん剤に加え、近年では免疫チェックポイント阻害薬などの新しい薬も治療に用いられています。
有棘細胞癌のリスク要因
| 主な要因 | 具体例 | 関連する前駆症状 |
|---|---|---|
| 紫外線 | 長年の日光曝露、色白の肌 | 日光角化症 |
| 慢性的な刺激・炎症 | やけどの痕、治りにくい傷、放射線皮膚炎 | - |
| その他 | ヒトパピローマウイルス(HPV)感染、免疫抑制状態 | ボーエン病(一部) |
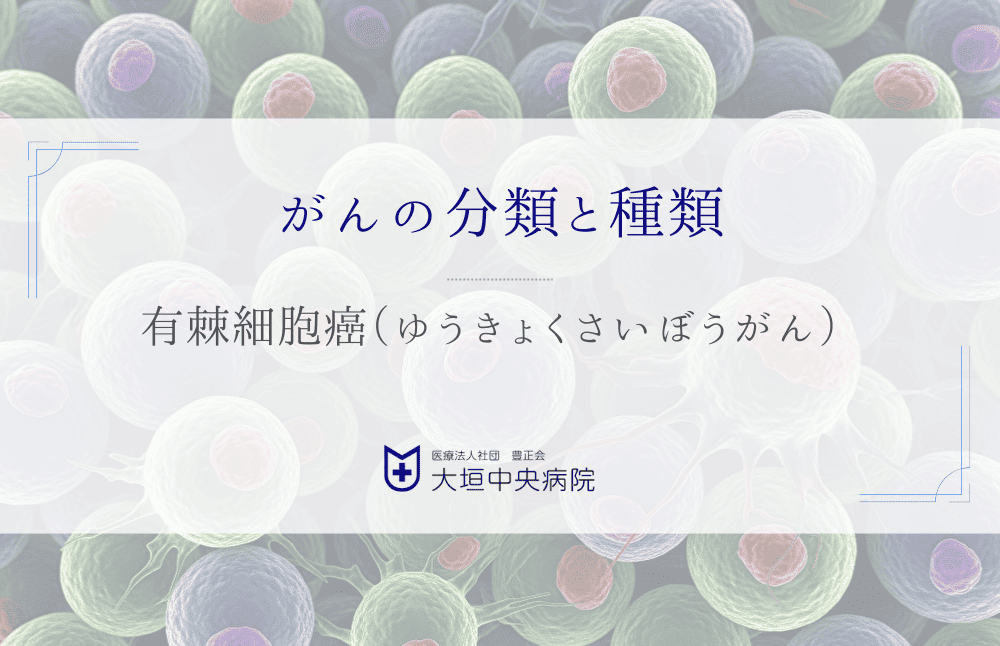
悪性黒色腫(メラノーマ) - 皮膚に発生する進行性のがん
悪性黒色腫は、メラノーマとも呼ばれ、皮膚の色素(メラニン)を作る細胞であるメラノサイトが悪性化したものです。
皮膚がんの中では発生頻度は高くありませんが、進行が速く、早期から転移しやすいため、最も悪性度の高いがんとして知られています。早期発見と早期治療が極めて重要です。
悪性黒色腫(メラノーマ)とは
メラノーマは、ほくろに似た黒っぽいシミやしこりとして現れることが多いですが、その性質は全く異なります。ほくろは良性の母斑細胞の集まりですが、メラノーマはがん細胞の増殖です。
日本人では、足の裏や手のひら、手足の爪に発生するタイプが多いことが特徴です。
見分けるためのポイント (ABCDEルール)
ほくろとメラノーマを見分けるための国際的な指標として「ABCDEルール」があります。これらの特徴に当てはまる場合は、専門医の診察を受けることを推奨します。
形状と色の変化
ABCDEルールは、メラノーマの視覚的な特徴をまとめたものです。すべてに当てはまるわけではありませんが、セルフチェックの際の参考になります。
- A (Asymmetry): 形が左右非対称である
- B (Border): 輪郭がギザギザしていて、周囲の皮膚との境界が不明瞭である
- C (Color): 色合いが均一でなく、黒、茶、青、赤、白などが混ざっている
- D (Diameter): 直径が6mm以上である(鉛筆の断面より大きい)
- E (Evolving): 形、大きさ、色、症状が変化する
発生部位と種類
メラノーマは、発生する部位や見た目の特徴から、主に4つのタイプに分類されます。
四肢末端黒子型
日本人で最も多いタイプで、全体の約半数を占めます。足の裏、手のひら、手足の指、爪に発生します。最初は茶色から黒褐色のシミとして始まり、徐々に色が濃くなったり、形が不規則になったりします。
爪にできると、黒い縦の線として現れ、進行すると爪が割れたり、周囲の皮膚に色がしみ出したりします。
表在拡大型
白色人種に最も多いタイプで、日本人では2番目に多いです。背中や胸、手足など、体のどこにでも発生します。
最初はわずかに盛り上がったシミとして始まり、数ヶ月から数年かけてゆっくりと横に広がっていきます。
結節型
メラノーマの中で最も悪性度が高いタイプです。最初から硬いしこりや結節として現れ、急速に大きくなります。
表面が崩れて出血しやすいのが特徴で、早期から深部へ浸潤し、転移を起こしやすいです。
悪性黒子型
主に高齢者の顔面など、日光に長年当たってきた部位に発生します。不規則な形の茶色から黒色のシミとして始まり、数年から数十年かけてゆっくりと広がります。
悪性黒色腫(メラノーマ)の主な種類と特徴
| 種類 | 好発部位 | 特徴 |
|---|---|---|
| 四肢末端黒子型 | 足の裏、手のひら、爪 | 日本人に最も多い。黒いシミや線として始まる。 |
| 表在拡大型 | 体幹、四肢 | 不規則な形のシミがゆっくりと広がる。 |
| 結節型 | 全身どこでも | 急速に大きくなる黒いしこり。進行が速い。 |
診断から治療までの流れ
メラノーマが疑われる場合、迅速な診断と治療計画の立案が必要です。
専門医による診察
まずはダーモスコピーで詳しく観察します。メラノーマが強く疑われる場合は、最初から部分的な生検は行わず、病変全体を切除する「切除生検」を行うのが一般的です。
これは、不完全な生検ががん細胞を散らばらせるリスクを避けるためです。
病期(ステージ)診断
切除した組織の病理検査で、がんの厚さ(浸潤の深さ)を測定します。この厚さが、後の治療方針や予後を予測する上で最も重要な指標となります。
さらに、リンパ節や他臓器への転移の有無を調べるために、センチネルリンパ節生検やCT、PETなどの画像検査を行い、病期を決定します。
主な治療法
メラノーマの治療は、病期に基づいて行います。早期であれば手術が中心ですが、進行している場合は薬物療法が重要な役割を果たします。
外科手術
転移のない早期のメラノーマに対する第一選択は、広範囲な外科的切除です。がんの周囲の正常な皮膚を1cmから2cm程度含めて、広く深く切除します。
センチネルリンパ節生検で転移が見つかった場合は、領域リンパ節郭清を追加することがあります。
薬物療法
手術で取りきれない進行・再発メラノーマや、遠隔転移がある場合には、薬物療法が中心となります。近年、治療は大きく進歩しており、免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬が治療成績を向上させています。
これらの薬は、患者さん自身の免疫力を高めてがんを攻撃したり、がん細胞の増殖に関わる特定の分子の働きを阻害したりします。
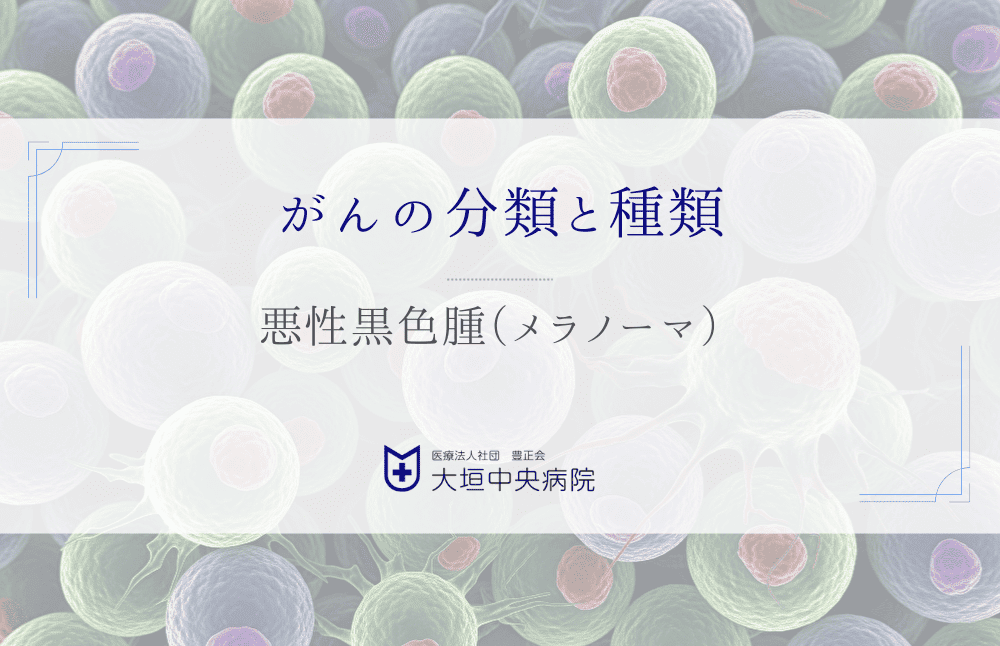
よくある質問
- 皮膚がんは遺伝しますか?
-
ほとんどの皮膚がんは遺伝しません。主な原因は紫外線や慢性的な刺激など、後天的な要因です。ただし、ごくまれに皮膚がんを発症しやすい特定の遺伝的素因を持つ家系もあります。
家族に若くしてメラノーマになった人がいる場合などは、一度専門医に相談してみるのもよいでしょう。
- 日焼け止めは皮膚がんの予防に有効ですか?
-
はい、有効です。紫外線は皮膚がんの最大の危険因子であり、日焼け止めを適切に使用することは、紫外線B波(UVB)とA波(UVA)の両方から皮膚を守り、がんのリスクを減らす上で重要です。
日焼け止めだけでなく、帽子や日傘、長袖の衣服などを活用し、総合的な紫外線対策を心がけることが大切です。
- ほくろとメラノーマの違いは何ですか?
-
ほくろは良性のできもので、形は左右対称に近く、境界も滑らかで、色も均一なことがほとんどです。
一方、メラノーマは悪性のがんであり、「ABCDEルール」で説明したように、形が非対称、境界が不明瞭、色が不均一、大きい、形や色が変化する、といった特徴があります。
急に大きくなったり、出血したりするほくろのようなものがあれば、注意が必要です。
- 治療後の生活で気をつけることはありますか?
-
治療後も定期的な通院と自己検診が重要です。治療した部位の再発や、別の場所に新しい皮膚がんが発生する可能性があるためです。
医師の指示に従って定期検診を受け、月に一度は全身の皮膚を自分でチェックする習慣をつけましょう。また、引き続き紫外線対策を徹底することも、新たな皮膚がんの予防につながります。
- 皮膚がんの検査は痛いですか?
-
ダーモスコピーによる観察は、拡大鏡で皮膚を見るだけなので全く痛みはありません。
確定診断に必要な皮膚生検は、局所麻酔の注射をする際にチクッとした痛みがありますが、麻酔が効けば検査中の痛みは感じません。
検査に対する不安が強い場合は、事前に医師に伝えておくとよいでしょう。
参考文献
WUNDERLICH, K., et al. Risk factors and innovations in risk assessment for melanoma, basal cell carcinoma, and squamous cell carcinoma. Cancers, 2024, 16.5: 1016.
FELLER, L., et al. Basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma and melanoma of the head and face. Head & face medicine, 2016, 12.1: 11.
QURESHI, Abrar A., et al. Geographic variation and risk of skin cancer in US women: differences between melanoma, squamous cell carcinoma, and basal cell carcinoma. Archives of internal medicine, 2008, 168.5: 501-507.
LEAR, J. T., et al. A comparison of risk factors for malignant melanoma, squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma in the UK. International journal of clinical practice, 1998, 52.3: 145-149.
STERN, Robert S.; STUDY, PUVA Follow-Up. The risk of squamous cell and basal cell cancer associated with psoralen and ultraviolet A therapy: a 30-year prospective study. Journal of the American Academy of Dermatology, 2012, 66.4: 553-562.
HOGUE, Latrice; HARVEY, Valerie M. Basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and cutaneous melanoma in skin of color patients. Dermatologic clinics, 2019, 37.4: 519-526.
LEAR, William; DAHLKE, Erin; MURRAY, Christian A. Basal cell carcinoma: review of epidemiology, pathogenesis, and associated risk factors. Journal of cutaneous medicine and surgery, 2007, 11.1: 19-30.
MILLER, Stanley J., et al. Basal cell and squamous cell skin cancers. Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 2010, 8.8: 836-864.
JONES, Owain T., et al. Recognising skin cancer in primary care. Advances in therapy, 2020, 37.1: 603-616.
FIRNHABER, Jonathon M. Diagnosis and treatment of basal cell and squamous cell carcinoma. American family physician, 2012, 86.2: 161-168.