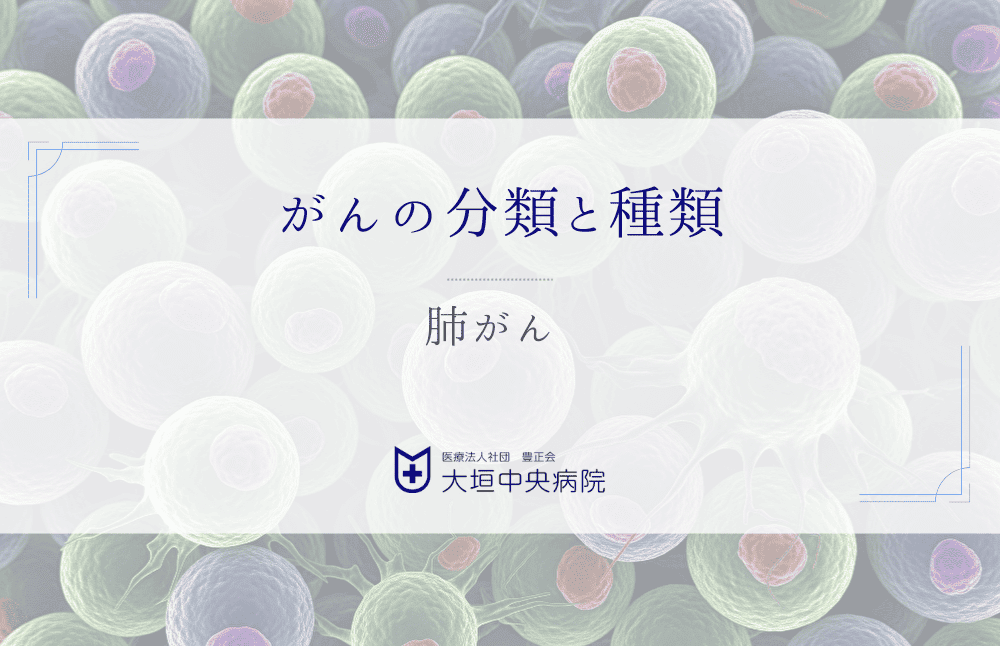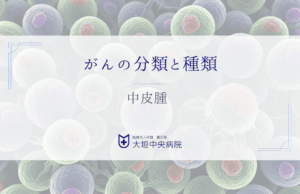肺がんとの診断は、ご本人やご家族にとって大きな衝撃を伴います。しかし、病気を正しく理解することは、不安を和らげ、ご自身が納得できる治療を選択するための第一歩です。
肺がんは一つの病気ではなく、性質の異なる多くの種類があり、治療法も多様化しています。
この記事では、肺がんの組織型による違いから、症状、検査、そして手術、薬物療法、放射線治療といった標準的な治療法まで、医学的な知識を網羅的に解説し、患者さんがご自身の状況を深く理解するための一助となることを目指します。
肺がんの組織型分類 – 小細胞がんと非小細胞がんの違い
肺がんの治療方針を決定する上で、最も基本となるのが「組織型」による分類です。
これは、がん細胞を顕微鏡で観察したときの顔つき(形態)の違いによるもので、大きく「非小細胞肺がん」と「小細胞肺がん」の2つに分けます。
この2つは、がんの性質、進行の速さ、そして治療法への反応が大きく異なるため、治療戦略を立てる上での最初の分岐点となります。
非小細胞肺がん(NSCLC)の概要
非小細胞肺がんは、肺がん全体の約85%を占める最も一般的なタイプです。小細胞肺がんに比べて、比較的ゆっくりと増殖する傾向があります。
そのため、がんが肺の内部に留まっている早期の段階で発見できれば、手術による根治を目指すことが可能です。
非小細胞肺がんは、さらに「腺がん」「扁平上皮がん」「大細胞がん」などのいくつかの種類に細分化します。
腺がん
非小細胞肺がんの中で最も多く、肺がん全体の半数近くを占めます。主に肺の末梢部(肺野部)に発生しやすい特徴があります。
喫煙との関連はありますが、扁平上皮がんに比べるとその関連は弱く、タバコを吸わない人に発生する肺がんの多くがこの腺がんです。
近年、特定の遺伝子変異が見つかることが多く、分子標的薬という特効薬のような薬が著しい効果を示すことがあります。
扁平上皮がん
腺がんに次いで多いタイプで、肺の中心部にある太い気管支に発生しやすい傾向があります。喫煙との関連が非常に強く、男性の喫煙者に多く見られます。
咳や血痰といった症状が出やすいのも特徴の一つです。
大細胞がん
非小細胞肺がんの中では比較的まれなタイプです。細胞が大きく、分化度が低い(細胞の形が未熟)という特徴があります。
肺の末梢部に発生することが多く、増殖が速い傾向を示します。
小細胞肺がん(SCLC)の概要
小細胞肺がんは、肺がん全体の約15%を占めます。このがんは、増殖が非常に速く、早い段階からリンパ節や他の臓器へ転移しやすいという悪性度の高い性質を持ちます。
発見された時点で、既にがんが広範囲に広がっていることも少なくありません。このため、手術の対象となることはまれで、治療の中心は抗がん剤による化学療法や放射線治療となります。
喫煙との関連が極めて強く、患者さんのほとんどが喫煙者です。
組織型による性質と治療方針の違い
| 組織型 | 主な特徴 | 基本的な治療方針 |
|---|---|---|
| 非小細胞肺がん | 増殖は比較的緩やか。遺伝子変異が見つかることがある。 | 早期は手術。進行期は薬物療法(分子標的薬、免疫療法、抗がん剤)、放射線治療。 |
| 小細胞肺がん | 増殖が非常に速く、転移しやすい。 | 抗がん剤(化学療法)と放射線治療が中心。手術の適応は限定的。 |
肺の構造と機能からみた発がんの仕組み
肺がんがどのようにして発生するのかを理解するためには、まず肺そのものの構造と働きを知ることが重要です。
私たちの肺は、生命維持に欠かせないガス交換という重要な役割を担っており、その繊細な構造が、がん発生の土壌となることもあります。
肺の基本構造とガス交換の働き
空気は気管を通って左右の気管支に分かれ、さらに枝分かれを繰り返して細い気管支となります。その末端には、ブドウの房のような形をした「肺胞」という小さな袋が無数に存在します。
この肺胞の薄い壁を毛細血管が取り巻いており、ここで吸い込んだ空気中の酸素を血液中に取り込み、血液中の二酸化炭素を空気中に排出する「ガス交換」を行っています。
発がんの引き金となる細胞の遺伝子変異
肺がんの直接的な原因は、気管支や肺胞を覆う細胞の遺伝子(DNA)に傷がつくことです。
タバコの煙に含まれる発がん物質などの有害物質を吸い込むと、これらの物質が細胞に取り込まれ、遺伝子を傷つけます。
通常、細胞には傷ついた遺伝子を修復する機能や、異常な細胞を排除する仕組みが備わっています。
しかし、長期間にわたって有害物質にさらされ続けると、修復が追いつかなくなったり、異常を監視する仕組みが壊れたりして、遺伝子の傷(変異)が蓄積していきます。
がん細胞の増殖と浸潤
がん遺伝子やがん抑制遺伝子といった、細胞の増殖をコントロールする重要な遺伝子に変異が起こると、細胞は正常な制御を失い、無秩序に増殖を始めます。これが「がん細胞」の始まりです。
がん細胞は、周囲の正常な組織に染み込むように広がっていき(浸潤)、近くのリンパ管や血管に入り込むと、リンパの流れや血流に乗って肺の他の場所や、脳、骨、肝臓といった他の臓器へと移動し、そこで新たな塊を作ります。
これを「転移」と呼びます。
喫煙と肺がんリスクの医学的関係性
肺がんを語る上で、喫煙との関係は避けて通れません。喫煙が肺がんの最大のリスク要因であることは、数多くの医学的研究によって証明されています。
タバコの煙が、いかにして肺の細胞をがん化させるのか、その関係性を詳しく見ていきましょう。
タバコ煙に含まれる発がん物質
タバコの煙には、ニコチンやタールをはじめとして、約7000種類の化学物質が含まれており、そのうちの約70種類が発がん物質であることが確認されています。
代表的なものには、ベンゾピレン、ニトロソアミン類、ヒ素、カドミウムなどがあります。これらの物質が肺の細胞に直接作用し、遺伝子を傷つけることで、がん発生の引き金を引きます。
喫煙指数(ブリンクマン指数)とリスク
| 喫煙指数 | 計算方法 | 肺がんリスクの目安 |
|---|---|---|
| 400以上 | 1日の喫煙本数 × 喫煙年数 | 肺がんのハイリスク群と見なされる。 |
| 600以上 | 1日の喫煙本数 × 喫煙年数 | リスクがさらに高まる。特にCOPD(慢性閉塞性肺疾患)を合併しやすい。 |
喫煙期間・本数とリスクの相関
肺がんのリスクは、タバコを吸い始めた年齢が若いほど、喫煙期間が長いほど、そして1日に吸う本数が多いほど高くなります。
喫煙のリスクを評価する指標として「喫煙指数(ブリンクマン指数)」があり、「1日の喫煙本数 × 喫煙年数」で計算します。この数値が400を超えると、肺がんのリスクが高いと判断します。
受動喫煙の危険性
タバコを吸わない人でも、周囲の人が吸うタバコの煙(副流煙)を吸い込む「受動喫煙」によって、肺がんのリスクが高まります。
副流煙には、喫煙者本人が吸い込む主流煙よりも高濃度の有害物質が含まれていることが分かっています。
家庭や職場など、日常的に受動喫煙の機会がある人は、そうでない人に比べて肺がんになるリスクが約1.2〜1.3倍高くなると報告されています。
禁煙によるリスク低減効果
禁煙を始めれば、肺がんのリスクは着実に低下します。もちろん、一度も吸ったことがない人のレベルまでリスクが下がるわけではありませんが、禁煙を続けることでリスクは着実に減少していきます。
例えば、禁煙後10年で、肺がんのリスクは喫煙を続けている人の約半分にまで低下すると言われています。何歳であっても、禁煙を始めるのに遅すぎることはありません。
見逃してはいけない肺がんの症状と進行パターン
肺がんは「サイレントキラー」とも呼ばれ、初期の段階では自覚症状がほとんど現れないことが多い病気です。症状が出たときには、既にがんが進行しているケースも少なくありません。
だからこそ、肺がんの可能性があるサインを見逃さず、早期発見につなげることが重要です。
初期段階で現れやすい症状
肺がんの初期症状は、風邪や気管支炎の症状と似ているため、見過ごされがちです。しかし、以下のような症状が2週間以上続く場合は、注意が必要です。
- なかなか治らない咳
- 痰、または血の混じった痰(血痰)
- 息切れ、動悸
- 胸の痛み
- 声のかすれ(嗄声)
咳や痰の変化に注意
特に注意したいのが「咳」の変化です。これまで咳の無かった人が咳をし始めたり、喫煙者の慢性的な咳の性質が変わったりした場合は、医療機関の受診を検討してください。
また、痰に血が混じる血痰は、肺がんの重要なサインの一つです。少量でも血が混じっていたら、必ず医師に相談することが大切です。
がんの進行に伴う症状
がんが大きくなったり、周囲の臓器に広がったりすると、よりはっきりとした症状が現れます。
がんが気管支を塞ぐことによる呼吸困難、胸に水がたまる(胸水)ことによる息苦しさ、食欲不振や原因不明の体重減少、全身の倦怠感などが挙げられます。
転移による特有の症状
肺がんは他の臓器に転移しやすい性質を持っています。転移した場所によって、特有の症状が現れます。
これらの症状は、肺がんそのものではなく、転移によって引き起こされるため、原因が肺にあるとは気づきにくいこともあります。
転移部位と見られる主な症状
| 転移部位 | 主な症状 | 解説 |
|---|---|---|
| 骨 | 持続的な痛み、骨折 | 特に背骨や腰、肋骨に転移しやすく、体を動かしたときに強まる痛みが出ることがある。 |
| 脳 | 頭痛、吐き気、めまい、手足の麻痺 | 転移した腫瘍が脳を圧迫することで、様々な神経症状を引き起こす。 |
| 肝臓 | 倦怠感、食欲不振、黄疸 | 転移がかなり進行しないと症状が出にくいことが多い。 |
胸部画像診断と気管支鏡検査の役割
咳や胸痛などの症状から肺がんが疑われる場合や、健康診断の胸部X線検査で異常な影が見つかった場合、診断を確定するためにいくつかの精密検査を行います。
これらの検査は、がんの有無だけでなく、その位置、大きさ、広がりを正確に把握し、治療方針を立てる上で重要な情報をもたらします。
胸部X線検査とCT検査
胸部X線(レントゲン)検査は、肺がん検診で広く行われる基本的な画像検査です。しかし、心臓や骨の影に隠れた小さながんや、淡いすりガラス状の陰影は、X線検査だけでは見つけにくいことがあります。
そのため、異常が疑われる場合には、より詳しく調べるために胸部CT検査を行います。
CT検査は、体を輪切りにしたような詳細な画像を撮影でき、ミリ単位の小さながんや、リンパ節への転移の有無などを評価することが可能です。
気管支鏡検査による組織診断
画像検査でがんが強く疑われる場合、最終的な確定診断のためには、がん細胞そのものを採取して顕微鏡で調べる「病理診断」が必要です。
そのための代表的な検査が「気管支鏡検査」です。
これは、先端にカメラが付いた細い管(気管支鏡)を口や鼻から挿入し、気管支の内部を直接観察しながら、がんが疑われる部分の組織や細胞を採取する検査です。
採取した組織を調べることで、がん細胞の有無だけでなく、肺がんの組織型(非小細胞がんか小細胞がんか、腺がんか扁平上皮がんかなど)を確定します。
その他の画像診断(PET検査など)
PET(陽電子放出断層撮影)検査は、がん細胞が正常な細胞よりも多くのブドウ糖を取り込む性質を利用した検査です。
ブドウ糖に似た薬剤を注射し、その薬剤が体のどこに集まるかを撮影することで、全身のがん細胞の位置を調べることができます。
肺の中の病変が良性か悪性かの判断や、リンパ節、骨、肝臓など他の臓器への遠隔転移の有無を評価するために行い、治療方針の決定に役立てます。
病期診断と遺伝子検査 – 治療方針決定の根拠
肺がんの診断が確定したら、次に行うのは「病期(ステージ)」の決定です。病期とは、がんが体の中でどのくらい進行しているかを示すもので、治療方針を決定する上で最も重要な指標となります。
また、近年の薬物療法の進歩に伴い、がん細胞の遺伝子情報を調べることも同様に重要になっています。
TNM分類によるステージ(病期)決定
肺がんの病期は、国際的に用いられている「TNM分類」に基づいて決定します。これは、以下の3つの要素を組み合わせて総合的に評価するものです。
TNM分類の構成要素
| 因子 | 評価内容 | 概要 |
|---|---|---|
| T因子 | 原発巣の大きさ・広がり | がんそのものの大きや、周囲の組織へどの程度広がっているかを示す。 |
| N因子 | 所属リンパ節への転移 | がんが肺の周辺にあるリンパ節に転移しているかどうか、その範囲を示す。 |
| M因子 | 遠隔転移 | 肺から離れた臓器(脳、骨、肝臓、副腎など)への転移の有無を示す。 |
各ステージの定義と予後
TNM分類の評価結果を総合して、病期をステージI(早期)からステージIV(進行期)までに分類します。
ステージが若いほど、がんが限られた範囲に留まっていることを意味し、一般的に治療成績(生存率)も良好です。逆にステージが進むほど、がんが広範囲に広がっていることを示します。
非小細胞肺がんのステージと5年生存率の目安
| ステージ | がんの広がりの目安 | 5年相対生存率(目安) |
|---|---|---|
| I期 | 腫瘍が肺内に限局し、リンパ節転移がない。 | 約80-90% |
| II期 | 肺内のリンパ節に転移がある。 | 約50-60% |
| III期 | 縦隔(左右の肺の間)のリンパ節に転移がある。 | 約20-40% |
| IV期 | 遠隔転移がある。 | 約5-10% |
※生存率はあくまで多くの患者さんのデータの平均値であり、個人の状況によって異なります。
小細胞肺がんの2年/5年相対生存率(目安)
小細胞肺がんは進行が速いため、ステージ分類の他に「限局型」と「進展型」で分けることが一般的です。
- 限局型(がんが片側の胸郭内にとどまる):
- 5年生存率:約20〜30%(化学放射線療法が奏功した場合)
- 進展型(がんが反対側の肺や他臓器に広がっている):
- 5年生存率:約1〜2%
- ※ただし、近年の免疫チェックポイント阻害薬の登場により、長期生存が可能になるケースも少しずつ増えています。
治療選択を変える遺伝子検査
非小細胞肺がん、特に腺がんでは、がん細胞の増殖に直接関わる特定の遺伝子に変異(ドライバー遺伝子変異)が見つかることがあります。
この変異がある場合、その遺伝子の働きをピンポイントで妨害する「分子標的薬」が劇的な効果を示す可能性があります。
そのため、治療開始前にがん組織を用いて遺伝子検査を行い、EGFR、ALK、ROS1、BRAFといった遺伝子に変異がないか調べることが標準的になっています。
この検査結果によって、抗がん剤ではなく分子標的薬を第一の治療選択肢として検討します。
PD-L1検査と免疫療法の適応
私たちの体には、がん細胞などの異物を攻撃する免疫システムが備わっています。
しかし、がん細胞の中には、免疫細胞にブレーキをかける「PD-L1」というタンパク質を表面に出して、免疫の攻撃から逃れているものがあります。
「免疫療法(免疫チェックポイント阻害薬)」は、このブレーキを解除し、免疫細胞が再びがんを攻撃できるようにする薬です。
治療前にがん組織のPD-L1発現率を調べることで、免疫療法が効きやすいかどうかを予測し、治療選択の参考にします。
外科治療の適応と手術法の選択基準
外科治療(手術)は、がんを物理的に取り除くことで根治を目指す治療法です。肺がんにおいては、がんが肺とその周辺のリンパ節に留まっている早期の非小細胞肺がんが主な対象となります。
患者さんの全身状態や肺機能なども考慮した上で、手術が可能かどうかを慎重に判断します。
手術が可能なステージ
手術の最も良い適応となるのは、遠隔転移がなく、リンパ節転移もないか、あってもごく軽度なステージI期およびII期の非小細胞肺がんです。
ステージIII期の一部でも、薬物療法や放射線治療と組み合わせることで手術が可能になる場合があります。一方、増殖が速く早期から全身に広がりやすい小細胞肺がんでは、手術の対象となるのは極めてまれです。
標準的な手術方法(肺葉切除術)
肺は右が上葉・中葉・下葉の3つ、左が上葉・下葉の2つの「肺葉」という区域に分かれています。肺がんに対する標準的な手術は、がんが存在する肺葉を丸ごと切除する「肺葉切除術」です。
同時に、転移の可能性がある周囲のリンパ節も一緒に切除(リンパ節郭清)し、がんの取り残しを防ぎます。
体への負担が少ない縮小手術
近年、CT検診の普及により、ごく早期の小さな肺がんが見つかる機会が増えました。
このような場合、肺葉よりも小さい単位(区域)で切除する「区域切除術」や、がんの部分だけを楔状に切り取る「部分切除術(楔状切除)」といった、肺の機能をより多く温存できる縮小手術を選択することがあります。
主な手術方法とその特徴
| 手術方法 | 切除範囲 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 肺葉切除術 | がんのある肺葉全体 | 標準的な肺がん手術 |
| 区域切除術 | 肺葉より小さい区域 | 比較的小さな早期がん |
| 胸腔鏡下手術(VATS) | (アプローチ法) | 多くの手術で適用可能 |
胸腔鏡下手術(VATS)の普及
従来の手術は、胸を大きく開く「開胸手術」が主流でした。
しかし現在では、胸に数か所の小さな穴を開け、そこからカメラ(胸腔鏡)と手術器具を挿入してモニターを見ながら行う「胸腔鏡下手術(VATS)」が広く普及しています。
この方法は傷が小さく、術後の痛みが少なく、回復も早いため、患者さんの体への負担を大幅に軽減します。
薬物療法の進歩 – 分子標的治療と免疫療法の実際
薬物療法は、手術が難しい進行・再発肺がんの治療の中心であり、また手術前後の補助療法としても重要な役割を担います。
かつては「抗がん剤(細胞障害性抗がん剤)」が主体でしたが、近年の研究の進歩により、「分子標的薬」と「免疫療法」という新しいタイプの薬が登場し、治療成績は飛躍的に向上しました。
分子標的薬の作用と対象となる遺伝子変異
分子標的薬は、がん細胞の増殖や生存に不可欠な特定の分子(タンパク質や遺伝子)だけを狙い撃ちする薬です。正常な細胞への影響が少ないため、従来の抗がん剤に比べて副作用が比較的軽い傾向があります。
ただし、効果を発揮するためには、標的となる遺伝子変異ががん細胞に存在することが条件です。
非小細胞肺がんでは、EGFR遺伝子変異に対するゲフィチニブやオシメルチニブ、ALK融合遺伝子に対するアレクチニブなどが代表的な分子標的薬です。
免疫チェックポイント阻害薬(免疫療法)の働き
免疫療法は、がん細胞そのものを直接攻撃するのではなく、患者さん自身が持つ免疫の力を利用してがんと闘う治療法です。
具体的には、がん細胞が免疫細胞にかけているブレーキ(PD-1/PD-L1など)を解除する「免疫チェックポイント阻害薬」を用います。
これにより、免疫細胞が再活性化し、がん細胞を異物として認識・攻撃できるようになります。ニボルマブやペムブロリズマブといった薬が、非小細胞肺がんや小細胞肺がんの治療に広く使われています。
従来の細胞障害性抗がん剤の役割
分子標的薬や免疫療法の対象とならない場合や、これらの治療効果が乏しくなった場合には、従来の細胞障害性抗がん剤(いわゆる抗がん剤)による化学療法を行います。
この薬は、細胞分裂が活発な細胞を攻撃する性質があるため、がん細胞だけでなく、骨髄や消化管、毛根などの正常な細胞も影響を受けやすく、吐き気や脱毛、白血球減少といった副作用が出やすいのが特徴です。
プラチナ製剤(シスプラチンなど)と他の抗がん剤を組み合わせる併用療法が標準的です。
主な薬物療法と特徴的な副作用
| 治療法 | 主な副作用 | 対策のポイント |
|---|---|---|
| 分子標的薬 | 皮疹、下痢、肝機能障害、間質性肺炎 | 保湿ケア、下痢止め、定期的な血液検査が重要。 |
| 免疫療法 | 甲状腺機能異常、大腸炎、皮膚障害、間質性肺炎 | 自己免疫に関連する多様な副作用に注意が必要。 |
| 抗がん剤 | 吐き気、脱毛、骨髄抑制(白血球減少など) | 吐き気止めなどの支持療法を積極的に行う。 |
放射線治療の位置づけと適応症例
放射線治療は、手術、薬物療法と並ぶがん治療の3本柱の一つです。高エネルギーのX線やガンマ線をがん病巣に照射することで、がん細胞の遺伝子にダメージを与えて破壊します。
体の外から照射する方法が一般的で、治療自体に痛みはありません。肺がんでは、様々な目的で放射線治療が行われます。
根治を目指す放射線治療
手術ができない早期の非小細胞肺がんに対して、根治を目指して放射線治療を行うことがあります。
また、局所進行がん(ステージIII期)で手術が難しい場合には、抗がん剤と放射線治療を同時に行う「化学放射線療法」が標準的な治療法です。
これにより、手術に匹敵する治療効果を目指します。
症状緩和を目的とした放射線治療
がんが骨や脳に転移し、痛みや麻痺などのつらい症状を引き起こしている場合に、その症状を和らげる目的で放射線治療を行います。
これを「緩和照射」と呼びます。例えば、骨転移による痛みを軽減したり、脳転移による神経症状を改善したりすることで、患者さんの生活の質(QOL)を維持する上で非常に重要な役割を果たします。
定位放射線治療(SBRT/ピンポイント照射)
定位放射線治療は、比較的小さな早期の肺がんに対して行われる高精度の放射線治療です。
様々な方向から放射線を病巣に集中させることで、周囲の正常な肺へのダメージを最小限に抑えつつ、がんに対しては手術に匹敵する高い線量を照射することができます。
高齢や合併症のために手術が難しい患者さんにとって、根治を目指せる有力な治療選択肢となります。
肺がん患者の生活管理と継続的ケア
肺がんの治療は、医療機関の中だけで完結するものではありません。
治療中はもちろん、治療が終わった後も、患者さん自身が日々の生活の中で体調を管理し、医療チームと連携しながら継続的なケアを受けていくことが、より良い療養生活と再発の早期発見につながります。
副作用マネジメントとセルフケア
薬物療法や放射線治療には、様々な副作用が伴います。吐き気、だるさ、皮膚のトラブル、口内炎など、現れる症状は治療法や個人によって異なります。
どのような副作用が起こりうるのかを事前に医師や看護師からよく聞き、その対処法を学んでおくことが大切です。
日々の体調の変化を記録し、つらい症状は我慢せずに医療スタッフに伝えることで、適切な支持療法を受けることができます。
栄養管理と身体活動の重要性
治療を乗り切るためには、体力の維持が重要です。バランスの取れた食事を心がけ、体重を維持するように努めましょう。食欲がないときでも、少量ずつでも口にできるものを見つける工夫が必要です。
また、無理のない範囲でのウォーキングなどの身体活動は、体力や筋力の維持、気分のリフレッシュにもつながります。
ただし、どのような運動が適切かは、ご自身の病状や治療内容によって異なるため、主治医に相談してください。
定期的な検査とフォローアップ
治療によってがんが目に見えなくなった後も、再発や転移の可能性は残ります。そのため、治療後も定期的に医療機関を受診し、胸部CT検査や血液検査などのフォローアップを受けることが必要です。
定期的な検査は、万が一再発した場合でも、早期に発見し、速やかに次の治療を開始するために不可欠です。
よくある質問
ここでは、肺がん患者さんやご家族からよく寄せられる質問にお答えします。
治療法選択の目安(非小細胞肺がん)
| ステージ | がんの状態 | 主な治療選択肢 |
|---|---|---|
| I期・II期 | がんが肺の中に留まっている | 手術が第一選択。手術が難しい場合は放射線治療。 |
| III期 | がんが胸の中(縦隔など)に広がっている | 化学放射線療法。症例により手術や薬物療法。 |
| IV期 | 遠隔転移がある | 薬物療法(分子標的薬、免疫療法、抗がん剤)。症状緩和のための放射線治療。 |
- 肺がんの生存率はどのくらいですか?
-
生存率は、がんの組織型やステージによって大きく異なります。
一般的に、がんが肺の中に留まっている早期のステージIで発見されれば5年相対生存率は80%を超えますが、遠隔転移のあるステージIVでは10%未満と厳しくなります。
ただし、これはあくまで統計上のデータであり、分子標的薬や免疫療法の登場により、進行がんでも長期にわたり元気に過ごされる方が増えています。
個々の状況は主治医にご確認ください。
- 治療の副作用が心配です
-
がん治療には副作用が伴うことが多いですが、その種類や程度は治療法や個人によって様々です。近年は、吐き気止めなど副作用を和らげるための「支持療法」も大きく進歩しています。
つらい症状を我慢せず、医師、看護師、薬剤師に相談することで、多くの副作用はコントロール可能です。
事前にどのような副作用が起こりうるか、どのような対策があるかを確認しておくことが大切です。
- セカンドオピニオンは受けた方が良いですか?
-
セカンドオピニオンは、現在の主治医以外の医師に治療方針の意見を聞くことです。ご自身の病状や治療法について理解を深め、納得して治療に臨むために、とても有意義な権利です。
特に、治療方針の選択肢が複数ある場合や、大きな決断を要する場合には、セカンドオピニオンを検討することをお勧めします。
希望する場合は、主治医に遠慮なく申し出て、紹介状や検査データを提供してもらいましょう。
肺の病気という点では、主に過去のアスベスト(石綿)へのばく露が原因で、肺を覆う胸膜や腹部を覆う腹膜などに発生する「中皮腫」も重要な疾患です。
長引く咳や胸の痛み、息切れといった肺がんと似た症状をきっかけに見つかることがありますが、発生する場所、原因、そして治療法は肺がんとは異なります。
特にアスベストを扱う職業に従事した経験のある方や、そのご家族は注意が必要です。中皮腫に関する詳しい情報や、アスベストばく露との関連については、中皮腫の解説記事をご参照ください。
以上
参考文献
COGNIGNI, Valeria, et al. The landscape of ALK-rearranged non-small cell lung cancer: a comprehensive review of clinicopathologic, genomic characteristics, and therapeutic perspectives. Cancers, 2022, 14.19: 4765.
RODAK, Olga, et al. Current landscape of non-small cell lung cancer: epidemiology, histological classification, targeted therapies, and immunotherapy. Cancers, 2021, 13.18: 4705.
JIANG, Wenxiao, et al. Personalized medicine in non-small cell lung cancer: a review from a pharmacogenomics perspective. Acta pharmaceutica sinica B, 2018, 8.4: 530-538.
ROTHSCHILD, Sacha I. Targeted therapies in non-small cell lung cancer—beyond EGFR and ALK. Cancers, 2015, 7.2: 930-949.
HENSING, Thomas, et al. A personalized treatment for lung cancer: molecular pathways, targeted therapies, and genomic characterization. Systems Analysis of Human Multigene Disorders, 2013, 85-117.
PANT, Janmejay, et al. Evolving strategies in NSCLC care: Targeted therapies, biomarkers, predictive models, and patient management. Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine, 2023, 20.3: 146-164.
GUO, Yijia, et al. Concurrent genetic alterations and other biomarkers predict treatment efficacy of EGFR-TKIs in EGFR-mutant non-small cell lung cancer: a review. Frontiers in Oncology, 2020, 10: 610923.
SYN, Nicholas Li-Xun, et al. Evolving landscape of tumor molecular profiling for personalized cancer therapy: a comprehensive review. Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 2016, 12.8: 911-922.
SRIVASTAVA, Shriyansh, et al. Unveiling the potential of proteomic and genetic signatures for precision therapeutics in lung cancer management. Cellular Signalling, 2024, 113: 110932.
ROSSI, Giulio, et al. A reevaluation of the clinical significance of histological subtyping of non—small-cell lung carcinoma: diagnostic algorithms in the era of personalized treatments. International journal of surgical pathology, 2009, 17.3: 206-218.
呼吸器系がんに戻る