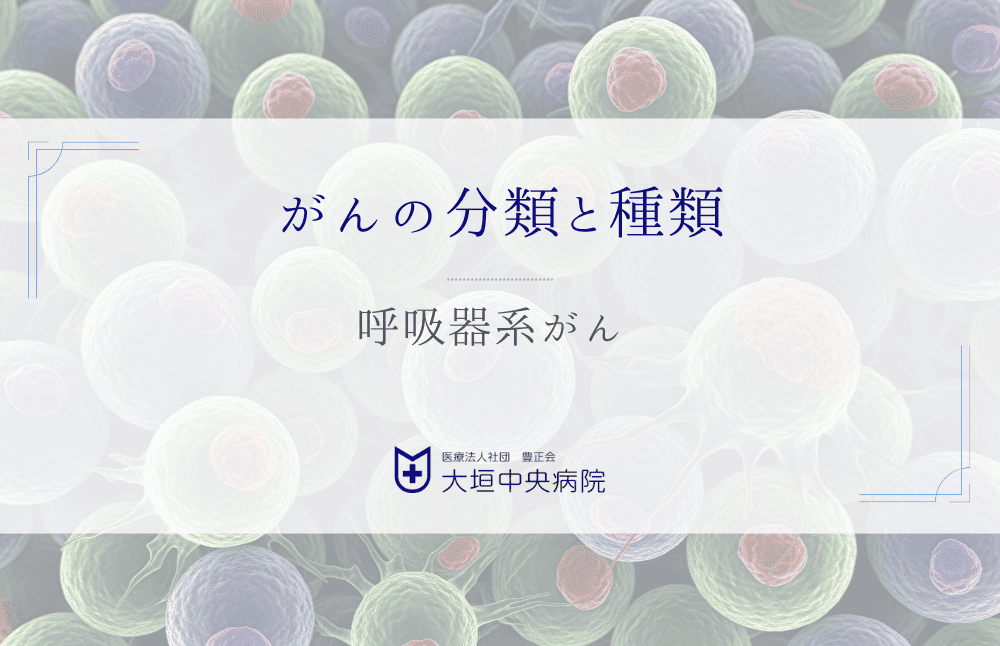呼吸器は、私たちが生命を維持するために空気中の酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する重要な役割を担っています。
この呼吸器に発生するがんを「呼吸器系がん」と呼び、中でも「肺がん」や「中皮腫」が代表的です。がんと診断されると、ご本人やご家族は大きな不安を感じるかもしれません。
この記事では、呼吸器系がんの基本的な知識、種類、症状、そしてどのような治療法があるのかを、一つひとつ丁寧に解説します。
肺がん
肺がんは、呼吸器系のがんの中で最も発生数が多く、日本人のがんによる死亡原因の上位を占める疾患です。気管支や肺胞の細胞が、何らかの原因でがん細胞に変化することで発生します。
早期発見と適切な治療が、その後の経過に大きく影響するため、正しい知識を持つことが重要です。ここでは、肺がんの種類や症状、検査、治療法について詳しく見ていきます。
肺がんとは
概要と発生部位
肺がんは、肺の組織に発生する悪性腫瘍の総称です。肺は、心臓を挟んで左右に一つずつあり、空気の通り道である気管支が木の枝のように広がり、その末端に肺胞という小さな袋がたくさん集まってできています。
ガス交換を行うこの肺胞や、気管支の粘膜を覆う細胞からがんが発生します。がんは進行すると周囲の組織に浸潤したり、リンパ液や血液の流れに乗って他の臓器に転移したりすることがあります。
主な原因
肺がんの最大の原因は喫煙です。たばこの煙に含まれる多くの発がん性物質が、長年にわたり気管支や肺の細胞を傷つけることで、がんが発生しやすくなります。
本人だけでなく、周囲の人のたばこの煙を吸う受動喫煙もリスクを高めることが分かっています。
その他、アスベスト(石綿)などの有害物質への職業的な曝露、大気汚染、遺伝的な要因、加齢なども関与すると考えられています。
肺がんの種類
肺がんは、がん細胞の見た目(組織型)によって、主に「非小細胞肺がん」と「小細胞肺がん」の2つに大別します。
この分類は、がんの性質や進行の速さ、治療法の選択に大きく関わるため、非常に重要です。
非小細胞肺がん
肺がん全体の約85-90%を占めるのが非小細胞肺がんです。小細胞肺がんに比べて、比較的ゆっくりと進行する傾向があります。
この非小細胞肺がんは、さらに「腺がん」「扁平上皮がん」「大細胞がん」などの種類に分かれます。腺がんは肺がんの中で最も多く、特に女性や喫煙しない人に発生する肺がんの多くがこのタイプです。
肺の末梢部に発生しやすい特徴があります。扁平上皮がんは、太い気管支に発生しやすく、喫煙との関連が深いがんです。
小細胞肺がん
肺がん全体の約10-15%を占めるタイプです。非常に増殖が速く、早い段階からリンパ節や他の臓器へ転移しやすいという悪性度の高い性質を持ちます。
喫煙との関連が極めて強いがんであり、発見された時点で既にがんが広範囲に広がっていることも少なくありません。進行が速い一方で、抗がん剤や放射線治療が効きやすいという特徴もあります。
症状の現れ方
肺がんは、初期の段階では自覚症状がほとんどないことが多く、健康診断の胸部X線検査などで偶然発見されるケースも珍しくありません。症状が現れたときには、ある程度進行している可能性があります。
初期症状
なかなか治らない咳や痰、血痰、胸の痛み、動いたときの息切れ、声のかすれ(嗄声)などが、肺がんのサインとして現れることがあります。
これらの症状は、風邪や気管支炎など他の呼吸器疾患の症状と似ているため、見過ごされやすい傾向にあります。2週間以上続くような場合は、専門医への相談を検討することが大切です。
進行した場合の症状
がんが大きくなったり、周りの臓器に広がったりすると、より強い症状が現れます。
例えば、がんが胸壁に及ぶと持続的な胸の痛みが生じ、気管支を塞ぐと肺炎や無気肺(肺がしぼんだ状態)を引き起こすことがあります。
また、骨に転移すると強い痛みや骨折の原因となり、脳に転移すると頭痛や吐き気、めまい、手足の麻痺などを引き起こすこともあります。
体重減少や食欲不振、原因不明の発熱も、進行がんの症状として見られます。
検査と診断
肺がんが疑われる場合、まず画像検査でがんの存在や位置、大きさを確認します。そして最終的には、がん細胞そのものを採取して調べることで確定診断を行います。
画像検査
最も基本的な検査は胸部X線(レントゲン)検査です。健康診断などでも広く行われます。ここで異常な影が見つかった場合、さらに詳しい情報を得るために胸部CT検査を実施します。
CT検査は、体を輪切りにしたような詳細な画像を得られるため、X線では見つけにくい小さながんや、がんの広がり、リンパ節への転移の有無などを評価するのに役立ちます。
その他、PET検査は、がん細胞が正常細胞より多くのブドウ糖を取り込む性質を利用して、全身への転移を調べるのに有用です。
組織や細胞の確認
確定診断には、がん細胞を直接観察することが必要です。そのための代表的な検査が気管支鏡検査です。口や鼻から細い内視鏡を気管支に挿入し、がんが疑われる部分の組織を採取(生検)します。
肺の末梢部など、気管支鏡が届かない場所に病変がある場合は、体の外から胸に針を刺して組織を採取する経皮的針生検を行うこともあります。
採取した組織や細胞を顕微鏡で詳しく調べ(病理診断)、がんの種類(組織型)を確定します。
肺がんの病期(ステージ)分類
| 病期(ステージ) | がんの大きさや広がり(T) | リンパ節への転移(N)と遠隔転移(M) |
|---|---|---|
| I期(早期) | がんが小さく、肺の中にとどまっている | リンパ節転移や遠隔転移はない |
| II期 | がんが大きくなった、または肺門リンパ節に転移がある | 遠隔転移はない |
| III期 | がんがさらに大きくなり、周囲の臓器に広がる、または縦隔リンパ節に転移がある | 遠隔転移はない |
| IV期(進行期) | がんの大きさやリンパ節転移の程度に関わらず、他の臓器への遠隔転移がある | 遠隔転移がある(脳、骨、肝臓、副腎など) |
治療法
肺がんの治療は、がんの種類(非小細胞か小細胞か)、病期(ステージ)、がん細胞の遺伝子変異の有無、そして患者さん自身の全身状態や希望などを総合的に考慮して決定します。
主な治療法には、手術、放射線治療、薬物療法があり、これらを単独で、あるいは組み合わせて行います。
手術(外科治療)
がんが肺の一部にとどまっており、リンパ節転移も限定的である場合(主にI期やII期、一部のIII期)に行う治療法です。
がんのある肺葉ごと、あるいは区域を切除し、周囲のリンパ節も一緒に取り除きます(リンパ節郭清)。
近年は、体の負担が少ない胸腔鏡下手術が広く行われるようになりました。根治を目指せる可能性が最も高い治療法ですが、心臓や肺の機能が手術に耐えられることが条件となります。
放射線治療
高エネルギーのX線などをがん細胞に照射して、がんを小さくする治療法です。
手術が難しい高齢者や、合併症を持つ患者さんの根治を目指す治療として、また、手術ができない進行がんの症状緩和、骨や脳への転移に対する治療としても用います。
化学療法(抗がん剤治療)と同時に行う化学放射線療法は、局所進行がんの標準的な治療法の一つです。
薬物療法
薬物療法は、飲み薬や点滴で薬剤を全身に行き渡らせ、がん細胞を攻撃する治療法です。進行・再発した非小細胞肺がんや、転移しやすい性質を持つ小細胞肺がんの治療の中心となります。
従来の「細胞障害性抗がん剤」に加え、近年では特定の遺伝子変異を持つがん細胞だけを狙い撃ちする「分子標的薬」や、自身の免疫力を高めてがんを攻撃する「免疫チェックポイント阻害薬」が登場し、治療成績が大きく向上しています。
治療開始前にがん組織の遺伝子検査を行い、どの薬が効果的かを調べることが一般的です。
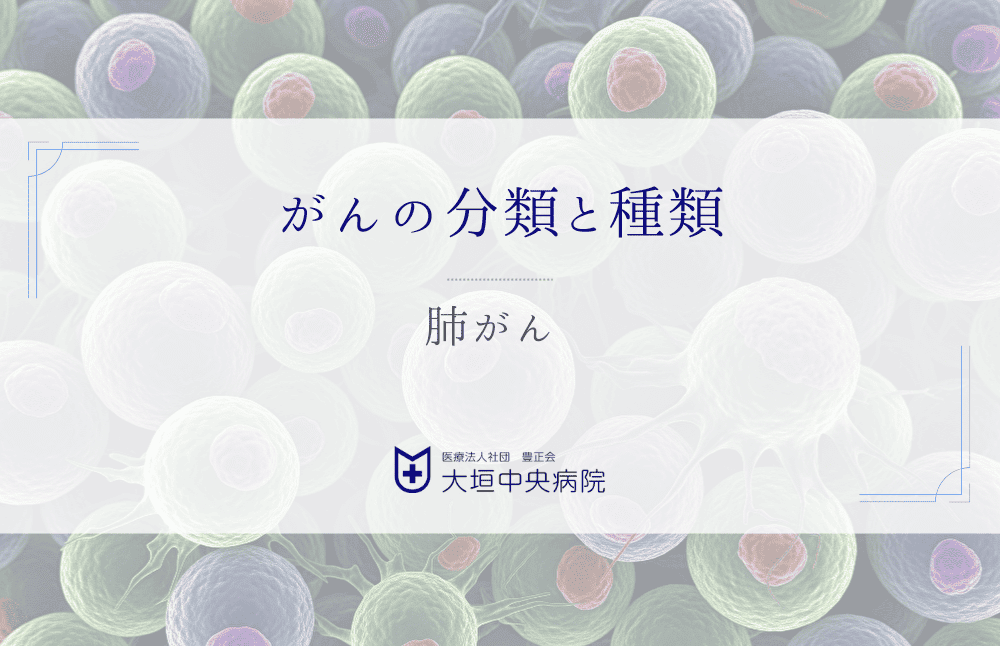
中皮腫
中皮腫は、肺そのものではなく、肺を覆う胸膜、心臓を覆う心膜、腹部の臓器を覆う腹膜といった「中皮細胞」から発生するまれながんです。
その発生には、アスベスト(石綿)への曝露が強く関与していることが知られています。アスベストを吸い込んでから数十年という非常に長い潜伏期間を経て発症するのが大きな特徴です。
中皮腫とは
概要と発生部位
中皮腫は、体の内臓を覆う薄い膜である中皮から発生する悪性腫瘍です。最も多く発生するのは肺を覆う胸膜で、これを「悪性胸膜中皮腫」と呼びます。
次いで、腹部の臓器を覆う腹膜に発生する「悪性腹膜中皮腫」があります。まれに、心臓を包む心膜や精巣を包む精巣鞘膜から発生することもあります。がんは膜状に広がるように進行していく特徴があります。
アスベスト(石綿)との関連
中皮腫の発生原因のほとんどは、アスベストの粉じんを吸い込むことにあると考えられています。アスベストは、かつて断熱材や建材として広く使用されていました。
非常に細い繊維であるため、吸い込むと肺の奥深くに達し、長期間体内に留まります。このアスベスト繊維が中皮細胞を刺激し続け、長い年月をかけてがん化を引き起こすのです。
曝露から発症までの潜伏期間は平均して40年から50年と非常に長く、過去にアスベスト関連の職業に従事していた人や、その家族、工場周辺の住民などに発症リスクがあります。
中皮腫の種類
中皮腫は、がん細胞の形によって「上皮型」「肉腫型」「二相型」の3つの組織型に分類されます。この分類は、がんの進行の仕方や治療法の選択、予後(病気の見通し)に影響します。
上皮型
中皮腫の中で最も多いタイプで、全体の約60%を占めます。比較的進行が緩やかで、他の型に比べて治療が効きやすい傾向があります。予後も比較的良好とされています。
肉腫型
全体の約10%を占めるタイプです。進行が速く、治療の効果が得られにくいことが多い、悪性度の高い型です。
二相型
上皮型と肉腫型の両方の特徴をあわせ持つタイプで、全体の約30%を占めます。どちらの成分が多いかによって、その後の経過は異なります。
症状の特徴
中皮腫の症状は、発生した部位によって異なります。また、アスベスト曝露から発症までの潜伏期間が非常に長いため、原因を特定しにくいこともあります。
胸膜中皮腫の症状
最も一般的な症状は、胸水(胸腔内に水がたまること)による息切れや呼吸困難です。また、胸の痛み、咳、体重減少、原因不明の発熱なども見られます。
症状が片側の胸に現れることが多いのも特徴です。
腹膜中皮腫の症状
腹水(腹腔内に水がたまること)によるお腹の張りや膨満感、腹痛、食欲不振、便秘などが主な症状です。腹部にしこりを感じることもあります。
潜伏期間の長さ
中皮腫の最大の特徴は、原因となるアスベストを吸い込んでから発症するまでに、20年から60年、平均で40年という極めて長い年月がかかる点です。
そのため、本人はアスベストを吸ったという自覚がない場合も少なくありません。若い頃の職業や住環境などが、高齢になってから発症する原因となるのです。
検査と診断
中皮腫の診断は、他の疾患との区別が難しく、専門的な知識と経験が必要です。画像検査で疑いを持ち、最終的には組織を採取して病理診断で確定します。
画像検査と血液検査
胸部X線検査やCT検査で、胸膜の肥厚や凹凸、胸水の貯留などを確認します。腹膜中皮腫の場合は、腹部CT検査や超音波(エコー)検査が有用です。
血液検査では、特定の腫瘍マーカー(SMRPなど)を測定することが診断の補助となりますが、これだけで確定診断はできません。
確定診断のための検査
確定診断のためには、がんが疑われる組織を採取する生検が必須です。胸膜中皮腫では、胸腔鏡という内視鏡を用いて胸膜の組織を直接観察しながら採取します。
腹膜中皮腫では、腹腔鏡を用いて腹膜の組織を採取します。採取した組織を顕微鏡で詳しく調べ、中皮腫であることを確定し、組織型(上皮型、肉腫型、二相型)を決定します。
中皮腫の主な治療法
| 治療法 | 目的 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 手術(外科治療) | がんを可能な限り取り除き、根治を目指す | 比較的早期で、全身状態が良好な患者さん |
| 薬物療法 | がんの進行を抑え、症状を和らげる | 手術が難しい進行・再発の患者さん |
| 放射線治療 | がんによる痛みを和らげる、手術後の再発を予防する | 症状緩和、術後補助療法など |
治療の考え方
中皮腫の治療は、病期、組織型、患者さんの年齢や全身状態を総合的に判断して、最適な方法を検討します。一つの治療法だけでなく、複数の治療法を組み合わせる「集学的治療」が基本となります。
集学的治療
根治を目指せる可能性がある場合は、手術、抗がん剤治療、放射線治療を組み合わせた集学的治療を行います。
例えば、手術の前に抗がん剤治療を行ってがんを小さくしたり(術前化学療法)、手術後に残っている可能性のあるがん細胞をたたくために放射線治療を行ったりします(術後放射線療法)。
症状を和らげる治療
がんが進行していて根治的な治療が難しい場合でも、薬物療法によってがんの進行を遅らせたり、放射線治療で痛みを和らげたり、胸水や腹水を抜いて呼吸困難やお腹の張りを改善したりするなど、症状を緩和し、生活の質(QOL)を維持するための治療を積極的に行います。
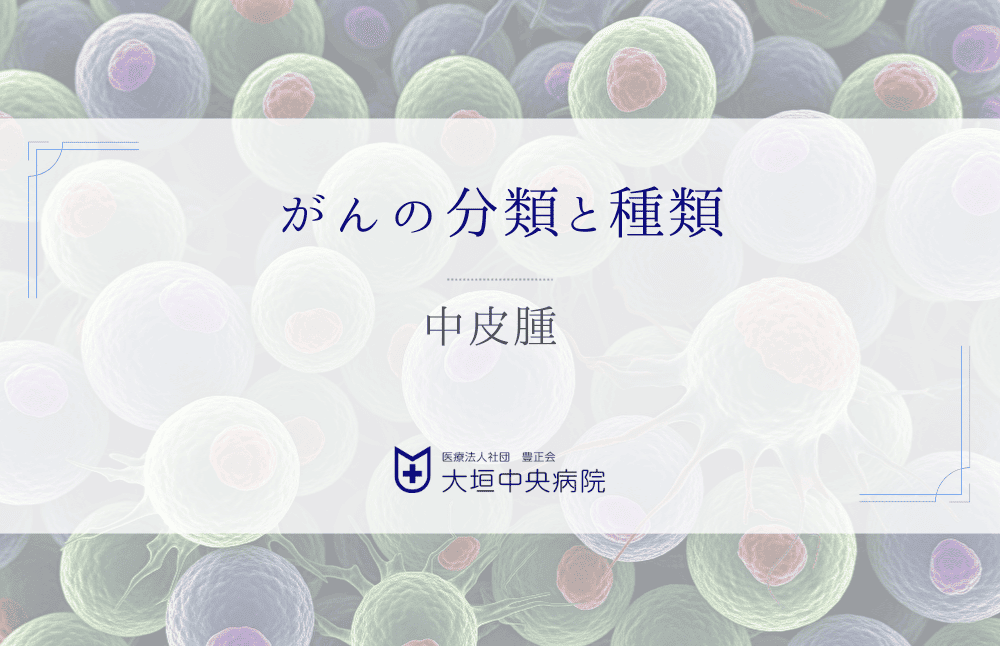
よくある質問
- 呼吸器系のがんは遺伝しますか?
-
一般的に、肺がんや中皮腫が親から子へ直接遺伝することはまれです。
しかし、家族に肺がんになった人がいる場合、全くいない人と比べて肺がんになりやすい「遺伝的感受性」を持つ可能性が指摘されています。
ただし、それ以上に喫煙などの生活習慣が発症に大きく影響します。家族歴がある方は、特に禁煙を心がけ、定期的にがん検診を受けることが大切です。
- 禁煙すれば肺がんのリスクはなくなりますか?
-
禁煙しても、肺がんのリスクがすぐにゼロになるわけではありません。喫煙によって受けた肺のダメージは、ある程度残ります。
しかし、禁煙を始めたその日からリスクは下がり始め、禁煙期間が長くなるほど、リスクは着実に低下していきます。
10年禁煙すると、喫煙を続けている人に比べて肺がんのリスクは約半分になると言われています。何歳であっても、禁煙を始めるのに遅すぎることはありません。
- アスベストを吸った可能性がある場合、どうすればよいですか?
-
過去にアスベスト関連の仕事に従事していた、あるいは家族にそのような方がいたなど、アスベスト曝露の心当たりがある場合は、まずその事実を認識しておくことが重要です。
すぐに何らかの症状が出るわけではありませんが、定期的に(年に1回程度)胸部X線検査などの健康診断を受けることをお勧めします。
咳や息切れ、胸の痛みなどの症状が現れた場合は、すぐに呼吸器科の専門医を受診し、アスベスト曝露の可能性があることを必ず伝えてください。
- 治療中の生活で気をつけることは何ですか?
-
治療中は体力や免疫力が低下しやすいため、心身ともに無理のない生活を送ることが基本です。
主治医や看護師、栄養士などと相談しながら、ご自身の体調に合わせて生活を整えていきましょう。
日常生活での心がけ
- 栄養バランスの取れた食事
- 無理のない範囲での適度な運動
- 十分な休息と睡眠
- 感染症予防(手洗い、うがい、人混みを避ける)
- 禁煙と節酒
がんは、呼吸器だけでなく体の様々な部位に発生する可能性があります。
それぞれの部位のがんについて特徴や治療法を知ることは、ご自身の体への理解を深め、健康管理意識を高める上で役立ちます。
例えば、男性では前立腺がん、女性では子宮がんや卵巣がん、男女共通では膀胱がんや腎臓がんなどを含む「泌尿生殖器系がん」も、早期発見と適切な治療が重要となる疾患群です。
これらの疾患についても知識を深めたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
以上
参考文献
COLLINS, Lauren G., et al. Lung cancer: diagnosis and management. American family physician, 2007, 75.1: 56-63.
HIRSCH, Fred R., et al. Lung cancer: current therapies and new targeted treatments. The Lancet, 2017, 389.10066: 299-311.
MOLINA, Julian R., et al. Non-small cell lung cancer: epidemiology, risk factors, treatment, and survivorship. In: Mayo clinic proceedings. Elsevier, 2008. p. 584-594.
MIHAJLOVIC, Marija, et al. Primary mucosal melanomas: a comprehensive review. International journal of clinical and experimental pathology, 2012, 5.8: 739.
ALDUAIS, Yaser, et al. Non-small cell lung cancer (NSCLC): A review of risk factors, diagnosis, and treatment. Medicine, 2023, 102.8: e32899.
HENDRIKS, Lizza EL, et al. Non-small-cell lung cancer. Nature Reviews Disease Primers, 2024, 10.1: 71.
ZAPPA, Cecilia; MOUSA, Shaker A. Non-small cell lung cancer: current treatment and future advances. Translational lung cancer research, 2016, 5.3: 288.
RAMALINGAM, Suresh S.; OWONIKOKO, Taofeek K.; KHURI, Fadlo R. Lung cancer: New biological insights and recent therapeutic advances. CA: a cancer journal for clinicians, 2011, 61.2: 91-112.
RODAK, Olga, et al. Current landscape of non-small cell lung cancer: epidemiology, histological classification, targeted therapies, and immunotherapy. Cancers, 2021, 13.18: 4705.
GRIDELLI, Cesare, et al. Non-small-cell lung cancer. Nature reviews Disease primers, 2015, 1.1: 1-16.