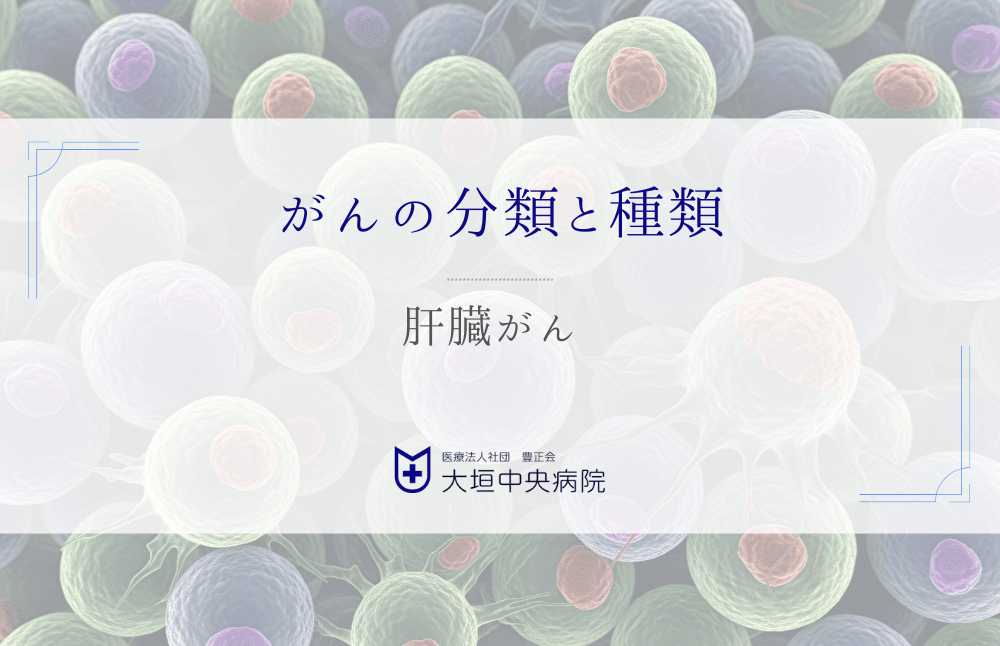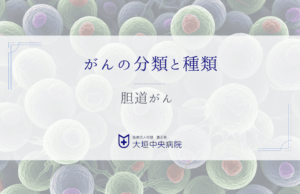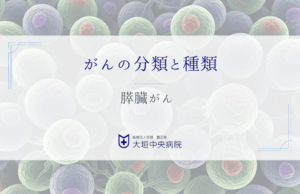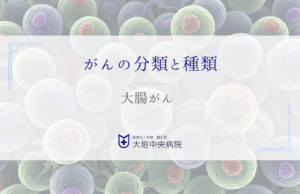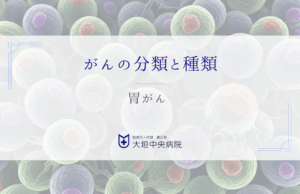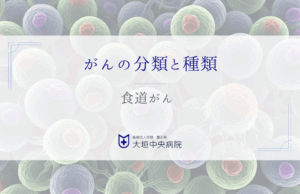肝臓がんという診断は、ご本人だけでなくご家族にとっても大きな衝撃です。
しかし、正確な知識を持つことが、不安を和らげ、これから進むべき道を照らす光となります。
この記事では、肝臓がんの基本的な情報から、原因、症状、検査、そして治療法に至るまで、あなたとご家族が知っておくべき大切な情報を網羅的に解説します。
肝臓がんとは何か – 病気の基本を理解する
肝臓がんは、肝臓の細胞が異常に増殖してできる悪性の腫瘍です。この病気を正しく理解するためには、まず、がんがどのように発生するかによって、大きく二つの種類に分けられることを知るのが重要です。
それぞれ性質が異なり、治療の方針も変わってきます。ここでは、その基本的な違いから解説を始めます。
肝臓から発生する「原発性肝がん」
原発性肝がんは、肝臓そのものの細胞から発生するがんです。日本で「肝臓がん」という場合、その90%以上がこのタイプに含まれる「肝細胞がん」を指します。
肝細胞がんは、多くの場合、長年の肝臓のダメージが背景にあります。
代表的な原発性肝がん「肝細胞がん」
肝細胞がんは、肝臓の主要な細胞である「肝細胞」ががん化するものです。
慢性的な肝臓の炎症や肝硬変が進行する過程で発生することが多く、背景にある肝臓の状態が治療法を考える上で非常に重要になります。
他の臓器から広がる「転移性肝がん」
転移性肝がんは、大腸や胃、肺など、他の臓器で発生したがん細胞が、血液の流れに乗って肝臓にたどり着き、そこで増殖するものです。
肝臓は多くの血液が流れ込む臓器であるため、他の臓器からのがんの転移が起こりやすい場所の一つです。この場合、治療は元の臓器のがん(原発巣)の性質に基づいて考えます。
原発性肝がんと転移性肝がんの比較
| 項目 | 原発性肝がん | 転移性肝がん |
|---|---|---|
| 発生の仕方 | 肝臓の細胞ががん化する | 他の臓器のがんが肝臓に広がる |
| 主な種類 | 肝細胞がん、肝内胆管がん | 原発巣(大腸がん、胃がん等)に準じる |
| 治療の考え方 | がんの進行度と肝機能で決定する | 元の臓器のがんに対する治療法が基本 |
肝臓がんの原因とリスク要因
肝臓がん、特に肝細胞がんの多くは、何の背景もなく突然発生するわけではありません。その多くは、長期間にわたる肝臓への負担が引き金となります。
主な原因を知り、ご自身の持つリスク要因を把握することは、予防や早期発見への第一歩です。
最大の原因はウイルス性肝炎
日本の肝細胞がんの最も大きな原因は、B型肝炎ウイルス(HBV)およびC型肝炎ウイルス(HCV)の持続的な感染です。
これらのウイルスに感染すると、肝臓で慢性的な炎症が続き、徐々に肝臓の細胞が壊れては再生するというサイクルを繰り返します。この過程で遺伝子に傷がつき、がんが発生しやすくなります。
肝硬変という土壌
肝硬変は、慢性的な肝臓の炎症によって肝臓が硬くなり、機能が著しく低下した状態です。ウイルス性肝炎やアルコールの過剰摂取などが原因で起こります。
肝硬変の状態は、それ自体が肝細胞がんの非常に高いリスク要因であり、「がんが発生しやすい土壌」ともいえます。肝硬変と診断された方は、特に注意深い経過観察が必要です。
近年増加する生活習慣との関連
ウイルス感染によらない肝臓がんも増えています。
特に注目されるのが、過度の飲酒によるアルコール性肝障害や、肥満、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病に関連する非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)です。
これらが進行すると、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)となり、肝硬変を経て肝細胞がんへと至るケースが問題になっています。
肝臓がんの主なリスク要因
| リスク要因 | 概要 | 関連する状態 |
|---|---|---|
| B型・C型肝炎ウイルス | 持続感染により慢性肝炎を引き起こす最大の原因。 | 慢性肝炎、肝硬変 |
| アルコールの過剰摂取 | 長期的な多量飲酒は肝臓に大きな負担をかける。 | アルコール性肝障害、肝硬変 |
| 肥満・糖尿病 | 脂肪肝から非アルコール性脂肪肝炎(NASH)に進行する。 | 脂肪肝、NASH |
症状と早期発見の重要性
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期の段階では自覚できる症状がほとんど現れません。これが肝臓がんの発見を遅らせる一因となっています。
症状が現れたときには、病気がかなり進行していることも少なくありません。だからこそ、症状のサインを見逃さず、リスクのある方は定期的な検査を受けることが極めて重要です。
気づきにくい初期症状
肝臓がんの初期症状は、あったとしても非常に軽微で、他の病気や単なる体調不良と間違えやすいものばかりです。
例えば、なんとなく体がだるい、食欲がないといった変化は、多忙な日常の中では見過ごされがちです。この段階でがんに気づくことは難しく、多くは健康診断や他の病気の検査で偶然発見されます。
進行とともに現れる症状
がんが大きくなったり、肝臓の機能が低下したりすると、よりはっきりとした症状が現れ始めます。
お腹の張り(腹水)、皮膚や白目が黄色くなる(黄疸)、むくみ、お腹のしこりや圧迫感、痛みなどがその代表です。
これらの症状は、肝臓がSOSを発しているサインであり、速やかに医療機関を受診する必要があります。
注意すべき症状のサイン
| 症状の段階 | 主な症状の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 初期症状 | 全身の倦怠感、食欲不振 | 自覚しにくく、見過ごされやすい。 |
| 進行期の症状 | 腹部の張り、黄疸、むくみ、痛み | 病気が進行している可能性を示すサイン。 |
検査と診断方法
肝臓がんが疑われる場合、あるいはリスクの高い方が定期的に受ける検診では、いくつかの検査を組み合わせて診断を確定していきます。
画像でがんの存在を直接確認する方法と、血液中の特定の物質を調べる方法が中心となります。これらの検査によって、がんの有無、大きさ、数、広がり、そして肝臓の状態を総合的に評価します。
血液検査で手がかりを探す
血液検査は、体への負担が少なく、がんのスクリーニング(ふるい分け)に役立ちます。
肝機能の状態を調べるAST(GOT)やALT(GPT)などの項目に加え、がん細胞が作り出す特殊な物質「腫瘍マーカー」を測定します。
腫瘍マーカーによる検査
肝細胞がんの代表的な腫瘍マーカーには、「AFP(アルファ・フェトプロテイン)」と「PIVKA-II(ピブカ・ツー)」があります。これらの数値が高い場合、肝細胞がんの存在が疑われます。
ただし、がんがあっても数値が上昇しないことや、肝炎や肝硬変だけでも数値が上がることがあるため、この検査だけで診断を確定することはできません。画像検査と合わせて判断します。
画像検査でがんを直接見る
がんの確定診断には、画像検査が欠かせません。超音波(エコー)検査は手軽に行えるため、最初のスクリーニングで広く用いられます。
より詳しく調べるためには、造影剤を使用したCT検査やMRI検査を行います。これらの検査によって、がんの正確な位置、大きさ、数、血管との関係などを詳細に把握できます。
主な画像診断検査
| 検査方法 | 特徴 | 目的 |
|---|---|---|
| 腹部超音波検査 | 体に負担が少なく、簡便に行える。 | がんのスクリーニング、大きさや形の確認。 |
| 造影CT/MRI検査 | 造影剤を使い、がんを鮮明に映し出す。 | がんの確定診断、詳細な性状の評価。 |
肝臓がんの病期(ステージ)分類
がんの治療方針を決定する上で、病状がどのくらい進行しているかを示す「病期(ステージ)」を正確に把握することが重要です。
肝臓がんのステージは、単にがんの大きさや数だけでなく、肝臓自体の機能がどの程度保たれているか(肝障害度)という、もう一つの重要な要素を組み合わせて総合的に判断します。
ステージを決める3つの要素
肝臓がんのステージ分類では、主に以下の3つの情報から総合的に評価します。
- 腫瘍の状態(大きさ、数、血管への広がり)
- 他の臓器への転移の有無
- 肝機能の状態(肝障害度)
肝障害度という重要な視点
肝臓がん治療の大きな特徴は、がんを治療するだけでなく、背景にある肝臓の機能(予備能)を守る必要がある点です。
どんなに早期のがんであっても、肝機能が著しく低下している場合は、体に大きな負担をかける治療(例えば大きな手術)を行うことができません。
そのため、治療法はがんの進行度と肝障害度のバランスをみて慎重に選択します。
ステージと治療方針の考え方
| ステージ(進行度) | 一般的ながんの状態 | 治療方針の方向性 |
|---|---|---|
| 早期 | がんが小さく、数が少ない。 | 根治を目指す局所的な治療(手術など)を検討する。 |
| 中間期 | がんが複数あるが、肝臓内に留まる。 | がんの進行を制御する治療(カテーテル治療など)が中心。 |
| 進行期 | 血管への広がりや、他の臓Cへの転移がある。 | 全身に効果を及ぼす薬物療法などを検討する。 |
生存率について
ステージは、今後の見通しを予測するための一つの指標でもあります。一般的に、ステージが進むほど5年相対生存率は低くなる傾向があります。
しかし、生存率は多くの患者さんのデータの平均値であり、個々の患者さんの状況を正確に表すものではありません。
あくまで一つの目安として捉え、担当医と今後の治療についてしっかりと話し合うことが大切です。
治療の選択肢と考え方
肝臓がんの治療法は多岐にわたります。
どの治療法を選択するかは、前述の「ステージ」と「肝障害度」を総合的に評価して、一人ひとりの患者さんにとって最善の方法を慎重に決定します。
ここでは、主な治療の選択肢と、それぞれの考え方について解説します。
根治を目指す外科治療(手術)
手術(肝切除術)は、がんの部分を肝臓の一部とともに切り取る治療法で、根治を目指せる強力な選択肢の一つです。
特に、がんの数が少なく、肝機能が良好に保たれている場合に検討します。がんを物理的に取り除くため、確実性が高い方法ですが、体への負担も大きいため、手術後に十分な肝臓の機能を維持できるかどうかの見極めが重要です。
体を傷つけにくい局所療法
体の外から針を刺してがんを直接治療する方法です。代表的なものに「ラジオ波焼灼療法(RFA)」があります。
超音波でがんの位置を確認しながら特殊な針を刺し、針の先端からラジオ波を流して熱を発生させ、がん細胞を焼き固めます。
手術に比べて体への負担が少なく、高齢の方や肝機能が少し低下している方でも行えることがあります。
カテーテルを用いた治療
足の付け根の血管から細い管(カテーテル)を挿入し、肝臓の動脈まで進めて行う治療です。主に「肝動脈化学塞栓療法(TACE)」が行われます。
これは、がんに栄養を送っている血管を塞栓物質で詰まらせ、同時に抗がん剤を注入することで、がんを兵糧攻めにする治療法です。手術が難しい複数の病変がある場合に良い適応となります。
全身に働きかける薬物療法
薬物療法は、がんが進行して手術や局所療法が難しい場合や、他の臓器への転移がある場合に行う全身治療です。
飲み薬である「分子標的薬」や、体の免疫の力を利用してがんを攻撃する「免疫チェックポイント阻害薬」など、近年新しい薬が次々と登場しています。
これらの薬は、がんの増殖を抑え、延命や症状緩和を目指します。
主な治療法の比較
| 治療法 | 主な対象 | 目的 |
|---|---|---|
| 手術(肝切除) | 早期で肝機能が良好な場合 | 根治 |
| 局所療法(ラジオ波など) | 早期で手術が難しい場合 | 根治またはそれに準じる効果 |
| カテーテル治療(TACE) | がんが複数ある中間期 | がんの進行抑制 |
| 薬物療法 | 進行期や転移がある場合 | 延命、症状緩和 |
再発や転移に対する考え方
肝臓がんの治療で難しい点の一つが、治療後の再発です。
肝臓がんの背景には慢性肝炎や肝硬変といった「がんができやすい土壌」があるため、一度がんを取り除いても、肝臓の別の場所に新しいがん(多中心性発生)が出現することがあります。
そのため、治療後も定期的な検査を継続し、再発を早期に発見して迅速に対応することが極めて重要です。
がん治療中の生活と心のケア
がんの治療は、身体的な負担だけでなく、精神的にも大きな影響を及ぼします。治療を乗り越え、自分らしい生活を続けるためには、副作用への対処、栄養管理、そして心のケアが同じように大切です。
家族や医療スタッフと協力しながら、生活の質(QOL)を保つ工夫をしていきましょう。
副作用との付き合い方
治療法によって様々な副作用が現れる可能性があります。例えば、薬物療法では倦怠感、食欲不振、皮膚障害などが、TACEでは発熱や腹痛などが起こることがあります。
どのような副作用が起こりうるのかを事前に医師や看護師からよく聞き、症状が現れたときには我慢せず、すぐに相談することが重要です。症状を和らげるための薬や工夫がたくさんあります。
治療を支える栄養と食事
治療中は食欲が落ちたり、味が変わったりすることがあります。しかし、治療を乗り切る体力を維持するためには、栄養バランスの取れた食事が基本です。
無理にたくさん食べようとせず、食べられるものを、食べられるときに、少量ずつでも口にするように心がけましょう。管理栄養士に相談し、食事の工夫についてアドバイスをもらうことも有効です。
不安や悩みを抱え込まない
がんという診断や治療の過程では、誰もが不安や恐怖、孤独感などを感じるものです。こうした気持ちを一人で抱え込む必要はありません。
ご家族や信頼できる友人に話すだけでも、気持ちが楽になることがあります。また、病院にはがん専門の相談員や心理士がいることも多いので、専門家のサポートを受けることも考えてみましょう。
緩和ケアという考え方
緩和ケアは、終末期の医療というイメージがあるかもしれませんが、本来はもっと広い意味を持ちます。
がんの治療に伴う身体的・精神的な苦痛を和らげ、患者さんとそのご家族がより良い生活を送れるように支えるためのアプローチです。
診断された早い段階から、痛みやだるさ、不安などのつらい症状があれば、緩和ケアチームに相談することができます。治療と並行して行うことで、生活の質を高める助けになります。
予防と定期検診の大切さ
肝臓がんの多くは、原因となる背景があります。つまり、その原因に対して対策を講じることで、発がんのリスクを下げることが可能です。
また、不幸にしてがんが発生してしまっても、早期に発見できれば根治の可能性が高まります。予防と定期検診は、肝臓がんから身を守るための両輪といえます。
肝炎ウイルスの検査と治療
肝臓がんの最大の原因であるB型・C型肝炎ウイルスは、血液検査で感染の有無を調べることができます。多くの自治体で無料または安価な検診制度があります。
もし感染が分かっても、近年はウイルスの増殖を抑える優れた薬があり、適切な治療を受けることで肝硬変や肝臓がんへの進行を大幅に防ぐことができます。
一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けることが推奨されます。
生活習慣の見直し
アルコールの飲み過ぎを控え、休肝日を設けることは肝臓をいたわる基本です。
また、肥満や糖尿病も肝臓がんのリスクを高めるため、バランスの取れた食事と適度な運動を心がけ、健康的な体重を維持することが、ウイルス感染以外の原因による肝臓がんの予防につながります。
リスクの高い方は定期的な検査を
肝炎ウイルスに感染している方、肝硬変と診断されている方、あるいは大量飲酒の習慣がある方など、肝臓がんのリスクが高い方は、症状がなくても定期的に専門医の診察を受ける必要があります。
定期検査の主な内容
- 血液検査(肝機能、腫瘍マーカー)
- 腹部超音波検査
これらの検査を半年に1回程度の頻度で受けることで、万が一がんが発生しても、治療がしやすい早期の段階で発見できる可能性が高まります。
よくある質問
- 一度治療が終わっても、なぜ再発するのですか?
-
肝臓がんの再発には二つのパターンがあります。
一つは、治療で取りきれなかった小さながんが再び大きくなる「転移による再発」。もう一つは、がんの土壌である肝硬変の肝臓から、全く新しいがんが発生する「多中心性発生」です。
このため、治療後も定期的な検査で肝臓全体を監視し続けることが重要になります。
- ステージIVだと、もう治療法はないのでしょうか?
-
ステージIVは進行した状態を指しますが、治療法がないわけではありません。
近年、効果の高い薬物療法が次々と登場しており、がんの進行を抑え、症状を和らげることで、より長く、より良い生活を送ることを目指します。
治療の選択肢は常に進歩していますので、希望を失わず、担当医とよく話し合うことが大切です。
- 治療の副作用が心配です
-
副作用の出方や程度は、治療法や個人によって様々です。医師や看護師は、どのような副作用が起こりうるか、またその対処法について事前に詳しく説明します。
つらい症状を我慢する必要はありません。症状をコントロールするための良い方法がたくさんありますので、些細なことでも医療スタッフに伝えるようにしてください。
緩和ケアチームも力になってくれます。
がんは臓器によってその性質や治療法が大きく異なります。肝臓と同じく消化器系のがんである「膵臓がん」も、早期発見が難しく、特有の課題を持つ病気です。
ご自身やご家族の健康を守るため、他のがんについても知識を深めておくことは有益です。
膵臓がんの症状や検査、治療法についてまとめた解説記事も、ぜひ合わせてお読みください。
参考文献
HUPPERT, Laura A.; GORDAN, John D.; KELLEY, Robin Kate. Checkpoint inhibitors for the treatment of advanced hepatocellular carcinoma. Clinical Liver Disease, 2020, 15.2: 53-58.
DONISI, Clelia, et al. Immune checkpoint inhibitors in the treatment of HCC. Frontiers in oncology, 2021, 10: 601240.
PERSONENI, Nicola, et al. Hepatotoxicity in patients with hepatocellular carcinoma on treatment with immune checkpoint inhibitors. Cancers, 2021, 13.22: 5665.
BIEWENGA, Maaike, et al. Checkpoint inhibitor induced hepatitis and the relation with liver metastasis and outcome in advanced melanoma patients. Hepatology international, 2021, 15.2: 510-519.
RIVEIRO-BARCIELA, Mar, et al. Retreatment with immune checkpoint inhibitors after a severe immune-related hepatitis: results from a prospective multicenter study. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2023, 21.3: 732-740.
MONGE, Cecilia, et al. Clinical indicators for long-term survival with immune checkpoint therapy in advanced hepatocellular carcinoma. Journal of Hepatocellular Carcinoma, 2021, 507-512.
LOMBARDI, Andrea; MONDELLI, Mario U. immune checkpoint inhibitors and the liver, from therapeutic efficacy to side effects. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 2019, 50.8: 872-884.
CHENG, Huijuan, et al. Trends in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma: immune checkpoint blockade immunotherapy and related combination therapies. American journal of cancer research, 2019, 9.8: 1536.
LEE, Pei-Chang, et al. Predictors of response and survival in immune checkpoint inhibitor-treated unresectable hepatocellular carcinoma. Cancers, 2020, 12.1: 182.
消化器系がんに戻る