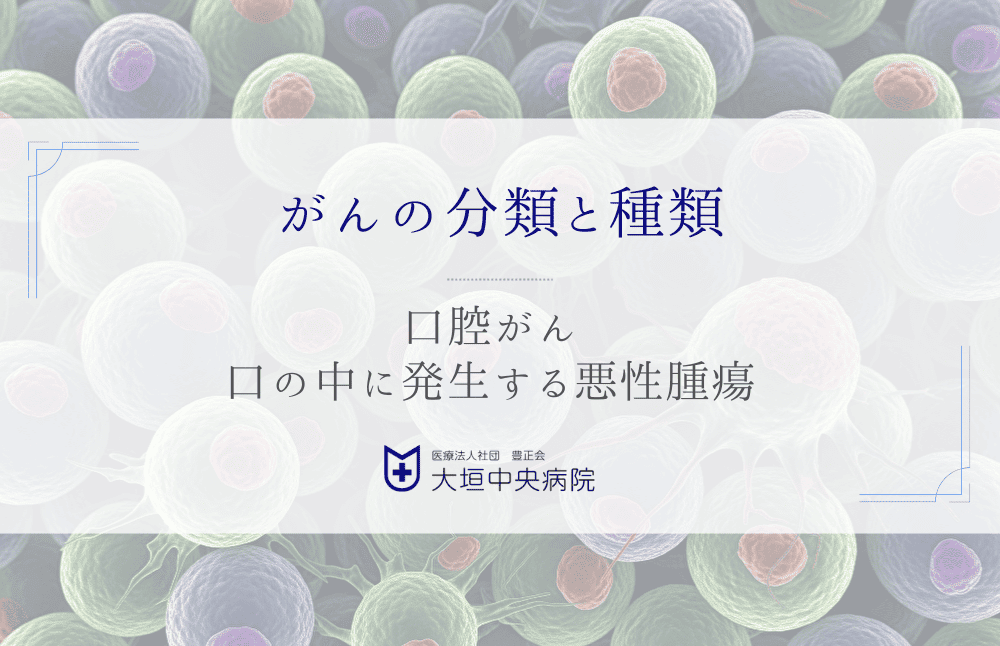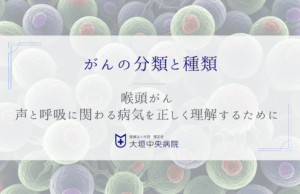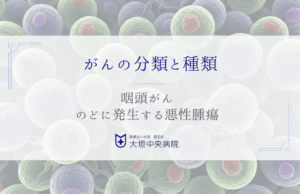口の中にがんができる「口腔がん」について、不安や疑問を抱えている方は少なくありません。
この記事は、口腔がんと診断された方や、その疑いがある方、そしてご家族の方々に向けて、正確な情報を分かりやすく提供することを目的としています。
口腔がんの基本的な知識から、原因、症状、検査、治療法、そして治療後の生活に至るまで、幅広く解説します。
口腔がんとは何か – 発生部位と基本的な特徴
口腔がんは、その名の通り口の中(口腔)に発生するがんの総称です。口は食事や会話、呼吸など、私たちが生きていく上で非常に重要な役割を担っています。
そのため、口腔がんは生活の質(QOL)に大きく影響を及ぼす可能性があります。ここでは、口腔がんがどこにでき、どのような特徴を持つのか、基本的な知識を解説します。
口腔がんの定義と発生部位
口腔がんは、口の中の粘膜から発生する悪性腫瘍です。発生する場所によって、舌がん、歯肉(しにく)がん、口底(こうてい)がん、頬粘膜(きょうねんまく)がん、口蓋(こうがい)がんなどに分類されます。
日本では、舌にできる「舌がん」が最も多く、口腔がん全体の半数以上を占めています。日頃から鏡で口の中をチェックする習慣をつけることが、早期発見につながります。
口腔がんが発生しやすい場所
| 発生部位 | 特徴 | 注意すべき初期症状の例 |
|---|---|---|
| 舌 | 最も発生頻度が高い。特に舌の側面(縁)にできやすい。 | 舌のしこり、治らない口内炎、出血 |
| 歯肉(歯ぐき) | 歯周病と間違われることがある。入れ歯の不具合で気づくことも。 | 歯ぐきの腫れ、歯のぐらつき、出血 |
| 口底(舌の下) | 舌の下側の部分。自分では見つけにくい場所。 | 舌の下のしこり、痛み、話しにくさ |
| 頬粘膜(頬の内側) | 歯が当たる部分にできやすい。白斑(はくはん)が見られることも。 | 頬の内側のしこり、ただれ、白い膜 |
代表的な口腔がんの種類
口腔がんの90%以上は「扁平上皮(へんぺいじょうひ)がん」という種類です。これは、口の中の表面を覆っている粘膜の細胞から発生します。
まれに、唾液を作る組織から発生する腺がんや、悪性黒色腫(メラノーマ)、肉腫などができることもあります。がんの種類によって進行の速さや治療法が異なるため、正確な診断が重要です。
主な口腔がんの種類
- 扁平上皮がん
- 腺様嚢胞がん
- 粘表皮がん
- 悪性黒色腫
口腔がんの進行度(ステージ)分類
がんの進行度合いは「ステージ」で表し、治療方針を決める上で重要な指標となります。
口腔がんのステージは、がんの大きさ(T)、頸部リンパ節への転移の有無(N)、他の臓器への遠隔転移の有無(M)を組み合わせた「TNM分類」を用いて決定します。
ステージは0期からⅣ期まであり、数字が大きくなるほど進行していることを示します。早期のステージであれば、治療による体への負担も少なく、良好な経過が期待できます。
口腔がんの主な原因とリスク因子
口腔がんがなぜ発生するのか、そのはっきりとした原因はまだ完全には解明されていません。しかし、長年の研究から、特定の生活習慣や要因が発症のリスクを高めることがわかっています。
これらのリスク因子を知り、可能な限り避けることが、口腔がんの有効な予防につながります。
生活習慣に関連するリスク
口腔がんの最大の原因として指摘されているのが、喫煙と飲酒です。タバコに含まれる多くの発がん性物質が、口の中の粘膜を直接刺激し、がん細胞の発生を促します。
また、アルコールもそれ自体に発がん性があるほか、発がん性物質を細胞内に浸透させやすくする作用があります。
喫煙と飲酒の相乗効果
特に注意が必要なのは、喫煙と飲酒の両方の習慣がある場合です。タバコを吸いながらお酒を飲むと、がんの発生リスクが片方だけの場合に比べて飛躍的に高まることが知られています。
この二つの習慣は、口腔がん予防の観点から、まず最初に見直すべき点と言えます。
その他のリスク因子
生活習慣以外にも、口腔がんのリスクを高める要因はいくつか存在します。例えば、合わない入れ歯や被せ物、欠けたり尖ったりした歯が長期間にわたって舌や頬の粘膜を刺激し続けることも、がんの発生原因となり得ます。
また、口の中が不衛生な状態であることもリスクを高めます。定期的な歯科検診で、口の中の状態をチェックしてもらうことが大切です。
口腔がんの主なリスク因子
| リスク因子 | 関連性 | 主な対策 |
|---|---|---|
| 喫煙 | 最大のリスク因子。受動喫煙も含む。 | 禁煙 |
| 飲酒 | 特に多量飲酒はリスクを高める。 | 節度ある飲酒、休肝日を設ける |
| 不適切な口腔環境 | 合わない義歯、虫歯、歯周病など。 | 定期的な歯科受診、適切な口腔ケア |
初期に気づくべき口腔がんのサイン
口腔がんは、体の表面に近い場所にできるため、自分で発見できる可能性があるがんです。しかし、初期の段階では痛みなどの自覚症状が少ないことも多く、見過ごされがちです。
どのようなサインに気をつければよいのかを知っておくことが、早期発見・早期治療への第一歩となります。
見た目でわかる初期症状
口の中を鏡で見たときに、普段と違う変化がないかを確認しましょう。特に注意したいのは、赤くなっている部分(紅板症)や白くなっている部分(白板症)です。これらは「前がん病変」といって、がんになる前の状態である可能性があります。
また、なかなか治らない口内炎や、粘膜のただれ、盛り上がったしこりなども重要なサインです。インターネットで口腔がんの写真を検索して参考にすることもできますが、自己判断は禁物です。
少しでも気になる症状があれば、専門医に相談してください。
感覚でわかる初期症状
見た目の変化だけでなく、感覚の変化にも注意が必要です。
例えば、口の中にしこりや硬い部分を感じる、食べ物が飲み込みにくい、口が開きにくい、舌や唇にしびれを感じる、原因不明の歯のぐらつきがある、といった症状です。
初期の口腔がんでは痛みを伴わないことも多いですが、進行すると持続的な痛みが出てくることもあります。
口内炎との見分け方
口の中にできるものとして最も身近なのが口内炎です。多くの人が経験したことがあるため、「また口内炎ができた」と軽く考えてしまうかもしれません。
しかし、口腔がんの初期症状は口内炎とよく似ているため、注意が必要です。見分けるためのポイントは「期間」と「形状」です。
口腔がんの初期症状と口内炎の違い
| 項目 | 口腔がんが疑われる場合 | 一般的な口内炎 |
|---|---|---|
| 治るまでの期間 | 2週間以上経っても治らない、または大きくなる。 | 通常1〜2週間で自然に治る。 |
| 形・硬さ | 境界が不明瞭で、周りが硬いしこりを伴うことがある。 | 円形または楕円形で、境界がはっきりしている。 |
| 痛み | 初期は痛みが無いことも多い。触ると出血しやすい。 | 食べ物などが触れると強い痛みを感じる。 |
診断の流れと検査方法
口の中に気になる症状を見つけたら、まずは専門の医療機関を受診することが重要です。口腔がんは、主に歯科、口腔外科、または耳鼻咽喉科で診療します。
ここでは、診断が確定するまでの一般的な流れと、どのような検査を行うのかについて説明します。
歯科や専門医での初期診察
最初の診察では、医師が症状について詳しく問診します。いつから症状があるのか、痛みはあるか、喫煙や飲酒の習慣はあるかなどを伝えます。その後、口の中を直接見て、触って調べる「視診」と「触診」を行います。
しこりの有無や硬さ、広がりなどを確認する、非常に重要な診察です。この段階でがんが疑われた場合、さらに詳しい検査に進みます。
確定診断のための検査
口腔がんの診断を確定させるために最も重要な検査が「生検(組織検査)」です。これは、疑わしい部分の組織を少量だけ採取し、顕微鏡で詳しく調べる検査です。
この検査によって、細胞が悪性(がん細胞)か良性か、またどのような種類のがん細胞なのかを確定します。局所麻酔で行うことが多く、痛みはほとんどありません。
がんの広がりを調べる検査
生検でがんと診断された場合、次にがんがどの程度広がっているかを調べるための検査を行います。これにより、がんのステージを決定し、最適な治療法を選択します。主な検査には、CTやMRIなどの画像検査があります。
これらの検査によって、がんの深さや大きさ、顎の骨への広がり、そして首のリンパ節への転移の有無などを詳細に評価します。
口腔がんの主な検査方法
| 検査名 | 目的 | 内容 |
|---|---|---|
| 視診・触診 | がんの疑いがあるか、しこりの有無などを調べる。 | 医師が直接、口の中を見て触って診察する。 |
| 生検(組織検査) | がんの確定診断。 | 病変の一部を採取し、顕微鏡でがん細胞の有無を調べる。 |
| CT・MRI検査 | がんの広がり(深さ、大きさ、転移)を調べる。 | X線や磁気を使って体の断面を撮影する。 |
口腔がんの治療法の選択肢
口腔がんの治療は、がんの進行度(ステージ)、発生した場所、がんの種類、そして患者さんご自身の年齢や全身の状態、希望などを総合的に考慮して決定します。
治療の主な柱は「手術」「放射線治療」「薬物療法」の三つです。これらの治療を単独で、あるいは組み合わせて行います。
手術(外科治療)
口腔がん治療の基本となるのが、がんを物理的に取り除く手術です。早期のがんであれば、がんの部分だけを切除する比較的小さな手術で済む場合もあります。
しかし、がんが進行している場合は、周囲の正常な組織を含めて広く切除する必要があります。
舌や顎の骨などを大きく切除した場合には、体の他の部分の組織(皮膚や骨など)を移植して、失われた部分を再建する「再建手術」を同時に行い、治療後の機能(話す、食べる)や見た目をできるだけ損なわないようにします。
また、首のリンパ節への転移がある場合や、その可能性が高い場合には、リンパ節を切除する手術(頸部郭清術)も行います。
放射線治療
放射線治療は、高エネルギーのX線などをがんに照射して、がん細胞を破壊する治療法です。手術のように体を切る必要がないため、臓器の形や機能を温存できるという利点があります。
早期のがんでは放射線治療単独で行うこともありますし、進行がんでは手術と組み合わせたり、薬物療法と同時に行ったりします。
薬物療法(化学療法など)
薬物療法は、抗がん剤などの薬剤を用いてがん細胞の増殖を抑えたり、破壊したりする治療法です。点滴や内服によって、薬剤が血液に乗って全身を巡るため、手術や放射線治療が難しい遠隔転移がある場合にも効果が期待できます。
近年では、がん細胞だけを狙い撃ちする「分子標的薬」や、自身の免疫力を利用してがんと戦う「免疫チェックポイント阻害薬」など、新しい薬も登場し、治療の選択肢が広がっています。
口腔がんのステージ別標準治療法
| ステージ | 主な治療法 | 補足 |
|---|---|---|
| 早期がん (Ⅰ, Ⅱ期) | 手術 または 放射線治療 | 機能温存を重視して治療法を選択する。 |
| 進行がん (Ⅲ, Ⅳ期) | 手術、放射線治療、薬物療法の組み合わせ | 複数の治療法を組み合わせた集学的治療を行う。 |
治療法の選択にあたっては、それぞれの治療のメリット・デメリットについて医師から十分な説明を受け、納得した上で決定することが大切です。
治療後の生存率についても、ステージや個々の状況によって異なりますので、主治医とよく話し合うことが重要です。
【口腔がん全体のステージ別5年相対生存率(目安)】 (全国がんセンター協議会等のデータより)
ステージI: 約80〜90%
※早期発見できれば、簡単な切除で済み、予後は非常に良好です。
ステージII: 約70〜80%
ステージIII: 約50〜60%
ステージIV: 約30〜40%
※進行すると、食事や会話の機能に影響が出る手術が必要になることが多いため、早期発見がQOL維持の鍵となります。
治療後に注意すべき合併症と副作用
口腔がんの治療は、がんを克服するために重要ですが、残念ながら様々な合併症や副作用を伴うことがあります。特に口は、食事や会話といった日常生活に直結する機能を持つため、治療による影響が出やすい部位です。
どのようなことが起こりうるのかを事前に知っておくことで、心の準備ができ、対策を立てやすくなります。
手術後の機能障害
手術で舌や顎、歯などを切除した場合、話すこと(構音障害)や、食べ物を噛んで飲み込むこと(摂食・嚥下障害)が難しくなることがあります。また、顔の見た目が変化することもあります。
これらの機能障害や見た目の変化に対しては、リハビリテーションが非常に重要です。言語聴覚士による発声訓練や飲み込みの訓練、歯科医師による特殊な入れ歯(顎補綴)の作製など、様々な専門家がサポートします。
放射線治療の副作用
放射線治療の副作用は、治療中から現れる急性のものと、治療が終わって数ヶ月から数年経ってから現れる晩発性のものがあります。
代表的な副作用には、口の中の粘膜が荒れる口内炎、唾液が出にくくなる口腔乾燥(ドライマウス)、味覚の変化などがあります。口腔乾燥は虫歯や歯周病のリスクを高めるため、治療中から治療後にかけて、徹底した口腔ケアが必要です。
治療後の一般的な副作用
- 摂食・嚥下障害(食べたり飲んだりする機能の低下)
- 構音障害(言葉をはっきりと発音できない)
- 唾液分泌低下(口の渇き)
- 味覚障害
- 開口障害(口が開きにくい)
再発予防と生活習慣の見直し
治療が無事に終了した後も、口腔がんとの付き合いは続きます。最も大切なのは、再発や新たな二次がんの発生を防ぐことです。
そのためには、定期的な検診を受けることと、がんの原因となった可能性のある生活習慣を見直すことが重要になります。
定期的な検診の重要性
治療後の経過観察のため、定期的に医療機関を受診します。診察では、視診や触診に加え、必要に応じて内視鏡検査や画像検査を行い、再発の兆候がないかをチェックします。
万が一再発した場合でも、早期に発見できれば、再び治療を行うことが可能です。医師の指示に従って、必ず検診を受け続けましょう。
また、かかりつけの歯科医院での定期的なチェックも、再発の早期発見や口腔ケアの維持に役立ちます。
禁煙と節度ある飲酒
口腔がんの最大の原因である喫煙と飲酒の習慣は、治療後も再発のリスクを高めます。治療を機に、きっぱりと禁煙することが強く推奨されます。飲酒についても、できるだけ控えるか、節度ある量にとどめることが大切です。
自身の力だけで難しい場合は、禁煙外来などを利用することも一つの方法です。
再発予防のための生活習慣
| 項目 | 具体的な行動 | 目的 |
|---|---|---|
| 定期検診 | 主治医の指示通りの受診、歯科でのチェック | 再発・二次がんの早期発見 |
| 生活習慣 | 禁煙、節酒 | 発がんリスクの低減 |
| 口腔ケア | 毎日の丁寧な歯磨き、うがい | 口腔内を清潔に保ち、感染を予防する |
口腔がん患者を支える医療チームと相談の場
口腔がんの治療は、一人の医師だけで行うものではありません。様々な分野の専門家がチームを組み、患者さん一人ひとりにとって最善の医療を提供します。また、治療や療養生活に関する悩みや不安を相談できる場所もあります。
これらのサポートを積極的に活用することが、安心して治療を受けることにつながります。
口腔がん治療を支える専門家たち
治療の中心となるのは口腔外科医や耳鼻咽喉科医ですが、その他にも放射線治療医、腫瘍内科医、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、言語聴覚士、理学療法士、医療ソーシャルワーカーなど、多くの専門家が関わります。
それぞれの専門性を活かして、治療からリハビリ、社会復帰までを総合的にサポートします。
医療チームの主な構成員
- 口腔外科医・耳鼻咽喉科医
- 放射線治療医・腫瘍内科医
- 歯科医師・歯科衛生士
- 看護師・薬剤師
- 管理栄養士・言語聴覚士
がん相談支援センターの活用
全国のがん診療連携拠点病院などには「がん相談支援センター」が設置されています。ここでは、その病院にかかっていなくても、誰でも無料で、がんに関する様々な相談ができます。
病気のこと、治療費のこと、今後の生活のことなど、不安に思うことがあれば、専門の相談員が話を聞き、情報提供や問題解決の手助けをしてくれます。
家族や周囲ができるサポート
がんと診断されると、患者さん本人はもちろん、ご家族や親しい友人も大きな衝撃を受けます。患者さんを支えるためには、どのようなサポートができるのでしょうか。
大切なのは、患者さんの気持ちに寄り添いながら、日常生活の中で具体的な手助けをしていくことです。
精神的な支えとなる関わり方
最も重要なのは、患者さんの話をじっくりと聞くことです。不安や恐怖、怒りなど、様々な感情を抱えている患者さんの気持ちを受け止め、共感する姿勢が大切です。
無理に励ましたり、安易なアドバイスをしたりするのではなく、ただそばにいて話を聞くだけでも、患者さんの心の大きな支えになります。
日常生活における具体的な手助け
治療による副作用で食事が思うように摂れなくなったり、体力が落ちて家事が困難になったりすることがあります。
そのような時には、食べやすいように調理を工夫したり、通院に付き添ったり、家事を分担したりといった具体的なサポートが助けになります。
ただし、何でもやってあげるのではなく、患者さん自身ができることは尊重し、本人の意思を確認しながら手助けすることが重要です。
家族ができるサポートの例
- 話をじっくり聞く
- 通院の付き添い
- 食事の準備や工夫
- 正確な情報の収集を手伝う
口腔がんと向き合うために大切な心構え
がんと診断された時、冷静でいられる人はいません。しかし、大きな不安の中でも、病気と向き合い、治療を乗り越えていくためには、いくつかの大切な心構えがあります。
自分一人で抱え込まず、情報を正しく理解し、主体的に治療に参加する姿勢が、より良い結果につながります。
正しい情報を得ることの重要性
インターネット上には様々な情報が溢れていますが、中には不正確なものや、いたずらに不安を煽るものも少なくありません。まずは主治医や医療チームからの説明をよく聞き、分からないことは遠慮せずに質問しましょう。
信頼できる情報源としては、国立がん研究センターのがん情報サービスや、関連学会のウェブサイトなどがあります。正しい知識は、過度な不安を和らげ、治療法を冷静に判断するための助けとなります。
自分の気持ちと向き合う
不安、恐怖、怒り、悲しみといった感情は、がんと診断されれば誰でも抱く自然なものです。これらの感情を無理に押し殺す必要はありません。信頼できる家族や友人、医療者に気持ちを話してみましょう。
話すことで気持ちが整理されたり、楽になったりすることがあります。必要であれば、臨床心理士や精神腫瘍科医などの心の専門家のサポートを受けることもできます。
よくある質問
- 口腔がんは痛いですか?
-
初期段階では痛みを伴わないことが多いのが口腔がんの特徴の一つです。そのため、発見が遅れる原因にもなります。しこりやただれなど、痛み以外の症状に気づいたら、すぐに専門医を受診することが重要です。
がんが進行すると、持続的な痛みや出血を伴うようになります。
- 舌がんの生存率はどのくらいですか?
-
がんの生存率は、発見された時点でのステージ(進行度)によって大きく異なります。舌がんの場合、ステージⅠなどの早期に発見されれば、5年相対生存率は90%以上と非常に良好です。
しかし、進行した状態で見つかると生存率は低下します。この数字はあくまで統計的なデータであり、個々の患者さんの状況によって経過は異なります。希望を持って治療に取り組むことが大切です。
- 手術後の見た目はどうなりますか?
-
手術の範囲によって異なります。小さな切除であれば、見た目の変化はほとんどありません。しかし、顎の骨を切除するなど大きな手術の場合は、顔の輪郭が変わることがあります。
現在は再建外科の技術が進歩しており、体の他の部分から皮膚や骨を移植することで、機能的・整容的な回復を目指します。治療前に、担当医から手術による変化と再建方法について十分な説明があります。
- 口腔がんは転移しますか?
-
はい、口腔がんは進行すると転移することがあります。最初に転移しやすいのは、首のリンパ節(頸部リンパ節)です。さらに進行すると、肺や肝臓、骨などの他の臓器に遠隔転移することもあります。
治療計画を立てる際には、CTやMRIなどの検査で転移の有無を詳しく調べます。
口腔がんと同様に、頭頸部(とうけいぶ)に発生するがんに「咽頭がん」があります。咽頭は鼻の奥から食道につながる部分で、上咽頭、中咽頭、下咽頭に分かれます。
特に、口を開けた時に見える喉の奥の部分(中咽頭)にできるがんは、口腔がんと原因や症状が似ていることがあります。喉の痛みや飲み込みにくさ、声の変化などが続く場合は、咽頭がんの可能性も考えられます。
口腔がんと合わせて、咽頭がんに関する正しい知識を持つことも重要です。当メディアでは咽頭がんについても詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
以上
参考文献
FERREIRA, Andressa Kelly Alves, et al. Survival and prognostic factors in patients with oral squamous cell carcinoma. Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal, 2020, 26.3: e387.
MASSANO, Joao, et al. Oral squamous cell carcinoma: review of prognostic and predictive factors. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontology, 2006, 102.1: 67-76.
CHAMOLI, Ambika, et al. Overview of oral cavity squamous cell carcinoma: Risk factors, mechanisms, and diagnostics. Oral oncology, 2021, 121: 105451.
SCIUBBA, James J. Oral cancer: the importance of early diagnosis and treatment. American journal of clinical dermatology, 2001, 2.4: 239-251.
FELLER, Liviu; LEMMER, Johan. Oral squamous cell carcinoma: epidemiology, clinical presentation and treatment. Journal of cancer therapy, 2012, 3.4: 263-268.
CARRERAS-TORRAS, Clàudia; GAY-ESCODA, Cosme. Techniques for early diagnosis of oral squamous cell carcinoma: Systematic review. Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal, 2015, 20.3: e305.
CAPOTE-MORENO, A., et al. Oral squamous cell carcinoma: epidemiological study and risk factor assessment based on a 39-year series. International journal of oral and maxillofacial surgery, 2020, 49.12: 1525-1534.
DE MORAIS, Everton Freitas, et al. Prognostic factors of oral squamous cell carcinoma in young patients: a systematic review. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2017, 75.7: 1555-1566.
LO, Wen-Liang, et al. Outcomes of oral squamous cell carcinoma in Taiwan after surgical therapy: factors affecting survival. Journal of oral and maxillofacial surgery, 2003, 61.7: 751-758.
LE CAMPION, Anna Carolina Omena Vasconcellos, et al. Low survival rates of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. International journal of dentistry, 2017, 2017.1: 5815493.