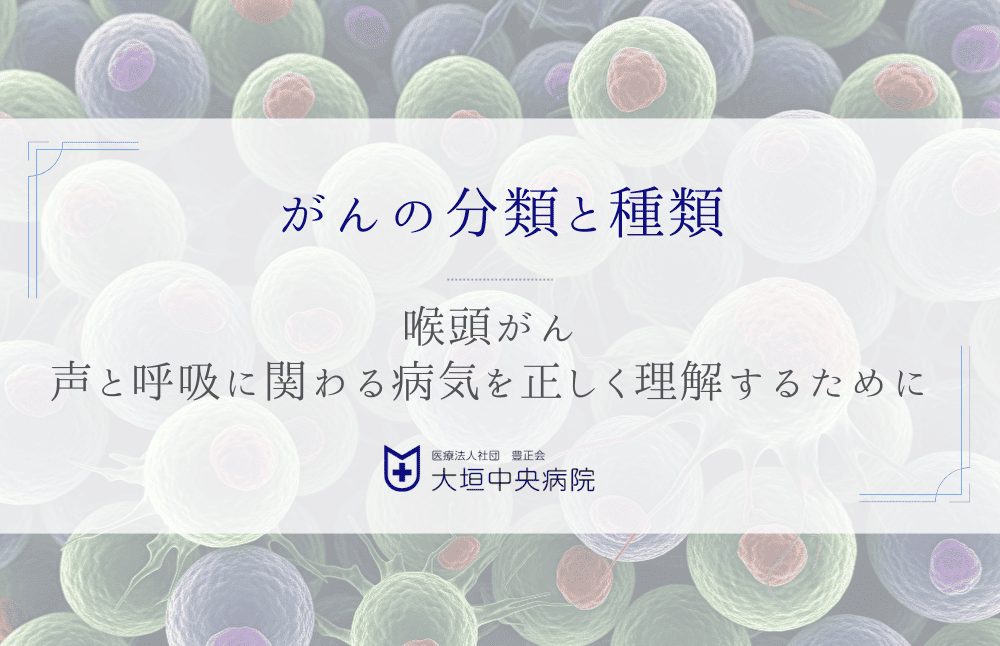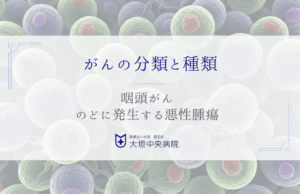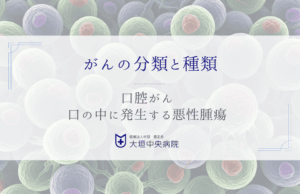喉頭がんは、声帯を含む「のど」の部分に発生するがんです。
声がれや呼吸のしづらさといった症状が現れることが多く、私たちの生活に深く関わる「話す」「呼吸する」「食べる」といった機能に影響を及ぼす可能性があります。
しかし、早期に発見し、適切な治療を受けることで、良好な経過を期待できるがんでもあります。
この記事では、喉頭がんの基本的な知識から、原因、症状、検査、治療法、そして治療後の生活に至るまでを網羅的に解説します。
喉頭がんとは何かを理解する
喉頭がんは、首の前方、一般的に「のどぼとけ」として知られる部分に位置する喉頭(こうとう)に発生する悪性腫瘍です。喉頭は呼吸の通り道であると同時に、声を出すための重要な器官でもあります。
この部分にがんができると、声や呼吸に関する様々な症状が現れます。ここでは、喉頭の基本的な構造と機能、がんの種類、そして治療方針の決定に重要な進行度(ステージ)について解説します。
喉頭の構造と機能
喉頭は、気管の入り口に位置し、主に軟骨で構成されています。その主な機能は以下の通りです。
- 発声機能:喉頭の中心部にある声帯を振動させて声を作ります。
- 呼吸機能:肺への空気の通り道としての役割を担います。
- 嚥下機能:食事の際に、食べ物が気管に入らないように防ぐ蓋(喉頭蓋)の役割を果たします。
これらの機能は日常生活に欠かせないものであり、喉頭がんの治療では、がんを治すことと同時にこれらの機能をいかに維持するかが大きな課題となります。
喉頭がんの定義と種類
喉頭がんは、がんが発生した部位によって主に3つの種類に分類します。発生部位によって初期症状や進行の仕方が異なり、治療方針にも影響を与えます。
喉頭がんの発生部位による分類
| 分類 | 発生部位 | 特徴的な初期症状 |
|---|---|---|
| 声門(せいもん)がん | 声帯 | ほぼ全てで声がれ(嗄声)が現れる。早期発見されやすい。 |
| 声門上(せいもんじょう)がん | 声帯より上部 | のどの違和感、飲み込むときの痛み。声がれは進行してから現れる。 |
| 声門下(せいもんか)がん | 声帯より下部 | 初期症状が出にくく、進行すると呼吸困難が現れる。発見が遅れやすい。 |
日本人に最も多いのは声門がんで、喉頭がん全体の60~65%を占めます。声がれという分かりやすい初期症状があるため、比較的早い段階で見つかることが多いのが特徴です。
進行度(ステージ)による分類
がんの進行度を示す指標として、国際的に「TNM分類」を用いたステージ分類を使用します。
これは、がんの大きさ(T因子)、頸部リンパ節への転移の有無(N因子)、他の臓器への遠隔転移の有無(M因子)を組み合わせて、ステージを0期からⅣ期に分類するものです。
このステージ分類は、治療方針を決定する上で極めて重要な情報となります。
ステージ分類の考え方
| ステージ | がんの状態(概要) |
|---|---|
| 0期 | ごく早期のがん。がんが粘膜の表面にとどまっている。 |
| Ⅰ期・Ⅱ期 | 早期がん。がんが喉頭内にとどまり、リンパ節転移がない。 |
| Ⅲ期・Ⅳ期 | 進行がん。がんが喉頭の広範囲に及ぶ、またはリンパ節や他の臓器に転移している。 |
発症の原因と関連するリスク因子
喉頭がんの発生には、特定の生活習慣が深く関わっていることが分かっています。特に、長年の喫煙と過度の飲酒は、発症リスクを著しく高める二大要因です。
これらのリスク因子を正しく理解し、生活習慣を見直すことが、喉頭がんの予防につながります。
最大のリスク因子 喫煙の影響
喉頭がんの最も大きな原因は喫煙です。患者の90%以上が喫煙者であるというデータもあり、タバコの煙に含まれる多くの発がん性物質が、喉頭の粘膜を長期間にわたって刺激し続けることで、がん細胞が発生しやすくなります。
喫煙年数が長く、喫煙本数が多いほどリスクは高まります。禁煙は、喉頭がんの最も効果的な予防策です。
飲酒との関連性
喫煙に次ぐリスク因子として、アルコールの摂取が挙げられます。
特に、日常的に多量の飲酒をする習慣は危険です。アルコールそのものに強い発がん性はありませんが、体内で分解される過程で生じるアセトアルデヒドという物質に発がん性があります。
さらに重要なのは、喫煙と飲酒の両方の習慣がある場合、それぞれのリスクが足し算ではなく掛け算のように作用し、発がんのリスクが飛躍的に高まることです。
喫煙と飲酒によるリスクの上昇
| 習慣 | 喉頭がん発症リスク |
|---|---|
| 非喫煙・非飲酒 | 基準 |
| 喫煙のみ | 約10倍 |
| 飲酒のみ | 約5倍 |
| 喫煙と飲酒の両方 | 数十倍に上昇 |
その他のリスク因子
喫煙や飲酒以外にも、以下のような因子がリスクを高める可能性を指摘されています。
- アスベストなどの有害物質への職業的曝露
- 逆流性食道炎による胃酸の刺激
- ヒトパピローマウイルス(HPV)への感染(中咽頭がんほど関連は強くない)
声や呼吸に現れる初期症状
喉頭がんは、発生した場所によって現れる症状が異なります。特に声門にがんができた場合は、比較的早い段階から症状が現れるため、早期発見の重要な手がかりとなります。
声やのどの些細な変化を見逃さず、気になる症状が続く場合は早めに専門医に相談することが大切です。
最も多い初期症状 声がれ(嗄声)
声がれ(させい)、専門的には嗄声(させい)と呼ばれる症状は、喉頭がん、特に声門がんの最も代表的な初期症状です。声帯にがんができることで、声帯の正常な振動が妨げられ、声がかすれたり、ガラガラ声になったりします。
風邪や声の出し過ぎによる一時的な声がれと異なり、1ヶ月以上続く場合は注意が必要です。理由のわからない声がれが長引くときは、耳鼻咽喉科を受診してください。
喉の違和感や痛み
声門上がんでは、初期症状として喉の異物感やいがらっぽさ、食べ物を飲み込むときの痛み(嚥下時痛)が現れることがあります。
これらの症状は咽頭炎などでも起こりますが、長く続く場合は検査を受けることが重要です。痛みが耳に放散する(放散痛)こともあります。
進行した場合に現れる症状
がんが進行し、腫瘍が大きくなると、より深刻な症状が現れます。これらは、がんが喉頭の機能を大きく損なっているサインです。
初期と進行期の症状比較
| 症状 | 初期 | 進行期 |
|---|---|---|
| 声がれ | 声門がんの主な症状 | ほぼ全てのがんで出現 |
| 呼吸困難 | まれ | がんが気道を塞ぐことで発生 |
| 血痰 | まれ | 腫瘍からの出血により発生 |
その他、首のリンパ節が腫れてしこりとして触れることもあります。これは、がんがリンパ節へ転移した兆候である可能性があります。
喉頭がんの検査と診断の流れ
喉頭がんが疑われる場合、診断を確定し、がんの広がりを正確に評価するために、いくつかの検査を段階的に行います。
問診から始まり、内視鏡による直接的な観察、そして確定診断のための組織検査、さらに進行度を調べるための画像検査へと進みます。これらの検査結果を総合的に判断し、最適な治療方針を決定します。
問診と視診
まず、医師が症状(いつから声がれがあるか、痛みはあるかなど)や生活習慣(喫煙歴、飲酒歴など)について詳しく聞き取ります。
その後、口を開けて喉の奥を観察したり、首を触ってリンパ節の腫れがないかなどを確認します。
喉頭内視鏡検査
細いファイバースコープを鼻または口から挿入し、喉頭を直接モニターに映し出して観察する検査です。喉頭の粘膜の状態、腫瘍の有無、大きさ、声帯の動きなどを詳細に確認できます。
外来で比較的簡単に行うことができ、喉頭がんの診断において中心的な役割を担う検査です。
生検(組織診)
喉頭内視鏡検査でがんが疑われる病変が見つかった場合、診断を確定するために行います。病変の一部を少量採取し、顕微鏡でがん細胞の有無を調べる検査です。これを病理診断と呼びます。
この検査によって初めて、がんであるかどうかの確定診断がつきます。
画像検査による進行度の評価
がんの診断が確定したら、次にがんがどの程度広がっているか(ステージ)を評価するために、CTやMRIなどの画像検査を行います。これにより、腫瘍の深さや周囲の組織への広がり、リンパ節や他の臓器への転移の有無を調べます。
主な画像検査とその目的
| 検査名 | 主な目的 |
|---|---|
| CT検査 | がんの広がり、特に軟骨への浸潤やリンパ節転移の評価。 |
| MRI検査 | CTと同様にがんの広がりを評価。特に軟部組織の描出に優れる。 |
| PET検査 | 全身のがん細胞の活動を調べる。遠隔転移の有無の評価に有用。 |
治療方法の選択肢と特徴
喉頭がんの治療は、がんの根治を目指すと同時に、喉頭が持つ発声、呼吸、嚥下といった重要な機能をいかに温存するかという点が大きな目標となります。
治療法は、がんのステージ、発生部位、患者さんの全身状態や希望などを総合的に考慮して決定します。主に、放射線治療、手術、薬物療法(抗がん剤治療)があり、これらを単独または組み合わせて行います。
喉頭温存を目指す治療
Ⅰ期・Ⅱ期の早期がんであれば、声を失わずにがんを治す「喉頭温存治療」が第一の選択肢となります。進行がんでも、状態によっては喉頭温存が可能な場合があります。
放射線治療
体の外から高エネルギーのX線をがんに照射して、がん細胞を破壊する治療法です。早期の声門がんであれば、放射線治療単独で高い治癒率が期待でき、声を温存できます。治療期間は通常6~7週間程度です。
化学放射線療法
放射線治療と抗がん剤治療を同時に行う方法です。放射線の効果を高める目的で抗がん剤を併用し、進行がんにおける喉頭温存を目指します。
放射線治療単独よりも高い効果が期待できますが、副作用も強くなる傾向があります。
レーザー手術などの喉頭部分切除術
口の中から内視鏡とレーザーを用いて、がん組織だけを精密に切除する手術です。体の負担が少なく、入院期間も短いという利点があります。主に早期のがんが対象となります。
根治を目指す手術 喉頭全摘出術
がんが大きく進行している場合や、放射線治療で治りきらなかった場合などに行う手術です。喉頭を全て摘出するため、がんは完全に取り除けますが、声を失い、首に永久気管孔(呼吸をするための穴)を造設する必要があります。
根治性は高いですが、生活への影響が最も大きい治療法です。
ステージ別の標準的な治療方針
治療法は個々の状況に応じて決まりますが、一般的な考え方としてステージごとの治療方針があります。
ステージ別治療法の選択肢
| ステージ | 主な治療法の選択肢 | 主な目的 |
|---|---|---|
| Ⅰ期・Ⅱ期(早期がん) | 放射線治療 または 喉頭部分切除術 | 機能温存と根治 |
| Ⅲ期・Ⅳ期(進行がん) | 化学放射線療法 または 喉頭全摘出術 | 根治(可能であれば機能温存) |
治療後に考えられる生活への影響
喉頭がんの治療は、生活の質(QOL)に大きな影響を与える可能性があります。特に、声、呼吸、食事といった基本的な機能に変化が生じることがあります。
治療を受ける前に、どのような変化が起こりうるのか、そしてそれに対してどのような対処法があるのかを理解しておくことは、治療後の生活へスムーズに適応するために非常に重要です。
声の変化と代用音声
喉頭全摘出術を受けた場合、声帯を失うため、手術前と同じように声を出すことはできなくなります。しかし、声をとりもどすための方法として「代用音声」があり、リハビリテーションによって習得します。
主な代用音声の方法
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 食道発声 | 空気を食道に取り込み、げっぷのように出すことで食道粘膜を振動させて発声する。習得に訓練が必要。 |
| 電気喉頭(EL) | 首に当てた器具を振動させ、その音を口の中で共鳴させて言葉にする。比較的容易に習得できる。 |
| シャント発声 | 気管と食道の間に小さな穴(シャント)を作り、器具を埋め込む。肺の空気を食道に送り込んで発声する。 |
どの方法が適しているかは、個人の状態や希望によって異なります。専門家と相談しながら、自分に合った方法を選択します。
呼吸の変化と永久気管孔の管理
喉頭全摘出術後は、首の付け根に作られた「永久気管孔(えいきゅうきかんこう)」という穴から直接呼吸することになります。
鼻や口を通らないため、吸い込む空気の加湿・加温ができなくなり、痰が増えたり、感染しやすくなったりします。そのため、気管孔の清潔を保ち、乾燥を防ぐための毎日のケアが必要になります。
嚥下(飲み込み)機能への影響
手術や放射線治療の影響で、食べ物や飲み物が飲み込みにくくなる「嚥下障害」が起こることがあります。
むせやすくなったり、食事がうまく摂れなくなったりすることもありますが、多くの場合、リハビリテーションや食事の工夫によって改善します。
再発や転移に関する知識
喉頭がんの治療後も、残念ながらがんが再び現れる「再発」や、別の臓器にがんが見つかる「転移」の可能性があります。そのため、治療が終わった後も定期的な検査を受け、体の状態を注意深く観察していくことが大切です。
再発や転移について正しく理解し、万が一の場合に備えることも治療の一環です。
再発の形式と時期
再発には、最初にがんができた場所(喉頭)に再びがんができる「局所再発」と、首のリンパ節にがんが現れる「頸部リンパ節再発」があります。
多くの再発は、治療後2年以内に起こることが多いため、この期間は特に慎重な経過観察が必要です。
転移しやすい部位
喉頭がんが最初に転移しやすい場所は、首のリンパ節です。リンパの流れに乗ってがん細胞が運ばれ、リンパ節で増殖します。さらに進行すると、血液の流れに乗って肺や肝臓、骨などの離れた臓器に転移(遠隔転移)することもあります。
再発・転移した場合の治療
再発や転移が見つかった場合の治療法は、再発した場所、これまでの治療内容、患者さんの全身状態などを考慮して慎重に決定します。手術、放射線治療、薬物療法などを組み合わせた集学的な治療が必要となることが多いです。
治療後の経過観察と生存率
治療効果の指標の一つとして「5年相対生存率」があります。これは、がんと診断された人のうち、5年後に生存している人の割合が、日本人全体の5年後の生存率と比較してどのくらいかを示す数値です。
喉頭がん全体の5年相対生存率は約80%と比較的良好ですが、ステージによって異なります。
喉頭がんのステージ別5年相対生存率(目安)
| ステージ | 5年相対生存率 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 95%以上 |
| Ⅱ期 | 約85% |
| Ⅲ期 | 約65% |
| Ⅳ期 | 約45% |
早期に発見し治療を開始することが、良好な結果につながることがわかります。
喉頭がんと向き合うためのサポート体制
がんと診断されると、身体的な苦痛だけでなく、精神的、社会的、経済的に様々な困難に直面することがあります。しかし、あなたは一人ではありません。
医療機関や地域社会には、患者さんとそのご家族を支えるための様々なサポート体制が用意されています。これらの支援を積極的に活用し、悩みや不安を抱え込まずに相談することが、治療を乗り越える上で大きな力となります。
医療チームによる支援
治療を行う医師や看護師だけでなく、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、言語聴覚士、医療ソーシャルワーカーなど、多くの専門家がチームとなってあなたを支えます。
治療の副作用対策、栄養管理、リハビリテーション、医療費の相談など、それぞれの専門分野からきめ細やかなサポートを提供します。
患者会や自助グループの役割
同じ病気を経験した仲間と語り合う場は、大きな心の支えになります。喉頭がんの患者さんで構成される患者会(例:銀鈴会など)では、代用音声の訓練法の情報交換や、日常生活の工夫、精神的な悩みの共有などを行っています。
同じ体験をしたからこそ分かり合える仲間との交流は、孤独感を和らげ、前向きな気持ちを取り戻すきっかけになるでしょう。
公的な支援制度の活用
喉頭がんの治療や後遺症により、経済的な負担が生じたり、生活に支障が出たりする場合があります。そのような場合に利用できる公的な支援制度があります。
- 身体障害者手帳:喉頭全摘出術を受けた場合、音声機能障害として認定され、様々な福祉サービスを受けられます。
- 障害年金:病気やけがによって生活や仕事などが制限される場合に受け取れる年金です。
- 高額療養費制度:医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。
これらの制度の詳細は、病院の相談窓口や医療ソーシャルワーカー、お住まいの市区町村の窓口で確認できます。
予防と日常生活での注意点
喉頭がんは、その発生に生活習慣が深く関わっているため、リスク因子を避けることで発症の可能性を下げることができるがんの一つです。また、万が一発症した場合でも、早期に発見できれば体への負担が少ない治療で治癒を目指せます。
日々の生活を見直し、体のサインに気を配ることが、喉頭がんから身を守るための最も確実な方法です。
禁煙の重要性
喉頭がんの予防において、禁煙は最も重要かつ効果的な手段です。今喫煙している方でも、禁煙すればその時点から発症リスクは低下し始め、禁煙期間が長くなるほどリスクは非喫煙者に近づいていきます。
自力での禁煙が難しい場合は、禁煙外来など専門家のサポートを受けることを検討してください。
節度ある飲酒
飲酒は適量を守ることが大切です。特に喫煙習慣のある方は、飲酒量を控えることで相乗的なリスク上昇を避けることができます。休肝日を設けるなど、アルコールと上手に付き合う習慣を身につけましょう。
バランスの取れた食事と生活習慣
緑黄色野菜や果物を多く含む、バランスの取れた食事は、様々な種類のがんのリスクを下げると考えられています。また、適度な運動や十分な睡眠を心がけ、体の免疫力を高く保つことも重要です。
早期発見のための自己チェック
日頃から自分の体の変化に注意を払うことが早期発見につながります。特に以下のような症状には注意してください。
- 1ヶ月以上続く声がれ
- のどの違和感や痛みの持続
- 飲み込みにくさ
- 首のしこり
これらの症状に気づいたら、自己判断で様子を見ずに、早めに耳鼻咽喉科を受診してください。
よくある質問
喉頭がんについて、患者さんやご家族からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 喉頭がんは遺伝しますか?
-
現在のところ、喉頭がんが直接的に遺伝するという明確な証拠はありません。
しかし、喫煙や飲酒といった生活習慣は家族内で似る傾向があるため、血縁者に喉頭がんになった方がいる場合は、ご自身の生活習慣を一度見直してみることをお勧めします。
- 治療中の痛みはどの程度ですか?
-
痛みの感じ方には個人差があります。放射線治療では、喉の粘膜が炎症を起こし、痛みを感じることがあります。手術後は、傷口の痛みがありますが、いずれも鎮痛剤を使って痛みをコントロールします。
痛みは我慢せず、医療スタッフに伝えることが大切です。
- 手術後の食事はどうなりますか?
-
喉頭全摘出術の場合、手術直後は鼻から胃に入れたチューブで栄養を摂りますが、傷が治れば口から食事を摂れるようになります。
気管と食道は完全に分離されるため、誤嚥(食べ物が気管に入ること)の心配はなくなります。ただし、飲み込む力が一時的に弱まることがあるため、リハビリテーションを行うこともあります。
- 声を失った後の仕事復帰は可能ですか?
-
もちろん可能です。多くの患者さんが、代用音声を習得したり、筆談や携帯端末などを活用したりして、仕事に復帰しています。
職場の理解と協力も重要ですので、どのような配慮が必要かなどを事前に話し合っておくとよいでしょう。障害者雇用支援制度などを活用することもできます。
喉頭がんの大きなリスク因子である喫煙と飲酒は、「口腔がん」の発症にも深く関わっています。口腔がんは、舌や歯ぐき、頬の内側など、口の中にできるがんです。喉頭がんと同様に、早期発見が治療の鍵となります。
口の中に治りにくい口内炎やしこり、ただれなどがある場合は、喉の症状と合わせて注意が必要です。喉頭がんについて理解を深めるとともに、お口の中の健康にも関心を持つことが、頭頸部領域のがんから身を守るために重要です。
口腔がんに関する詳しい情報も、ぜひ一度ご覧ください。
参考文献
MURARIU, Maria Octavia, et al. Long-Term Quality of Life and Functional Outcomes in Patients with Total Laryngectomy. Cancers, 2025, 17.6: 1011.
BAIRD, Brandon Jackson, et al. Treatment of early-stage laryngeal cancer: a comparison of treatment options. Oral oncology, 2018, 87: 8-16.
FORASTIERE, Arlene A., et al. Use of larynx-preservation strategies in the treatment of laryngeal cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. Journal of Clinical Oncology, 2018, 36.11: 1143-1169.
JUNG, Eun Kyung, et al. Comparison of long-term treatment outcomes of T2N0M0 laryngeal squamous cell carcinoma using different treatment methods. Oncology letters, 2020, 20.1: 921-930.
KNOPF, Andreas, et al. Treatment regimens for laryngeal and hypopharyngeal squamous cell carcinoma: a “real life” multicenter study of 2307 patients. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2024, 1-13.
ELICIN, Olgun; GIGER, Roland. Comparison of current surgical and non-surgical treatment strategies for early and locally advanced stage glottic laryngeal cancer and their outcome. Cancers, 2020, 12.3: 732.
OBID, Randa; REDLICH, Magi; TOMEH, Chafeek. The treatment of laryngeal cancer. Oral and Maxillofacial Surgery Clinics, 2019, 31.1: 1-11.
MURARIU, Maria Octavia, et al. Psychological Distress and Quality of Life in Patients with Laryngeal Cancer: A Review. In: Healthcare. MDPI, 2025. p. 1552.
NAKAJIMA, Aya, et al. Preserving Laryngo‐Esophageal Function in Patients With Hypopharyngeal Cancer Treated With Radiotherapy: Predictive Factors and Long‐Term Outcomes. Cancer Medicine, 2024, 13.21: e70374.
LI, Wan-Xin, et al. Efficacy of larynx preservation surgery and multimodal adjuvant therapy for Hypopharyngeal Cancer: a case series study. Ear, Nose & Throat Journal, 2023, 102.7: NP319-NP326.