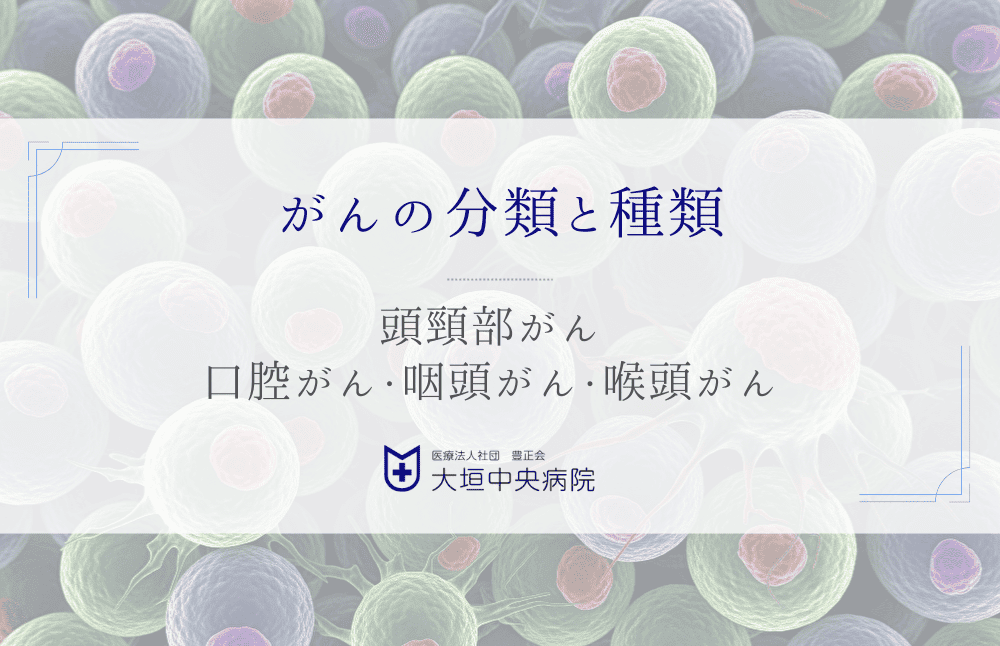頭頸部がんは、脳、目、食道を除く、首から上の領域に発生するがんの総称です。具体的には、鼻や口、のど(咽頭・喉頭)、唾液腺などに発生します。
この領域は、呼吸、食事、発声といった、私たちが生きていく上で非常に重要な機能を担っています。そのため、がんの治療においては、がんを治すことと同時に、これらの機能をいかに維持するかが大きな課題となります。
頭頸部がんは発生する場所によって、口腔がん、咽頭がん、喉頭がんなど、さまざまな種類に分類され、それぞれ症状や治療法が異なります。
この記事では、代表的な頭頸部がんについて、その特徴や診断、治療の選択肢を詳しく解説し、病気と向き合う上での理解を深める手助けをします。
口腔がん
口腔がんは、口の中に発生するがんの総称です。舌、歯ぐき(歯肉)、頬の内側の粘膜、口の底(口腔底)、上あご(硬口蓋)など、さまざまな場所に発生する可能性があります。
口の中は自分で観察しやすいため、比較的早期に発見できる可能性があるがんの一つです。しかし、初期段階では口内炎と見分けがつきにくく、発見が遅れることも少なくありません。
普段から口の中の状態に関心を持ち、異変を感じた際には早めに専門医に相談することが重要です。
口腔がんとは何か
口腔がんは、口の中の粘膜から発生する悪性腫瘍です。その多くは扁平上皮がんという種類に分類されます。
喫煙や過度の飲酒が主な危険因子として知られており、これらが口の中の粘膜を長期間刺激することで、がんが発生しやすくなると考えられています。
また、合わない入れ歯や被せ物、虫歯で欠けた歯などが常に粘膜に当たる物理的な刺激も、原因の一つとなることがあります。
口腔がんが発生する部位
がんが発生する部位によって、舌がん、歯肉がん、口腔底がん、頬粘膜がん、硬口蓋がんと呼び分けます。この中で最も発生頻度が高いのは舌がんで、口腔がん全体の半数以上を占めます。
次いで歯肉がんが多く見られます。それぞれの部位で症状の現れ方や進行の仕方が異なるため、正確な診断が求められます。
主な種類
口腔がんの90%以上は、粘膜の表面を覆う扁平上皮という細胞から発生する扁平上皮がんです。初期の段階では、粘膜が白くなったり(白板症)、赤くなったり(紅板症)する変化が見られることがあります。
これらは前がん病変と呼ばれ、がんになる前の状態と考えられています。まれに、唾液を作る組織から発生する腺がんや、悪性黒色腫、肉腫などが口の中に発生することもあります。
主な症状
口腔がんの症状は、発生した場所やがんの進行度によってさまざまです。初期の段階では痛みを伴わないことも多く、口内炎と間違えやすいのが特徴です。
なかなか治らない口内炎や、口の中のできもの、しこり、ただれ、出血などがある場合は注意が必要です。がんが進行すると、痛みや食事がしみる、話しにくい、口が開きにくいといった症状が現れます。
また、首のリンパ節に転移すると、首にしこりを触れることもあります。
口腔がんの部位別初期症状の例
| 発生部位 | 主な初期症状 | 注意点 |
|---|---|---|
| 舌 | 舌の縁や裏側のしこり、ただれ | 痛みを伴わないことが多い |
| 歯肉(歯ぐき) | 歯ぐきの腫れ、出血、入れ歯の不具合 | 歯周病と間違えやすい |
| 口腔底(舌の下) | 舌の下のしこり、ただれ | 食事がしみることがある |
診断と検査
口腔がんが疑われる場合、まずは専門医による診察が行われ、確定診断のために詳しい検査を進めます。
診断では、がんの有無だけでなく、がんの広がりや深さ、転移の有無を正確に把握することが、適切な治療方針を立てる上で大切です。
視診と触診
医師が直接口の中を見て、病変の大きさ、形、色などを観察します。同時に、指で直接触れて、しこりの有無や硬さ、広がりを確認します。首のリンパ節が腫れていないかも触診で調べます。
視診と触診は、診断の第一歩となる基本的ながらも重要な診察です。
生検(組織検査)
確定診断のために行う検査です。病変の一部を少量採取し、顕微鏡で詳しく調べて、がん細胞の有無を確認します。局所麻酔を用いるため、検査中の痛みはほとんどありません。
この検査によって、がんの種類(組織型)も判明し、治療方針の決定に役立てます。
画像検査
がんの深さや周囲の組織への広がり、リンパ節や他の臓器への転移を調べるために、CT検査、MRI検査、PET検査などの画像検査を行います。
これらの検査から得られる情報をもとに、がんの進行度(ステージ)を決定し、一人ひとりの状態に合わせた治療計画を立てます。
治療法
口腔がんの治療は、手術、放射線治療、薬物療法が三つの柱です。がんの進行度や発生した場所、患者さんの全身の状態などを総合的に考慮して、これらの治療法を単独で、あるいは組み合わせて行います。
治療の目標は、がんを根治させることと、食事や会話といった口の機能をできるだけ温存することです。
手術療法
がんを完全に取り除くための中心的な治療法です。がんの大きさや広がりに応じて、がん組織とその周囲の正常な組織を一緒に切除します。がんが顎の骨にまで及んでいる場合は、顎の骨の一部を切除することもあります。
また、首のリンパ節への転移がある場合や、その可能性が高い場合には、首のリンパ節も同時に切除します(頸部郭清術)。
切除した範囲が広い場合は、体の他の部分から皮膚や筋肉、骨などを移植して、失われた組織を再建する手術も行います。
放射線治療
高エネルギーのX線などをがんに照射して、がん細胞を破壊する治療法です。体の外から放射線を照射する方法(外部照射)が一般的です。
手術が難しい場合や、手術後の再発予防、機能温存を目的として行います。薬物療法と組み合わせて治療効果を高めることもあります。
薬物療法
抗がん剤などの薬剤を用いて、がん細胞の増殖を抑えたり、破壊したりする治療法です。進行して手術が難しい場合や、再発・転移した場合に行うことが多い治療法です。
近年では、特定の分子を標的とする分子標的薬や、自身の免疫力を利用してがんと闘う免疫チェックポイント阻害薬なども使用され、治療の選択肢が広がっています。
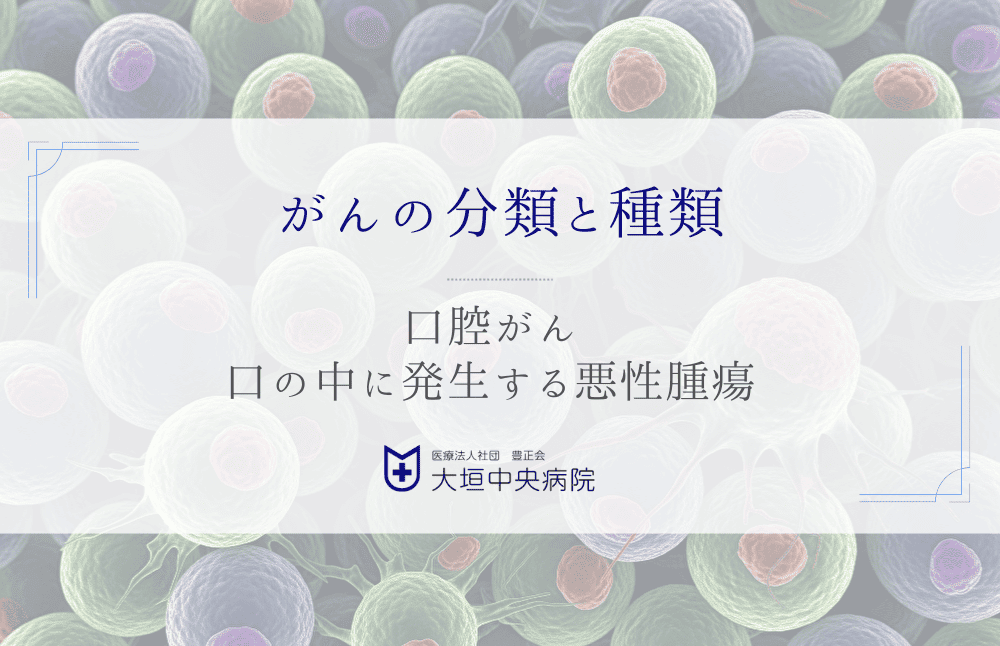
咽頭がん
咽頭は、鼻の奥から食道の入り口まで続く管状の器官で、上から順に上咽頭、中咽頭、下咽頭の3つの部分に分かれています。咽頭がんは、これらの部位の粘膜に発生するがんです。
発生する場所によって症状や性質が大きく異なり、治療法も変わってきます。特に中咽頭がんと下咽頭がんは、喫煙と過度の飲酒が大きく関与していることが分かっています。
一方で、上咽頭がんはウイルス感染が関連しているなど、それぞれに特徴があります。
咽頭がんの分類
咽頭は部位によって機能や構造が異なるため、がんの性質も異なります。そのため、治療方針を立てる上で、どの部位にがんが発生したかを特定することが非常に重要です。
上咽頭がん
鼻の最も奥、頭蓋骨の底の部分に位置するのが上咽頭です。この部位にできるがんは、EBウイルスというウイルスの感染が関連していることが知られています。初期症状が出にくく、発見されたときには進行していることも少なくありません。
耳の症状(耳閉感、難聴)や鼻の症状(鼻づまり、鼻血)、首のリンパ節の腫れがきっかけで見つかることが多いのが特徴です。
中咽頭がん
口を開けたときに正面に見える、口蓋扁桃(いわゆる扁桃腺)や舌の付け根(舌根)などが含まれる部位です。
以前は喫煙や飲酒が主な原因でしたが、近年、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染に関連する中咽頭がんが世界的に増加しています。
HPV関連のがんは、比較的若い世代にも見られ、放射線治療や薬物療法が効きやすいという特徴があります。
下咽頭がん
咽頭の最も下、食道の入り口付近にできるがんです。初期には症状がほとんどなく、のどの違和感や飲み込みにくさ、声のかすれなどが現れたときには、がんが進行している場合が多いです。
食道に近いため、食道がんを合併することもあります。
考えられる原因
咽頭がんの発生には、生活習慣やウイルス感染が深く関わっています。原因を知ることは、予防や早期発見につながります。
咽頭がんの主な危険因子
- 喫煙
- 過度の飲酒
- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染
特に、長期間の喫煙と飲酒は、中咽頭がんと下咽頭がんの最も重要な危険因子です。タバコに含まれる発がん物質やアルコールが分解されてできるアセトアルデヒドが、のどの粘膜を傷つけ、がんの発生を促します。
また、HPVは主に性交渉によって感染するウイルスで、これが中咽頭の粘膜に持続的に感染することで、がんを引き起こすことがあります。
症状の現れ方
咽頭がんの症状は、がんが発生した部位によって大きく異なります。初期段階では無症状のことも多く、注意が必要です。何らかの症状が長く続く場合は、専門医の診察を受けることが大切です。
咽頭がんの部位による症状の違い
| 発生部位 | 代表的な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 上咽頭 | 鼻づまり、鼻血、耳の聞こえにくさ | 首のしこりが初発症状のことも多い |
| 中咽頭 | のどの痛み、飲み込むときの違和感 | 食べ物がしみることがある |
| 下咽頭 | 声がれ、のどの異物感、嚥下困難 | 症状が出たときには進行していることが多い |
検査と診断の流れ
のどの症状で医療機関を受診すると、まず問診と視診が行われます。がんが疑われる場合には、より詳しい検査に進み、診断を確定させます。
内視鏡検査
鼻や口から細いカメラ(内視鏡)を挿入し、咽頭の粘膜を直接観察します。病変の有無、大きさ、広がりなどを詳細に確認できます。検査中に、疑わしい部分の組織を採取して生検を行うことも可能です。
画像診断(CT、MRIなど)
がんの深さや周囲の臓器への広がり、リンパ節への転移などを評価するために、CTやMRIなどの画像検査を行います。治療方針を決定する上で重要な情報となります。
病理診断
内視鏡検査の際に採取した組織を顕微鏡で調べ、がん細胞の有無や種類を確定させる検査です。最終的な診断はこの病理診断によって下されます。
治療の選択
咽頭がんの治療は、がんの部位や進行度、患者さんの状態を考慮して決定します。機能を温存することが重視されるため、放射線治療や薬物療法が中心となることが多いですが、手術が必要な場合もあります。
放射線治療と薬物療法の組み合わせ
多くの咽頭がん、特に上咽頭がんと中咽頭がんでは、放射線治療が治療の主体となります。多くの場合、治療効果を高めるために抗がん剤を併用する化学放射線療法が行われます。
この治療法は、手術をせずにがんを治すことを目指すもので、のどの機能を温存できる可能性が高いという利点があります。
手術
がんが放射線治療で制御できない場合や、再発した場合などに手術が選択されます。下咽頭がんでは、進行度によって最初から手術が選択されることもあります。
手術では、がんの部位や広がりによって、咽頭の一部または全部を切除します。切除範囲が広い場合は、体の他の部分の組織を使って再建手術を行います。
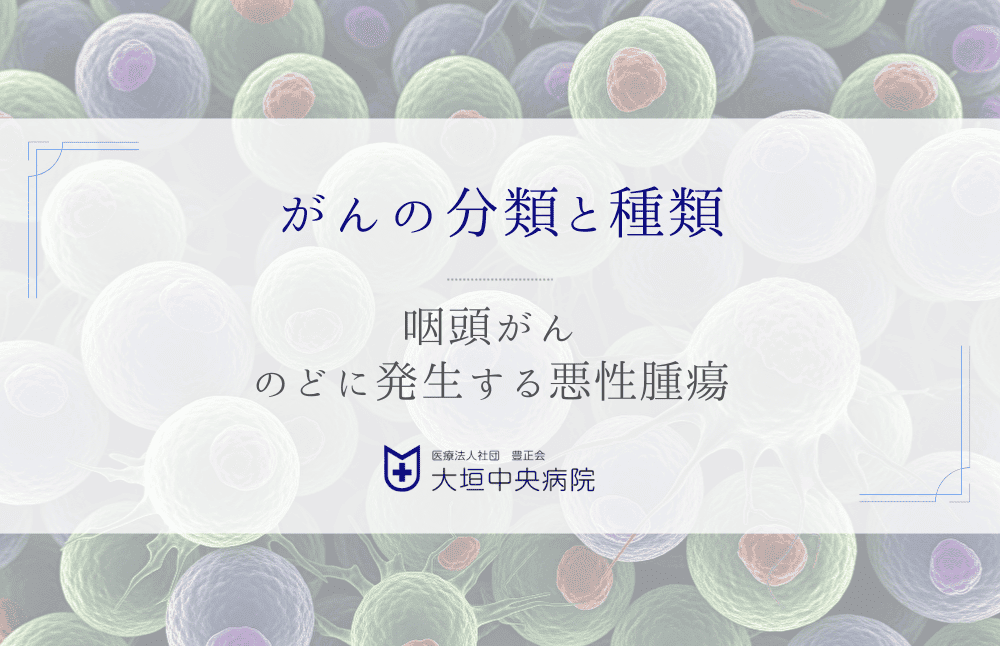
喉頭がん
喉頭は、一般的に「のどぼとけ」として知られる部分にあり、気管の入り口に位置しています。喉頭には、声を出すための声帯があり、発声という重要な役割を担っています。
また、呼吸の際の空気の通り道であると同時に、食べ物が気管に入らないように防ぐ蓋(喉頭蓋)としての働きも持っています。喉頭がんは、この喉頭の粘膜から発生するがんで、頭頸部がんの中では比較的発生頻度が高いがんです。
主な原因は喫煙であり、患者さんの9割以上が喫煙者であると報告されています。
喉頭の役割とがんの発生部位
喉頭は、声帯がある声門、その上の声門上、その下の声門下の3つの領域に分けられます。がんがどの領域から発生したかによって、症状の現れ方や治療法が大きく異なります。
声門がん
声帯そのものから発生するがんで、喉頭がんの中で最も多く見られます。非常に早い段階から声のかすれ(嗄声)という症状が現れるため、早期発見されやすいのが大きな特徴です。
早期に発見できれば、放射線治療やレーザー手術などで、声を失うことなく治療できる可能性が高いです。
声門上がん
声帯よりも上部に発生するがんです。初期には症状が出にくく、のどの違和感や異物感、飲み込むときの痛みといった症状で気づかれることが多いです。声がれが現れる頃には、がんが進行している可能性があります。
また、首のリンパ節に転移しやすく、首のしこりが初発症状となることもあります。
声門下がん
声帯よりも下、気管に近い部分に発生するがんで、喉頭がんの中では最もまれです。この部位も初期症状が出にくく、がんが大きくなって呼吸が苦しくなるなどの症状が出てから発見されることが少なくありません。
初期に気づきやすい症状
喉頭がんの最も代表的な初期症状は、声の変化です。特に、声門にがんができた場合は、ごく初期から声がかすれます。
風邪や声の出しすぎによる一時的な声がれとは異なり、原因が思い当たらないのに声がれが2週間以上続く場合は、注意が必要です。
その他、がんが進行すると、のどの痛み、血の混じった痰、息苦しさ、飲み込みにくさなどの症状が現れます。
診断方法
声がれなどの症状で耳鼻咽喉科を受診すると、喉頭がんを念頭に置いた診察と検査が行われます。咽頭がんと同様に、内視鏡検査で喉頭を直接観察し、疑わしい部分があれば組織を採取して病理診断で確定します。
がんの広がりを調べるために、CTやMRIなどの画像検査も行い、進行度を正確に評価します。
喉頭がんの進行度(T分類)の概要
| 分類 | 声帯の状態 | 特徴 |
|---|---|---|
| T1 | がんが声帯に限局 | 声帯の動きは正常 |
| T2 | がんが声門上部または下部に進展 | 声帯の動きが悪いことがある |
| T3 | がんが喉頭内に留まるが声帯の動きが停止 | 声の機能が大きく損なわれる |
治療方針の決定
喉頭がんの治療では、がんを治すことと、喉頭の重要な機能である発声、呼吸、嚥下(飲み込み)をいかに温存するかという二つの側面を考慮して、治療方針を決定します。
進行度やがんの発生部位によって、治療の選択肢は大きく異なります。
早期がんの治療
早期の声門がんであれば、機能温存を最優先に考えます。治療法としては、体の外から放射線を照射する放射線治療や、口から内視鏡を入れてレーザーでがんを切除する経口的切除術が選択されます。
どちらの治療法も、高い確率でがんを治すことができ、声を温存できる可能性が高いです。どちらを選択するかは、がんの状態や患者さんの希望を考慮して決定します。
進行がんの治療
がんが進行している場合は、複数の治療法を組み合わせた集学的治療が必要となります。
以前は喉頭をすべて摘出する喉頭全摘術が標準的な治療でしたが、近年では、できるだけ喉頭を温存するために、抗がん剤と放射線治療を組み合わせる化学放射線療法が第一に検討されます。
この治療でがんが制御できない場合や、再発した場合などに喉頭全摘術が検討されます。喉頭を全摘出すると、自分の声で話すことができなくなりますが、食道発声や電気喉頭といった代用音声で、再び会話をすることが可能です。
声の機能を温存するための治療
喉頭がんの治療において、声の温存は非常に重要な課題です。早期がんに対する放射線治療やレーザー手術はもちろん、進行がんであっても、化学放射線療法によって喉頭を温存できる可能性が追求されます。
また、手術が必要な場合でも、がんの広がりによっては喉頭の一部だけを切除する喉頭部分切除術が可能なこともあり、発声機能を残せる場合があります。
治療を選択する際には、担当医と十分に話し合い、それぞれの治療法の利点と欠点を理解することが大切です。
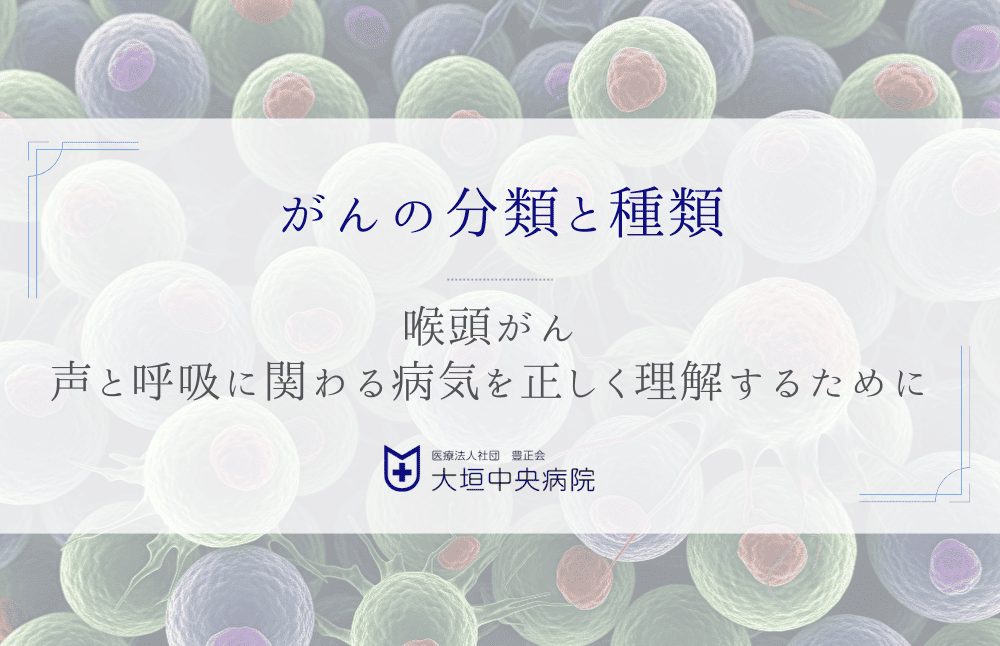
よくある質問
- 頭頸部がんの予防はできますか?
-
すべての頭頸部がんを完全に予防する方法はありませんが、危険因子を避けることで発生のリスクを減らすことは可能です。最も重要な予防策は禁煙です。
喫煙は口腔がん、咽頭がん、喉頭がんの最大の危険因子であり、禁煙することでリスクを大幅に下げることができます。また、過度の飲酒を控えることも重要です。
喫煙と飲酒の両方の習慣がある人は、リスクがさらに高まるため特に注意が必要です。バランスの取れた食事や、口の中を清潔に保つことも予防につながります。
中咽頭がんの原因となるHPV感染については、ワクチン接種が予防に有効です。
- 治療後の生活で気をつけることは何ですか?
-
治療後の生活では、治療によって生じた後遺症とうまく付き合っていくことが大切になります。例えば、手術や放射線治療の影響で、飲み込みにくさ(嚥下障害)や口の渇き(口腔乾燥)、味覚の変化などが起こることがあります。
嚥下障害に対しては、食事の形態を工夫したり、リハビリテーションを行ったりします。口腔乾燥に対しては、こまめな水分補給や保湿剤の使用が有効です。
また、治療後は定期的な通院と検査が重要です。再発や転移、あるいは別の場所に新しくがんが発生(二次がん)する可能性がないかを継続的に確認していく必要があります。
生活習慣の改善、特に禁煙と節酒は、再発や二次がんの予防においても非常に重要です。
- 家族としてどのようにサポートすればよいですか?
-
ご家族のサポートは、患者さんが安心して治療を受け、治療後の生活を送る上で大きな力となります。まずは、患者さんの病気や治療について正しく理解し、不安や悩みに耳を傾けることが大切です。
治療中は、副作用による体調の変化や、食事、会話の困難さなど、さまざまな困難に直面します。食事の準備を手伝ったり、コミュニケーションの方法を一緒に考えたりするなど、具体的なサポートが助けになります。
また、治療後は外見の変化や機能障害によって、患者さんが精神的な落ち込みを経験することもあります。
そのようなときは、焦らずに寄り添い、必要であれば専門のカウンセラーやソーシャルワーカーに相談することも検討しましょう。ご家族自身も無理をせず、支援を受けながら患者さんを支えていくことが重要です。
頭頸部のがんと同様に、脳や神経系に発生する腫瘍も、私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります。
「脳・神経系腫瘍」の記事では、良性・悪性の違いや、代表的な腫瘍である神経膠腫(グリオーマ)や髄膜腫、聴神経腫瘍などについて、その症状や診断、最新の治療法までを網羅的に解説しています。
手術や放射線治療、薬物療法といった治療の選択肢や、それぞれの特徴についても詳しく説明しており、病気への理解を深める一助となるでしょう。
頭頸部のがんについて関心をお持ちの方は、関連する領域である脳や神経の病気についても、ぜひ一度ご覧ください。
参考文献
MARUR, Shanthi; FORASTIERE, Arlene A. Head and neck squamous cell carcinoma: update on epidemiology, diagnosis, and treatment. In: Mayo Clinic Proceedings. Elsevier, 2016. p. 386-396.
YAO, Mike, et al. Current surgical treatment of squamous cell carcinoma of the head and neck. Oral oncology, 2007, 43.3: 213-223.
ANDERSON, Garrett, et al. An updated review on head and neck cancer treatment with radiation therapy. Cancers, 2021, 13.19: 4912.
LICITRA, L., et al. Squamous cell carcinoma of the head and neck: ESMO clinical recommendations for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 2009, 20: iv121-iv122.
CORVÒ, Renzo. Evidence-based radiation oncology in head and neck squamous cell carcinoma. Radiotherapy and Oncology, 2007, 85.1: 156-170.
GRÉGOIRE, Vincent, et al. Squamous cell carcinoma of the head and neck: EHNS–ESMO–ESTRO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of oncology, 2010, 21: v184-v186.
JOHNSON, Daniel E., et al. Head and neck squamous cell carcinoma. Nature reviews Disease primers, 2020, 6.1: 92.
JESSE, Richard H.; FLETCHER, Gilbert H. Treatment of the neck in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck. Cancer, 1977, 39.S2: 868-872.
YAO, Min, et al. Intensity-modulated radiation treatment for head-and-neck squamous cell carcinoma—the University of Iowa experience. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 2005, 63.2: 410-421.
MAGHAMI, Ellie, et al. Diagnosis and management of squamous cell carcinoma of unknown primary in the head and neck: ASCO guideline. Journal of Clinical Oncology, 2020, 38.22: 2570-2596.