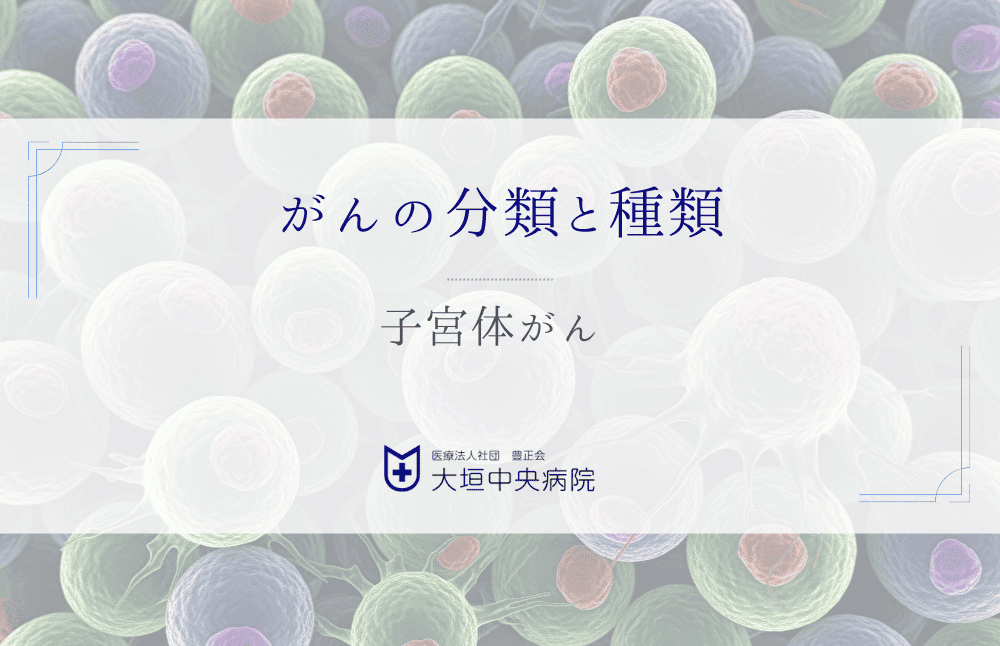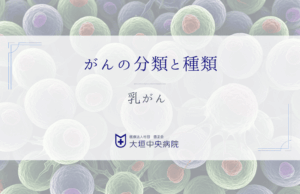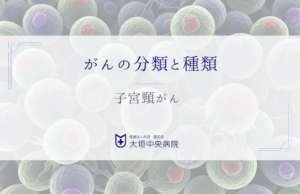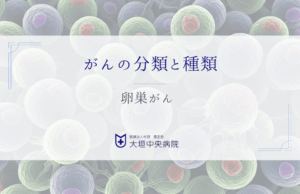子宮体がんは、子宮の奥に位置する「体部」の内側を覆う子宮内膜から発生するがんです。特に閉経後の女性に多く見られ、その最も一般的な初期症状は不正出血です。
この記事では、子宮体がんの基本的な知識から、症状、原因、リスク要因、検査方法、そして治療法に至るまでを詳しく解説します。
ご自身の体の変化に気づき、適切な行動をとるための一助として、また、がんと向き合う上での正しい情報を得るために、ぜひお役立てください。
子宮体がんとは – 発生部位と基本的特徴
子宮体がんは、女性特有のがんの一つであり、その発生数には増加傾向が見られます。このがんを正しく理解するためには、まず、どこに発生し、どのような特徴を持つのかを知ることが第一歩です。
子宮頸がんとしばしば混同されますが、発生部位も原因も全く異なる病気です。ここでは、子宮体がんの基本的な事柄について解説します。
子宮体がんの発生部位
子宮は、西洋梨を逆さにしたような形をした臓器です。大きく分けて、下部の「頸部」と上部の「体部」の二つの部分から成り立っています。
子宮体がんは、このうち胎児が育つ場所である「体部」に発生します。
子宮内膜という場所
より詳しく言うと、子宮体がんのほとんどは、子宮体部の内側を覆っている「子宮内膜」という組織から発生します。
子宮内膜は、女性ホルモンの影響を受けて周期的に厚くなったり剥がれ落ちたりを繰り返す組織で、この剥がれ落ちる現象が月経です。
この子宮内膜の細胞が、何らかの原因で異常な増殖を始め、がん化することで子宮体がんとなります。
子宮頸がんとの違い
子宮にできるがんとしてよく知られる子宮頸がんと子宮体がんは、同じ子宮に発生するものの、多くの点で異なります。
これらの違いを理解することは、適切な検診や予防行動につながるため非常に重要です。
発生場所と原因の比較
| 項目 | 子宮体がん | 子宮頸がん |
|---|---|---|
| 発生部位 | 子宮の奥(体部)の子宮内膜 | 子宮の入り口(頸部) |
| 主な原因 | 女性ホルモン(エストロゲン)のバランス | ヒトパピローマウイルス(HPV)の持続感染 |
| 好発年齢 | 50~60代(閉経後)に多い | 20~30代の若年層に多い |
子宮体がんの種類
子宮体がんは、組織学的特徴(顕微鏡で見たときの顔つき)によっていくつかの種類に分類されます。この分類は、がんの性質や治療方針を決定する上で重要な情報となります。
類内膜がんと特殊型
子宮体がんの約80%以上を占めるのが「類内膜がん」です。これは比較的おとなしい性質を持つことが多く、女性ホルモンであるエストロゲンの影響を受けて発生すると考えられています。
一方、少数ですが「漿液性がん」や「明細胞がん」といった特殊なタイプも存在します。
これらはエストロゲンの影響とは無関係に発生することが多く、類内膜がんに比べて進行が速く、転移しやすい性質を持つため、より慎重な治療計画が必要です。
不正出血が示す子宮体がんの初期症状
子宮体がんは、比較的早い段階で症状が現れやすいがんの一つです。最も代表的なサインである「不正出血」に気づくことが、早期発見の鍵となります。
ここでは、子宮体がんの初期症状としてどのようなものがあるか、また進行した場合にどのような症状が現れるかについて詳しく見ていきます。
最も多い初期症状「不正出血」
子宮体がんの患者さんの約90%に不正出血が見られます。これは、がん組織がもろく、簡単に出血するために起こります。
月経ではない時期の出血や、月経の量が異常に多い、だらだらと長く続くといった変化があれば、注意が必要です。
不正出血とはどのような症状か
不正出血には様々なパターンがあります。少量で茶色っぽいおりものとして現れることもあれば、鮮血が少量見られることもあります。
閉経前の方では、月経周期が不規則になったり、経血量が増えたりする(過多月経)といった症状として現れることもあります。
閉経後の不正出血は特に注意が必要
すでに閉経しているにもかかわらず、たとえ少量であっても性器から出血があった場合は、特に注意が必要です。
閉経後は本来出血がないはずなので、このような症状は体の異常を示す重要なサインです。ためらわずに婦人科を受診することが大切です。
その他の注意すべき症状
不正出血以外にも、注意すべき症状がいくつかあります。
これらの症状は、子宮体がん以外の原因でも起こり得ますが、複数の症状が重なる場合や、症状が続く場合は、専門医に相談しましょう。
症状の具体例
| 症状の種類 | 具体的な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| おりものの異常 | 水っぽいおりもの、膿のようなおりもの、血が混じったおりもの | 色や量、においの変化に気づいたら注意 |
| 下腹部痛・骨盤痛 | 月経痛とは異なる痛み、持続的な痛み | がんが進行し、子宮が大きくなることで生じる場合がある |
| 性交時痛 | 性交時に痛みを感じる | がんが周囲の組織に影響を与えている可能性 |
進行した場合の症状と転移
がんが進行し、子宮の外にまで広がると、より重い症状が現れます。がんが膀胱や直腸を圧迫することで頻尿や排便困難が起こったり、骨盤内の神経に広がることで腰痛や足の痛みを引き起こしたりします。
さらに、リンパ節や肺、肝臓など遠くの臓器に転移すると、全身の倦怠感や体重減少といった症状が現れることもあります。
閉経後に増加する子宮体がんのリスク要因
子宮体がんは、特に50代から60代の閉経期を迎えた女性に多く見られます。これは、ライフステージの変化に伴う体内のホルモン環境の変化が大きく関わっています。
どのような要因が子宮体がんの発症リスクを高めるのかを理解し、自分に当てはまるものがないかを確認することが、予防や早期発見につながります。
なぜ閉経後にリスクが高まるのか
閉経前は、卵巣から分泌される二つの女性ホルモン、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)がバランスを取り合っています。
しかし、閉経後はプロゲステロンの分泌がほぼなくなり、エストロゲンが優位な状態が続きやすくなります。このホルモンバランスの乱れが、子宮体がんの大きな原因となります。
主なリスク要因一覧
子宮体がんの発症には、ホルモン環境だけでなく、体質や生活習慣、既往歴など様々な要因が関わっています。以下に主なリスク要因を挙げます。
- 出産経験がない、または少ない
- 閉経が遅い(52歳以降など)
- 肥満
- 糖尿病、高血圧
- 乳がんや大腸がんの既往歴または家族歴
生活習慣との関連
近年、食生活の欧米化が子宮体がんの増加の一因として指摘されています。特に、高脂肪・高カロリーな食事は肥満につながりやすく、これが発症リスクを高める重要な要因です。
肥満や食生活の影響
肥満、特に閉経後の肥満は注意が必要です。脂肪組織は、副腎から分泌される男性ホルモンをエストロゲンに変換する働きを持っています。
そのため、脂肪組織が多いと体内のエストロゲン量が増加し、子宮内膜を過剰に刺激し続けることになり、がん化のリスクを高めます。
バランスの取れた食事と適度な運動による体重管理は、子宮体がんの予防において非常に重要です。
エストロゲンとホルモンバランスの影響
子宮体がん、特に最も多い類内膜がんの発症には、女性ホルモンである「エストロゲン」が深く関与しています。
エストロゲンそのものは女性の体にとって必要不可欠なホルモンですが、その作用が過剰になることで、がんのリスクが高まります。
ここでは、エストロゲンがどのように子宮体がんに関わるのか、そしてホルモンバランスが乱れる原因について解説します。
エストロゲンが子宮内膜に与える影響
エストロゲンには、子宮内膜を増殖させる(厚くする)働きがあります。
排卵後にはもう一つの女性ホルモンであるプロゲステロンが分泌され、このプロゲステロンが増殖した子宮内膜を維持し、妊娠に適した状態に整えます。
妊娠が成立しない場合、両方のホルモンが減少し、増殖した子宮内膜は剥がれ落ちて月経として排出されます。
エストロゲンの刺激が続くことの問題
しかし、何らかの理由でプロゲステロンの作用が十分に得られず、エストロゲンの刺激だけが長期間続くと、子宮内膜は増殖し続けることになります。
この状態が続くと、内膜の細胞に異常が起こりやすくなり、「子宮内膜増殖症」という前がん病変を経て、やがて子宮体がんへと進行する可能性があるのです。
ホルモンバランスを乱す要因
エストロゲンが相対的に優位になる(プロゲステロンの作用が弱まる)状態は、様々な要因によって引き起こされます。
これらの要因を持つ人は、持たない人に比べて子宮体がんのリスクが高いと考えられます。
エストロゲンが優位になる状態の例
| 要因 | 説明 | 関連キーワード |
|---|---|---|
| 出産経験がない | 妊娠・授乳期間中は排卵が止まり、エストロゲンの刺激から守られるため、経験がないと刺激を受ける期間が長くなる | 原因 |
| 排卵障害 | 多嚢胞性卵巣症候群などで排卵が起こりにくいと、プロゲステロンが分泌されず、エストロゲンの刺激が続く | 子宮内膜症 |
| 肥満 | 脂肪組織でエストロゲンが作られるため、体内のエストロゲンレベルが高くなる | 肥満 |
ホルモン療法との関連
更年期障害の治療などでホルモン補充療法(HRT)を受ける場合、その内容によっては子宮体がんのリスクに影響を与えることがあります。
子宮がある人がエストロゲン単独のホルモン療法を受けると、子宮体がんのリスクが上昇することが知られています。そのため、通常はプロゲステロンを併用する治療法を選択し、リスクを相殺します。
治療を受ける際は、医師と十分に話し合い、適切な方法を選択することが重要です。
病期(ステージ)別に見る進行度と治療選択
子宮体がんの治療方針は、がんの進行度、すなわち「病期(ステージ)」によって大きく異なります。ステージは、がんが子宮のどの深さまで達しているか、また他の臓器への広がりの有無によって決まります。
正確なステージ診断に基づき、手術、放射線治療、抗がん剤治療、ホルモン療法などを組み合わせた治療計画を立てます。
子宮体がんの病期(ステージ)分類
子宮体がんのステージは、主に手術によって摘出した組織を病理検査で詳しく調べることで確定します。これを「手術進行期分類」と呼びます。
ステージはⅠ期からⅣ期に分けられ、数字が大きくなるほどがんが進行していることを示します。
ステージの定義(FIGO 2009 手術進行期分類の概要)
| ステージ | がんの広がり | 進行度 |
|---|---|---|
| Ⅰ期 | がんが子宮体部に留まっている | 早期 |
| Ⅱ期 | がんが子宮頸部に広がっている | 進行 |
| Ⅲ期 | がんが子宮の外に広がっているが、骨盤内に留まっている | 進行 |
| Ⅳ期 | がんが膀胱や直腸の粘膜に広がっている、または骨盤を越えて遠隔転移している | 進行 |
ステージごとの主な治療法
治療の基本は手術ですが、ステージやがんの組織型、患者さんの全身状態などを考慮して、最適な治療法を決定します。
初期段階の治療
ステージⅠ期やⅡ期といった早期のがんでは、手術が治療の主体です。基本的には、子宮と両側の卵巣・卵管を摘出する手術を行います。
がんの悪性度や筋層への浸潤の深さによっては、骨盤内や傍大動脈のリンパ節も摘出(郭清)することがあります。
手術後の病理検査の結果次第では、再発リスクを減らすために追加で抗がん剤治療や放射線治療を行うこともあります。
進行した場合の治療
ステージⅢ期やⅣ期の進行がん、あるいは再発した場合には、一つの治療法だけでは不十分なため、複数の治療法を組み合わせた集学的治療を行います。
手術で可能な限り腫瘍を取り除いた後、抗がん剤治療や放射線治療を追加するのが一般的です。
また、がん細胞がホルモンの影響を受けるタイプ(ホルモン受容体陽性)で、進行がゆっくりな場合には、ホルモン療法が選択されることもあります。
5年生存率の目安
5年相対生存率とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標です。
日本人のがん患者さん全体の5年後の生存率と比較した数値で、100%に近いほど治療による効果が高いことを意味します。
ステージ別の5年相対生存率(全国がんセンター協議会データより)
| ステージ | 5年相対生存率 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 約92.5% |
| Ⅱ期 | 約82.8% |
| Ⅲ期 | 約62.6% |
| Ⅳ期 | 約23.0% |
このデータが示すように、子宮体がんは早期に発見し治療を開始すれば、良好な予後が期待できるがんです。
不正出血などの症状に気づいたら、ためらわずに婦人科を受診することがいかに重要かがわかります。
手術療法と術後の生活への影響
子宮体がん治療の根幹をなすのが手術です。がんを取り除き、正確な進行度を確定させるという二つの重要な目的があります。手術によって体は変化し、術後の生活に様々な影響が及ぶ可能性があります。
どのような手術が行われ、術後にどのような変化が起こりうるのかを事前に理解しておくことは、不安を和らげ、前向きに治療と向き合うために大切です。
子宮体がんの基本的な手術方法
子宮体がんの標準的な手術は、子宮、両側の卵巣と卵管をすべて摘出する方法です。
単純子宮全摘出術と両側付属器摘出術
最も基本となる術式は「単純子宮全摘出術」と「両側付属器(卵巣・卵管)摘出術」です。
子宮体がんが卵巣に転移しやすい性質を持つため、閉経後であれば再発のリスクを減らす目的で、卵巣と卵管も同時に摘出するのが一般的です。
これにより、がんの根治を目指します。
進行度に応じた追加の手術
術前の検査や術中の所見で、がんが子宮の外に広がっている可能性が疑われる場合には、骨盤内や腹部大動脈周囲のリンパ節を摘出する「リンパ節郭清」を追加します。
リンパ節への転移の有無は、術後の治療方針を決める上で極めて重要な情報となります。また、がんが周囲の臓器にまで広がっている場合には、それらの臓器の一部を合併切除することもあります。
手術による身体的な変化と後遺症
手術後は、いくつかの身体的な変化や後遺症が起こる可能性があります。これらは生涯続くこともありますが、適切なケアによって症状を和らげることができます。
リンパ浮腫のリスクとケア
リンパ節郭清を行った場合に起こりうる代表的な後遺症が「リンパ浮腫」です。脚のリンパの流れが滞り、むくみやだるさ、皮膚の硬化などが生じます。
一度発症すると完治は難しいですが、弾性ストッキングの着用や専門的なマッサージ、スキンケアなどで症状をコントロールすることが可能です。
卵巣欠落症状とホルモン補充療法
閉経前の女性が両側の卵巣を摘出した場合、女性ホルモンが急激に失われるため、ホットフラッシュ、発汗、動悸、気分の落ち込みといった更年期障害と同様の症状(卵巣欠落症状)が強く現れることがあります。
これらの症状に対しては、がんの性質を考慮した上で、ホルモン補充療法などの治療を行うことがあります。
術後の生活で心がけること
手術後は、体力の回復に合わせて徐々に元の生活に戻していきます。退院後の生活では、いくつかの点に注意が必要です。
日常生活への復帰と注意点
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 運動 | ウォーキングなどの軽い運動から始め、徐々に強度を上げる。腹圧のかかる激しい運動は医師に相談する。 |
| 食事 | バランスの取れた食事を心がける。便秘を防ぐために食物繊維や水分を十分に摂る。 |
| 入浴 | シャワーは早期から可能。湯船に浸かるのは、医師の許可が出てからにする。 |
検診による早期発見の重要性と検査方法
子宮体がんは、早期に発見すれば治癒率が非常に高いがんです。そのためには、体のサインを見逃さないことと、必要に応じて適切な検査を受けることが重要になります。
特にリスク要因を持つ方は、検診の重要性を理解し、積極的に受けることを検討しましょう。ここでは、子宮体がんの検査方法について詳しく解説します。
なぜ早期発見が重要なのか
子宮体がんが子宮体部に留まっているステージⅠ期で発見された場合の5年生存率は90%を超えます。しかし、がんが進行し、遠くの臓器にまで転移したステージⅣ期になると、その数値は大幅に低下します。
このことからも、症状が軽いうちに、あるいは無症状の段階でがんを発見し、治療を開始することが、良好な予後を得るためにいかに大切かがわかります。
子宮体がんの主な検査方法
子宮体がんが疑われる場合、いくつかの検査を段階的に行い、診断を確定していきます。
検査の流れ(問診から確定診断まで)
まず問診で自覚症状や既往歴、家族歴などを確認します。次に内診で子宮や卵巣の状態を触診し、超音波(エコー)検査で子宮内膜の厚さなどを画像で確認します。
これらの検査で疑いが強まった場合に、細胞や組織を採取する精密検査へと進みます。
各検査方法の詳細
| 検査名 | 方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 超音波検査 | プローブ(探触子)を腟内に挿入し、子宮や卵巣を観察する | 子宮内膜の厚さを測定できる。内膜が厚い場合に疑いが強まる。痛みは少ない。 |
| 子宮内膜細胞診 | 細いブラシやチューブを子宮内に挿入し、内膜の細胞をこすり取って調べる | 外来で行える比較的簡単な検査。子宮体がん検診として行われる。多少の痛みを伴うことがある。 |
| 子宮内膜組織診 | 細胞診より太い器具で内膜の組織を一部かき取り、詳しく調べる | 細胞診で異常があった場合などに行う確定診断のための検査。細胞診より痛みが強いことがある。 |
子宮内膜症と検査の注意点
子宮内膜症は、本来子宮の内側にあるべき内膜組織が、子宮以外の場所(卵巣、腹膜など)で増殖する病気です。
子宮体がんとは直接的な関連は低いとされていますが、月経痛や不正出血など、似た症状を示すことがあります。また、まれに卵巣にできた子宮内膜症(チョコレートのう胞)からがんが発生することもあります。
子宮内膜症の診断を受けている方は、定期的な婦人科でのチェックを継続することが大切です。
肥満・糖尿病と発症リスクの関連性
子宮体がんのリスク要因として、生活習慣に関わるものが注目されています。中でも「肥満」と「糖尿病」は、子宮体がんの発症と密接な関係があることが多くの研究で明らかになっています。
これらの生活習慣病が、なぜ子宮体がんのリスクを高めるのか。その理由を知り、生活習慣を見直すことが、有効な予防策となります。
肥満が子宮体がんリスクを高める理由
肥満、特に体脂肪の増加は、子宮体がんの最も重要なリスク要因の一つです。
BMI(Body Mass Index)が25以上の肥満の人は、標準体重の人に比べて子宮体がんになるリスクが2~3倍高くなると報告されています。
脂肪細胞とエストロゲン産生
この主な原因は、ホルモンバランスへの影響です。
閉経後の女性の体内では、卵巣からのエストロゲン分泌は停止しますが、副腎から分泌される男性ホルモンの一種が、脂肪組織に存在するアロマターゼという酵素の働きによってエストロゲンに変換されます。
つまり、体脂肪が多い(肥満である)ほど、体内で作られるエストロゲンの量が増加します。この過剰なエストロゲンが子宮内膜を継続的に刺激し、細胞のがん化を促進してしまうのです。
糖尿病と子宮体がんの関係
糖尿病、特に2型糖尿病の患者さんは、子宮体がんの発症リスクが高いことが知られています。この背景には、インスリンというホルモンが関わっています。
高インスリン血症の影響
2型糖尿病の患者さんやその予備軍では、血糖値を下げるインスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」という状態が見られます。
体はこれを補うために、より多くのインスリンを分泌しようとするため、血液中のインスリン濃度が高い状態(高インスリン血症)になります。
この高濃度のインスリンが、子宮内膜細胞の増殖を直接的に促す作用を持つため、がん化のリスクを高めると考えられています。
リスク軽減のための生活習慣改善
肥満や糖尿病は、生活習慣の改善によって予防・管理が可能です。これは、子宮体がんのリスクを低減させることにも直結します。
- 適正体重の維持(BMI 25未満を目指す)
- バランスの取れた食事(野菜や果物を多く、脂肪や糖分は控えめに)
- 定期的な運動習慣(ウォーキングなど、無理なく続けられるもの)
これらの健康的な生活習慣を心がけることは、子宮体がんだけでなく、様々な病気の予防につながるため、積極的に取り組むことが重要です。
予後と再発予防のための経過観察
子宮体がんの治療を無事に終えた後も、再発の可能性はゼロではありません。そのため、治療後の「経過観察」は、予後をより良くするために非常に重要な役割を果たします。
定期的に通院し、必要な検査を受けることで、万が一の再発を早期に発見し、迅速に対応することができます。ここでは、経過観察の目的や内容、そして再発した場合の治療について解説します。
治療後の経過観察の目的
経過観察の最大の目的は、がんの再発をできるだけ早い段階で見つけることです。子宮体がんの再発は、治療後2~3年以内に起こることが多いとされています。
早期に発見できれば、再び治療を行うことで治癒を目指せる可能性が高まります。
また、治療による後遺症(リンパ浮腫など)の管理や、心身のケアを行う上でも、定期的な受診は大切な機会となります。
経過観察の具体的な内容と頻度
経過観察のスケジュールは、がんのステージや組織型、再発のリスクに応じて個別に設定されますが、一般的には以下のような間隔で行います。
定期的な診察と検査のスケジュール(一例)
| 期間 | 頻度 | 主な検査内容 |
|---|---|---|
| 治療後1~3年 | 1~4ヶ月に1回 | 問診、内診、血液検査(腫瘍マーカー)、CT検査など |
| 治療後4~5年 | 6ヶ月に1回 | 問診、内診、血液検査(腫瘍マーカー)など |
| 治療後6年以降 | 1年に1回 | 問診、内診など |
再発した場合の治療法
万が一、再発が確認された場合の治療法は、再発した場所や範囲、これまでの治療内容、患者さんの全身状態などを総合的に判断して決定します。
再発部位に応じた治療選択
再発が腟や骨盤内など、局所的な範囲に留まっている場合は、放射線治療や、可能であれば再手術を検討します。
一方、肺や肝臓など、遠くの臓器に転移している(遠隔再発)場合は、全身に効果が及ぶ抗がん剤治療やホルモン療法が治療の中心となります。
再発がんの治療は、がんの進行を抑え、症状を和らげながら、QOL(生活の質)を維持していくことも重要な目標となります。
よくある質問
子宮体がんについて、患者さんやそのご家族からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 子宮体がん検診は痛いですか?
-
子宮内膜から細胞や組織を採取する際に、月経痛のような痛みや違和感を伴うことがあります。痛みの感じ方には個人差が大きく、ほとんど痛みを感じない方もいれば、強く感じる方もいます。
検査前に医師や看護師に不安な気持ちを伝えておくと、リラックスできるよう配慮してくれるでしょう。検査にかかる時間は短いため、多くの場合、我慢できる範囲の痛みです。
- 子宮体がんは遺伝しますか?
-
ほとんどの子宮体がんは遺伝とは関係なく発生しますが、ごく一部に遺伝が強く関わるものがあります。
「リンチ症候群」という遺伝性疾患の家系では、子宮体がんや大腸がんなど、様々な種類のがんを発症するリスクが高いことが知られています。
血縁者に若くして大腸がんや子宮体がんになった方が複数いる場合は、遺伝カウンセリングについて主治医に相談してみることをお勧めします。
- 治療後、妊娠・出産は可能ですか?
-
子宮体がんの標準治療は子宮全摘出術であるため、治療後に妊娠・出産することはできなくなります。
しかし、ごく早期の類内膜がん(ステージⅠA期で悪性度の低いもの)で、将来的に妊娠を強く希望する場合には、厳格な条件のもとで「ホルモン療法」を選択し、子宮を温存する治療(妊孕性温存療法)が検討されることがあります。
この治療は適応が限られ、再発リスクも伴うため、実施できる医療機関で専門医と十分に相談することが必要です。
- 抗がん剤治療の副作用にはどのようなものがありますか?
-
抗がん剤の種類によって異なりますが、一般的に見られる副作用には、吐き気・嘔吐、食欲不振、口内炎、脱毛、倦怠感、白血球や血小板の減少(感染しやすくなる、出血しやすくなる)、手足のしびれ(末梢神経障害)などがあります。
近年は、吐き気止めなど副作用を軽減する支持療法が進歩しており、多くの副作用はコントロール可能です。治療中はつらい症状を我慢せず、医療スタッフに伝えることが大切です。
子宮体がんと同様に、女性特有のがんとして注意が必要なものに「卵巣がん」があります。
卵巣がんは「サイレントキラー(沈黙の殺人者)」とも呼ばれ、初期症状がほとんどなく、進行した状態で見つかることが多いがんです。
お腹の張りや食欲不振など、見過ごしやすい症状がサインであることもあります。
子宮体がんのリスク要因でもあるホルモン環境の変化は、卵巣にも影響を与えます。女性の健康を守るためには、子宮だけでなく、卵巣の健康にも目を向けることが重要です。
卵巣がんの基礎知識やリスク、検査について理解を深めるために、以下の記事もあわせてご覧ください。
以上
参考文献
CHIA, V. M., et al. Obesity, diabetes, and other factors in relation to survival after endometrial cancer diagnosis. International Journal of Gynecological Cancer, 2007, 17.2: 441-446.
KOLEHMAINEN, Anne, et al. Clinical factors as prognostic variables among molecular subgroups of endometrial cancer. PLoS One, 2020, 15.11: e0242733.
MU, Nan, et al. Insulin resistance: a significant risk factor of endometrial cancer. Gynecologic oncology, 2012, 125.3: 751-757.
GAO, Huiqiao; LU, Qi; ZHANG, Jianxin. Factors affecting the postoperative survival rate of obese Asian patients with endometrial cancer. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2025, 45.1: 2480856.
SALTZMAN, Babette S., et al. Diabetes and endometrial cancer: an evaluation of the modifying effects of other known risk factors. American journal of epidemiology, 2008, 167.5: 607-614.
FRIBERG, Emilie; MANTZOROS, Christos S.; WOLK, Alicja. Diabetes and risk of endometrial cancer: a population-based prospective cohort study. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 2007, 16.2: 276-280.
SOLIMAN, Pamela T., et al. Risk factors for young premenopausal women with endometrial cancer. Obstetrics & Gynecology, 2005, 105.3: 575-580.
LINDEMANN, K., et al. Body mass, diabetes and smoking, and endometrial cancer risk: a follow-up study. British journal of cancer, 2008, 98.9: 1582-1585.
SHOFF, Suzanne M.; NEWCOMB, Polly A. Diabetes, body size, and risk of endometrial cancer. American journal of epidemiology, 1998, 148.3: 234-240.
SHAW, Eileen, et al. Obesity and endometrial cancer. Obesity and cancer, 2016, 107-136.
婦人科系がんに戻る