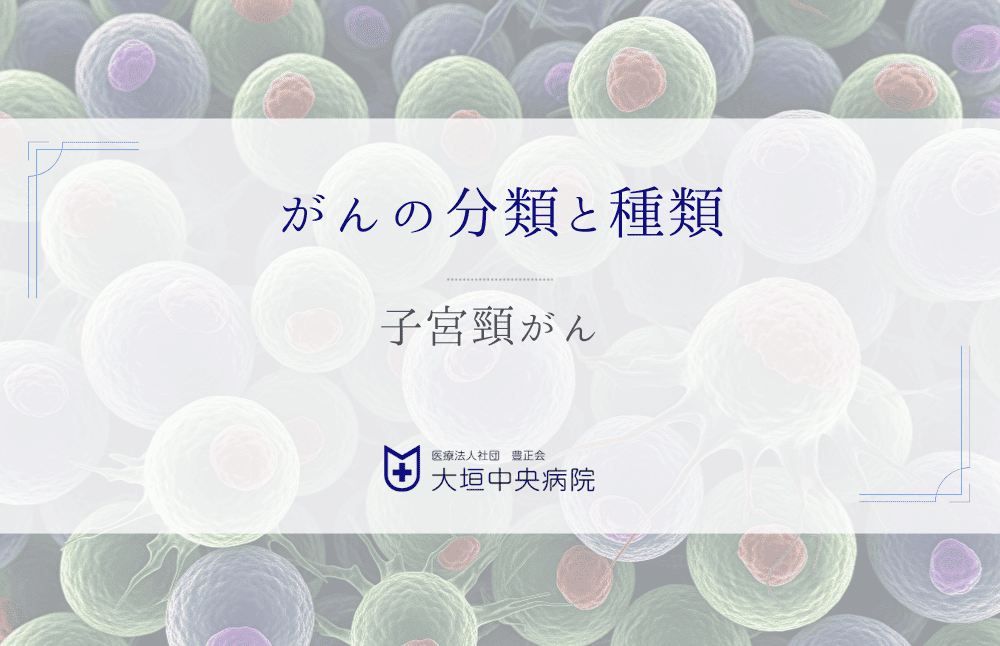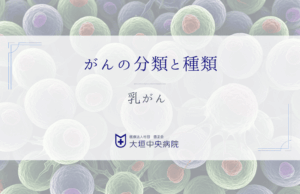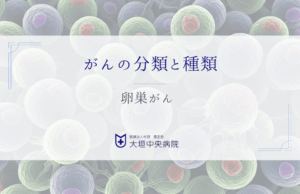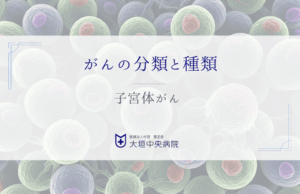子宮頸がんは、女性特有のがんの中でも特に20代から40代の若い世代で増加傾向にあります。
しかし、このがんは原因がほぼ特定されており、ワクチンによる予防と定期的な検診による早期発見が可能な「予防できるがん」です。
この記事では、子宮頸がんの基本的な知識から、その原因となるHPV、症状、検査、そして治療法に至るまでを詳しく解説します。
正しい情報を得て、あなた自身の、そして大切な人の健康を守るための一歩を踏み出しましょう。
子宮頸がんとは何か – 発生部位と特徴
子宮頸がんは、その名の通り子宮の「頸部(けいぶ)」という部分に発生するがんです。女性の健康を考える上で、このがんがどこにでき、どのような特徴を持つのかを理解することは非常に重要です。
まずは、子宮頸がんの基本的な知識から見ていきましょう。
子宮の入り口「子宮頸部」にできるがん
子宮は、妊娠時に胎児を育む洋梨のような形をした臓器です。その下部にある、腟につながる細長い部分を「子宮頸部」と呼びます。
子宮頸がんは、この子宮頸部の表面を覆う細胞から発生します。
子宮頸部の構造と役割
子宮頸部は、子宮本体(体部)と腟をつなぐ通路の役割を果たします。普段は細菌などが子宮内に侵入するのを防ぎ、排卵期には精子が通過しやすくなるように粘液を分泌します。
また、出産時には産道の一部として大きく開きます。この子宮頸部は、二つの異なる種類の上皮細胞で覆われており、その境界領域はがんが発生しやすい場所として知られています。
子宮頸がんの主な種類
子宮頸がんは、発生する細胞の種類によって、主に「扁平上皮(へんぺいじょうひ)がん」と「腺がん」の二つに大別します。
どちらの種類であるかによって、がんの性質や進行の仕方に違いが見られます。
扁平上皮がん
子宮頸がんの中で最も多く、全体の約70~80%を占めます。子宮頸部のうち、腟に近い部分を覆っている扁平上皮細胞から発生します。
比較的進行が緩やかで、検診による細胞診で発見しやすい特徴があります。
腺がん
全体の約20%を占め、近年増加傾向にあります。子宮頸部の奥側、子宮体部に近い部分の管状の腺細胞から発生します。
扁平上皮がんに比べて、がん細胞が奥に隠れていることが多く、検診で見つけにくい場合があります。
扁平上皮がんと腺がんの特徴比較
| 項目 | 扁平上皮がん | 腺がん |
|---|---|---|
| 発生頻度 | 約70~80% | 約20%(増加傾向) |
| 発生場所 | 子宮頸部の外側(腟側) | 子宮頸部の内側(子宮体部側) |
| 検診での発見しやすさ | 比較的発見しやすい | 発見しにくいことがある |
なぜ子宮頸がんは「予防できるがん」なのか
多くのがんがその原因を一つに特定することが難しい中、子宮頸がんは例外的な存在です。
原因がほぼ解明されており、がんになる前の段階で発見し、有効な予防法を実践できるため、「予防できるがん」として知られています。この事実は、私たちに希望と行動の指針を与えてくれます。
原因がほぼ解明されている
子宮頸がんの最大の原因は、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの持続的な感染であることがわかっています。すべてのがんの中で、これほど明確に原因が特定されているものは稀です。
この発見が、子宮頸がんの予防戦略の基盤となっています。
HPV感染という明確な原因
子宮頸がん患者の99%以上からHPVが検出されることから、このウイルスが発がんの直接的な引き金であることは間違いありません。
原因がウイルスであるため、その感染を防ぐことが、がんの予防に直結します。
がんになる前の段階で発見できる
子宮頸がんは、ある日突然発生するわけではありません。HPVに感染した後、数年から十年以上という長い年月をかけて、がんになる手前の状態である「前がん病変(異形成)」を経て進行します。
この前がん病変の段階で発見し、治療を行えば、がんへの進行を防ぐことが可能です。
検診による前がん病変の発見
子宮頸がん検診は、がんそのものだけでなく、この前がん病変を発見することを大きな目的としています。定期的な検診を受けることで、自覚症状がないうちから体の変化を捉え、早期に対応できます。
有効な予防法が存在する
原因がわかり、がんになる前の段階を発見できるため、子宮頸がんには二段構えの有効な予防法があります。それが「一次予防」としてのワクチン接種と、「二次予防」としての定期検診です。
HPVワクチンによる一次予防
原因となるHPVの感染そのものを防ぐのがHPVワクチンです。性交渉を経験する前に接種することで、特に高い予防効果が期待できます。これががんの発生を未然に防ぐ一次予防です。
定期的な検診による二次予防
ワクチンで全てのHPV感染を防げるわけではないため、定期的な検診で前がん病変やごく初期のがんを発見し、早期治療につなげることが二次予防として重要です。
この二つの予防法を組み合わせることで、子宮頸がんのリスクを大幅に減らすことができます。
HPV(ヒトパピローマウイルス)と発がんの関連
子宮頸がんを語る上で、HPV(ヒトパピローマウイルス)の存在は避けて通れません。このウイルスがどのようにしてがんを引き起こすのか、その関連性を理解することが、正しい予防行動につながります。
HPVとはどのようなウイルスか
HPVは非常にありふれたウイルスで、100種類以上の型が存在します。皮膚や粘膜に感染し、多くはイボの原因となりますが、一部の型が子宮頸がんなどの原因となります。
多くの人が一生に一度は感染するウイルス
性交渉の経験がある女性であれば、約80%が生涯に一度はHPVに感染するといわれています。つまり、HPVへの感染自体は特別なことではありません。
感染しても、ほとんどの場合は体の免疫力によって自然にウイルスが排除されます。
感染経路としての性交渉
HPVの主な感染経路は性交渉です。皮膚や粘膜の接触によって感染するため、コンドームの使用で感染リスクをある程度減らすことはできますが、完全に防ぐことはできません。
発がん性の高いハイリスク型HPV
HPVには多くの型がありますが、子宮頸がんの原因となるのは、発がん性の高い「ハイリスク型」と呼ばれる特定の型です。
特に16型と18型は、子宮頸がんの原因の約60~70%を占めることがわかっています。
持続感染ががん化の原因
問題となるのは、ハイリスク型HPVが自然に排除されず、長期間にわたって子宮頸部に感染し続ける「持続感染」の状態です。
この持続感染が数年から十数年続くと、感染した細胞が徐々に異常な形(異形成)に変化し、やがてその一部ががん細胞へと変化していくことがあります。これが子宮頸がんの発生する流れです。
主なハイリスク型HPVの種類
| HPV型 | 子宮頸がんとの関連 | 備考 |
|---|---|---|
| 16型 | 原因の約50~60% | 最もリスクが高い型の一つ |
| 18型 | 原因の約10~15% | 腺がんとの関連が比較的高い |
| その他 | 31, 33, 45, 52, 58型など | 16型、18型に次いで多い |
子宮頸がんの症状と進行段階
子宮頸がんは「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」と表現されることがあるように、初期の段階では自覚症状がほとんどありません。症状が現れたときには、がんが進行している可能性もあります。
だからこそ、症状の有無にかかわらず検診を受けることが大切ですが、どのような症状に注意すべきかを知っておくことも重要です。
初期段階では自覚症状がほとんどない
前がん病変や、ごく初期の上皮内がんの段階では、痛みや出血などの症状はまずありません。この無症状の期間が、検診の重要性を物語っています。
症状がないから大丈夫と自己判断せず、定期的に体の状態をチェックする機会を持つことが、自分を守る最善の方法です。
進行すると現れる主な症状
がんが進行し、周囲の組織に広がり始めると、様々な症状が現れるようになります。以下のような症状に気づいたら、ためらわずに婦人科を受診してください。
不正出血
最も代表的な症状が不正出血です。月経以外の時期に出血したり、月経が長引いたり、閉経後に出血したりといった症状が見られます。
特に、がん組織はもろく出血しやすいため、性交渉の際に出血する「接触出血」は、子宮頸がんを疑う重要なサインの一つです。
おりものの変化
おりものの量が増えたり、色(茶褐色や黒っぽい色)やにおいに変化が見られたりすることがあります。水っぽいおりものが大量に出ることも症状の一つです。
月経の変化や下腹部痛
月経の量が増えたり、月経痛がひどくなったりすることもあります。さらにがんが進行すると、下腹部や腰に痛みを感じるようになります。
注意すべき症状
- 月経ではない時の出血(不正出血)
- 性交渉の際の出血
- 濃い茶色や黒っぽいおりもの、水っぽいおりもの
- 月経血の量が増える、月経期間が長引く
- 下腹部や腰の痛み
がんの進行度を示すステージ(病期)
子宮頸がんの治療方針は、がんの広がり具合を示す「ステージ(病期)」に基づいて決定します。
ステージは、がんが子宮頸部にとどまっているか、周囲の臓器や遠くの臓器にまで広がっているかによって分類します。
子宮頸がんのステージ分類(簡略版)
| ステージ | がんの広がり | 主な状態 |
|---|---|---|
| I期 | がんが子宮頸部に限局している | 初期のがん。手術が中心となる。 |
| II期 | がんが子宮頸部を超えて広がっているが、骨盤壁には達していない | 腟壁などに広がっている状態。 |
| III期 | がんが骨盤壁まで達している、または水腎症などを引き起こしている | 主に放射線治療と化学療法の併用。 |
| IV期 | がんが膀胱や直腸に広がっている、または遠隔転移している | 全身的な治療(薬物療法など)が中心。 |
検診で見つかる前がん病変の重要性
子宮頸がん検診の最大の意義は、がんそのものを早期発見することだけではありません。むしろ、がんになる一歩手前の状態である「前がん病変」を見つけ出し、がんへの進行を未然に防ぐことにあります。
この前がん病変の段階で適切に対処することが、子宮を守り、健康を守る鍵となります。
前がん病変とは
前がん病変は、「異形成(いけいせい)」とも呼ばれます。これは、HPVに持続感染した子宮頸部の細胞が、正常な細胞とは異なる異常な形に変化した状態を指します。
この時点ではまだ「がん」ではありませんが、放置すると一部ががんに進行する可能性があります。
異形成と呼ばれる細胞の変化
異形成の細胞は、核が大きくなったり形が不揃いになったりといった特徴を持ちます。子宮頸がん検診で採取した細胞を顕微鏡で観察する「細胞診」によって、この変化を捉えることができます。
前がん病変の分類と進行
異形成は、細胞の異常の程度によって「軽度」「中等度」「高度」の3段階に分類します。この分類は、その後の対応方針を決める上で重要な指標となります。
軽度・中等度・高度異形成(CIN1~3)
国際的にはCIN(Cervical Intraepithelial Neoplasia)という分類を用います。CIN1が軽度異形成、CIN2が中等度異形成、CIN3が高度異形成および上皮内がんに相当します。
数字が大きくなるほど、がんへと進行するリスクが高まります。
異形成の分類と対応
| 分類 | 状態 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 軽度異形成 (CIN1) | 多くは自然に正常な状態に戻る | 定期的な経過観察が中心 |
| 中等度異形成 (CIN2) | 自然に治ることもあるが、進行する可能性も | 慎重な経過観察、または治療を検討 |
| 高度異形成 (CIN3) | がんに進行するリスクが高い | 治療が必要 |
前がん病変の段階での治療
高度異形成(CIN3)や、場合によっては中等度異形成(CIN2)と診断された場合、がんへの進行を防ぐための治療を行います。
この段階での治療は、子宮を温存できる比較的体への負担が少ない方法が中心となります。
経過観察と円錐切除術
軽度異形成の場合は、定期的な検査で自然に治るかどうかを確認する「経過観察」が基本です。治療が必要な場合は、「円錐切除術」という手術が一般的に行われます。
これは、子宮頸部の病変部分を円錐状に切除する手術です。診断と治療を兼ねることができ、切除範囲が小さいため、その後の妊娠や出産も十分に可能です。
治療方法と選択肢 – 病期別アプローチ
子宮頸がんの治療は、がんの進行度(ステージ)、がんの種類(扁平上皮がんか腺がんか)、年齢、全身の状態、そして将来の妊娠希望の有無などを総合的に考慮して、一人ひとりに合った方法を決定します。
ここでは、主な治療法とその選択について解説します。
ステージに応じた治療法の選択
治療の基本方針は、がんがどのくらい広がっているかを示すステージによって大きく異なります。早期であればあるほど、体への負担が少なく、子宮を温存できる可能性も高くなります。
ステージ別標準治療の概要
| ステージ | 主な治療法 | 子宮温存の可能性 |
|---|---|---|
| 0期(上皮内がん) | 円錐切除術 | 可能 |
| I期~II期初期 | 手術(広汎子宮全摘出術など)、または放射線治療 | ごく早期であれば可能な場合も |
| II期後半~IV期A | 同時化学放射線療法(CCRT) | 困難 |
| IV期B(遠隔転移) | 薬物療法(化学療法、分子標的薬など) | 困難 |
主な治療法
子宮頸がんの治療は、「手術(外科治療)」「放射線治療」「薬物療法(化学療法)」の三つが大きな柱です。これらを単独で、あるいは組み合わせて治療を進めます。
手術(外科治療)
がんが子宮頸部やその周辺にとどまっている早期の段階で中心となる治療法です。病変の広がりによって、切除する範囲が変わります。
- 円錐切除術 前がん病変やごく初期のがんに対して行います。子宮を温存できます。
- 単純子宮全摘出術 子宮のみを摘出する手術です。
- 広汎子宮全摘出術 子宮とともに、その周りの組織やリンパ節も広く切除する手術で、I期からII期前半の標準的な手術です。
放射線治療
高エネルギーのX線などを照射して、がん細胞を破壊する治療法です。体の外から照射する方法(外部照射)と、腟の中から直接照射する方法(腔内照射)があります。
手術が難しい進行がんや、手術後の再発予防目的で行います。化学療法と同時に行う「同時化学放射線療法」は、進行がんの標準治療です。
薬物療法(化学療法)
抗がん剤を用いて、がん細胞の増殖を抑えたり破壊したりする治療法です。主に、進行・再発したがんに対して行います。
放射線治療の効果を高める目的で併用したり、手術の前にがんを小さくするために行ったりすることもあります。
近年では、特定の分子を標的とする「分子標的薬」や、免疫の力を利用する「免疫チェックポイント阻害薬」なども登場し、治療の選択肢が広がっています。
治療後の生活と生存率
治療法にかかわらず、治療後は定期的な通院で再発がないかなどをチェックします。また、生存率は治療成績を示す指標の一つですが、あくまで全体のデータであり、個々の状況とは異なります。
早期に発見し、適切な治療を受けることが、より良い結果につながります。
ステージ別5年相対生存率
| ステージ | 5年相対生存率(目安) |
|---|---|
| I期 | 90%以上 |
| II期 | 約70~80% |
| III期 | 約50% |
| IV期 | 約20~30% |
ワクチンによる一次予防の効果と対象
子宮頸がんの最大の原因であるHPVの感染を未然に防ぐ「一次予防」として、最も有効な手段がHPVワクチンです。
ワクチンについての正しい知識を持つことは、がんから自分自身を守るための第一歩です。
HPVワクチンの役割
HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となるハイリスク型HPVのうち、特に感染頻度の高い種類の感染を予防するものです。
体内にウイルスの感染を防ぐ「抗体」を作らせることで、将来のがんのリスクを大幅に低減させます。
HPV感染を防ぐことによるがん予防
ワクチンは、ウイルスそのものではなく、ウイルスの殻の部分だけを遺伝子組換え技術で人工的に合成したものです。そのため、ワクチン接種によってHPVに感染する心配は一切ありません。
安全に免疫だけを獲得し、実際のウイルスが侵入してきた際にそれを排除する力を身につけることができます。
ワクチンの種類と対象年齢
現在、日本で公費(無料)で接種できるHPVワクチンには3種類あります。どのワクチンも、子宮頸がんの主な原因であるHPV16型と18型の感染を予防する効果があります。
2価・4価・9価ワクチンの違い
ワクチンの「価」とは、予防できるHPVの型の数を表します。2価ワクチンは16型・18型、4価ワクチンはそれに加えて良性のいぼ(尖圭コンジローマ)の原因となる6型・11型を予防します。
9価ワクチンは、さらに他の5種類のハイリスク型HPV(31, 33, 45, 52, 58型)の感染も防ぐことができ、子宮頸がんの原因の約90%をカバーするとされています。
HPVワクチンの種類と特徴
| ワクチンの種類 | 予防できるHPV型 | 子宮頸がん予防効果 |
|---|---|---|
| 2価ワクチン(サーバリックス) | 16, 18型 | 約60~70% |
| 4価ワクチン(ガーダシル) | 6, 11, 16, 18型 | 約60~70% |
| 9価ワクチン(シルガード9) | 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58型 | 約90% |
定期接種とキャッチアップ接種
小学校6年生から高校1年生相当の女子は、公費でHPVワクチンを接種できます(定期接種)。
また、積極的勧奨が差し控えられていた時期に接種機会を逃した、平成9年度から平成19年度生まれまでの女性を対象に、無料で接種できる「キャッチアップ接種」も実施しています。
ワクチン接種後の注意点
HPVワクチンは非常に有効な予防法ですが、万能ではありません。接種後も注意すべき点があります。
ワクチンで全てのHPV感染は防げない
現在最も予防効果の高い9価ワクチンでも、全ての発がん性HPVの感染を防げるわけではありません。また、すでに感染しているHPVを排除する効果もありません。
接種後も定期的な検診が必要
そのため、ワクチンを接種したからといって安心するのではなく、20歳を過ぎたら定期的に子宮頸がん検診を受けることが、がんから身を守るために引き続き重要です。
ワクチンと検診、この二つを組み合わせることが、最も確実な予防策です。
定期検診による早期発見の意義
HPVワクチンががんの発生を未然に防ぐ「一次予防」であるのに対し、定期的な検診は、万が一HPVに感染し、細胞に変化が起きたとしても、それをがんになる前の「前がん病変」やごく初期の段階で発見する「二次予防」として極めて重要です。
症状のない段階で体のサインを捉えることが、未来の健康を守ります。
子宮頸がん検診の内容
日本の自治体が推奨する子宮頸がん検診は、主に「細胞診」という検査です。近年では、原因となるHPVの有無を直接調べる「HPV検査」を併用することもあります。
細胞診(スメア検査)
ブラシやヘラのような器具で子宮頸部の表面を優しくこすり、細胞を採取します。採取した細胞を顕微鏡で観察し、異常な形をした細胞がないかを専門家が確認する検査です。
痛みはほとんどなく、短時間で終わります。
HPV検査
細胞診と同じように採取した細胞を用いて、子宮頸がんの原因となるハイリスク型HPVに感染しているかどうかを調べる検査です。
細胞診と併用することで、より精度の高い検診が可能になります。
検診を受ける頻度と推奨年齢
日本のガイドラインでは、20歳以上の女性は2年に1回、子宮頸がん検診を受けることを推奨しています。性交渉の経験があれば、20歳を待たずに検診を受けることも検討すると良いでしょう。
検診結果とその後の対応
検診で「要精密検査」という結果が出ても、すぐに「がん」というわけではありません。落ち着いて、必ず指示に従い精密検査を受けてください。
精密検査では、コルポスコープという拡大鏡で子宮頸部を詳しく観察し、必要であれば組織を少し採取して調べる「組織診(生検)」を行い、最終的な診断をします。
検診から診断までの流れ
- 子宮頸がん検診(細胞診・HPV検査)
- 結果通知(異常なし or 要精密検査)
- 精密検査(コルポスコープ診・組織診)
- 最終診断・方針決定
リスク要因と日常生活での注意点
子宮頸がんの最大の原因はハイリスク型HPVの持続感染ですが、それ以外にもがんの発生に関わるいくつかのリスク要因が知られています。
これらの要因を理解し、日常生活で注意を払うことも、予防の一環として大切です。
子宮頸がんの主なリスク要因
HPV感染以外で、がんへの進行を助長する可能性のある要因について見ていきましょう。
喫煙
喫煙は、子宮頸がんの最も重要なリスク要因の一つです。タバコに含まれる有害物質が、HPVを排除する免疫の働きを弱めたり、細胞のがん化を促進したりすることがわかっています。
喫煙者は非喫煙者に比べて、子宮頸がんになるリスクが1.5~2倍高くなると報告されています。
その他のリスク要因
- 多くの出産経験
- 経口避妊薬(ピル)の長期服用
- 他の性感染症(クラミジアなど)への感染
- 免疫力の低下(HIV感染や免疫抑制剤の使用など)
予防のためにできること
子宮頸がんから身を守るために、私たちが日常生活の中で実践できることは明確です。
HPVワクチン接種
最も効果的な一次予防です。対象年齢の方は、接種を積極的に検討することが重要です。
定期的な検診受診
二次予防の柱です。20歳を過ぎたら、2年に1度は必ず検診を受けましょう。症状がなくても続けることが大切です。
禁煙とバランスの取れた生活
喫煙している場合は、禁煙することが直接的なリスク低減につながります。
また、バランスの取れた食事や適度な運動、十分な睡眠を心がけ、体の免疫力を高く保つことも、HPVの排除を助け、健康維持に役立ちます。
よくある質問
- HPVに感染したら、必ず子宮頸がんになりますか?
-
いいえ、なりません。HPVに感染しても、そのうちの90%以上は自己の免疫力によって2年以内に自然に排除されます。
ウイルスが排除されずに長期間感染し続ける「持続感染」の状態になった場合に、ごく一部の人が数年から十数年かけて前がん病変、そして子宮頸がんへと進行する可能性があります。
感染自体を過度に恐れる必要はありません。
- 子宮頸がん検診は痛いですか?
-
痛みはほとんどありません。子宮頸部から細胞を採取する際に、器具による違和感や、軽い生理痛のような鈍い痛みを感じる方もいますが、一瞬で終わります。
力を抜いてリラックスして受けるのがコツです。不安な場合は、事前に医師や看護師に伝えておくと良いでしょう。
- HPVワクチンを接種すれば、もう検診は受けなくても大丈夫ですか?
-
いいえ、ワクチンを接種しても検診は必要です。HPVワクチンは、子宮頸がんの主な原因となるいくつかのハイリスク型HPVの感染を防ぎますが、すべての型の感染を防げるわけではありません。
ワクチンと検診の両方を組み合わせることで、子宮頸がんを最も効果的に予防できます。
- 性交渉の経験がなくても検診は必要ですか?
-
HPVの主な感染経路は性交渉であるため、性交渉の経験がない方が子宮頸がんになるリスクは極めて低いと考えられます。そのため、検診の必要性は低いといえます。
ただし、何か気になる症状(不正出血など)がある場合は、性交渉の経験の有無にかかわらず婦人科を受診してください。
- パートナーも何か気をつけることはありますか?
-
HPVは男性にも感染し、中咽頭がんや肛門がん、陰茎がんなどの原因となることがあります。男性がワクチンを接種することも、自身のがん予防と、パートナーへの感染を防ぐ上で有効です。
また、お互いの健康を守るために、コンドームの使用や、特定のパートナーとの信頼関係を築くことも大切です。
この記事では子宮の入り口にできる「子宮頸がん」について解説しました。一方で、子宮の奥、赤ちゃんが育つ本体部分にできる「子宮体がん」という別のがんも存在します。
子宮体がんは、閉経後の女性に多く、不正出血が主なサインとなるなど、子宮頸がんとは原因も好発年齢も異なります。
二つのがんの違いを正しく理解し、それぞれに応じた予防や検診の知識を持つことが、女性の健康を守る上でとても重要です。
子宮体がんについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
以上
参考文献
LEW, Jie-Bin, et al. Primary HPV testing versus cytology-based cervical screening in women in Australia vaccinated for HPV and unvaccinated: effectiveness and economic assessment for the National Cervical Screening Program. The Lancet Public Health, 2017, 2.2: e96-e107.
KJAER, Susanne K., et al. Real-world effectiveness of human papillomavirus vaccination against cervical cancer. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2021, 113.10: 1329-1335.
CHAN, Chee Kai, et al. Human papillomavirus infection and cervical cancer: epidemiology, screening, and vaccination—review of current perspectives. Journal of oncology, 2019, 2019.1: 3257939.
TAY, Kaijun; TAY, Sun K. The impact of cytology screening and HPV vaccination on the burden of cervical cancer. Asia‐Pacific Journal of Clinical Oncology, 2011, 7.2: 154-159.
EL-ZEIN, Mariam; RICHARDSON, Lyndsay; FRANCO, Eduardo L. Cervical cancer screening of HPV vaccinated populations: cytology, molecular testing, both or none. Journal of Clinical Virology, 2016, 76: S62-S68.
TEOH, Deanna, et al. Test performance of cervical cytology among adults with vs without human papillomavirus vaccination. JAMA Network Open, 2022, 5.5: e2214020-e2214020.
KIM, Jane J.; ORTENDAHL, Jesse; GOLDIE, Sue J. Cost-effectiveness of human papillomavirus vaccination and cervical cancer screening in women older than 30 years in the United States. Annals of internal medicine, 2009, 151.8: 538-545.
CANFELL, Karen, et al. Cervical screening with primary HPV testing or cytology in a population of women in which those aged 33 years or younger had previously been offered HPV vaccination: results of the Compass pilot randomised trial. PLoS medicine, 2017, 14.9: e1002388.
SIGURDSSON, K. Cervical cancer: cytological cervical screening in Iceland and implications of HPV vaccines. Cytopathology, 2010, 21.4: 213-222.
KIM, Jane J., et al. Optimal cervical cancer screening in women vaccinated against human papillomavirus. Journal of the National Cancer Institute, 2017, 109.2: djw216.
婦人科系がんに戻る