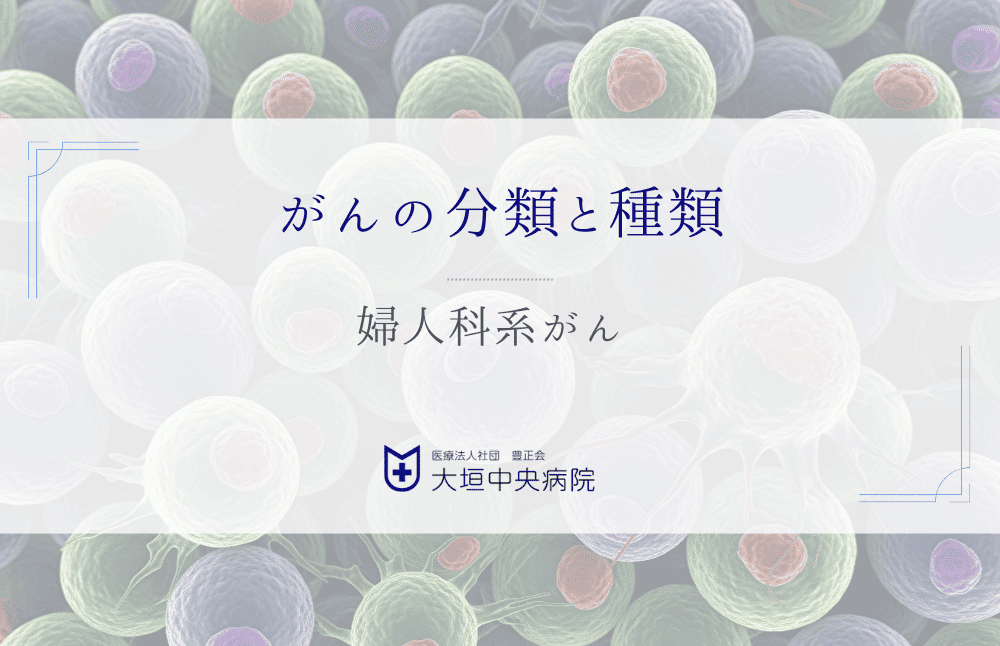婦人科系がんは、女性特有の臓器である子宮、卵巣、卵管、腟、外陰部に発生するがんの総称です。また、女性に多いがんとして乳がんも広く認識されています。
これらのがんは、女性のライフステージに深く関わるホルモンの影響を受けることが多く、それぞれに特徴的な原因、症状、治療法があります。
早期発見が治療成績を大きく左右するため、定期的な検診と自身の体への関心が重要です。
この記事では、代表的な婦人科系がんと乳がんについて、その基礎知識から検査、治療法までを分かりやすく解説し、がんと向き合う上での理解を深める手助けをします。
婦人科系がん - 基礎知識
女性の生殖機能に関わる臓器に発生するがんをまとめて婦人科系がんと呼びます。発生する部位によって、子宮体がんと子宮頸がん、卵巣がんなどに分類されます。
それぞれのがんは性質が異なり、リスク因子や好発年齢、進行の仕方にも違いが見られます。
女性ホルモンのバランスや特定のウイルス感染、遺伝的要因などが発症に関与することが知られており、正しい知識を持つことが予防と早期発見につながります。
婦人科系がんとは
婦人科系がんは、女性の骨盤内にある臓器に発生する悪性腫瘍です。
具体的には、子宮の内部(子宮体部)にできる子宮体がん、子宮の入り口(子宮頸部)にできる子宮頸がん、そして卵巣にできる卵巣がんが代表的です。
これらの臓器は妊娠や出産に深く関わるため、治療法を選択する際には、がんの根治を目指すことと、将来の妊娠・出産を希望するかどうか(妊よう性温存)を考慮する必要があります。
主な種類と特徴
子宮体がんは閉経後の女性に多く、不正性器出血が主な症状です。子宮頸がんは若い世代にも発症し、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が主な原因です。
卵巣がんは初期症状が出にくく、進行した状態で見つかることが多いという特徴があります。これらのがんは、定期的な検診によって早期に発見できる可能性があります。
婦人科系がんに共通するリスク因子
婦人科系がんには、それぞれ特有のリスク因子がありますが、共通する点も見られます。
例えば、肥満は子宮体がんのリスクを高めることが知られていますし、遺伝的な要因は卵巣がんや乳がんの発症に関わることがあります。
また、出産経験がないことや初経年齢が早いこと、閉経年齢が遅いことなど、女性ホルモンであるエストロゲンに長期間さらされることが、一部のがんのリスクを高める可能性があります。
早期発見の重要性
いずれの婦人科系がんも、早期に発見し治療を開始することが、良好な治療結果を得るために極めて重要です。特に子宮頸がんや乳がんは、検診による早期発見が有効であることが証明されています。
卵巣がんのように有効な検診方法が確立されていないがんもありますが、体に異変を感じた際には、ためらわずに婦人科を受診することが大切です。
「いつもと違う」という感覚を無視しないようにしましょう。
主な婦人科系がんの比較
| がんの種類 | 好発年齢 | 主な原因・リスク因子 |
|---|---|---|
| 子宮体がん | 50-60代 | エストロゲンの長期的な刺激、肥満、糖尿病など |
| 子宮頸がん | 20-40代 | ヒトパピローマウイルス(HPV)の持続感染 |
| 卵巣がん | 40-60代 | 遺伝的要因、出産経験がないことなど |
子宮体がん - 子宮内膜から発生するがん
子宮体がんは、子宮の奥にある体部の内側を覆う「子宮内膜」という組織から発生します。そのため、子宮内膜がんとも呼ばれます。
閉経期前後の女性に多く見られ、近年、食生活の欧米化やライフスタイルの変化に伴い、日本でも増加傾向にあります。
幸い、比較的早期に発見されやすいがんの一つであり、不正性器出血という分かりやすいサインが現れることが多いのが特徴です。
子宮体がんの原因
子宮体がんの発生には、女性ホルモンの一つであるエストロゲン(卵胞ホルモン)が深く関わっています。
エストロゲンが子宮内膜を増殖させる働きを持つのに対し、もう一つの女性ホルモンであるプロゲステロン(黄体ホルモン)は増殖を抑える働きをします。
この二つのホルモンのバランスが崩れることが、発症の引き金になると考えられています。
エストロゲンとの関連
出産経験がない、閉経が遅い、肥満、月経不順といった状態は、体内のエストロゲン濃度が高い状態を長く維持することにつながります。これにより、子宮内膜が過剰に増殖し、がん化するリスクが高まります。
特に、閉経後に脂肪組織でエストロゲンが作られるため、肥満は重要なリスク因子です。
その他のリスク因子
ホルモン補充療法の中でエストロゲン単独の治療を受けている場合や、乳がんの治療薬であるタモキシフェンを服用している場合も、子宮体がんのリスクが上がることが知られています。
また、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を持つ人や、遺伝的にがんになりやすい体質(リンチ症候群など)の人も注意が必要です。
主な症状
子宮体がんの最も代表的な症状は、不正性器出血です。特に閉経後に少量の出血が続く場合は、注意深く観察し、速やかに医療機関を受診することが大切です。
閉経前であっても、月経不順や月経時以外の出血、長引く月経などが見られる場合は、検査を受けることを推奨します。
不正性器出血
子宮体がん患者の約90%が不正性器出血を経験します。
閉経後に出血があった場合はもちろん、閉経前でも月経の量が増えたり、期間が長引いたり、月経と無関係な出血があったりした場合には、婦人科を受診してください。
おりものに血が混じる、茶褐色のおりものが出る、といった症状もサインの一つです。
検査と診断
不正性器出血などの症状がある場合、婦人科で検査を行います。まずは問診で症状や既往歴などを詳しく聞き、内診や超音波(エコー)検査で子宮や卵巣の状態を調べます。
子宮体がんが疑われる場合には、確定診断のために子宮内膜の組織を採取する検査が必要です。
検査の流れ
| 検査段階 | 検査内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 初期検査 | 問診、内診、経腟超音波検査 | 子宮内膜の厚さや子宮・卵巣の異常を確認 |
| 確定診断 | 子宮内膜組織診(細胞診・組織診) | 子宮内膜の細胞や組織を採取し、がん細胞の有無を顕微鏡で調べる |
| 進行度診断 | CT検査、MRI検査、PET検査 | がんの広がりや転移の有無を調べる |
治療法
子宮体がんの治療は、がんの進行度(ステージ)、組織型(がんの顔つき)、患者の年齢や全身状態などを総合的に判断して決定します。
治療の基本は手術であり、がんが子宮にとどまっている早期の段階であれば、手術だけで治癒を目指せることも少なくありません。
手術療法
基本的な手術は、子宮、両側の卵巣・卵管を摘出する「単純子宮全摘出術・両側付属器切除術」です。がんの広がりによっては、骨盤内や傍大動脈のリンパ節も切除(リンパ節郭清)することがあります。
近年では、患者の体への負担が少ない腹腔鏡下手術やロボット支援下手術も広く行われるようになっています。
放射線療法と薬物療法
手術が難しい場合や、手術後の再発リスクが高いと判断された場合には、放射線療法や薬物療法(化学療法、ホルモン療法)を追加します。
放射線療法は、骨盤内に放射線を照射してがん細胞を攻撃する治療です。薬物療法は、抗がん剤やホルモン剤を用いて、全身に広がった可能性のあるがん細胞を治療します。
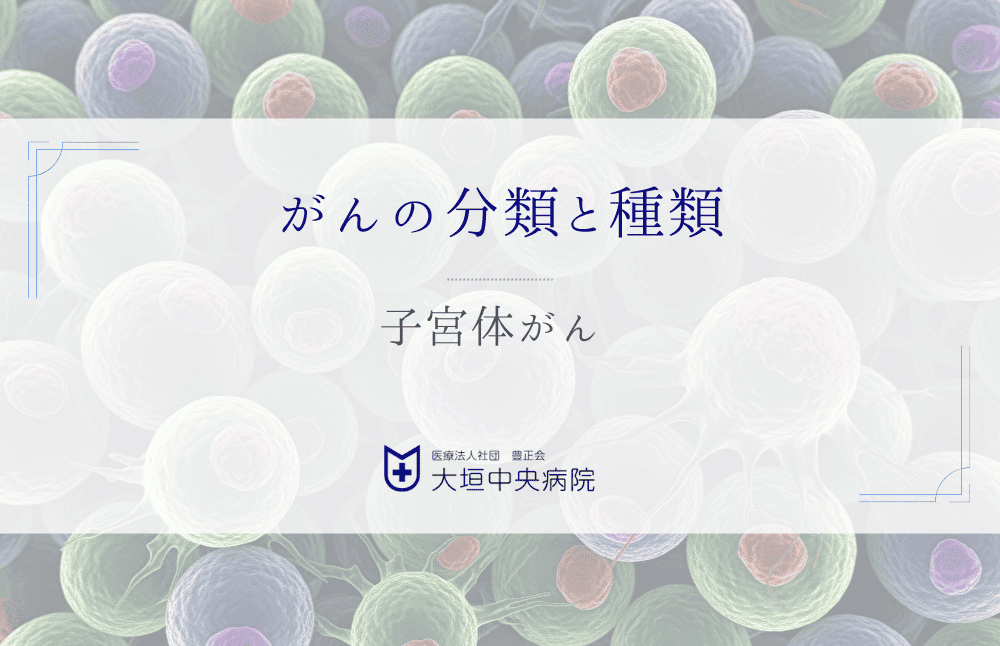
子宮頸がん - 若い世代にも多いがん
子宮頸がんは、子宮の入り口部分である子宮頸部に発生するがんです。
かつては40-50代に多いがんでしたが、近年では20-30代の若い女性にも増加しており、日本では年間約1万1000人が診断され、約2900人が命を落としています。
しかし、子宮頸がんは原因がほぼ解明されており、予防や早期発見が可能ながんでもあります。
子宮頸がんの原因
子宮頸がんの発生には、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスが深く関わっています。HPVは性交渉によって感染するごくありふれたウイルスで、多くの女性が一生に一度は感染すると言われています。
感染しても、ほとんどの場合は自己の免疫力によって自然に排除されます。
HPV(ヒトパピローマウイルス)感染
HPVには多くの型がありますが、そのうちの特定のハイリスク型HPVが長期間にわたって感染し続ける(持続感染)と、子宮頸部の細胞が異常な形に変化(異形成)し、数年から十数年かけてがんに進行することがあります。
喫煙は、HPVの排除を妨げ、がんへの進行を助ける要因となるため、禁煙が重要です。
症状と進行
子宮頸がんは、初期の段階では自覚症状がほとんどありません。そのため、症状がないからといって安心はできず、定期的な検診が非常に重要になります。
がんが進行すると、不正性器出血や性交渉時の出血、普段と違うおりものなどの症状が現れることがあります。
初期症状はほとんどない
がんになる前の「異形成」や、ごく初期のがん(上皮内がん)の段階では、痛みや出血などの症状は全くないことが普通です。
この段階で発見できれば、子宮を温存し、体への負担が少ない治療で治癒を目指すことが可能です。だからこそ、症状が出る前に検診で発見することが大切なのです。
進行した場合の症状
がんが進行し、周囲の組織に広がると、様々な症状が現れます。性交渉の際の出血、月経以外の不正出血、濃い茶色や膿のようなおりものの増加などが見られます。
さらに進行すると、下腹部痛や腰痛、足のむくみ、血尿などが現れることもあります。これらの症状がある場合は、すぐに婦人科を受診してください。
予防と検診
子宮頸がんは、原因となるHPV感染を予防すること、そして検診によってがんになる前の段階で発見することで、防ぐことができるがんです。
予防と検診の両方について、正しい知識を持つことが自分の体を守る上で必要です。
HPVワクチン
HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となるハイリスク型HPVのうち、特に重要な型への感染を防ぐ効果があります。
性交渉を経験する前に接種することが最も効果的とされていますが、その後でも一定の効果は期待できます。
ワクチンは感染を予防するものであり、すでに感染しているウイルスを排除したり、発症した異形成やがんを治療したりする効果はありません。
子宮頸がん検診
子宮頸がん検診では、子宮頸部の細胞をブラシなどでこすり取り、異常な細胞がないかを顕微鏡で調べます(細胞診)。痛みはほとんどなく、短時間で終わる検査です。
日本では20歳以上の女性に、2年に1回の検診を推奨しています。検診で異常が見つかった場合は、精密検査を行い、必要に応じて治療を開始します。
進行度(ステージ)と治療法の選択肢
| 進行度(ステージ) | がんの広がり | 主な治療法 |
|---|---|---|
| 0期(上皮内がん) | がんが頸部の上皮内にとどまる | 円錐切除術など(子宮温存可能) |
| I期 | がんが子宮頸部にとどまる | 手術(広汎子宮全摘出術)、放射線療法 |
| II期以降 | がんが子宮頸部を超えて広がる | 放射線療法と化学療法の同時併用、薬物療法 |
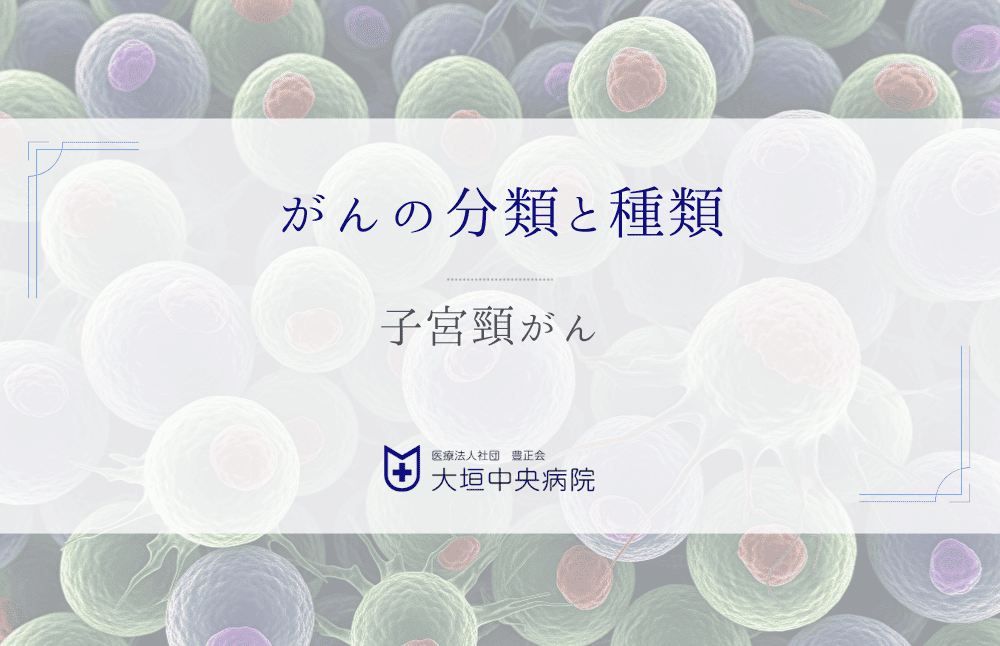
卵巣がん - 静かに進行するがん
卵巣がんは、卵子を作り、女性ホルモンを分泌する卵巣に発生するがんです。
卵巣は骨盤の深い部分に位置するため、腫瘍がある程度の大きさになるまで症状が出にくく、早期発見が難しいがんの一つとして知られています。
「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」とも呼ばれ、進行した状態で見つかることが多いのが特徴です。
卵巣がんの特徴
卵巣がんには、発生する組織の由来によっていくつかの種類(組織型)があり、それぞれ性質が異なります。進行が比較的ゆっくりなタイプから、急速に増殖して広がるタイプまで様々です。
また、腹腔内(お腹の中)にがん細胞が散らばりやすい(腹膜播種)という性質を持っています。
サイレントキラーと呼ばれる理由
卵巣は沈黙の臓器とも言われ、初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。
お腹の張りや食欲不振、頻尿といった症状が出ることがありますが、これらは他の病気でもよく見られる症状のため、がんとは気づかずに見過ごされがちです。
症状を自覚して受診したときには、すでにがんが進行しているケースが少なくありません。
リスク因子
卵巣がんの明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかのリスク因子が知られています。特に遺伝的な要因が他の婦人科系がんに比べて大きいと考えられています。
生活習慣との関連については、はっきりとした結論は出ていません。
遺伝的要因とその他の要因
血縁者に乳がんや卵巣がんになった人がいる場合、卵巣がんの発症リスクが高まることがあります。
特に、BRCA1またはBRCA2という遺伝子に変異があると、リスクが著しく高まることがわかっています(遺伝性乳がん卵巣がん症候群)。
その他のリスク因子としては、出産経験がないこと、子宮内膜症にかかったことがあることなどが挙げられます。一方、経口避妊薬(ピル)の服用は、卵巣がんのリスクを下げることが知られています。
主な症状
卵巣がんの症状は、非特異的で曖昧なものが多く、早期発見をさらに難しくしています。
しかし、これまでになかった症状が続いたり、徐々に悪化したりする場合には注意が必要です。自身の体の小さな変化に気づくことが重要です。
初期症状の乏しさ
初期には症状がないことがほとんどです。腫瘍が大きくなるにつれて、下腹部にしこりを感じたり、お腹が張る感じ(腹部膨満感)がしたり、食欲がなくなったりすることがあります。
ウエストがきつくなったと感じることもあります。
進行に伴う症状
がんが進行し、腹水がたまると、お腹が大きく膨れてきます。また、腫瘍が周囲の膀胱や直腸を圧迫することで、頻尿や便秘といった症状も現れます。
さらに進行すると、息切れや胸の痛み、体重減少などが見られることもあります。
検査と治療
お腹の張りなどの症状で受診した場合、問診、内診、経腟超音波検査などを行います。
これらの検査で卵巣の腫れが確認され、がんが疑われる場合には、CTやMRIなどの画像検査や腫瘍マーカー(血液検査)を追加して、より詳しく調べます。
診断に用いる主な検査
| 検査の種類 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 画像検査(超音波、CT、MRI) | 体の断面を撮影する | 腫瘍の大きさ、形状、広がりを確認する |
| 腫瘍マーカー(血液検査) | 血液中のがん関連物質を測定する | がんの存在や種類の推定、治療効果の判定の補助とする |
| 手術(試験開腹) | お腹を開けて組織を採取する | がんの確定診断と進行度を決定する |
治療の基本方針
卵巣がんの治療は、手術と薬物療法(化学療法)を組み合わせて行うのが基本です。まず手術で、がんを可能な限り取り除きます。同時に、がんの広がりを正確に診断します。
手術後は、体内に残っている可能性のある微小ながん細胞をたたくために、抗がん剤による化学療法を行います。
近年では、特定の遺伝子変異を持つがんに対して、分子標的薬という新しいタイプの薬も使われるようになっています。
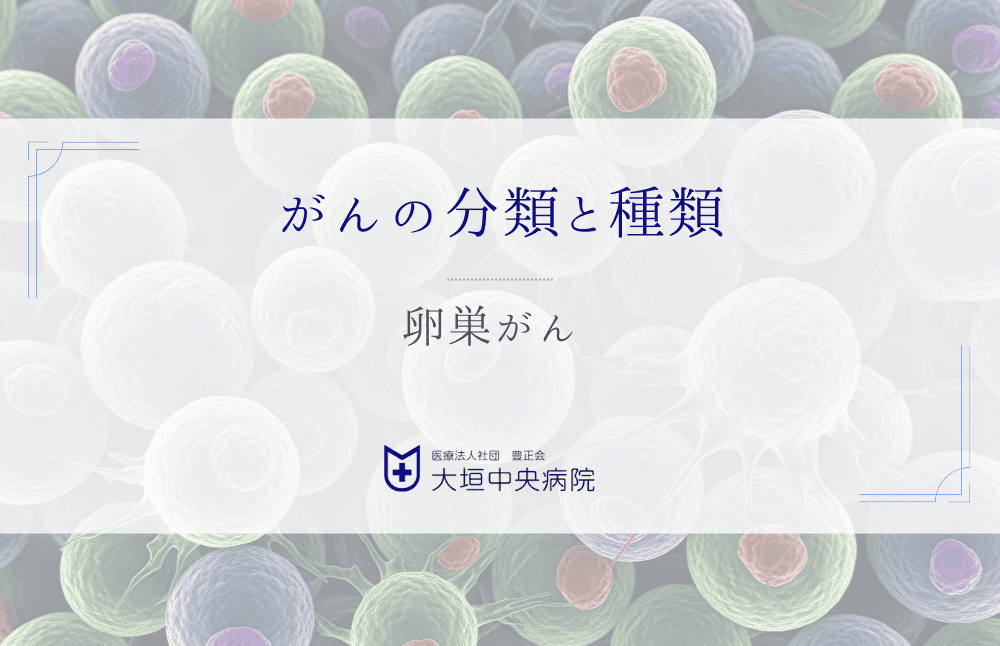
乳がん - 女性が最もかかりやすいがん
乳がんは、乳房にある乳腺の組織に発生するがんです。日本人女性のがんの中で最も罹患数が多く、9人に1人が生涯のうちに乳がんにかかると言われています。
30代から増加し始め、40代後半から60代後半にピークを迎えますが、どの年代の女性にとっても注意が必要ながんです。
早期に発見すれば治癒率が非常に高いがんであり、自己検診と定期的な検診が鍵となります。
乳がんの基礎知識
乳がんの多くは、母乳を運ぶ管である乳管から発生します(乳管がん)。一部は、母乳を作る小葉から発生します(小葉がん)。
乳がんは、女性ホルモンの影響を受けて増殖するタイプ(ホルモン受容体陽性乳がん)や、特定のタンパク質(HER2)が多く発現しているタイプなど、いくつかの性質(サブタイプ)に分類され、その性質に合わせた治療法が選択されます。
日本人女性に最も多いがん
食生活の欧米化、晩婚化、出産数の減少など、ライフスタイルの変化が乳がんの増加に関係していると考えられています。
乳がんは女性にとって非常に身近な病気であり、他人事と考えずに、正しい知識を持って向き合うことが大切です。家族や親しい友人が乳がんにかかったという経験を持つ人も少なくないでしょう。
主な症状
乳がんの最も多い症状は、乳房のしこりです。痛みは伴わないことがほとんどです。
しこり以外にも、乳房の皮膚や乳頭に変化が現れることがあります。月に一度の自己検診(セルフチェック)を習慣にし、普段の自分の乳房の状態を知っておくことで、小さな変化にも気づきやすくなります。
自己検診で気づく変化
鏡の前で乳房の形やひきつれがないかを確認したり、入浴時に石鹸のついた手で触れてしこりがないかを確認したりする方法があります。
以下のような変化に気づいたら、すぐに乳腺外科や乳腺クリニックを受診してください。
- しこりや硬い部分がある
- 乳頭から血液の混じった分泌物が出る
- 乳房の皮膚にひきつれ、くぼみ、ただれがある
- 乳頭がへこむ、陥没する
リスク因子
乳がんの発症には、女性ホルモンであるエストロゲンが深く関わっています。エストロゲンにさらされる期間が長いほど、リスクは高まります。
また、生活習慣や遺伝的要因も発症に影響を与えることが知られています。
女性ホルモンと生活習慣
初経年齢が早い、閉経年齢が遅い、出産経験がない、初産年齢が高いといったことは、リスクを高める要因です。また、閉経後の肥満、飲酒習慣、運動不足などもリスクを上げることがわかっています。
一方、授乳経験はリスクを下げるとされています。血縁者に乳がんになった人がいる場合も、リスクが高くなることがあります。
検査と診断
乳がん検診や、しこりなどの症状で受診した場合、まずは問診と視触診を行います。その後、マンモグラフィ(乳房X線検査)や超音波(エコー)検査などの画像検査で詳しく調べます。
これらの検査でがんが疑われた場合は、確定診断のために、しこりの一部を針で採取して調べる生検(組織診)が必要です。
乳がん検診の種類
| 検査方法 | 対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| マンモグラフィ | 40歳以上(国の指針) | 乳房を圧迫してX線撮影。微細な石灰化の発見に優れる。 |
| 超音波(エコー)検査 | 全年齢(特に若年層) | 超音波で乳腺内部を観察。高濃度乳腺(デンスブレスト)でのしこりの発見に優れる。 |
| 生検(組織診・細胞診) | がんが疑われる場合 | 針で組織や細胞を採取し、顕微鏡でがん細胞の有無を確定させる。 |
治療法の選択
乳がんの治療は、手術、放射線療法、薬物療法(ホルモン療法、化学療法、分子標的薬)を組み合わせて行います。
がんの性質(サブタイプ)、進行度、患者の年齢や希望などを考慮して、一人ひとりに合った治療計画を立てます。これを個別化治療と呼びます。
個別化治療の考え方
手術では、がんの大きさや場所に応じて、乳房を部分的に切除する方法(乳房温存手術)や、すべてを切除する方法(乳房全切除術)があります。
乳房を全切除した場合でも、同時にまたは後日、乳房を再建することが可能です。手術後は、再発を防ぐために放射線療法や薬物療法を追加することが一般的です。
治療法の選択肢は多岐にわたるため、医師とよく相談し、納得して治療に臨むことが重要です。
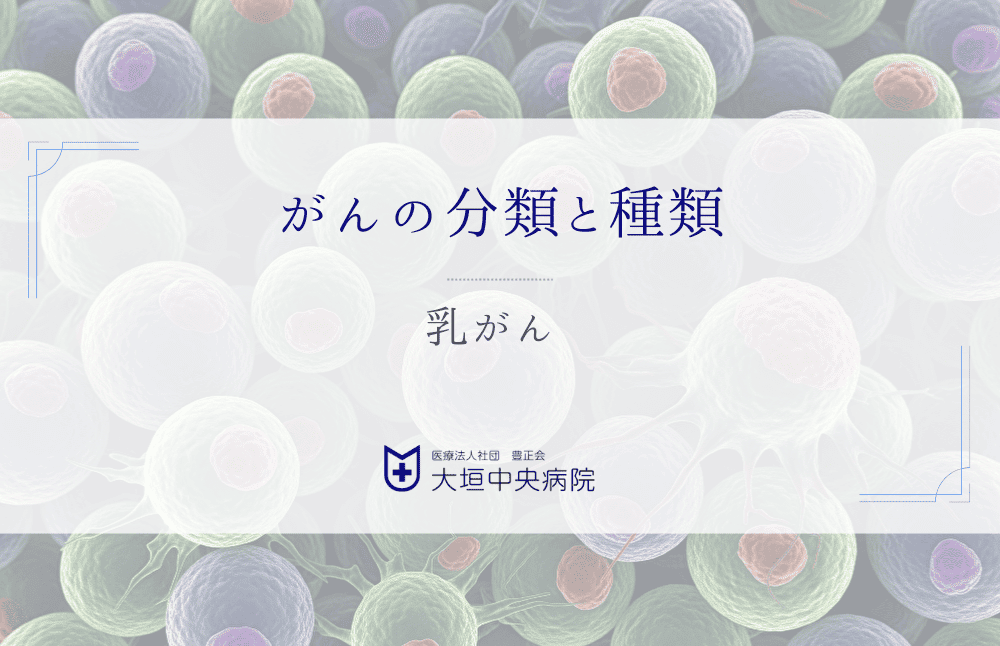
よくある質問
がんと診断されたとき、あるいはがんについて知ろうとするとき、多くの疑問や不安が浮かぶことでしょう。ここでは、婦人科系がんや乳がんに関して多く寄せられる質問とその回答をまとめました。
正しい情報を得ることが、不安を和らげ、前向きに治療に取り組むための第一歩となります。
- 婦人科系がんの検診は何歳から受けるべきですか?
-
がんの種類によって推奨される開始年齢は異なります。子宮頸がん検診は、国の指針では20歳以上の女性が対象です。2年に1回の受診が推奨されています。
子宮体がんについては、すべての人を対象とした有効な検診方法は確立されていませんが、不正性器出血など気になる症状があれば、年齢に関わらず速やかに婦人科を受診してください。
特に閉経後は注意が必要です。
- 遺伝とがんの関係について教えてください
-
すべてのがんが遺伝するわけではありませんが、一部のがんでは遺伝的な要因が強く関わっていることがわかっています。
婦人科系がんや乳がんでは、血縁者に同じ病気の方が複数いる場合、遺伝性のがんの可能性があります。代表的なものに「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)」があります。
心配な方は、遺伝カウンセリングを実施している医療機関に相談することをお勧めします。
- 治療中の生活で気をつけることはありますか?
-
治療法によって注意点は異なりますが、一般的にはバランスの取れた食事、十分な休息、無理のない範囲での運動が大切です。
治療の副作用で体力が落ちたり、食欲がなくなったりすることもありますので、主治医や看護師、栄養士に相談しながら、自分に合った生活ペースを見つけましょう。
感染症予防のために、手洗いやうがいを心がけることも重要です。
- がんと診断された後の心のケアはどうすればよいですか?
-
がんの診断は、誰にとっても大きな衝撃です。不安や落ち込み、怒りなど、様々な感情が湧き上がるのは自然なことです。一人で抱え込まず、家族や信頼できる友人に気持ちを話してみましょう。
また、多くの病院には、がん患者さんやそのご家族の相談に乗る「がん相談支援センター」が設置されています。
専門の相談員や臨床心理士が、心のつらさや生活上の悩みについて一緒に考えてくれますので、ぜひ活用してください。
- 婦人科系がん検診はどのくらいの頻度で受ければよいですか?
-
推奨される検診の頻度は、がんの種類や年齢によって異なります。子宮頸がん検診は、多くの自治体で20歳以上の女性を対象に2年に1回の受診を推奨しています。
子宮体がんと卵巣がんには、国が推奨する確立された検診方法はありませんが、不正出血などの気になる症状がある場合や、リスク因子がある場合は、年齢にかかわらず速やかに婦人科を受診することが大切です。
定期的に婦人科のかかりつけ医を持ち、自身の状況に合わせて相談するのがよいでしょう。
- 治療による副作用にはどのようなものがありますか?
-
治療法によって副作用は様々です。手術では、術後の痛みや出血、感染のリスクがあります。
また、卵巣を摘出すると女性ホルモンが欠乏し、更年期障害のような症状(ほてり、発汗、気分の落ち込みなど)が現れることがあります。
放射線治療では、治療部位に応じて皮膚の炎症や、下痢、排尿障害などが起こることがあります。
薬物療法(化学療法)では、吐き気、脱毛、口内炎、倦怠感、白血球減少による感染症のリスク増加などが代表的な副作用です。
これらの副作用を和らげるための支持療法も進歩していますので、つらい症状は我慢せず医療スタッフに相談することが重要です。
- 遺伝性のがんが心配です。何をすればよいですか?
-
血縁者の中に、若くして乳がんや卵巣がんになった人が複数いる場合などは、遺伝性の要因が関わっている可能性があります。
特に「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)」が知られています。心配な場合は、遺伝カウンセリングや遺伝子検査を実施している医療機関に相談することをお勧めします。
遺伝カウンセリングでは、専門家が遺伝に関する正確な情報を提供し、心理的なサポートを行いながら、遺伝子検査を受けるかどうかを一緒に考えてくれます。
検査を受けることで、ご自身の将来のリスクを知り、予防的な対策(リスク低減手術など)や、より頻繁な検診を検討することができます。
- 治療後、妊娠・出産は可能ですか?
-
がんの種類、進行度、治療法によって、妊娠・出産の可能性(妊よう性)は大きく異なります。
子宮頸がんのごく初期であれば、子宮を温存する円錐切除術で治療でき、その後の妊娠も可能です。
子宮体がんや卵巣がんでも、特定の条件を満たす早期のがんであれば、子宮や片方の卵巣を残す「妊よう性温存治療」を選択できる場合があります。
ただし、この治療には適応基準があり、再発のリスクなども考慮して慎重に判断する必要があります。
治療を開始する前に、将来子どもを持つことを希望している場合は、その意思をはっきりと担当医に伝え、妊よう性温存の可能性について十分に話し合うことが大切です。
この記事では、女性ホルモンと関連の深い婦人科系がんと乳がんについて解説しました。
ホルモンは私たちの体の機能を正常に保つために重要な役割を果たしますが、そのバランスが崩れると、がんの発生リスクに影響を与えることがあります。
甲状腺や副腎、下垂体といった内分泌器官に発生する「内分泌系がん」も、ホルモンとの関連が指摘されるがんの一つです。これらの臓器は全身のホルモンバランスを司る重要な役割を担っています。
もし、ホルモンとがんの関連性についてさらに理解を深めたい場合は、内分泌系がんに関する記事もあわせてお読みになることをお勧めします。
婦人科系がんと同様に、女性の体と健康に深く関わるのが「乳がん」です。
乳がんは日本人女性が最もかかりやすいがんであり、その発生には女性ホルモンが関与している点で、一部の婦人科系がんとも共通点があります。
また、遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)のように、乳がんと卵巣がんの発症リスクが連動する場合もあります。
ご自身の体を総合的に理解し、健康を守るためには、婦人科系がんだけでなく、乳がんについても正しい知識を持つことがとても重要です。
乳がんのセルフチェックの方法や検診、治療法についてまとめた記事も、ぜひ併せてお読みください。
以上
参考文献
GHOSH, Anirbita, et al. Gynaecologic cancers: an outline of the symptoms, risk factors and the treatment options to make women aware. World J. Pharm. Res, 2020, 9.7: 952-970.
STEWART, Christine; RALYEA, Christine; LOCKWOOD, Suzy. Ovarian cancer: an integrated review. In: Seminars in oncology nursing. WB Saunders, 2019. p. 151-156.
GOLIA D'AUGE, Tullio, et al. Prevention, screening, treatment and follow-up of gynecological cancers. State of art and future perspectives. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 2023, 50.8: 1-8.
KWOLEK, Deborah Gomez, et al. Ovarian, uterine, and vulvovaginal cancers: screening, treatment overview, and prognosis. Medical Clinics, 2023, 107.2: 329-355.
KEYVANI, Vahideh, et al. Epidemiological trends and risk factors of gynecological cancers: an update. Medical Oncology, 2023, 40.3: 93.
BARAL, Sumit Kumar, et al. A comprehensive discussion in vaginal cancer based on mechanisms, treatments, risk factors and prevention. Frontiers in Oncology, 2022, 12: 883805.
LIBERTO, Juliane M., et al. Current and emerging methods for ovarian cancer screening and diagnostics: a comprehensive review. Cancers, 2022, 14.12: 2885.
BOON, Siaw Shi, et al. Review of the standard and advanced screening, staging systems and treatment modalities for cervical cancer. Cancers, 2022, 14.12: 2913.
ADAMS, Tracey S.; ROGERS, Linda J.; CUELLO, Mauricio A. Cancer of the vagina: 2021 update. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2021, 155: 19-27.
LEDFORD, Leah Rc; LOCKWOOD, Suzy. Scope and epidemiology of gynecologic cancers: an overview. In: Seminars in oncology nursing. WB Saunders, 2019. p. 147-150.