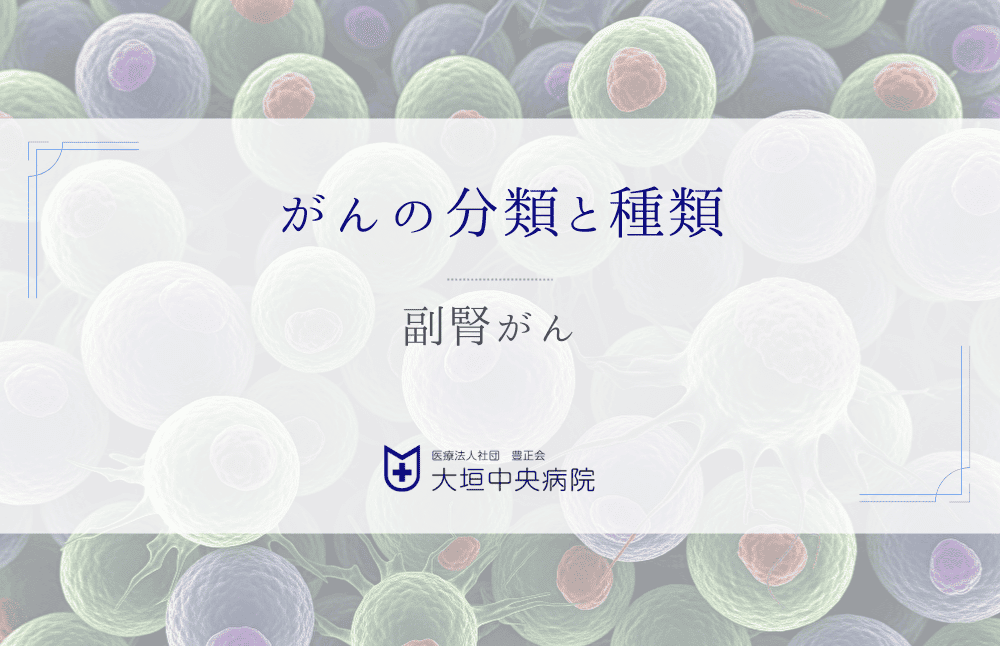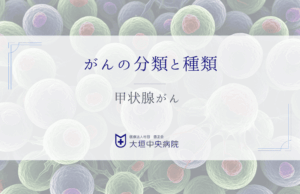副腎がんは、腎臓の上にある「副腎」という小さな臓器に発生する悪性の腫瘍です。100万人に1人程度と非常に稀な「希少がん」の一種であり、情報が少なく不安を感じる方も多いかもしれません。
このがんは、体に必要なホルモンを過剰に作り出すことで、高血圧や肥満など様々な症状を引き起こすタイプと、ホルモンを作らずに腫瘍が大きくなることで発見されるタイプがあります。
この記事では、副腎がんの基本的な情報から、症状、原因、検査、そして手術やミトタンを用いた治療法まで、患者さんが知りたい情報を分かりやすく解説します。
副腎がんの概要と発症頻度
副腎がんは、その希少性から多くの人にとって馴染みの薄い病気かもしれません。しかし、体内のホルモンバランスを司る重要な臓器に発生するため、その影響は全身に及びます。
ここでは、副腎という臓器の働きから、副腎がんがどのような病気であるか、そしてどのくらいの頻度で発生するのかという基本的な知識を解説します。
副腎とはどのような臓器か
副腎は、左右の腎臓の上に乗っている、重さ5グラムほどの小さな臓器です。小さいながらも、生命維持に欠かせない様々なホルモンを分泌する重要な内分泌器官です。
副腎は、外側の「皮質」と内側の「髄質」という二つの部分から構成されており、それぞれ異なるホルモンを産生しています。
副腎から分泌される主なホルモンとその働き
| 産生部位 | ホルモンの種類 | 主な働き |
|---|---|---|
| 副腎皮質 | コルチゾール | ストレス対応、血糖値の上昇、抗炎症作用 |
| 副腎皮質 | アルドステロン | 血圧の調節、体内の塩分・水分バランスの維持 |
| 副腎皮質 | 性ホルモン(アンドロゲン・エストロゲン) | 第二次性徴の発現など |
| 副腎髄質 | カテコールアミン(アドレナリンなど) | 心拍数の増加、血圧の上昇 |
副腎がん(副腎皮質がん)とは
一般的に「副腎がん」という場合、その多くは副腎の皮質から発生する「副腎皮質がん」を指します。
副腎皮質がんは悪性腫瘍であり、周囲の組織に浸潤したり、肺や肝臓などの他の臓器に転移したりする性質を持っています。
このがんは、ホルモンを過剰に産生する「機能性腫瘍」と、ホルモンを産生しない「非機能性腫瘍」に分けられます。
希少がんとしての位置づけ
副腎皮質がんは、がんの中でも特に発生頻度が低い「希少がん」に分類されます。そのため、診断や治療の経験が豊富な医療機関が限られており、専門的な知識を持つ医師による診療が重要になります。
患者数が少ないことから、治療法の開発や臨床試験の実施が難しいという課題も抱えています。
発症頻度と生存率の概観
副腎皮質がんの発生頻度は、年間100万人に1~2人程度と報告されており、非常に稀です。発症年齢は二つのピークがあり、10歳未満の小児と40~50代の成人に多く見られます。
生存率は、がんの進行度(ステージ)によって大きく異なります。腫瘍が副腎内にとどまっている早期の段階で発見され、手術で完全に取り除くことができれば、良好な経過を期待できます。
しかし、発見時にすでに他の臓器へ転移している場合、治療は困難を伴います。正確な生存率については、個々の患者さんの状態によって変わるため、主治医とよく相談することが大切です。
副腎がんの主な症状とホルモン異常による影響
副腎がんの症状は、ホルモンを産生するかどうかによって大きく異なります。ホルモン産生腫瘍の場合は、過剰に分泌されるホルモンの種類に応じた多彩な症状が全身に現れます。
一方、ホルモン非産生腫瘍では、がん自体が大きくなるまで症状が出にくく、発見が遅れる傾向があります。
ホルモン産生腫瘍の症状
副腎皮質がんの約60%は、何らかのホルモンを過剰に産生する機能性腫瘍です。これにより、体に様々な変化が引き起こされます。
クッシング症候群(コルチゾール過剰)
最も多く見られるのが、コルチゾールの過剰分泌によるクッシング症候群です。
特徴的な身体的変化として、顔が丸くなる「満月様顔貌(ムーンフェイス)」、首の後ろや肩周りに脂肪がつく「バッファローハンプ」、お腹周りを中心に脂肪がつく「中心性肥満」などがあります。
また、皮膚が薄くなってあざができやすくなったり、腹部に赤い筋(赤色皮膚線条)が現れたりすることもあります。高血圧や高血糖、骨粗しょう症、気分の落ち込みなども引き起こします。
男性化・女性化症状(性ホルモン過剰)
性ホルモンが過剰に産生されると、性別に合わない身体的特徴が現れることがあります。
女性でアンドロゲン(男性ホルモン)が過剰になると、声が低くなる、体毛が濃くなる(多毛)、月経不順、にきびなどの男性化症状が見られます。
一方、男性でエストロゲン(女性ホルモン)が過剰になると、乳房が女性のように膨らむ(女性化乳房)などの症状が現れます。
アルドステロン症(アルドステロン過剰)と高血圧
アルドステロンが過剰に分泌されると、体内にナトリウムと水分が溜まり、カリウムが排出されやすくなります。その結果、治療抵抗性の高血圧が生じます。
通常の降圧薬では血圧が下がりにくいのが特徴です。また、血液中のカリウム濃度が低下することで、筋力低下や手足のしびれなどが起こることもあります。
ホルモン過剰による主な症状
| 過剰なホルモン | 主な症状 | 関連する病態 |
|---|---|---|
| コルチゾール | 中心性肥満、満月様顔貌、高血圧、高血糖 | クッシング症候群 |
| アンドロゲン | 多毛、声の低音化、月経不順(女性) | 男性化症状 |
| アルドステロン | 治療抵抗性の高血圧、低カリウム血症 | 原発性アルドステロン症 |
ホルモン非産生腫瘍の症状
ホルモンを産生しない非機能性腫瘍の場合、初期には自覚症状がほとんどありません。腫瘍がかなり大きくなってから、周囲の臓器を圧迫することによる症状で気づかれることが多くなります。
腫瘍増大による腹痛や腹部膨満感
腫瘍が大きくなると、お腹の張り(腹部膨満感)や腹痛、腰痛を感じることがあります。食欲不振や吐き気を伴うこともあります。
他の病気の検査で腹部のCTなどを撮影した際に、偶然発見される「偶発腫瘍」として見つかるケースも少なくありません。
症状から考える受診の目安
急激な体重増加、なかなか治らない高血圧、原因不明の体毛の変化など、上記の症状に心当たりがある場合は、内分泌内科や専門の医療機関を受診することを検討してください。
特に、複数の症状が同時に現れている場合は注意が必要です。腹痛やお腹の張りが続く場合も、消化器内科やかかりつけ医に相談しましょう。
副腎がんの原因と関係がある要因
副腎がんがなぜ発生するのか、その明確な原因はまだ解明されていません。しかし、いくつかの遺伝的な要因が発症リスクを高めることが知られています。
ここでは、副腎がんの原因として現在考えられていることや、関連が指摘されている要因について解説します。
副腎がんの明確な原因
ほとんどの副腎皮質がんは、特定の原因がなく偶発的に発生する「散発性」です。現時点では、特定の生活習慣や環境因子が直接的な原因となって発症するという明確な証拠は見つかっていません。
原因特定の難しさと現状
副腎がんが希少がんであることが、原因究明を難しくしている一因です。症例数が少ないため、大規模な疫学研究を行うことが困難であり、発症に至る詳細な仕組みの解明は今後の研究課題となっています。
がん細胞の遺伝子変異に関する研究が進んでおり、将来的には発症の仕組み解明につながることが期待されます。
遺伝的要因と関連疾患
副腎皮質がんの一部は、特定の遺伝性疾患の一症状として発症することがあります。家族に同じような病気の方がいる場合や、若年で発症した場合には、遺伝的要因が関わっている可能性を考慮します。
関連する可能性のある遺伝性疾患
- リー・フラウメニ症候群
- ベックウィズ・ヴィーデマン症候群
- 多発性内分泌腫瘍症1型(MEN1)
- リンチ症候群
リー・フラウメニ症候群など
特に有名なのが「リー・フラウメニ症候群」です。
これは、がん抑制遺伝子であるTP53遺伝子の生まれつきの変異が原因で、副腎皮質がんのほか、乳がんや脳腫瘍、肉腫など、様々な種類のがんを若いうちから発症しやすい体質です。
遺伝的要因が疑われる場合には、遺伝カウンセリングを受け、遺伝子検査について相談することも選択肢の一つです。
生活習慣との関連性
現段階で、喫煙、飲酒、食事といった特定の生活習慣が副腎皮質がんのリスクを直接高めるという科学的根拠は確立されていません。
しかし、がん予防の観点から、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙など、健康的な生活習慣を心がけることは、あらゆる病気の予防にとって重要です。
副腎がんの検査方法と診断の流れ
副腎がんが疑われる場合、診断を確定するためにいくつかの検査を段階的に行います。ホルモン異常の有無を調べる血液検査や尿検査、そして腫瘍の場所や大きさを特定する画像検査が中心となります。
これらの検査結果を総合的に評価して、診断を下します。
診断のための初期検査
まずは、問診で自覚症状や既往歴、家族歴などを詳しく聞き取ります。その後、身体診察で血圧測定や、クッシング症候群に特徴的な身体所見がないかなどを確認します。
血液検査・尿検査によるホルモン測定
副腎がんの診断において、ホルモン検査は極めて重要です。血液や尿を採取し、副腎皮質から分泌されるコルチゾール、アルドステロン、性ホルモン(DHEA-Sなど)の値を測定します。
これにより、腫瘍がホルモンを産生しているか(機能性か)、産生している場合はどのホルモンが過剰なのかを評価します。
ホルモンの分泌は1日のうちで変動するため、24時間分の尿を溜めて測定する蓄尿検査も行います。
主なホルモン検査項目
| 検査の種類 | 主な測定項目 | 目的 |
|---|---|---|
| 血液検査 | コルチゾール、ACTH、レニン、アルドステロン、DHEA-S | 各ホルモンの血中濃度を測定する |
| 尿検査 | 尿中遊離コルチゾール、17-KS、17-OHCS | 1日のホルモン総産生量を評価する |
画像診断による腫瘍の特定
ホルモン検査で異常が見つかった場合や、症状から腫瘍が疑われる場合には、画像検査で副腎の状態を詳しく調べます。
CT検査の役割と特徴
副腎腫瘍の診断において、CT検査は最も基本的で重要な画像検査です。CT検査により、腫瘍の正確な位置、大きさ、形状、周囲の臓器への広がり(浸潤)などを詳細に評価できます。
副腎皮質がんは、良性腫瘍に比べてサイズが大きい、形が不整である、内部に出血や壊死を伴う、といった特徴を示すことが多く、CT画像はこれらの鑑別に役立ちます。
造影剤を使用することで、さらに詳しい情報を得ることができます。
MRI検査やPET検査の活用
MRI検査は、CT検査とは異なる原理で体内を画像化する検査です。特に、腫瘍と周囲の血管との関係を詳しく見る場合や、腫瘍の内部構造をより詳細に評価したい場合に有用です。
PET検査は、がん細胞がブドウ糖を多く取り込む性質を利用して、がんの広がりや転移の有無を全身的に調べる検査です。遠隔転移が疑われる場合や、治療効果の判定などに用いられます。
確定診断への道のり
画像検査で悪性が強く疑われる特徴的な所見があり、ホルモン検査の結果などを合わせれば、手術前にほぼ副腎皮質がんと診断できる場合が多いです。
生検のリスクと適応
他の多くのがんでは、組織の一部を採取して顕微鏡で調べる生検によって確定診断を行いますが、副腎がんが疑われる場合には、生検は原則として行いません。
その理由は、生検の際に針を刺すことで、がん細胞が腹腔内に散らばってしまう「播種(はしゅ)」のリスクがあるためです。播種が起こると、がんが腹腔内で広がり、根治が難しくなる可能性があります。
そのため、診断は画像検査とホルモン検査の結果から総合的に判断し、最終的な確定診断は、手術で摘出した腫瘍の病理組織検査によって行います。
癌としての副腎がんの進行度と分類
副腎がんの治療方針を決定し、今後の見通しを予測するためには、がんがどのくらい進行しているか(病期、ステージ)を正確に評価することが重要です。
また、摘出した腫瘍組織を顕微鏡で調べて、がん細胞の顔つき(悪性度)を評価することも、予後を予測する上で大切な情報となります。
病期(ステージ)分類の考え方
副腎がんの病期分類には、いくつかの種類がありますが、現在、国際的に広く用いられているのがENSAT(European Network for the Study of Adrenal Tumors)分類です。
これは、腫瘍の大きさ、周囲の組織への広がり、リンパ節転移の有無、遠隔転移の有無に基づいて、ステージIからIVまでの4段階に分類します。
ENSAT病期分類の概要
| ステージ | 腫瘍の状態 |
|---|---|
| ステージ I | 腫瘍の大きさが5cm以下で、副腎内にとどまっている |
| ステージ II | 腫瘍の大きさが5cmを超え、副腎内にとどまっている |
| ステージ III | リンパ節転移がある、または周囲の臓器に浸潤している |
| ステージ IV | 他の臓器への遠隔転移がある |
【副腎がん(副腎皮質がん)の5年生存率(目安)】 ※ENSAT分類に基づく一般的な傾向
- ステージI: 約80%以上
- ※早期発見で手術により完全切除できれば、良好な予後が期待できます。
- ステージII: 約50〜60%
- ステージIII: 約20〜40%
- ステージIV: 10%未満
- ※進行がんは厳しい予後となりますが、ミトタンや化学療法によるコントロールを目指します。
腫瘍の悪性度の評価
手術で摘出した腫瘍は、病理医が顕微鏡で詳しく調べます。その際、腫瘍の悪性度を客観的に評価するための指標が用いられます。
Weissスコア
副腎皮質腫瘍の良性・悪性を鑑別するために広く用いられているのが「Weissスコア」です。これは、核の異型性、核分裂像の数、静脈への浸潤など、9つの項目を評価し、点数化するものです。
合計点が3点以上の場合に、副腎皮質がんと診断されます。このスコアは、悪性度の指標となり、点数が高いほど再発のリスクが高いと考えられています。
転移しやすい部位
副腎がんは、血液の流れに乗って他の臓器に転移することがあります。転移は、がんが進行した状態であることを意味し、治療がより複雑になります。
主な遠隔転移の部位
- 肺
- 肝臓
- 骨
- リンパ節
肺、肝臓、骨への転移
副腎がんが最も転移しやすい臓器は肺です。次いで肝臓、骨などにも転移が見られます。転移がある場合は、ステージIVと診断され、手術だけでなく、薬物療法を中心とした全身的な治療が必要になります。
骨に転移すると、痛みや骨折の原因となることがあります。
副腎がんの治療法と選択の考え方
副腎がんの治療は、がんの進行度、ホルモン産生の有無、患者さん自身の全身状態などを総合的に考慮して決定します。
治療の基本は手術による腫瘍の切除ですが、進行度に応じて薬物療法や放射線治療を組み合わせます。希少がんであるため、経験豊富な専門施設で治療を受けることが極めて重要です。
治療の基本方針
治療方針は、内分泌内科医、泌尿器科医、腫瘍内科医、放射線治療医、病理医など、様々な分野の専門家が集まるカンファレンス(キャンサーボード)で慎重に検討します。
専門医(名医)との連携の重要性
副腎がんは診断も治療も専門性が高く、経験豊富な医師(いわゆる「名医」)やチーム医療体制が整った施設での治療が望まれます。希少がんであるため、すべての病院で十分な治療経験があるわけではありません。
主治医と相談の上、必要であればセカンドオピニオンを求めたり、専門施設を紹介してもらったりすることも大切な選択です。
手術(外科治療)
がんが副腎に限局している場合(ステージI〜II)や、周囲の臓器への浸潤があっても完全に取りきれると判断される場合(一部のステージIII)には、根治を目指して手術を行います。
根治を目指す副腎摘出術
手術の目的は、腫瘍を周囲の組織ごと、破綻させずに一塊として完全に取り除くことです。これを「根治的副腎摘出術」と呼びます。
手術中に腫瘍を傷つけてしまうと、がん細胞が腹腔内に散らばり、再発のリスクが高まるため、非常に慎重な操作が求められます。一般的に、お腹を大きく開ける開腹手術が行われます。
主な治療法の比較
| 治療法 | 対象となる主なステージ | 目的 |
|---|---|---|
| 手術(外科治療) | I、II、一部のIII | がんの根治 |
| 薬物療法(ミトタンなど) | 切除不能、転移・再発例、術後補助療法 | がんの進行抑制、再発予防 |
| 放射線治療 | 骨転移などによる症状緩和 | 痛みの軽減など |
手術の適応と限界
手術でがんを完全に取りきれるかどうかが、その後の経過に最も大きく影響します。
しかし、発見時にすでに主要な血管に浸潤していたり、複数の臓器に転移していたりするなど、手術による完全切除が困難な場合もあります。
そのような場合は、薬物療法が治療の中心となります。
薬物療法
手術でがんを取りきれない場合や、手術後に再発・転移が見られた場合、また再発リスクが高い場合の術後補助療法として薬物療法を行います。
ミトタンによる治療
副腎皮質がんの薬物療法において中心的な役割を果たすのが「ミトタン」という薬剤です。
ミトタンは、副腎皮質の細胞を破壊する作用を持ち、がんの増殖を抑える効果や、ホルモンの産生を抑制する効果が期待されます。
治療効果が現れるまでに時間がかかることや、副作用の管理が重要であることから、専門医のもとで慎重に使用します。定期的に血中濃度を測定し、至適な濃度を維持するように投与量を調整します。
細胞障害性抗がん剤(化学療法)
ミトタンの効果が不十分な場合や、がんが急速に進行する場合には、一般的な抗がん剤を用いた化学療法を検討します。
エトポシド、ドキソルビシン、シスプラチンという3種類の薬剤を組み合わせる「EDP療法」が標準的な治療法の一つです。これらの薬剤は、ミトタンと併用されることもあります。
放射線治療の位置づけ
副腎皮質がんは、一般的に放射線治療が効きにくいがんとされています。そのため、がんを根治させる目的で放射線治療を行うことは稀です。
しかし、骨への転移による痛みが強い場合など、症状を和らげる目的(緩和的治療)で放射線治療を行うことがあります。
治療に伴う副作用と生活上の工夫
副腎がんの治療は、体への負担を伴うことがあります。特に、手術やミトタンによる薬物療法では、特有の副作用が生じる可能性があります。
どのような副作用が起こりうるかを事前に理解し、適切に対処していくことが、治療を継続し、生活の質を維持する上で重要です。
手術後の合併症とケア
副腎摘出術は、比較的大きな手術であり、術後には出血、感染、創部痛、周囲臓器の損傷などの合併症が起こる可能性があります。また、手術後は一時的に腸の動きが悪くなることもあります。
入院中は、医師や看護師の指示に従い、痛み止めを使用したり、早期に離床して歩行訓練を行ったりすることで、回復を促します。
ミトタン治療の副作用と対策
ミトタンは、副腎皮質がんの治療に重要な薬剤ですが、多くの患者さんで副作用が見られます。副作用の程度には個人差がありますが、うまく付き合っていくための工夫が必要です。
ミトタンの主な副作用と対処法
| 副作用の種類 | 主な症状 | 対処法の例 |
|---|---|---|
| 消化器症状 | 食欲不振、吐き気、嘔吐、下痢 | 吐き気止めの使用、食事の工夫(少量頻回食など) |
| 神経症状 | めまい、ふらつき、傾眠(眠気が続く) | 車の運転や危険な作業を避ける、十分な休息 |
| 全身症状 | 倦怠感、皮膚の発疹 | 無理のない範囲での活動、保湿ケア |
消化器症状や神経症状への対応
ミトタンの副作用で最も多いのが、食欲不振や吐き気といった消化器症状です。食事を一度にたくさん摂るのが難しい場合は、少量ずつ回数を分けて食べるなどの工夫が有効です。
吐き気が強い場合は、医師に相談して吐き気止めを処方してもらいましょう。また、めまいや眠気などの神経症状が現れることもあるため、治療中は自動車の運転や機械の操作には十分な注意が必要です。
ホルモン補充療法の必要性
手術で片方の副腎を摘出し、かつミトタン治療を行う場合、残った正常な副腎の機能も抑制されてしまいます。また、ミトタンはがん細胞だけでなく正常な副腎皮質の細胞にも作用します。
その結果、生命維持に必要なコルチゾールなどのホルモンが不足する「副腎不全」という状態になります。
これを補うため、ステロイドホルモン剤(ヒドロコルチゾンなど)を内服する「ホルモン補充療法」が必要です。
発熱時や体調不良時には、通常より多くのホルモンが必要になるため、薬の量を増やすなどの対応(シックデイ・ルール)が重要になります。この治療は、生涯にわたって継続する必要があります。
再発や転移を防ぐための経過観察とフォローアップ
副腎がんの治療が終わった後も、再発や転移の可能性を念頭に置いた長期的な経過観察が欠かせません。
定期的に医療機関を受診し、必要な検査を受けることで、万が一再発した場合でも早期に発見し、迅速に次の治療へつなげることができます。
定期的な検査の重要性
治療後のフォローアップの目的は、再発の早期発見と、治療による副作用や合併症の管理です。医師の指示に従い、定期的な通院を継続することが大切です。
CT検査やホルモン検査によるモニタリング
経過観察では、定期的に画像検査とホルモン検査を行います。画像検査では、主に胸部から骨盤部にかけてのCT検査を行い、腫瘍が再発していないか、肺や肝臓などに新たな転移が出現していないかを確認します。
ホルモンを産生していた腫瘍の場合は、血液検査や尿検査でホルモン値を測定することも、再発の鋭敏なマーカーとなります。
経過観察で行う検査の例
| 検査の種類 | 頻度の目安(術後) | 目的 |
|---|---|---|
| CT検査 | 3~6ヶ月ごと | 局所再発や遠隔転移の有無を確認 |
| ホルモン検査 | 3~6ヶ月ごと | ホルモン値の上昇による再発の発見 |
| 診察 | 1~3ヶ月ごと | 体調変化の確認、副作用の管理 |
※検査の頻度は、病状や再発リスクに応じて個別に決定します。
再発時の治療選択肢
残念ながら再発してしまった場合でも、治療の選択肢はあります。再発した場所や個数、全身状態などを考慮して、最適な治療法を検討します。
再手術や薬物療法の検討
再発した病変が限られた場所にあり、手術で取りきれると判断された場合は、再度手術を行うことがあります。
手術が困難な場合や、複数の場所に再発・転移が見られる場合は、ミトタンや化学療法(EDP療法など)による薬物療法が中心となります。
近年では、新しい分子標的薬などの臨床試験も行われており、治療の選択肢は少しずつ増えつつあります。
長期的な視点での体調管理
副腎がんの治療後は、再発への不安を抱えながら生活することになります。不安な気持ちや体調の変化については、一人で抱え込まずに主治医や看護師、家族などに相談することが大切です。
また、ホルモン補充療法を受けている場合は、自己判断で薬を中断しないようにし、日々の体調管理をしっかりと行いましょう。
副腎がんに関するよくある質問
- 副腎がんは遺伝しますか?
-
ほとんどの副腎がんは遺伝しませんが、一部にリー・フラウメニ症候群などの遺伝性疾患が背景にある場合があります。
家族にがんが多い、若年で発症したなど、遺伝的な要因が心配な場合は、主治医に相談し、遺伝カウンセリングを受けることを検討してもよいでしょう。
- 治療中の食事で気をつけることはありますか?
-
基本的に、特定の食品ががんを悪化させる、あるいは改善するという科学的根拠はありません。バランスの取れた食事を心がけることが基本です。
ただし、ミトタンの副作用で食欲がない場合は、食べやすいものを少量ずつ摂る工夫が必要です。
また、クッシング症候群による高血圧や高血糖がある場合は、塩分や糖分の管理について医師や管理栄養士の指導を受けてください。
- 「名医」はどのように探せばよいですか?
-
副腎がんは希少がんであるため、治療経験が豊富な専門施設で治療を受けることが重要です。
「名医」の定義は難しいですが、一つの目安として、日本内分泌学会や日本泌尿器科学会などの専門医資格を持つ医師が在籍しているか、また、希少がんの診療実績が多い大学病院やがん専門病院などが挙げられます。
現在かかっている主治医に相談し、専門施設を紹介してもらうのが一般的な方法です。
- 副腎皮質がんと診断されましたが、セカンドオピニオンは受けた方がよいですか?
-
はい、セカンドオピニオンを聞くことは、患者さんの権利であり、非常に有益です。
特に副腎がんのような希少がんで、治療法が複雑な場合には、別の専門医の意見を聞くことで、現在の診断や治療方針への理解が深まり、納得して治療に臨むことができます。
主治医にセカンドオピニオンを希望する旨を伝え、紹介状や検査データを用意してもらいましょう。
- 生存率のデータはどのように解釈すればよいですか?
-
インターネットなどで目にする生存率は、多くの患者さんのデータを集計した平均的な数値であり、個々の患者さん一人ひとりの未来を予測するものではありません。
生存率は、がんのステージ、悪性度、治療法、年齢、全身状態など多くの要因に影響されます。
あくまで参考情報の一つとして捉え、数字に一喜一憂しすぎず、ご自身の治療に前向きに取り組むことが大切です。詳しい見通しについては、主治医とよく話し合ってください。
副腎と同じく、私たちの体にはホルモンを産生する「内分泌器官」がいくつか存在します。
その代表的なものの一つが、首の前側にある甲状腺です。甲状腺にもがんが発生することがあり、これを甲状腺がんといいます。
甲状腺がんは、副腎がんと同様にホルモンバランスに影響を与えることがありますが、多くはおとなしい性質で進行がゆっくりであるという特徴があります。
内分泌器官のがんについてさらに理解を深めたい方は、こちらの甲状腺がんの解説記事もご覧ください。
以上
参考文献
LUTON, Jean-Pierre, et al. Clinical features of adrenocortical carcinoma, prognostic factors, and the effect of mitotane therapy. New England Journal of Medicine, 1990, 322.17: 1195-1201.
SCOLLO, Claudia, et al. Prognostic factors for adrenocortical carcinoma outcomes. Frontiers in Endocrinology, 2016, 7: 99.
BERRUTI, Alfredo, et al. Long-term outcomes of adjuvant mitotane therapy in patients with radically resected adrenocortical carcinoma. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2017, 102.4: 1358-1365.
MEGERLE, Felix, et al. Mitotane monotherapy in patients with advanced adrenocortical carcinoma. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2018, 103.4: 1686-1695.
POSTLEWAIT, Lauren M., et al. Outcomes of adjuvant mitotane after resection of adrenocortical carcinoma: a 13-institution study by the US Adrenocortical Carcinoma Group. Journal of the American College of Surgeons, 2016, 222.4: 480-490.
PUGLISI, Soraya, et al. Mitotane concentrations influence outcome in patients with advanced adrenocortical carcinoma. Cancers, 2020, 12.3: 740.
ARENAS, C.; MELIÁN, C.; PÉREZ‐ALENZA, M. D. Long‐term survival of dogs with adrenal‐dependent hyperadrenocorticism: a comparison between mitotane and twice daily trilostane treatment. Journal of veterinary internal medicine, 2014, 28.2: 473-480.
TŐKE, Judit, et al. Prognostic factors and mitotane treatment of adrenocortical cancer. Two decades of experience from an institutional case series. Frontiers in Endocrinology, 2022, 13: 952418.
AL-WARD, Ruaa; ZSEMBERY, Celeste; HABRA, Mouhammed Amir. Adjuvant therapy in adrenocortical carcinoma: prognostic factors and treatment options. Endocrine Oncology, 2022, 2.1: R90-R101.
OHSUGI, Haruyuki, et al. Prognostic Factors Among Patients with Non-metastatic Adrenocortical Carcinoma. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2025, 23.2: e159772.
内分泌系がんに戻る