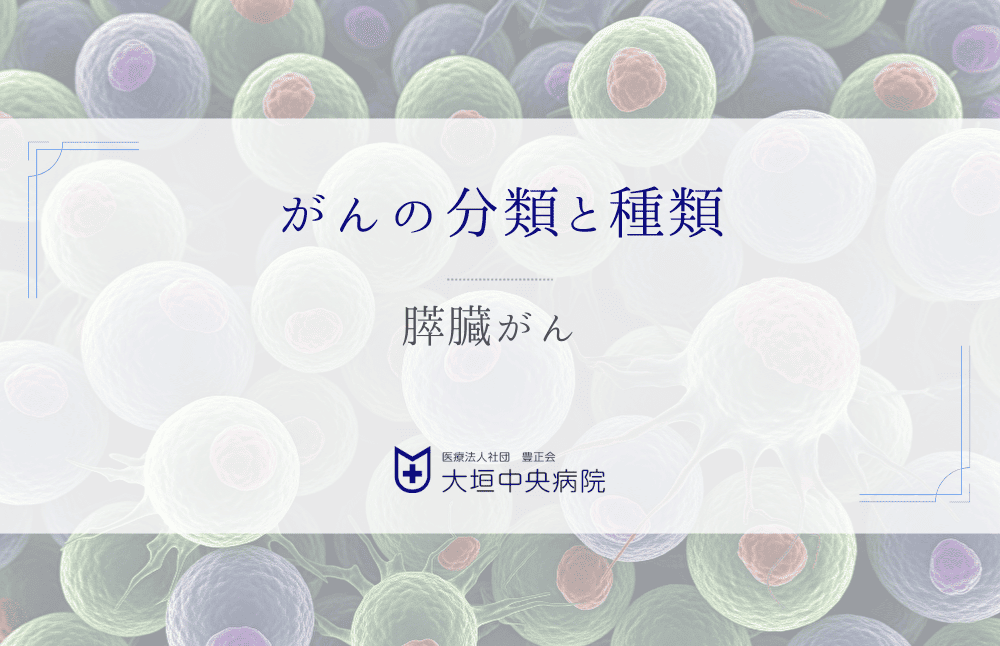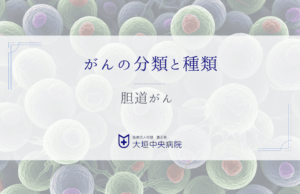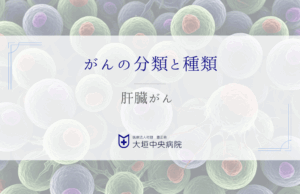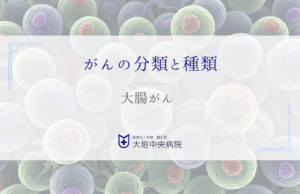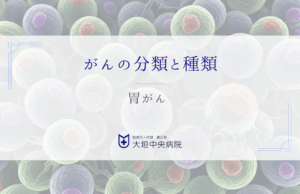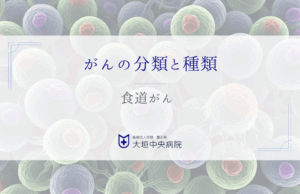膵臓がんは、早期発見が難しく、進行が速いことで知られるがんです。しかし、医学の進歩により、その性質や治療法についての理解は着実に深まっています。
この記事では、膵臓がんがなぜ「静かな病気」と呼ばれるのかという基本的な疑問から、診断に必要な検査、ステージごとの生存率、そして手術や抗がん剤を用いた具体的な治療の選択肢まで、現在分かっている医学的な事実を網羅的に解説します。
ご自身やご家族が膵臓がんと向き合う上で、正確な知識を得て、納得のいく治療を選択するための一助となることを目指します。
膵臓がんが「静かな病気」と呼ばれる理由
膵臓がんは、初期の段階では自覚できる症状がほとんど現れないため、「静かな病気(サイレント・ディジーズ)」という異名をもちます。
多くの患者さんが異変に気づいたときには、すでにがんが進行しているケースが少なくありません。
なぜこれほどまでに発見が難しいのか、その背景には膵臓の解剖学的な特徴と、症状の非特異性が深く関わっています。
初期症状の乏しさ
膵臓がんの最大の特徴は、がんが小さいうちは特有の症状を引き起こさない点にあります。
腹部の違和感や食欲不振といった漠然とした不調は、多くの人が経験するものであり、がんのサインとは考えにくいのが実情です。この症状の乏しさが、発見を遅らせる最も大きな原因となっています。
膵臓の解剖学的な位置
膵臓は、胃の裏側、体の深い部分に位置する後腹膜臓器です。この位置関係のため、腫瘍が大きくなっても周囲の臓器を圧迫しにくく、症状として表面化しにくいのです。
体の奥深くにあることで、体外からの触診で異常を見つけることはほぼ不可能であり、通常の健康診断などで行う腹部超音波検査でも、腸管ガスなどの影響で全体を明瞭に観察することが難しい場合があります。
症状が現れた時点での進行度
背中の痛みや黄疸といった、より膵臓がんに特徴的とされる症状が現れたときには、がんがすでに大きくなっていたり、周囲の重要な血管や胆管にまで広がっていたりすることが多いです。
症状の出現が、がんの進行を示唆するサインとなってしまうことが、この病気の難しい側面です。
他の疾患との症状の類似性
膵臓がんの初期にみられる症状は、他のより一般的な消化器系の病気や、整形外科的な疾患の症状と非常によく似ています。
このため、患者さん自身も、また場合によっては初期の診療にあたる医師でさえも、膵臓がんを第一に疑うことが難しい場合があります。
胃腸の不調との混同
上腹部の不快感、食欲不振、なんとなく胃の調子が悪いといった症状は、慢性胃炎や胃潰瘍、逆流性食道炎など、頻度の高い疾患でもよくみられます。
そのため、まずは胃薬を服用して様子を見るという対応が取られがちで、その間に診断の機会を逃してしまう可能性があります。
背中の痛みと整形外科疾患
膵臓は背中側に近い位置にあるため、がんが大きくなると背中に痛みを引き起こすことがあります。
しかし、多くの人が経験する腰痛や背部痛は、筋肉の疲労や椎間板の問題など、整形外科的な原因によるものが大半です。
そのため、まずは整形外科を受診し、原因が特定できないまま時間が経過してしまうことも少なくありません。
膵臓がんの初期症状と似た症状を持つ疾患
| 膵臓がんの症状 | 類似する症状を持つ疾患 | 主な診療科 |
|---|---|---|
| 腹部の違和感・食欲不振 | 慢性胃炎、胃潰瘍、逆流性食道炎 | 消化器内科 |
| 背中の痛み | 変形性脊椎症、椎間板ヘルニア、筋筋膜性腰痛 | 整形外科 |
| 体重減少 | 甲状腺機能亢進症、糖尿病、うつ病 | 内分泌内科、精神科 |
膵臓の役割と膵臓がん発生のメカニズム
膵臓は、私たちの生命維持に欠かせない2つの重要な機能、すなわち消化を助ける「外分泌機能」と、血糖値をコントロールする「内分泌機能」を担っています。
膵臓がんの多くは、このうち外分泌機能に関わる膵管の細胞から発生します。その発生には、遺伝的な要因と、長年の生活習慣が複雑に関与すると考えられています。
消化を助ける膵臓の働き
私たちが食事から栄養を吸収するためには、膵臓の働きが欠かせません。食べ物を分解する強力な消化酵素を分泌することで、消化・吸収を円滑に進める役割を担っています。
外分泌機能と消化酵素
膵臓の体積の大部分を占める外分泌腺では、「膵液」という消化液が作られます。
膵液には、炭水化物を分解するアミラーゼ、タンパク質を分解するトリプシン、脂肪を分解するリパーゼなど、様々な消化酵素が含まれています。
これらの酵素は膵管という管を通って十二指腸に送り出され、食物と混ざり合うことでその効果を発揮します。
血糖値を調節する内分泌機能
膵臓は消化だけでなく、体内のエネルギーバランスを保つ上でも中心的な役割を果たします。特に血糖値のコントロールは、膵臓が分泌するホルモンによって厳密に管理されています。
インスリンと糖尿病との関連
膵臓内には「ランゲルハンス島」という細胞の集まりが点在しており、ここから血糖値を下げる「インスリン」や、逆に血糖値を上げる「グルカゴン」といったホルモンが血液中に直接分泌されます。この働きが内分泌機能です。
膵臓がんができて膵臓の機能が低下したり、がん自体がインスリンの働きを妨げる物質を出したりすると、血糖値のコントロールが乱れ、糖尿病を新たに発症したり、もともとあった糖尿病が急に悪化したりすることがあります。
これは、膵臓がんを発見する重要な手がかりの一つです。
膵臓がんの発生原因とリスク因子
膵臓がんがなぜ発生するのか、その正確な原因はまだ完全には解明されていません。しかし、これまでの研究から、いくつかの危険因子(リスク因子)が明らかになっています。
これらのリスクが重なることで、発症の可能性が高まると考えられています。
遺伝的要因と家族歴
血縁関係のある家族の中に膵臓がんと診断された方がいる場合、いない人と比べて発症リスクが高まることが知られています。
特に、親子や兄弟姉妹に2人以上の膵臓がん患者さんがいる家系では、そのリスクはさらに高くなります。特定の遺伝子の変異が関与する家族性膵がんという病態も存在します。
生活習慣に潜むリスク
喫煙は、膵臓がんの最も確実なリスク因子として知られています。喫煙者は非喫煙者に比べて約1.5倍から2倍、膵臓がんになりやすいというデータがあります。
また、過度の飲酒、肥満、慢性膵炎、そして前述の糖尿病も、膵臓がんのリスクを高める要因です。
膵臓がんの主なリスク因子
| リスク因子の種類 | 具体的な内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 生活習慣 | 喫煙、過度の飲酒、肥満 | 特に喫煙は影響が大きい |
| 既往歴 | 慢性膵炎、糖尿病 | 急な糖尿病の発症・悪化は要注意 |
| 家族歴 | 血縁者に膵臓がん患者がいる | 遺伝的要因が関与する場合がある |
見逃しやすい初期症状と進行時の特徴的な変化
膵臓がんは初期症状に乏しい病気ですが、注意深く観察すれば、体からのサインを捉えることができるかもしれません。
漠然とした不調が続く場合は、単なる体調不良と片付けずに、その変化に注意を払うことが大切です。がんが進行すると、よりはっきりとした特徴的な症状が現れるようになります。
注意すべき初期症状のサイン
膵臓がんの初期症状は、非常に曖昧で非特異的です。しかし、以下のような症状が複数重なったり、しばらく続いたりする場合には、一度専門医に相談することを検討すべきです。
なんとなくの腹部不快感
特定の場所を指し示すことができないような、みぞおち周辺の漠然とした不快感や鈍い痛みが現れることがあります。「胃がもたれる」「すっきりしない」といった感覚として自覚されることも多いです。
食後に症状が強まる傾向が見られることもあります。
食欲不振と体重減少
特別な理由がないにもかかわらず、食欲がわかなくなり、食事量が減ることがあります。それに伴い、ダイエットなどをしているわけでもないのに体重が数ヶ月で数キログラム以上減少する場合は、注意が必要です。
これは、がんが体のエネルギーを消費したり、消化吸収能力が低下したりするために起こります。
背中の痛みとその特徴
膵臓がんによる背中の痛みは、しばしば「体の奥から響くような鈍い痛み」と表現されます。体を前にかがめると少し楽になり、仰向けに寝ると強くなるという特徴が見られることがあります。
湿布を貼っても改善しない、持続的な痛みが続く場合は、内臓からのサインである可能性を考える必要があります。
膵臓がんの初期症状チェックリスト
- 原因不明の腹部の不快感や痛み
- 食欲の低下
- 意図しない体重の減少(半年で5%以上)
- 背中や腰の重い痛み
- 急に糖尿病になった、または悪化した
がんの進行に伴う明確な症状
がんが大きくなり、周囲の臓器に影響を及ぼし始めると、より特徴的な症状が現れます。これらの症状は、病気が進行しているサインであり、速やかな医療機関の受診が必要です。
皮膚や目が黄色くなる黄疸
膵臓の頭部(膵頭部)にがんができると、近くを通る「総胆管」という管を圧迫します。
総胆管は肝臓で作られた胆汁を十二指腸へ流す通り道ですが、ここが塞がれると胆汁が血液中に逆流し、ビリルビンという黄色い色素が体に溜まります。
その結果、白目の部分や皮膚が黄色くなる「閉塞性黄疸」という状態になります。尿の色が濃くなったり、便の色が白っぽくなったり、皮膚に強いかゆみが出たりすることもあります。
糖尿病の急な発症や悪化
前述の通り、膵臓がんの影響でインスリンの働きが悪くなり、血糖コントロールが困難になることがあります。
これまで健康だった人が突然糖尿病と診断されたり、食事療法や薬で安定していた糖尿病患者さんの血糖値が急にコントロール不能になったりした場合は、その背景に膵臓がんが隠れている可能性を考慮し、精密な検査が重要になります。
膵臓がんの診断に必要な検査と検査の限界
膵臓がんの診断は、単一の検査で確定するものではなく、血液検査、画像検査、そして組織検査を段階的に組み合わせて行います。
体の奥深くにあるという膵臓の特性上、診断には専門的な技術と複数の検査による総合的な判断が必要です。それぞれの検査には長所と短所があり、その限界を理解することも大切です。
診断への第一歩となる血液検査
健康診断などでも行われる血液検査は、膵臓がんの可能性を探るための最初の手がかりとなります。体への負担が少なく、簡便に行えるのが利点ですが、これだけで診断を確定することはできません。
腫瘍マーカー(CA19-9など)の役割
腫瘍マーカーは、がん細胞が作り出す特殊な物質で、血液中で測定します。膵臓がんでは「CA19-9」や「CEA」といった項目がよく用いられます。
これらの数値が高い場合、膵臓がんの存在が疑われますが、早期のがんでは数値が上昇しないことも多く、逆にがんでなくても慢性膵炎や胆管炎などで高値を示すこともあります。
そのため、診断の補助や、治療効果の判定、再発のモニタリングなどに利用します。
画像でがんを探す主要な検査
血液検査で異常が疑われた場合、次に画像検査で膵臓の状態を直接的に評価します。複数の画像検査を組み合わせることで、がんの存在や大きさ、周囲への広がり(転移)などを詳細に調べます。
超音波(エコー)検査
腹部超音波検査は、体表面からプローブという機器を当てて超音波を発信し、臓器からの反響を画像化する検査です。簡便で体に負担がないため、スクリーニング検査として広く行われます。
しかし、膵臓は体の深部にあるため、体格や腸内ガスの影響で観察しにくいという限界があります。
CT検査とMRI検査
CT検査はX線を、MRI検査は磁気を利用して体の断面を撮影する検査です。
造影剤を使用することで、より鮮明な画像を得ることができ、小さな病変の検出や、がんの広がり、血管への浸潤、遠隔転移の有無などを評価する上で中心的な役割を果たします。
特にCT検査は、膵臓がんの診断と病期(ステージ)決定に最も重要な検査と位置づけられています。
超音波内視鏡検査(EUS)
先端に超音波装置がついた内視鏡(スコープ)を口から挿入し、胃や十二指腸の中から膵臓を直接観察する検査です。
体の表面からの超音波検査と比べて、消化管ガスの影響を受けずに膵臓に非常に近い位置から観察できるため、小さな腫瘍の発見に極めて高い能力を発揮します。
必要に応じて、そのまま針を刺して組織を採取することも可能です。
確定診断のための組織検査
画像検査でがんが強く疑われた場合、最終的な確定診断のために、がん細胞の一部を採取して顕微鏡で調べる「病理診断」を行います。
これにより、がんの種類(組織型)を特定し、治療方針を決定します。
生検による病理診断の重要性
組織を採取する方法を「生検」と呼びます。前述の超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)や、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)という検査を用いて膵管内の細胞を採取する方法などがあります。
採取した組織を病理医が詳しく調べることで、がん細胞の存在を確定し、その性質を評価します。この確定診断があって初めて、手術や抗がん剤治療といった本格的な治療が開始されます。
膵臓がんの主要な検査とその目的
| 検査の種類 | 検査の目的 | 長所と短所 |
|---|---|---|
| 血液検査(腫瘍マーカー) | がんの可能性のスクリーニング、治療効果判定 | 簡便だが、早期がんでは正常なことも多い |
| 腹部超音波検査 | がんの有無や膵管拡張の評価 | 低侵襲だが、体格やガスで描出困難な場合がある |
| 造影CT/MRI検査 | がんの存在、大きさ、広がり、転移の評価 | 全身を詳細に評価できるが、造影剤アレルギーのリスクがある |
| 超音波内視鏡検査 (EUS) | 小さな病変の発見、組織の採取(生検) | 検出能が高いが、内視鏡挿入による負担がある |
病期分類と予後 – 医学的データが示す現実
膵臓がんの治療方針を決定し、今後の見通し(予後)を予測するためには、がんがどのくらい進行しているかを正確に評価する「病期分類(ステージング)」が重要です。
ステージは、がんの大きさ、リンパ節への転移、他の臓器への遠隔転移の3つの要素を基に決定されます。
残念ながら、膵臓がんは他のがんと比較して予後が厳しいがんですが、ステージごとの生存率を正しく理解することは、治療と向き合う上で大切です。
膵臓がんのステージ(病期)分類
世界的に広く用いられている「UICC TNM分類」に基づき、膵臓がんのステージは0期からIV期までの5段階に分けられます。この分類は、治療法を選択する際の最も重要な指標となります。
がんの大きさと広がりによる分類
T因子(Tumor)は、原発巣である膵臓内でのがんの大きさと、周囲の組織への広がり具合を示します。がんが膵臓内にとどまっているか、周囲の主要な血管にまで及んでいるかによって細かく分類されます。
リンパ節への転移の有無
N因子(Node)は、膵臓の近くにあるリンパ節へのがんの転移の有無と、その個数を示します。リンパ節はがん細胞が他の場所へ広がるための中継地点となるため、転移の有無は予後に大きく影響します。
遠隔転移(肝臓、肺など)の評価
M因子(Metastasis)は、肝臓、肺、腹膜など、膵臓から離れた臓器への遠隔転移の有無を示します。遠隔転移がある場合はステージIVと診断され、治療方針が大きく変わります。
膵臓がんのステージ(UICC TNM分類 第8版に基づく簡略版)
| ステージ | がんの状態 | 主な治療方針 |
|---|---|---|
| 0期 | ごく早期のがんが膵管内にとどまっている | 手術 |
| I期・II期 | がんが膵臓内またはその近くにとどまっている | 手術と化学療法 |
| III期 | がんが周囲の重要な血管を巻き込んでいる | 化学療法、化学放射線療法 |
| IV期 | 肝臓や肺など他の臓器に遠隔転移がある | 化学療法 |
ステージごとの生存率と予後
膵臓がんの予後は、発見されたときのステージに大きく左右されます。
生存率は、治療を受ける上で誰もが気になる情報ですが、あくまで多くの患者さんのデータの平均値であり、個々の患者さんの未来を決定づけるものではないことを理解する必要があります。
5年相対生存率のデータ
「5年相対生存率」とは、あるがんと診断された人が、治療開始から5年後に生存している割合を、日本人全体の5年後の生存率と比較して示す指標です。
最新のデータ(全国がん登録2015年症例)によると、膵臓がん全体の5年相対生存率は12.7%と、他のがんに比べて低い水準にあります。
これは、発見時に進行していることが多いという膵臓がんの特性を反映しています。
予後を左右する因子
ステージ以外にも、予後に関わる因子はいくつかあります。
手術でがんを完全に取り切れたかどうか(切除断端の状態)、患者さん自身の全身状態(パフォーマンスステータス)、治療に対する反応性などが、その後の経過に影響を与えます。
ステージ別5年相対生存率の目安
| ステージ | 5年相対生存率(目安) |
|---|---|
| I期 | 約40-50% |
| II期 | 約15-20% |
| III期 | 約5% |
| IV期 | 約1-2% |
※この数値はあくまで全国的な統計データに基づく目安であり、個々の状況によって異なります。
手術適応の判断基準と外科治療の実際
膵臓がんにおいて、根治(がんを完全に取り除くこと)を目指せる唯一の治療法が外科手術です。しかし、診断された時点で手術が可能な患者さんは全体の約20%にとどまります。
手術ができるかどうかは、がんの進行度、特に周囲の重要な血管へのがんの広がり(浸潤)や、遠隔転移の有無によって厳密に判断されます。
手術が可能と判断される条件
手術の適応は、画像検査の結果を基に、外科医、内科医、放射線科医などが集まるカンファレンスで総合的に検討します。
患者さんの全身状態や併存疾患も考慮して、安全に手術を乗り越えられるかどうかも重要な判断材料です。
遠隔転移がないことの重要性
肝臓や肺、腹膜など、膵臓から離れた臓器にがんが転移している(ステージIV)場合、手術で膵臓のがんを取り除いても、体内に残ったがん細胞が再び増殖するため、根治は望めません。
このため、遠隔転移がないことが手術の絶対条件となります。
主要な血管へのがんの広がり
膵臓の周囲には、腹腔動脈や上腸間膜動脈といった、消化管全体を栄養する非常に重要な血管が走行しています。
がんがこれらの動脈に広く浸潤している場合、安全に切除することが困難なため、手術の適応外(切除不能)と判断されます。
門脈という血管への浸潤であれば、血管を一緒に切除して再建する手術が可能な場合もあります。
代表的な手術の方法
手術の方法は、がんが膵臓のどの部分にできているかによって決まります。いずれも消化器外科手術の中では極めて難易度が高く、長時間を要する複雑な手術です。
膵頭十二指腸切除術
膵臓の頭部(膵頭部)にがんができた場合に行われる標準的な手術です。がんのある膵頭部とともに、十二指腸、胆管、胆嚢、そして場合によっては胃の一部までを一緒に切除します。
切除後は、残った膵臓、胆管、胃(または空腸)を小腸とつなぎ合わせる「再建」という手技が必要になります。
膵体尾部切除術
膵臓の体部から尾部(体の左側)にかけてがんができた場合に行われます。がんのある膵体尾部を、多くの場合、脾臓と一緒に切除します。膵頭十二指腸切除術のような複雑な再建は通常必要ありません。
膵臓がんの主な手術方法
| 手術名 | がんの発生部位 | 切除する主な臓器 |
|---|---|---|
| 膵頭十二指腸切除術 | 膵頭部 | 膵頭部、十二指腸、胆管、胆嚢 |
| 膵体尾部切除術 | 膵体部・膵尾部 | 膵体尾部、脾臓 |
手術後の合併症と回復
膵臓の手術は、体への負担が大きく、術後には様々な合併症が起こる可能性があります。手術を乗り越え、順調に回復するためには、術後の綿密な管理が重要です。
起こりうる合併症のリスク
最も注意が必要な合併症は「膵液瘻(すいえきろう)」です。これは、膵臓と小腸をつないだ部分から、消化酵素を多く含む膵液が漏れ出してしまう状態で、腹腔内の感染や出血の原因となります。
その他にも、縫合不全、腹腔内膿瘍、出血、胆管炎、胃内容排泄遅延など、様々な合併症のリスクがあります。
化学療法と放射線治療の役割と効果
手術が困難な進行がんや、手術後に再発を予防する目的で、化学療法(抗がん剤治療)や放射線治療が行われます。これらの治療は、がん細胞を直接攻撃し、増殖を抑えることを目的とします。
近年の治療薬や治療技術の進歩により、その効果は着実に向上しており、膵臓がん治療において中心的な役割を担っています。
全身に作用する化学療法(抗がん剤治療)
化学療法は、抗がん剤を点滴や内服で投与し、血液の流れに乗って全身のがん細胞に作用させる治療法です。目に見えない微小な転移にも効果が期待できるため、膵臓がん治療の様々な場面で用いられます。
手術前後の補助化学療法
手術でがんを取り切れた場合でも、再発のリスクを減らすために、術後に化学療法(術後補助化学療法)を行います。
また、手術が可能かどうかの境界線上にあるがん(ボーダーライン・リセクタブル)に対しては、手術前に化学療法を行い、がんを小さくしてから手術に臨む「術前補助化学療法」が標準的な治療となっています。
切除不能・再発膵臓がんに対する治療
手術ができない進行がんや、術後に再発したがんに対しては、化学療法が治療の中心となります。
がんの進行を抑え、症状を和らげることで、生存期間の延長と生活の質(QOL)の維持を目指します。
患者さんの全身状態やがんの性質に応じて、複数の薬剤を組み合わせる多剤併用療法が選択されます。
主な抗がん剤の種類と副作用
膵臓がんの化学療法では、ゲムシタビン、S-1(ティーエスワン)、ナブパクリタキセル、イリノテカン、オキサリプラチンといった薬剤が、単独または組み合わせて用いられます。
これらの薬剤はがん細胞だけでなく、正常な細胞にも影響を与えるため、吐き気、食欲不振、脱毛、骨髄抑制(白血球や血小板の減少)、末梢神経障害(手足のしびれ)などの副作用が現れることがあります。
副作用の対策も治療の重要な一部です。
主な抗がん剤の種類
- ゲムシタビン(ジェムザール)
- S-1(ティーエスワン)
- FOLFIRINOX療法(複数の薬剤の組み合わせ)
- ゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法
局所的にがんを叩く放射線治療
放射線治療は、高エネルギーのX線などをがんのある場所に集中して照射し、がん細胞のDNAにダメージを与えて破壊する局所療法です。
単独で行われることは少なく、多くの場合、化学療法と組み合わせてその効果を高めます。
化学療法との併用
手術はできないものの遠隔転移はない局所進行膵臓がん(ステージIII)に対して、化学療法と放射線治療を同時に行う「化学放射線療法」が選択されることがあります。
これにより、局所のがんを制御し、症状の進行を遅らせる効果が期待できます。
痛みなどの症状緩和を目的とした照射
がんが骨に転移して強い痛みを引き起こしている場合や、腫瘍による圧迫症状を和らげたい場合に、緩和的な目的で放射線治療を行うことがあります。
比較的少ない回数の照射で、症状を効果的に軽減させることが可能です。
緩和ケアの重要性と生活の質の維持
緩和ケアは、がん治療に伴う身体的・精神的な苦痛を和らげ、患者さんとそのご家族が、その人らしい生活を送れるように支えるためのアプローチです。
かつては「終末期医療」というイメージがありましたが、現在では、がんと診断された早期の段階から、治療と並行して行うべき重要なケアと位置づけられています。
緩和ケアとは何か
世界保健機関(WHO)は、緩和ケアを「生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者とその家族のQOL(生活の質)を、痛みやその他の身体的、心理社会的、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確な評価と対応を行うことによって、苦しみを予防し和らげることを通して向上させるアプローチ」と定義しています。
診断初期からの関わり
痛み、吐き気、倦怠感といった身体的な症状だけでなく、不安や落ち込みといった精神的なつらさも、緩和ケアの対象です。
これらの苦痛は、治療の継続を困難にしたり、日常生活に大きな支障をきたしたりします。
診断されたときから緩和ケアチームが関わることで、これらのつらさを早期に和らげ、患者さんが前向きに治療に取り組めるようサポートします。
身体的な苦痛の緩和
膵臓がんは、進行すると様々な身体的苦痛を伴うことがあります。
これらの症状を医療用麻薬や様々な薬剤、神経ブロックなどを用いて積極的にコントロールすることが、QOLの維持には必要です。
痛みや吐き気への対処
がんによる痛みは、膵臓がんの患者さんが経験する最もつらい症状の一つです。痛みの強さに応じて、非オピオイド鎮痛薬からオピオイド(医療用麻薬)まで、段階的に薬剤を調整します。
また、抗がん剤の副作用やがんによる消化管の圧迫で起こる吐き気に対しても、効果的な制吐剤を用いて対処します。
黄疸によるかゆみの管理
黄疸が出現すると、全身に耐え難いかゆみが生じることがあります。これは胆汁中の成分が皮膚を刺激するためです。抗ヒスタミン薬や特定の薬剤の内服、スキンケアなどで症状の緩和を図ります。
場合によっては、内視鏡を使って胆管にステントという管を留置し、胆汁の流れを改善する処置も行います。
緩和ケアで対応する主な症状
| 症状の種類 | 具体的な症状 | 主な対処法 |
|---|---|---|
| 身体的苦痛 | 痛み、吐き気、倦怠感、食欲不振、かゆみ | 薬物療法、神経ブロック、放射線治療、栄養指導 |
| 精神的苦痛 | 不安、抑うつ、不眠、せん妄 | カウンセリング、薬物療法、家族へのサポート |
| 社会的苦痛 | 仕事や経済的な問題、家族内の役割変化 | 医療ソーシャルワーカーによる相談支援 |
精神的・社会的なサポート
がんと診断されることは、患者さん本人だけでなく、ご家族にとっても大きな衝撃です。将来への不安や治療への恐怖、経済的な心配など、様々な問題に直面します。
これらのつらさに寄り添い、共に解決策を探していくことも緩和ケアの重要な役割です。
不安や抑うつとの向き合い方
つらい気持ちを一人で抱え込まず、医師や看護師、臨床心理士などの専門家に話すことが大切です。気持ちを整理し、客観的なアドバイスを得ることで、心の負担が軽くなることがあります。
必要に応じて、抗不安薬や抗うつ薬などの薬物療法も有効です。
膵臓がんとの向き合い方 – 患者・家族へのサポート
膵臓がんと診断されたとき、多くの情報が一度に提供され、混乱や不安を感じるのは当然のことです。
このような状況の中で、納得のいく治療を選択し、病気と向き合っていくためには、信頼できる情報を基に、医療チームと良好な関係を築き、利用できる社会的サポートを積極的に活用することが重要になります。
正確な情報を得ることの重要性
インターネット上には、科学的根拠の乏しい情報や、個人の体験談に基づいた情報が溢れています。
不確かな情報に惑わされず、公的機関や専門学会が発信する信頼性の高い情報源にあたることが、冷静な判断の第一歩です。
信頼できる情報源の活用
国立がん研究センターが運営する「がん情報サービス」や、日本膵臓学会、日本癌治療学会などのウェブサイトは、標準的な治療法や最新の研究成果について、正確で分かりやすい情報を提供しています。
まずはこれらの情報に目を通し、基本的な知識を身につけることが助けになります。
情報収集と相談の窓口
- 国立がん研究センター がん情報サービス
- 担当医、看護師、薬剤師などの医療スタッフ
- がん診療連携拠点病院などに設置されている「がん相談支援センター」
- 患者会・家族会
治療方針の決定への参加
現在の医療では、医師が一方的に治療方針を決めるのではなく、患者さん自身が病状や治療法の選択肢について十分な説明を受け、自らの価値観や希望に基づいて治療法を選択する「インフォームド・コンセント(説明と同意)」が基本です。
分からないことや不安なことは、遠慮なく質問し、納得できるまで話し合うことが大切です。
セカンドオピニオンの活用
担当医以外の医師の意見を聞く「セカンドオピニオン」は、現在の診断や治療方針についての理解を深め、納得して治療に臨むために有効な手段です。
セカンドオピニオンを求めることは、担当医との信頼関係を損なうものではなく、患者さんの正当な権利として認められています。
利用できる社会資源とサポート体制
がんの治療には、医療費の負担や、仕事との両立、家族の介護など、様々な社会的な問題が付随します。これらの問題について相談できる窓口や、経済的な負担を軽減するための制度があります。
がん相談支援センター
全国のがん診療連携拠点病院などに設置されている無料で利用できる相談窓口です。
専門の相談員(看護師やソーシャルワーカー)が、病気に関する一般的な情報提供から、療養生活上の悩み、経済的な問題まで、幅広い相談に対応してくれます。
患者さん本人だけでなく、ご家族も利用できます。
患者会や家族会
同じ病気を経験した仲間と話すことは、大きな心の支えになります。
治療に関する情報交換だけでなく、医療者には話しにくい悩みや不安を分かち合うことで、孤独感が和らぎ、前向きな気持ちを取り戻すきっかけになることがあります。
よくある質問
膵臓がんについて、患者さんやご家族から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。個々の状況によって異なる場合があるため、詳細は必ず担当医にご確認ください。
- 膵臓がんは遺伝しますか?
-
膵臓がんの大部分は遺伝と直接関係なく発生しますが、一部に遺伝的要因が強く関与する「家族性膵がん」が存在します。
血縁者(特に親子、兄弟姉妹)に膵臓がんになった方が複数いる場合は、発症リスクが高いと考えられます。心配な場合は、遺伝カウンセリング外来などで相談することも可能です。
- 背中の痛みが続きますが、膵臓がんの可能性はありますか?
-
背中の痛みの原因は、整形外科的な疾患が圧倒的に多いですが、膵臓がんの症状である可能性もゼロではありません。
特に、体を前にかがめると楽になる、何をしても痛みが改善しない、腹部の不快感や体重減少など他の症状も伴う、といった場合は、一度消化器内科の受診を検討することをお勧めします。
- 治療中は食事で何に気をつければよいですか?
-
膵臓がんの治療中や手術後は、消化吸収機能が低下することがあります。基本は、消化が良く、高タンパク・高カロリーの食事を心がけることです。
一度にたくさん食べられない場合は、食事の回数を1日5〜6回に分けるなどの工夫が有効です。脂肪分の多い食事は下痢の原因になることがあるため、注意が必要です。
管理栄養士に相談し、個々の状況に合った食事指導を受けることが大切です。
食事の工夫の例
ポイント 具体的な工夫 目的 消化しやすくする 食材を細かく刻む、よく煮込む 胃腸への負担を軽減 少量で栄養を摂る 間食を取り入れる、栄養補助食品を活用する 体重減少の防止 脂肪を控える 揚げ物を避け、蒸す・煮る調理法を選ぶ 下痢や脂肪便の予防 - 抗がん剤の副作用が心配です。
-
抗がん剤治療には、様々な副作用が伴う可能性がありますが、近年は副作用を予防したり、症状を和らげたりするための支持療法が大きく進歩しています。
吐き気に対する優れた制吐剤や、白血球を増やす薬などがあります。つらい症状を我慢せず、早めに医師や看護師、薬剤師に伝えることが重要です。
症状に応じて適切な対策を講じることで、多くの場合、治療を継続することが可能です。
膵臓のすぐ隣に位置し、症状や検査、治療法に多くの共通点を持つがんに「胆道がん」があります。
胆道は、肝臓で作られた胆汁を十二指腸まで運ぶ管(胆管)と、胆汁を一時的に蓄える袋(胆嚢)からなり、ここに発生するがんを総称して胆道がんと呼びます。
膵臓がんと同様に黄疸が初期症状となることが多く、診断や治療が難しいがんです。
膵臓について理解を深めた今、隣接する臓器のがんについても知ることは、ご自身の体への理解をさらに深める一助となるでしょう。
もしご興味があれば、胆道がんに関する解説記事もあわせてご覧ください。
以上
参考文献
GHEORGHE, Gina, et al. Early diagnosis of pancreatic cancer: the key for survival. Diagnostics, 2020, 10.11: 869.
GOBBI, Paolo G., et al. The prognostic role of time to diagnosis and presenting symptoms in patients with pancreatic cancer. Cancer epidemiology, 2013, 37.2: 186-190.
WATANABE, Ichiro, et al. Onset symptoms and tumor locations as prognostic factors of pancreatic cancer. Pancreas, 2004, 28.2: 160-165.
WALTER, Fiona M., et al. Symptoms and patient factors associated with diagnostic intervals for pancreatic cancer (SYMPTOM pancreatic study): a prospective cohort study. The lancet Gastroenterology & hepatology, 2016, 1.4: 298-306.
KALSER, Martin H.; BARKIN, Jamie; MACINTYRE, John M. Pancreatic cancer. Assessment of prognosis by clinical presentation. Cancer, 1985, 56.2: 397-402.
KANJI, Zaheer S.; GALLINGER, Steven. Diagnosis and management of pancreatic cancer. Cmaj, 2013, 185.14: 1219-1226.
PRIMAVESI, Florian. Clinical Presentation and Symptoms in Pancreatic Cancer. In: Textbook of Pancreatic Cancer: Principles and Practice of Surgical Oncology. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 357-368.
MCGUIGAN, Andrew, et al. Pancreatic cancer: A review of clinical diagnosis, epidemiology, treatment and outcomes. World journal of gastroenterology, 2018, 24.43: 4846.
NARKHEDE, Rajvilas A., et al. Diagnosis and management of pancreatic adenocarcinoma in the background of chronic pancreatitis: core issues. Digestive Diseases, 2019, 37.4: 315-324.
STORNELLO, Caterina, et al. Diagnostic delay does not influence survival of pancreatic cancer patients. United European Gastroenterology Journal, 2020, 8.1: 81-90.
消化器系がんに戻る