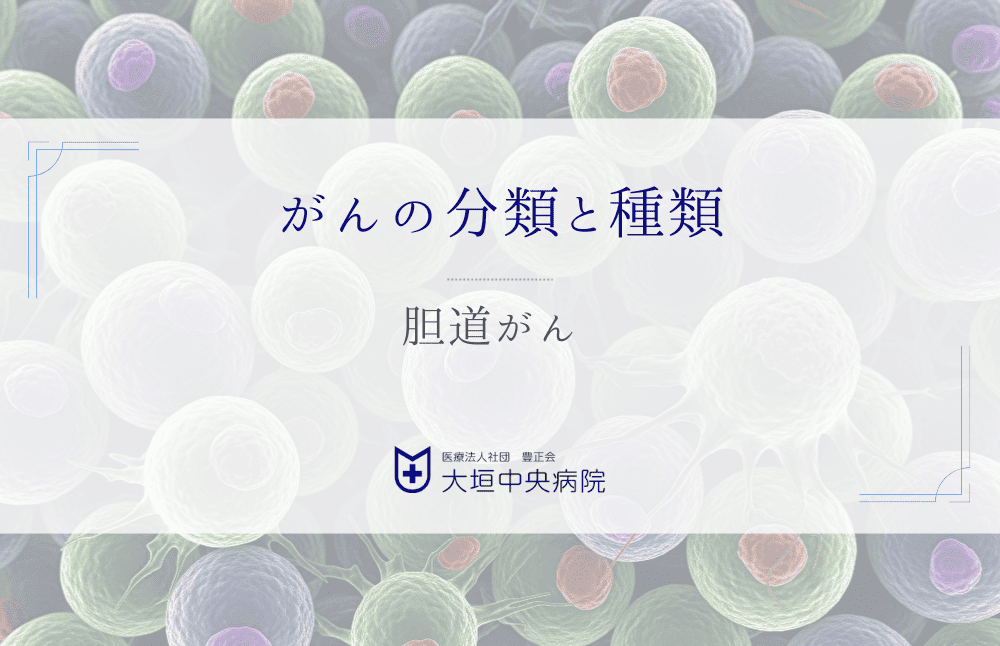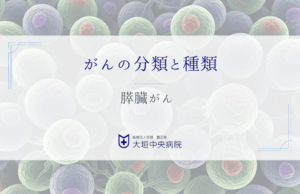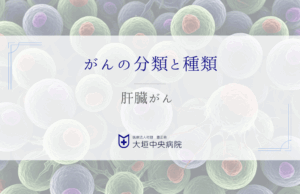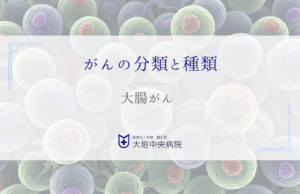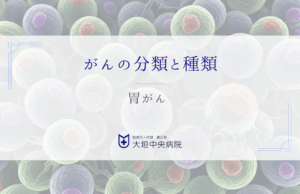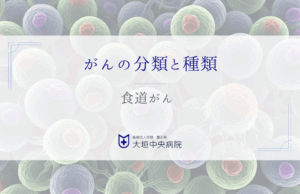胆道がんは、肝臓で作られた胆汁を十二指腸へ運ぶ「胆道」に発生する悪性腫瘍の総称です。発生部位によって胆管がんや胆嚢がんなどに分類され、それぞれ特徴が異なります。
初期症状が現れにくく、発見が難しいがんの一つですが、近年の診断技術や治療法の進歩は目覚ましいものがあります。
この記事では、胆道がんの基本的な知識から、診断、治療、そして療養生活のサポートに至るまで、患者さんとご家族が病気と向き合う上で必要な情報を、医学的知見に基づき詳しく解説します。
胆道がんの分類と発生部位別の特徴
胆道がんは一つの病気ではなく、発生した場所によっていくつかの種類に分けられます。それぞれの特徴を理解することは、ご自身の病状を把握する第一歩となります。
ここでは、がんがどこにでき、どのような性質を持つのかを詳しく見ていきましょう。
胆道がんとは – 発生部位による分類
胆道がんは、がんが発生した場所に応じて、大きく「胆管がん」「胆嚢がん」「十二指腸乳頭部がん」の3つに分類します。
特に胆管がんは、発生部位によってさらに細かく分けられ、治療方針も異なります。
肝内胆管がん
肝臓の中を走る細い胆管に発生するがんです。肝臓がん(肝細胞がん)とは区別されます。初期には症状が出にくく、進行すると肝機能の低下や腹痛などの症状が現れることがあります。
肝外胆管がん
肝臓の外にある比較的太い胆管に発生するがんです。がんができた場所によって、肝臓の出口付近にできる「肝門部領域胆管がん」と、十二指腸に近い側にできる「遠位胆管がん」に分けられます。胆汁の流れが塞がれやすいため、黄疸の症状で発見されることが多いのが特徴です。
胆嚢がん
胆汁を一時的に貯めておく袋状の臓器である胆嚢に発生するがんです。胆石を持つ人に発生するリスクが高いことが知られています。
早期の段階では自覚症状がほとんどなく、胆石症の手術の際に偶然発見されるケースもあります。進行すると腹痛や黄疸が見られます。
胆道がんの種類と特徴
| がんの種類 | 主な発生部位 | 比較的見られやすい初期症状 |
|---|---|---|
| 肝内胆管がん | 肝臓内の胆管 | 症状は出にくい、倦怠感 |
| 肝門部領域胆管がん | 肝臓の出口付近の胆管 | 黄疸、皮膚のかゆみ |
| 遠位胆管がん | 十二指腸に近い胆管 | 黄疸、腹痛、白色便 |
| 胆嚢がん | 胆嚢 | 症状は出にくい、右上腹部の違和感 |
| 十二指腸乳頭部がん | 胆管の十二指腸への出口 | 黄疸、発熱(胆管炎) |
胆道の構造と機能 – がん発生の背景を理解する
なぜこの場所にがんができるのか。その背景を理解するために、胆道の構造と働きについて知ることが大切です。
胆道は消化を助ける重要な役割を担っており、その複雑な構造が、がんの発生や進行に影響を与えます。
胆汁の通り道「胆道」
胆道は、肝臓で作られる消化液「胆汁」を、十二指腸まで運ぶ管(くだ)の総称です。肝臓内の無数の細い胆管から始まり、次第に合流して太い管となり、肝臓の外へ出ます。
肝臓の外で胆嚢と合流し、最終的に膵臓の中を通り、十二指腸乳頭部という場所で十二指腸に開口します。
胆嚢の役割
胆嚢は、肝臓の下に位置する西洋梨のような形をした臓器です。肝臓で作られた胆汁を一時的に貯蔵し、約5~10倍に濃縮する働きがあります。
食事、特に脂肪分の多い食物を摂取すると、胆嚢は収縮して濃縮した胆汁を胆管へ送り出し、消化を助けます。
胆道の主な機能
- 脂肪の消化・吸収の補助
- ビタミンの吸収促進
- 体内の不要な物質の排泄
胆道がんの発生原因
胆道がんの明確な原因は完全には解明されていませんが、いくつかの危険因子が指摘されています。最も重要なのは、胆道に長期間続く「慢性的な炎症」です。
炎症が繰り返されることで細胞が傷つき、修復の過程で遺伝子に異常が生じ、がん化につながると考えられています。
胆石や原発性硬化性胆管炎、膵・胆管合流異常症などが、慢性的な炎症を引き起こす代表的な原因です。
見落としがちな胆道がんの初期症状と警告サイン
胆道がんは「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」とも呼ばれるように、初期には特徴的な症状がほとんどありません。
しかし、注意深く観察すれば、体からの警告サインに気づくことができるかもしれません。ここでは、見落としてはならない症状について解説します。
黄疸 – 最も注意すべき症状
胆道がんの症状として最も特徴的なのが黄疸です。がんによって胆管が狭くなったり塞がれたりすると、胆汁が正常に流れなくなり、胆汁に含まれるビリルビンという黄色い色素が血液中に逆流します。
これにより、皮膚や眼球の白目の部分が黄色く染まります。尿の色が濃くなったり(褐色尿)、便の色が白っぽく(白色便)なったりすることもあります。
また、ビリルビンが皮膚に沈着することで、強いかゆみを生じることもあります。
腹痛や体重減少などの非特異的な症状
右上腹部の鈍い痛みや違和感、食欲不振、原因不明の体重減少、全身の倦怠感なども胆道がんの症状として現れることがあります。
しかし、これらの症状は他の多くの病気でも見られるため、胆道がんに特有のものではありません。そのため、胃の調子が悪いなどと考え、発見が遅れる原因にもなります。
症状が続く場合は、自己判断せずに医療機関を受診することが重要です。
胆道がんの進行度と主な症状
| 進行度 | 主な症状 | 解説 |
|---|---|---|
| 初期 | 無症状、または軽い倦怠感 | 自覚症状はほとんどないことが多い。 |
| 進行期 | 黄疸、腹痛、体重減少 | がんが大きくなり、胆管を圧迫したり周囲に広がったりすることで症状が現れる。 |
| 末期 | 強い腹痛、腹水、背部痛 | がんがさらに広がり、腹膜への転移(腹膜播種)や遠隔転移を起こすと重篤な症状が出る。 |
画像診断の重要性と胆道がん特有の検査法
症状から胆道がんが疑われた場合、次に行うのが画像検査です。
がんの存在を確かめ、その位置や広がり、転移の有無を正確に把握することが、適切な治療方針を立てる上で極めて重要になります。
診断の第一歩 – 腹部超音波検査
腹部超音波(エコー)検査は、体に負担が少なく、簡便に行えるため、最初に行うことが多い検査です。
胆嚢や肝臓、太い胆管の状態を観察し、胆嚢の壁が厚くなっていないか、胆管が拡張していないかなどを調べます。胆石の有無も確認できます。
がんの広がりを評価するCT・MRI検査
CT検査やMRI検査は、体の断面を撮影し、がんの正確な位置や大きさ、周囲の臓器への広がり(浸潤)、リンパ節や他の臓器への転移を評価するために行います。
造影剤を使用することで、より詳細な情報を得ることができます。
MRCP(磁気共鳴胆管膵管撮影)
MRIの技術を応用して、胆管や膵管の状態を立体的に描き出す検査です。体に管を入れることなく、胆管の狭窄や閉塞の様子を詳細に観察できるため、診断に非常に役立ちます。
確定診断のための精密検査
画像検査でがんが強く疑われた場合、最終的な確定診断のために、がん細胞の一部を採取して顕微鏡で調べる「病理診断」を行います。
そのための検査として、ERCPやPTCSがあります。
ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)
口から内視鏡を挿入し、十二指腸まで進め、胆管の出口から細い管を入れて造影剤を注入し、胆管の形をX線で撮影します。
同時に、胆管内の細胞や組織をブラシや鉗子で採取したり、胆汁を採取したりして、がん細胞の有無を調べます。
主な検査方法の目的と特徴
| 検査方法 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 腹部超音波検査 | スクリーニング、胆管拡張の確認 | 簡便で体に負担が少ない。 |
| CT検査 | がんの広がり、転移の評価 | 短時間で広範囲を撮影できる。 |
| MRI検査/MRCP | 胆管の詳細な観察、肝転移の評価 | 放射線被ばくがなく、胆管の描出に優れる。 |
| ERCP | 確定診断(組織採取)、黄疸の治療 | 直接胆管を観察・処置できるが、合併症のリスクもある。 |
胆道がんの病期と予後因子の医学的評価
検査によってがんが確定すると、次はその進行度、すなわち「病期(ステージ)」を決定します。
ステージは、がんの広がり具合を示すもので、治療方針の決定や、今後の病状の見通し(予後)を予測する上で重要な指標となります。
病期(ステージ)分類の考え方
胆道がんのステージは、国際的に用いられている「TNM分類」に基づいて決定します。これは、以下の3つの要素を組み合わせて評価するものです。
- T因子: がんが胆道壁のどの深さまで達しているか(深達度)
- N因子: 周囲のリンパ節への転移の有無と範囲
- M因子: 肝臓や肺など、離れた臓器への転移(遠隔転移)の有無
これらの組み合わせにより、早期のステージ0から最も進行したステージIVbまで分類します。
胆道がんのステージ分類の概要
| ステージ | がんの広がり(一般的な目安) |
|---|---|
| ステージI | がんが胆道壁内にとどまっている。 |
| ステージII | がんが胆道壁を越えて広がっているが、主要な血管には及んでいない。 |
| ステージIII | がんが周囲の主要な血管に広がっている。または、広範囲のリンパ節に転移がある。 |
| ステージIV | 離れた臓器に転移(遠隔転移)がある。 |
予後を左右する因子
胆道がんの予後、つまり今後の病状の見通しや生存率は、いくつかの因子によって影響を受けます。
最も重要な因子はステージですが、それ以外にも、手術でがんを完全に取り切れるか(根治切除の可否)、がんの悪性度の高さ(組織型)、患者さん自身の全身状態や栄養状態なども、予後に大きく関わります。
一般的に、ステージが進むほど予後は厳しくなる傾向にありますが、治療法の進歩により、進行がんでも長期生存できるケースが増えています。
部位・ステージ別の5年相対生存率(目安)
※全がん協加盟施設の生存率協同調査(2011-2013年診断症例)等のデータを基にした一般的な目安です。
生存率はあくまで多くの患者さんのデータの平均値であり、個々の患者さんの余命を示すものではありません。また、治療法の進歩により、数値は年々向上しています。
| ステージ | 胆嚢がん | 胆管がん(肝外) | 状態の目安 |
| I期 | 80〜90% | 70〜80% | がんが壁の浅い層にとどまる(早期) |
| II期 | 60〜70% | 40〜50% | 壁を越えて少し広がっている |
| III期 | 30〜40% | 20〜30% | リンパ節転移や周囲臓器への浸潤あり |
| IV期 | 3〜5% | 2〜3% | 遠隔転移あり、または手術困難な広がり |
外科治療の適応と手術の種類 – 根治性と安全性の両立
がんが他の臓器に転移しておらず、体力的に可能であれば、外科手術によるがんの切除が根治(完全に治すこと)を目指すための最も基本的な治療法となります。
胆道がんの手術は複雑で、高い技術を要します。
根治を目指す唯一の治療法 – 手術
手術の目的は、がん細胞を体の中から完全に取り除くことです。
そのため、がん本体だけでなく、がんが広がっている可能性のある周囲の組織やリンパ節も一緒に切除します(リンパ節郭清)。
手術が可能かどうかは、がんの進行度や患者さんの全身状態を総合的に評価して慎重に判断します。
発生部位に応じた手術方法
胆道がんの手術は、がんが発生した場所によって切除する範囲が大きく異なります。
胆嚢がんの手術
早期の胆嚢がんであれば、胆嚢を摘出するだけで済む場合があります。
しかし、がんが進行している場合は、胆嚢に隣接する肝臓の一部や、周囲のリンパ節、時には胆管も一緒に切除する「拡大胆嚢摘出術」が必要になります。
胆管がんの手術
胆管がんの手術は、がんの部位によって術式が大きく変わります。肝門部領域胆管がんでは、胆管と一緒に肝臓の広範囲(半分以上)を切除する「肝切除」を行います。
遠位胆管がんでは、胆管、十二指腸、膵臓の一部(膵頭部)をまとめて切除する「膵頭十二指腸切除術」という非常に大きな手術が必要となります。これらは消化器外科の中でも特に難易度の高い手術です。
胆道がんの主な手術方法
| がんの種類 | 主な手術方法 | 切除する主な臓器 |
|---|---|---|
| 胆嚢がん | 拡大胆嚢摘出術 | 胆嚢、肝臓の一部、リンパ節 |
| 肝門部領域胆管がん | 肝切除+胆管切除 | 肝臓(右葉または左葉以上)、胆管、リンパ節 |
| 遠位胆管がん | 膵頭十二指腸切除術 | 膵臓の一部、十二指腸、胆管、胆嚢、リンパ節 |
手術の合併症と再発リスク
胆道がんの手術は大規模になることが多く、術後に出血、感染、縫合不全(つなぎ目がうまくつかないこと)などの合併症が起こる可能性があります。
また、手術で目に見えるがんをすべて取り除いたとしても、画像検査ではわからない微小な転移が残っている可能性があり、術後に再発することがあります。
そのため、手術後も定期的な検査が必要です。
薬物療法の現状と治療効果の実際
手術でがんを取り除くことが難しい場合や、手術後に再発してしまった場合には、薬物療法(抗がん剤治療)が中心となります。
近年の薬物療法の進歩は著しく、治療の選択肢も増えています。
手術が難しい場合の化学療法
切除ができない進行胆道がんや、遠隔転移がある場合に行う化学療法の目的は、がんの進行を抑え、症状を和らげることで、できるだけ長く、より良い生活を送れるようにすることです。
治療効果や副作用を慎重に見ながら、治療を継続していきます。
標準的な化学療法のレジメン
現在、胆道がんに対する標準的な初回化学療法として推奨されているのは、「ゲムシタビン」と「シスプラチン」という2種類の抗がん剤を組み合わせる「GC療法」です。
この治療法は、がんを縮小させ、生存期間を延長する効果が証明されています。
GC療法の効果がなくなった場合や、副作用で続けられなくなった場合には、二次治療として別の抗がん剤(S-1など)を使用します。
主な化学療法薬と注意すべき副作用
| 薬剤名 | 主な副作用 |
|---|---|
| ゲムシタビン | 骨髄抑制(白血球・血小板減少)、吐き気、倦怠感、発熱 |
| シスプラチン | 強い吐き気、腎機能障害、聴力低下、末梢神経障害 |
| S-1(エスワン) | 下痢、口内炎、食欲不振、色素沈着 |
近年の進歩 – 分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬
最近では、がん細胞が持つ特定の遺伝子の変異を標的とする「分子標的薬」や、人間が本来持つ免疫の力でがんを攻撃する「免疫チェックポイント阻害薬」が登場し、治療成績の向上に貢献しています。
これらの薬を使用するためには、がん組織を用いて遺伝子検査を行い、薬の効果が期待できるタイプのがんかどうかを調べる必要があります。
すべての患者さんに使えるわけではありませんが、治療の新たな選択肢となっています。
術後補助化学療法
手術でがんを完全に取り除いた後でも、目に見えないがん細胞が残っていて再発する可能性があります。この再発のリスクを少しでも減らすために行うのが「術後補助化学療法」です。
手術後、半年から1年程度、抗がん剤治療を行います。これにより、再発率を下げ、生存率を改善する効果が期待できます。
黄疸管理と症状緩和の重要性
胆道がんの治療では、がんそのものと戦うと同時に、がんによって引き起こされる様々なつらい症状を和らげることも非常に重要です。
特に黄疸は、生活の質(QOL)を著しく低下させるため、積極的な管理が必要です。
胆道閉塞による黄疸への対処
がんによって胆管が塞がり黄疸が出現した場合、まず胆汁の流れを回復させる「胆道ドレナージ」という処置を行います。
これにより黄疸が改善すると、食欲が回復したり、全身状態が良くなったりして、化学療法などの本格的な治療を開始できるようになります。
胆道ドレナージの種類と選択
胆道ドレナージには、内視鏡を使う方法と、体の外から針を刺す方法があります。
内視鏡的胆道ドレナージ(ERBD/EBS)
口から内視鏡を入れ、胆管の詰まっている部分に「ステント」と呼ばれる細い管を留置して、胆汁の流れ道を確保する方法です。
体外にチューブが出ないため、日常生活への影響が少ないのが利点です。
経皮経肝胆道ドレナージ(PTBD)
体の右側から、皮膚、肝臓を通して胆管に直接チューブを挿入し、体外に胆汁を排出する方法です。内視鏡での処置が難しい場合などに行います。
チューブを常に体外に留置する必要があるため、管理が必要です。
胆道ドレナージの種類と特徴
| 処置方法 | アプローチ | 特徴 |
|---|---|---|
| 内視鏡的ドレナージ | 口から(内視鏡) | 体への負担が比較的少ない。体外にチューブが出ない。 |
| 経皮経肝的ドレナージ | 体の外から(穿刺) | 確実性が高いが、体外にチューブを留置する必要がある。 |
痛みや倦怠感に対する緩和ケア
がんによる腹痛や背部痛、倦怠感、食欲不振などの症状は、患者さんの心身に大きな苦痛を与えます。
緩和ケアは、これらの症状を医療用麻薬などの鎮痛薬や様々な工夫で積極的に和らげ、患者さんが自分らしい生活を送れるように支援する医療です。
緩和ケアは終末期だけでなく、がんと診断された早期の段階から、がん治療と並行して行うことが大切です。
胆道がんと診断された患者・家族への支援体制
がんと診断されると、患者さん本人だけでなく、ご家族も大きな不安や戸惑いを抱えます。病気や治療のこと、今後の生活のことなど、様々な悩みに直面します。
一人で抱え込まず、利用できる様々なサポートを活用することが大切です。
精神的なサポートと情報提供
多くの病院には「がん相談支援センター」が設置されています。
ここでは、専門の相談員(看護師やソーシャルワーカーなど)が、病気に関する医学的な質問から、治療費の心配、心の悩みまで、無料で相談に応じてくれます。
正しい情報に基づき、今後のことを整理していく手助けをします。
医療ソーシャルワーカーとの連携
医療ソーシャルワーカーは、療養生活に伴う経済的、社会的な問題の解決を支援する専門家です。
高額療養費制度や障害年金などの社会保障制度の活用について、具体的なアドバイスを提供します。
患者会やサロンの活用
同じ病気を経験した人々と話すことは、大きな心の支えになります。
患者会やがんサロンでは、治療の経験や副作用の対処法など、実用的な情報を交換したり、共感し合ったりすることで、孤独感を和らげることができます。
利用できる主な支援リソース
- がん相談支援センター(各がん診療連携拠点病院など)
- 医療ソーシャルワーカー(病院の相談室など)
- 患者会・患者サロン
- 公的な相談窓口(保健所など)
よくある質問
- 胆道がんの生存率はどのくらいですか?
-
胆道がんの5年相対生存率は、がん全体の平均と比較すると低い傾向にあり、全体で約25%程度です。
しかし、これはあくまで統計上の数値であり、ステージによって大きく異なります。ステージIで発見され、根治的な手術ができた場合の5年生存率は50%を超えます。
早期発見と適切な治療が予後を改善する鍵となります。
- 胆石があると胆嚢がんになりますか?
-
胆石があることは、胆嚢がんの危険因子の一つとされています。特に、長期間胆石を持っている場合や、胆嚢壁に石灰化が見られる「陶器様胆嚢」の場合は、リスクが高まると考えられています。
しかし、胆石を持つ人のうち、実際に胆嚢がんになるのはごく一部です。過度に心配する必要はありませんが、定期的に腹部超音波検査を受けることが推奨されます。
- 治療中の食事で気をつけることはありますか?
-
胆道がんの治療中、特に黄疸がある場合や手術後は、脂肪の消化吸収能力が低下することがあります。
そのため、天ぷらやフライなどの油っこい食事は控えめにし、消化の良い、バランスの取れた食事を心がけることが大切です。
食欲がない時は、無理せず食べられるものを少量ずつ、回数を分けて摂取するなどの工夫をしましょう。栄養状態を良好に保つことが、治療を乗り切る体力につながります。
胆道は、膵臓の中を貫通して十二指腸につながるなど、膵臓と解剖学的に非常に密接な関係にあります。
そのため、胆道がんとすい臓がんは、症状や検査、治療法において共通点が多く見られます。特に、遠位胆管がんと膵頭部がんは、発生部位が近いため、鑑別が難しいこともあります。
胆道がんについて理解を深めるとともに、関連の深い「すい臓がん」についても知ることは、ご自身の病状や治療への理解をより一層深める助けとなるでしょう。
以上
参考文献
PARK, Chan Su, et al. Prognostic factors in patients treated with pembrolizumab as a second-line treatment for advanced biliary tract cancer. Cancers, 2022, 14.17: 4323.
GOTO, Takuma, et al. High response rate and prolonged survival of unresectable biliary tract cancer treated with a new combination therapy consisting of intraarterial chemotherapy plus radiotherapy. Frontiers in Oncology, 2020, 10: 597813.
CHEN, Yong, et al. The combination of radiation therapy and immunotherapy is effective and well-tolerated for unresectable biliary tract cancer. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 2022, 113.4: 816-824.
LI, Zhihao, et al. Recent advances in systemic therapy for advanced biliary tract cancer: A systematic review and meta-analysis using reconstructed RCT survival data. JHEP Reports, 2025, 7.3: 101290.
NGHIEM, Van, et al. Short-and long-term survival of metastatic biliary tract cancer in the United States from 2000 to 2018. Cancer Control, 2023, 30: 10732748231211764.
WANG, Fang, et al. Assessing the prognostic value of 13 Inflammation-Based scores in patients with unresectable or advanced biliary tract carcinoma after immunotherapy. ImmunoTargets and Therapy, 2024, 541-557.
AMIT, Uri, et al. Clinical outcomes and risk stratification in unresectable biliary tract cancers undergoing radiation therapy. Radiation Oncology, 2024, 19.1: 102.
BOILEVE, Alice, et al. Immunotherapy in advanced biliary tract cancers. Cancers, 2021, 13.7: 1569.
RAMIREZ, DE Renteria, et al. Prognosis related to treatment plan in patients with biliary tract cancer: A nationwide database study. Cancer epidemiology, 2024, 93: 102688.
SUZUKI, Hideo, et al. Prognostic Significance of Lymphocyte-to-Monocyte Ratio in Patients With Unresectable Biliary Tract Cancer Undergoing Systemic Chemotherapy. Cancer Diagnosis & Prognosis, 2025, 5.1: 132.
消化器系がんに戻る