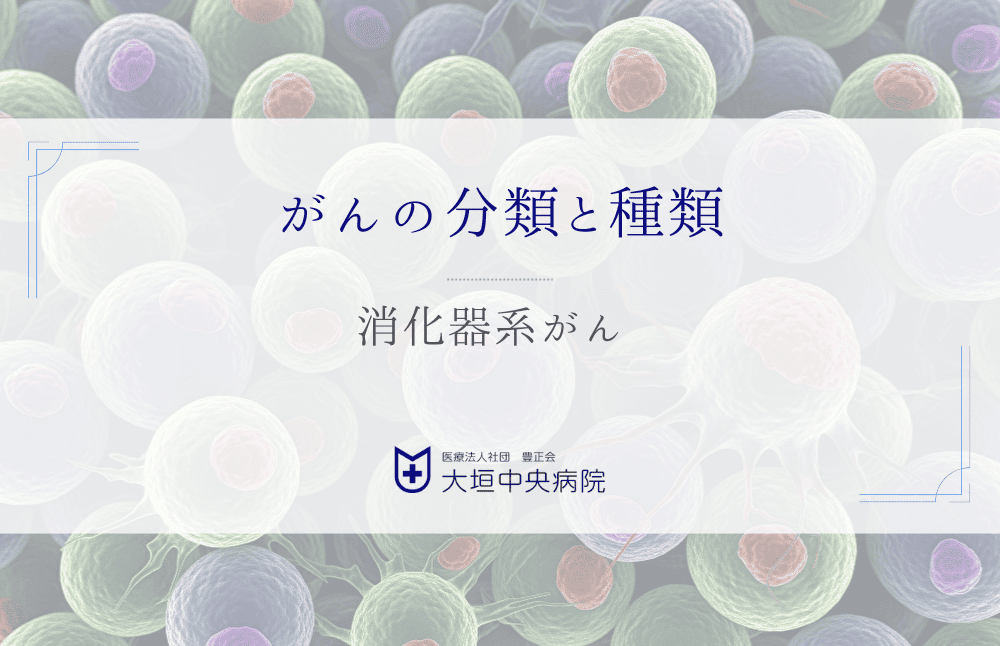消化器系がんは、食道、胃、大腸、肝臓、膵臓、胆道など、食べ物の通り道や消化に関わる臓器に発生するがんの総称です。
日本では、胃がんや大腸がんの罹患率が高く、多くの人が関心を寄せています。早期発見・早期治療が重要ですが、そのためには、がんの種類ごとの特徴や症状、検査方法について正しく知ることが大切です。
この記事では、それぞれの消化器系がんについて、基本的な情報から治療の選択肢までを分かりやすく解説します。ご自身やご家族の健康を守るための知識として、ぜひお役立てください。
食道がん
食道は、喉と胃をつなぐ管状の臓器で、食べ物を胃へ送る役割を担います。この食道の粘膜から発生するがんが食道がんです。
日本では男性に多く、特に飲酒と喫煙が大きなリスク要因として知られています。早期の段階では自覚症状がほとんどないため、リスクのある人は定期的な検診が重要です。
食道がんとは
食道がんの約90%は扁平上皮(へんぺいじょうひ)がんという種類です。
食道の壁は内側から粘膜、粘膜下層、固有筋層、外膜という層構造になっており、がんは最も内側の粘膜から発生し、進行するにつれて外側の層へと深く広がっていきます。
また、周囲のリンパ節や、肺、肝臓などの他の臓器に転移することもあります。
原因とリスク
食道がんの発生には、生活習慣が深く関わっています。特に、長期間にわたる飲酒と喫煙の習慣は、リスクを著しく高めることが分かっています。
アルコールを摂取すると体内でアセトアルデヒドという発がん性物質に分解されますが、この物質を分解する酵素の働きが弱い人は、食道がんになりやすい傾向があります。
熱い飲食物を頻繁に摂る習慣も、食道粘膜への刺激となり、リスクを高める可能性があります。
症状
早期の食道がんでは、症状を感じることはほとんどありません。がんが進行すると、食べ物がつかえる感じや、飲み込むときの違和感、胸の痛みなどが現れます。
さらに進行すると、声のかすれ(嗄声)、体重減少、胸や背中の痛みなどが生じることがあります。
これらの症状は他の病気でも起こり得ますが、気になる症状が続く場合は専門医に相談することが大切です。
検査と診断
食道がんが疑われる場合、まず内視鏡検査(胃カメラ)を行います。内視鏡で食道の粘膜を直接観察し、疑わしい部分があれば組織を採取して病理検査(生検)を行い、がん細胞の有無を確定します。
がんの広がりや転移の有無を調べるためには、CT検査やMRI検査、超音波内視鏡検査(EUS)、PET検査など、複数の画像検査を組み合わせて総合的に判断します。
食道がんのステージと治療法
| ステージ | がんの状態 | 主な治療法 |
|---|---|---|
| 0期 | がんが粘膜内にとどまる | 内視鏡治療 |
| I期 | がんが粘膜下層までにとどまる | 内視鏡治療、手術、化学放射線療法 |
| II期 - III期 | がんが筋層より深く広がる、またはリンパ節転移がある | 手術、化学放射線療法、化学療法 |
治療法
食道がんの治療は、がんの進行度(ステージ)、体の状態、年齢などを考慮して決定します。
治療法には、内視鏡治療、手術、放射線治療、薬物療法(化学療法)があり、これらを単独または組み合わせて行います。
ステージ0やI期の一部では、内視鏡でがんを切除する治療が可能です。
がんがより進行している場合は、食道と周囲のリンパ節を切除する手術や、放射線と抗がん剤を併用する化学放射線療法が中心となります。
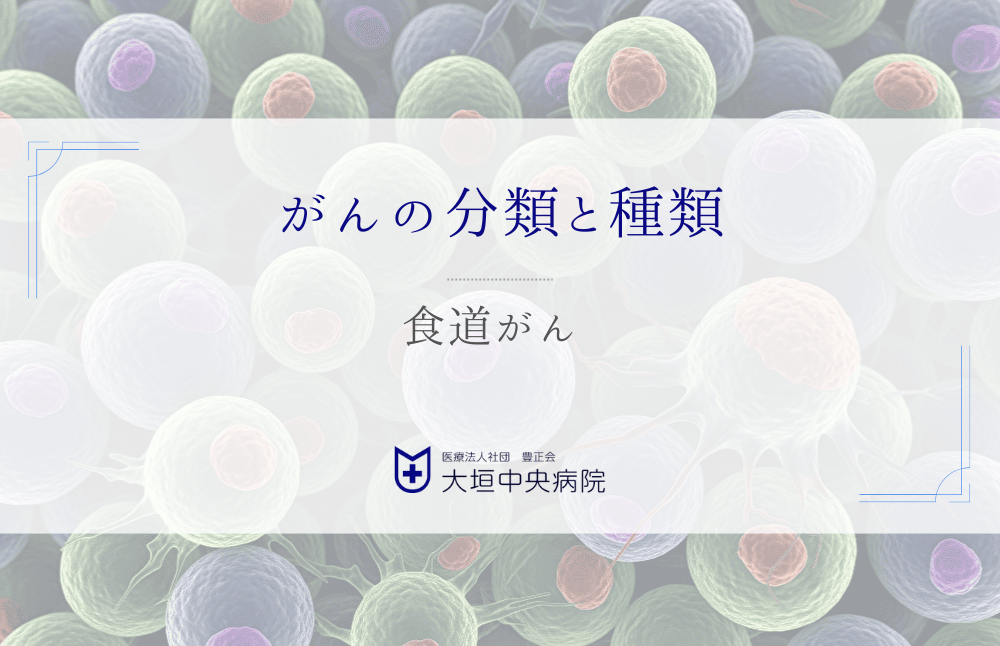
胃がん
胃がんは、胃の壁の最も内側にある粘膜の細胞が、何らかの原因でがん細胞に変化する病気です。
かつては日本人に最も多いがんでしたが、近年は診断技術の進歩やピロリ菌の除菌治療の普及により、死亡率は減少傾向にあります。
しかし、依然として罹患率は高く、早期発見が重要ながんの一つです。
胃がんの概要
胃がんの多くは「腺がん」という種類で、胃液などを分泌する腺細胞から発生します。
がんは胃の粘膜から発生し、徐々に胃壁の奥深くへと浸潤し、やがて胃の外側にある臓器にまで広がったり、リンパ液や血液の流れに乗って他の臓器へ転移したりします。
進行の仕方によって、特定の場所に固まって増殖する「限局型」と、胃壁の中にしみ込むように広がっていく「びまん型」に大別されます。
原因と予防
胃がんの最大の原因は、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の持続的な感染です。ピロリ菌が胃に感染すると慢性的な炎症が起こり、胃の粘膜が萎縮する「萎縮性胃炎」という状態になります。
この状態が長く続くと、胃がんが発生しやすくなると考えられています。その他、塩分の多い食事、喫煙などもリスク要因とされています。
ピロリ菌の検査と除菌治療は、胃がんの予防に有効です。
主な症状
早期の胃がんには特有の症状はありません。胃炎や胃潰瘍と似たような、胃の不快感、胸やけ、食欲不振などが現れることもありますが、症状がないまま進行することも少なくありません。
進行すると、胃の痛み、吐き気、体重減少、黒い便(タール便)などの症状が出ることがあります。
これらの症状は胃がん以外の病気でも起こるため、自己判断せずに医療機関を受診することが必要です。
検査方法
胃がんの検査では、内視鏡検査(胃カメラ)とX線検査(バリウム検査)が一般的です。
内視鏡検査は、胃の内部を直接観察できるため、小さな病変の発見に優れており、同時に組織を採取して病理検査で確定診断ができます。X線検査は、胃の形や粘膜の状態を大まかに把握するのに役立ちます。
がんと診断された場合は、CT検査などでがんの深さや転移の有無を調べ、進行度を決定します。
胃がんの進行度と治療法
| 進行度 | がんの状態 | 主な治療法 |
|---|---|---|
| 早期がん | がんが粘膜または粘膜下層にとどまる | 内視鏡治療、手術 |
| 進行がん | がんが筋層より深くに達する | 手術、薬物療法 |
| 転移がある場合 | 他の臓器に転移している | 薬物療法 |
治療の選択肢
胃がんの治療法は、がんの進行度や全身の状態に基づいて決定します。がんが粘膜内にとどまり、リンパ節転移の可能性が極めて低い場合は、内視鏡的切除術(ESD)で胃を温存した治療が可能です。
がんがもう少し進行している場合は、がんを含む胃の一部または全部と、周囲のリンパ節を切除する手術が標準的な治療となります。
手術が難しい場合や、再発・転移した場合には、薬物療法(化学療法や分子標的薬など)を行います。
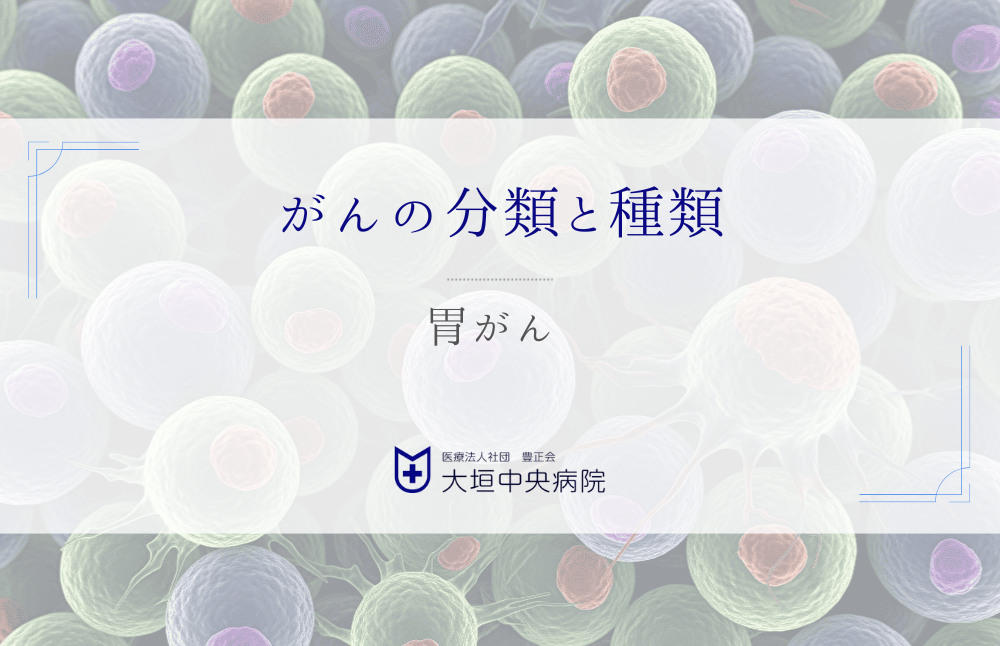
大腸がん
大腸がんは、長さ約2メートルの大腸(結腸・直腸)に発生するがんです。食生活の欧米化などに伴い、日本でも罹患者数・死亡者数ともに増加傾向にあります。
多くはポリープががん化して発生するため、ポリープの段階で切除することで予防が可能です。早期に発見すれば治癒率が非常に高いがんの一つであり、定期的な検診の受診が推奨されます。
大腸がんについて
大腸は結腸と直腸に分けられ、結腸にできるがんを結腸がん、直腸にできるがんを直腸がんと呼び、両方を合わせて大腸がんといいます。
大腸がんの発生には二つの経路があり、一つは良性のポリープ(腺腫)が徐々に大きくなり、その一部ががん化する経路、もう一つは正常な粘膜から直接がんが発生する経路です。
多くは前者の腺腫から発生すると考えられています。
リスクを高める要因
大腸がんのリスクを高める要因としては、食生活、運動不足、肥満、喫煙、過度の飲酒などが挙げられます。
特に、赤肉(牛・豚・羊など)や加工肉の過剰摂取、食物繊維の摂取不足といった食生活の乱れが関与していると考えられています。
また、家族に大腸がんになった人がいる場合や、遺伝性の疾患(家族性大腸腺腫症など)がある場合は、リスクが高まることが知られています。
自覚症状
早期の大腸がんでは、ほとんど自覚症状がありません。進行すると、血便、便通の異常(便秘や下痢を繰り返す)、便が細くなる、残便感、腹痛、お腹の張りなどの症状が現れることがあります。
肛門に近い直腸にがんができた場合は、血便などの症状が比較的早期から現れやすいですが、結腸がんの場合は症状が出にくく、進行してから見つかることも少なくありません。
貧血や体重減少をきっかけに発見されることもあります。
検査と診断
大腸がん検診として広く行われているのが、便潜血検査です。
これは、便に血液が混じっていないかを調べる簡単な検査で、陽性となった場合は精密検査として大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を行います。
大腸内視鏡検査は、肛門から内視鏡を挿入し、大腸の内部を直接観察する検査です。ポリープやがんが発見された場合は、その場で組織を採取したり、小さなポリープであれば切除したりすることも可能です。
大腸がん検診の種類と特徴
| 検査名 | 方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 便を採取して提出する | 簡単で体への負担が少ない一次検診 |
| 大腸内視鏡検査 | 肛門から内視鏡を挿入する | 大腸全体を直接観察でき、診断と治療を同時に行える |
| 注腸X線検査 | 肛門からバリウムと空気を注入する | 大腸全体の形や大きさ、病変の位置を把握できる |
治療の進め方
大腸がんの治療は、内視鏡治療、手術、薬物療法、放射線治療をがんの進行度に応じて使い分けます。ごく早期のがんであれば、大腸内視鏡を用いてがんを切除できます。
がんが粘膜下層より深く浸潤している場合は、がんのある腸管と周囲のリンパ節を切除する手術が必要です。
直腸がんでは、手術の前後に薬物療法や放射線治療を組み合わせて、再発を防いだり、肛門を温存したりする工夫をします。転移がある場合は、薬物療法が治療の中心となります。
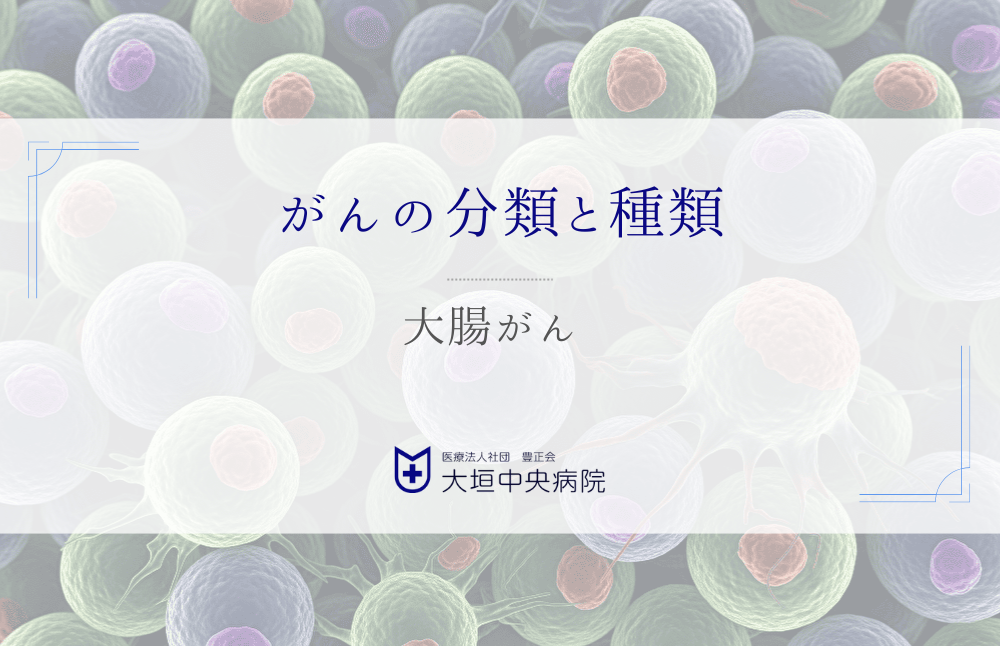
肝臓がん
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、病気がかなり進行するまで症状が現れにくい特徴があります。
肝臓がんは、肝臓の細胞から発生するがんで、その多くは肝炎ウイルスの持続感染による慢性肝炎や肝硬変を背景として発生します。
そのため、肝臓がんの治療では、がんそのものへの治療と同時に、肝臓の機能をいかに維持するかという点が重要になります。
肝臓がんの種類
肝臓にできるがんには、肝臓の細胞ががん化する「原発性肝がん」と、他の臓器にできたがんが肝臓に転移する「転移性肝がん」があります。一般的に肝臓がんという場合、原発性肝がんを指します。
原発性肝がんの9割以上は、肝細胞から発生する「肝細胞がん」で、残りは肝臓の中の胆管から発生する「肝内胆管がん」です。
主な原因
日本の肝細胞がんの最大の原因は、C型肝炎ウイルス(HCV)およびB型肝炎ウイルス(HBV)の持続感染です。
これらのウイルスに感染すると、肝臓に慢性的な炎症が起こり、肝硬変へと進行し、その過程でがんが発生します。
近年はウイルス性肝炎に対する治療が進歩したため、ウイルス感染を原因とする肝臓がんは減少傾向にあります。
一方で、飲酒や肥満、糖尿病などを背景とした非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)からの肝臓がんが増加しており、注意が必要です。
症状の現れ方
肝臓は予備能力が高いため、がんが小さいうちはほとんど症状がありません。
がんが進行したり、背景にある肝硬変が悪化したりすると、腹部のしこりや圧迫感、痛み、発熱、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、腹水(お腹に水がたまる)、むくみ、体重減少などの症状が現れます。
肝硬変が進行している場合は、吐血や意識障害などを起こすこともあります。
診断までの流れ
肝臓がんの診断では、まず腹部超音波(エコー)検査を行います。
この検査でがんが疑われた場合は、造影剤を用いたCT検査やMRI検査といった精密な画像検査で、がんの大きさや個数、性質などを詳しく調べます。
また、血液検査で腫瘍マーカー(AFP、PIVKA-II)を測定することも診断の助けになります。これらの検査で診断が確定できない場合は、お腹に針を刺して肝臓の組織を採取する肝生検を行うこともあります。
肝臓がんの主な治療法
| 治療法 | 対象 | 概要 |
|---|---|---|
| 肝切除術 | がんが3個以下で肝機能が良好な場合 | がんを含む肝臓の一部を切除する手術 |
| ラジオ波焼灼療法 | がんが3cm・3個以下の場合 | 針を刺してラジオ波でがんを焼き固める治療 |
| 肝動脈化学塞栓療法 | がんが複数ある、または切除・焼灼が困難な場合 | がんを栄養する血管を詰まらせて兵糧攻めにする治療 |
治療法の概要
肝臓がんの治療は、がんの進行度(大きさ、個数、転移の有無)と、肝機能の状態(肝障害度)を総合的に評価して決定します。
主な治療法は、手術(肝切除)、ラジオ波焼灼療法(RFA)、肝動脈化学塞栓療法(TACE)の三つです。肝機能が保たれており、がんの個数が少ない場合は、根治を目指せる肝切除やRFAを選択します。
これらが難しい場合はTACEを行います。さらに進行した場合には、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬による薬物療法を行います。
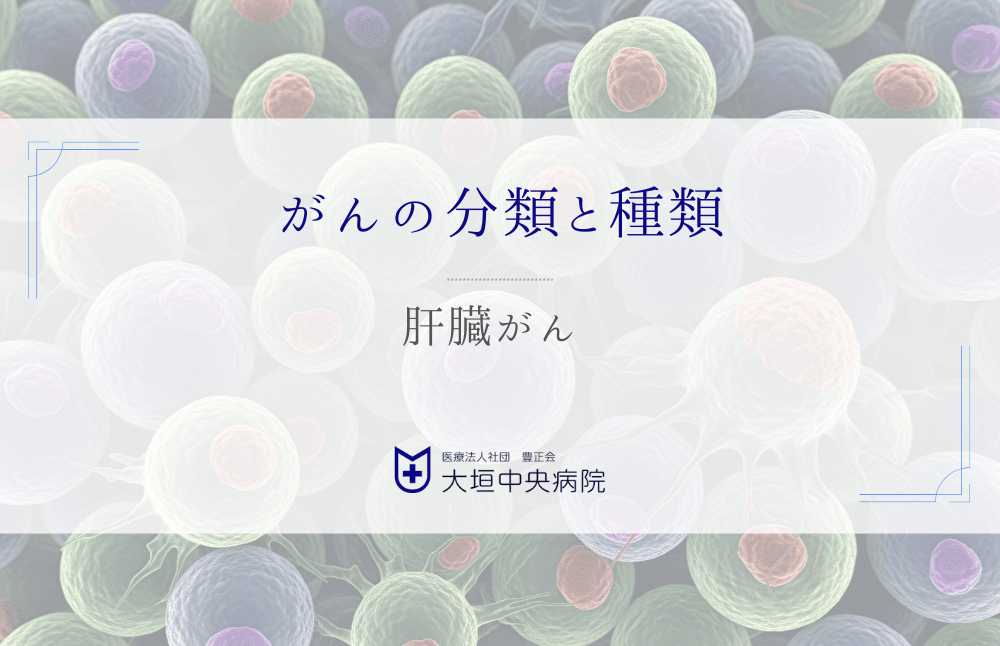
膵臓がん
膵臓は、胃の後ろ側にある長さ15cmほどの臓器で、消化酵素を含む膵液を分泌する(外分泌機能)とともに、血糖値を調節するインスリンなどのホルモンを分泌する(内分泌機能)重要な役割を担っています。
この膵臓にできるがんが膵臓がんで、非常に発見が難しく、進行が速いことから「難治がん」の代表とされています。
膵臓がんの特徴
膵臓がんは、初期症状がほとんどなく、症状が出たときにはすでに進行していることが多いのが特徴です。
また、体の深い部分にあるため、通常の検診などでは見つけにくく、診断が難しいことも治療を困難にする一因です。
がんの進行が速く、周囲の重要な血管や臓器に広がりやすいうえ、早期から他の臓器に転移しやすい性質を持っています。
危険因子
膵臓がんの確実な危険因子とされているのは喫煙です。その他、家族に膵臓がんになった人がいる(家族歴)、肥満、慢性膵炎、糖尿病などもリスクを高めることが知られています。
特に、急に糖尿病を発症したり、これまで安定していた糖尿病が急に悪化したりした場合は、膵臓がんが隠れている可能性も考えられるため、注意が必要です。
膵臓がんのリスク要因
- 喫煙
- 家族歴
- 肥満
- 慢性膵炎
- 糖尿病
初期症状
膵臓がんの初期には、特徴的な症状はありません。進行してくると、腹痛や背中の痛み、食欲不振、体重減少などが現れます。
がんが膵臓の頭部(十二指腸側)にできると、胆管を圧迫して胆汁の流れが悪くなり、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)が比較的早い段階で現れることがあります。
これは膵臓がんを発見する重要な手がかりとなります。体部や尾部(脾臓側)にがんができた場合は、症状が出にくく、発見が遅れる傾向があります。
診断方法
膵臓がんが疑われる場合、腹部超音波検査やCT検査、MRI検査などの画像検査を行います。中でも、造影剤を使ったCT検査は、がんの存在や広がりを評価するために重要です。
より詳しく調べるためには、超音波内視鏡検査(EUS)や内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)といった専門的な検査を行います。
EUSは、内視鏡の先端についた超音波装置で、胃や十二指腸の中から膵臓を詳しく観察する検査で、小さな病変の発見に優れています。
膵臓がんの主な検査
| 検査名 | 目的 | 内容 |
|---|---|---|
| 造影CT/MRI検査 | がんの存在、位置、広がり、転移の評価 | 造影剤を注射してX線や磁気で撮影する |
| 超音波内視鏡検査 (EUS) | 小さな病変の発見、組織の採取 | 内視鏡で胃や十二指腸から膵臓を観察する |
| ERCP | 膵管や胆管の観察、組織や細胞の採取 | 内視鏡を使い膵管や胆管に造影剤を注入する |
治療の選択
膵臓がんの治療は、手術、薬物療法(化学療法)、放射線治療を組み合わせて行います。唯一、根治が期待できる治療法は手術ですが、発見時に手術が可能な患者さんは全体の20%程度にとどまります。
手術ができない場合や、手術後に再発を防ぐ目的で、薬物療法が中心となります。近年、効果の高い抗がん剤が複数登場し、治療成績は向上しつつあります。
放射線治療は、痛みなどの症状を和らげる目的や、薬物療法と組み合わせて行われることがあります。
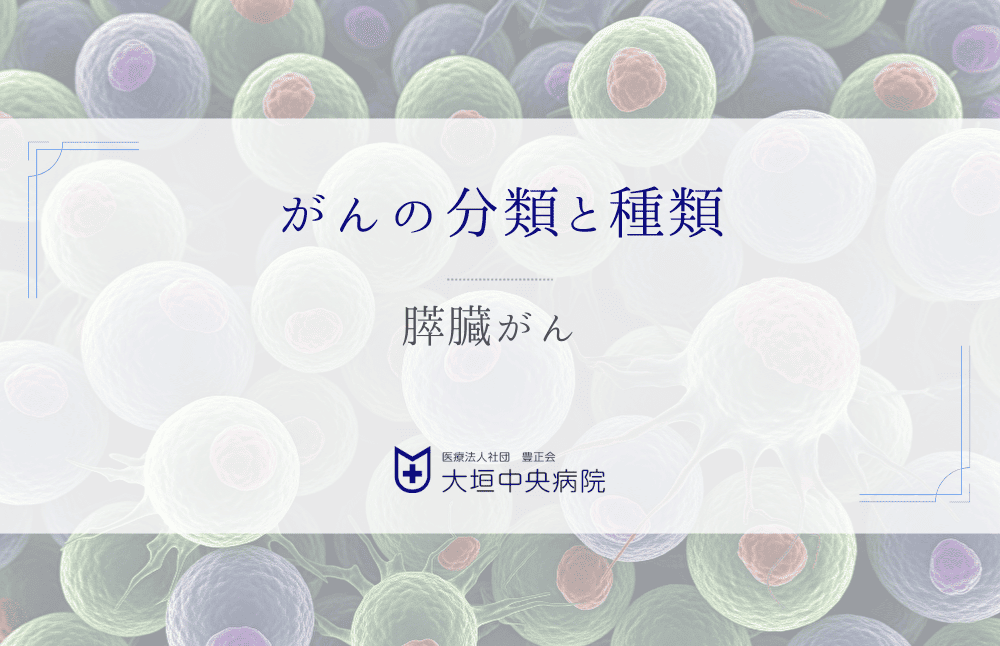
胆道がん
胆道は、肝臓で作られた胆汁を十二指腸まで運ぶ管(胆管)と、胆汁を一時的に貯めておく袋(胆のう)の総称です。この胆道に発生するがんを胆道がんと呼びます。
発生する場所によって、胆のうがん、胆管がん(肝内胆管がん、肝門部領域胆管がん、遠位胆管がん)に分類されます。膵臓がんと同様に、早期発見が難しく、治療が難しいがんの一つです。
胆道がんとは
胆道がんは、胆汁の通り道である胆管や、胆汁を蓄える胆のうの上皮から発生する悪性腫瘍です。日本では、人口10万人あたりの死亡率が比較的高いがんとして知られています。
解剖学的に周囲に肝臓、膵臓、十二指腸、主要な血管などが密集しているため、進行するとこれらの臓器に広がりやすく、手術が複雑になることがあります。
考えられる原因
胆道がんの発生原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかのリスク要因が指摘されています。胆のうがんでは、胆石や、陶器のように硬くなる陶器様胆のうがリスクとされています。
胆管がんでは、先天的な奇形である膵・胆管合流異常症や、原発性硬化性胆管炎という病気がリスクを高めることが分かっています。
また、特定の化学物質への曝露も原因となることが報告されています。
主な症状
胆道がんの最も特徴的な症状は黄疸です。がんによって胆管が塞がれ、胆汁が流れにくくなることで起こります。黄疸に伴い、皮膚のかゆみ、濃い色の尿、白っぽい便などの症状が現れます。
胆のうがんの場合は、初期には症状はほとんどありませんが、進行すると右上腹部の痛みやしこり、食欲不振、体重減少などがみられることがあります。
胆管炎を併発すると、発熱や悪寒、腹痛(右上腹部痛)が起こります。
検査と診断
黄疸などの症状から胆道がんが疑われる場合、まず腹部超音波検査や血液検査を行います。
次に、CT検査やMRI検査(特にMRCPという胆管や膵管を詳しく見る撮影法)で、がんの場所や広がり、周辺臓器への影響を詳しく評価します。
診断を確定するためには、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)や経皮経肝胆道ドレナージ(PTCD)といった手技を用いて、胆管内の組織や細胞を採取して調べることが必要です。
胆道がんの発生部位と特徴
| 部位 | 特徴 | 主な初期症状 |
|---|---|---|
| 胆のうがん | 胆汁を貯める袋に発生。胆石を持つ人に多い傾向。 | 症状が出にくい。進行すると腹痛など。 |
| 肝門部領域胆管がん | 肝臓の出口付近の太い胆管に発生。 | 黄疸が出やすい。 |
| 遠位胆管がん | 膵臓の中を通る下流の胆管に発生。 | 黄疸が出やすい。 |
治療法
胆道がんの治療の基本は、がんを切除する手術です。手術が可能であれば、がんが発生した部位に応じて、胆のう、胆管、肝臓の一部、膵臓の一部などを周囲のリンパ節とともに切除します。
手術が難しい場合や、手術後の再発予防、再発した場合の治療として、薬物療法(化学療法)が行われます。放射線治療は、症状緩和などの目的で行われることがあります。
黄疸がある場合は、まず内視鏡や体外からチューブを入れて胆汁の流れを良くする処置(ドレナージ)を行います。
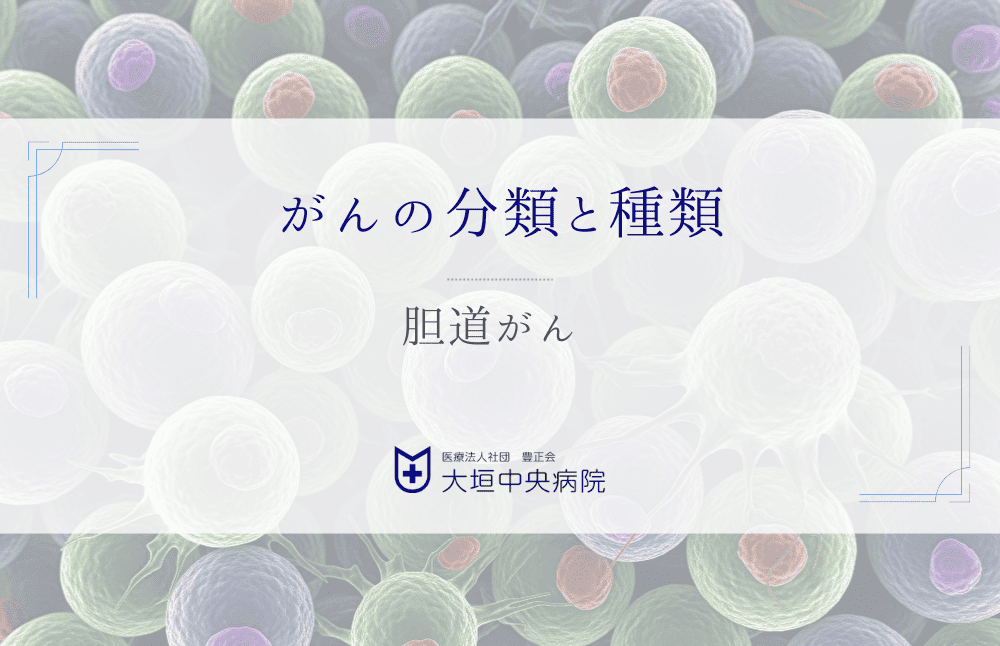
よくある質問
- 消化器系がんの予防はできますか?
-
すべてのがんを完全に予防する方法はありませんが、リスクを減らすことは可能です。胃がんにおけるピロリ菌の除菌、肝臓がんにおける肝炎ウイルス治療は非常に有効な予防策です。
また、多くの消化器系がんに共通するリスク要因として、喫煙、過度の飲酒、偏った食生活、肥満などが挙げられます。
禁煙、節度ある飲酒、バランスの取れた食事、適度な運動を心がけることが、がんの予防につながります。
- 治療中の食事で気をつけることは何ですか?
-
治療内容やがんの種類、患者さん個々の状態によって注意点は異なります。例えば、胃や食道の手術後は、消化しやすいように少量ずつ頻回に分けて食べる工夫が必要です。
大腸の手術後は、腸の負担を減らすため、一時的に食物繊維を控えることもあります。薬物療法中は、副作用で食欲が落ちたり、味覚が変わったりすることもあります。
基本的には、栄養バランスの取れた食事を、無理なく食べられる範囲で摂ることが大切です。詳しくは主治医や管理栄養士に相談してください。
- 遺伝は関係しますか?
-
ほとんどの消化器系がんは遺伝とは関係なく発生しますが、一部に遺伝が強く関わるものがあります。
「遺伝性腫瘍」と呼ばれ、特定の遺伝子の変異が親から子へ受け継がれることで、がんになりやすい体質となるものです。大腸がんでは「リンチ症候群」や「家族性大腸腺腫症」が知られています。
血縁者に若くしてがんになった人が多いなど、遺伝が心配な場合は、遺伝カウンセリングなどで相談することもできます。
がんには消化器系以外にも、さまざまな種類があります。肺や気管支など、呼吸に関わる臓器に発生する「呼吸器系がん」も、日本人にとって注意が必要ながんの一つです。
特に肺がんは、喫煙との関連が深いことで知られていますが、非喫煙者でも発症することがあります。
呼吸器系がんの種類や症状、最新の治療法について理解を深めることは、ご自身や大切な人の健康を守る上で重要です。下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
以上
参考文献
YUSEFI, Ali Reza, et al. Risk factors for gastric cancer: a systematic review. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP, 2018, 19.3: 591.
HERSZENYI, Laszlo; TULASSAY, Zsolt. Epidemiology of gastrointestinal and liver tumors. European Review for Medical & Pharmacological Sciences, 2010, 14.4.
ESO, Yuji; SENO, Hiroshi. Current status of treatment with immune checkpoint inhibitors for gastrointestinal, hepatobiliary, and pancreatic cancers. Therapeutic advances in gastroenterology, 2020, 13: 1756284820948773.
CREW, Katherine D.; NEUGUT, Alfred I. Epidemiology of upper gastrointestinal malignancies. In: Seminars in oncology. WB Saunders, 2004. p. 450-464.
VALLE, Juan W., et al. Biliary tract cancer. The Lancet, 2021, 397.10272: 428-444.
NAEMI, Amin, et al. Applications of Artificial Intelligence for Metastatic Gastrointestinal Cancer: A Systematic Literature Review. Cancers, 2025, 17.3: 558.
EVERHART, James E.; RUHL, Constance E. Burden of digestive diseases in the United States part I: overall and upper gastrointestinal diseases. Gastroenterology, 2009, 136.2: 376-386.
DUFFAUD, Florence; BLAY, Jean-Yves. Gastrointestinal stromal tumors: biology and treatment. Oncology, 2003, 65.3: 187-197.
FANOTTO, Valentina, et al. Primary tumor resection for metastatic colorectal, gastric and pancreatic cancer patients: In search of scientific evidence to inform clinical practice. Cancers, 2023, 15.3: 900.
WANG, Ding-Kang, et al. Targeted immunotherapies in gastrointestinal cancer: from molecular mechanisms to implications. Frontiers in immunology, 2021, 12: 705999.