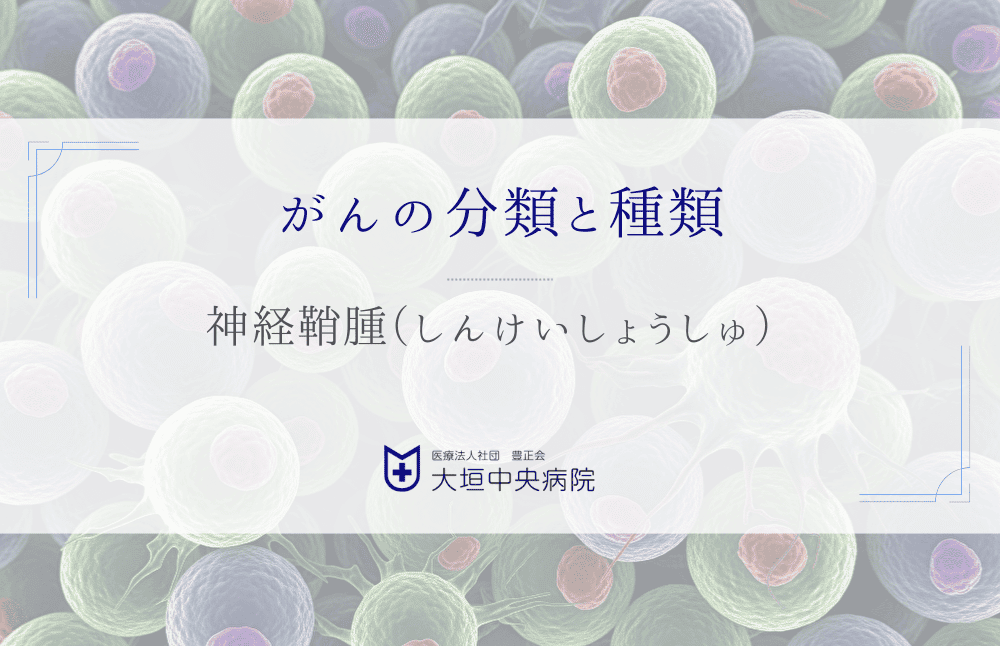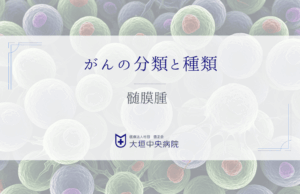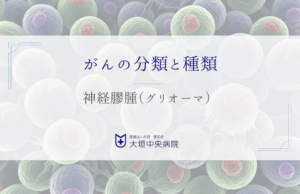「神経鞘腫」という診断を受け、不安や疑問を抱えている方は少なくないでしょう。この腫瘍は、脳や脊髄、手足の末梢神経など、体のさまざまな神経から発生する可能性があります。
その多くは良性ですが、「腫瘍」と聞くと「がんではないのか」と心配になるのは当然のことです。
この記事では、神経鞘腫とはどのような病気なのか、その性質や症状、検査、そして治療の選択肢について、基本的な知識から詳しく解説します。
ご自身の状態を正しく理解し、これからどのように向き合っていくかを考えるための一助となれば幸いです。正しい知識は、不安を和らげ、前向きな一歩を踏み出すための力になります。
神経鞘腫とは何か – まず知っておきたい基本
この病気について理解を深める第一歩として、まずは神経鞘腫がどのようなもので、体のどこに、なぜできるのかという基本的な事柄を解説します。
神経の構造と腫瘍の発生には密接な関係があります。
神経鞘腫の概要
神経鞘腫は、末梢神経を構成する細胞の一つである「シュワン細胞」から発生する腫瘍です。神経そのものではなく、神経線維を包み、保護している「神経鞘」という部分にできます。
ほとんどの場合、ゆっくりと成長する良性の腫瘍です。
神経を包む「鞘(さや)」にできる腫瘍
私たちの体には、脳から指令を伝えたり、感覚を伝えたりするための神経が網の目のように張り巡らされています。この神経線維は、電線を覆うビニールの被覆のように、神経鞘によって保護されています。
神経鞘腫は、この被覆の部分が異常に増殖してできる、こぶのようなものです。
そのため、神経そのものを破壊することは少ないですが、大きくなるにつれて神経を圧迫し、さまざまな症状を引き起こす原因となります。
主に良性の腫瘍
神経鞘腫の大きな特徴は、そのほとんどが「良性」である点です。良性とは、増殖のスピードが遅く、体の他の部分に転移することがない性質を指します。
そのため、悪性腫瘍、つまり「がん」のように命に直接関わる危険性は低いと考えられています。
発生の原因
神経鞘腫が発生する明確な原因は、まだ完全には解明されていません。しかし、一部には特定の遺伝的な病気が関わっていることが知られています。
明確な原因は不明なことが多い
多くの神経鞘腫は、特定の原因がなく偶発的に発生します。生活習慣や環境が直接的な原因となるという証拠は見つかっていません。
誰にでも起こりうる病気の一つと理解することが大切です。
神経線維腫症2型との関連
まれに、神経線維腫症2型(NF2)という遺伝性の病気が原因で神経鞘腫が発生することがあります。
NF2の患者さんは、体のさまざまな場所に複数の神経鞘腫ができる特徴があり、特に両側の聴神経に腫瘍(聴神経腫瘍)ができることが多いです。
神経鞘腫の基本情報
| 項目 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 発生起源 | シュワン細胞 | 神経線維を保護する細胞 |
| 主な性質 | 良性 | 増殖が遅く、転移はまれ |
| 発生部位 | 全身の末梢神経 | 頭蓋内、脊髄、四肢など |
神経鞘腫は「がん」なのでしょうか – 知っておきたい腫瘍の性質
「腫瘍」と診断されると、多くの方が「がん」との違いについて疑問を持つでしょう。
ここでは、腫瘍の性質である「良性」と「悪性」の違いを明確にし、神経鞘腫がどちらに分類されるのか、その医学的な位置づけを解説します。
良性腫瘍と悪性腫瘍(がん)の違い
腫瘍は、その性質によって大きく「良性」と「悪性」に分けられます。この二つの違いを理解することは、病気と向き合う上で非常に重要です。
増殖のスピードと転移の有無
最も大きな違いは、増殖の仕方と転移の有無です。
良性腫瘍は、周囲の組織を押しのけるようにゆっくりと大きくなりますが、組織の奥深くまで染み込むように広がる(浸潤)ことや、血液やリンパの流れに乗って他の臓器に広がる(転移)ことはありません。
一方、悪性腫瘍(がん)は、増殖スピードが速く、周囲に浸潤したり、他の臓器に転移したりする性質を持っています。
神経鞘腫のほとんどは良性
診断された神経鞘腫の9割以上は良性です。そのため、過度に心配する必要はありませんが、良性であっても症状を引き起こすことがあるため、適切な経過観察や治療が求められます。
ゆっくりと大きくなる性質
良性の神経鞘腫は、年単位で非常にゆっくりと成長します。
そのため、発見されてもすぐに治療が必要とはならず、まずは定期的な検査で大きさの変化を見守る「経過観察」が選択されることも少なくありません。
他の部位への転移は極めてまれ
良性であるため、神経鞘腫が他の臓器に転移することは基本的にありません。
治療の目的は、転移を防ぐことではなく、腫瘍が大きくなることによる神経の圧迫症状を解消、または予防することにあります。
良性腫瘍と悪性腫瘍(がん)の比較
| 性質 | 良性腫瘍(神経鞘腫など) | 悪性腫瘍(がん) |
|---|---|---|
| 増殖速度 | 遅い | 速い |
| 周囲への広がり | 押しのけるように増殖(圧排性) | 染み込むように増殖(浸潤性) |
| 転移 | しない | する可能性がある |
体からのサインを見逃さない – 部位によって異なる症状 (##)
神経鞘腫は、発生した場所によってさまざまな症状を引き起こします。どのような症状が現れるのかを知ることは、病気の早期発見や状態の把握につながります。
ここでは、体の部位ごとに現れやすい症状について具体的に見ていきます。
症状が現れる仕組み
神経鞘腫による症状の多くは、腫瘍そのものが悪さをしているというよりは、腫瘍が大きくなることで周囲の神経や組織を圧迫することが原因で起こります。
腫瘍による神経の圧迫が主な原因
神経は非常にデリケートな組織です。
神経鞘腫がゆっくりと大きくなる過程で、神経が圧迫されたり、引き伸ばされたりすると、その神経が支配している領域に痛みやしびれ、麻痺などの症状が現れます。
症状の種類や強さは、圧迫されている神経の場所と機能によって決まります。
発生部位別の主な症状
神経鞘腫は全身のあらゆる神経に発生する可能性があるため、症状も多岐にわたります。代表的な発生部位と、それに伴う症状を紹介します。
聴神経腫瘍の症状(めまい、耳鳴りなど)
頭蓋内にできる神経鞘腫の中で最も多いのが、聴神経にできる「聴神経腫瘍」です。聴神経は、音を聞くための「蝸牛神経」と、体のバランスを保つための「前庭神経」から成り立っています。
そのため、初期症状として片側の耳鳴りや難聴、ふらつきやめまいなどが現れることが多いです。
脊髄に発生した場合の症状(痛み、しびれ)
脊髄の神経から発生した場合は、腫瘍が脊髄そのものや、そこから枝分かれする神経根を圧迫します。これにより、首や背中、腰の痛み、手足のしびれや感覚の鈍さ、筋力の低下などが起こります。
症状の出る範囲は、腫瘍ができた脊髄の高さによって異なります。
手足の末梢神経に発生した場合
腕や脚の神経にできた場合は、その部分に硬いこぶとして触れることがあります。また、腫瘍のある場所を叩くと、その神経が支配する領域に痛みが響く「ティネル様サイン」が見られることもあります。
症状としては、しびれや痛みが代表的です。
部位別の初期症状の例
- 頭蓋内(聴神経など) – 耳鳴り、難聴、めまい
- 脊髄 – 首、背中、腰の痛み、手足のしびれ
- 四肢 – 触れるこぶ、痛み、感覚異常
- 体幹 – 肋間神経痛のような痛み
聴神経腫瘍の主な症状と進行
| 段階 | 主な症状 | 腫瘍の状態 |
|---|---|---|
| 初期 | 片側の耳鳴り、難聴、ふらつき | 腫瘍が比較的小さく、聴神経を圧迫し始めた段階 |
| 中期 | 顔面のしびれや麻痺(顔面神経麻痺) | 腫瘍が大きくなり、隣接する顔面神経を圧迫 |
| 後期 | 頭痛、嘔吐、歩行困難、意識障害 | 腫瘍がさらに増大し、脳幹を圧迫 |
どのように見つかるのか – 検査と診断までの道のり (##)
気になる症状があって医療機関を受診してから、神経鞘腫と診断が確定するまでには、いくつかの検査が必要です。
ここでは、診断に至るまでの一般的な流れと、それぞれの検査が持つ役割について詳しく解説します。
診断に至るまでの流れ
診断は、まず患者さんから症状を詳しく聞き、身体的な所見を確認することから始まります。その上で、画像検査などを用いて腫瘍の存在と状態を評価します。
問診と神経学的検査
医師はまず、どのような症状がいつから、どのように現れているのかを詳しく尋ねます。
その後、ハンマーなどを使って手足の反射を見たり、感覚や力の入り具合を調べたりする「神経学的検査」を行い、どの神経に異常があるのかを推定します。
画像検査による詳細な評価
神経学的検査で異常が疑われた場合、腫瘍の有無や正確な位置、大きさを確認するために画像検査を行います。
特にMRI検査は、神経鞘腫の診断において中心的な役割を果たします。
MRI検査の重要性
MRI(磁気共鳴画像)検査は、磁力と電波を使って体の内部を鮮明に写し出す検査です。特に、神経や筋肉といった柔らかい組織の描出に優れており、神経鞘腫の診断には欠かせません。
造影剤という薬剤を注射して撮影すると、腫瘍の形や性質がより明確になり、診断の精度が高まります。
CT検査との違いと役割
CT(コンピュータ断層撮影)検査は、X線を使って体の断面を撮影する検査です。MRIに比べて検査時間が短く、骨の情報を得るのに適しています。
神経鞘腫の診断においては、腫瘍が周囲の骨にどのような影響を与えているかを確認する目的などで補助的に用いられることがあります。
確定診断のための組織検査
画像検査で神経鞘腫が強く疑われた場合でも、最終的な確定診断は、腫瘍の一部を採取して顕微鏡で調べる「病理組織診断」によって行います。
これにより、良性か悪性かの判断も確定します。
生検の必要性
生検とは、腫瘍の組織の一部を採取することです。手術で腫瘍をすべて摘出する場合は、その摘出した組織を調べることで確定診断となります。
手術前に確定診断が必要な場合や、悪性の可能性が疑われる場合には、針を刺して組織を採取することもあります。
神経鞘腫の診断に用いる主な検査
| 検査の種類 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 神経学的検査 | 異常のある神経の部位を特定 | 問診と合わせて行い、診断の方向性を決める |
| MRI検査 | 腫瘍の存在、位置、大きさ、性質の評価 | 神経などの軟部組織の描出に優れ、診断の中心となる |
| 病理組織診断 | 良性・悪性の確定診断 | 手術で摘出した組織や生検で採取した組織を調べる |
あなたにとっての選択肢 – 経過観察・手術・放射線による治療 (##)
神経鞘腫と診断された後の治療方針は、腫瘍の状態や患者さん自身の状況によって異なります。すべてのケースで直ちに治療が必要なわけではありません。
ここでは、主な選択肢である「経過観察」「手術」「放射線治療」について、それぞれの特徴や目的を解説します。
治療方針を決める上で大切なこと
最適な治療方針は一つではありません。医師とよく相談し、ご自身の希望も伝えながら、納得のいく選択をすることが重要です。
腫瘍の大きさ、場所、症状の程度を考慮
治療方針は、腫瘍の大きさや発生している場所、症状の有無やその強さ、さらには患者さんの年齢や全身の状態などを総合的に評価して決定します。
例えば、腫瘍が小さく無症状であれば経過観察を、症状が強い場合や増大傾向があれば積極的な治療を検討します。
経過観察という選択
神経鞘腫は良性でゆっくりとしか大きくならないため、特に症状がない場合や、腫瘍が非常に小さい場合には、すぐに治療を行わず様子を見る「経過観察」が第一の選択肢となることがあります。
定期的なMRI検査で変化を追う
経過観察では、半年に一度、あるいは一年に一度といった頻度でMRI検査を行い、腫瘍の大きさに変化がないかを確認します。多くの場合は何年も大きさが変わらないこともあります。
腫瘍が大きくなったり、新たな症状が出たりした時点で、改めて治療を検討します。
手術による腫瘍の摘出
症状の原因となっている腫瘍を取り除く、最も根本的な治療法が手術です。腫瘍が大きく神経への圧迫が強い場合や、症状が進行している場合に選択されます。
神経機能を温存する手術
手術の最大の目標は、腫瘍を摘出しつつ、もとになっている神経の機能を可能な限り温存することです。
神経鞘腫は神経線維を包む鞘から発生するため、神経そのものを傷つけずに腫瘍だけを剥がすように摘出できる場合があります。
手術用の顕微鏡や、術中に神経の機能を監視するモニタリング装置を用いて、安全で精密な手術を行います。
手術の目的と限界
手術の目的は、症状の改善と、将来的な腫瘍の増大を防ぐことです。しかし、腫瘍が神経と強く癒着している場合など、機能を温存するために意図的に腫瘍を一部残すこともあります。
その場合は、残った腫瘍に対して放射線治療を追加したり、再度経過観察を行ったりします。
放射線による治療
放射線治療は、高エネルギーの放射線を腫瘍に集中して照射し、腫瘍が大きくなるのを抑える治療法です。体を切開する必要がないため、身体的な負担が少ないという利点があります。
ガンマナイフやサイバーナイフ
神経鞘腫の放射線治療では、「定位放射線治療」という方法が用いられます。これは、ガンマナイフやサイバーナイフといった特殊な装置を使い、多方向から放射線を腫瘍の一点に集中させる技術です。
これにより、周囲の正常な組織への影響を最小限に抑えながら、腫瘍に高い線量を照射することができます。
放射線治療の対象となる場合
手術が難しい場所にある腫瘍、比較的小さな腫瘍、手術後に残存した腫瘍、あるいは高齢や他の病気のために手術が困難な患者さんなどが良い対象となります。
放射線治療は腫瘍を消し去るのではなく、増大を制御することを主な目的とします。
各治療法の概要と比較
| 治療法 | 目的 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 経過観察 | 腫瘍の変化を監視 | 無症状、または症状が軽く、腫瘍が小さい場合 |
| 手術 | 腫瘍の摘出、神経の圧迫解除 | 症状が強い、腫瘍が大きい、増大傾向がある場合 |
| 放射線治療 | 腫瘍の増大を抑制 | 手術が困難な場合、手術後の残存腫瘍など |
良性から悪性のがんへ変わる可能性 – 悪性末梢神経鞘腫瘍について
「良性の神経鞘腫が、がんに変わることはないのか」という点は、多くの方が心配されることでしょう。その可能性はゼロではありませんが、非常にまれです。
ここでは、神経鞘腫の悪性化について、その頻度や特徴、治療法を解説します。
悪性化の頻度
良性の神経鞘腫が悪性化することは、極めてまれな現象です。過度に心配する必要はありませんが、可能性が皆無ではないことを知識として知っておくことは大切です。
極めてまれだがゼロではない
一般的な神経鞘腫が悪性化する確率は1%未満とも言われ、非常に低いものです。
ただし、前述の神経線維腫症1型(NF1、NF2とは異なる病気)という遺伝性疾患を持つ患者さんの場合は、悪性化のリスクが少し高まることが知られています。
悪性末梢神経鞘腫瘍(MPNST)とは
神経鞘腫が悪性化した場合、「悪性末梢神経鞘腫瘍(Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor, MPNST)」と呼ばれます。
これは、増殖が速く、周囲の組織に浸潤したり、肺などに転移したりする性質を持つ「肉腫」という悪性腫瘍の一種です。
急激な増大や強い痛みがサイン
悪性化を疑うサインとして、これまで変化のなかったこぶが数週間から数ヶ月の単位で急に大きくなる、安静にしていても続くような強い痛みが出現する、といった症状があります。
このような変化に気づいた場合は、速やかに主治医に相談することが重要です。経過観察中の定期的なMRI検査は、このような変化を早期に捉える目的もあります。
悪性化した場合の治療
悪性末梢神経鞘腫瘍と診断された場合は、良性腫瘍とは異なる、がんに準じた集学的な治療が必要となります。
手術が中心となる治療戦略
治療の基本は、腫瘍を周囲の正常な組織を含めて広く切除する手術です。再発を防ぐために、腫瘍を完全に取り切ることが目標となります。
補助的な化学療法や放射線治療
手術だけでは不十分な場合や、再発・転移のリスクが高いと考えられる場合には、手術の前後に抗がん剤による化学療法や放射線治療を組み合わせることがあります。
これらの治療は、専門的な知識を持つ医療機関で、慎重な検討のもとに行います。
良性神経鞘腫と悪性末梢神経鞘腫瘍の違い
| 項目 | 良性神経鞘腫 | 悪性末梢神経鞘腫瘍(MPNST) |
|---|---|---|
| 頻度 | 非常に多い | 非常にまれ |
| 増殖速度 | 遅い | 速い |
| 症状 | 無症状または神経圧迫症状 | 急激な増大、強い痛み、麻痺 |
| 治療 | 経過観察、手術、放射線治療 | 広範な手術、化学療法、放射線治療 |
知っておきたい治療後の経過と生活 – 上手に付き合っていくために
治療を終えた後、どのような経過をたどるのか、生活の中でどのような点に気をつければよいのかは、多くの方が関心を持つ点です。
ここでは、治療後の予後や後遺症との向き合い方、そして定期的な検査の重要性について解説します。
治療後の予後
予後とは、病気の経過や治癒の見通しのことを指します。良性の神経鞘腫の場合、予後は一般的に良好です。
良性の場合、予後は良好
手術や放射線治療によって腫瘍が適切にコントロールされれば、生命に影響が及ぶことはほとんどありません。治療後は、多くの患者さんがもとの社会生活に復帰しています。
病気と上手に付き合いながら、自分らしい生活を送ることが可能です。
神経鞘腫の予後と治療成績(目安)
※良性のため、生命に関わることは稀ですが、治療によって腫瘍をコントロールできる確率です。
- 5年生存率:健常者とほぼ変わりません
- ※良性腫瘍であるため、天寿を全うできることがほとんどです。
- 手術(全摘出)後の再発率: 数%未満
- ※完全に摘出できれば、再発することは非常に稀です。
- 放射線治療(ガンマナイフ等)の制御率: 約90〜95%
- ※治療後5〜10年以上経過しても、腫瘍が大きくならず安定している確率です。
後遺症との向き合い方
治療によって、もとになっていた神経の機能に影響が残り、何らかの後遺症が出現する可能性があります。これは治療の限界とも言える部分であり、向き合っていくことが大切になります。
神経症状が残る可能性
例えば、聴神経腫瘍の治療後には聴力の低下や顔面神経麻痺が、脊髄の腫瘍の治療後には手足のしびれや筋力低下が残ることがあります。
これらの症状は、治療直後が最も強く、時間とともに少しずつ回復していくことも多いですが、完全には元に戻らない場合もあります。
リハビリテーションの重要性
残った機能障害に対しては、リハビリテーションが重要な役割を果たします。
理学療法士や作業療法士といった専門家の指導のもと、筋力トレーニングや日常生活動作の訓練を行うことで、失われた機能を補い、生活の質(QOL)を維持・向上させることができます。
定期的な検査の必要性
治療が終わった後も、医療機関との関係が終わるわけではありません。定期的な通院と検査は、長期的な安心のために必要です。
再発の確認
手術で腫瘍をすべて取りきれなかった場合や、放射線治療を行った場合には、残った腫瘍が再び大きくならないかを確認するために、定期的なMRI検査が必要です。
また、完全に摘出できた場合でも、ごくまれに同じ場所から再発することがあるため、数年間は経過観察を行うのが一般的です。
治療後の生活で心がけたいこと
- 主治医の指示に従い、定期的な通院を続ける
- 新たな症状や、以前の症状の変化に気づいたら相談する
- 必要に応じてリハビリテーションに積極的に取り組む
- バランスの取れた食事や適度な運動を心がける
神経鞘腫はがん保険の対象になるのか – 確認すべきポイント
病気の治療には経済的な側面も関わってきます。ご自身が加入している医療保険やがん保険が使えるのかどうかは、切実な問題です。
ここでは、神経鞘腫と診断された場合に、がん保険がどのように扱われるかについて解説します。
保険適用の基本
がん保険の給付対象となるかどうかは、保険の契約(約款)で定められている「がん」の定義によって決まります。
「がん(悪性新生物)」の定義
ほとんどのがん保険では、給付の対象となる「がん」を「悪性新生物」と定義しています。これは、病理組織診断によって悪性と診断されたものを指します。
したがって、良性腫瘍は原則としてこの定義には含まれません。
良性腫瘍の場合の取り扱い
神経鞘腫のほとんどは良性であるため、一般的ながん保険の診断給付金などの対象にはならないことが多いです。
しかし、契約内容によっては給付を受けられる可能性もあります。
一般的には対象外が多い
良性の神経鞘腫は「がん」ではないため、がんと診断されたときに一時金が支払われる「がん診断給付金」の対象にはならないのが一般的です。
これは重要なポイントなので、誤解のないように理解しておく必要があります。
特約によっては給付の可能性も
ただし、保険商品によっては、脳にできた良性腫瘍(良性脳腫瘍)を手術した場合に給付金が支払われる特約が付いていることがあります。
聴神経腫瘍などの頭蓋内にできた神経鞘腫は、この対象となる可能性があります。また、入院や手術に対する給付金は、がん保険ではなく、通常の医療保険から支払われます。
悪性化した場合
万が一、神経鞘腫が悪性化し、悪性末梢神経鞘腫瘍(MPNST)と診断された場合は、状況が変わります。
悪性末梢神経鞘腫瘍は対象になる
悪性末梢神経鞘腫瘍は、病理学的に「悪性新生物」に分類されます。そのため、がん保険の定める「がん」の定義に合致し、診断給付金や入院・手術給付金などの支払い対象となります。
ご自身の保険契約の確認
最終的に保険が適用されるかどうかは、ご自身が加入している保険の契約内容次第です。不明な点は必ず確認しましょう。
約款の確認と保険会社への問い合わせ
まずは保険証券や契約のしおり(ご契約の約款)を手元に用意し、「がん」の定義や給付条件に関する項目を確認することが第一です。
その上で、不明な点があれば、保険会社のコールセンターや担当者に直接問い合わせ、ご自身の病名(神経鞘腫)を伝えて給付対象になるかを確認するのが最も確実な方法です。
がん保険の適用に関する一般的な考え方
| 診断名 | 分類 | がん保険の適用 |
|---|---|---|
| 神経鞘腫 | 良性腫瘍 | 原則として対象外(特約等で例外あり) |
| 悪性末梢神経鞘腫瘍 | 悪性新生物(肉腫) | 対象となる |
よくある質問
ここでは、神経鞘腫と診断された患者さんやそのご家族からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 神経鞘腫は遺伝しますか?
-
ほとんどの神経鞘腫は遺伝とは関係なく偶発的に発生します。ただし、ごくまれに「神経線維腫症2型(NF2)」という遺伝性の病気の一症状として発生することがあります。
ご家族に同じような病気の方が複数いるなど、遺伝に関して心配な点がある場合は、主治医や遺伝カウンセリングの専門家に相談することをお勧めします。
- 治療中に仕事を続けることはできますか?
-
治療方針によって異なります。経過観察の場合は、定期的な通院を除けば、基本的にこれまで通りの仕事や生活を続けることが可能です。
手術や放射線治療を行う場合は、治療期間中とその後の回復期間中に一定の休みが必要です。
体の状態や仕事の内容によって復帰のタイミングは個人差がありますので、主治医や職場の産業医などとよく相談することが大切です。
- 食生活で気をつけることはありますか?
-
現時点では、特定の食品が神経鞘腫の発生や増大に影響を与えるという科学的な根拠はありません。
特別な食事制限は必要ありませんので、特定の食品を過剰に摂取したり、逆に避けたりせず、栄養バランスの取れた食事を規則正しく摂ることを心がけてください。
健康的な食生活は、治療に臨む上での体力維持や、治療後の回復を支える上で重要です。
- 小さな神経鞘腫が見つかりました。すぐに手術は必要ですか?
-
いいえ、すぐには必要ない場合が多いです。偶然発見された小さな神経鞘腫で、特に症状がない場合は、前述の通り「経過観察」が第一の選択肢となります。
神経鞘腫は成長が非常にゆっくりであるため、慌てて治療を決める必要はありません。
定期的にMRI検査で大きさの変化を追い、腫瘍が大きくなったり症状が出たりする兆候が見られた時点で、改めて手術や放射線治療といった次のステップを検討します。
主治医と相談しながら、落ち着いて方針を決めていきましょう。
この記事では末梢神経から発生する神経鞘腫について解説しましたが、脳や脊髄といった中枢神経そのものから発生する腫瘍もあります。
その代表的なものが「神経膠腫(グリオーマ)」です。神経膠腫は、神経細胞を支えるグリア細胞から発生する腫瘍の総称で、その性質は比較的おとなしいものから進行の速い悪性のものまで様々です。
発生する場所が脳や脊髄の中心部であるため、神経鞘腫とは異なる症状や治療法が選択されます。脳腫瘍に関する理解をさらに深めたい方は、神経膠腫についての解説記事もあわせてご覧ください。
二つの病気の違いを知ることで、ご自身の状態をより多角的に理解する助けとなるでしょう。
参考文献
HASEGAWA, Toshinori, et al. Long-term outcomes of sporadic vestibular schwannomas treated with recent stereotactic radiosurgery techniques. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 2020, 108.3: 725-733.
WATANABE, Shinya, et al. Stereotactic radiosurgery for vestibular schwannomas: average 10-year follow-up results focusing on long-term hearing preservation. Journal of Neurosurgery, 2016, 125.Supplement_1: 64-72.
BALOSSIER, Anne, et al. Long-term hearing outcome after radiosurgery for vestibular schwannoma: a systematic review and meta-analysis. Neurosurgery, 2023, 92.6: 1130-1141.
ROTTER, Juliana, et al. Surgery versus radiosurgery for facial nerve schwannoma: a systematic review and meta-analysis of facial nerve function, postoperative complications, and progression. Journal of Neurosurgery, 2020, 135.2: 542-553.
CARLSON, Matthew L., et al. Long-term quality of life in patients with vestibular schwannoma: an international multicenter cross-sectional study comparing microsurgery, stereotactic radiosurgery, observation, and nontumor controls. Journal of neurosurgery, 2015, 122.4: 833-842.
HASEGAWA, Toshinori, et al. Long-term safety and efficacy of stereotactic radiosurgery for vestibular schwannomas: evaluation of 440 patients more than 10 years after treatment with Gamma Knife surgery. Journal of neurosurgery, 2013, 118.3: 557-565.
SHINYA, Yuki, et al. Long-term outcomes of stereotactic radiosurgery for trigeminal, facial, and jugular foramen schwannoma in comparison with vestibular schwannoma. Cancers, 2021, 13.5: 1140.
WHITMEYER, Max, et al. Resection of vestibular schwannomas after stereotactic radiosurgery: a systematic review. Journal of Neurosurgery, 2020, 135.3: 881-889.
MARTIN, Juan J., et al. Cranial nerve preservation and outcomes after stereotactic radiosurgery for jugular foramen schwannomas. Neurosurgery, 2007, 61.1: 76-81.
POLLOCK, Bruce E., et al. Patient outcomes after vestibular schwannoma management: a prospective comparison of microsurgical resection and stereotactic radiosurgery. Neurosurgery, 2006, 59.1: 77-85.
脳・神経系腫瘍に戻る