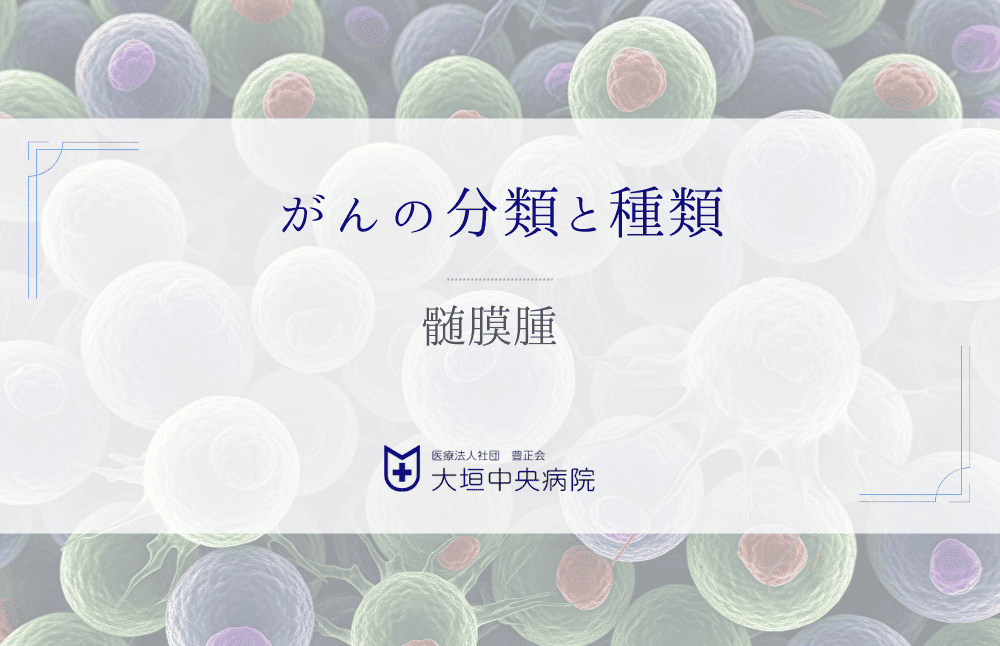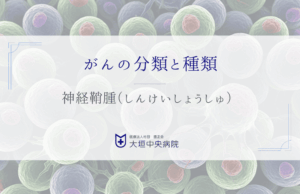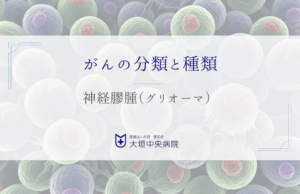「脳腫瘍」と聞くと、多くの方が深刻な「がん」を想像し、大きな不安を感じるかもしれません。しかし、脳腫瘍には様々な種類があり、その性質も一様ではありません。
この記事で解説する「髄膜腫(ずいまくしゅ)」は、脳腫瘍の中でも比較的多く見られるものの一つですが、その多くは良性です。
この記事では、髄膜腫とはどのような腫瘍なのか、がんとの関係性、注意すべき症状、検査や治療法の選択肢について、正確な情報を分かりやすく解説します。
ご自身やご家族が髄膜腫と診断された方、あるいは脳の健康に関心を持つすべての方が、正しい知識を得て、過度な不安を和らげる一助となれば幸いです。
髄膜腫とは何か – 脳を守る膜にできる腫瘍の基本
まず、髄膜腫がどのようなものであるか、基本的なところから理解を深めましょう。この腫瘍は、脳そのものではなく、脳を保護している膜から発生するという特徴があります。
この構造的な違いが、髄膜腫の性質や治療法を考える上で重要なポイントになります。
脳を包む膜「髄膜」の役割
私たちの脳は、頭蓋骨のすぐ内側にある「髄膜」という薄い膜によって三重に包まれ、守られています。
髄膜は外側から硬膜、くも膜、軟膜という構造になっており、外部の衝撃から脳を保護したり、脳の栄養に関わる重要な役割を担っています。
髄膜腫は、このうち主に「くも膜」を構成する細胞から発生する腫瘍です。
ほとんどが良性の脳腫瘍
髄膜腫は、脳腫瘍全体の中では発生頻度が高い腫瘍ですが、その大部分はゆっくりと増殖する「良性」の腫瘍です。そのため、すぐに命に関わるようなケースは多くありません。
しかし、良性であっても腫瘍が大きくなることで周囲の脳を圧迫し、様々な症状を引き起こす可能性があります。また、ごく一部には増殖が速い「悪性」のものも存在します。
髄膜腫の主な特徴
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 発生母地 | 脳を包む髄膜(主としてくも膜の細胞) |
| 性質 | 約90%以上が良性(WHOグレード1) |
| 増殖速度 | 多くは非常にゆっくり |
髄膜腫の発生原因
髄膜腫がなぜ発生するのか、その明確な原因はまだ完全には解明されていません。しかし、いくつかの危険因子が関連している可能性を指摘されています。
例えば、中年以降の女性に多く見られることから、女性ホルモンが関与しているという説があります。また、頭部への高線量の放射線治療を受けた経験がある場合、発生リスクが高まることが知られています。
ただし、ほとんどの髄膜腫は、これらの因子とは無関係に偶発的に発生すると考えられています。
この腫瘍と「がん」との関係性 – 知っておくべき違い
髄膜腫について知る上で、多くの方が疑問に思うのが「がんとの違い」です。腫瘍という言葉から「がん」を連想しがちですが、医学的には明確な区別があります。
ここでは、その関係性を正しく理解するためのポイントを解説します。
一般的に髄膜腫は「がん」ではない
医学的に「がん」とは、体の様々な場所で発生する「悪性腫瘍」のことを指します。
悪性腫瘍は、無秩序に増殖し、周囲の組織に染み込むように広がり(浸潤)、体の他の場所に飛び火する(転移)という性質を持ちます。
一方、髄膜腫の大部分を占める「良性」の腫瘍は、増殖が緩やかで、周囲の組織を押しのけるように大きくなりますが、浸潤や転移をすることはありません。
この性質の違いから、良性の髄膜腫は一般的に「がん」とは区別します。
良性腫瘍と悪性腫瘍(がん)の性質の違い
| 性質 | 良性腫瘍(多くの髄膜腫) | 悪性腫瘍(がん) |
|---|---|---|
| 増殖速度 | ゆっくり | 速い |
| 周囲への広がり方 | 圧迫する(膨張性) | 染み込む(浸潤性) |
| 転移 | しない | する可能性がある |
悪性髄膜腫という存在
ただし、髄膜腫の中には少数ながら悪性の性質を持つものが存在します。これらは「悪性髄膜腫」と呼ばれ、増殖スピードが速く、周囲の脳組織や骨へ浸潤することがあります。
非常に稀ですが、他の臓器へ転移する例も報告されています。このような悪性の髄膜腫は、「がん」の一種として扱われ、良性の場合とは異なる、より積極的な治療を必要とします。
腫瘍の悪性度は、後述する「グレード」によって分類します。
見過ごしやすい体のサイン – こんな症状に注意が必要
髄膜腫は非常にゆっくりと大きくなるため、初期段階では症状が現れないことがほとんどです。症状が出現する場合も、その内容は腫瘍が脳のどの部分を圧迫しているかによって大きく異なります。
そのため、見過ごしやすい体のサインに気づくことが早期発見につながります。
腫瘍の発生場所で変わる症状
脳は場所によってつかさどる機能が異なります。例えば、運動を制御する場所、感覚を処理する場所、言語を理解する場所などです。髄膜腫がこれらの場所を圧迫すると、その機能に応じた症状が現れます。
例えば、運動野の近くにできれば手足の麻痺が、視神経の近くにできれば視力障害が起こる可能性があります。
発生部位と現れやすい症状の例
| 発生部位 | 主な症状 |
|---|---|
| 円蓋部(頭頂部) | けいれん、手足の麻痺・しびれ |
| 嗅窩部(前頭部の底) | 嗅覚の低下、性格の変化 |
| 蝶形骨縁部(目の奥) | 視力低下、視野障害、眼球運動の障害 |
注意すべき具体的な症状
髄膜腫によって引き起こされる可能性のある症状は多岐にわたります。以下に代表的なものを挙げますが、これらの症状は他の病気でも起こりうるものです。
気になる症状が続く場合は、自己判断せず専門医に相談することが重要です。
- 持続的な頭痛、特に朝方に強い頭痛
- けいれん発作
- 手足の動かしにくさ(麻痺)や感覚の鈍さ(しびれ)
- 視力の低下、物が二重に見える、視野が狭くなる
- 言葉が話しにくい、ろれつが回らない
どのように見つかるのか – 診断と精密検査の流れ
髄膜腫が疑われる場合、いくつかの検査を組み合わせて診断を進めます。近年では、脳ドックなどの普及により、無症状の段階で偶然発見されるケースも増えています。
ここでは、診断に至るまでの一般的な検査の流れを解説します。
最初のステップ – 問診と神経学的検査
まず、医師が患者さんから症状の詳しい内容や経過を聴き取ります(問診)。その後、体の動きや感覚、反射などを調べる神経学的検査を行い、脳のどの部分に異常がある可能性が高いかを推定します。
これらの情報をもとに、次に必要となる画像検査を計画します。
画像診断が確定の鍵
髄膜腫の診断において、画像診断は極めて重要です。特にCT検査とMRI検査が中心的な役割を果たします。
CT検査(コンピュータ断層撮影)
X線を使って体の断面を撮影する検査です。比較的短時間で検査でき、特に腫瘍に伴う骨の変化や出血の有無を確認するのに役立ちます。
多くの場合、造影剤という薬剤を注射して、腫瘍の形状や性質をより詳しく調べます。
MRI検査(磁気共鳴画像)
強力な磁石と電波を使って、体の内部を様々な角度から詳細に撮像する検査です。CTよりも脳の軟部組織を鮮明に描出できるため、髄膜腫の診断には最も有用な検査とされています。
腫瘍の正確な位置、大きさ、周囲の脳との関係性を詳細に把握することができます。こちらも造影剤を使用することが一般的です。
CT検査とMRI検査の比較
| 検査項目 | CT検査 | MRI検査 |
|---|---|---|
| 原理 | X線 | 磁気と電波 |
| 得意なこと | 骨の描出、短時間での撮影 | 軟部組織(脳)の詳細な描出 |
| 髄膜腫診断での役割 | 初期のスクリーニング、骨への影響評価 | 確定診断、詳細な状態把握 |
良性から悪性まで – 悪性度(グレード)とがんの可能性
画像検査で髄膜腫の存在が確認された後、治療方針を決める上で最も重要な情報となるのが、腫瘍の「悪性度(グレード)」です。
このグレードによって、腫瘍の増殖する速さや再発のリスクが大きく異なり、がんとしての性質を持つかどうかが決まります。
WHOによる悪性度分類(グレード)
髄膜腫の悪性度は、世界保健機関(WHO)が定めた基準に基づいて、グレード1からグレード3までの3段階に分類します。
このグレードは、手術で摘出した腫瘍組織を顕微鏡で詳しく調べる「病理診断」によって最終的に確定します。
WHOグレード分類の詳細
| グレード | 名称 | 特徴と概要 |
|---|---|---|
| グレード1 | 髄膜腫(良性) | 最も一般的(約90%)。増殖は非常にゆっくりで、再発率は低い。 |
| グレード2 | 異型性髄膜腫 | 良性と悪性の中間的な性質。増殖が速めで、再発リスクが比較的高い。 |
| グレード3 | 退形成性/悪性髄膜腫 | 明らかな悪性(がん)。増殖が非常に速く、再発率も高い。 |
グレードごとの特徴と再発率
グレード1の良性髄膜腫は、手術で完全に取り除くことができれば、再発のリスクはかなり低くなります。一方、グレード2は再発しやすいため、手術後に放射線治療を追加することを検討します。
グレード3は悪性度が高く、手術と放射線治療を組み合わせた積極的な治療を行っても再発のリスクが高いため、慎重な経過観察が必要です。
このように、グレードは治療後の見通し(生存率など)を予測する上でも重要な指標となります。
【髄膜腫のグレード別5年生存率(目安)】 (日本脳神経外科学会等のデータを参考にした目安)
※悪性の場合は再発しやすく予後が厳しくなりますが、手術と放射線治療でコントロールを目指します。
グレード1(良性):90%以上
※大部分がこのタイプです。完全に切除できれば、天寿を全うできる(健常者と変わらない余命)可能性が高いです。
グレード2(異型性): 約70〜80%
グレード3(悪性): 約30〜40%
※悪性の場合は再発しやすく予後が厳しくなりますが、手術と放射線治療でコントロールを目指します。
治療の選択肢を理解する – 経過観察・手術・放射線治療
髄膜腫の治療法は、主に「経過観察」「手術」「放射線治療」の3つです。
どの治療法を選択するかは、腫瘍のグレード、大きさ、発生場所、そして患者さん自身の年齢や健康状態、希望などを総合的に考慮して決定します。
担当医と十分に話し合い、納得のいく治療法を選ぶことが大切です。
何もせず見守る「経過観察」
腫瘍が小さく、症状がない、あるいは非常に軽微な場合、特に高齢の患者さんでは、すぐに治療を開始せず、定期的なMRI検査で腫瘍の大きさに変化がないかを見守る「経過観察」という選択肢があります。
これは、良性の髄膜腫の多くが非常にゆっくりとしか大きくならないため、治療に伴うリスクを避けるための合理的な判断です。
多くの患者さんがこの方法で長期間、問題なく生活しています。
基本となる治療法「手術(外科治療)」
腫瘍が大きく脳を圧迫して症状が出ている場合や、増大傾向が見られる場合、また悪性が疑われる場合には、手術による腫瘍の摘出が第一の選択肢となります。
手術の最大の目的は、症状の原因となっている腫瘍を取り除き、正常な脳への圧迫を解除することです。また、摘出した腫瘍で病理診断を行い、正確なグレードを確定させるという重要な役割もあります。
手術には開頭手術が必要となり、一定期間の入院を要します。信頼できる経験豊富な医師(名医)を探すことも、治療の成功にとって重要な要素です。
手術の目的
- 症状の改善
- 腫瘍の増大を止める
- 正確な病理診断(グレードの確定)
手術が難しい場合の「放射線治療」
腫瘍が脳の深い場所にある、重要な神経や血管を巻き込んでいるなどの理由で手術が難しい場合や、手術後に残った腫瘍に対して、放射線治療を行うことがあります。
また、高齢や他の病気のために手術が困難な場合にも選択されます。放射線を腫瘍に集中して照射し、腫瘍細胞の増殖を抑えたり、腫瘍を小さくしたりする効果が期待できます。
ガンマナイフやサイバーナイフといった、正常な脳への影響を最小限に抑える高精度な放射線治療も広く行われています。
主な治療法の比較
| 治療法 | 対象となる主なケース | メリット |
|---|---|---|
| 経過観察 | 無症状、小型、高齢者 | 体への負担がない |
| 手術 | 有症状、増大傾向、悪性疑い | 根本的な治療、確実な病理診断 |
| 放射線治療 | 手術困難な部位、術後残存、再発 | 体への負担が少ない |
悪性と診断されたがんへの向き合い方
髄膜腫の中でもグレード2(異型性)やグレード3(悪性)と診断された場合、それは「がん」としての性質を持つことを意味し、良性の場合とは異なる治療戦略が必要です。
再発のリスクが高いため、より徹底した治療と慎重な経過観察が求められます。
グレード2・3の治療戦略
悪性髄膜腫の治療の基本は、手術で可能な限り腫瘍を摘出することです。
しかし、悪性の場合は周囲の組織に染み込むように広がっていることがあり、手術だけで完全に取り除くことが難しいケースも少なくありません。
そのため、手術後に残った腫瘍細胞を叩き、再発を防ぐ目的で放射線治療を追加することが標準的な治療方針となります。
手術と放射線治療の組み合わせ
この「手術」と「放射線治療」を組み合わせる治療法を「集学的治療」と呼びます。
まず手術で腫瘍の大部分を取り除いて症状を和らげ、その後、目に見えないレベルで残っている可能性のある腫瘍細胞に対して放射線を照射します。
この二段階の治療によって、再発率を下げ、より長期的なコントロールを目指します。治療計画は、患者さん一人ひとりの状態に合わせて慎重に立てます。
治療後の生活と定期的な検査の重要性
髄膜腫の治療を終え、退院した後の生活も非常に重要です。治療の効果を維持し、万が一の再発に備えるためには、ご自身の体調管理と定期的な検査を継続することが大切になります。
退院後の生活で気をつけること
手術や放射線治療の後は、体力が回復するまでに時間がかかります。焦らず、無理のない範囲で徐々に元の生活に戻していくことが大切です。
バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけ、心身ともに健康な状態を保つことが、回復を助け、再発予防にもつながります。
後遺症との付き合い方
腫瘍があった場所や治療の影響によっては、手足の麻痺や感覚障害、記憶力の低下といった後遺症が残ることがあります。これらの症状に対しては、リハビリテーションが有効です。
理学療法士や作業療法士などの専門家の助けを借りながら、根気強く機能回復訓練を続けることで、生活の質を向上させることが可能です。
なぜ定期的な検査が必要なのか
髄膜腫は、たとえ良性であっても、また治療が成功したように見えても、数年後、あるいは十数年後に再発する可能性があります。特にグレード2や3の場合はそのリスクが高まります。
再発した腫瘍も、小さいうちに発見できれば、治療の選択肢が広がり、体への負担も少なくて済みます。そのため、治療後も定期的にMRI検査を受け、再発の兆候がないかをチェックし続けることが極めて重要です。
多くの患者さんの体験談を綴ったブログなどでも、定期検診の大切さが語られています。
再発のリスクと長期的な経過について
髄膜腫と診断された方が最も心配することの一つが「再発」です。
再発のリスクはゼロではありませんが、どのような場合にリスクが高まるのかを知り、長期的な視点で病気と付き合っていく心構えが大切です。
再発しやすいケースとは
髄膜腫の再発リスクは、いくつかの因子によって左右されます。最も大きな因子は、前述の「WHOグレード」です。グレードが高いほど、再発率は高くなります。
もう一つの重要な因子は、「手術による摘出度」です。手術で腫瘍を完全に取り切れたか、あるいは一部が残ってしまったかによって、その後の再発率が大きく変わります。
再発リスクに影響する主な因子
| 因子 | リスクが高いケース | リスクが低いケース |
|---|---|---|
| WHOグレード | グレード2、グレード3 | グレード1 |
| 手術での摘出度 | 部分摘出、亜全摘出 | 全摘出 |
| 発生場所 | 重要な神経や血管に近く、摘出しにくい場所 | 摘出しやすい場所 |
再発した場合の治療法
万が一再発した場合でも、治療法がなくなるわけではありません。初回の治療と同様に、手術や放射線治療が選択肢となります。
再発した腫瘍の状態や患者さんの体力などを考慮し、最も適した治療法を再度検討します。一度治療した場所であっても、近年の技術の進歩により、安全に再手術や再照射を行えるケースが増えています。
よくある質問
ここでは、髄膜腫に関して患者さんやご家族からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 髄膜腫の原因は何ですか?遺伝はしますか?
-
明確な原因は不明ですが、一部で放射線被曝やホルモンが関連すると考えられています。ほとんどは遺伝せず、偶発的に発生します。
- 手術のための入院期間はどのくらいですか?
-
腫瘍の大きさや場所、手術の方法によって異なりますが、一般的には術後の経過観察を含めて2週間から1ヶ月程度が目安です。
- 治療後の生存率はどのくらいですか?
-
予後はグレードに大きく左右されます。グレード1の良性であれば、生命への影響はほとんどありません。
グレード2や3の場合でも、適切な治療により長期的にコントロールできることが多くなっています。
- 名医を見つけるにはどうすればよいですか?
-
脳神経外科、特に脳腫瘍を専門とする医師が多く在籍する病院を探すことが第一歩です。セカンドオピニオンを活用し、複数の医師の意見を聞くことも有効です。
髄膜腫と同じく、脳や脊髄の神経から発生する良性腫瘍に「神経鞘腫(しんけいしょうしゅ)」があります。
特に聴神経にできるものが多く、めまい、耳鳴り、難聴といった症状で発見されることがあります。
髄膜腫と同様に多くは良性で、ゆっくりと増殖しますが、発生する場所が異なるため、現れる症状や治療法に違いがあります。
脳腫瘍に関する理解をさらに深めるために、神経鞘腫についての解説記事もあわせてご覧になることをお勧めします。
二つの腫瘍の違いを知ることで、ご自身の状態をより正確に把握する助けとなるでしょう。
参考文献
PETTERSSON-SEGERLIND, Jenny, et al. Long-term follow-up, treatment strategies, functional outcome, and health-related quality of life after surgery for WHO grade 2 and 3 intracranial meningiomas. Cancers, 2022, 14.20: 5038.
DE JESÚS, Orlando, et al. Long-term follow-up of patients with meningiomas involving the cavernous sinus: recurrence, progression, and quality of life. Neurosurgery, 1996, 39.5: 915-920.
KWEE, L. E., et al. Spinal meningiomas: Treatment outcome and long-term follow-up. Clinical Neurology and Neurosurgery, 2020, 198: 106238.
NAKAMURA, Masaya, et al. Long-term surgical outcomes of spinal meningiomas. Spine, 2012, 37.10: E617-E623.
SIMONETTI, G., et al. Long term follow up in 183 high grade meningioma: A single institutional experience. Clinical Neurology and Neurosurgery, 2021, 207: 106808.
DE ALMEIDA, Antonio Nogueira, et al. Clinical outcome, tumor recurrence, and causes of death: a long-term follow-up of surgically treated meningiomas. World neurosurgery, 2017, 102: 139-143.
DE ALMEIDA, Antonio Nogueira, et al. Clinical outcome, tumor recurrence, and causes of death: a long-term follow-up of surgically treated meningiomas. World neurosurgery, 2017, 102: 139-143.
LAM SHIN CHEUNG, Victor, et al. Meningioma recurrence rates following treatment: a systematic analysis. Journal of neuro-oncology, 2018, 136.2: 351-361.
SUGHRUE, Michael E., et al. Outcome and survival following primary and repeat surgery for World Health Organization Grade III meningiomas. Journal of neurosurgery, 2010, 113.2: 202-209.
KIM, Chi Heon, et al. Long-term recurrence rates after the removal of spinal meningiomas in relation to Simpson grades. European Spine Journal, 2016, 25.12: 4025-4032.
PETTERSSON-SEGERLIND, Jenny, et al. Long-term 25-year follow-up of surgically treated parasagittal meningiomas. World neurosurgery, 2011, 76.6: 564-571.
脳・神経系腫瘍に戻る