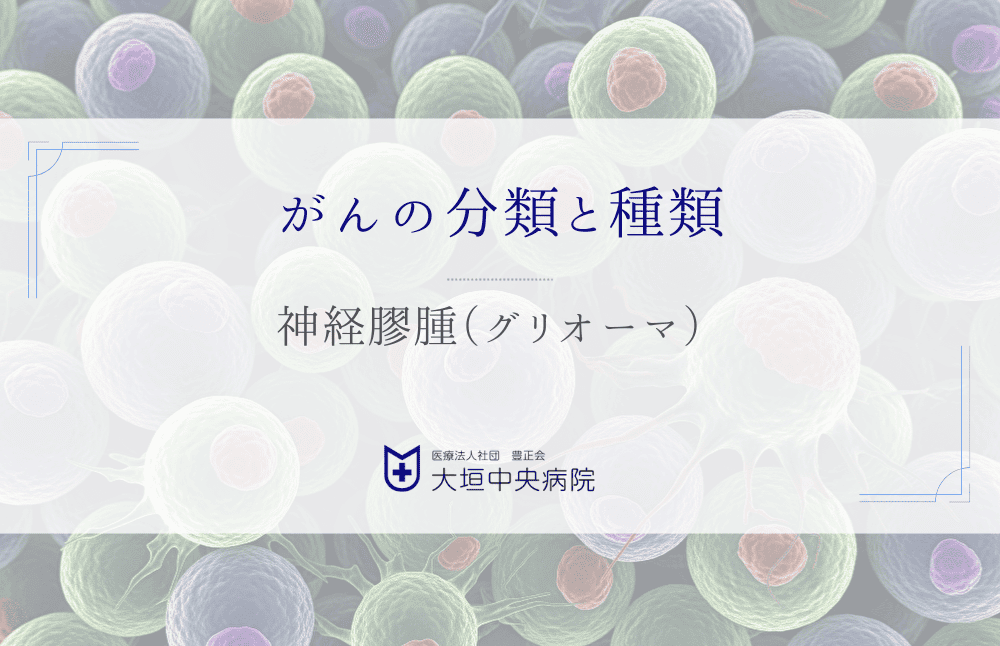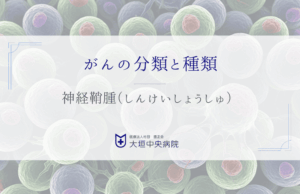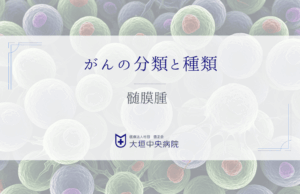「神経膠腫(グリオーマ)」という言葉を聞いたことがありますか。これは、脳や脊髄を構成する「神経膠細胞(グリア細胞)」から発生する脳腫瘍の一種です。
原発性脳腫瘍の中では最も発生頻度が高く、その性質は比較的おだやかなものから、進行が速い悪性のものまで多岐にわたります。
この記事では、神経膠腫の基礎知識から、症状、検査、悪性度を示すグレード、標準的な治療法、そして治療後の生活に至るまで、がんと向き合う患者さんやご家族が知っておきたい情報を網羅的に解説します。
神経膠腫(グリオーマ)とは – 脳にできるがんの基礎知識
ここでは、神経膠腫がどのような病気なのか、その基本的な特徴について解説します。脳腫瘍には様々な種類がありますが、その中でも神経膠腫は特別な位置を占めています。
脳のどの部分から発生し、どのような種類があるのかを理解することは、病気全体を把握する上で非常に重要です。
神経膠腫(グリオーマ)の概要
神経膠腫は、脳そのものから発生する「原発性脳腫瘍」の代表的なものです。脳の神経細胞を支え、栄養を供給するなどの役割を担う神経膠細胞(グリア細胞)が腫瘍化したものを指します。
正常な脳組織としみ込むように広がる(浸潤する)性質を持つため、周囲の正常な脳との境界が不明瞭であることが大きな特徴です。
このため、手術で完全に取り除くことが難しい場合があります。グリオーマという別名でも広く知られています。
神経膠細胞の役割と腫瘍化
私たちの脳は、情報を処理する主役である「神経細胞(ニューロン)」と、それを支える「神経膠細胞(グリア細胞)」から成り立っています。
神経膠細胞は、神経細胞が正常に機能するための環境を整える重要な役割を担っています。この神経膠細胞が、何らかの原因で異常に増殖を始めることで神経膠腫が発生します。
どの種類の神経膠細胞が腫瘍化したかによって、神経膠腫の種類が分類されます。
脳腫瘍全体における神経膠腫の位置づけ
脳腫瘍は、発生起源によって大きく二つに分けられます。脳自体から発生する「原発性脳腫瘍」と、体の他の部位にできたがんが脳に転移してきた「転移性脳腫瘍」です。
神経膠腫は原発性脳腫瘍に含まれ、その中でも最も頻度が高い腫瘍です。
原発性脳腫瘍と転移性脳腫瘍
| 分類 | 発生起源 | 代表的な腫瘍 |
|---|---|---|
| 原発性脳腫瘍 | 脳や脊髄、それらを包む膜などから発生 | 神経膠腫、髄膜腫、下垂体腺腫など |
| 転移性脳腫瘍 | 他の臓器のがん(肺がん、乳がんなど)が脳に転移 | 肺がん、乳がん、大腸がんの脳転移など |
グリオーマの種類と特徴
グリオーマは、由来する細胞の種類によって主に3つに大別されます。それぞれ性質や好発年齢が異なります。
星細胞腫(アストロサイトーマ)
神経膠細胞の一種である星細胞(アストロサイト)から発生します。グリオーマの中で最も多く見られます。
悪性度によってグレード1から4に分類され、最も悪性度の高いグレード4は「膠芽腫(グリオブラストーマ)」と呼ばれます。
乏突起膠腫(オリゴデンドログリオーマ)
乏突起膠細胞(オリゴデンドロサイト)から発生する腫瘍です。比較的進行が緩やかで、放射線治療や化学療法が効きやすい傾向があります。
特定の遺伝子変異(IDH遺伝子変異と1p/19q染色体共欠失)を持つことが特徴です。
上衣腫(エペンディモーマ)
脳の中心部にある脳室の壁を覆う上衣細胞から発生します。小児に発生することが多いですが、成人でも見られます。
腫瘍の発生部位や遺伝子の特徴によって、予後や治療法が異なります。
見過ごさないで – 神経膠腫が示す体のサイン
神経膠腫の症状は、腫瘍が脳のどの部分にできたか、またどのくらいの大きさかによって様々です。初期段階では症状が出にくいこともありますが、病状の進行とともに体に変化が現れます。
ここでは、注意すべき症状について具体的に解説します。
腫瘍の場所によって異なる局所症状
脳は部位ごとに異なる機能を担っているため、腫瘍ができた場所の機能が障害されることで特有の症状が現れます。これを「局所症状(巣症状)」と呼びます。
例えば、言語機能に関わる部分に腫瘍ができれば言葉が出にくくなり、運動機能に関わる部分であれば手足の麻痺が起こります。
主な局所症状の例
| 発生部位 | 主な機能 | 現れやすい症状 |
|---|---|---|
| 前頭葉 | 思考、判断、運動、人格 | 手足の麻痺、性格の変化、意欲低下 |
| 側頭葉 | 記憶、言語の理解、聴覚 | 言葉の理解が難しい、記憶障害、けいれん |
| 頭頂葉 | 感覚、空間認識、計算 | 手足のしびれ、左右の認識が難しい |
| 後頭葉 | 視覚 | 視野が狭くなる、物が見えにくい |
頭蓋内圧亢進による全般症状
頭蓋骨の内部は容量が決まっているため、腫瘍が大きくなったり、その周りにむくみ(脳浮腫)が生じたりすると、頭蓋骨の中の圧力(頭蓋内圧)が高まります。
これにより、腫瘍の場所に関わらず共通した症状が現れます。
- 頭痛(特に朝方に強い)
- 吐き気、嘔吐
- ものが二重に見える(複視)
- 視力低下
これらの症状は頭蓋内圧亢進症状と呼ばれ、病状が進行しているサインである可能性があります。特に、これまで経験したことのないような頭痛が続く場合は注意が必要です。
また、大人のてんかん発作(けいれん)で初めて脳腫瘍が見つかることも少なくありません。
どのように見つかるのか – 診断と精密検査の流れ
気になる症状があり医療機関を受診した場合、どのような検査を経て神経膠腫の診断に至るのでしょうか。診断を確定し、適切な治療方針を立てるためには、いくつかの段階を踏んだ検査が必要です。
ここでは、診断までの一般的な流れを解説します。
問診と神経学的検査
まず、医師がどのような症状がいつから現れたか、どのように変化してきたかを詳しく聞き取ります。
その後、体の動きや感覚、反射などを調べる神経学的検査を行い、脳のどの部分に異常があるかを推定します。この段階で脳の病気が疑われる場合、次に画像検査に進みます。
画像診断による脳の評価
脳内の様子を画像として映し出し、腫瘍の有無や大きさ、場所などを調べる検査です。主にCTとMRIが用いられます。
CT(コンピュータ断層撮影)検査
X線を使って体の断面を撮影する検査です。短時間で検査が終わり、緊急時にも有用です。
脳出血の有無などを調べるのに優れていますが、神経膠腫の詳細な評価にはMRIの方が適していることが多いです。
MRI(磁気共鳴画像)検査
強力な磁石と電波を使って、より詳細な脳の断面像を撮影する検査です。腫瘍の性質や広がり、周囲の正常な脳との関係を詳しく評価できます。
造影剤という薬剤を注射して撮影すると、腫瘍の活動性や悪性度について、より多くの情報が得られます。
画像検査の比較
| 検査項目 | CT検査 | MRI検査 |
|---|---|---|
| 原理 | X線 | 磁気と電波 |
| 検査時間 | 短い(数分) | 長い(30分〜1時間) |
| 情報の詳しさ | 比較的簡便 | 非常に詳細 |
確定診断のための組織検査(生検)
画像検査だけでは、腫瘍の種類や悪性度を完全に確定することはできません。
最終的な診断を下すためには、手術によって腫瘍の一部または全部を採取し、顕微鏡で詳しく調べる病理診断が必要です。この組織を採取する手技を「生検」と呼びます。
遺伝子検査の重要性
近年では、採取した組織を用いて遺伝子レベルでの解析を行うことが標準的になっています。
特にIDH遺伝子や1p/19q染色体などの異常を調べることは、腫瘍を正確に分類し、治療方針の決定や予後の予測に極めて重要です。
がんの悪性度を示す「グレード」とは何か
神経膠腫の治療方針や予後を考える上で、最も重要な指標の一つが「グレード」です。これは、世界保健機関(WHO)が定めた基準に基づく腫瘍の悪性度の分類です。
グレードが高いほど、腫瘍の増殖速度が速く、悪性度が高いことを意味します。
WHOによる悪性度分類
神経膠腫は、病理診断の結果に基づいてグレード1からグレード4までの4段階に分類されます。この分類は、治療法を選択する際の大きな指針となります。
WHOグレード分類の概要
| グレード | 悪性度 | 増殖の速さ |
|---|---|---|
| グレード1 | 良性 | 非常にゆっくり |
| グレード2 | 低悪性度 | 比較的ゆっくり |
| グレード3 | 悪性 | 速い |
| グレード4 | 最も悪性 | 非常に速い |
各グレードの予後と特徴
グレードによって、腫瘍の性質や治療後の経過(予後)が大きく異なります。
グレード2(びまん性星細胞腫など)
悪性度は低いものの、正常な脳組織にしみ込むように広がっており、時間とともに悪性度を増してグレード3や4に移行することがあります。
そのため、長期的な経過観察と適切なタイミングでの治療介入が重要です。
グレード3(退形成性星細胞腫など)
明確な悪性腫瘍であり、増殖速度が速くなります。手術、放射線治療、化学療法を組み合わせた積極的な治療が必要です。
グレード4(膠芽腫)
神経膠腫の中で最も悪性度が高く、進行が非常に速い腫瘍です。膠芽腫(グリオブラストーマ)とも呼ばれます。
治療は困難を伴いますが、手術、放射線治療、化学療法を組み合わせた集学的治療で予後の改善を目指します。
グリオーマというがんと向き合うための標準的な治療法
神経膠腫の治療は、一つの方法だけで完結することは少なく、複数の治療法を組み合わせて行います。
腫瘍のグレード、種類、遺伝子情報、発生した場所、そして患者さんご自身の年齢や全身の状態などを総合的に考慮して、最も適した治療方針を決定します。
手術(外科的治療)
治療の基本となるのが手術です。可能な限り腫瘍を摘出することで、頭蓋内圧を下げて症状を緩和し、その後の放射線治療や化学療法の効果を高めることができます。
また、摘出した組織で正確な病理診断を下すという重要な目的もあります。
摘出の目的と限界
手術の目標は、麻痺や言語障害といった後遺症を出すことなく、安全に最大限の腫瘍を摘出することです。
しかし、神経膠腫は正常な脳にしみ込むように広がっているため、画像で見える範囲の腫瘍をすべて取り除いても、目に見えないがん細胞が残っていることがほとんどです。
そのため、手術だけで完治することは難しく、他の治療法との組み合わせが必須となります。
放射線治療
高エネルギーのX線などを照射して、がん細胞を破壊する治療法です。手術後に残ったがん細胞を叩く目的や、手術が困難な場合に中心的な治療法として行います。
通常、5〜6週間にわたって、平日に毎日少しずつ照射を続けます。
化学療法(薬物療法)
抗がん剤を用いてがん細胞の増殖を抑える治療法です。飲み薬や点滴で投与します。特に悪性度の高い神経膠腫(グレード3、4)では、放射線治療と併用して行われることが標準的です。
テモゾロミドという飲み薬が広く用いられています。
膠芽腫(グレード4)に対する標準治療
| 治療段階 | 治療内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 初期治療 | 手術 + 放射線治療と化学療法(テモゾロミド)の同時併用 | 最大限の腫瘍除去と残存腫瘍の制御 |
| 維持療法 | 化学療法(テモゾロミド)の継続 | 再発を遅らせる |
治療後の経過と再発について知っておくべきこと
一通りの初期治療が終わった後も、神経膠腫との付き合いは続きます。治療後の経過はどうか、再発の可能性はどのくらいあるのか、そしてもし再発した場合はどうするのか。
これらは患者さんやご家族にとって大きな関心事です。ここでは、治療後の流れと再発について解説します。
定期的な経過観察の重要性
治療後は、再発や変化がないかを確認するために、定期的にMRI検査を行います。
検査の頻度は、腫瘍のグレードや治療後の状態によって異なりますが、最初は1〜3ヶ月ごと、状態が落ち着いてくれば半年ごと、1年ごとと間隔を延ばしていきます。
定期的な検査は、万が一の再発を早期に発見し、速やかに対処するために不可欠です。
再発した場合の治療選択肢
神経膠腫は、残念ながら再発しやすい腫瘍です。特に悪性度の高いものではその傾向が強くなります。
再発した場合の治療法は、初回治療の内容、再発までの期間、患者さんの全身状態などを考慮して慎重に決定します。
- 再手術
- 再度の放射線治療
- 異なる種類の抗がん剤による化学療法
- 分子標的薬や治験への参加
生存率と向き合う
生存率は、同じ診断を受けた多くの人々のデータを集計した統計的な指標であり、個々の患者さんの余命を正確に示すものではありません。
しかし、病状の全体像を把握するための一つの目安となります。生存率はグレードによって大きく異なります。
グレード別の5年生存率の目安
| WHOグレード | 代表的な腫瘍 | 5年生存率(目安) |
|---|---|---|
| グレード2 | びまん性星細胞腫 | 約50-70% |
| グレード3 | 退形成性星細胞腫 | 約20-40% |
| グレード4 | 膠芽腫 | 約10%以下 |
これらの数値はあくまで過去のデータに基づく平均値です。新しい治療法の開発により、治療成績は少しずつ向上しています。
数字に一喜一憂するのではなく、ご自身の治療に前向きに取り組むことが大切です。
がん治療と生活の調和 – QOLを維持するためのヒント
がんの治療を受けながら、自分らしい生活を維持することは非常に重要です。
QOL(Quality of Life、生活の質)を高く保つためには、治療による副作用とうまく付き合い、心と体のケアを心がける必要があります。
ここでは、治療と生活を両立させるためのヒントをいくつか紹介します。
治療による副作用との付き合い方
手術、放射線治療、化学療法には、それぞれ副作用が伴うことがあります。どのような副作用が起こりうるかを事前に理解し、対処法を知っておくことで、不安を軽減できます。
主な治療法と副作用の例
| 治療法 | 起こりうる主な副作用 | 対処法の例 |
|---|---|---|
| 手術 | 感染、出血、神経症状の悪化 | 抗生物質、リハビリテーション |
| 放射線治療 | 倦怠感、脱毛、皮膚炎、脳のむくみ | 十分な休息、ステロイド薬 |
| 化学療法 | 吐き気、食欲不振、倦怠感、骨髄抑制 | 吐き気止め、感染予防 |
心のケアとサポート体制
がんと診断されたことによるショックや、治療への不安、将来への心配など、心の負担は計り知れません。一人で抱え込まず、家族や友人、医療スタッフに気持ちを話すことが大切です。
また、多くの病院には、がん患者さんやそのご家族の相談に乗る「がん相談支援センター」が設置されています。心理的なサポートを受けることも、治療を乗り越える上で大きな助けとなります。
信頼できる情報源を見つける
インターネット上には様々な情報が溢れていますが、そのすべてが正確とは限りません。不確かな情報に惑わされないよう、信頼できる情報源を活用することが重要です。
国立がん研究センターのがん情報サービスや、治療を受けている医療機関が提供する情報を参考にしましょう。
他の患者さんのブログなどを参考にする際は、あくまで個人の体験談として捉え、ご自身の治療方針については必ず主治医と相談することが大切です。
神経膠腫の原因 – 現在わかっていること
「なぜ自分がこの病気になったのか」と、その原因を知りたいと思うのは自然なことです。しかし、残念ながら、ほとんどの神経膠腫では、発生の明確な原因はまだわかっていません。
ここでは、現時点で原因として考えられていること、また関連が低いとされていることについて解説します。
明確な原因は特定されていない
多くの生活習慣病とは異なり、神経膠腫の発生に直接結びつく特定の食事や生活習慣は見つかっていません。
携帯電話の電磁波との関連も長年研究されていますが、科学的に明確な因果関係は証明されていません。
ほとんどの神経膠腫は、明らかな原因がなく、偶然に遺伝子の変異が積み重なって発生すると考えられています。
関連が指摘されている要因
確率は非常に低いものの、いくつかの要因がリスクを高める可能性が指摘されています。
- 遺伝的要因 – 特定の遺伝性疾患(神経線維腫症1型など)を持つ家系では、神経膠腫の発生率がわずかに高くなることが知られています。しかし、これは極めて稀なケースです。
- 放射線被ばく – 頭部への高線量の放射線治療を受けた経験がある場合、数年から数十年後に脳腫瘍が発生するリスクが上がることが報告されています。
よくある質問
- 神経膠腫は遺伝しますか?
-
ほとんどの神経膠腫は遺伝しません。ごく稀に、特定の遺伝性疾患の一部として家族内で発生することがありますが、一般的には遺伝を心配する必要はありません。
- 名医を探すにはどうすればよいですか?
-
神経膠腫の治療は、脳神経外科、放射線治療科、腫瘍内科などが連携して行うチーム医療が重要です。
特定の「名医」一人を探すというよりは、多くの症例を扱い、十分な設備と経験を持つ医療機関を選ぶことが大切です。
日本脳神経外科学会や日本脳腫瘍学会のウェブサイトで専門医のいる施設を調べることも一つの方法です。
脳腫瘍には、神経膠腫以外にも様々な種類があります。その中でも比較的発生頻度が高いものに「髄膜腫」があります。
髄膜腫は、脳そのものではなく、脳を包む「髄膜」から発生する腫瘍で、そのほとんどが良性です。
神経膠腫のように脳にしみ込むように広がることはなく、ゆっくりと大きくなるため、無症状のまま経過することもあります。
症状や治療法は神経膠腫とは異なります。脳腫瘍に関する理解をさらに深めるために、髄膜腫についての記事もあわせてご覧になることをお勧めします。
参考文献
LOTE, Knut, et al. Survival, prognostic factors, and therapeutic efficacy in low-grade glioma: a retrospective study in 379 patients. Journal of clinical oncology, 1997, 15.9: 3129-3140.
SCHIFF, David; BROWN, Paul D.; GIANNINI, Caterina. Outcome in adult low-grade glioma: the impact of prognostic factors and treatment. Neurology, 2007, 69.13: 1366-1373.
PROGNOSTIK, Düflük Evreli Gliomlarda. Efficacy of prognostic factors on survival in patients with low grade glioma. Turkish neurosurgery, 2008, 18.4: 336-344.
LUO, Chen, et al. The prognosis of glioblastoma: a large, multifactorial study. British journal of neurosurgery, 2021, 35.5: 555-561.
KREX, Dietmar, et al. Long-term survival with glioblastoma multiforme. Brain, 2007, 130.10: 2596-2606.
GUPTA, Tejpal; SARIN, Rajiv. Poor-prognosis high-grade gliomas: evolving an evidence-based standard of care. The lancet oncology, 2002, 3.9: 557-564.
PELLERINO, Alessia, et al. Epidemiology, risk factors, and prognostic factors of gliomas. Clinical and Translational Imaging, 2022, 10.5: 467-475.
HIRAI, Toshinori, et al. Prognostic value of perfusion MR imaging of high-grade astrocytomas: long-term follow-up study. American Journal of Neuroradiology, 2008, 29.8: 1505-1510.
STYLLI, Stanley S., et al. Photodynamic therapy of high grade glioma–long term survival. Journal of clinical neuroscience, 2005, 12.4: 389-398.
KRISHNATRY, Rahul, et al. Clinical and treatment factors determining long‐term outcomes for adult survivors of childhood low‐grade glioma: a population‐based study. Cancer, 2016, 122.8: 1261-1269.
脳・神経系腫瘍に戻る