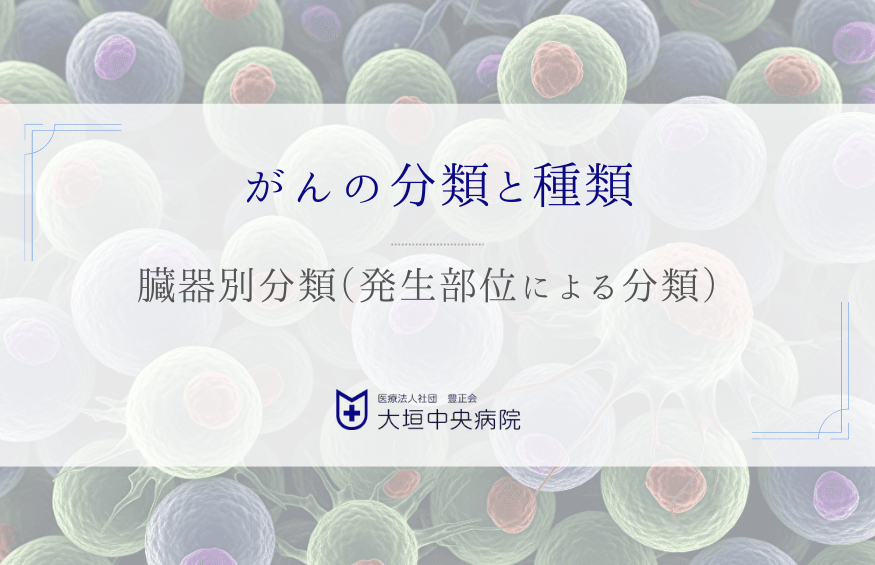がんと診断されたとき、多くの人がまず直面するのは、自分のがんが体のどこに発生し、どのような性質を持つのかという情報です。
がんは発生した臓器や組織によって「臓器別」に分類し、それぞれ特徴や進行の仕方、治療法が異なります。
この分類を理解することは、ご自身の状態を正しく把握し、医師との対話を深め、納得して治療に臨むための第一歩です。
この記事では、がんを発生部位ごとに分け、それぞれの代表的ながんの種類、特徴、症状について詳しく解説します。
ご自身やご家族ががんと向き合う上で、基本的な知識を整理し、今後の療養生活の指針を立てる一助となれば幸いです。
消化器系のがん
食べ物の通り道である消化管や、消化を助ける臓器に発生するがんをまとめて消化器系がんと呼びます。口から食道、胃、小腸、大腸、肛門へと続く消化管と、肝臓、胆嚢、膵臓などが含まれます。
日本では、胃がんや大腸がんの罹患者数が多く、食生活の欧米化などの生活習慣の変化も発生に影響を与えていると考えられています。
早期発見が治療成績を大きく左右するため、定期的な検診が重要です。
食道がん
主な症状と進行
食道がんの初期段階では自覚症状がほとんどありません。がんが進行すると、食べ物を飲み込む際の違和感や、胸の奥がしみるような感覚が現れます。
さらに進行すると、食べ物がつかえる感じや体重減少、声のかすれといった症状が出ます。
食道壁の粘膜から発生し、徐々に外側に向かって深く広がり、周囲のリンパ節や肺、肝臓などの臓器に転移することがあります。
検査と診断
食道がんの診断では、まずバリウムを飲んで食道の形をX線で撮影する食道造影検査を行います。より詳しく調べるためには、内視鏡(胃カメラ)検査が有効です。
内視鏡で食道の粘膜を直接観察し、疑わしい部分があれば組織を採取して病理検査を行い、がん細胞の有無を確定します。進行度を調べるためにはCT検査やPET検査も用います。
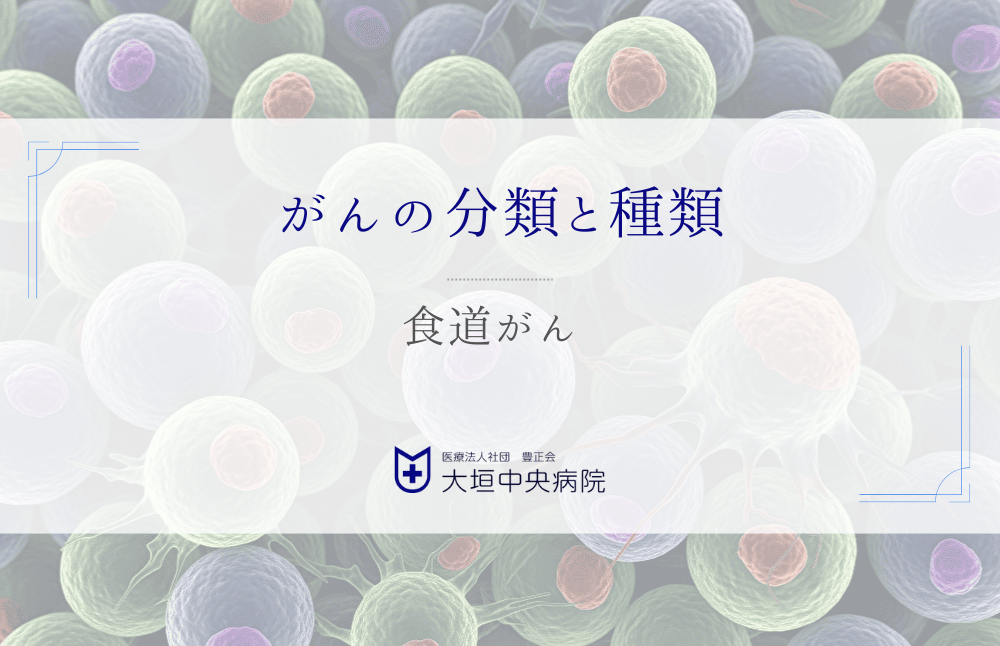
胃がん
ピロリ菌との関連
胃がんの発生要因として、ヘリコバクター・ピロリ菌の持続的な感染が大きく関わっていることが分かっています。
ピロリ菌が胃の粘膜に長くすみ着くと、慢性的な炎症を引き起こし、胃粘膜の萎縮が進みます。この萎縮した粘膜から胃がんが発生しやすくなると考えられています。
ピロリ菌の除菌治療は、胃がんの発生リスクを低減させる効果が期待できます。
早期発見の重要性
胃がんも初期には特有の症状がほとんどありません。そのため、症状がないうちから定期的に胃がん検診(内視鏡検査やバリウム検査)を受けることが、早期発見には極めて重要です。
早期の胃がんであれば、内視鏡による切除だけで治療が完了することも多く、体への負担も少なく済みます。進行すると、胃の不快感や痛み、食欲不振、体重減少などの症状が現れます。
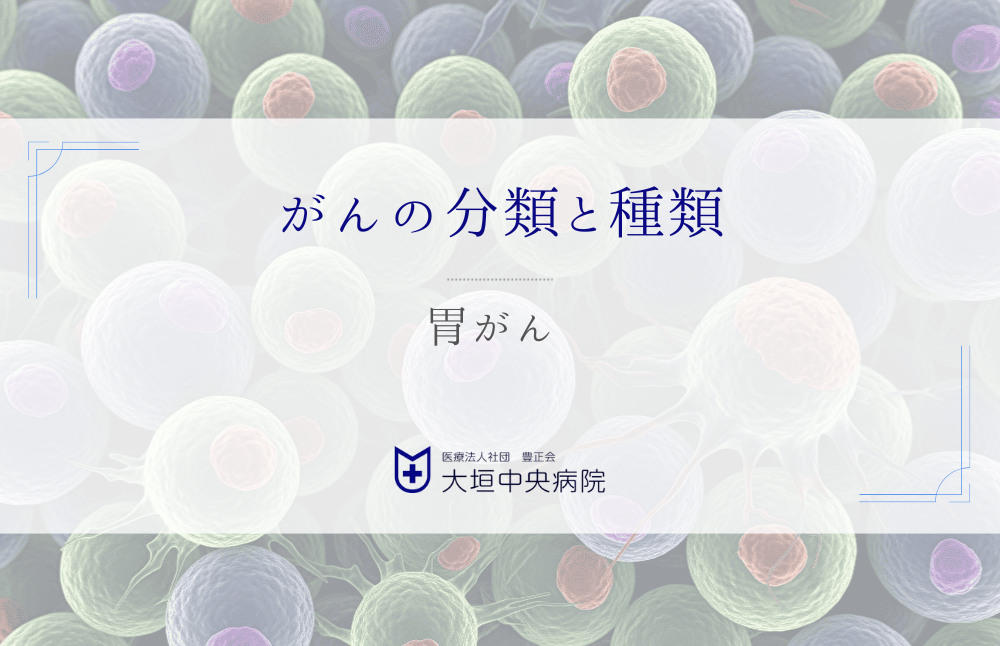
大腸がん(結腸がん・直腸がん)
近年増加傾向にある理由
大腸がんの罹患者数と死亡者数は、日本で増加傾向にあります。この背景には、食生活の欧米化が関係していると考えられています。
動物性脂肪や赤肉の摂取量増加、食物繊維の摂取量減少などが、大腸がんの発生リスクを高める要因です。また、肥満や運動不足といった生活習慣も関連が指摘されています。
診断に用いる検査
大腸がんの検診では、まず便に混じった血液を調べる便潜血検査を行います。この検査で陽性となった場合、精密検査として全大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を実施します。
内視鏡で大腸の内部を隅々まで観察し、ポリープやがんが疑われる病変があれば、その場で組織を採取したり、小さなポリープであれば切除したりすることも可能です。
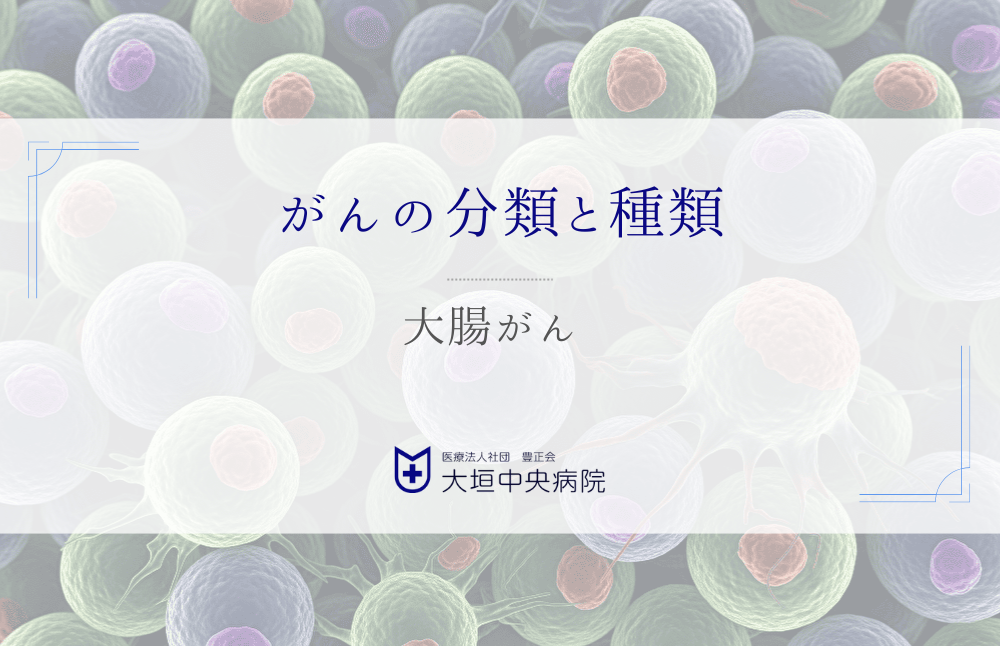
肝臓がん
肝炎ウイルスとの関係
日本の肝臓がんの多くは、B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスの持続的な感染が原因で起こる慢性肝炎や肝硬変から発生します。
ウイルスの感染によって肝臓の細胞が長期間にわたり破壊と再生を繰り返す中で、遺伝子変異が蓄積し、がん化すると考えられています。
近年は、ウイルス感染以外の原因、特に脂肪肝からの肝臓がんも増加しています。
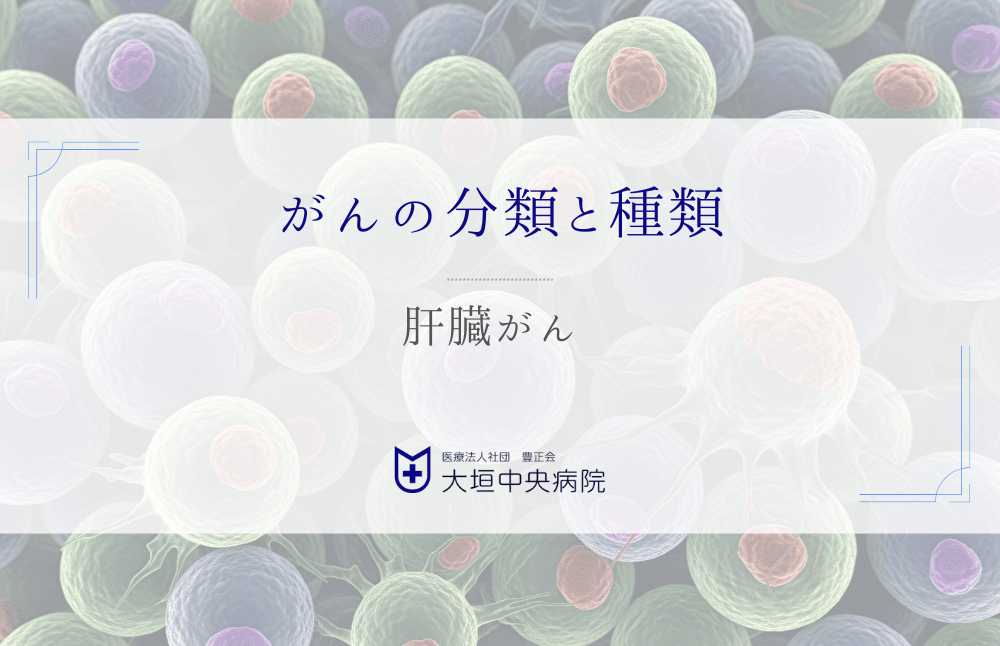
膵臓がん
発見が難しい理由
膵臓がんは、早期発見が非常に難しいがんの一つです。その理由として、膵臓が体の深い部分にあり、胃や腸などの臓器に囲まれているため、超音波検査などでも見つけにくいことが挙げられます。
また、初期には特徴的な症状が現れにくく、腹痛や背中の痛み、黄疸、体重減少などの症状が出たときには、すでに進行しているケースが多く見られます。
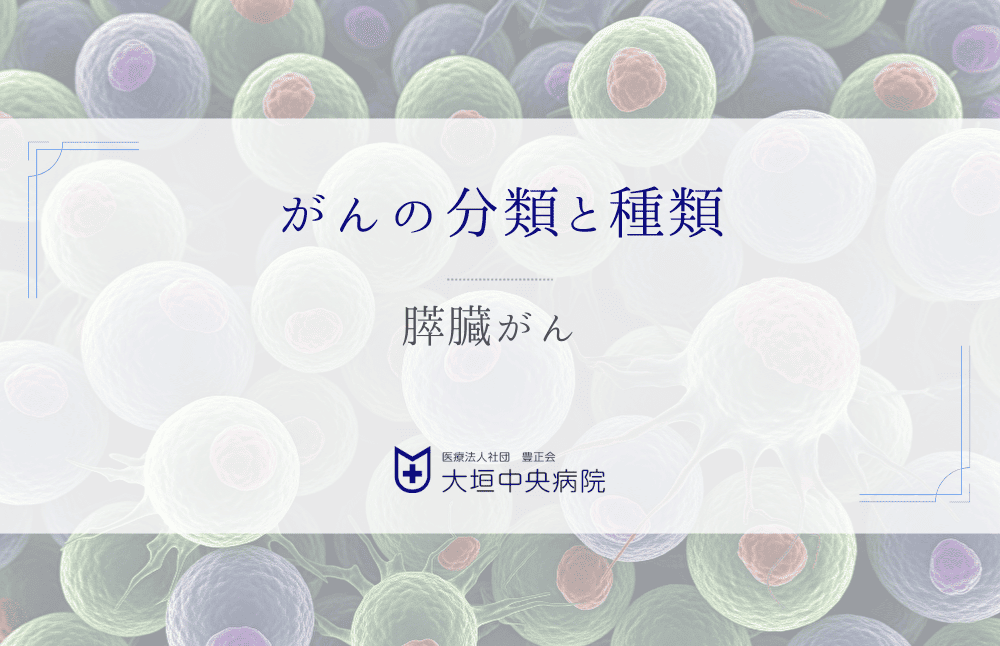
胆道がん
胆道がんは、胆汁の通り道である胆道(胆管や胆嚢)に発生する悪性腫瘍です。胆管がんと胆嚢がんに大別され、初期症状に乏しいため発見が困難で、進行してから診断されることが多いのが特徴です。
主な症状として黄疸、腹痛、発熱、体重減少があります。胆石症や胆管炎の既往、高齢、喫煙などがリスク因子とされています。診断には血液検査、CT、MRI、内視鏡検査などが用いられます。
治療は外科手術が第一選択ですが、進行例では化学療法や放射線療法を組み合わせます。早期発見が困難なため5年生存率は比較的低く、予後は厳しいがんの一つです。
定期的な健診による早期発見と、症状がある場合の速やかな受診が重要です。
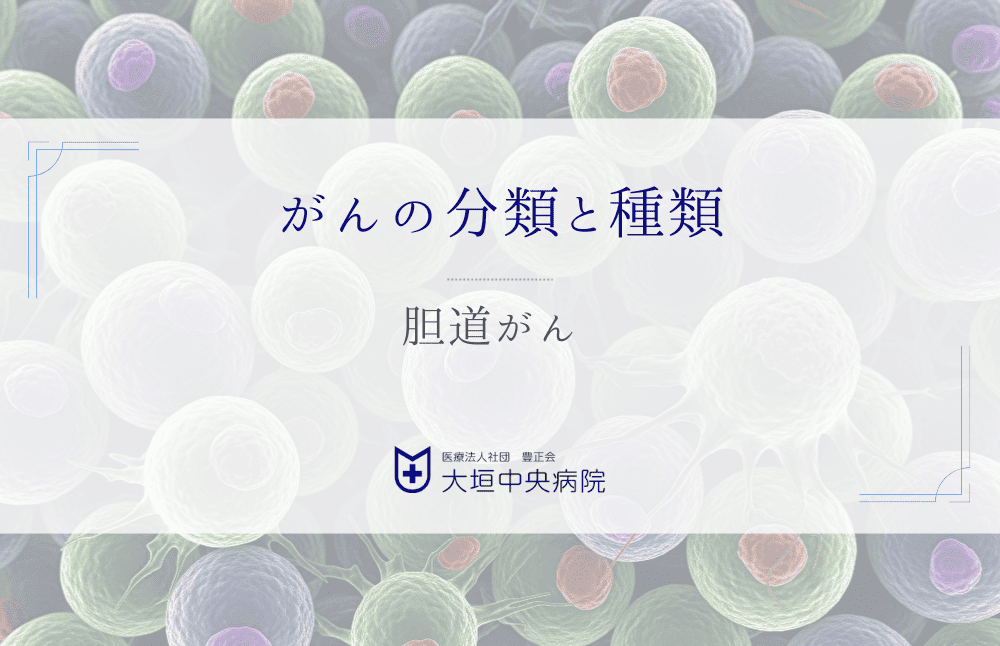
消化器系がんの種類と主な症状
| がんの種類 | 主な発生部位 | 注意したい症状 |
|---|---|---|
| 食道がん | 食道 | 飲み込む際の違和感、胸の痛み |
| 胃がん | 胃 | 胃の不快感、食欲不振、黒い便 |
| 大腸がん | 結腸・直腸 | 血便、便通異常(便秘・下痢) |
| 肝臓がん | 肝臓 | 腹部の張り、黄疸、倦怠感 |
| 膵臓がん | 膵臓 | 腹痛、背中の痛み、体重減少 |
| 胆道がん | 胆道 | 黄疸・腹痛・体重減少が主症状 |
呼吸器系のがん
呼吸器系のがんは、空気の通り道である気道や、ガス交換を行う肺に発生するがんの総称です。代表的なものに肺がんがあり、日本ではがんによる死亡原因の第1位となっています。
喫煙が最大の原因とされていますが、受動喫煙や大気汚染など、喫煙以外の要因も関わっています。声帯にできる喉頭がんなどもこの分類に含まれます。
肺がん
非小細胞肺がんと小細胞肺がん
肺がんは、がん細胞の見た目(組織型)によって、大きく「非小細胞肺がん」と「小細胞肺がん」の2つに分類します。
非小細胞肺がんは肺がん全体の約85%を占め、さらに腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんなどに分けられます。進行は比較的緩やかです。
一方、小細胞肺がんは約15%を占め、進行が非常に速く、早い段階から転移しやすいという特徴があります。この分類によって治療方針が大きく異なります。
喫煙以外の原因
肺がんの最大の原因は喫煙ですが、タバコを吸わない人でも肺がんになることがあります。他人のタバコの煙を吸う受動喫煙もリスクを高めます。
その他、アスベスト(石綿)やラドンガスといった有害物質への曝露、PM2.5などの大気汚染、遺伝的な要因なども肺がんの原因となり得ます。
特に腺がんは、非喫煙者の女性にも比較的多く見られるタイプです。
肺がんの主な組織型
| 分類 | 組織型 | 特徴 |
|---|---|---|
| 非小細胞肺がん | 腺がん | 肺がんの中で最も多く、非喫煙者にも発生する。 |
| 扁平上皮がん | 喫煙との関連が強く、肺の中心部に発生しやすい。 | |
| 大細胞がん | 細胞が大きく、増殖が速い傾向がある。 | |
| 小細胞肺がん | - | 増殖が非常に速く、転移しやすい。喫煙との関連が極めて強い。 |
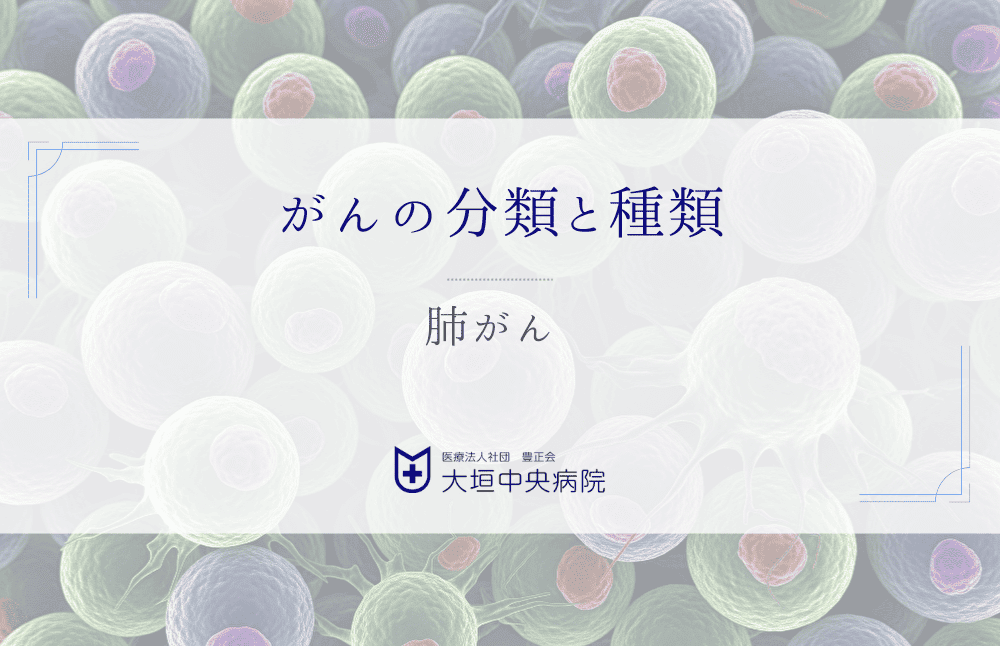
中皮腫
中皮腫は、胸膜や腹膜などの中皮と呼ばれる薄い膜に発生する悪性腫瘍です。最も多いのは胸膜中皮腫で、肺を覆う胸膜に腫瘍が形成されます。
主な原因はアスベスト(石綿)への曝露で、建設業や造船業などでアスベストを扱った職歴のある方に多く見られます。潜伏期間は20-50年と非常に長く、症状として息切れ、胸痛、咳などが現れます。
診断は画像検査や組織検査で行われますが、早期発見は困難です。治療は手術、化学療法、放射線療法を組み合わせて行いますが、予後は厳しく、根治的治療が困難な場合が多いとされています。
アスベスト規制により新規患者は減少傾向にありますが、過去の曝露による発症は今後も続くと予想されます。
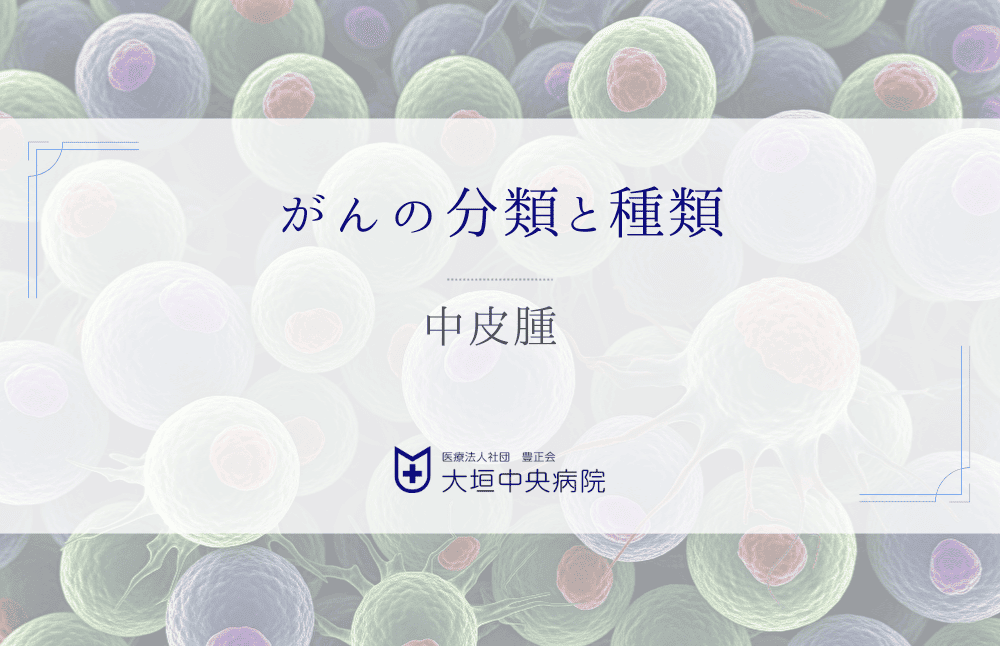
泌尿生殖器系のがん
尿を生成・排泄する腎臓や膀胱、尿管などの泌尿器と、男性の生殖器である前立腺や精巣に発生するがんを指します。高齢化に伴い、特に前立腺がんの患者数は増加しています。
血尿は、この領域のがんに共通する重要なサインの一つであり、早期発見の手がかりとなります。
腎臓がん
腎臓がんの多くは、尿を作る細胞(尿細管)ががん化する腎細胞がんです。初期は無症状ですが、進行すると血尿、腹部のしこり、わき腹の痛みなどが現れます。
健康診断などの超音波検査やCT検査で偶然発見されるケースが増えています。
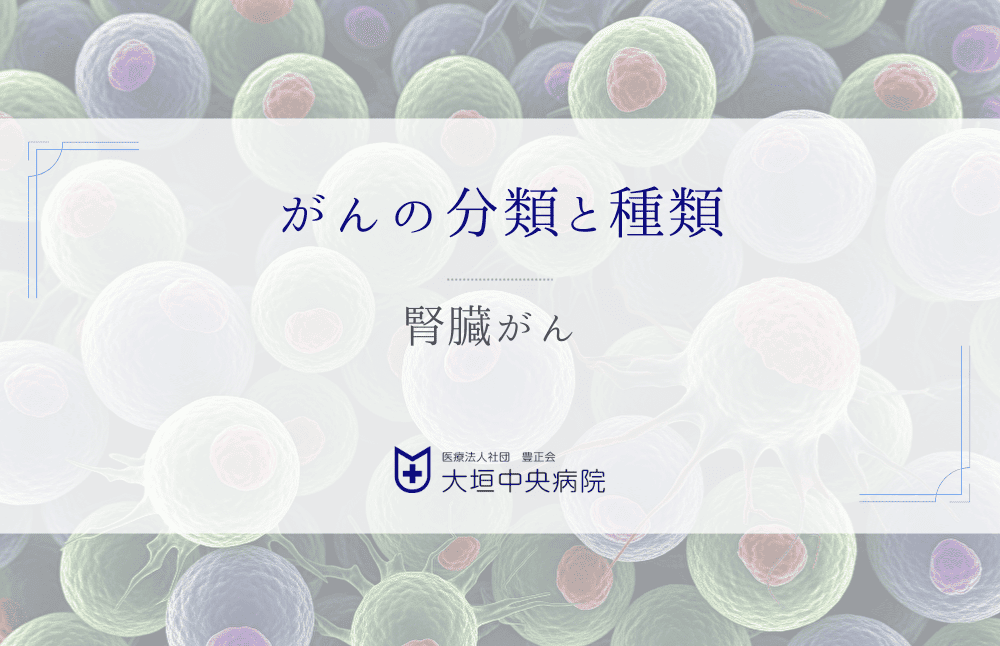
膀胱がん
膀胱がんは、膀胱の内側を覆う尿路上皮という粘膜から発生します。最も特徴的な症状は、痛みを伴わない肉眼的な血尿です。
一度血尿が出ても自然に止まることがあるため、放置せずに泌尿器科を受診することが重要です。喫煙が大きなリスク要因であることが知られています。
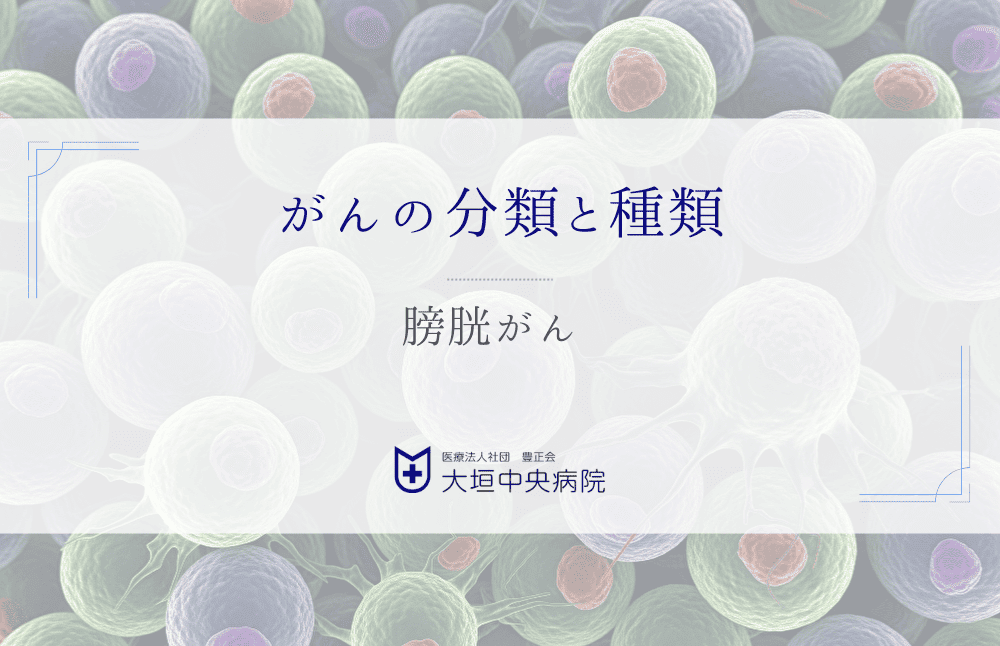
前立腺がん
前立腺は男性のみにある臓器で、膀胱のすぐ下に位置します。前立腺がんは、初期にはほとんど症状が出ません。
進行すると、尿が出にくい、頻尿、残尿感といった排尿に関する症状や、骨への転移による腰痛などが現れます。血液検査でPSA(前立腺特異抗原)の値を調べることで、早期発見のきっかけになります。
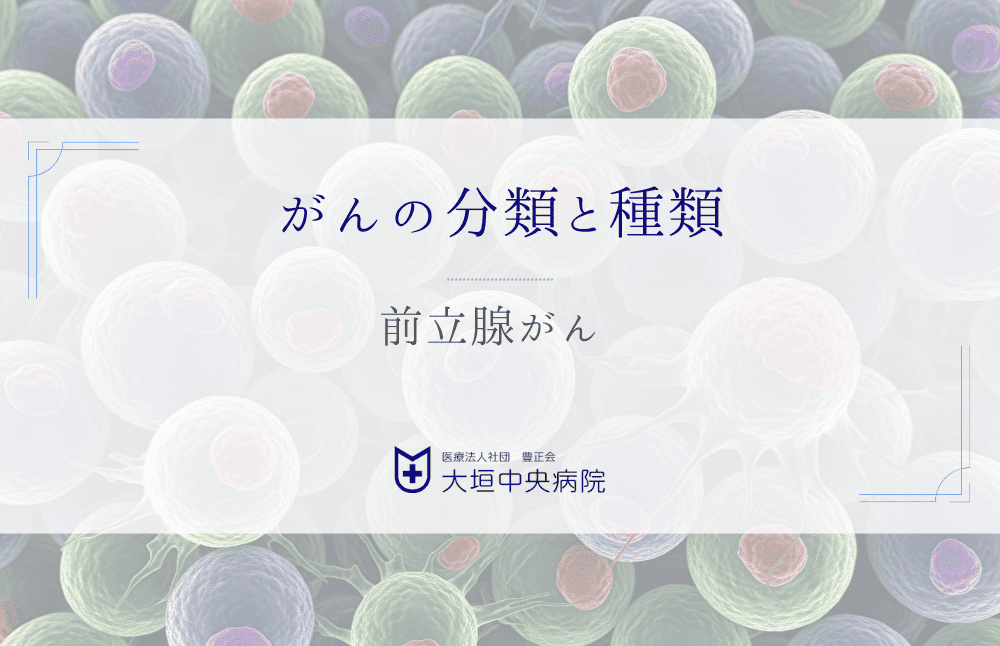
精巣がん
精巣がんは、男性の精巣(睾丸)に発生する悪性腫瘍です。20~40代の比較的若い男性に多く見られ、男性がん全体の約1%を占めます。主な症状は精巣の腫れや硬いしこり、痛みや重い感じなどです。
早期発見が重要で、自己検診により異常を感じたら泌尿器科を受診すべきです。
精巣がんは胚細胞腫瘍が大部分を占め、セミノーマと非セミノーマに分類されます。
転移しやすいがんですが、化学療法や放射線療法に非常によく反応するため、早期発見・治療により90%以上の高い治癒率を誇ります。
治療法は手術による精巣摘除が基本で、病期に応じて追加治療を行います。妊孕性への配慮も重要な治療方針の一つです。

主な泌尿器系がんの検査
| がんの種類 | 初期症状のサイン | 重要な検査 |
|---|---|---|
| 腎臓がん | 血尿、腹部のしこり | 超音波検査、CT検査 |
| 膀胱がん | 痛みのない血尿 | 尿検査、膀胱鏡検査 |
| 前立腺がん | 初期は無症状、進行すると排尿困難 | PSA検査、直腸診 |
| 精巣がん | 精巣の腫れ痛 | 超音波血液検 |
婦人科系のがん
女性特有の臓器である、子宮、卵巣、乳房などに発生するがんを指します。女性ホルモンが関与するものも多く、ライフステージの変化とともにリスクも変動します。
子宮頸がんや乳がんは、検診による早期発見が可能な代表的ながんであり、定期的な受診が推奨されます。
子宮頸がん
子宮の入り口部分(子宮頸部)に発生するがんで、そのほとんどがHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因であることが分かっています。20代から30代の若い世代での発症が増加傾向にあります。
HPVワクチン接種と、20歳からの定期的な子宮頸がん検診が予防と早期発見に有効です。
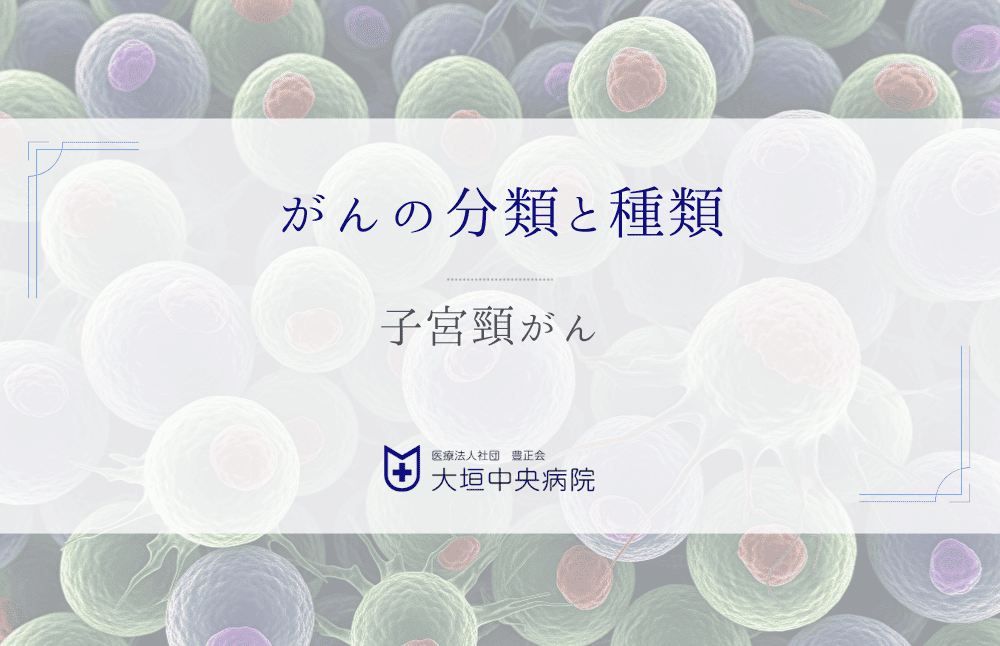
子宮体がん
子宮の奥、胎児が育つ部分(子宮体部)の内膜から発生するがんです。主な症状は不正出血で、特に閉経後の不正出血は重要なサインです。
エストロゲンという女性ホルモンが長く作用することが発生に関与しており、出産経験がない、肥満、糖尿病などがリスク要因となります。
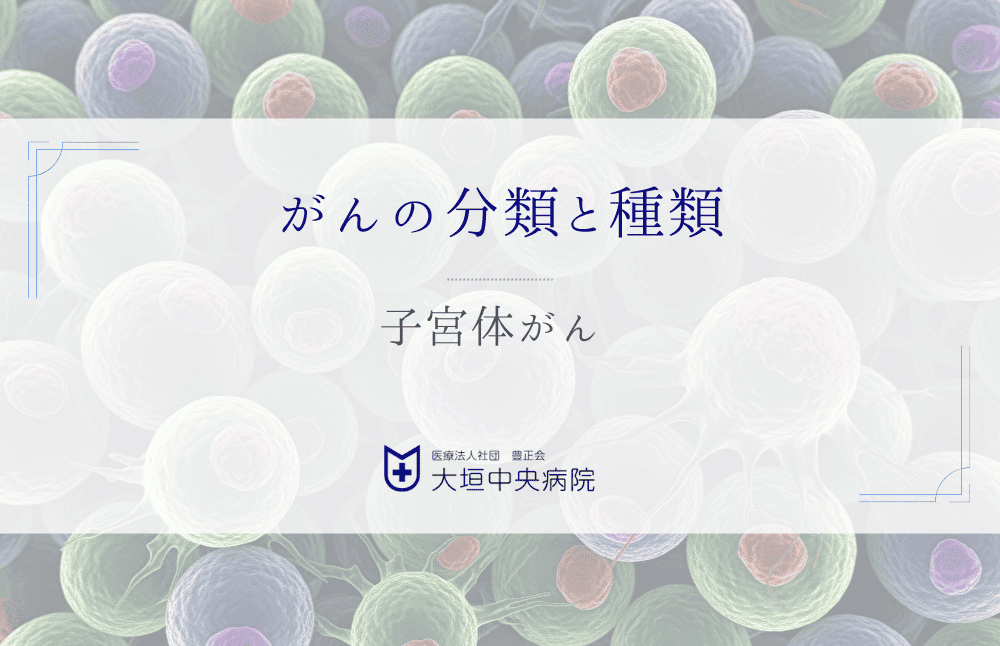
卵巣がん
卵巣は骨盤の深い部分にあるため、がんが発生しても初期症状が出にくく、「サイレントキラー(静かなる殺人者)」とも呼ばれます。
お腹の張りや食欲不振、頻尿などの症状が出たときには、すでに進行していることが多いのが特徴です。そのため、診断が難しく、治療が困難なケースも少なくありません。
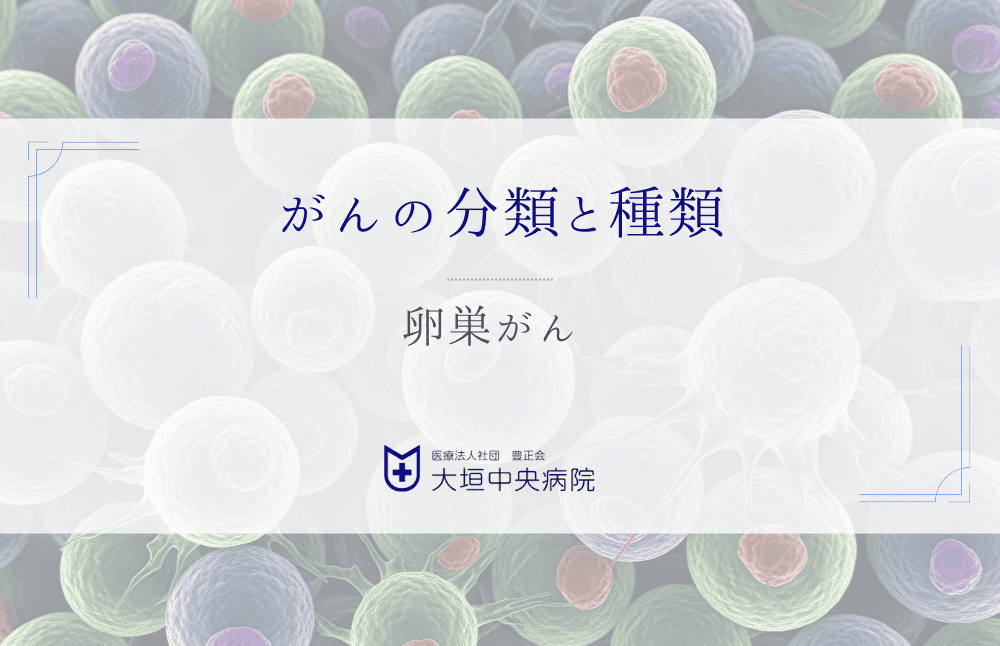
乳がん
乳房にある母乳を作る組織(乳腺)から発生します。女性が最もかかりやすいがんであり、40代後半から60代後半に発症のピークがあります。
自分で乳房を触ってしこりを発見することが早期発見のきっかけになることも多く、定期的な自己検診と、40歳からのマンモグラフィ検診が大切です。
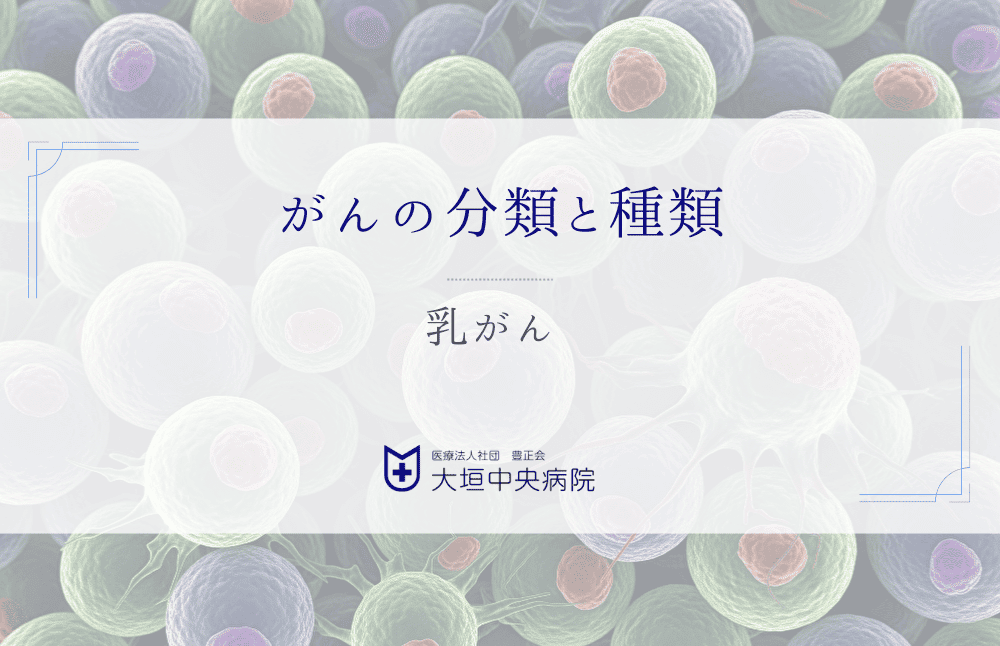
婦人科系がんの検診と自己チェック
| がんの種類 | 主な検診方法 | 自己チェックのポイント |
|---|---|---|
| 子宮頸がん | 細胞診 | 不正出血、おりものの異常 |
| 子宮体がん | 細胞診、組織診 | 閉経後の不正出血 |
| 卵巣がん | 経腟超音波検査と腫瘍マーカー | 腹部膨満感や下腹部痛の持続 |
| 乳がん | マンモグラフィ、超音波検査 | 乳房のしこり、ひきつれ、分泌物 |
内分泌系のがん
ホルモンを産生し、体の様々な機能を調節する内分泌器官に発生するがんです。代表的なものに甲状腺がんがあります。
多くは進行が比較的緩やかで、予後が良いとされていますが、種類によっては進行が速いものもあります。
甲状腺がん
首の前部にある甲状腺に発生するがんです。多くは痛みなどの自覚症状がなく、首のしこりや腫れで気づかれます。進行は緩やかな「乳頭がん」がほとんどを占め、予後は良好です。
しかし、まれに進行の速い未分化がんなどもあります。健康診断などで首の腫れを指摘されて発見されることもあります。
甲状腺がんの主な組織型
| 組織型 | 割合 | 特徴 |
|---|---|---|
| 乳頭がん | 約90% | 進行が非常に緩やかで、予後が良い。 |
| 濾胞がん | 約5% | 乳頭がんに次いで多く、比較的予後が良い。 |
| 髄様がん | 約1-2% | 遺伝性のことがある。 |
| 未分化がん | 約1-2% | 進行が非常に速く、悪性度が高い。 |
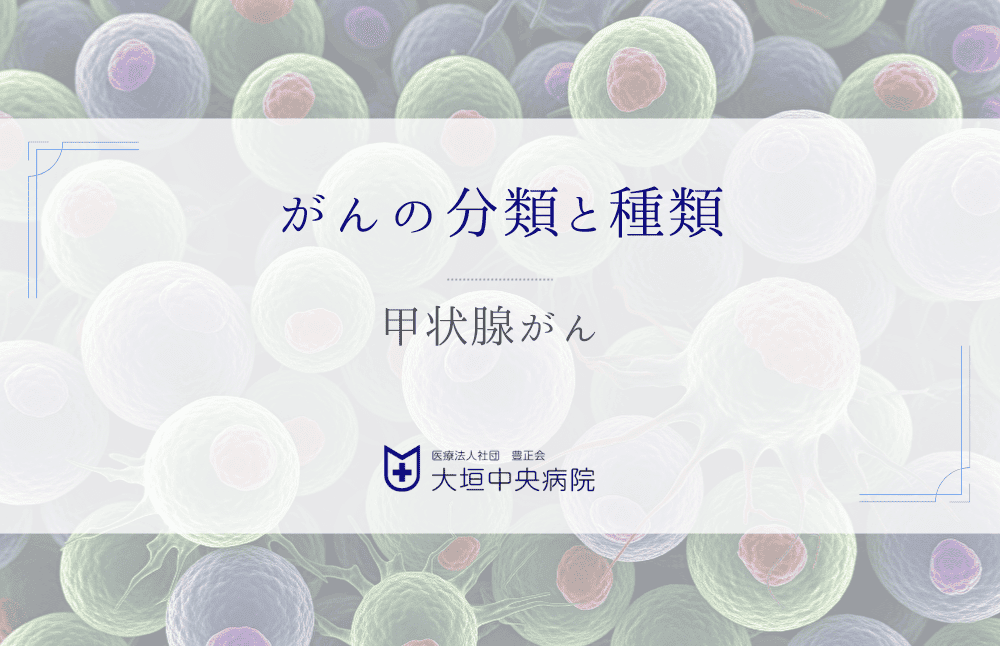
副腎がん
副腎がんは、副腎に発生する悪性腫瘍で、非常に稀ながん(年間発症率10万人に1-2人程度)です。副腎は腎臓の上に位置する内分泌器官で、コルチゾールやアドレナリンなどのホルモンを分泌します。
副腎がんは機能性と非機能性に分類されます。機能性では過剰なホルモン分泌により、高血圧、糖尿病、満月様顔貌、筋力低下などの症状が現れます。
非機能性では腫瘍が大きくなるまで無症状のことが多く、腹痛や腫瘤として発見されます。
診断にはCTやMRI検査、ホルモン検査が用いられます。治療の基本は外科的切除ですが、転移しやすく予後は厳しいがんとして知られています。
早期発見のため、原因不明の高血圧や糖尿病がある場合は専門医への相談が重要です。
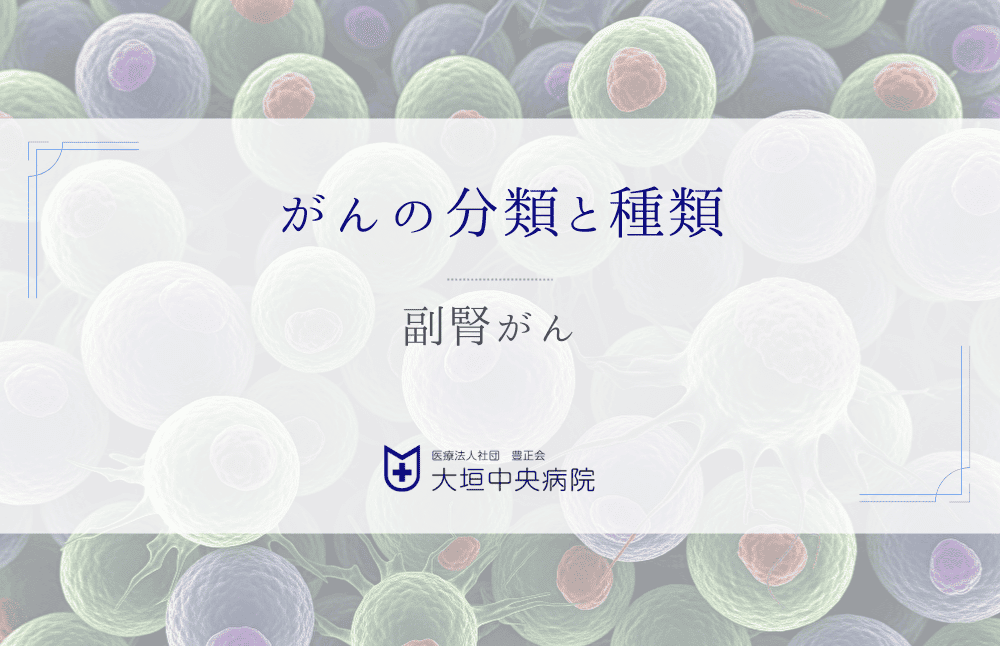
頭頸部のがん
頭頸部がんは、脳と眼を除いた、頭から首の部分に発生するがんの総称です。具体的には、鼻、口、のど(咽頭・喉頭)、唾液腺などが含まれます。
話す、食べる、呼吸するといった、人が生きていく上で重要な機能に関わる部位に発生するため、治療の際には機能温存も大きな課題となります。喫煙と飲酒が二大リスク要因です。
口腔がん
口腔がんは口の中に発生する悪性腫瘍で、舌、歯肉、頬の粘膜、口底、硬口蓋などに生じます。日本では年間約8,000人が発症し、男性に多く見られます。
主な原因は喫煙と飲酒で、両方の習慣がある人はリスクが特に高くなります。その他、HPV感染、慢性的な刺激、栄養不足も関与します。
初期症状として、治りにくい口内炎、白斑や赤斑、しこり、出血、痛み、舌の動きにくさなどがあります。2週間以上続く症状は要注意です。
診断は視診、触診、生検で行います。治療は手術、放射線療法、化学療法を組み合わせ、早期発見なら5年生存率は90%以上と良好です。
予防には禁煙・節酒、口腔衛生の維持、定期的な歯科検診が重要です。
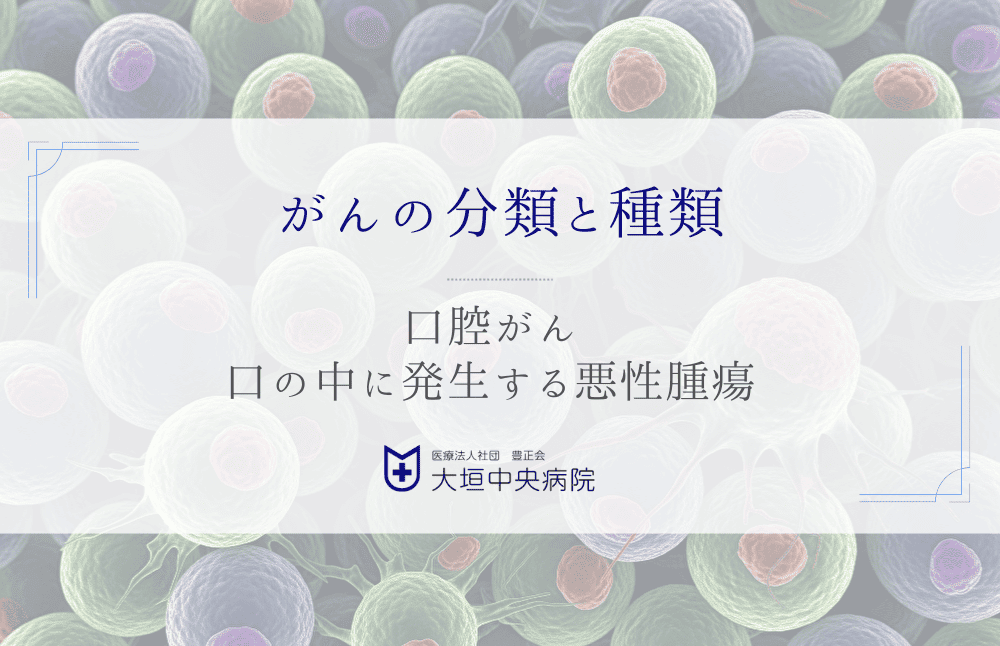
咽頭がん
咽頭がんは、のどの奥にある咽頭に発生するがんです。上咽頭、中咽頭、下咽頭の3つの部位に分類され、それぞれ原因や症状が異なります。
主な原因は喫煙と飲酒で、特に両方を併用すると発症リスクが大幅に高まります。近年、HPV(ヒトパピローマウイルス)感染による中咽頭がんも増加傾向にあります。
初期症状として、のどの痛み、嚥下困難、声のかすれ、首のリンパ節腫脹などがあります。進行すると呼吸困難や出血を伴うことがあります。
診断は内視鏡検査や組織検査により行い、治療は手術、放射線療法、化学療法を組み合わせて実施します。
早期発見・治療により予後の改善が期待できるため、持続する症状がある場合は耳鼻咽喉科での検査が重要です。
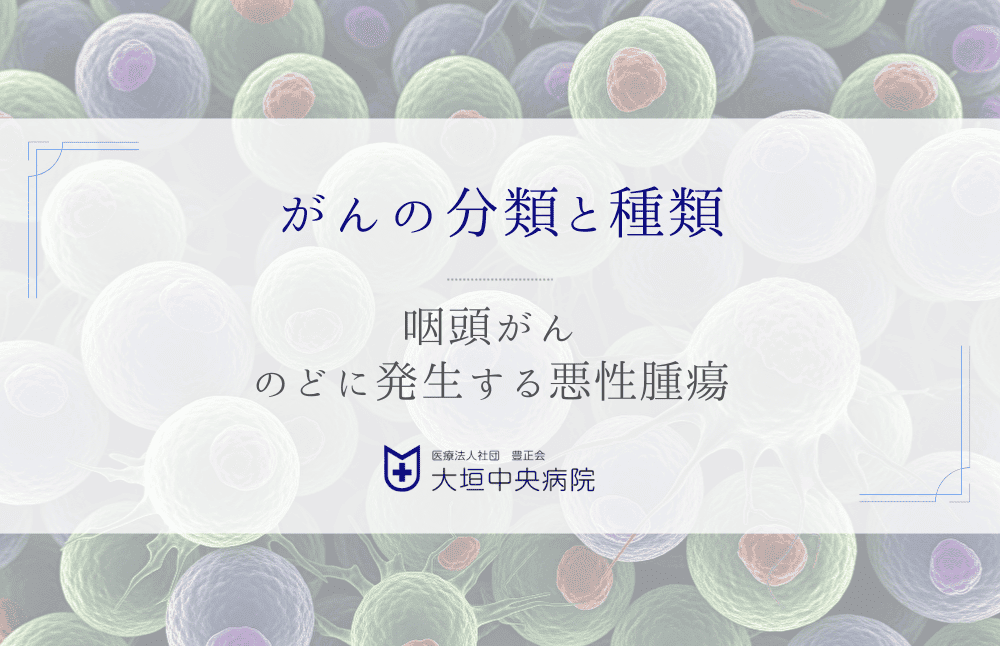
喉頭がん
喉頭がんは、声帯やその周辺の喉頭に発生する悪性腫瘍です。主な原因は喫煙と過度の飲酒で、特に両方の習慣がある場合にリスクが高まります。男性に多く見られ、50歳以降の発症が一般的です。
初期症状として最も重要なのは声の変化(嗄声)で、2週間以上続く場合は要注意です。進行すると呼吸困難、嚥下障害、首のしこり、耳の痛みなどが現れます。
診断は内視鏡検査や生検で行われ、治療は病期により異なります。早期なら放射線治療や内視鏡手術、進行例では喉頭摘出術が必要な場合もあります。
近年は機能温存治療も発達しており、声帯を残す手術や化学放射線療法も選択肢となっています。禁煙・禁酒が最も効果的な予防法です。
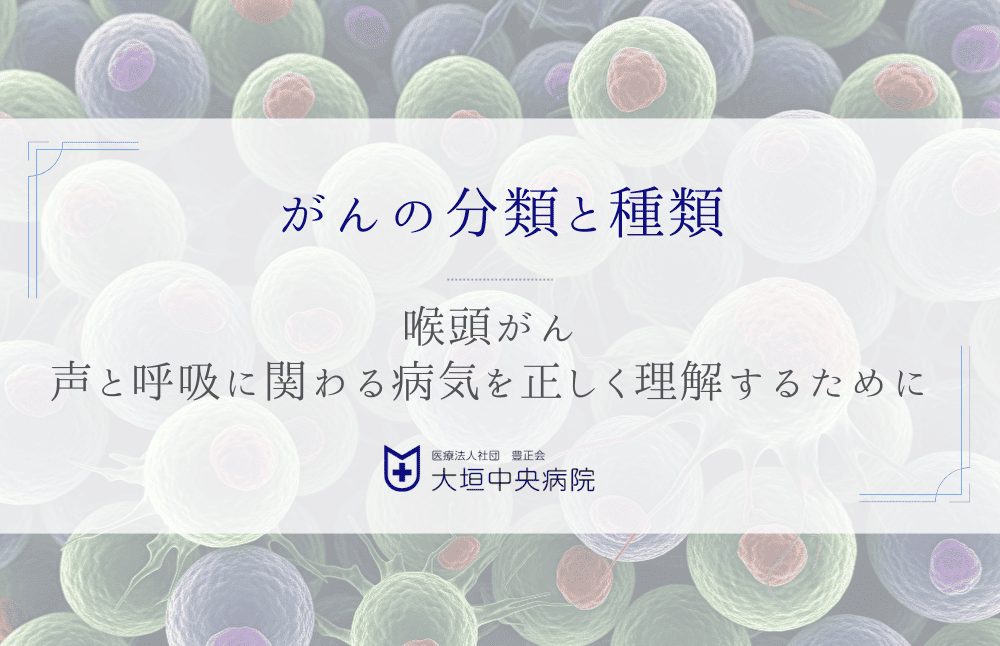
頭頸部がんのリスク因子
| リスク因子 | 関連するがん | 補足 |
|---|---|---|
| 喫煙 | 口腔・咽頭・喉頭がん全般 | 最も大きな原因。受動喫煙も含む。 |
| 飲酒 | 口腔・咽頭・喉頭がん全般 | 喫煙と合わさるとリスクが相乗的に高まる。 |
| HPV | 中咽頭がん | ウイルスの感染が原因となるタイプがある。 |
脳・神経系のがん
脳や脊髄などの中枢神経系に発生する腫瘍を指します。他の臓器から転移してきた「転移性脳腫瘍」と、脳そのものから発生した「原発性脳腫瘍」に大別されます。
良性腫瘍も含まれますが、頭蓋骨内部という限られた空間に発生するため、良性であっても大きくなることで脳を圧迫し、深刻な症状を引き起こすことがあります。
脳腫瘍の分類
原発性脳腫瘍と転移性脳腫瘍
原発性脳腫瘍は、脳を構成する細胞そのものから発生する腫瘍です。神経膠腫(グリオーマ)や髄膜腫などが代表的です。
一方、転移性脳腫瘍は、肺がんや乳がんなど、体の別の場所で発生したがん細胞が、血液の流れに乗って脳に移動し、そこで増殖したものです。成人の脳腫瘍では、転移性脳腫瘍の頻度が高くなります。
主な症状
脳腫瘍の症状は、腫瘍ができた場所と大きさによって様々です。共通して見られる症状として、頭蓋骨内の圧力が高まることによる、持続的な頭痛や吐き気、嘔吐があります。
また、腫瘍が脳の特定の部分を圧迫したり破壊したりすることで、手足の麻痺やしびれ、けいれん発作、言語障害、視力障害など、局所的な症状が現れます。
主な原発性脳腫瘍の種類
| 腫瘍の名称 | 発生源 | 特徴 |
|---|---|---|
| 神経膠腫 (グリオーマ) | 脳の神経細胞を支えるグリア細胞 | 原発性脳腫瘍の中で最も多い。悪性度が高いものが多い。 |
| 髄膜腫 | 脳を覆う髄膜 | 多くは良性で、ゆっくりと増殖する。 |
| 下垂体腺腫 | 脳下垂体 | ホルモン産生の異常や視力障害を引き起こす。 |
神経膠腫
神経膠腫(しんけいこうしゅ)は、脳や脊髄の神経膠細胞(グリア細胞)から発生する腫瘍です。脳腫瘍の中で最も頻度が高く、全脳腫瘍の約40-50%を占めます。
WHO分類により悪性度がグレード1から4に分類され、グレード1・2は低悪性度、グレード3・4は高悪性度とされます。最も悪性度の高いグレード4は膠芽腫と呼ばれます。
症状は腫瘍の部位により異なりますが、頭痛、嘔吐、けいれん、運動麻痺、言語障害、視野欠損などが現れます。診断にはMRIやCT検査が用いられ、確定診断には病理組織検査が必要です。
治療は手術による摘出が基本で、放射線治療や化学療法を組み合わせた集学的治療が行われます。予後は悪性度により大きく異なり、低悪性度では長期生存が期待できますが、高悪性度では厳しい経過をたどることが多いのが現状です。
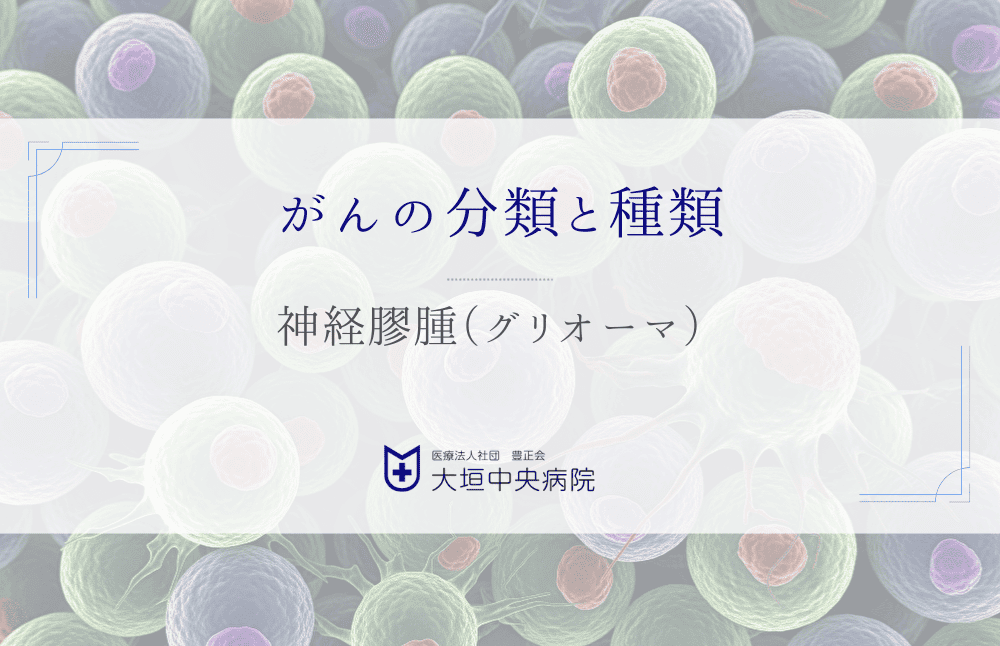
髄膜腫
髄膜腫は、脳や脊髄を覆う髄膜という薄い膜から発生する腫瘍です。脳腫瘍の中で最も頻度が高く、全体の約30-40%を占めます。多くは良性で、40-60歳代の女性に好発する傾向があります。
症状は腫瘍の発生部位によって異なり、頭痛、けいれん、視野障害、運動麻痺、言語障害などが現れることがあります。しかし、小さな髄膜腫では無症状のことも多く、健康診断のMRIで偶然発見されることもあります。
診断にはCTやMRI検査が有効で、特徴的な画像所見を示します。治療は腫瘍の大きさ、部位、症状の有無によって決定され、経過観察、外科的摘出術、放射線治療などが選択されます。
良性の場合、完全摘出により根治が期待できますが、重要な部位にある場合は慎重な治療方針が必要です。
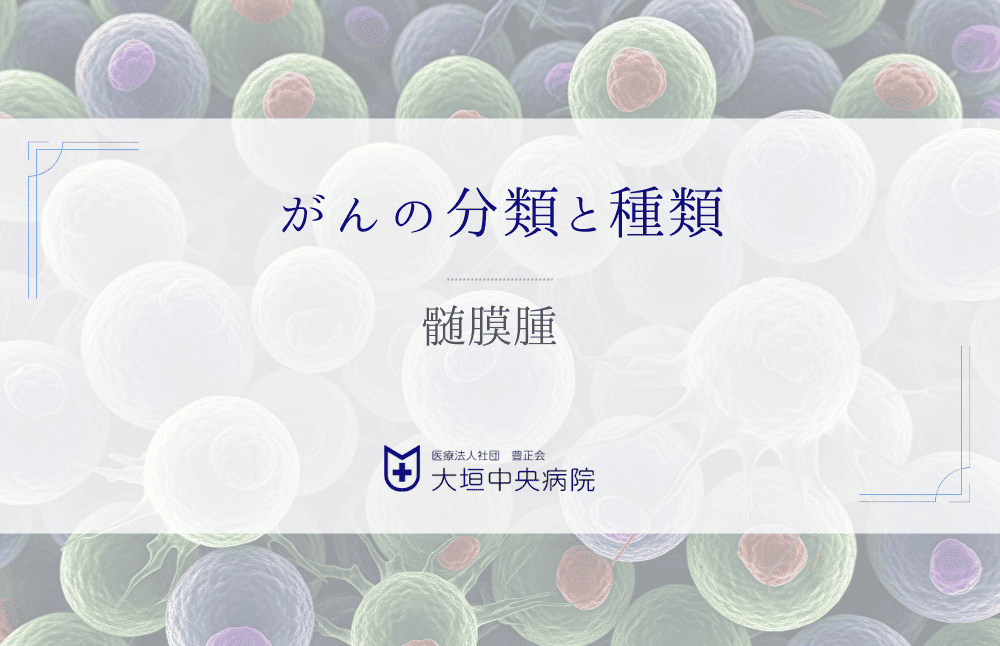
神経鞘腫
神経鞘腫は、末梢神経を覆うシュワン細胞から発生する良性腫瘍です。全身のあらゆる神経に発生する可能性がありますが、特に聴神経(前庭神経鞘腫)、三叉神経、脊髄神経根に多く見られます。
症状は腫瘍の発生部位により異なります。聴神経鞘腫では難聴や耳鳴り、めまいが生じ、脊髄神経鞘腫では神経根症状として痛みやしびれが現れます。四肢の神経鞘腫では局所の腫瘤として触知されることもあります。
診断にはMRI検査が有効で、造影剤使用により腫瘍の性状を詳しく評価できます。治療は手術による摘出が基本ですが、小さく無症状の場合は経過観察を選択することもあります。
悪性化は稀ですが、急速な増大や神経症状の悪化がある場合は早期の治療介入が必要です。
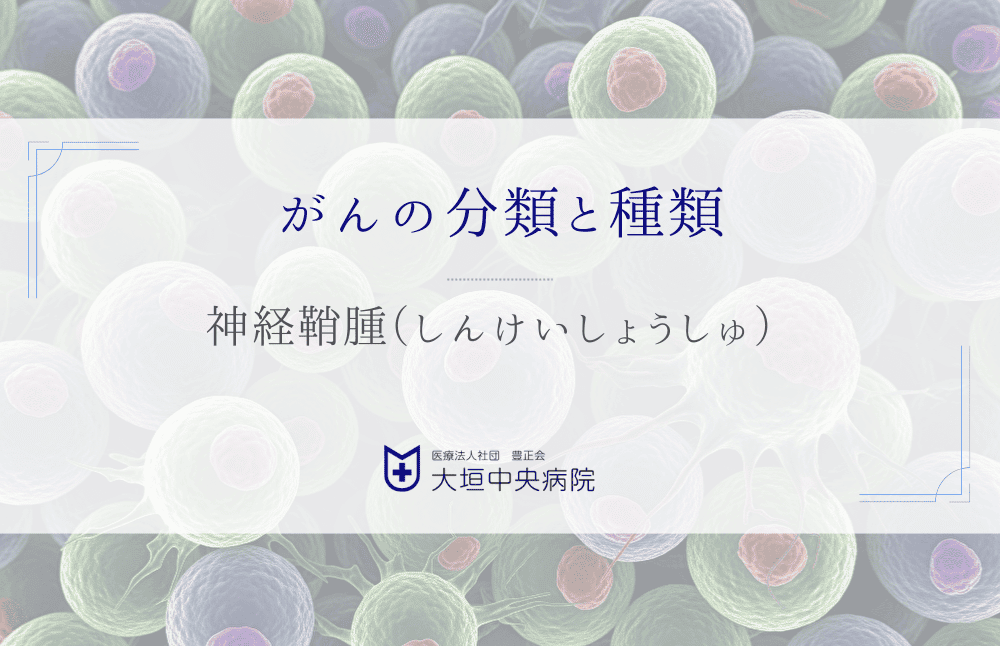
皮膚のがん
皮膚がんは、体の最も外側を覆う皮膚に発生するがんです。日光(紫外線)に当たりやすい顔や首、手足などに発生することが多いのが特徴です。
様々な種類がありますが、代表的なものに悪性黒色腫(メラノーマ)、基底細胞がん、有棘細胞がんがあります。ほくろやしみに似た外見をすることがあり、早期発見には日頃のセルフチェックが重要です。
悪性黒色腫(メラノーマ)
悪性黒色腫(メラノーマ)は、皮膚のメラニン色素を作る細胞(メラノサイト)から発生する悪性腫瘍です。皮膚がんの中でも特に悪性度が高く、転移しやすいことが特徴です。
主な原因は紫外線の過度な曝露で、色白の人や日焼けしやすい人にリスクが高まります。また、多数のほくろがある人や家族歴のある人も注意が必要です。
早期発見のポイントは「ABCDE」として知られています。A(非対称性)、B(境界不整)、C(色調不均一)、D(直径6mm以上)、E(隆起・変化)です。既存のほくろの形や色の変化、新たな黒い斑点の出現、かゆみや出血も危険信号です。
治療は早期なら外科的切除で完治可能ですが、進行すると化学療法や免疫療法が必要になります。予防には日焼け止めの使用や帽子の着用など、紫外線対策が重要です。
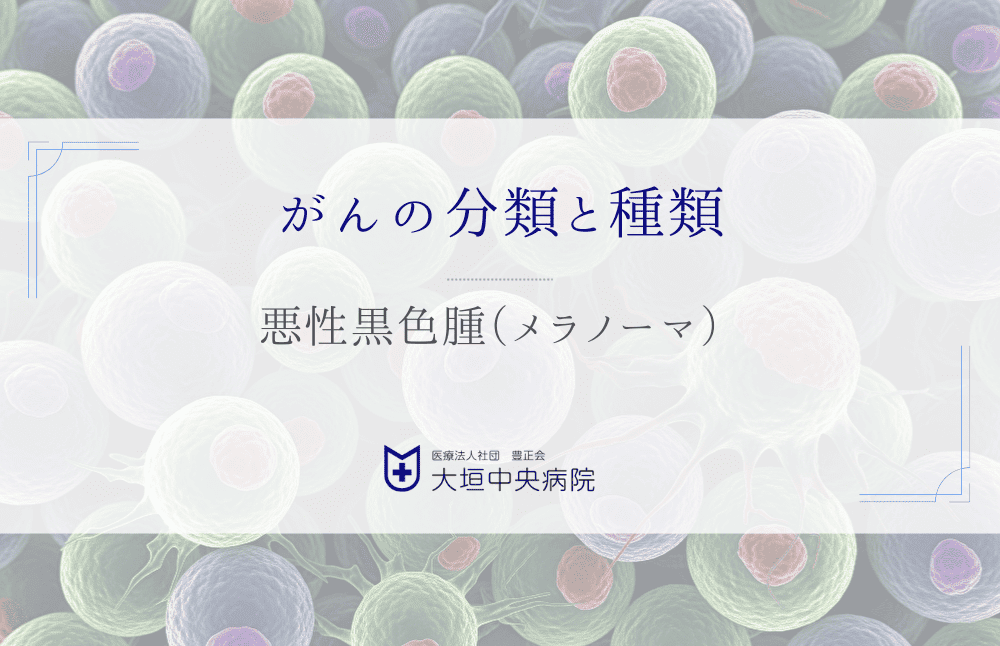
基底細胞がん
基底細胞がんは、皮膚がんの中で最も頻度が高く、皮膚の最下層にある基底細胞から発生する悪性腫瘍です。主な原因は長年の紫外線曝露で、高齢者や色白の人に多く見られます。
典型的には顔面、特に鼻や額、眼瞼周囲に黒褐色や赤色の結節として現れ、中央部が潰瘍化することがあります。進行は緩やかで、他の臓器への転移はほとんどありませんが、放置すると局所で深く浸潤し、周囲組織を破壊します。
診断は皮膚生検で確定し、治療は外科的切除が第一選択です。小さな病変では液体窒素による凍結療法や光線力学的療法も選択肢となります。
予後は良好で、適切な治療により治癒率は95%以上です。日頃からの紫外線対策と皮膚の自己観察が予防と早期発見に重要です。
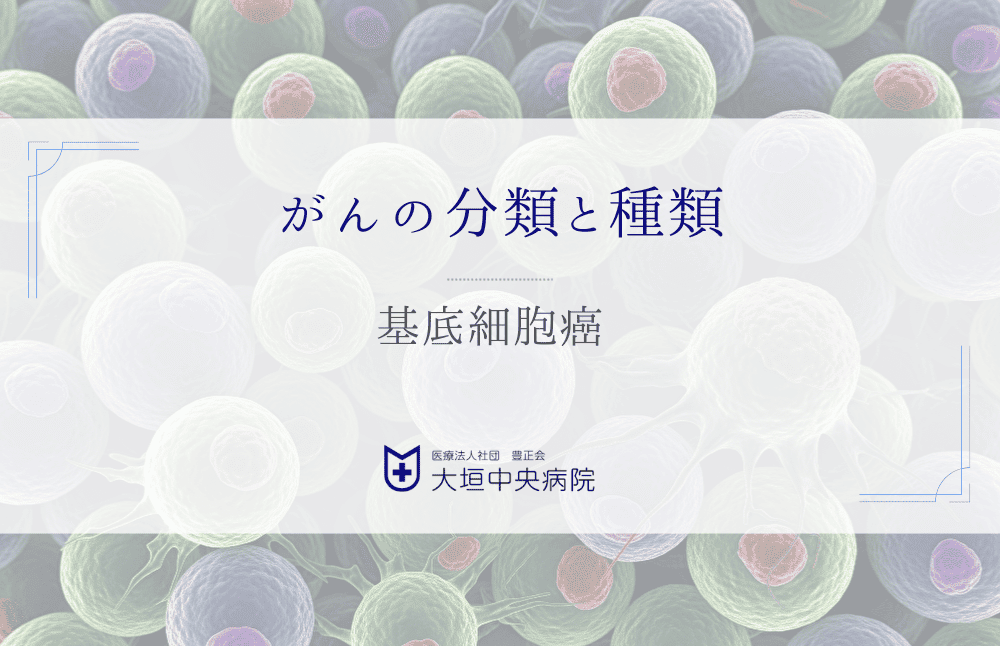
有棘細胞がん
有棘細胞がんは皮膚の表皮にある有棘細胞から発生する悪性腫瘍で、皮膚がんの中で2番目に多い疾患です。
主な原因は長期間の紫外線曝露で、高齢者や色白の人、屋外作業者に多く見られます。初期は赤い斑点や盛り上がった病変として現れ、進行すると潰瘍化や出血を伴います。
顔面、首、手の甲など日光に当たりやすい部位に好発し、放置すると周囲組織に浸潤したり、リンパ節や他の臓器に転移する可能性があります。早期発見・早期治療が重要で、手術による切除が基本治療となります。
日頃から日焼け対策を行い、皮膚の変化に注意して定期的な皮膚科受診を心がけることが予防と早期発見につながります。
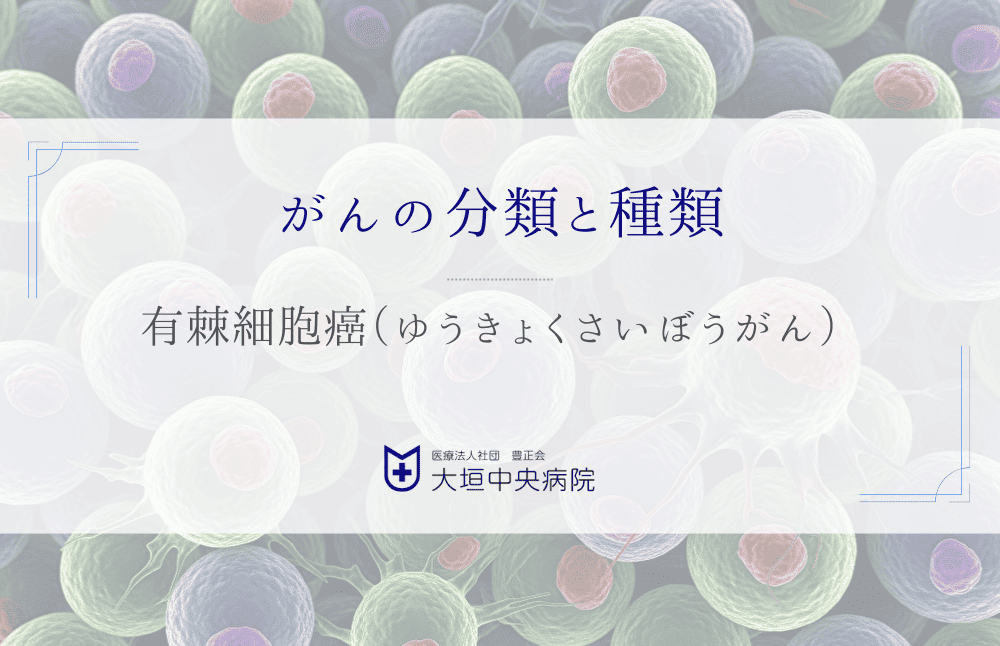
皮膚がんのセルフチェックポイント
| チェック項目 | 内容 | 悪性黒色腫の可能性 |
|---|---|---|
| 形状 (Asymmetry) | 形が左右非対称か | 非対称である |
| 境界 (Border) | 縁がギザギザしているか | 境界が不鮮明・ギザギザ |
| 色 (Color) | 色に濃淡があるか | 色がまだら・不均一 |
がんのステージ(病期)に関するよくある質問
- がんのステージ(病期)とは何ですか?
-
がんの進行度を示す指標です。ステージ(病期)とは、がんがどのくらい進行しているかを示す世界共通の指標です。
がんの大きさ、周囲の組織への広がり、リンパ節への転移の有無、他の臓器への転移(遠隔転移)の有無という3つの要素を総合的に評価して決定します。
一般的に、ローマ数字を用いてStage I(早期)からStage IV(進行)のように分類します。
- なぜステージを分類する必要があるのですか?
-
治療方針を決定する上で重要だからです。ステージ分類は、今後の治療方針を決定するための最も重要な情報の一つです。
例えば、早期のがんであれば手術や内視鏡治療が中心になりますが、進行して他の臓器に転移している場合は、抗がん剤治療や放射線治療などの全身治療が主体となります。
また、治療後の経過を予測する上でも参考にします。
- TNM分類とは何ですか?
-
がんの広がりを評価する国際的な基準で、TNM分類は、ステージを決定するための国際的な分類法です。
T(Tumor)は元のがん(原発巣)の大きさや広がり、N(Nodes)は所属リンパ節への転移の有無と範囲、M(Metastasis)は他の臓ഗ്യへの遠隔転移の有無を示します。
このT・N・Mの3つの要素の組み合わせによって、最終的なステージ(Stage I〜IV)が決定します。
- ステージは治療の途中で変わりますか?
-
基本的には診断時のステージが治療の基準となります。ステージは、治療を開始する前の様々な検査結果に基づいて決定した「初回治療時の進行度」を指します。
治療によってがんが小さくなったり、あるいは再発したりしても、最初に診断されたステージそのものが変更されることはありません。
治療の効果やその後の経過は、あくまで初回診断時のステージを基準として評価します。
この記事では、がんのステージに関する基本的な質問にお答えしました。
しかし、ご自身の治療方針を深く理解するためには、ステージ分類の基準である「TNM分類」について、もう少し詳しく知ることが助けになります。
T・N・Mの各因子が具体的に何を意味し、どのように組み合わさってステージが決定するのかを把握することで、医師からの説明がより明確に理解できるようになります。
次の記事では、TNM分類の具体的な見方や、ステージと生存率の関係など、一歩進んだ内容を詳しく解説しています。ぜひご自身の状況と照らし合わせながらお読みください。
参考文献
CARBONE, Antonino. Cancer classification at the crossroads. Cancers, 2020, 12.4: 980.
SMOLARZ, Beata; NOWAK, Anna Zadrożna; ROMANOWICZ, Hanna. Breast cancer—epidemiology, classification, pathogenesis and treatment (review of literature). Cancers, 2022, 14.10: 2569.
DOS SANTOS SILVA, Isabel. Cancer epidemiology: principles and methods. IARC, 1999.
TOTHILL, Richard W., et al. An expression-based site of origin diagnostic method designed for clinical application to cancer of unknown origin. Cancer Research, 2005, 65.10: 4031-4040.
ZAMWAR, Udit M.; ANJANKAR, Ashish P.; ANJANKAR, Ashish. Aetiology, epidemiology, histopathology, classification, detailed evaluation, and treatment of ovarian cancer. Cureus, 2022, 14.10.
BELLIZZI, Andrew M. An algorithmic immunohistochemical approach to define tumor type and assign site of origin. Advances in anatomic pathology, 2020, 27.3: 114-163.
RAI, Ritu, et al. An overview of breast cancer epidemiology, risk factors, classification, genetics, diagnosis and treatment. Vantage: Journal of Thematic Analysis, 2023, 4.1: 45-67.
PICCIOLI, Andrea, et al. Bone metastases of unknown origin: epidemiology and principles of management. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2015, 16.2: 81-86.
MCGUIGAN, Andrew, et al. Pancreatic cancer: A review of clinical diagnosis, epidemiology, treatment and outcomes. World journal of gastroenterology, 2018, 24.43: 4846.
SAWICKI, Tomasz, et al. A review of colorectal cancer in terms of epidemiology, risk factors, development, symptoms and diagnosis. Cancers, 2021, 13.9: 2025.