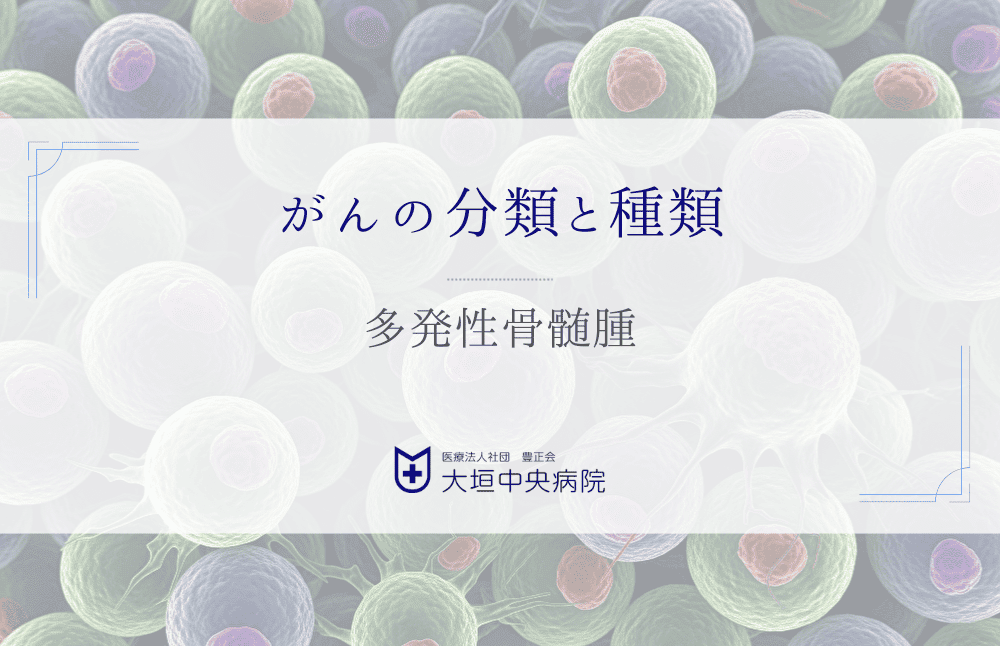多発性骨髄腫は、血液細胞の一種である「形質細胞」が、骨の中心部にある「骨髄」でがん化する病気です。
この記事では、多発性骨髄腫の基本的な知識から、特徴的な症状、検査、そして薬物療法や自家移植といった治療法までを、患者様とそのご家族が理解しやすいように詳しく解説します。
多発性骨髄腫の基本 – 血液がんの一種としての特徴
多発性骨髄腫を正しく理解するためには、まず、この病気が血液のがんであること、そして私たちの体を守る免疫システムと深く関わっていることを知るのが大切です。
骨の中で静かに進行するため、初期には気づきにくい特徴があります。
形質細胞の役割と異常
私たちの体には、細菌やウイルスといった外敵から身を守るための免疫システムが備わっています。その中心的な役割を担うのが、白血球の一種であるリンパ球です。
形質細胞は、このリンパ球が成熟した最終形態であり、外敵と戦うための「抗体」というタンパク質を産生する重要な細胞です。
しかし、この形質細胞ががん化すると、異常な抗体(M蛋白)を無秩序に作り続けるようになり、体に様々な不調を引き起こします。
骨髄の機能
骨髄は、骨の中心部にあるスポンジ状の柔らかい組織で、血液細胞(赤血球、白血球、血小板)を作り出す「造血工場」としての役割を担います。
多発性骨髄腫では、この骨髄でがん化した形質細胞(骨髄腫細胞)が増殖し、正常な血液細胞の産生を妨げます。これが貧血や感染症にかかりやすくなる原因の一つです。
血液がんの中での位置づけ
| がんの種類 | 主ながん化する細胞 | 主な発生場所 |
|---|---|---|
| 白血病 | 未熟な血液細胞 | 骨髄 |
| 悪性リンパ腫 | リンパ球 | リンパ節など |
| 多発性骨髄腫 | 成熟した形質細胞 | 骨髄 |
多発性骨髄腫の「多発性」の意味
この病名が示す「多発性」とは、がん化した形質細胞が骨髄の中の一か所にとどまらず、全身の様々な骨の骨髄で増殖する性質を指します。
そのため、背骨や肋骨、骨盤など、複数の骨に病変が生じることが多く、これが骨の痛みや骨折の原因となります。
形質細胞のがん化 – 正常な免疫細胞が変異する仕組み
正常な形質細胞がなぜがん化するのか、その詳細な原因はまだ完全には解明されていません。
しかし、遺伝子の変異が積み重なることで、細胞の増殖をコントロールする機能が失われ、がん化に至ると考えられています。
M蛋白の産生と影響
がん化した形質細胞(骨髄腫細胞)は、正常な抗体とは異なり、体を守る機能を持たない均一な異常タンパク質を大量に産生します。
これを「M蛋白(エムたんぱく)」と呼びます。このM蛋白が血液中に増えると、血液がドロドロになったり、腎臓に沈着して腎障害を引き起こしたりします。
M蛋白とは何か
| 項目 | 正常な抗体 | M蛋白 |
|---|---|---|
| 産生細胞 | 正常な形質細胞 | 骨髄腫細胞 |
| 種類 | 多種多様 | 単一(モノクローナル) |
| 機能 | 免疫機能を持つ | 免疫機能を持たない |
免疫機能の低下
骨髄腫細胞が増殖し、異常なM蛋白が増加する一方で、正常な抗体の産生は抑制されます。その結果、体の免疫力が全体的に低下し、肺炎や尿路感染症などの感染症にかかりやすくなります。
がん化の明確な原因
多発性骨髄腫の直接的な原因は特定されていません。遺伝的な要因が関与することもありますが、親から子へ遺伝する病気ではありません。
多くの場合は、加齢に伴う遺伝子の後天的な変化が引き金になると考えられています。
現在考えられているリスク要因
明確な原因は不明ですが、いくつかのリスク要因が指摘されています。
高齢であること(多くは60代以降に発症)、男性であること、また、特定の化学物質や放射線への曝露などが関連する可能性も研究されていますが、はっきりとした因果関係は確立していません。
特徴的な症状 – 骨の痛みから腎機能低下まで
多発性骨髄腫の症状は多彩で、個人差も大きいのが特徴です。病気の進行に伴って現れる代表的な症状は、その頭文字をとって「CRAB(クラブ)基準」と呼ばれ、診断や治療開始の判断に重要です。
CRAB基準で見る主要な症状
CRABは、高カルシウム血症(Calcium)、腎障害(Renal impairment)、貧血(Anemia)、骨病変(Bone lesions)の4つの主要な臓器障害を示します。
これらの症状は、骨髄腫細胞の増殖やM蛋白の影響によって引き起こされます。
C 高カルシウム血症
骨髄腫細胞が骨を破壊(骨吸収)することで、骨に含まれるカルシウムが血液中に溶け出し、血液中のカルシウム濃度が異常に高くなります。
これにより、喉の渇き、吐き気、意識の混濁などの症状が現れることがあります。
R 腎障害
M蛋白が腎臓の尿細管に詰まったり、高カルシウム血症が腎臓に負担をかけたりすることで、腎機能が低下します。これを腎障害と呼びます。
初期には自覚症状が乏しいですが、進行するとむくみや尿量の減少が見られます。
A 貧血
骨髄で骨髄腫細胞が増えすぎると、正常な赤血球を作るスペースが圧迫されます。
赤血球が減少すると、体中に酸素を運ぶ能力が低下し、貧血の状態になります。動悸、息切れ、倦怠感などが主な症状です。
B 骨病変
骨髄腫細胞は、骨を壊す細胞(破骨細胞)を活性化させる物質を放出します。
これにより、骨がもろくなり、骨の痛み(特に腰や背中、肋骨)や、ささいなことで骨折してしまう病的骨折を引き起こします。これを骨病変と呼びます。
CRAB基準の概要
| 基準 | 主な症状 | 原因 |
|---|---|---|
| C: 高カルシウム血症 | 喉の渇き、意識混濁 | 骨の破壊によるカルシウムの溶出 |
| R: 腎障害 | むくみ、尿量減少 | M蛋白の沈着、高カルシウム血症 |
| A: 貧血 | 倦怠感、息切れ | 正常な造血機能の抑制 |
| B: 骨病変 | 骨の痛み、病的骨折 | 骨を壊す細胞の活性化 |
その他の注意すべき症状
CRAB基準以外にも、注意すべき症状がいくつかあります。これらは病気の存在を示すサインである可能性があります。
倦怠感と体重減少
貧血によるものだけでなく、がん細胞が体力を消耗させることで、強い倦怠感や原因不明の体重減少が起こることがあります。
感染症への抵抗力低下
正常な抗体が作られなくなるため、免疫力が低下します。そのため、風邪やインフルエンザが重症化しやすくなったり、肺炎を繰り返したりすることがあります。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
診断の流れ – 血液検査から骨髄検査まで
多発性骨髄腫の診断は、血液検査や尿検査といった比較的簡単な検査から始まり、確定診断のためには骨髄の検査が必要になります。
一連の検査を通して、病気の有無だけでなく、その進行度や体の状態を総合的に評価します。
初期段階で行う検査
健康診断や他の病気の検査で偶然異常が見つかり、診断のきっかけとなることも少なくありません。特に血液検査は重要な手がかりを与えてくれます。
血液検査の重要性
血液検査では、M蛋白の有無や量、貧血の程度、腎機能、カルシウム値などを調べます。これらの項目は、病気の存在を示唆するだけでなく、病状の把握や治療効果の判定にも用いる重要な指標です。
| 検査項目 | 調べる内容 | 異常値が示すこと |
|---|---|---|
| 総蛋白・アルブミン | 血液中のタンパク質の量 | M蛋白の存在 |
| 血球計算 | 赤血球、白血球、血小板の数 | 貧血の有無 |
| 腎機能検査(Crなど) | 腎臓の働き | 腎障害の有無 |
| カルシウム値 | 血液中のカルシウム濃度 | 骨病変の進行度 |
尿検査で調べる項目
M蛋白の一部は分子量が小さいため、腎臓でろ過されて尿中に排出されることがあります。これを「ベンス・ジョーンズ蛋白」と呼び、尿検査でこのタンパク質の有無を調べることが診断の一助となります。
確定診断のための精密検査
血液検査や尿検査で多発性骨髄腫が疑われた場合、診断を確定するために、より詳しい検査を行います。
骨髄検査(骨髄穿刺・生検)
確定診断において最も重要な検査です。局所麻酔をした上で、通常は骨盤の骨(腸骨)に専用の針を刺し、骨髄液と骨髄組織の一部を採取します。
この検査で、骨髄の中に骨髄腫細胞(形質細胞)がどのくらいの割合で存在するかを顕微鏡で確認します。骨髄中の形質細胞が10%以上を占める場合に、多発性骨髄腫と診断されます。
画像検査による骨病変の確認
骨の状態を評価するために、画像検査を行います。全身の骨のレントゲン撮影(骨X線撮影)が基本ですが、より詳細な骨病変を描出するためにCTやMRI、PET-CTなどの検査を行うこともあります。
- レントゲン撮影
- CT検査
- MRI検査
- PET-CT検査
がん細胞の増殖パターン – 骨髄内での進行過程
多発性骨髄腫と診断された後、治療方針を決定し、今後の見通し(予後)を予測するために、病気がどのくらい進行しているのかを評価する「病期分類(ステージング)」を行います。
病期(ステージ)分類
現在、国際的に広く用いられているのが「国際ステージングシステム(ISS)」と、それに染色体異常などの情報を加えた「改訂国際ステージングシステム(R-ISS)」です。
これらは血液検査の結果に基づいて、病期を3段階に分類します。
国際ステージングシステム(ISS)
血液中の「アルブミン」と「β2ミクログロブリン」という2つのタンパク質の測定値に基づいて、ステージⅠ、Ⅱ、Ⅲの3段階に分類します。
β2ミクログロブリンの値が高いほど、体内の骨髄腫細胞の量が多いことを示し、病期が進んでいると判断します。
改訂国際ステージングシステム(R-ISS)
ISSの分類に、骨髄腫細胞が持つ「染色体異常」の種類と、血液中の「LDH」という酵素の値を加えて、より正確に予後を予測する分類法です。
予後良好、中間、不良の3つのリスクグループに分けます。
| 分類 | 評価項目 | 目的 |
|---|---|---|
| ISS | アルブミン、β2ミクログロブリン | 腫瘍量の推定 |
| R-ISS | ISSの項目 + 染色体異常 + LDH値 | より精密な予後予測 |
病気の進行と予後
病期分類は、あくまで統計的なデータに基づいた予測であり、個々の患者さんの経過を完全に決定づけるものではありません。近年、新しい治療薬が次々と登場し、治療成績は著しく向上しています。
予後を考える上では、病期だけでなく、年齢や全身の状態、治療への反応性なども含めて総合的に判断することが重要です。
生存率の考え方
生存率は、同じ病気と診断された多くの人々のデータを集計したもので、治療の進歩とともに年々改善しています。これはあくまで目安であり、個人の余命を示すものではありません。
担当医とよく話し合い、自分に合った治療を続けることが大切です。
治療戦略の選択 – 薬物療法から造血幹細胞移植まで
多発性骨髄腫の治療は、病気の進行を抑え、症状を和らげ、生活の質(QOL)を維持することを目的とします。
治療法は、年齢や全身の状態、病期、そして患者さん自身の希望などを考慮して総合的に決定します。
治療開始の判断基準
M蛋白が認められても、CRAB基準などの臓器障害がない場合は「無症候性骨髄腫」とされ、すぐには治療を開始せず、定期的な検査で経過を観察します。
症状が出現したり、特定のバイオマーカーが悪化したりした時点で治療を開始するのが一般的です。
初期治療(寛解導入療法)
診断後、最初に行う治療を「寛解導入療法」と呼びます。この段階では、複数の薬を組み合わせた薬物療法(化学療法)によって、まず体内の骨髄腫細胞をできるだけ減らすことを目指します。
移植適応がある場合の治療
年齢が比較的若く(一般的に65歳~70歳以下)、主要な臓器の機能が保たれている場合は、「自家移植(自家末梢血幹細胞移植)」という強力な治療の対象となります。
この場合、移植を前提とした薬の組み合わせで寛解導入療法を行います。
移植適応がない場合の治療
高齢であったり、他の合併症があったりして自家移植が難しい場合は、移植を行わない前提で、体の負担が比較的少ない薬の組み合わせによる治療を継続します。
地固め療法と維持療法
寛解導入療法の後、治療効果をさらに高めるために「地固め療法」を行うことがあります。自家移植もこの地固め療法の一つと位置づけられます。
その後、得られた寛解状態をできるだけ長く維持するために、比較的副作用の少ない薬を少量で長期間使用する「維持療法」を行います。
自家移植(造血幹細胞移植)の役割
自家移植は、大量の抗がん剤を投与して骨髄中の骨髄腫細胞を徹底的に叩いた後、あらかじめ採取・凍結しておいた自分自身の造血幹細胞を体に戻し、造血機能を回復させる治療法です。
より深い寛解を目指すための強力な地固め療法です。
| 治療段階 | 目的 | 主な治療法 |
|---|---|---|
| 寛解導入療法 | 骨髄腫細胞を減らす | 多剤併用薬物療法 |
| 地固め療法 | 寛解をより深くする | 自家移植、追加の薬物療法 |
| 維持療法 | 寛解を長く維持する | 副作用の少ない薬の長期投与 |
新規薬剤による治療 – 分子標的薬と免疫調節薬の役割
2000年代以降、多発性骨髄腫の治療は、新しい作用を持つ薬剤の登場によって大きく変わりました。
これらの薬は、骨髄腫細胞が持つ特有の性質を標的にするため、従来の抗がん剤よりも効果が高く、副作用の出方も異なります。
治療を変えた新しい薬
分子標的薬と免疫調節薬は、現在の多発性骨髄腫治療の中心となる薬剤です。これらを組み合わせることで、高い治療効果が期待できます。
分子標的薬(プロテアソーム阻害薬など)
骨髄腫細胞が異常なM蛋白を大量に作るために利用する「プロテアソーム」という酵素の働きを阻害する薬です。
これにより、骨髄腫細胞内に不要なタンパク質が蓄積し、細胞死(アポトーシス)に導きます。
免疫調節薬(IMiDs)
骨髄腫細胞の増殖を直接抑制する作用に加え、患者さん自身の免疫細胞(T細胞やNK細胞)を活性化させ、がん細胞への攻撃力を高める作用も持ち合わせています。
その他の薬物療法
上記の薬剤以外にも、様々な作用を持つ薬が治療に用いられます。
抗体薬
骨髄腫細胞の表面にある特定の目印(抗原)に結合し、免疫細胞ががんを攻撃するのを助けたり、がん細胞に直接ダメージを与えたりする薬です。
従来の化学療法
アルキル化剤など、古くから使われている抗がん剤も、新しい薬と組み合わせて用いられることがあります。
また、ステロイドは骨髄腫細胞を減少させる効果があり、ほとんどの治療レジメンで併用されます。
| 薬剤の種類 | 主な作用 | 代表的な薬剤群 |
|---|---|---|
| 分子標的薬 | がん細胞の特定の分子を狙う | プロテアソーム阻害薬 |
| 免疫調節薬 | 免疫を高め、がんを攻撃 | IMiDs |
| 抗体薬 | がん細胞の目印に結合する | 抗CD38抗体など |
予後と長期管理 – 寛解と再発への対応
多発性骨髄腫は、治療によって症状が落ち着く「寛解」と、再び病状が悪化する「再発」を繰り返すことが多い慢性的な疾患です。
そのため、病気と長く付き合っていくという視点での長期的な管理が重要になります。
寛解の定義と状態
寛解とは、治療によって骨髄腫細胞が検知できないレベルまで減少し、症状や検査値の異常が改善された状態を指します。
しかし、画像や検査では見つけられない微量の骨髄腫細胞が体内に残っている可能性があるため、「治癒」とは区別されます。
再発時の治療方針
再発した場合でも、現在では多くの治療選択肢があります。治療方針は、前回の治療内容や効果の持続期間、再発時の患者さんの状態などを考慮して決定します。
初回治療で使った薬の有効性
初回の治療から再発までの期間が長かった場合は、同じ薬でも再び効果が期待できることがあります。期間が短い場合は、異なる作用を持つ別の薬への変更を検討します。
新しい治療選択肢の検討
近年、再発・難治性の多発性骨髄腫に対しても、新しい分子標的薬や抗体薬、さらにはCAR-T細胞療法といった新たな治療法が開発されており、治療の選択肢は広がり続けています。
支持療法の重要性
病気そのものに対する治療と並行して、病気や治療に伴う様々な症状や副作用を和らげる「支持療法」も極めて重要です。これにより、患者さんの生活の質を保ちながら、治療を継続しやすくなります。
骨病変への対策
骨の破壊を抑え、骨の痛みを和らげるために、ビスフォスフォネート製剤やデノスマブといった骨吸収抑制薬を定期的に投与します。
感染症予防
免疫力が低下しているため、感染症の予防が大切です。
手洗いやうがいの励行、人混みを避けるなどの基本的な対策に加え、必要に応じて抗菌薬や抗ウイルス薬の予防内服、ワクチンの接種などを行います。
- 骨吸収抑制薬の投与
- 痛みに対する鎮痛薬の使用
- 感染症の予防と早期治療
- 貧血に対する輸血や造血刺激因子製剤
よくある質問
- 多発性骨髄腫は遺伝しますか?
-
いいえ、多発性骨髄腫が親から子へ直接遺伝することは基本的にありません。
血縁者に発症した方がいるとリスクがわずかに高まる可能性は指摘されていますが、多くの場合は遺伝とは関係なく発症します。
- M蛋白とは具体的に何ですか?
-
M蛋白は、がん化した一つの形質細胞(骨髄腫細胞)から作られる、均一な構造を持つ異常なタンパク質(モノクローナルタンパク質)のことです。
体を守る働きはなく、むしろ腎障害や血液循環の悪化など、様々な問題を引き起こす原因物質です。
- 治療中の日常生活で気をつけることはありますか?
-
免疫力が低下するため、感染症対策が最も重要です。手洗いやうがいを徹底し、生ものを避け、人混みへの外出を控えるなどの工夫が大切です。
また、骨がもろくなっているため、転倒しないように注意し、重いものを持つのは避けてください。詳しくは担当医や看護師に相談しましょう。
- 自家移植は誰でも受けられますか?
-
A自家移植は非常に強力な治療ですが、体への負担も大きいため、誰でも受けられるわけではありません。
一般的には、年齢が65歳~70歳以下で、心臓や肺、腎臓などの主要な臓器に重い合併症がないことが条件となります。最終的には、個々の患者さんの状態を総合的に評価して適応を判断します。
参考文献
CHO, Hee Jeong, et al. Development of a new risk stratification system for patients with newly diagnosed multiple myeloma using R-ISS and 18F-FDG PET/CT. Blood Cancer Journal, 2021, 11.12: 190.
PEKTAŞ, Gökhan, et al. Evaluation of current survival and prognostic factors in multiple myeloma: Staging ISS or R-ISS?. HEALTH SCIENCES QUARTERLY, 2025, 5.1: 65-74.
OZAKI, Shuji, et al. Evaluation of the Revised International Staging System (R-ISS) in Japanese patients with multiple myeloma. Annals of Hematology, 2019, 98.7: 1703-1711.
GALIENI, Piero, et al. The detection of circulating plasma cells may improve the revised international staging system (R‐ISS) risk stratification of patients with newly diagnosed multiple myeloma. British journal of haematology, 2021, 193.3: 542-550.
SCHAVGOULIDZE, Anais, et al. Heterogeneity in long-term outcomes for patients with Revised International Staging System stage II, newly diagnosed multiple myeloma. Haematologica, 2022, 108.5: 1374.
YAVORKOVSKY, Leonid L. The role of staging in multiple myeloma. Expert Review of Hematology, 2023, 16.12: 933-942.
LEE, Koeun, et al. Comprehensive updates in the role of imaging for multiple myeloma management based on recent international guidelines. Korean Journal of Radiology, 2021, 22.9: 1497.
SHANG, Yufeng, et al. Evaluation of prognostic staging systems of multiple myeloma in the era of novel agents. Hematological Oncology, 2022, 40.2: 212-222.
ZHONG, Ling, et al. Revised International Staging System (R-ISS) stage-dependent analysis uncovers oncogenes and potential immunotherapeutic targets in multiple myeloma (MM). Elife, 2022, 11: e75340.
CIFTCILER, Rafiye; CIFTCILER, Ali Erdinc; DAGLI, Mehmet. Assessment of the Prognostic Importance of The Revised International Staging System Based on Plasmacytoma Presentation in Recently Diagnosed Patients with Multiple Myeloma. Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion, 2025, 41.1: 31-37.