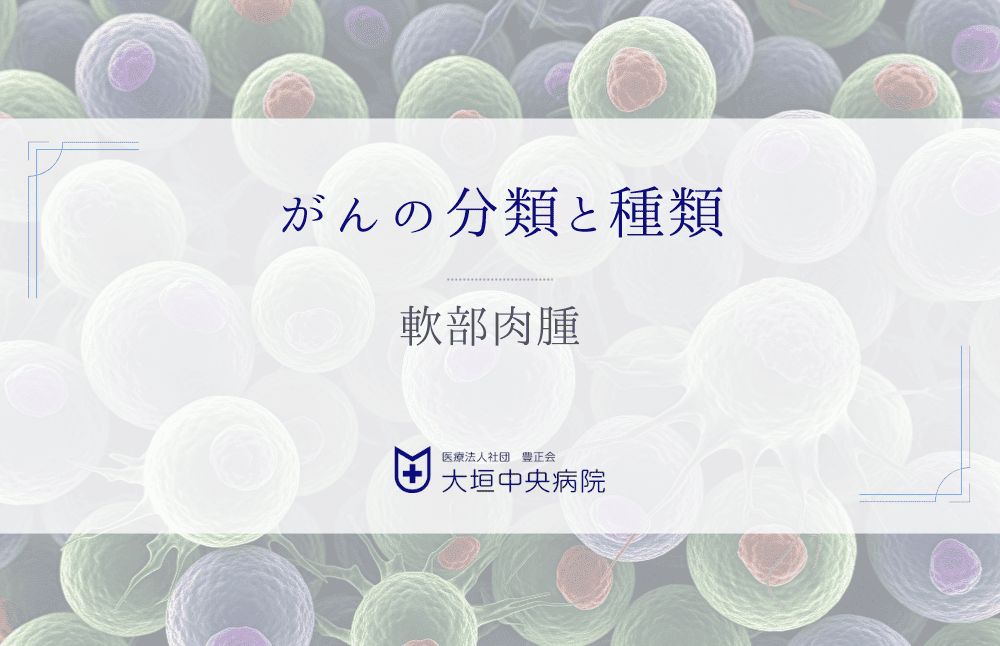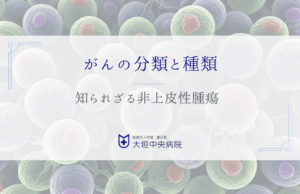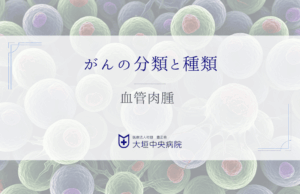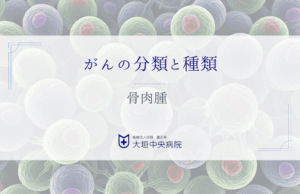体にできた「しこり」に気づき、不安を感じていませんか。軟部肉腫は、筋肉や脂肪、血管といった体の軟部組織から発生する悪性腫瘍(がん)の一種です。
発生頻度が低く「希少がん」に分類されるため情報が少なく、診断や治療について多くの疑問を抱えるかもしれません。
この記事では、軟部肉腫の基本的な知識から、多様な種類、発見が遅れやすい症状、詳しい検査方法、そして手術や抗がん剤、放射線治療を含む治療戦略まで、患者さんが知りたい情報を網羅的に解説します。
軟部肉腫とは – 軟部組織に発生する悪性腫瘍の概要
私たちの体は骨や内臓、皮膚など様々な要素で構成されています。その中で、臓器と骨、皮膚を除いた筋肉、脂肪、線維組織、血管、神経などを「軟部組織」と呼びます。
軟部肉腫は、これらの軟部組織から発生する悪性腫瘍の総称です。全身のあらゆる場所に発生する可能性がありますが、特に太ももなどの四肢にできることが多いのが特徴です。
軟部組織の役割とがんの発生原因
軟部組織は体を支え、動かし、栄養を運ぶなど、生命維持に重要な役割を担っています。この組織の細胞が異常に増殖することで腫瘍ができます。
腫瘍には良性と悪性があり、悪性のものが「軟部肉腫」です。軟部肉腫の明確な発生原因は、多くの場合わかっていません。
しかし、一部では遺伝的な要因が関与するケースや、過去に受けた放射線治療が原因となる可能性を指摘しています。
特定の化学物質への曝露や、リンパ浮腫が長期間続く状態もリスク要因として考えますが、ほとんどの患者さんには当てはまりません。
希少がんとしての位置づけと課題
軟部肉腫は、がん全体から見ると非常に発生頻度が低い「希少がん」です。人口10万人あたり年間数人程度しか発生しないため、多くの医師にとっても馴染みが薄い病気といえます。
この希少性が、診断の遅れや治療経験が豊富な病院を見つけることの難しさにつながっています。そのため、軟部肉腫の疑いがある場合は、肉腫の治療を専門とする医師や病院で診察を受けることが極めて重要です。
信頼できる情報を集め、適切な医療機関にたどり着くことが、治療の第一歩となります。
軟部肉腫の主な特徴
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 発生部位 | 全身の軟部組織(四肢、体幹、後腹膜など) |
| 発生頻度 | 希少がん(全悪性腫瘍の約1%) |
| 主な初期症状 | 痛みを伴わないことが多い「しこり」や腫れ |
50種類以上の多様性 – 軟部肉腫の分類と特徴
「軟部肉腫」と一言でいっても、その性質は一つではありません。顕微鏡で見たときの細胞の顔つき(組織型)によって、50種類以上に細かく分類されます。
この組織型の違いが、腫瘍の振る舞いや治療法の選択、そして将来の見通し(生存率)に大きく影響するため、正確な分類が非常に重要です。
主要な組織型とその特徴
数ある組織型の中でも、発生頻度が高い代表的なものがいくつかあります。例えば、脂肪細胞に似た「脂肪肉腫」、平滑筋に由来する「平滑筋肉腫」、線維組織から発生する「線維肉腫」などです。
それぞれ好発年齢や発生しやすい部位、悪性度などに特徴があります。どの組織型に分類されるかによって、治療方針、特に抗がん剤の効果が大きく変わってきます。
代表的な軟部肉腫の組織型
| 組織型 | 由来する組織 | 主な発生部位 |
|---|---|---|
| 脂肪肉腫 | 脂肪組織 | 四肢、後腹膜 |
| 平滑筋肉腫 | 平滑筋 | 子宮、消化管、後腹膜 |
| 横紋筋肉腫 | 横紋筋 | 小児の頭頸部、泌尿生殖器 |
| 滑膜肉腫 | 不明(関節滑膜ではない) | 四肢の関節周辺 |
| 血管肉腫 | 血管内皮細胞 | 皮膚(特に頭皮)、肝臓 |
組織型が治療方針と生存率に与える影響
組織型の診断は、治療戦略を立てる上での根幹をなします。例えば、横紋筋肉腫は抗がん剤治療が比較的効きやすいタイプですが、多くの軟部肉腫は抗がん剤への反応が限定的です。
また、放射線治療の効果も組織型によって異なります。さらに、5年生存率などの予後も組織型と悪性度によって大きく変動します。
したがって、自分の病気がどの組織型なのかを正確に把握することが、治療法を理解し、予後を見通す上で大切になります。
発見が遅れやすい理由 – 痛みのない腫瘤という特性
軟部肉腫は、初期の段階では自覚症状がほとんどないため、発見が遅れがちになるという大きな課題があります。
多くの患者さんは、体に「しこり」ができていることに気づいて初めて医療機関を訪れますが、その時点である程度大きくなっていることも少なくありません。
初期症状としての「痛みのないしこり」
軟部肉腫の最も代表的な初期症状は、痛みを伴わない「しこり」や「腫れ」(無痛性腫瘤)です。
痛みがないため、「ただの脂肪の塊だろう」「そのうち治るだろう」と自己判断してしまい、受診が遅れる原因となります。
しかし、悪性腫瘍である軟部肉腫は自然に消えることはなく、時間とともに大きくなっていきます。
体に原因不明のしこりを見つけた場合は、痛みがなくても安易に考えず、早めに専門の病院を受診することが重要です。
しこり以外の症状が現れるケース
腫瘍が初期の段階を過ぎて大きくなると、周囲の神経や血管、臓器を圧迫し始め、様々な症状を引き起こします。
- 神経の圧迫による痛みやしびれ
- 血管の圧迫によるむくみ(浮腫)
- 消化管の近くにできれば腹痛や下血
- 肺の近くにできれば咳や呼吸困難
これらの症状が現れたときには、病気が進行している可能性があります。
特に、しこりが急速に大きくなる、5cm以上の大きさになる、体の深い部分(筋肉の中など)にできるといった特徴がある場合は、悪性の可能性を考えて精密な検査が必要です。
軟部肉腫の診断プロセス – 画像検査から病理診断まで
軟部肉腫の診断は、慎重かつ段階的に進めます。問診や触診から始まり、画像検査で腫瘍の大きさや場所、性質を詳しく調べ、最終的に腫瘍の一部を採取する「生検」によって確定診断に至ります。
正しい治療方針を立てるためには、これらの検査を通じて正確な情報を得ることが大切です。
専門医による問診と触診
診断の第一歩は、医師による丁寧な問診です。いつからしこりに気づいたか、大きさや硬さに変化はあるか、痛みなどの他の症状はあるか、過去の病歴などを詳しく伝えます。
その後、医師がしこりに直接触れて、その大きさ、硬さ、可動性(周囲の組織とくっついているか)、熱感などを確認します。
この段階で、良性か悪性かの大まかな見当をつけます。経験豊富な名医は、触診だけで多くの情報を得ることができます。
画像検査の役割と種類
触診の次は、画像検査で腫瘍の内部を詳しく観察します。複数の検査を組み合わせることで、より正確な情報を得ます。
MRI検査の重要性
MRI検査は、軟部肉腫の診断において最も重要な画像検査です。
磁気と電波を使って体の断面を撮影し、腫瘍の正確な大きさ、形状、内部の性状(脂肪、液体、出血など)、そして周囲の血管や神経との位置関係を詳細に描き出します。
手術計画を立てる上で欠かせない情報を提供してくれます。
CT検査とPET検査
CT検査は、X線を使って体の断面を撮影する検査です。特に、軟部肉腫が転移しやすい肺や肝臓の状態を調べるのに有用です。
一方、PET検査は、がん細胞がブドウ糖を多く取り込む性質を利用して、がんの活動性や全身への広がりを評価する検査です。
これらの検査を組み合わせることで、病気の進行度(ステージ)を判断します。
主な画像検査の目的
| 検査名 | 主な目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| MRI検査 | 腫瘍の性状と広がりを評価 | 軟部組織の描出に優れる。手術計画に必須。 |
| CT検査 | 遠隔転移(特に肺)の確認 | 短時間で広範囲を撮影できる。 |
| PET検査 | がんの活動性と全身への広がりを評価 | 良悪性の鑑別や転移巣の発見に役立つ。 |
確定診断のための生検
画像検査だけでは、良性か悪性かの最終的な判断はできません。確定診断のためには、腫瘍の一部を採取して顕微鏡で調べる「生検(せいけん)」が必要です。
生検で得られた組織を病理医が詳しく観察し、がん細胞の有無、組織型、悪性度(グレード)を決定します。この病理診断の結果が、その後の治療方針を決定する最も重要な情報となります。
がんの悪性度と進行 – グレード分類が示す予後の違い
軟部肉腫の治療方針や予後を考える上で、「悪性度(グレード)」と「病期(ステージ)」という2つの指標が非常に重要になります。
これらは、がんの顔つきの悪さや、体の中での広がり具合を示しており、今後の治療計画の土台となります。
予後を予測するグレード分類
グレードとは、生検で採取した組織を顕微鏡で観察したときの、がん細胞の「顔つきの悪さ」を示す指標です。
正常な細胞とどれくらい異なっているか、細胞分裂の頻度はどれくらいか、などを基に評価します。一般的に、グレードは1から3の3段階に分類されます。
悪性度(グレード)の分類
| グレード | 顔つき | 特徴 |
|---|---|---|
| G1(低悪性度) | おとなしい | 増殖が比較的遅く、転移のリスクも低い。 |
| G2(中間悪性度) | 中間 | G1とG3の中間の性質を持つ。 |
| G3(高悪性度) | 悪い | 増殖が速く、転移や再発のリスクが高い。 |
グレードが高いほど、がんの増殖スピードが速く、転移や再発を起こしやすいことを意味します。
このため、グレードは手術後の補助療法(放射線治療や抗がん剤)を行うかどうかを判断する際の重要な材料となります。
病期(ステージ)の決定要因
ステージとは、がんが体の中でどれくらい進行しているかを示す指標です。主に以下の3つの要素を組み合わせて決定します。
- T因子:腫瘍(Tumor)の大きさ
- N因子:所属リンパ節(Nodes)への転移の有無
- M因子:遠隔転移(Metastasis)の有無
これにグレードの情報を加味して、総合的にステージをI期からIV期に分類します。ステージが進むほど、がんは進行している状態です。
特に、肺などの他の臓器に遠隔転移がある場合は、最も進行したステージIVと診断されます。ステージは、治療法の選択や生存率を予測するための目安として用います。
TNM分類とステージの関係(簡略版)
| ステージ | 腫瘍の大きさ・グレード | 転移の状態 |
|---|---|---|
| I期 | 大きさ問わず・低悪性度 | 転移なし |
| II期・III期 | 大きさや深さによる・高悪性度 | 転移なし |
| IV期 | 大きさ・悪性度問わず | 遠隔転移あり |
軟部肉腫の5年相対生存率(目安)
ステージI(低悪性度・転移なし): 90%以上
ステージII(高悪性度・転移なし): 70〜80%前後
ステージIII(高悪性度・深部/大型): 50〜60%前後
ステージIV(遠隔転移あり): 10〜20%未満
※これは軟部肉腫全体の一般的な傾向であり、組織型(脂肪肉腫、平滑筋肉腫など)によって異なります。
治療戦略の決定 – 手術を中心とした集学的治療
軟部肉腫の治療は、がんを完全に取り除くことを目指す「局所治療」と、全身に広がったがん細胞を叩く「全身治療」を組み合わせて行います。
治療の根幹をなすのは手術ですが、がんの悪性度やステージに応じて放射線治療や化学療法を組み合わせる「集学的治療」によって、根治性と機能温存の両立を目指します。
治療の基本となる外科手術
転移がない軟部肉腫において、根治を目指せる唯一の治療法が外科手術です。手術の目的は、腫瘍を完全に取り除くことです。
再発を防ぐため、腫瘍本体だけでなく、その周囲の正常な組織を一定の厚みで含めて切除する「広範切除術」が標準的な方法です。取り残しがあると、そこから再発するリスクが高まります。
手術を補助する放射線治療
放射線治療は、高エネルギーのX線を照射してがん細胞を破壊する治療法です。手術と組み合わせることで、治療効果を高める役割を果たします。
- 術前照射:手術前に照射し、腫瘍を小さくして手術をしやすくする。切除範囲を小さくできる可能性がある。
- 術後照射:手術で取り除いた部分に照射し、目に見えない微小ながん細胞を叩いて局所再発のリスクを減らす。
特に、悪性度が高い腫瘍や、切除断端が陽性(がん細胞が残っている可能性がある)の場合に、術後の放射線治療を積極的に検討します。
集学的治療の考え方
集学的治療とは、手術、放射線治療、化学療法(抗がん剤治療)という異なるアプローチを戦略的に組み合わせる治療法です。
個々の患者さんの病状(組織型、グレード、ステージ)や全身状態、年齢などを総合的に評価し、最も効果的と考えられる治療の組み合わせを選択します。
例えば、「術前化学療法 → 手術 → 術後放射線治療」のように、複数の治療を順序立てて行います。このアプローチにより、治療成績の向上と、患者さんのQOL(生活の質)の維持を目指します。
治療法の組み合わせ例
| 目的 | 治療法の組み合わせ |
|---|---|
| 局所再発の抑制 | 手術 + 放射線治療 |
| 機能温存 | 術前化学療法/放射線治療 + 手術 |
| 全身への効果 | 化学療法 +(手術/放射線治療) |
化学療法が効くがん・効かないがん – 組織型による治療選択
化学療法(抗がん剤治療)は、薬剤を用いて全身のがん細胞を攻撃する治療法です。転移がある場合や、手術が難しい場合、また再発リスクが非常に高い高悪性度のがんに対して行います。
しかし、軟部肉腫は組織型によって抗がん剤の効き目が大きく異なるため、その適応は慎重に判断します。
抗がん剤治療の目的と対象
抗がん剤治療の主な目的は、遠隔転移したがんを制御すること、そして手術後の再発を予防することです。すでに肺などに転移が見つかっているステージIVの患者さんでは、化学療法が治療の中心となります。
また、悪性度が非常に高く、手術だけでは再発のリスクが高いと考えられる場合に、手術の前後に行う補助化学療法を検討することがあります。
組織型による感受性の違い
全ての軟部肉腫に抗がん剤が同じように効くわけではありません。小児に多い横紋筋肉腫やユーイング肉腫などは化学療法の感受性が高く、治療の柱となります。
一方で、成人に多い脂肪肉腫や平滑筋肉腫など、多くの組織型では抗がん剤の効果は限定的です。そのため、組織型を考慮せずに一律に化学療法を行うことはありません。
組織型と化学療法の感受性
| 化学療法の感受性 | 代表的な組織型 |
|---|---|
| 高い | 横紋筋肉腫、ユーイング肉腫、骨外性粘液型軟骨肉腫 |
| 限定的 | 脂肪肉腫、平滑筋肉腫、未分化多形肉腫など多くの成人型肉腫 |
分子標的薬という選択肢
近年、がん細胞の増殖に関わる特定の分子だけを狙って作用する「分子標的薬」が登場し、軟部肉腫の治療選択肢も広がりました。
従来の抗がん剤とは異なり、正常な細胞への影響が少ないのが特徴です。進行性の軟部肉腫に対して、パゾパニブなどの分子標的薬が用いられることがあります。
これらの薬剤が適応となるかどうかは、組織型や遺伝子変異の有無などを基に判断します。
再発リスクと定期検査 – 長期経過観察の重要性
軟部肉腫は、治療によってがんが完全に取り除かれたように見えても、残念ながら再発する可能性があります。
そのため、治療が終わった後も、長期にわたって定期的に検査を受け、経過を観察していくことが非常に重要です。再発を早期に発見し、迅速に治療を開始することが、その後の経過を大きく左右します。
局所再発と遠隔転移
再発には、最初にがんができた場所(またはそのすぐ近く)に再びがんが現れる「局所再発」と、肺や肝臓、骨など、離れた臓器にがんが現れる「遠隔転移」の2種類があります。
再発のリスクは、元のがんの悪性度(グレード)や大きさ、手術で完全に取り切れたかどうかなどに影響されます。
特に高悪性度の腫瘍では、治療後5年以上経過してから再発することもあるため、油断はできません。
治療後のフォローアップの重要性
治療後の定期検査は、再発の兆候をいち早く捉えるための監視活動です。通常、治療後数年間は3〜6ヶ月に1回、その後は1年に1回といった頻度で、問診、触診、画像検査(CTやMRI)などを行います。
定期検査の項目例
| 検査項目 | 主な目的 |
|---|---|
| 問診・触診 | 自覚症状の確認、局所再発のチェック |
| 胸部CT検査 | 最も多い転移先である肺のチェック |
| MRI検査 | 手術部位の局所再発のチェック |
この定期的なフォローアップを通じて、万が一再発が見つかった場合でも、腫瘍が小さいうちに対処できる可能性が高まります。
患者自身の体調管理と情報収集
定期検査とともに、患者さん自身が日々の体調の変化に気を配ることも大切です。
手術した部位の新たな「しこり」や腫れ、原因不明の咳や痛みなど、気になる症状があれば、次の予約を待たずに主治医に相談しましょう。
また、闘病経験を綴ったブログなどを参考に、同じ病気を経験した人の声に触れることも、精神的な支えや情報収集の一助となることがあります。
ただし、医学的な情報については、主治医や信頼できる公的機関からの情報を基本とすることが重要です。
よくある質問
- 軟部肉腫の原因は何ですか?
-
ほとんどの軟部肉腫では、明確な原因はわかっていません。
しかし、一部では遺伝子の異常が関わる特定の遺伝性疾患(神経線維腫症1型など)や、過去に受けた放射線治療、特定の化学物質への曝露などがリスク要因として知られています。
ただ、これらに当てはまる患者さんはごく一部であり、多くの場合は原因不明で発生します。
- 良い病院や名医はどうやって探せばよいですか?
-
軟部肉腫は希少がんであるため、治療経験が豊富な専門施設で診てもらうことが重要です。
まずは、国立がん研究センターの「希少がんセンター」のウェブサイトで情報を探したり、お住まいの地域の「がん診療連携拠点病院」に相談するのが良いでしょう。
これらの病院では、肉腫を専門とする医師(名医)が在籍している可能性が高いです。
また、診断や治療方針に疑問があれば、セカンドオピニオンを積極的に活用し、複数の専門家の意見を聞くことも大切です。
- 治療後の生活で気をつけることはありますか?
-
最も重要なのは、主治医の指示に従って定期検査をきちんと受け続けることです。
それに加えて、バランスの取れた食事や適度な運動を心がけ、心身ともに健康な状態を保つことが、再発予防や体力維持につながります。
手術部位によってはリハビリテーションが必要な場合もあります。また、がんという経験は心にも大きな負担をかけます。
不安や落ち込みが続く場合は、一人で抱え込まず、家族や友人、医療スタッフ、あるいは患者会などに相談することも検討してください。
軟部肉腫には多くの種類がありますが、その中でも血管の内側を覆う「血管内皮細胞」から発生するものを「血管肉腫」と呼びます。
血管肉腫は、高齢者の頭皮や顔にできることが多く、青紫色のあざのような見た目を呈することが特徴です。
進行が速く、転移を起こしやすい悪性度の高いがんであり、早期発見と専門的な治療が求められます。
軟部肉腫の一種である血管肉腫の症状や検査、治療法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の解説記事もあわせてご覧ください。
以上
参考文献
NYSTROM, Lukas M., et al. Multidisciplinary management of soft tissue sarcoma. The Scientific World Journal, 2013, 2013.1: 852462.
CLARKSON, Paul; FERGUSON, Peter C. Primary multidisciplinary management of extremity soft tissue sarcomas. Current Treatment Options in Oncology, 2004, 5.6: 451-462.
NAKAYAMA, Robert, et al. A multidisciplinary approach to soft-tissue sarcoma of the extremities. Expert Review of Anticancer Therapy, 2020, 20.10: 893-900.
ROBINSON, Emma, et al. Multidisciplinary management of soft-tissue sarcoma. Radiographics, 2008, 28.7: 2069-2086.
GÓMEZ, Jorge; TSAGOZIS, Panagiotis. Multidisciplinary treatment of soft tissue sarcomas: an update. World journal of clinical oncology, 2020, 11.4: 180.
AWAD, Nadia, et al. Multidisciplinary approach to treatment of soft tissue sarcomas requiring complex oncologic resections. Annals of vascular surgery, 2018, 53: 212-216.
MONTERO LUIS, Ángel; PÉREZ AGUILAR, Damián; LÓPEZ MARTÍN, José Antonio. Multidisciplinary management of soft tissue sarcomas. Clinical and Translational Oncology, 2010, 12.8: 543-553.
SINHA, Shiba; PEACH, A. Howard S. Diagnosis and management of soft tissue sarcoma. Bmj, 2010, 341.
GRONCHI, Alessandro; OLMI, Patrizia; CASALI, Paolo Giovanni. Combined modalities approach for localized adult extremity soft-tissue sarcoma. Expert Review of Anticancer Therapy, 2007, 7.8: 1135-1144.
CAMPBELL, Shauna R.; WOOLEY, Joseph R.; NYSTROM, Lukas M. Modern multidisciplinary management of soft tissue sarcoma of the extremity and trunk. JCO Oncology Practice, 2024, 20.7: 907-914.
非上皮性腫瘍(肉腫)に戻る