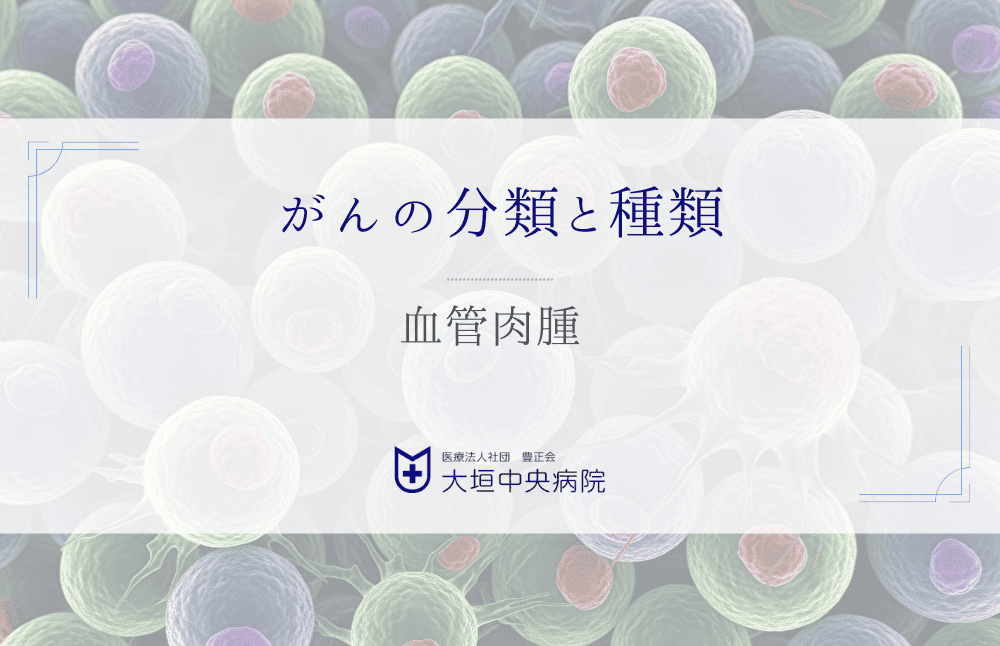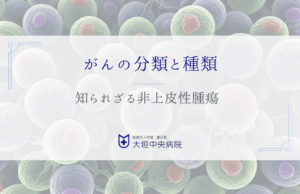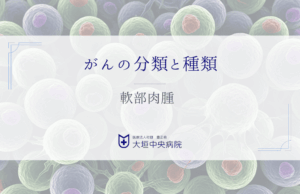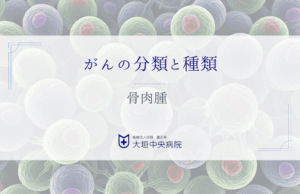血管肉腫は、私たちの体中に張り巡らされた血管の内側を覆う「血管内皮細胞」から発生する、非常にまれで悪性度の高いがんです。
皮膚、特に高齢者の頭部や顔に現れることが多く、初期にはただの「あざ」や「内出血」のように見えるため、発見が遅れがちになるという深刻な課題を抱えています。
このがんは進行が速く、転移や再発のリスクも高いため、病気について正しく理解し、適切なタイミングで専門的な治療を受けることが極めて重要です。
この記事では、血管肉腫の基本的な知識から、特徴的な症状、原因、診断、そして現在の治療法まで、がんと向き合う患者さんやご家族が知っておくべき情報を分かりやすく解説します。
血管肉腫の基本 – 血管を作る細胞ががん化する病気
私たちの体を維持するために不可欠な血液を運ぶ「血管」。この血管の内壁は、血管内皮細胞という薄い細胞の層で覆われています。
血管肉腫は、この血管内皮細胞が異常に増殖し、がん化することで発生する病気です。これは骨や筋肉、脂肪といった軟部組織から発生する「肉腫」というがんの一種に分類されます。
全身のあらゆる場所にできる可能性がありますが、その性質や発生部位には一定の傾向が見られます。
希少がんとしての位置づけ
血管肉腫は、すべてのがんの中でも極めて発生頻度が低い「希少がん」の一つです。肉腫全体の中でも約1%程度しか占めないため、多くの人にとって馴染みのない病名かもしれません。
この希少性が、診断や治療における専門知識の重要性を一層高めています。情報が少ない中で不安を感じるかもしれませんが、専門医のもとで着実に治療を進めることが大切です。
血管由来とリンパ管由来
厳密には、血管肉腫は血液が流れる血管から発生するものと、リンパ液が流れるリンパ管から発生するものに大別されます。
しかし、臨床現場ではこれらをまとめて血管肉腫(または脈管肉腫)として扱うことが一般的です。どちらも内皮細胞が起源であるという共通点があり、似たような性質を示します。
発生母地による分類
| 発生母地 | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
| 血管 | Hemangiosarcoma | 血液を運ぶ血管の内皮細胞ががん化したもの。 |
| リンパ管 | Lymphangiosarcoma | リンパ液を運ぶリンパ管の内皮細胞ががん化したもの。 |
| 総称 | Angiosarcoma | 上記二つを含む、脈管系由来の悪性腫瘍の総称。 |
頭部・顔面に現れる紫斑 – 皮膚血管肉腫の特徴的な症状
血管肉腫が最も多く発生するのは皮膚であり、その中でも特に高齢者の頭部や顔面、頭皮に好発します。
初期の症状は、多くの場合、痛みやかゆみを伴わない皮膚の変化として現れるため、見過ごされやすいという危険な特徴があります。
見逃されやすい初期症状「あざ」や「内出血」
血管肉腫の最も典型的な初期症状は、まるでどこかにぶつけたかのような「あざ(紫斑)」や「内出血」に見える病変です。色は赤紫色、暗赤色、青紫色など様々で、形も不規則な斑点状であることが多いです。
しかし、通常のあざと決定的に違うのは、数週間から数ヶ月経っても自然に消えることがなく、
むしろ徐々に大きくなったり、色が変わったり、数が増えたりする点です。「治らないあざ」は、血管肉腫を疑うべき最も重要なサインと言えます。
症状の進行と変化
病状が進行すると、皮膚にはさらに明確な変化が現れます。これらの症状に気づいた場合は、ためらわずに皮膚科を受診することが重要です。
しこり(結節)の形成
はじめは平坦だった病変が、次第に盛り上がり、硬い「しこり(結節)」を触れるようになります。このしこりは、血豆のように見えることもあり、徐々に大きくなっていきます。
複数のしこりが融合して、大きな塊を形成することもあります。
潰瘍と出血
腫瘍がさらに大きくなると、表面の皮膚が破れて「潰瘍」ができます。この潰瘍部分は非常にもろく、少しの刺激で簡単に出血するようになります。
洗顔や洗髪、あるいは寝ている間に枕にこすれるだけで出血が起こり、なかなか止まらないことも珍しくありません。この出血が、貧血の原因となることもあります。
主な皮膚症状の進行段階
| 進行段階 | 主な症状 | 注意点 |
|---|---|---|
| 初期 | あざ、内出血様の紫斑 | 数週間経っても消えず、むしろ拡大する。 |
| 中期 | しこり(結節)、腫瘤 | 病変が盛り上がり、硬さを伴う。 |
| 進行期 | 潰瘍形成、易出血性 | わずかな刺激で出血し、止血が困難になる。 |
なぜ高齢者に多いのか – 発症リスクと背景因子
血管肉腫の明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの危険因子(リスク因子)が発症に関与していると考えられています。
特に、高齢者の頭部に発生する皮膚血管肉腫には、長年の生活習慣が影響している可能性が指摘されています。
長年の紫外線曝露という原因
最も有力な原因の一つと考えられているのが、長年にわたる紫外線への曝露です。
日光に晒されやすい顔面や頭皮に好発することから、紫外線が皮膚の血管内皮細胞にダメージを与え続け、がん化の引き金になるのではないかと考えられています。
農業や漁業、屋外での建設作業など、長期間屋外で仕事をしてきた方に発症リスクが高い傾向があります。
放射線治療の既往
過去に別のがん(乳がんや子宮頸がんなど)の治療のために放射線治療を受けたことがある場合、その照射範囲内の皮膚や軟部組織から数年~数十年後に血管肉腫が発生することがあります。
これは「放射線誘発性血管肉腫」と呼ばれ、確立されたリスク因子の一つです。
慢性的なリンパ浮腫
乳がんの手術で脇の下のリンパ節を切除した後などに、腕が慢性的にむくむ「リンパ浮腫」という状態が続くことがあります。
このリンパ浮腫が長期間続くと、その部位の皮膚から血管肉腫が発生することがあり、「スチュワート・トリーブス症候群」という名前で知られています。
これは、リンパの流れが滞ることが、局所的な免疫機能の低下などを引き起こし、がんの発生につながると考えられています。
血管肉腫の主なリスク因子
| リスク因子 | 関連する状況 |
|---|---|
| 紫外線曝露 | 高齢者の顔面・頭皮、屋外労働者 |
| 放射線治療歴 | 他のがん治療での照射部位 |
| 慢性リンパ浮腫 | 乳がん術後などの腕のむくみ |
極めて予後不良ながん – 血管肉腫の進行速度と転移
血管肉腫は、数あるがんの中でも特に悪性度が高く、予後が厳しい(予後不良)がんとして知られています。
その主な理由は、がん細胞の増殖スピードが非常に速いことと、早期から体の他の部位へ転移しやすい性質を持っているためです。
高い再発率と転移のリスク
血管肉腫は、治療によって目に見えるがんがなくなった後も、高い確率で「再発」や「転移」を起こします。
特に、血液の流れに乗ってがん細胞が全身に運ばれる「血行性転移」を早期から起こしやすいのが特徴です。
最も多い転移先は「肺」
血管肉腫が最も転移しやすい臓器は「肺」です。肺に転移すると、咳や息切れ、血痰などの症状が出ることがありますが、初期には無症状のことも少なくありません。
肺転移が進行すると、肺に穴が開いてしぼんでしまう「気胸」という危険な合併症を引き起こすこともあり、突然の呼吸困難に見舞われる可能性があります。
そのため、診断時には必ずCT検査で肺の状態を詳しく調べます。
その他の転移部位
- 肝臓
- 骨
- リンパ節
生存率と予後を左右する因子
血管肉腫の5年生存率は、報告によって幅がありますが、一般的に低い傾向にあります。しかし、これはあくまで過去のデータを含む統計上の数値であり、個々の患者さんの未来を決定づけるものではありません。
近年の治療法の進歩により、生存率は少しずつ改善しています。予後(病気の見通し)に影響を与える主な因子は、診断された時点での腫瘍の大きさや、遠隔転移の有無です。
皮膚血管肉腫の5年相対生存率(目安)
- ステージI(腫瘍が5cm以下):約30〜50%
- ステージII以上(5cm超または転移あり):10〜20%未満
※血管肉腫は進行が速く、早期発見が非常に難しい難治がんの一つですが、早期の手術と放射線治療の組み合わせで長期生存されている方もいらっしゃいます。
予後に影響する主な臨床的因子
| 因子 | 予後が良い傾向 | 予後が厳しい傾向 |
|---|---|---|
| 腫瘍の大きさ | 5cm以下 | 5cmを超える |
| 発生部位 | 四肢、体幹 | 頭頸部、内臓 |
| 遠隔転移 | なし | あり(特に肺転移) |
診断の難しさと重要性 – 生検から確定診断までの過程
血管肉腫の診断を確定させるためには、専門的な検査が欠かせません。初期症状が他の皮膚疾患と似ているため、見た目だけで判断することは非常に困難です。
正確な診断こそが、適切な治療への第一歩となります。
確定診断のための皮膚生検
血管肉腫が疑われる場合、診断を確定するために必ず「皮膚生検」を行います。これは、局所麻酔をした上で、疑わしい病変部の一部をメスで切り取り、その組織を顕微鏡で詳しく調べる病理検査です。
病理医が、組織の中にがん細胞が存在するかどうか、またそれが血管内皮細胞由来のがんであるかを判断します。
病期(ステージ)を決定する画像検査
生検によって血管肉腫の診断が確定したら、次はがんが体のどのくらいまで広がっているか(病期)を調べるための全身検査を行います。
血管肉腫は進行が速く、早期から転移を起こしやすいため、このステージング検査は治療方針を決める上で極めて重要です。
全身への広がりを調べる主な検査
- CT検査
- MRI検査
- PET-CT検査
これらの画像検査によって、原発巣の深さや広がり、リンパ節への転移、そして肺や肝臓などの遠隔臓器への転移の有無を詳細に評価し、総合的に病期を決定します。
限られた治療選択肢 – 手術・放射線・薬物療法の現状
血管肉腫の治療は、一つの方法だけで完結することは難しく、手術、放射線治療、薬物療法(抗がん剤など)を組み合わせた「集学的治療」が基本となります。
どの治療法をどのように組み合わせるかは、がんの発生部位、大きさ、病期、そして患者さん自身の全身状態などを総合的に考慮して、専門医が慎重に判断します。
根治を目指すための手術(外科的切除)
がんが特定の場所にとどまっており、遠隔転移がない場合、治療の基本は手術による腫瘍の切除です。根治(がんを完全に治すこと)を目指す上で最も重要な治療法と位置づけられています。
しかし、血管肉腫は正常な組織との境界が不明瞭なことが多く、目に見える腫瘍の周囲にもがん細胞が染み込むように広がっている(浸潤している)傾向があります。
そのため、再発を防ぐ目的で、腫瘍の周りの正常な皮膚や組織を、安全域(マージン)として含めて広範囲に切除する必要があります。
再発予防と症状緩和のための放射線治療
放射線治療は、手術後の局所再発のリスクを減らす目的(術後補助療法)や、手術が困難な場合に症状を和らげる目的で行います。高エネルギーのX線などを照射して、がん細胞を破壊する治療法です。
特に頭部のような広範囲で複雑な形状の部位には、病変の形に合わせて精密に放射線を照射できる特殊な装置が用いられることもあります。
放射線治療の主な役割
| 治療の目的 | 主な内容 |
|---|---|
| 術後補助療法 | 手術で取り切れなかった可能性のある微小ながん細胞を叩き、局所再発を防ぐ。 |
| 根治的照射 | 手術が困難な場合に、根治を目指して放射線治療を主体に行う。 |
| 緩和的照射 | 転移による痛みや出血などの症状を和らげる。 |
全身に広がるがん細胞と闘う薬物療法
手術や放射線治療が局所的な治療であるのに対し、薬物療法は血液の流れに乗って全身に行き渡り、体のあちこちに散らばったがん細胞を攻撃する全身治療です。
すでに転移がある場合や、手術ができない場合、あるいは手術後の再発予防のために行われます。
中心となる抗がん剤「パクリタキセル」
現在、血管肉腫の治療で中心的な役割を担っているのが「パクリタキセル」というタキサン系の抗がん剤です。
この薬は血管肉腫に対して比較的高い効果を示すことが分かっており、標準治療薬として広く用いられています。
その他の治療薬
パクリタキセルの効果が不十分な場合や、副作用で使えない場合には、他の抗がん剤や、がん細胞の増殖に関わる特定の分子を狙い撃ちする「分子標的薬」が使用されることがあります。
また、近年では、人間が本来持つ免疫の力でがんと闘う「免疫チェックポイント阻害薬」を用いた治療も研究が進められています。
主な薬物療法の選択肢
| 薬剤の種類 | 代表的な薬剤名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 抗がん剤 | パクリタキセル、エリブリン | 細胞分裂を阻害してがん細胞を攻撃する。 |
| 分子標的薬 | パゾパニブ | がんの増殖や血管新生に関わる分子を標的とする。 |
| 免疫療法 | ペムブロリズマブなど | 免疫ががんを攻撃する力を高める。 |
早期発見でも困難な闘い – がん細胞の浸潤性という課題
血管肉腫との闘いが困難である大きな理由の一つに、がん細胞の「浸潤性」という性質があります。
これは、がん細胞が木の根のように、周囲の正常な組織の隙間に染み込むように広がっていく性質のことです。
このため、見た目や画像検査で確認できる腫瘍の塊よりも、実際のがんの広がりは大きいことが珍しくありません。
手術における完全切除の難しさ
手術では、この目に見えないがん細胞の広がりを想定して、腫瘍から十分な距離をとって広範囲に切除します。
しかし、それでも微小ながん細胞を取り残してしまう可能性が常にあり、これが手術後の局所再発の大きな原因となります。
特に顔面や頭皮では、機能や容貌を保つために切除できる範囲に限界があり、完全な切除がさらに難しくなります。
治療抵抗性と再発
血管肉腫のがん細胞は、抗がん剤や放射線治療に対して抵抗性を示しやすいという性質も持っています。治療によって一時的に縮小しても、生き残ったがん細胞が再び増殖を始め、再発につながることがあります。
この治療抵抗性が、予後を厳しくする一因となっています。
血管肉腫の治療における課題
| 課題 | 内容 | 治療への影響 |
|---|---|---|
| 高い浸潤性 | がん細胞が周囲に染み込むように広がる。 | 手術での完全切除が難しく、局所再発の原因となる。 |
| 治療抵抗性 | 薬物療法や放射線治療が効きにくい性質を持つ。 | 治療効果が限定的になり、再発しやすい。 |
肝臓・心臓の血管肉腫 – 臓器別の特徴と対応
血管肉腫は皮膚に発生することが最も多いですが、まれに肝臓や心臓、乳房といった内臓の血管から発生することもあります。
これらの臓器に発生した場合、症状の現れ方や治療法が皮膚の場合とは異なるため、注意が必要です。
肝血管肉腫
肝臓に発生する血管肉腫は、初期にはほとんど症状がありません。進行すると、腹部の膨満感や痛み、体重減少、黄疸などが見られます。最も危険なのは、腫瘍が破裂して腹腔内に大量出血を起こすことです。
これは命に関わる緊急事態であり、突然の腹痛やショック症状で発症することがあります。
治療は、可能であれば手術による肝切除を行いますが、発見された時点で多発していることが多く、薬物療法が中心となるケースが少なくありません。
心血管肉腫
心臓に発生する血管肉腫は、原発性心臓悪性腫瘍の中で最も頻度が高いものです。
発生する部位によって症状は異なりますが、心臓のポンプ機能が妨げられることによる息切れやむくみ(心不全症状)、不整脈、あるいは腫瘍の一部が剥がれて血管を詰まらせる塞栓症などを引き起こします。
診断も治療も極めて難しく、予後は非常に厳しいのが現状です。
内臓発生の血管肉腫の特徴
| 発生臓器 | 主な初期症状 | 注意すべき合併症 |
|---|---|---|
| 肝臓 | 無症状、腹部膨満感 | 腫瘍破裂による腹腔内出血 |
| 心臓 | 息切れ、むくみ、不整脈 | 心不全、塞栓症 |
| 乳房 | 痛みを伴わないしこり | 皮膚への浸潤、潰瘍形成 |
よくある質問
血管肉腫と診断された患者さんやご家族からよく寄せられる質問にお答えします。
- 血管肉腫は遺伝しますか?
-
ほとんどの血管肉腫は遺伝とは無関係に発生する「孤発性」のものです。
ただし、ごくまれに特定の遺伝性疾患(神経線維腫症1型など)に伴って発生することが報告されていますが、一般的なケースではありません。
家族に血管肉腫の患者さんがいるからといって、必ずしも遺伝を心配する必要はありません。
- 治療中の生活で気をつけることは何ですか?
-
治療中は、体力の消耗や免疫力の低下が起こりやすくなります。十分な栄養と休息を心がけることが基本です。皮膚に病変がある場合は、刺激を避けて清潔に保つことが大切です。
特に放射線治療中は皮膚がデリケートになるため、保湿ケアや紫外線対策が重要になります。
抗がん剤治療中は、副作用の出方に応じて、感染予防(手洗いやうがい)や食事の工夫など、担当の医師や看護師の指導に従ってください。
- 診断されたら、どの診療科にかかればよいですか?
-
皮膚に症状がある場合は、まずは皮膚科を受診するのが一般的です。
皮膚生検で診断が確定した後は、肉腫の治療を専門とする腫瘍内科、形成外科、放射線治療科などが連携して治療にあたる「集学的治療チーム」のある、がん専門病院や大学病院で治療を受けることが望ましいです。
希少がんであるため、治療経験が豊富な施設を選ぶことが重要です。
がんは、皮膚や消化管などの表面を覆う「上皮細胞」から発生するものが大半を占めますが、それ以外の細胞から発生する「非上皮性腫瘍(肉腫)」も存在します。
これらは発生頻度が低く、診断や治療に専門的な知識を要します。血管肉腫もその一つですが、他にも神経、脂肪、筋肉など、体の様々な支持組織から発生する多様ながんがあります。
これらのまれながんについて理解を深めることは、ご自身の病気や治療法を多角的に捉える助けとなるかもしれません。
以下の記事で、知られざる非上皮性腫瘍の世界を詳しく解説しています。
以上
参考文献
LETSA, Ioanna, et al. Angiosarcoma of the face and scalp: effective systemic treatment in the older patient. Journal of Geriatric Oncology, 2014, 5.3: 276-280.
NIWA, Masanari, et al. Clinical outcomes of radiation therapy for angiosarcoma of the scalp and face: a multi-institutional observational study. Cancers, 2023, 15.14: 3696.
OGAWA, K., et al. Treatment and prognosis of angiosarcoma of the scalp and face: a retrospective analysis of 48 patients. The British journal of radiology, 2012, 85.1019: e1127-e1133.
FUJISAWA, Y., et al. Chemoradiotherapy with taxane is superior to conventional surgery and radiotherapy in the management of cutaneous angiosarcoma: a multicentre, retrospective study. British Journal of Dermatology, 2014, 171.6: 1493-1500.
FUJIMURA, Taku, et al. Cutaneous angiosarcoma treated with taxane-based chemoradiotherapy: a multicenter study of 90 Japanese cases. Skin Health and Disease, 2023, 3.1: ski2. 180.
BI, Siwei, et al. Management of cutaneous angiosarcoma: an update review. Current Treatment Options in Oncology, 2022, 23.2: 137-154.
PATEL, Samir H., et al. Angiosarcoma of the scalp and face: the Mayo Clinic experience. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 2015, 141.4: 335-340.
YAMAKAWA, Kohei, et al. A review of cutaneous angiosarcoma: epidemiology, diagnosis, prognosis, and treatment options. Japanese Journal of Clinical Oncology, 2025, hyaf071.
CRISTESCU, Adriana Nicoleta, et al. Personalized Treatment for Scalp Angiosarcoma. Journal of Clinical Medicine, 2025, 14.4: 1278.
FUJISAWA, Yasuhiro, et al. Comparison between taxane-based chemotherapy with conventional surgery-based therapy for cutaneous angiosarcoma: a single-center experience. Journal of dermatological treatment, 2014, 25.5: 419-423.
非上皮性腫瘍(肉腫)に戻る