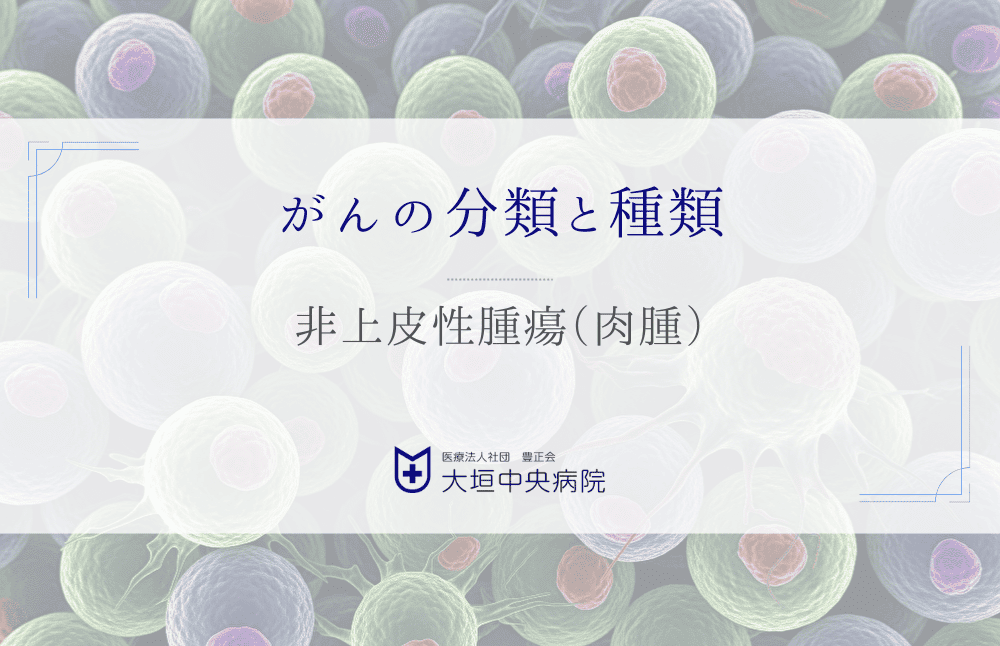非上皮性腫瘍、一般に「肉腫(サルコーマ)」と呼ばれるこのがんは、体の支持組織である骨、軟骨、筋肉、脂肪、血管などから発生します。
胃や肺などの臓器の表面を覆う「上皮細胞」から発生する一般的な「癌(がん)」とは異なり、発生頻度が低く「希少がん」に分類されます。
その種類は50以上に及び、発生部位や性質も多岐にわたるため、診断や治療には高度な専門知識が求められます。この記事では、代表的な肉腫の種類やその特徴、診断アプローチについて詳しく解説します。
骨肉腫 - 骨にできる悪性腫瘍
骨に発生する悪性腫瘍の中で最も代表的なものが骨肉腫です。特に、体の成長が著しい思春期から若年成人期にかけて発症することが多いのが特徴で、骨が活発に作られる過程と関連があると考えられています。
早期に発見し、適切な治療を開始することが、良好な治療成績を得るために極めて重要です。
骨肉腫とは何か
骨肉腫は、骨を形成する細胞ががん化することによって発生する悪性腫瘍です。
骨そのものから発生する「原発性骨悪性腫瘍」の代表格であり、体のどの骨にも発生する可能性がありますが、特に膝関節周辺の大腿骨(太ももの骨)や脛骨(すねの骨)、肩関節に近い上腕骨(腕の骨)が好発部位として知られています。
発生しやすい部位
骨の成長が盛んな「骨幹端」と呼ばれる部位、つまり骨の両端に近い部分によく発生します。これは、細胞分裂が活発な領域であることが関係していると推測されています。
中でも膝関節は、人体で最も大きな関節であり、骨の成長も活発なため、骨肉腫の発生が最も多い場所です。
このため、若年者が膝の痛みや腫れを訴える場合、成長痛やスポーツによる怪我と安易に判断せず、注意深い観察が必要です。
好発年齢
発症のピークは10代で、全骨肉腫患者のおよそ6割を占めます。次いで、高齢者にも小さなピークが見られますが、これは他の病気(ページェット病など)に続発する形で発生することがあります。
若年層に多いという事実は、本人だけでなく家族にとっても大きな衝撃となり、心身両面でのサポートが大切になります。
主な症状
骨肉腫の初期症状は、他の良性の疾患や外傷による症状と見分けがつきにくいことがあります。しかし、がんの進行とともに症状は特徴的なものになっていきます。
症状が続く場合は、整形外科、特に骨軟部腫瘍を専門とする医師の診察を受けることが望まれます。
持続する痛みや腫れ
最も一般的な症状は、発生部位の痛みや腫れです。初期の痛みは運動後に感じる程度で、安静にすると和らぐこともありますが、進行するにつれて安静時や夜間にも痛みが続くようになります。
市販の鎮痛薬が効きにくくなることも特徴の一つです。腫れは、初期には分かりにくいものの、徐々に硬い「こぶ」として触れることができるようになります。
病的骨折
腫瘍によって骨の強度が低下すると、通常では骨折を起こさないような軽い衝撃、例えば立ち上がったり、くしゃみをしたりといった日常的な動作で骨折することがあります。
これを「病的骨折」と呼びます。強い痛みを伴い、突然歩けなくなるなどの症状で気づかれることも少なくありません。
診断への道のり
症状から骨肉腫が疑われる場合、正確な診断を下すために複数の検査を段階的に行います。診断を確定し、病気の広がり(病期)を正確に把握することが、適切な治療方針を立てる上での基礎となります。
骨肉腫の診断で用いる主な画像検査
| 検査方法 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| X線(レントゲン)検査 | 骨の変化を最初に確認 | 骨の破壊や、腫瘍が骨の外に作る骨(骨形成)の様子を観察する。 |
| CT検査 | 骨の詳細な構造と肺転移の確認 | X線よりも詳細に骨の破壊状態を把握できる。肺への転移の有無を調べる上で必須の検査。 |
| MRI検査 | 腫瘍の広がりを評価 | 腫瘍の正確な大きさ、骨の中での広がり、周囲の筋肉や血管、神経との位置関係を詳細に描出する。 |
生検による確定診断
画像検査で骨肉腫が強く疑われた場合、最終的な診断を確定するために「生検」を行います。生検とは、腫瘍の一部を採取し、顕微鏡で詳しく調べる病理診断のことです。
これにより、腫瘍が良性か悪性か、悪性であればどのような種類のがん細胞からできているのかを確定します。治療方針を左右する極めて重要な検査であり、経験豊富な専門医が慎重に行います。

軟部肉腫 - 筋肉・脂肪・血管などに発生する希少がん
軟部肉腫は、筋肉、脂肪、線維組織、血管、神経といった骨以外の「軟部組織」から発生する悪性腫瘍の総称です。体のあらゆる場所に発生する可能性があり、その種類は非常に多岐にわたります。
初期には症状が乏しいことが多く、発見されたときにはある程度進行しているケースも少なくありません。
軟部肉腫の多様性
一口に軟部肉腫といっても、その発生起源となる細胞によって多くの「組織型」に分類されます。
組織型によって、腫瘍の性質、進行の速さ、転移のしやすさ、治療法への反応性が異なるため、正確な組織型の診断が治療の第一歩となります。
代表的な種類
軟部肉腫には50以上の組織型が存在しますが、代表的なものとして脂肪細胞から発生する「脂肪肉腫」、筋肉(平滑筋)から発生する「平滑筋肉腫」、由来がはっきりしない「未分化多形肉腫」などがあります。
それぞれ好発年齢や発生部位に一定の傾向が見られます。
発生部位の広がり
約半数は腕や脚(四肢)に発生しますが、お腹の中(後腹膜)や胸壁、頭頸部など、体の深部に発生することもあります。
体の表面に近い場所にできれば「しこり」として気づきやすい一方、体の深部に発生した場合は、腫瘍がかなり大きくなるまで症状が出ないため、発見が遅れる原因となります。
注意すべき初期症状
軟部肉腫の最も一般的な初期症状は「しこり」や「腫れ」です。しかし、多くの場合、痛みを伴わないため、放置されてしまう傾向があります。以下の特徴を持つしこりには注意が必要です。
痛みのない「しこり」
軟部肉腫の多くは、初期段階では痛みを伴いません。そのため、ただの脂肪のかたまり(脂肪腫)など、良性のものだと思い込んでしまうことがあります。
しかし、痛みの有無は良性・悪性の判断基準にはなりません。痛みがなくても、体に新たなしこりを見つけた場合は、一度専門医に相談することが大切です。
しこりの増大
良性の腫瘍は大きさがほとんど変わらないことが多いのに対し、悪性である軟部肉腫は時間とともに徐々に大きくなる傾向があります。
数週間から数ヶ月の単位で明らかにサイズが大きくなるしこりや、直径が5cmを超えるような大きなしこりは、悪性の可能性を考慮する必要があります。
診断における重要な検査
軟部肉腫の診断も、骨肉腫と同様に画像検査と生検が中心となります。特に、周囲の組織との関係を詳細に把握できるMRI検査が重要な役割を果たします。
代表的な軟部肉腫の種類と特徴
| 組織型 | 主な発生部位 | 特徴 |
|---|---|---|
| 脂肪肉腫 | 大腿部、後腹膜 | 最も頻度の高い軟部肉腫の一つ。悪性度には幅がある。 |
| 平滑筋肉腫 | 子宮、後腹膜、消化管 | 平滑筋のある場所ならどこにでも発生しうる。女性に多い。 |
| 未分化多形肉腫 | 四肢(特に大腿部) | 高齢者の四肢の深い部分に発生することが多い。悪性度が高い。 |
画像診断による評価
しこりの場所や大きさを確認するために、超音波(エコー)検査やCT検査、MRI検査を行います。
中でもMRI検査は、腫瘍と周囲の筋肉、血管、神経との位置関係を鮮明に描き出すことができるため、手術計画を立てる上で不可欠な情報を提供します。
造影剤を使用することで、腫瘍の性質についてもある程度の推測が可能です。
組織型を特定する生検
最終的な診断は、生検による病理診断で決まります。軟部肉腫は種類が非常に多いため、診断には肉腫の病理診断に精通した専門医の存在が極めて重要です。
場合によっては、遺伝子検査などを追加して、より正確な組織型の特定を目指します。
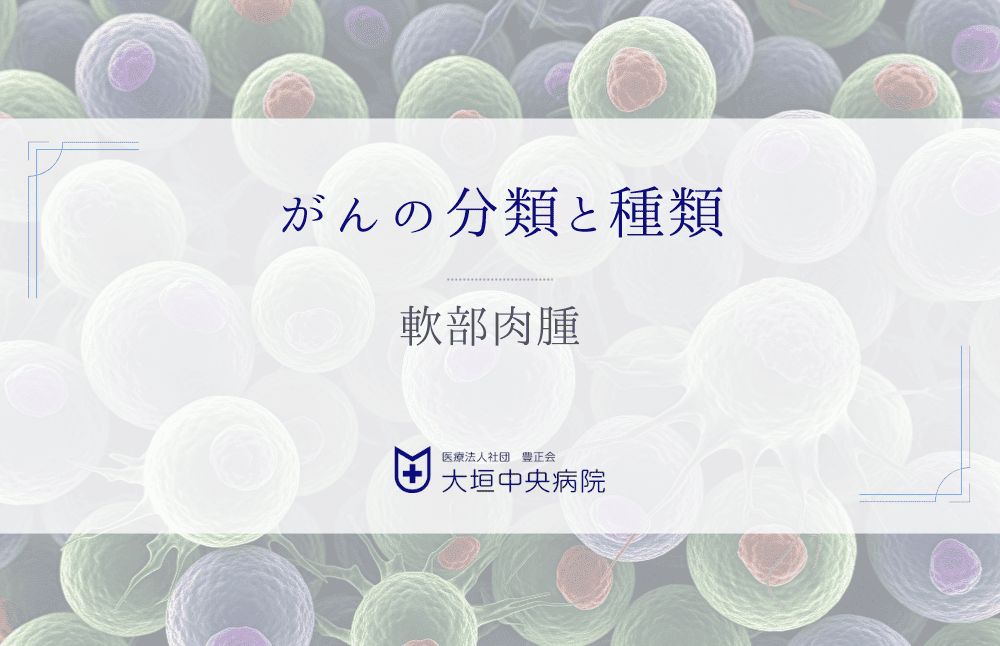
血管肉腫 - 血管内皮細胞から発生する悪性腫瘍
血管肉腫は、血管やリンパ管の内側を覆っている「内皮細胞」から発生する悪性度の高い肉腫です。皮膚に発生することが多いですが、肝臓や心臓、乳房など、全身のあらゆる臓器に発生する可能性があります。
進行が非常に速く、転移しやすいため、迅速な診断と治療が求められます。
血管肉腫の特徴
血管肉腫は、発生部位によって症状や見た目が大きく異なります。特に高齢者の頭皮や顔面に発生することが多いのが特徴です。
皮膚に現れる症状
皮膚に発生した場合、初期には赤紫色や青紫色のあざ、あるいは暗赤色の血豆のような見た目を呈します。少し盛り上がった斑点や結節(しこり)として現れることもあります。
病変部は出血しやすく、かさぶたを伴ったり、潰瘍になったりすることも珍しくありません。一見すると、ただの打ち身や皮膚炎に見えるため、診断が遅れる一因となっています。
内臓に発生する場合
肝臓や脾臓、心臓などの内臓に発生した場合は、特有の初期症状に乏しく、発見はさらに困難になります。
腫瘍が大きくなることによる腹痛や胸痛、あるいは腫瘍が破裂することによる体内での出血(腹腔内出血や心タンポナーデなど)で初めて見つかることもあります。
これらの状況は、命に関わる緊急事態となる可能性があります。
診断の難しさ
血管肉腫は発生頻度が低い上に、その見た目が他の一般的な皮膚疾患と似ているため、診断は容易ではありません。専門医による慎重な診察と評価が必要です。
血管肉腫の発生部位と主な症状
| 発生部位 | 主な初期症状 | 進行時の特徴 |
|---|---|---|
| 皮膚(特に頭頸部) | あざ、しみ、血豆様の皮疹 | 出血、潰瘍形成、周囲への拡大 |
| 乳房 | 皮膚の変色、しこり | 放射線治療後に発生することがある |
| 肝臓・脾臓 | 無症状、腹痛 | 腫瘍の破裂による腹腔内出血 |
他の皮膚疾患との鑑別
特に皮膚に発生した血管肉腫は、血管腫(良性の血管のできもの)、紫斑(内出血)、接触皮膚炎、ケロイドなど、多くの良性疾患との見分けが難しい場合があります。
症状が長引く、範囲が拡大する、出血を繰り返すなどの場合は、血管肉腫の可能性を疑い、皮膚科や形成外科の専門医を受診することが重要です。
ダーモスコピーという特殊な拡大鏡を用いた診察が、診断の助けになることもあります。
確定診断のための生検
疑わしい病変が見つかった場合、診断を確定するためには皮膚の一部を採取する「皮膚生検」が必須です。採取した組織を病理医が顕微鏡で観察し、血管肉腫に特徴的な所見が認められれば診断が確定します。
病変が広範囲に及ぶ場合は、複数の場所から生検を行うこともあります。
治療方針の決定
血管肉腫の治療は、発生した場所、病気の広がり、患者さんの全身状態などを総合的に考慮して決定します。複数の治療法を組み合わせる「集学的治療」が基本となります。
外科的切除の重要性
治療の基本は、可能であれば腫瘍を外科的に完全に切除することです。
血管肉腫は、目に見える範囲よりも広く浸潤していることが多いため、腫瘍の周囲の正常な組織を含めて、十分な安全域をとって切除する必要があります。
しかし、顔面や頭部など、広範囲の切除が難しい場所に発生することも多く、その場合は他の治療法との組み合わせを検討します。
化学療法と放射線治療の役割
手術が困難な場合や、すでに転移が見られる場合には、化学療法(抗がん剤治療)が治療の中心となります。
また、手術後の再発を予防する目的や、手術ができない場合の症状緩和を目的として、放射線治療を行うこともあります。これらの治療法は、病状に応じて単独または組み合わせて用いられます。
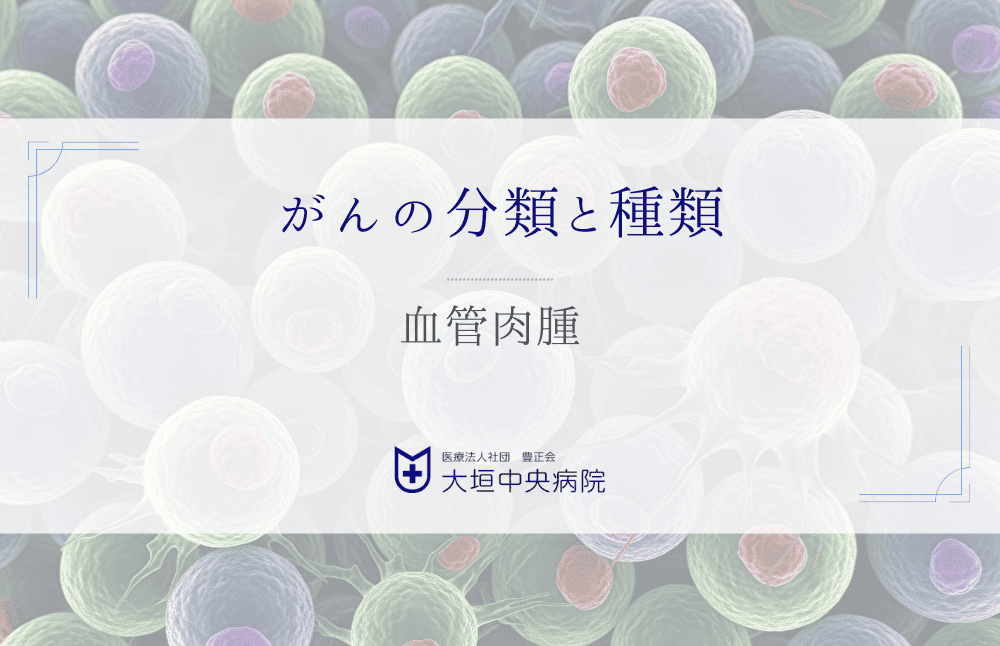
知られざる非上皮性腫瘍 - 神経・脂肪・筋肉由来の多様ながん
これまで述べてきた骨肉腫や代表的な軟部肉腫以外にも、非上皮性腫瘍には多種多様なものが存在します。発生頻度はさらに低くなりますが、それぞれが特有の性質を持っています。
ここでは、その中でも比較的知られている消化管間質腫瘍(GIST)や、その他の希少な肉腫について触れます。
消化管間質腫瘍(GIST)
GIST(ジスト)は、食道、胃、小腸、大腸といった消化管の壁に発生する肉腫の一種です。
消化管の動きを調節する神経叢に存在する特殊な細胞(カハールの介在細胞)が異常に増殖して発生すると考えられています。粘膜から発生する一般的な胃がんや大腸がんとは異なる性質を持ちます。
消化管の壁に発生
GISTは消化管の筋肉の層から発生するため、内側(粘膜側)または外側(漿膜側)に向かって発育します。内視鏡検査では、粘膜の下に盛り上がった「粘膜下腫瘍」として観察されます。
初期は無症状のことが多いですが、腫瘍が大きくなると腹痛、腹部膨満感、出血による貧血や下血などの症状が現れます。
分子標的薬の効果
GISTの多くは、「KIT(キット)遺伝子」や「PDGFRA(血小板由来増殖因子受容体α)遺伝子」という特定の遺伝子に変異があることが分かっています。
この変異遺伝子が作る異常なたんぱく質が、がん細胞の増殖のスイッチを入れ続けています。このスイッチを狙い撃ちする「分子標的薬」が開発され、GISTの治療は大きく進歩しました。
手術が困難な場合や再発した場合でも、高い治療効果が期待できます。
悪性末梢神経鞘腫瘍(MPNST)
MPNSTは、末梢神経を鞘(さや)のように包んでいる「シュワン細胞」などから発生する悪性の軟部肉腫です。腕や脚の太い神経に沿って発生することが多いですが、体幹や頭頸部にも発生します。
その他の希少な肉腫
肉腫には、ここで挙げた以外にも数多くの種類があります。それぞれが独自の臨床的特徴や病理学的所見を示します。
- ユーイング肉腫
- 横紋筋肉腫
- 明細胞肉腫
- 胞巣状軟部肉腫
神経線維腫症1型との関連
MPNSTの患者さんのおよそ半数は、「神経線維腫症1型(NF1)」または「レックリングハウゼン病」と呼ばれる遺伝性疾患を持つことが知られています。
NF1の患者さんは、体に多数のカフェオレ斑(茶色いあざ)や神経線維腫(良性の神経の腫瘍)ができるのが特徴ですが、その神経線維腫ががん化してMPNSTになるリスクが一般の人よりも高いのです。
そのため、NF1の患者さんで、急に大きくなるしこりや痛みを伴うしこりが現れた場合は、MPNSTの可能性を念頭に置いた検査が必要です。
希少な非上皮性腫瘍の例
| 腫瘍名 | 主な発生部位 | 関連情報 |
|---|---|---|
| 消化管間質腫瘍(GIST) | 胃、小腸 | KIT遺伝子変異と分子標的薬が特徴。 |
| 悪性末梢神経鞘腫瘍(MPNST) | 四肢、体幹の末梢神経 | 神経線維腫症1型(NF1)との関連が深い。 |
| 横紋筋肉腫 | 頭頸部、泌尿生殖器、四肢 | 小児に発生する軟部肉腫で最も多い。 |
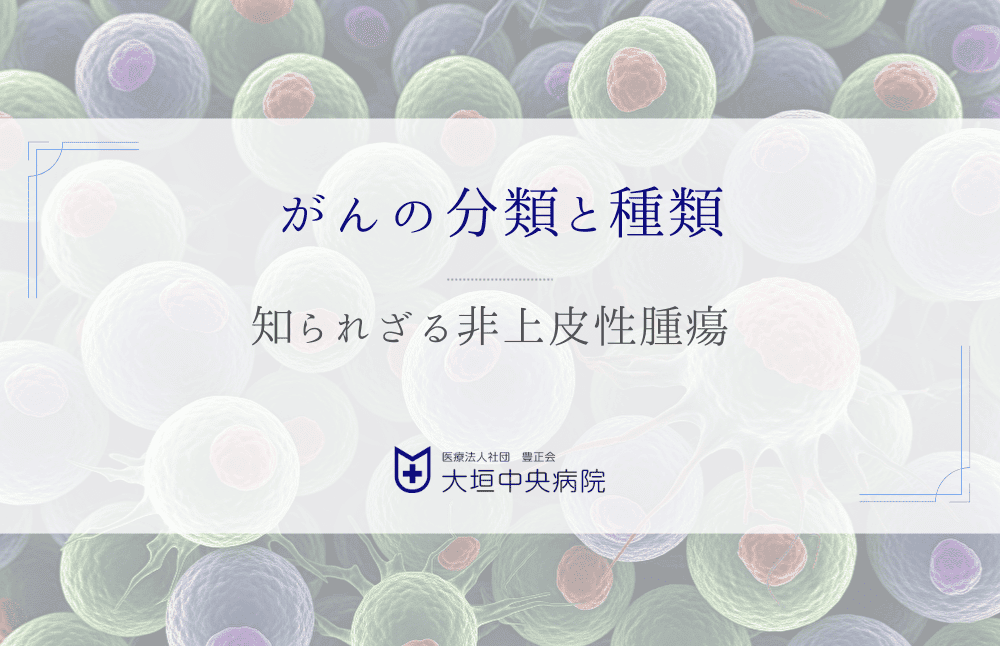
よくある質問
非上皮性腫瘍(肉腫)と診断された患者さんやご家族から、よく寄せられる質問についてお答えします。病気への理解を深め、不安を少しでも和らげる一助となれば幸いです。
- 肉腫は遺伝しますか?
-
ほとんどの肉腫は、遺伝とは無関係に偶然発生する「孤発性」のものです。しかし、一部の肉腫では、発症しやすくなる遺伝的な背景(遺伝性疾患)が存在することが知られています。
例えば、前述の悪性末梢神経鞘腫瘍(MPNST)と神経線維腫症1型(NF1)の関係や、骨肉腫と網膜芽細胞腫(眼のがん)の原因遺伝子との関連などが挙げられます。
ご自身の病気やご家族の病歴について心配な点があれば、主治医や遺伝カウンセリングの専門家に相談することをお勧めします。
- 治療後の生活で気をつけることは?
-
肉腫の治療後は、再発や転移がないかを確認するための定期的な検査が長期にわたって必要です。検査の間隔は、肉腫の種類や病期、治療後の経過時間によって異なります。
また、手術で骨や筋肉を広範囲に切除した場合や、放射線治療を受けた場合は、体の機能に影響が残ることがあります。
筋力や関節の動きを回復させるためのリハビリテーションは、生活の質を維持、向上させるために非常に重要です。日常生活での無理のない活動を心がけ、体調の変化に注意を払いましょう。
- 診断が難しいのはなぜですか?
-
肉腫の診断が難しい理由はいくつかあります。第一に、発生頻度が非常に低い「希少がん」であるため、多くの医師が日常診療で経験する機会が少ないことが挙げられます。
第二に、軟部肉腫だけでも50種類以上の組織型があり、それぞれを正確に鑑別するには、肉腫の病理診断に精通した専門医の眼が不可欠だからです。
良性の腫瘍や他の疾患との見分けがつきにくいことも、診断を難しくする要因です。
これらの理由から、肉腫が疑われる場合は、多くの診療科が連携し、豊富な経験を持つ施設で診断・治療を受けることが望ましいと言えます。
治療法選択における考慮点
考慮する要素 具体的内容 解説 病理組織型と悪性度 脂肪肉腫、平滑筋肉腫など 腫瘍の性質を決定づける最も重要な情報。治療法への反応性も異なる。 病期(ステージ) 腫瘍の大きさ、深さ、転移の有無 病気の進行度を示し、治療の強度や目的(根治、延命など)を決定する。 患者さんの状態 年齢、持病、全身状態(PS) 治療の負担に耐えられるかを評価し、安全に治療を行うために重要。
この記事では、骨や筋肉といった体の構造を支える組織から発生する「肉腫」について解説しました。
一方で、がんには血液細胞やリンパ球など、血液を作り出す組織や免疫を担う組織から発生する「造血器腫瘍」という大きな分類があります。
これには白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などが含まれます。多くの場合、肉腫のように固形の「かたまり」を作らず、血液やリンパの流れに乗って全身に広がりやすいという特徴があります。
異なる種類のがんの成り立ちを知ることは、がんという病気全体への理解を深める上で役立ちます。造血器腫瘍に関する詳しい情報は、以下の記事で解説しています。
以上
参考文献
KUMAR, Dhruv. Pathology of bone and soft tissue sarcomas. In: Sarcoma: A Multidisciplinary Approach to Treatment. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 23-41.
SZENDRŐI, Miklós, et al. Diagnosis and treatment of soft tissue sarcomas. In: European instructional lectures. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. p. 37-50.
SCHWARZKOPF, Eugenia; BOLAND, Patrick. Mesenchymal and Non‐Epithelial tumors of the pelvis. Surgical Management of Advanced Pelvic Cancer, 2021, 283-297.
BANSAL, Abhinav, et al. WHO classification of soft tissue tumours 2020: an update and simplified approach for radiologists. European journal of radiology, 2021, 143: 109937.
WANG, Xuezhe, et al. Advancements in diagnosis and treatment of cardiac sarcomas: a comprehensive review. Current Treatment Options in Oncology, 2025, 26.2: 103-127.
CRAIG, P. J. An overview of uncommon cutaneous malignancies, including skin appendageal (adnexal) tumours and sarcomas. Clinical Oncology, 2019, 31.11: 769-778.
TROPÉ, Claes G.; ABELER, Vera M.; KRISTENSEN, Gunnar B. Diagnosis and treatment of sarcoma of the uterus. A review. Acta oncologica, 2012, 51.6: 694-705.
MAVROGENIS, Andreas F., et al. State-of-the-art approach for bone sarcomas. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 2015, 25.1: 5-15.
MIETTINEN, Markku. Primary soft tissue tumors with epithelial differentiation. Modern Soft Tissue Pathology: Tumors and Non‐Neoplastic Conditions, 2017, 744-776.
MATSUMOTO, Seiichi. Changes in the diagnosis and treatment of soft tissue sarcoma in Japan, 1977–2016. Journal of Orthopaedic Science, 2018, 23.3: 441-448.