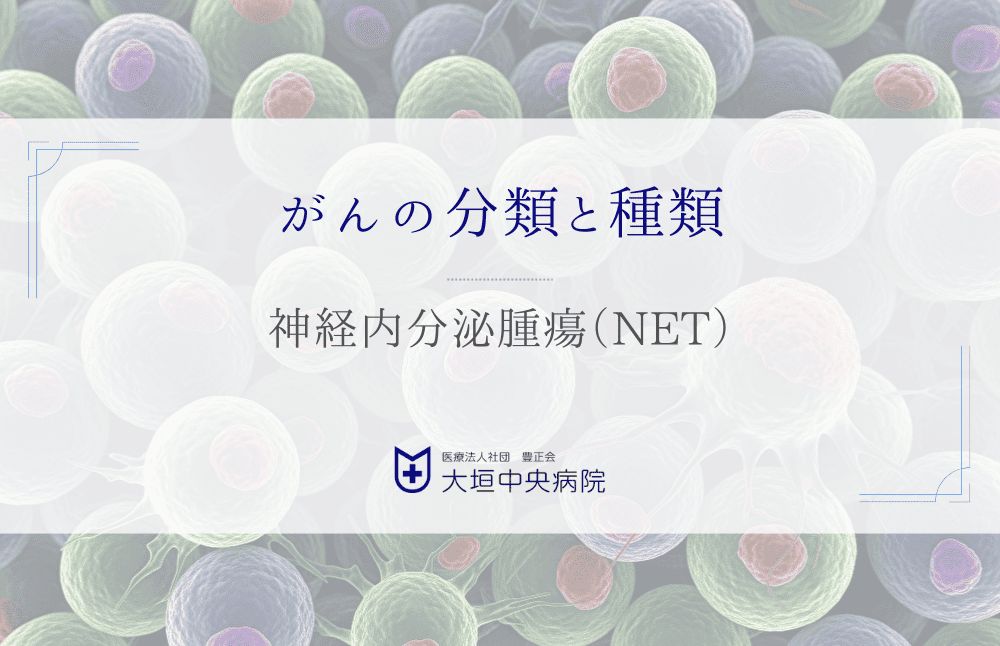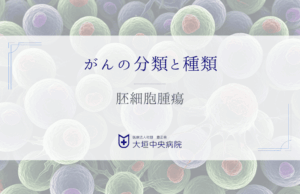神経内分泌腫瘍(NET)は、ホルモンなどを産生する神経内分泌細胞から発生する、比較的まれな腫瘍です。
体のさまざまな場所に発生する可能性があり、ホルモンを過剰に産生することで下痢や動悸といった多様な症状を引き起こすことがあります。
進行が緩やかなものから速いものまで性質はさまざまで、診断や治療には専門的な知識が求められます。この記事では、NETの基本的な知識から症状、診断、そして最新の治療法までを詳しく解説します。
神経内分泌腫瘍(NET)とは – 全身に発生しうる希少がん
神経内分泌腫瘍(Neuroendocrine Neoplasm、略してNEN)は、私たちの体内でホルモンやペプチドを産生し、分泌する役割を持つ「神経内分泌細胞」から発生する腫瘍の総称です。
このうち、悪性度の比較的低いものを神経内分泌腫瘍(Neuroendocrine Tumor、略してNET)と呼びます。全身のあらゆる臓器に発生する可能性がありますが、特に膵臓や消化管によく見られます。
神経内分泌細胞から発生する腫瘍
神経内分泌細胞は、神経系の特徴と内分泌系(ホルモン産生)の特徴を併せ持つ特殊な細胞です。これらの細胞は全身に散らばっており、体の状態を一定に保つために重要な役割を担っています。
この細胞が異常に増殖することでNETが発生します。かつては「カルチノイド」と呼ばれていましたが、現在ではより広い概念であるNETという名称で呼ばれることが一般的です。
希少がんとしてのNET
NETは、がん全体の中では発生頻度が低い「希少がん」の一つに分類されます。しかし、近年の診断技術の向上や疾患への認知度が高まったことにより、診断される患者さんの数は増加傾向にあります。
それでもなお、症状が特異的でないために診断が遅れるケースも少なくありません。
機能性と非機能性の違い
NETは、ホルモンを過剰に産生して特徴的な症状を引き起こす「機能性NET」と、ホルモン産生がほとんどなく症状が現れにくい「非機能性NET」に大別されます。
非機能性NETは、腫瘍が大きくなって周囲の臓器を圧迫したり、転移したりして初めて見つかることが多くあります。
| 分類 | 特徴 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 機能性NET | ホルモンを過剰に産生する | 下痢、皮膚紅潮、低血糖、胃潰瘍など |
| 非機能性NET | ホルモン産生による症状がない | 腹痛、黄疸、腫瘤感(腫瘍増大による) |
NETの主な症状 – ホルモン産生による多様なサイン
NETの症状は、腫瘍が産生するホルモンの種類や発生した場所によって大きく異なります。そのため、他の病気と間違われたり、原因不明の体調不良として見過ごされたりすることがあります。
特徴的な症状を知ることが、早期発見の手がかりになります。
機能性NETが引き起こす特有の症状
機能性NETは、産生するホルモンの種類に応じた多彩な症状を示します。例えば、消化管NETの一部ではセロトニンという物質が過剰に作られ、「カルチノイド症候群」と呼ばれる特徴的な症状群が現れます。
これには、激しい下痢や顔面が赤くなるホットフラッシュ、喘息のような呼吸困難、心臓の弁に異常が起きる心臓弁膜症などが含まれます。
膵NETにおけるホルモン症状
膵臓にできる機能性NETでは、インスリンを過剰に産生して重い低血糖発作を起こす「インスリノーマ」や、胃酸の分泌を促すガストリンを過剰に産生し、難治性の胃・十二指腸潰瘍を多発させる「ガストリノーマ(ゾリンジャー・エリソン症候群)」などがあります。
| 機能性膵NETの種類 | 産生ホルモン | 主な症状 |
|---|---|---|
| インスリノーマ | インスリン | 低血糖症状(冷や汗、動悸、意識障害) |
| ガストリノーマ | ガストリン | 難治性の胃・十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、下痢 |
| グルカゴノーマ | グルカゴン | 移動性壊死性紅斑、糖尿病、体重減少 |
非機能性NETの症状
一方、非機能性NETはホルモンによる症状がないため、発見が遅れがちです。腫瘍が大きくなるにつれて、腹部のしこりや痛み、食欲不振、体重減少、黄疸といった症状が現れます。
また、他の病気の検査や健康診断の際に偶然発見されることも少なくありません。肝臓などへの転移が先に見つかり、詳しく調べる中で元の病巣がNETであったと判明するケースもあります。
発生部位と種類 – 消化管NETと膵NETを中心に
NETは全身のあらゆる場所に発生する可能性がありますが、その約60~70%は消化管(Gastrointestinal tract)と膵臓(Pancreas)に発生します。
これらを総称して「消化管膵神経内分泌腫瘍(GEP-NET)」と呼びます。
消化管NET
消化管NETは、胃、十二指腸、小腸、虫垂、大腸、直腸など、消化管のあらゆる部位に発生します。発生部位によって性質や症状が異なります。
例えば、直腸にできるNETは比較的小さなものが多く、内視鏡検査で偶然発見されることがほとんどです。
一方で、小腸にできるNETはホルモン症状を伴いやすく、発見時にはすでに転移していることもあります。
膵NET(PanNEN)
膵臓に発生するNET(Pancreatic Neuroendocrine Neoplasm, PanNEN)は、機能性と非機能性に分けられます。前述のインスリノーマやガストリノーマは機能性膵NETの代表例です。
膵NETの約60~80%は非機能性であり、症状が出にくいため進行した状態で見つかる傾向があります。
主なGEP-NETの発生部位
| 発生部位 | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| 膵臓 | 機能性、非機能性ともに発生。 | インスリノーマ、ガストリノーマなど。 |
| 小腸 | カルチノイド症候群の原因となりやすい。 | 多発することもある。 |
| 直腸 | 内視鏡で偶然発見されることが多い。 | 多くは進行が緩やか。 |
| 胃 | 自己免疫性胃炎に関連するものもある。 | ガストリン値の上昇が関与。 |
肺やその他の部位に発生するNET
GEP-NET以外では、肺に発生するNETが比較的多く見られます。これは「気管支カルチノイド」とも呼ばれ、咳や血痰、肺炎などの症状で発見されることがあります。
その他、甲状腺、副腎、卵巣、腎臓など、極めてまれですが体の様々な部位に発生する可能性があります。
診断への道のり – 確定診断に至るまでの精密検査
NETの診断は、症状や発生部位が多様であるため、簡単ではありません。問診や診察でNETが疑われた場合、血液検査、画像検査、そして最終的には病理診断を組み合わせて総合的に判断します。
血液検査・尿検査
機能性NETが疑われる場合、血液中や尿中のホルモン値を測定します。これにより、どのホルモンが過剰に産生されているかを調べ、腫瘍の種類を推定します。
また、NETに共通してみられる腫瘍マーカー(クロモグラニンAなど)も診断の補助として用いられます。
画像診断
腫瘍の場所や大きさ、広がり(転移の有無)を調べるために画像検査を行います。
- CT検査・MRI検査
- 超音波内視鏡検査(EUS)
- 内視鏡検査(胃カメラ、大腸カメラ)
これらに加え、NETの診断で特に重要なのが「ソマトスタチン受容体シンチグラフィ(SRS)」です。多くのNET細胞の表面には、「ソマトスタチン受容体」という特殊なたんぱく質が発現しています。
この受容体に結合する放射性物質を注射し、その集まりを画像化することで、非常に小さな腫瘍や転移巣まで見つけ出すことができます。
近年では、より高感度なPET検査の一種である「Ga-68 DOTATOC PET/CT」も行われるようになっています。
病理診断 – 診断確定の鍵
最終的な診断は、腫瘍の一部を採取(生検)し、顕微鏡で詳しく調べる病理診断によって確定します。この検査では、腫瘍が本当にNETであるかを確認するだけでなく、その悪性度(グレード)を評価します。
悪性度の評価には「Ki-67(ケーアイろくじゅうなな)指数」という指標が重要です。
Ki-67指数による悪性度評価
Ki-67指数は、細胞分裂の活発さを示すマーカーで、この値が高いほど腫瘍の増殖スピードが速いことを意味します。この指数に基づいて、NETはG1、G2、G3の3段階に分類されます。
| グレード | Ki-67指数 | 増殖の速さ |
|---|---|---|
| G1 | 3%未満 | 緩やか |
| G2 | 3~20% | 中程度 |
| G3 | 20%超 | 速い |
NETの進行度と予後 – Ki-67指数と生存率の関係
NETの治療方針や今後の見通し(予後)を考える上で、腫瘍の悪性度(グレード)と進行度(ステージ)を正確に把握することが極めて重要です。
これらは、患者さん一人ひとりに合った治療計画を立てるための基礎となります。
WHO分類(G1, G2, G3)
NETの悪性度は、世界保健機関(WHO)が定める分類に従って評価します。
これは前述のKi-67指数と、顕微鏡で見たときの細胞分裂の数に基づいて、G1(低グレード)、G2(中グレード)、G3(高グレード)に分けられます。
G1が最も進行が緩やかで、G3が最も速いタイプです。このグレード分類は、薬物療法の選択など、治療方針を決定する上で非常に重要な情報となります。
進行度(ステージ)分類
ステージ分類は、腫瘍の大きさ、周囲のリンパ節への転移の有無、そして肝臓や骨など他の臓器への遠隔転移の有無によって決まります。
一般的に、腫瘍が原発臓器にとどまっている早期の段階(ステージI、II)と、リンパ節や他の臓器に転移している進行した段階(ステージIII、IV)に分けられます。
ステージが進んでいるほど、全身的な治療が必要になります。
NETの生存率
NETの生存率は、グレード、ステージ、原発臓器、治療法など多くの要因によって変動します。一般的に、G1やG2といった進行の緩やかなNETは、他のがんに比べて長期的な生存が期待できることが多いです。
しかし、発見時にすでに遠隔転移がある場合や、G3のような悪性度の高いタイプでは、予後は厳しくなる傾向があります。
NETの5年生存率の一般的な傾向
以下の表はあくまで一般的な傾向であり、個々の患者さんの状態によって大きく異なることを理解してください。
| 状態 | 5年生存率(目安) | 解説 |
|---|---|---|
| 限局(転移なし) | 約90%以上 | 手術による根治が期待できる。 |
| 領域(リンパ節転移など) | 約60~80% | 集学的な治療が必要となる。 |
| 遠隔転移あり | 約20~60% | グレードや転移部位により幅がある。 |
集学的治療のアプローチ – 手術、薬物療法、PRRTの組み合わせ
NETの治療は、一つの方法だけで完結することは少なく、外科医、内科医、放射線科医などが連携して治療方針を決定する「集学的治療」が基本となります。
腫瘍の性質、進行度、患者さんの全身状態などを総合的に考慮して、最適な治療法を組み合わせていきます。
根治を目指す手術(外科治療)
腫瘍が原発臓器に限局しており、遠隔転移がない場合、治療の第一選択は手術による完全切除です。膵臓や消化管の一部を腫瘍とともに切除することで、根治を目指します。
また、NETは肝臓に転移しやすい性質がありますが、転移巣が肝臓の一部に限られている場合には、原発巣と同時に肝転移巣を切除する手術を行うこともあります。
これにより、長期的な生存や症状の改善が期待できます。
進行・再発NETに対する治療戦略
手術による切除が困難な進行・再発NETに対しては、薬物療法や放射線療法が治療の中心となります。
これらの治療の目的は、腫瘍の増殖を抑え、ホルモン過剰産生による症状を和らげることで、病気と共存しながら生活の質(QOL)を維持・向上させることです。
複数の治療法を適切なタイミングで切り替えたり、組み合わせたりしながら、長期的なコントロールを目指します。
薬物療法の選択肢 – 症状緩和と腫瘍増殖抑制を目指す
進行したNETに対する薬物療法には、いくつかの種類があります。腫瘍のグレード(G1, G2, G3)や原発部位(消化管か膵臓か)、ソマトスタチン受容体の発現状況などに応じて、適切な薬剤を選択します。
ソマトスタチンアナログ製剤
多くのNET細胞に発現しているソマトスタチン受容体に作用する薬です。この薬は、ホルモンの過剰分泌を抑えることで、下痢や皮膚紅潮といったつらい症状を劇的に改善する効果があります。
さらに、腫瘍の増殖を抑制する効果も証明されており、特にG1、G2の進行が緩やかなNETの治療の根幹をなす薬物療法です。
分子標的薬
がん細胞の増殖に関わる特定の分子(たんぱく質や遺伝子)の働きをピンポイントで阻害する薬です。NETの治療では、mTOR(エムトール)阻害薬やマルチキナーゼ阻害薬などが用いられます。
ソマトスタチンアナログ製剤の効果が不十分になった場合や、特定のタイプの膵NETなどで使用します。
細胞障害性抗がん剤(化学療法)
いわゆる「抗がん剤」で、細胞分裂が活発な細胞を攻撃することで効果を発揮します。そのため、増殖スピードの速いG3のNETや、一部の膵NETに対して有効性が高いとされています。
副作用も比較的強く出ることがあるため、適応は慎重に判断します。
PRRT(ペプチド受容体放射性核種療法)
PRRTは、「届ける放射線治療」とも呼ばれる比較的新しい治療法です。ソマトスタチンアナログに微量の放射性物質を結合させた薬剤を点滴で投与します。
すると、薬剤がNET細胞のソマトスタチン受容体に結合し、細胞の内側から放射線を照射して腫瘍を攻撃します。
この治療は、ソマトスタチン受容体が陽性の手術不能または再発のNETに対して高い治療効果を示します。
| 治療法 | 主な対象 | 目的 |
|---|---|---|
| ソマトスタチンアナログ | G1/G2 NET、機能性NET | 症状緩和、腫瘍増殖抑制 |
| 分子標的薬 | 膵NET、進行性NET | 腫瘍増殖抑制 |
| PRRT | ソマトスタチン受容体陽性のNET | 腫瘍縮小、増殖抑制 |
治療後の生活と経過観察 – 長期的な視点での付き合い方
NETは進行が緩やかなタイプが多く、治療後も長く付き合っていくことになる病気です。そのため、定期的な検査による経過観察と、日常生活におけるセルフケアが非常に重要になります。
定期的な検査の重要性
治療後も、再発や転移、あるいは残存している腫瘍の状態を把握するために、定期的に画像検査(CT、MRIなど)や血液検査を行います。
検査の頻度は、腫瘍のグレードや治療内容によって異なりますが、数ヶ月から半年に一度程度行うのが一般的です。
特に、ホルモン症状がある場合は、その変化が病状の悪化を示すサインである可能性もあるため、注意深く観察します。
経過観察の検査項目例
| 検査の種類 | 目的 | 頻度の目安 |
|---|---|---|
| 画像検査(CT/MRI) | 腫瘍の大きさの変化、新たな転移の有無を確認 | 3~12ヶ月ごと |
| 血液検査(腫瘍マーカー) | クロモグラニンAなどの数値の変動を監視 | 3~6ヶ月ごと |
| ホルモン検査 | 機能性NETの活動性を評価 | 症状に応じて |
症状のセルフモニタリング
日々の体調の変化を自分で記録しておくことも大切です。
特に、下痢の回数や程度、腹痛の有無、体重の変化などをメモしておくと、診察の際に医師に正確な情報を伝えることができ、適切な対応につながります。
栄養管理と食事の工夫
NETの患者さん、特に消化管や膵臓に腫瘍がある場合や手術を受けた後は、消化吸収機能が低下したり、下痢を起こしやすくなったりすることがあります。
- 一度にたくさん食べず、少量ずつ何回かに分けて食べる。
- 脂肪の多い食事や刺激の強い香辛料を避ける。
- 下痢がひどい場合は、水分と電解質の補給を心がける。
このような工夫で、症状を緩和できる場合があります。必要に応じて、管理栄養士に相談し、個々の状態に合った食事指導を受けることも有効です。
よくある質問
- NETは遺伝しますか?
-
ほとんどのNETは遺伝とは関係なく発生します(散発性)。しかし、ごく一部に「多発性内分泌腫瘍症1型(MEN1)」などの遺伝性疾患が背景にある場合があります。
血縁者にNETや内分泌系の疾患を持つ方が複数いる場合は、主治医に相談することをお勧めします。
- 生存率はどのくらいですか?
-
NETの生存率は、腫瘍の悪性度(グレード)、発生部位、進行度(ステージ)によって大きく異なります。進行が緩やかなG1やG2のNETで、転移がない場合は長期的な生存が期待できます。
一方で、悪性度の高いG3や遠隔転移がある場合は、より集中的な治療が必要となり、予後も変わってきます。
個別の見通しについては、ご自身の詳しい病状をもとに主治医に確認することが大切です。
- 治療にはどのような副作用がありますか?
-
治療法によって副作用は異なります。手術では、切除する臓器に応じた後遺症(消化吸収障害や糖尿病など)が起こりえます。
薬物療法では、ソマトスタチンアナログ製剤で下痢や腹痛、胆石などが、分子標的薬では口内炎、高血圧、下痢、疲労感などが見られます。
PRRTでは、吐き気や一時的な骨髄抑制(血液細胞の減少)、腎機能への影響などが報告されています。副作用の多くは、支持療法によって軽減することが可能です。
- 膵臓のNETと診断されましたが、手術は必要ですか?
-
膵臓のNETでも、腫瘍が膵臓内にとどまっており、全身状態が良好であれば、手術による切除が第一選択となります。
特に、機能性NETでつらいホルモン症状がある場合や、非機能性でも腫瘍が大きい、あるいは増大傾向にある場合は、積極的に手術を検討します。
ただし、すでに広範な転移がある場合や、手術のリスクが高いと判断される場合は、薬物療法などの他の治療法を選択することもあります。
- PRRTは誰でも受けられますか?
-
PRRTは、ソマトスタチン受容体シンチグラフィやGa-68 DOTATOC PET/CT検査で、腫瘍にソマトスタチン受容体が十分に発現していること(陽性であること)が確認された患者さんが対象となります。
また、腎臓や骨髄の機能が一定の基準を満たしていることも条件です。これらの適応基準を満たすかどうかを専門医が慎重に判断した上で、治療が行われます。
この記事をお読みの方の中には、他の希少がんについて関心をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
アスベスト(石綿)への曝露が原因で発症する「中皮腫」も、診断や治療が難しい希少がんの一つです。
中皮腫は主に胸膜(肺を覆う膜)や腹膜(お腹の内側を覆う膜)に発生する悪性腫瘍で、息切れや胸の痛み、お腹の張りなどの症状が現れます。
以下の記事では、中皮腫の原因から症状、最新の治療法までを詳しく解説しています。
以上
参考文献
KALISZEWSKI, Krzysztof, et al. Advances in the diagnosis and therapeutic management of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms (GEP-NENs). Cancers, 2022, 14.8: 2028.
PISCOPO, Leandra, et al. Diagnosis, management and theragnostic approach of gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms. Cancers, 2023, 15.13: 3483.
DAI, Meng, et al. Recent advances in diagnosis and treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms. World Journal of Gastrointestinal Surgery, 2022, 14.5: 383.
MARCHESE, Ugo, et al. Multimodal management of grade 1 and 2 pancreatic neuroendocrine tumors. Cancers, 2022, 14.2: 433.
CANAKIS, Andrew; LEE, Linda S. Current updates and future directions in diagnosis and management of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms. World journal of gastrointestinal endoscopy, 2022, 14.5: 267.
KOFFAS, Apostolos, et al. Diagnostic work-up and advancement in the diagnosis of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms. Frontiers in surgery, 2023, 10: 1064145.
LEE, Lingaku; RAMOS-ALVAREZ, Irene; JENSEN, Robert T. Predictive factors for resistant disease with Medical/Radiologic/Liver-directed anti-tumor treatments in patients with advanced pancreatic neuroendocrine neoplasms: Recent advances and controversies. Cancers, 2022, 14.5: 1250.
RAYMOND, Lauren M., et al. The state of peptide receptor radionuclide therapy and its sequencing among current therapeutic options for gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors. Neuroendocrinology, 2021, 111.11: 1086-1098.
SEDLACK, Andrew JH, et al. Update in the management of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors. Cancer, 2024, 130.18: 3090-3105.
PAUL, Davinder, et al. Personalized treatment approach to gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors: a medical oncologist’s perspective. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 2016, 28.9: 985-990.
特殊な腫瘍に戻る