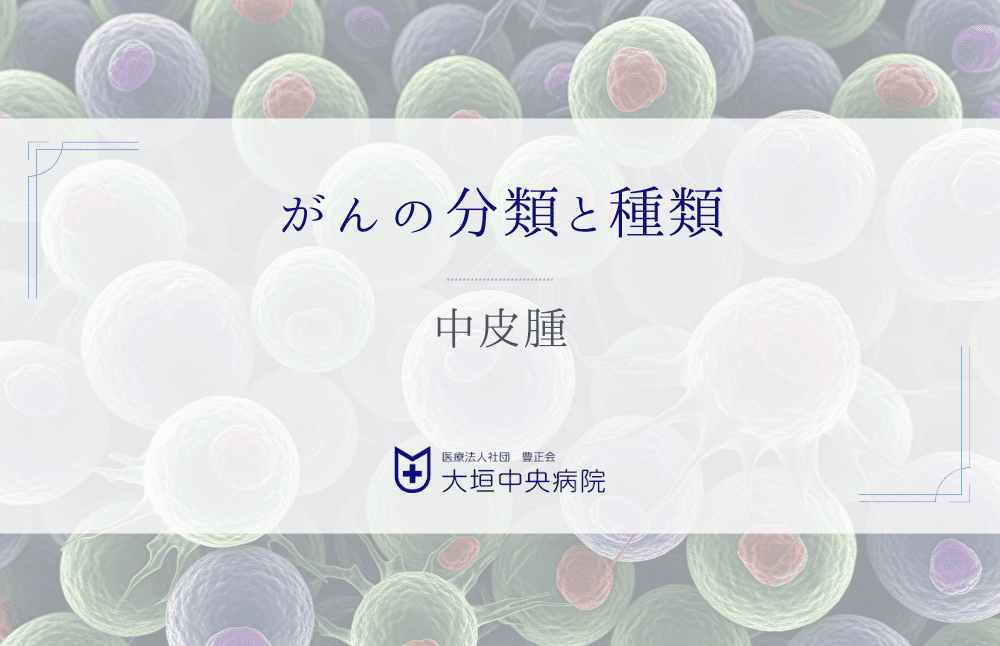中皮腫は、肺を覆う胸膜や腹部の臓器を覆う腹膜などに発生する、まれながんです。その発症には、過去に吸い込んだアスベスト(石綿)が深く関わっていることが分かっています。
アスベスト曝露から数十年という長い潜伏期間を経て発症するため、原因に心当たりがないと感じる方も少なくありません。
この記事では、中皮腫とはどのような病気なのか、その原因、症状、検査や治療法、そして公的な救済制度について、患者さんとご家族が知っておくべき情報を詳しく解説します。
希少がんである中皮腫と向き合い、納得のいく治療を選択するための一助となれば幸いです。
中皮腫とは何か – 胸膜や腹膜に発生する悪性腫瘍
中皮腫は、私たちの体の内側、臓器の表面を覆っている「中皮細胞」から発生する悪性腫瘍です。
体のさまざまな場所に発生する可能性がありますが、そのほとんどは肺を包む「胸膜」か、胃や腸などの腹部の臓器を覆う「腹膜」に生じます。
この病気の性質を正しく理解することが、治療への第一歩となります。
中皮細胞から発生するがん
中皮細胞は、胸腔(肺が収まる空間)や腹腔(腹部の臓器が収まる空間)の内側を覆う薄い膜を形成しています。この膜は、臓器がスムーズに動くための潤滑油のような役割を担っています。
この正常な中皮細胞が、何らかの原因でがん化し、無秩序に増殖を始めたものが中皮腫です。がん細胞は周囲の組織に染み込むように広がる(浸潤)、あるいは他の臓器に転移するという特徴を持ちます。
主な発生部位
中皮腫が発生する部位によって、その名称や症状は異なります。最も多いのは胸膜に発生するもので、次いで腹膜となります。
心臓を覆う心膜や精巣を覆う精巣鞘膜に発生することもありますが、その頻度は非常にまれです。
胸膜中皮腫
全中皮腫の約80~90%を占めるのが胸膜中皮腫です。肺そのものではなく、肺を覆う胸膜に発生します。
がんが進行すると、胸膜が厚くなり、肺の膨らみを妨げたり、胸に水が溜まったり(胸水)することで、さまざまな症状を引き起こします。
腹膜中皮腫
腹膜中皮腫は、中皮腫全体の約10~20%に見られます。
お腹の中の臓器を覆う腹膜にがんが発生し、進行すると腹部に水が溜まったり(腹水)、腸の動きを妨げたりすることがあります。
中皮腫の発生部位と特徴
| 発生部位 | 名称 | 特徴 |
|---|---|---|
| 胸膜(肺を覆う膜) | 悪性胸膜中皮腫 | 最も頻度が高い。胸水貯留、胸の痛み、咳、息切れなどの症状が出やすい。 |
| 腹膜(腹部臓器を覆う膜) | 悪性腹膜中皮腫 | 腹水貯留、腹部の膨満感、腹痛、便秘などの症状が出やすい。 |
| 心膜(心臓を覆う膜) | 悪性心膜中皮腫 | 非常にまれ。心臓の動きを妨げ、動悸や呼吸困難を引き起こすことがある。 |
中皮腫の主な原因
中皮腫を発症する最大の原因は、アスベスト(石綿)の粉じんを吸い込むことであると科学的に証明されています。
アスベストは、かつて建材や断熱材として広く使用されていましたが、その有害性が明らかになり、現在では原則として製造・使用が禁止されています。
しかし、過去に曝露した影響が、数十年後に現れるのがこの病気の恐ろしい点です。
アスベスト曝露と中皮腫発症の深い関係性
中皮腫の診断を受けたとき、多くの方が「なぜ自分が」と感じるかもしれません。その答えの多くは、過去のアスベスト曝露にあります。
自分では意識していなくても、仕事や生活環境の中にアスベストが存在し、知らず知らずのうちに吸い込んでいた可能性があります。
この原因を理解することは、病気と向き合う上で、また、利用できる公的制度を知る上で非常に重要です。
アスベスト(石綿)とは
アスベストは、天然に存在する繊維状の鉱物です。熱や摩擦に強く、安価であったため、「奇跡の鉱物」として、建設資材、電気製品、自動車部品など、非常に多くの工業製品に使用されてきました。
しかし、その繊維は極めて細かく、飛散すると空気中に浮遊し、呼吸によって容易に肺の奥深くまで吸入されてしまいます。
曝露から発症までの長い潜伏期間
アスベストを吸い込んでも、すぐに症状が出るわけではありません。アスベスト繊維は体内で分解されずに長く留まり、数十年かけて中皮細胞をがん化させると考えられています。
この潜伏期間は平均して40年から50年と非常に長く、曝露した時期を特定することが難しい場合もあります。若い頃に従事していた仕事が原因で、高齢になってから発症するケースが典型例です。
職業性曝露と環境曝露
アスベスト曝露には、仕事で直接アスベストを取り扱っていた「職業性曝露」と、その周辺で生活していたことによる「環境曝露」があります。
過去にアスベストを扱う工場や解体現場の近くに住んでいた方、あるいはアスベストを扱う作業員の家族が、作業着に付着した粉じんを吸い込んでしまうといったケースも報告されています。
アスベスト曝露の可能性がある職業例
| 業種 | 具体的な作業内容 |
|---|---|
| 建設・解体業 | 建物の解体、断熱材の吹き付け・除去、配管工事 |
| 造船・車両修理 | 船舶の断熱材施工・修理、自動車のブレーキ・クラッチ修理 |
| 電気・設備工事 | 電気配線の被覆材の取り扱い、ボイラーの保守 |
アスベスト関連疾患と公的救済
中皮腫や肺がんなど、アスベストが原因で健康被害を受けた方々を救済するための公的な制度があります。
仕事が原因である場合は「労働者災害補償保険(労災保険)」、仕事以外が原因の場合や、労災の対象とならない中小事業主などは「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿健康被害救済制度)」の対象となる可能性があります。
これらの制度を利用することで、治療費の給付や療養手当などを受けることができます。
申請手続きには専門的な知識が必要な場合もあるため、病院の相談窓口や専門の弁護士に相談することも一つの方法です。
労災保険と石綿健康被害救済制度の主な違い
| 制度名 | 対象者 | 主な給付内容 |
|---|---|---|
| 労災保険制度 | アスベスト業務に従事していた労働者 | 療養(補償)給付、休業(補償)給付、遺族(補償)給付など |
| 石綿健康被害救済制度 | 労災保険の対象とならない方(家族、周辺住民など) | 医療費、療養手当、弔慰金など |
なぜ中皮腫は「希少がん」と呼ばれるのか
中皮腫は、他のがんと比較して患者さんの数が少ないため「希少がん」に分類されます。希少がんであることは、診断や治療において特有の課題を生むことがあります。
患者さんが少ないからこそ、正しい情報を集め、専門的な医療機関につながることが一層重要になります。
希少がんの定義
一般的に、日本においては「人口10万人あたりの年間発生数が6例未満」のがんを希少がんと定義しています。この定義に基づくと、中皮腫は希少がんに該当します。
患者数が少ないため、一般的ながんほど情報が多くなく、治療経験が豊富な医師や病院も限られてくる傾向があります。
日本における中皮腫の発生状況
日本で中皮腫により亡くなる方は、年間で1500人を超えています。
アスベストの使用がピークであった1970年代から1990年代の曝露が原因となり、発症者数は今後も増加し、2030年頃にピークを迎えると予測されています。
決して他人事ではない病気であり、社会全体で向き合うべき課題です。
希少がんであることの課題
患者数が少ないことは、いくつかの課題につながります。これらの課題を理解し、対策を考えることが大切です。
希少がんが抱える課題
- 診断や治療に関する情報が少ない
- 診療経験が豊富な医師や病院が限られる
- 新しい治療法の開発が進みにくい
- 同じ病気の患者と出会う機会が少ない
診断・治療の情報不足
患者数が少ないため、大規模な臨床試験の実施が難しく、治療法の確立が他のがんに比べて遅れる傾向があります。
そのため、患者さん自身やご家族が、積極的に情報を集め、納得できる治療を選択していく姿勢が求められます。
専門医や病院の少なさ
中皮腫の診断や治療には、高度な専門知識と経験が必要です。しかし、どの病院でも専門的な医療を受けられるわけではありません。
そのため、できるだけ早期に、中皮腫の診療実績が豊富な専門病院を見つけ、相談することが治療成績を向上させる鍵となります。
中皮腫の初期症状と診断の難しさ
中皮腫は、発症の初期段階では特徴的な症状が現れにくく、他の病気と間違われることも少なくありません。そのため診断が遅れがちになるという問題点があります。
どのような症状に注意すべきかを知り、疑わしい場合はためらわずに専門の医療機関で検査を受けることが、早期発見・早期治療につながります。
気づきにくい初期症状
中皮腫の症状は、がんが発生した場所によって異なります。胸膜中皮腫と腹膜中皮腫では、現れる症状が大きく違います。
胸膜中皮腫と腹膜中皮腫の主な初期症状
| 種類 | 主な初期症状 | 解説 |
|---|---|---|
| 胸膜中皮腫 | 息切れ、胸の痛み、咳 | 胸に水が溜まる(胸水)ことで肺が圧迫されたり、がんが胸壁に広がったりすることで生じる。 |
| 腹膜中皮腫 | 腹部の膨満感、腹痛、食欲不振 | お腹に水が溜まる(腹水)ことや、がんが腸を圧迫することなどで生じる。 |
これらの症状は、風邪や加齢によるものと自己判断してしまいがちです。
しかし、特にアスベスト曝露の心当たりがある方で、これらの症状が続く場合は、中皮腫の可能性を念頭に置いた検査が必要です。
診断に至るまでの検査
中皮腫の診断は、複数の検査を組み合わせて慎重に行います。
まずは画像検査でがんの存在や広がりを確認し、最終的には組織の一部を採取して顕微鏡で調べる病理診断で確定します。
画像検査
胸部X線(レントゲン)検査やCT検査、PET検査などを行います。これらの検査で、胸水や腹水の有無、胸膜や腹膜の肥厚、腫瘍(しゅよう)のかたまりなどを確認します。
これにより、がんの存在やおおよその広がりを把握することができます。
病理診断(確定診断)
診断を確定させるためには、がんが疑われる組織の一部を採取(生検)し、顕微鏡で詳しく調べる「病理診断」が不可欠です。
胸膜中皮腫の場合は胸腔鏡(きょうくうきょう)という内視鏡を、腹膜中皮腫の場合は腹腔鏡(ふくくうきょう)を用いて組織を採取するのが一般的です。
この検査によって、中皮腫であることの確定、そしてがんの組織型(上皮型、肉腫型、二相型)を判断します。組織型は、治療方針や余命の予測にも関わる重要な情報です。
専門医への早期相談の重要性
中皮腫の診断は非常に専門性が高く、経験豊富な医師による判断が求められます。
地域の病院で原因不明の胸水や腹水を指摘された場合、あるいはアスベスト曝露歴があって気になる症状がある場合は、呼吸器内科や腫瘍内科、特に中皮腫の専門外来がある病院へ早期に相談することが大切です。
診断が確定すれば、速やかに適切な治療計画を立てることができます。
胸膜中皮腫と腹膜中皮腫の違い
中皮腫は発生部位によって大きく二つに分けられますが、胸膜中皮腫と腹膜中皮腫は、単に場所が違うだけでなく、症状の現れ方や病気の進行、そして治療法の考え方にも違いがあります。
それぞれの特徴を理解しておくことが、ご自身の病状を把握する上で役立ちます。
発生部位による症状の違い
前述の通り、症状は発生部位に大きく依存します。胸膜中皮腫では、肺や心臓といった胸部の臓器が圧迫されることによる呼吸器症状や循環器症状が中心となります。
一方、腹膜中皮腫では、消化管や腹部の臓器が影響を受けることによる消化器症状が主体となります。
進行の仕方の違い
胸膜中皮腫は、胸膜に沿って広がり、徐々に肺を覆い尽くすように進行していくのが特徴です。進行すると、反対側の胸膜や心膜、横隔膜を越えて腹腔内へ広がることがあります。
腹膜中皮腫は、腹膜全体に種をまくように広がる(播種)傾向があります。がんが腹膜の広い範囲に散らばることで、腸閉塞(イレウス)などを引き起こしやすくなります。
治療法選択への影響
治療法も、発生部位によって考え方が異なります。胸膜中皮腫では、手術、抗がん剤治療、放射線治療を組み合わせた集学的治療が標準的です。
特に手術は、広範囲に広がった胸膜を切除する大がかりなものになることがあります。
腹膜中皮腫に対しても集学的治療が行われますが、特に「腹膜切除術」と「周術期腹腔内化学療法」を組み合わせた治療法が、一部の施設で専門的に行われています。
これは、手術で目に見えるがんを切除した後に、温めた抗がん剤をお腹の中に直接流すという治療法です。
胸膜中皮腫と腹膜中皮腫の比較
| 項目 | 胸膜中皮腫 | 腹膜中皮腫 |
|---|---|---|
| 主な症状 | 息切れ、胸痛、咳 | 腹部膨満感、腹痛、便秘 |
| 進行の特徴 | 胸膜に沿って連続的に広がる | 腹膜全体に播種(種まき)状に広がる |
| 主な治療法 | 手術、抗がん剤、放射線治療の組み合わせ | 腹膜切除と腹腔内化学療法など |
中皮腫の病期分類と進行度
がんの治療方針を決定する上で、病気の進行度、すなわち「病期(ステージ)」を正確に把握することが極めて重要です。
病期は、がんがどのくらい広がっているかを示す指標であり、治療法の選択や今後の見通し(余命)を予測するための基礎となります。中皮腫の病期分類は、胸膜と腹膜で異なる基準を用います。
病期(ステージ)とは
病期は、がんの大きさや広がり、リンパ節への転移の有無、他の臓器への遠隔転移の有無によって決定されます。
一般的に、病期が早い(ステージIなど)ほどがんは限られた範囲に留まっており、進行する(ステージIVなど)につれてより広範囲に広がっていることを意味します。
医師はこの病期に基づいて、最も効果が期待できる治療計画を立てます。
胸膜中皮腫のTNM分類
胸膜中皮腫の病期分類には、国際的に広く用いられている「TNM分類」が使われます。
これは、T(原発腫瘍の広がり)、N(所属リンパ節への転移の有無と範囲)、M(遠隔転移の有無)の3つの要素を組み合わせて、ステージIからIVまでの4段階に分類するものです。
胸膜中皮腫の病期(ステージ)の概要
| 病期 | がんの広がりの目安 |
|---|---|
| ステージ I | がんは片側の胸膜に限局している。 |
| ステージ II | がんは片側の胸膜にとどまるが、肺や横隔膜に浸潤している。 |
| ステージ III | がんは胸壁や心膜など、より広範囲に浸潤しているか、胸の中のリンパ節に転移している。 |
| ステージ IV | がんは反対側の胸腔に広がったり、遠くの臓器に転移(遠隔転移)したりしている。 |
この分類は複雑であり、最終的な病期は手術で切除した組織を詳しく調べてから確定することもあります。
腹膜中皮腫のPCI(腹膜がん指数)
腹膜中皮腫には、胸膜中皮腫のような確立されたTNM分類がありません。
その代わりに、腹腔内のがんの広がりを評価する指標として「PCI(Peritoneal Cancer Index:腹膜がん指数)」が用いられることがあります。
これは、腹腔内を13の領域に分け、それぞれの領域のがんの大きさを点数化し、その合計点で進行度を評価する方法です。PCIのスコアが低いほど、がんは限局していると判断されます。
病期診断が治療方針と余命予測に与える影響
病期診断は、治療の目標設定に直結します。早期であれば、がんを完全に取り除くことを目指す「根治的治療(手術など)」の対象となる可能性があります。
一方、進行期であれば、がんの進行を抑え、症状を和らげることで、生活の質(QOL)を維持しながらがんと共存することを目指す治療が中心となります。
また、病期は統計的なデータに基づいた余命の予測にも用いられますが、これはあくまで平均的な目安であり、個々の患者さんの状態や治療の効果によって大きく異なることを理解しておく必要があります。
現在の標準的な治療法と選択肢
中皮腫の治療は、病期、組織型、患者さんの全身状態や年齢、希望などを総合的に考慮して決定します。
単独の治療法で治すことは難しく、多くの場合、手術、薬物療法、放射線治療を組み合わせた「集学的治療」を行います。
どのような治療法があり、それぞれにどのような目的や特徴があるのかを理解し、主治医とよく相談して治療方針を決めることが大切です。
集学的治療の考え方
集学的治療とは、異なる種類の治療法を組み合わせることで、より高い治療効果を目指すアプローチです。
例えば、手術の前に抗がん剤治療を行ってがんを小さくしたり(術前化学療法)、手術後に残っている可能性のある微小ながんを叩くために放射線治療や抗がん剤治療を行ったり(術後補助療法)します。
患者さん一人ひとりの状態に合わせて、最適な治療の組み合わせを考えます。
手術(外科治療)
手術は、がんを物理的に取り除く治療法です。目的によって、根治を目指す手術と、症状を和らげるための手術に分けられます。
根治を目指す手術
がんが比較的限られた範囲にとどまっている場合に検討されます。
胸膜中皮腫では、壁側胸膜、臓側胸膜、肺、心膜、横隔膜を一体として切除する「胸膜肺全摘術」や、肺を温存して胸膜を切除する「胸膜切除/肺剥皮術」などがあります。
これらは非常に体に負担の大きい手術であり、実施できる病院や患者さんの条件が限られます。
症状緩和のための手術
がんによる症状を和らげることを目的とします。
例えば、胸水や腹水が溜まって呼吸困難や腹部膨満感がある場合に、管を入れて水を抜いたり、胸膜や腹膜を癒着させて水が溜まりにくくする処置(胸膜癒着術など)を行ったりします。
薬物療法(抗がん剤・免疫療法)
薬物療法は、薬剤を用いてがん細胞の増殖を抑えたり、破壊したりする治療法です。手術が難しい進行期の中皮腫の治療の中心となります。また、手術の前後に補助的に用いることもあります。
主な薬物療法の種類
- 化学療法(従来の抗がん剤)
- 分子標的治療
- 免疫療法(免疫チェックポイント阻害薬)
抗がん剤治療
細胞分裂が活発ながん細胞を攻撃する薬剤(細胞障害性抗がん剤)を用います。中皮腫では、シスプラチンとペメトレキセドの併用療法が標準的な治療法として長年用いられてきました。
副作用として、吐き気、食欲不振、脱毛、骨髄抑制(白血球や血小板の減少)などが出ることがあります。
免疫チェックポイント阻害薬
近年、中皮腫の治療に大きな変化をもたらしたのが免疫療法です。私たちの体には、がん細胞を異物として攻撃する免疫機能が備わっていますが、がん細胞は免疫にブレーキをかけることで攻撃から逃れようとします。
免疫チェックポイント阻害薬は、このブレーキを解除し、免疫が再びがん細胞を攻撃できるようにする薬です。
ニボルマブとイピリムマブの併用療法などが、一次治療(最初に行う薬物療法)として承認されており、従来の抗がん剤を上回る効果が報告されています。
放射線治療
高エネルギーのX線などをがん細胞に照射してダメージを与える治療法です。胸膜中皮腫では、手術後の補助療法として、あるいは手術ができない場合の症状緩和(痛みなど)を目的として行われることがあります。
広範囲に広がる中皮腫の性質上、がん全体に十分な量の放射線を照射することは難しく、その役割は限定的です。
治療法の選択と相談
どの治療法を選択するかは、患者さんの人生を左右する重要な決断です。主治医から病状や各治療法のメリット・デメリットについて十分な説明を受け、分からないことや不安なことは遠慮なく質問しましょう。
セカンドオピニオンを聞くことも有効な手段です。最終的には、ご自身とご家族が納得できる治療法を、主治医と共に探していくことが重要です。
治療方針の決定に際し、専門的な知識を持つ弁護士に相談し、労災申請などの見通しを立てておくことも、安心して治療に専念するために役立ちます。
他のがんと比較した中皮腫の特徴
中皮腫は、肺がんなど他の胸部のがんとしばしば比較されますが、その性質にはいくつかの特徴的な違いがあります。
これらの違いを理解することは、中皮腫という病気への理解を深め、治療の難しさや特有の課題を把握する上で助けとなります。
浸潤性の広がり方
多くのがんが、まず「かたまり(腫瘤)」を形成し、そこから大きくなっていくのに対し、中皮腫は膜状に薄く、広く染み込むように広がっていく(浸潤性発育)という大きな特徴があります。
このため、CTなどの画像検査でも病変の正確な範囲を捉えることが難しく、手術で完全に取り除くことが困難な一因となっています。
中皮腫と一般的な肺がんとの比較
| 項目 | 中皮腫 | 一般的な肺がん(非小細胞肺がん) |
|---|---|---|
| 発生母地 | 中皮細胞(胸膜、腹膜など) | 気管支や肺胞の上皮細胞 |
| 主な原因 | アスベスト曝露 | 喫煙、大気汚染など |
| 進展様式 | 膜状に薄く広がる(浸潤性) | かたまり(腫瘤)を形成して増大 |
治療抵抗性
中皮腫は、一般的に抗がん剤や放射線治療が効きにくい「治療抵抗性」のがんの一つとされています。
その理由は完全には解明されていませんが、がん細胞自体の性質や、腫瘍内の血流が乏しいことなどが関係していると考えられています。
近年、免疫チェックポイント阻害薬が登場し、治療成績は向上しつつありますが、依然として治療が難しいがんであることに変わりはありません。
診断から治療開始までの時間
初期症状が乏しく、診断が難しいことに加え、希少がんであるため専門病院への紹介に時間がかかることがあります。
また、診断を確定させるための生検や、アスベスト曝露歴の調査、公的制度の申請準備など、治療を開始するまでに多くの手順を踏む必要があります。
この期間、患者さんやご家族は大きな不安を抱えることになります。迅速に診断から治療へとつなげる体制の整備が課題です。
中皮腫患者さんの生活の質を支える医療
中皮腫の治療は、単にがんを攻撃するだけでなく、治療に伴う身体的・精神的な苦痛を和らげ、患者さんがその人らしい生活を送れるように支援することも同じくらい重要です。
これを「緩和ケア」や「支持療法」と呼びます。治療の早い段階から、これらのケアを積極的に取り入れていくことが、生活の質(QOL)を高く保つことにつながります。
緩和ケアの重要性
緩和ケアと聞くと、終末期の医療というイメージを持つ方がいるかもしれませんが、それは誤解です。
緩和ケアは、がんと診断されたときから始まる、痛み、息苦しさ、だるさ、不安といったさまざまなつらさを和らげるためのケアです。
がん治療と並行して行うことで、患者さんがより良い状態で治療に臨めるようになり、結果として治療効果の向上や延命にもつながることが分かっています。
主治医や看護師、専門の緩和ケアチームに、つらい症状や不安な気持ちを遠慮なく相談してください。
栄養サポートとリハビリテーション
がんそのものや治療の副作用によって、食欲が低下したり、体力が落ちたりすることがあります。栄養状態や体力の低下は、治療の継続を困難にし、回復を遅らせる原因となります。
管理栄養士による食事のアドバイスや、理学療法士による無理のない範囲でのリハビリテーションは、治療を乗り切るための体力を維持し、QOLを向上させる上でとても大切です。
経済的・社会的支援の活用
中皮腫の治療は長期にわたることがあり、経済的な負担も大きくなります。利用できる公的な支援制度を積極的に活用することが、安心して治療に専念するために必要です。
利用できる可能性のある公的支援
- 労災保険制度
- 石綿健康被害救済制度
- 高額療養費制度
- 障害年金
- 介護保険
これらの制度は申請手続きが複雑な場合があります。特に労災保険や石綿健康被害救済制度の申請には、アスベスト曝露を証明する資料などが必要となり、専門的な知識が求められます。
このような場合、アスベスト問題に詳しい弁護士に相談することで、手続きをスムーズに進められる可能性があります。
多くの法律事務所が無料相談を実施しているので、一度情報を集めてみることをお勧めします。
信頼できる病院選び
中皮腫のような希少がんの治療では、病院選びが極めて重要です。多くの症例を経験している専門病院では、診断から治療、緩和ケアまで、質の高いチーム医療が提供されます。
また、新しい治療法(治験)に参加できる可能性もあります。現在の主治医に相談の上、セカンドオピニオンを求めるなどして、納得のいく病院を見つけることが大切です。
よくある質問
- アスベストを吸ったら必ず中皮腫になりますか?
-
いいえ、必ずしもそうではありません。アスベストを吸い込んだ人のうち、中皮腫を発症するのはごく一部です。
しかし、アスベスト曝露は中皮腫の最大のリスク要因であることは間違いありません。曝露量が多いほど、また曝露期間が長いほど、発症のリスクは高まるとされています。
ご自身の曝露歴に不安がある場合は、定期的に胸部X線検査などの検診を受けることが推奨されます。
- 中皮腫の余命はどのくらいですか?
-
中皮腫の余命は、病期(ステージ)、組織型(上皮型、肉腫型、二相型)、患者さんの年齢や全身状態、そして行われる治療法によって大きく異なります。
そのため、一概に「何年」と言うことはできません。近年、免疫療法などの新しい治療法の登場により、治療成績は着実に向上しています。
統計的なデータはあくまで目安として捉え、主治医と今後の見通しについてよく話し合うことが重要です。
- 労災や救済制度の申請は難しいですか?弁護士に相談すべきですか?
-
申請手続きは、必要書類の収集や申立書の作成など、煩雑な面があることは事実です。特に、過去の職業歴やアスベスト曝露を証明することが難しい場合があります。
ご自身やご家族だけで進めるのが困難だと感じた場合は、アスベスト関連疾患に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、証拠収集のアドバイスや手続きの代行など、専門的なサポートを提供してくれます。これにより、患者さんやご家族は治療に専念できるという大きなメリットがあります。
- 家族にうつることはありますか?
-
中皮腫は、ウイルスや細菌による感染症ではないため、人から人へうつる(感染する)ことは絶対にありません。
患者さんのご家族や周りの方が、通常の生活を送る上で特別な注意を払う必要はありません。
- 良い病院はどうやって探せばよいですか?
-
信頼できる病院を探すには、いくつかの方法があります。まずは、現在かかっている主治医に相談し、専門施設を紹介してもらうのが一般的です。
また、がん診療連携拠点病院の相談支援センターでは、地域の医療機関に関する情報を提供しています。
患者会や支援団体のウェブサイトで、中皮腫の診療実績が豊富な病院のリストを公開している場合もあります。複数の情報源から、ご自身にとって最善と思える病院を探すことが大切です。
病院選びのポイント
- 中皮腫の診療実績が豊富か
- 呼吸器内科、腫瘍内科、呼吸器外科、放射線科などが連携するチーム医療体制があるか
- 診断や治療方針について、分かりやすく十分に説明してくれるか
- 緩和ケアや相談支援体制が整っているか
以上
参考文献
BERZENJI, Lawek; VAN SCHIL, Paul. Multimodality treatment of malignant pleural mesothelioma. F1000Research, 2018, 7: F1000 Faculty Rev-1681.
WEDER, Walter; OPITZ, Isabelle. Multimodality therapy for malignant pleural mesothelioma. Annals of cardiothoracic surgery, 2012, 1.4: 502.
OPITZ, Isabelle, et al. A new prognostic score supporting treatment allocation for multimodality therapy for malignant pleural mesothelioma: a review of 12 years’ experience. Journal of Thoracic Oncology, 2015, 10.11: 1634-1641.
CAO, Christopher, et al. Systematic review of trimodality therapy for patients with malignant pleural mesothelioma. Annals of cardiothoracic surgery, 2012, 1.4: 428.
VAN SCHIL, Paul E., et al. Multimodal management of malignant pleural mesothelioma: where are we today?. 2014.
HOLZKNECHT, Arnulf, et al. Multimodal treatment of malignant pleural mesothelioma: real-world experience with 112 patients. Cancers, 2022, 14.9: 2245.
LANG-LAZDUNSKI, Loïc; ZHANG, Yu Zhi; NICHOLSON, Andrew G. Multimodality Therapy Including Pleurectomy/Decortication in Pleural Mesothelioma: Long-Term Outcomes in 152 Consecutive Patients A Retrospective Cohort Study. Annals of Surgery, 2025, 10.1097.
LAROSE, Frédéric, et al. Malignant pleural mesothelioma: Comparison of surgery-based trimodality therapy to medical therapy at two tertiary academic institutions. Lung cancer, 2021, 156: 151-156.
APRILE, Vittorio, et al. Hyperthermic intrathoracic chemotherapy for malignant pleural mesothelioma: the forefront of surgery-based multimodality treatment. Journal of Clinical Medicine, 2021, 10.17: 3801.
NERAGI-MIANDOAB, Siyamek. Multimodality approach in management of malignant pleural mesothelioma. European Journal of Cardio-thoracic surgery, 2006, 29.1: 14-19.