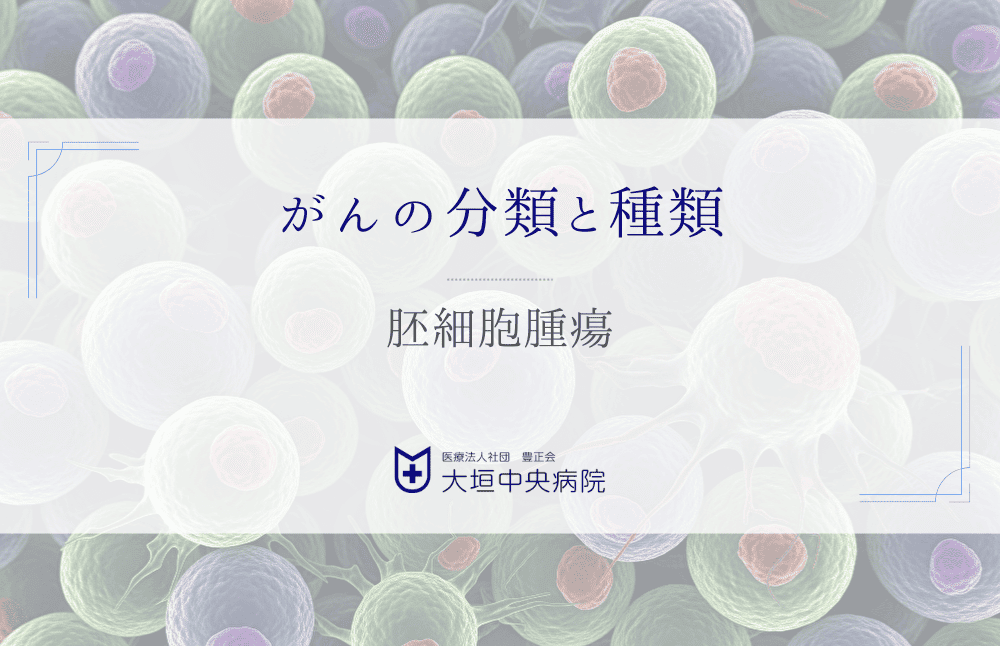胚細胞腫瘍は、主に精子や卵子のもとになる「生殖細胞」から発生する特殊な腫瘍です。
多くは思春期から30代の若年層に発症し、精巣や卵巣にできることが多いですが、胸部(縦隔)など体の中心線に沿った様々な部位に現れることもあります。
良性のものから悪性のものまで多様な顔つきを持ちますが、特に悪性の場合でも化学療法が劇的に効きやすいという大きな特徴があり、たとえ進行した状態で見つかっても治癒を目指せるがんの一つです。
この記事では、胚細胞腫瘍の基礎知識から診断、治療、そして治療後の生活までを詳しく解説します。
胚細胞腫瘍とは – 生殖細胞由来の特殊な腫瘍群
私たちの体を作る細胞は、大きく分けて体細胞と生殖細胞の二つに分類できます。胚細胞腫瘍は、後者の生殖細胞に由来するという、他のがんとは異なる発生起源を持つ腫瘍です。
この特殊な出自が、胚細胞腫瘍の多様な性質や治療への高い反応性の背景にあります。
生殖細胞の起源と腫瘍化
生殖細胞は、胎児期のごく初期に体の中心部で発生し、その後、男性では精巣へ、女性では卵巣へと移動して定着します。
しかし、この移動の過程で一部の生殖細胞が体の中心線上の別の場所(例えば、胸の中央にある縦隔や、お腹の奥深くにある後腹膜など)に迷い込んでしまうことがあります。
これらの迷入した細胞が、何らかのきっかけで異常な増殖を始めると、「性腺外胚細胞腫瘍」と呼ばれる腫瘍になります。
もちろん、本来の場所である精巣や卵巣で腫瘍化することの方がはるかに多く、これらは「性腺胚細胞腫瘍」と呼びます。
セミノーマと非セミノーマ
胚細胞腫瘍は、顕微鏡で見たときの組織の顔つき(組織型)によって、大きく「セミノーマ(精上皮腫)」と「非セミノーマ」の二つに分類します。
この分類は、腫瘍の性質や進行の速さ、治療法の選択に直結するため、極めて重要です。
非セミノーマはさらに、胎児性がん、卵黄嚢腫瘍、絨毛がん、未熟奇形腫といった複数のタイプに分かれ、しばしばこれらの成分が混在した「混合型」として見つかります。
良性から悪性まで – 胚細胞腫瘍の多様な病型
胚細胞腫瘍と一言でいっても、その性質は様々です。ほとんどの場合、手術だけで治癒する良性のものから、急速に進行し、全身に転移する悪性のものまで幅広く存在します。
正確な病理診断によってその性質を見極め、適切な治療方針を立てることが大切です。
良性胚細胞腫瘍の代表例
良性の胚細胞腫瘍で最も代表的なものは「成熟奇形腫」です。
これは、生殖細胞が様々な体の組織(皮膚、毛髪、歯、神経、脂肪など)に分化したもので、多くは卵巣や精巣、仙尾部(お尻のあたり)に発生します。
悪性化することはまれで、基本的には手術で腫瘍を完全に取り除くことで治癒します。
悪性胚細胞腫瘍の種類
悪性の胚細胞腫瘍は、前述の通りセミノーマと非セミノーマに大別されます。両者は治療への反応性が大きく異なります。
セミノーマ(精上皮腫)
セミノーマは、比較的ゆっくりと進行する傾向があります。このタイプの最大の特徴は、放射線治療と化学療法の両方に対する感受性が非常に高いことです。
そのため、たとえ転移がある場合でも、これらの治療法を組み合わせることで高い確率での治癒が期待できます。
非セミノーマ
非セミノーマは、セミノーマに比べて進行が速く、転移しやすい傾向があります。複数の組織型が混在することが多く、どの成分が主体かによって性質が異なります。
非セミノーマは放射線治療が効きにくいため、治療の主体は化学療法と手術になります。化学療法への感受性はセミノーマ同様に非常に高く、進行した場合でも治癒を目指せるがんです。
セミノーマと非セミノーマの主な違い
| 項目 | セミノーマ | 非セミノーマ |
|---|---|---|
| 進行速度 | 比較的緩やか | 比較的速い |
| 主な治療法 | 化学療法、放射線治療、手術 | 化学療法、手術 |
| 主な腫瘍マーカー | hCG(軽度上昇)、LDH | AFP、hCG、LDH |
なぜ若年層に多いのか – 発症年齢と性別の特徴
胚細胞腫瘍は、小児から高齢者まであらゆる年齢層で発症する可能性がありますが、そのピークは10代後半から30代の思春期・若年成人層にあります。
これは他のがんにはあまり見られない際立った特徴であり、その理由はまだ完全には解明されていません。
発症のピークと思春期の関連
発症のピークが思春期以降にあることから、性ホルモンの活発な分泌が、胎生期から体内に存在していた異常な生殖細胞の増殖を促す引き金になっているのではないか、という仮説があります。
しかし、直接的な因果関係はまだ証明されておらず、現在も研究が続けられています。
性別による発生部位の違い
発症には性別による違いも見られます。男性ではそのほとんどが精巣に発生する「精巣がん(精巣腫瘍)」として見つかります。一方、女性では卵巣に発生する「卵巣胚細胞腫瘍」が主です。
また、体の中心線上に発生する性腺外胚細胞腫瘍は、男性にやや多い傾向があります。
年齢層別にみた胚細胞腫瘍の特徴
| 年齢層 | 主な発生部位 | 主な組織型 |
|---|---|---|
| 乳幼児期 | 仙尾部、卵巣 | 卵黄嚢腫瘍、成熟奇形腫 |
| 思春期・若年成人 | 精巣、卵巣、縦隔 | セミノーマ、非セミノーマ各型 |
| 中高年以降 | 精巣 | セミノーマ(精母細胞性) |
精巣がん・卵巣がんとの関連性
胚細胞腫瘍の多くは、生殖腺である精巣または卵巣に発生します。したがって、精巣がんや卵巣がんの一部は、病理学的には胚細胞腫瘍に分類されることになります。
これらの部位に発生した場合、特有の症状が現れることがあります。
精巣に発生する胚細胞腫瘍
精巣がんは、若年男性のがんの中では比較的頻度が高いものです。早期発見が治療成績を大きく左右するため、症状を知っておくことが重要です。
主な症状 しこりと痛み
最も一般的な初期症状は、精巣の「痛みのないしこり」や「腫れ」です。片側の精巣が大きくなったり、硬くなったりすることで気づくことが多いです。
進行すると、鈍い痛みや下腹部に不快感を覚えることもあります。転移が起こると、転移した場所に応じた症状、例えば腹部のリンパ節への転移による腰痛や、肺への転移による咳や息切れなどが現れます。
自己検診の重要性
精巣のしこりは自分で触って気づくことが可能です。
月に一度、入浴時などリラックスしているときに、左右の精巣の大きさや硬さに変わりがないか、しこりがないかを自分で確認する「自己検診」の習慣が、早期発見につながります。
卵巣に発生する胚細胞腫瘍
卵巣に発生する胚細胞腫瘍は、卵巣がん全体の数パーセントを占めるにすぎませんが、やはり若年層に多いのが特徴です。
腹部の膨満感や痛み
卵巣は骨盤の深いところにあるため、初期には症状が出にくいことが多いです。腫瘍が大きくなるにつれて、お腹の張り(膨満感)や下腹部痛、頻尿などの症状が現れます。
時には、腫瘍がねじれる「茎捻転」を起こして、急激な激しい腹痛で発症することもあります。
精巣・卵巣胚細胞腫瘍の主な初期症状
| 発生部位 | 主な初期症状 | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| 精巣 | 痛みのないしこり、腫れ | 左右差、硬さの変化 |
| 卵巣 | 下腹部の張り、腹痛 | 症状が出にくく進行しやすい |
胚細胞腫瘍の発生部位 – 性腺から縦隔まで
胚細胞腫瘍は、精巣や卵巣といった性腺だけでなく、体の様々な場所に発生する可能性があります。
これを「性腺外胚細胞腫瘍」と呼び、胎児期における生殖細胞の移動経路に沿って見つかることが多いのが特徴です。
性腺外胚細胞腫瘍とは
性腺外胚細胞腫瘍は、精巣や卵巣に全く異常がないにもかかわらず、それ以外の場所に原発するものを指します。
発生頻度は胚細胞腫瘍全体の5%程度とまれですが、発生する部位によって特有の症状を引き起こすため、診断が難しい場合があります。
主な発生部位
性腺外胚細胞腫瘍は、体の中心線上に発生する傾向があります。
- 縦隔(前縦隔)
- 後腹膜
- 仙尾部
- 頭蓋内(松果体、神経下垂体部)
縦隔
縦隔は、左右の肺に挟まれた胸の中央部分を指し、性腺外胚細胞腫瘍が最も発生しやすい部位です。
腫瘍が大きくなると、周囲の気管や血管、神経を圧迫し、咳、胸の痛み、息苦しさ、顔や腕のむくみ(上大静脈症候群)などの症状を引き起こします。
性腺外胚細胞腫瘍の発生部位と主な症状
| 発生部位 | 主な圧迫症状 | その他 |
|---|---|---|
| 縦隔 | 咳、胸痛、呼吸困難 | 顔や腕のむくみ |
| 後腹膜 | 腹痛、腰痛、腹部膨満 | 足のむくみ |
| 頭蓋内 | 頭痛、嘔吐、視力障害 | ホルモン異常(尿崩症など) |
腫瘍マーカーが診断の鍵となる理由
胚細胞腫瘍の診療において、「腫瘍マーカー」は極めて重要な役割を果たします。腫瘍マーカーとは、がん細胞が作り出す特殊な物質のことで、血液検査で測定できます。
胚細胞腫瘍は特徴的なマーカーを産生するため、診断の補助、治療効果の判定、そして再発の早期発見に非常に役立ちます。
主要な腫瘍マーカー
胚細胞腫瘍で特に重要となるのは、AFP、hCG、LDHの3つの腫瘍マーカーです。これらは単独または複数組み合わせて上昇します。
各マーカーが示すもの
AFP(アルファ・フェトプロテイン)
AFPは、主に卵黄嚢腫瘍というタイプの非セミノーマで産生されます。正常な成人ではほとんど作られないため、この値が高い場合は卵黄嚢腫瘍成分の存在を強く疑います。
純粋なセミノーマや絨毛がんでは上昇しません。
hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)
hCGは、主に絨毛がんというタイプの非セミノーマで著しく高い値を示します。妊娠検査薬で陽性反応が出るのはこのhCGを検出しているためです。
セミノーマでも約10-15%の患者さんで軽度の上昇を見ることがありますが、高値であれば非セミノーマ(特に絨毛がん)の存在を考えます。
胚細胞腫瘍の組織型と腫瘍マーカーの関係
| 組織型 | AFP | hCG |
|---|---|---|
| セミノーマ | (−) | (−) or (+)軽度 |
| 卵黄嚢腫瘍 | (+) | (−) |
| 絨毛がん | (−) | (++)高値 |
| 胎児性がん | (+) or (−) | (+) or (−) |
診断と治療方針決定への活用
これらの腫瘍マーカーの値は、病理診断がつく前から治療方針を立てる上で重要な情報となります。例えば、AFPが高値であれば非セミノーマとして治療計画を立てます。
また、転移がある進行がんの場合、治療前のマーカーの値は、後述する予後予測にも用いられ、治療の強度を決定する因子の一つになります。
治療が始まると、マーカー値の低下は化学療法が効いている証拠となり、逆に治療後に再び上昇すれば再発を意味します。
他のがんと異なる胚細胞腫瘍の治療成績
胚細胞腫瘍は「治癒を目指せるがん」の代表格です。その最大の特徴は、悪性度が高く、進行が速いタイプであっても、化学療法に対する感受性が極めて高い点にあります。
このため、発見時に肺や肝臓、脳などに遠隔転移があるステージIVの状態であっても、根治を目標に強力な治療を行います。
高い治癒率の背景
なぜ胚細胞腫瘍がこれほど化学療法に弱いのか、その理由は完全には解明されていませんが、腫瘍細胞の遺伝子修復能力が低いことや、細胞増殖の周期が速いことなどが関係していると考えられています。
特に、シスプラチンという抗がん剤の登場が、胚細胞腫瘍の治療成績を飛躍的に向上させました。
予後分類の重要性
転移を有する進行性の胚細胞腫瘍では、国際的な予後分類(IGCCCG分類)を用いて、患者さんを「予後良好群」「予後中間群」「予後不良群」の3つのグループに分けます。
この分類は、原発巣が精巣か性腺外か、転移が肺にあるかそれ以外の臓器(肝臓、骨、脳など)にあるか、そして治療前の腫瘍マーカー(AFP, hCG, LDH)の値に基づいて行います。
この分類によって、治癒が期待できる確率がある程度予測でき、治療の強度(化学療法のコース数など)を決定する際の重要な指標となります。
進行性胚細胞腫瘍の国際予後分類(IGCCCG)の概要
| 予後分類 | 5年生存率の目安 | 主な条件(非セミノーマの場合) |
|---|---|---|
| 良好群 | 約92% | 精巣/後腹膜原発、肺転移のみ、マーカー低値 |
| 中間群 | 約80% | 精巣/後腹膜原発、肺転移のみ、マーカー中等度上昇 |
| 不良群 | 約48% | 縦隔原発、または非肺臓器転移、またはマーカー高値 |
化学療法への高い感受性がもたらす治療効果
胚細胞腫瘍の治療戦略は、病期(ステージ)、組織型(セミノーマか非セミノーマか)、そして前述の予後分類に基づいて決定します。
その中でも、特に悪性腫瘍に対する治療の根幹をなすのが化学療法です。
標準的な化学療法レジメン
現在、世界の標準治療として確立しているのが、3種類の抗がん剤(ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチン)を組み合わせる「BEP療法」です。
肺に副作用をもたらす可能性のあるブレオマイシンを使わず、エトポシドとシスプラチンの2剤で行う「EP療法」も、患者さんの状態に応じて選択します。
これらの化学療法を、予後分類に応じて3〜4コース(1コースは約3週間)行います。
手術と化学療法の連携
手術も治療の重要な柱です。原発巣(精巣など)の摘出は、正確な診断と局所のコントロールのために基本となります。
化学療法後の残存腫瘍に対する手術
転移がある患者さんでは、まず化学療法を行います。化学療法によって多くの腫瘍は消滅または縮小しますが、画像上、腫瘍が残存することがあります。
特に非セミノーマの場合、この残存腫瘍には、壊死組織だけでなく、治療抵抗性の悪性細胞や、良性の奇形腫成分が含まれている可能性があります。
奇形腫は化学療法や放射線治療が無効であり、放置すると増大したり、まれに悪性化(二次性悪性腫瘍)したりすることがあるため、手術による摘出が必要です。
放射線治療の位置づけ
放射線治療は、セミノーマに対して非常に高い効果を発揮します。早期のセミノーマでは、手術後の再発予防目的でリンパ節領域に照射を行うことがあります。
また、進行したセミノーマでも、化学療法後の残存腫瘍に対してや、骨や脳への転移による症状を和らげる目的で放射線治療を行うことがあります。非セミノーマに対しては、原則として放射線治療は行いません。
小児がんとしての胚細胞腫瘍の特徴
胚細胞腫瘍は小児に発生する固形がんの中でも比較的頻度が高いものです。成人の場合とは異なる特徴がいくつかあり、治療においても小児特有の配慮が必要です。
好発部位と組織型
小児、特に乳幼児期では、性腺よりも性腺外、とりわけ仙尾部(お尻の部分)に発生することが最も多いです。次いで卵巣、精巣の順となります。
組織型としては、良性の成熟奇形腫や、悪性では卵黄嚢腫瘍が多く、成人に多いセミノーマはまれです。
小児に対する治療の考え方
小児がんの治療では、がんを治すことと同時に、治療によって生じる可能性のある長期的な影響(晩期合併症)をできるだけ少なくすることが大きな目標となります。
胚細胞腫瘍の治療に用いるシスプラチンは腎機能障害や聴力障害を、ブレオマイシンは肺線維症を、エトポシドは二次性白血病を引き起こすリスクがあります。
また、放射線治療は成長期の骨の発育に影響を与えたり、二次がんのリスクを高めたりします。
そのため、小児の治療では、これらのリスクを考慮し、抗がん剤の投与量を調整したり、可能な限り放射線治療を避けたりするなど、慎重な治療計画を立てます。
治療後の長期フォローアップの重要性
胚細胞腫瘍は治癒率が高いがんですが、治療が終わればすべて完了というわけではありません。
治療後の人生を健やかに過ごすためには、再発のチェックと、治療による影響(晩期合併症)の管理を目的とした長期的なフォローアップが重要です。
再発のモニタリング
胚細胞腫瘍の再発は、その80%以上が治療終了後2年以内に起こります。そのため、治療後数年間は特に注意深い経過観察が必要です。
定期的な検査
フォローアップでは、定期的に通院し、問診、身体診察、そして血液検査による腫瘍マーカー(AFP, hCG, LDH)の測定を行います。
これに加えて、胸部X線写真やCTスキャンなどの画像検査を定期的に行い、転移が出やすい肺や後腹膜のリンパ節などをチェックします。
検査の頻度は、治療後からの期間や再発のリスクに応じて調整します。
フォローアップの検査項目例
| 検査項目 | 目的 | 頻度の目安(治療後初期) |
|---|---|---|
| 診察・問診 | 自覚症状の確認 | 1〜3ヶ月ごと |
| 腫瘍マーカー | 再発の早期発見 | 1〜3ヶ月ごと |
| 画像検査(CTなど) | 転移の有無の確認 | 3〜6ヶ月ごと |
晩期合併症への対策
晩期合併症は、治療が終わってから数ヶ月、あるいは数年以上経ってから現れる健康上の問題です。胚細胞腫瘍の治療で用いた化学療法や放射線治療は、将来的に様々な影響を及ぼす可能性があります。
- 心血管系疾患(高血圧、脂質異常症、心筋梗塞など)
- 二次がん(白血病、固形がん)
- 聴力障害、耳鳴り
- 腎機能障害
- 末梢神経障害(手足のしびれ)
- 妊孕性(にんようせい)の低下
これらのリスクを管理するため、定期的な健康診断や、必要に応じた専門的な検査(心電図、聴力検査など)を受けることが大切です。
また、禁煙やバランスの取れた食事、適度な運動といった健康的な生活習慣を心がけることも、晩期合併症のリスクを低減させる上で重要です。
よくある質問 (Q&A)
- 治療による副作用にはどのようなものがありますか?
-
化学療法の最中には、吐き気、食欲不振、口内炎、脱毛、骨髄抑制(白血球や血小板の減少)といった短期的な副作用が起こります。
これらは支持療法(吐き気止めなど)で軽減できます。治療後、長期的に問題となる可能性があるのが「晩期合併症」で、心臓や腎臓への影響、聴力低下、二次がんのリスクなどが挙げられます。
どのような副作用が起こりうるかは、受けた治療の種類や量によって異なります。
- 妊孕性(子供を作る能力)は維持できますか?
-
胚細胞腫瘍の治療は、精子や卵子を作る機能に影響を与える可能性があります。特に男性の場合、精巣摘出や化学療法によって精子を作る能力が低下したり失われたりすることがあります。
そのため、治療を開始する前に、将来子供を持つことを希望する場合には、精子や卵子、あるいは受精卵を凍結保存する「妊孕性温存療法」について主治医と相談することが強く推奨されます。
- 家族が胚細胞腫瘍になった場合、自分も発症しやすいですか?
-
胚細胞腫瘍のほとんどは遺伝性ではなく、散発的に発生します。
しかし、親子や兄弟で発症したという報告も少数ながらあり、何らかの遺伝的な要因が関与する可能性は完全には否定されていません。
血縁者に胚細胞腫瘍の患者さんがいる場合、一般の人よりは発症リスクがわずかに高まる可能性はありますが、過度に心配する必要はありません。
気になる症状があれば、早めに専門医に相談することが大切です。
胚細胞腫瘍について理解を深めていただけたでしょうか。がんには様々な種類があり、それぞれに特徴的な性質があります。
例えば、ホルモンを産生するという特殊な性質を持つ「神経内分泌腫瘍(NET)」もその一つです。胚細胞腫瘍とは発生起源も症状も異なりますが、比較的まれながんであるという共通点もあります。
ご自身の、あるいは大切な方のがんに対する理解をさらに深めるために、こちらの記事もぜひご覧ください。
以上
参考文献
CHOVANEC, Michal, et al. Late adverse effects and quality of life in survivors of testicular germ cell tumour. Nature Reviews Urology, 2021, 18.4: 227-245.
CHOVANEC, M., et al. Long-term toxicity of cisplatin in germ-cell tumor survivors. Annals of Oncology, 2017, 28.11: 2670-2679.
WONG, Jordan, et al. Long term toxicity of intracranial germ cell tumor treatment in adolescents and young adults. Journal of neuro-oncology, 2020, 149.3: 523-532.
TRAVIS, Lois B., et al. Adolescent and young adult germ cell tumors: epidemiology, genomics, treatment, and survivorship. Journal of Clinical Oncology, 2024, 42.6: 696-706.
HAUGNES, Hege S., et al. Long-term and late effects of germ cell testicular cancer treatment and implications for follow-up. Journal of Clinical Oncology, 2012, 30.30: 3752-3763.
STEIN, Kevin. The long term effects of cancer and cancer treatment: Research at the american cancer society. In: VI European Conference on Cured and Chronic Cancer Patients; Edisciences: Siracusa, Italy. 2016. p. 81.
FUNG, Chunkit, et al. Toxicities associated with cisplatin‐based chemotherapy and radiotherapy in long‐term testicular cancer survivors. Advances in urology, 2018, 2018.1: 8671832.
MAROTO, P.; ANGUERA, G.; MARTIN, C. Long-term toxicity of the treatment for germ cell-cancer. A review. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 2018, 121: 62-67.
CHEN, Rong-Long; LIN, Han-Ting; CHEN, Liuh-Yow. Chemotherapy for extracranial germ cell tumours in paediatric, adolescent, and young adult patients. ONCOLOGY, 2017.
TAKAHASHI, Ryohei, et al. Current clinical perspective of urological oncology in the adolescent and young adult generation. International Journal of Clinical Oncology, 2023, 28.1: 28-40.
特殊な腫瘍に戻る