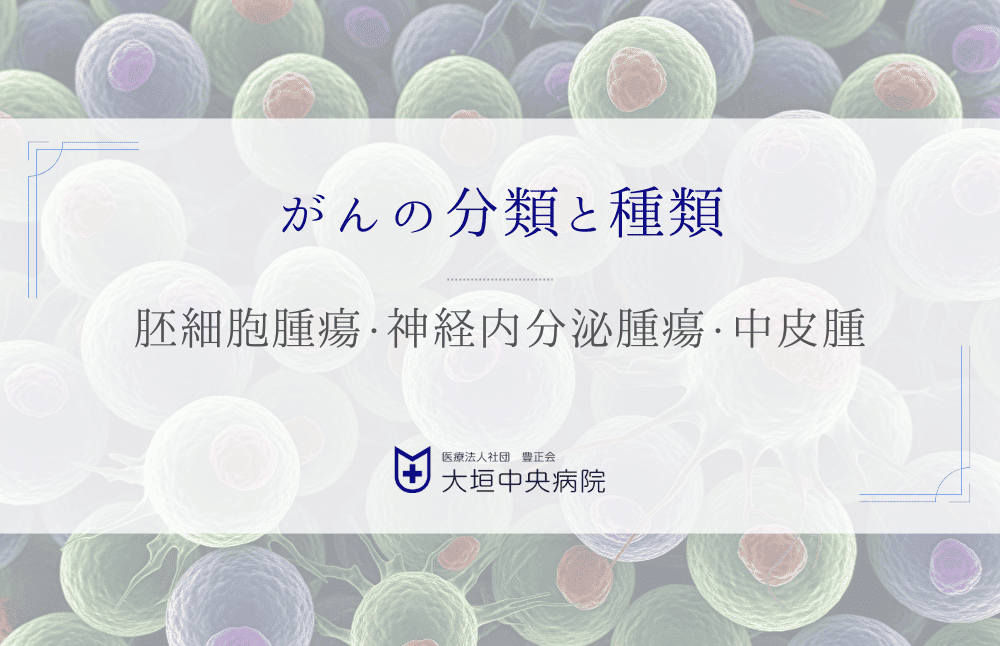癌には様々な種類が存在しますが、中には発生頻度が低く、診断や治療に特有の知識を要する「特殊な腫瘍」があります。
この記事では、そのような腫瘍の中から「胚細胞腫瘍」「神経内分泌腫瘍」「中皮腫」の三つを取り上げ、それぞれの特徴、症状、診断、治療法について詳しく解説します。
これらの腫瘍は発生する起源や性質が大きく異なり、正しい知識を持つことが、ご自身の状態を理解し、治療に向き合う上で重要です。
胚細胞腫瘍 - 生殖細胞から発生する多様な腫瘍群
胚細胞腫瘍は、胎児期に精子や卵子になる前の「原始生殖細胞」から発生する腫瘍の総称です。
本来、生殖細胞は精巣や卵巣に存在しますが、発生の過程で体の中心線に沿って移動する際に一部が迷入し、胸部(縦隔)や腹部(後腹膜)、脳内(頭蓋内)など、生殖腺以外の場所からも発生することがあります。
非常に多様な組織像を示し、良性から悪性まで幅広い性質を持つのが特徴です。
胚細胞腫瘍とは何か
発生起源と特徴
私たちの体を作る細胞は、大きく体細胞と生殖細胞に分けられます。胚細胞腫瘍は後者の生殖細胞に由来します。胎児が母親の胎内で成長する過程で、将来精子や卵子になる原始生殖細胞が作られます。
これらの細胞が何らかの理由で異常に増殖することで腫瘍を形成します。
一つの腫瘍の中に、神経、筋肉、骨、軟骨、毛髪など、様々な組織が混在する「奇形腫」もこの腫瘍群に含まれ、その多様性が大きな特徴です。
好発年齢と部位
胚細胞腫瘍は、10代後半から30代の若年成人に多く見られます。最も発生頻度が高いのは精巣で、男性の固形がんの中では比較的まれですが、この年代では最も多い悪性腫瘍の一つです。
次いで卵巣、そして体の中心線上に位置する縦隔、仙尾部、後腹膜、頭蓋内の松果体などに発生します。部位によって症状や治療法が異なるため、発生部位の特定は非常に重要です。
主な種類と分類
胚細胞腫瘍は、組織学的な特徴から大きく「セミノーマ」と「非セミノーマ」に大別します。この分類は治療方針を決定する上で極めて重要です。
セミノーマ(精上皮腫)
セミノーマは、胚細胞腫瘍の中で最も多いタイプです。比較的ゆっくりと進行する傾向があり、特に放射線治療と化学療法に対する感受性が高いという特徴があります。
そのため、転移がある場合でも高い治癒率を期待できます。卵巣に発生した場合は「ディスジャーミノーマ」と呼びます。
非セミノーマ
非セミノーマは、セミノーマ以外の胚細胞腫瘍をまとめた呼び方で、複数の組織型が混在することが多いです。胎児性癌、卵黄嚢腫瘍、絨毛癌、未熟奇形腫などが含まれます。
セミノーマに比べて進行が速く、転移しやすい傾向があります。治療は主に化学療法と外科手術を組み合わせて行います。放射線治療の効果は限定的です。
成熟奇形腫と未熟奇形腫
奇形腫は、体の様々な組織に分化した細胞を含む腫瘍です。分化の度合いが正常な組織に近いものを「成熟奇形腫」と呼び、基本的には良性です。
一方で、胎児期の組織に似た未熟な細胞を含むものを「未熟奇形腫」と呼び、悪性の性質を持つ可能性があります。
特に非セミノーマの中に奇形腫の成分が含まれることも多く、治療後の残存腫瘍として見られることもあります。
症状と発見のきっかけ
部位別の主な症状
症状は腫瘍が発生した部位によって大きく異なります。精巣腫瘍の場合は、痛みや発熱を伴わない精巣の腫れや硬化が最も一般的な初期症状です。
縦隔に発生した場合は、胸の痛み、咳、呼吸困難、顔や腕のむくみなどが現れます。卵巣腫瘍では、腹部の膨満感や下腹部痛、不正出血などがきっかけで発見されることがあります。
腫瘍マーカーの役割
胚細胞腫瘍の一部は、AFP(アルファ・フェトプロテイン)、hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)、LDH(乳酸脱水素酵素)といった特定の物質を血液中に放出します。これらを「腫瘍マーカー」と呼びます。
これらのマーカーは、診断の補助、治療効果の判定、再発の早期発見において非常に有用な指標となります。
特に非セミノーマではAFPやhCGが上昇することが多く、セミノーマではhCGが軽度上昇することがあります。
胚細胞腫瘍の分類と特徴
| 分類 | 主な組織型 | 特徴 |
|---|---|---|
| セミノーマ | 精上皮腫、ディスジャーミノーマ | 進行は比較的緩やか。放射線や化学療法が効きやすい。 |
| 非セミノーマ | 胎児性癌、卵黄嚢腫瘍、絨毛癌 | 進行が速い傾向。化学療法と手術が治療の中心。 |
| 奇形腫 | 成熟奇形腫、未熟奇形腫 | 様々な組織が混在。良性から悪性の可能性がある。 |
診断と治療法
診断は、身体診察、画像検査、血液検査を組み合わせて進めます。最終的には、手術で摘出した腫瘍組織を顕微鏡で調べる病理組織学的診断によって確定します。
治療は、腫瘍の種類(セミノーマか非セミノーマか)、進行度(病期)、発生部位、全身の状態を総合的に判断して決定します。
化学療法、放射線治療、外科手術を単独または組み合わせて行う集学的治療が基本です。
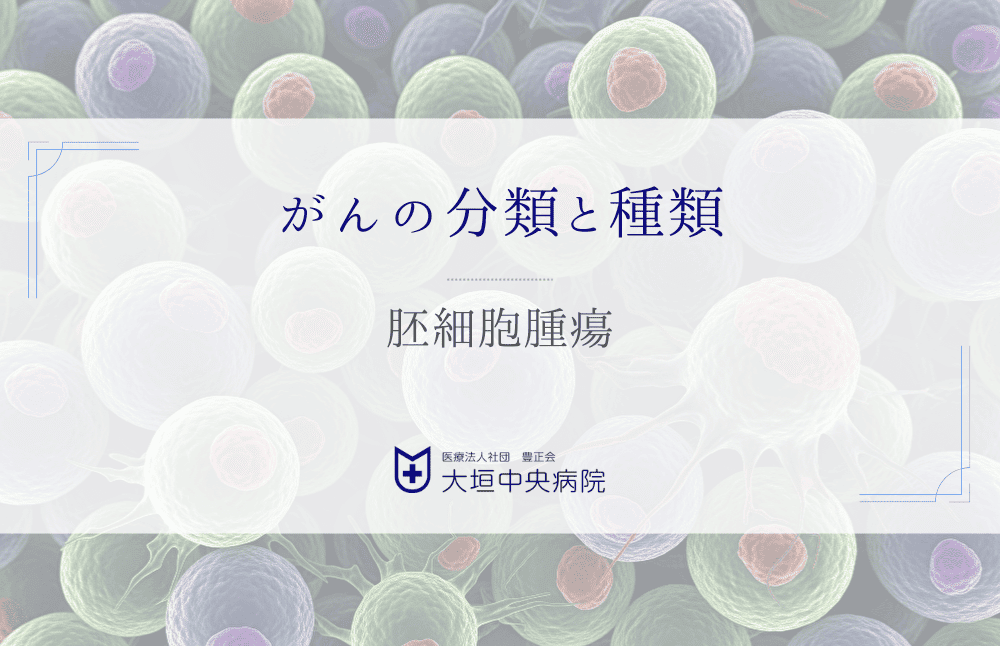
神経内分泌腫瘍(NET) - ホルモンを産生する特殊な腫瘍群
神経内分泌腫瘍(Neuroendocrine Tumor, NET)は、ホルモンやペプチドを産生する「神経内分泌細胞」から発生する腫瘍の総称です。
これらの細胞は全身に分布しているため、NETは消化器(膵臓、消化管)や肺など、体の様々な場所に発生する可能性があります。
進行が非常に緩やかなものから、急速に増大する悪性度の高いものまで、その性質は多岐にわたります。
神経内分泌腫瘍(NET)の基礎知識
神経内分泌細胞とは
神経内分泌細胞は、神経細胞と内分泌(ホルモン産生)細胞の両方の性質を併せ持つ特殊な細胞です。
体の状態に応じて、セロトニン、ガストリン、インスリン、グルカゴンといった様々なホルモンや生理活性物質を血液中に放出し、体の機能を調整する役割を担っています。
この細胞が腫瘍化することでNETが発生します。
腫瘍の発生と進行速度
NETは、体のどこにでも発生する可能性がありますが、約6割が消化器(特に膵臓、直腸、小腸)、約3割が肺や気管支に発生します。
多くは進行が年単位と非常にゆっくりで、無症状のまま経過し、検診や他の病気の検査で偶然発見されることも少なくありません。
しかし、一部には進行が速く、悪性度の高いタイプ(神経内分泌がん、NEC)も存在するため、正確な診断が重要です。
分類とグレード
機能性と非機能性
NETは、ホルモンを過剰に産生して特有の症状を引き起こす「機能性NET」と、ホルモン産生がほとんどなく症状が現れにくい「非機能性NET」に分けられます。
機能性NETの例としては、インスリンを過剰に産生して低血糖発作を起こす「インスリノーマ」や、セロトニンなどにより下痢や顔面の紅潮を引き起こす「カルチノイド症候群」を伴うNETが挙げられます。
非機能性NETは、腫瘍が大きくなるまで症状が出にくいため、発見が遅れる傾向があります。
WHO分類(G1, G2, G3, NEC)
NETの悪性度は、腫瘍細胞の増殖能力に基づいて分類します。
細胞分裂の頻度や、増殖能を示すKi-67(ケーアイろくじゅうなな)指数によって、G1(低グレード)、G2(中グレード)、G3(高グレード)に分けられます。
G1が最も進行が遅く、G3になるほど進行が速くなります。
さらに、組織の形態が明らかにがんであり、増殖能力が非常に高いものは「神経内分泌がん(Neuroendocrine Carcinoma, NEC)」として区別し、NETとは異なる治療戦略をとります。
NETの悪性度グレード分類
| グレード | Ki-67指数 | 予後の傾向 |
|---|---|---|
| G1(低) | 3%未満 | 進行は非常に緩やか。 |
| G2(中) | 3% - 20% | 緩やかに進行する。 |
| G3(高) | 20%超 | 進行が速い傾向がある。 |
診断へのアプローチ
診断には様々な検査を組み合わせます。腫瘍の場所や種類を特定するために、内視鏡検査(胃カメラや大腸カメラ)、超音波内視鏡(EUS)、CT、MRIなどの画像検査を行います。
確定診断には、内視鏡や針を使って腫瘍の一部を採取し、顕微鏡で調べる生検(病理組織診断)が必要です。また、多くのNETの細胞表面には「ソマトスタチン受容体」という目印が存在します。
この性質を利用した「ソマトスタチン受容体シンチグラフィ(SRS)」や「Ga-DOTATOC PET/CT」は、全身のNETの広がりを調べるのに非常に有用な検査です。
治療戦略
NETの治療は、腫瘍のグレード、場所、広がり、症状の有無などを考慮して慎重に決定します。転移がなく切除可能な場合は、外科手術が第一選択です。
切除が困難な場合や転移がある場合は、薬物療法が中心となります。薬物療法には、ホルモンの働きを抑えたり、腫瘍の増殖を抑制したりする「ソマトスタチンアナログ製剤」、特定の分子を標的とする「分子標的薬」、そして細胞障害性の「抗がん剤」などがあります。
また、ソマトスタチン受容体を利用して放射線を腫瘍細胞に直接届ける「PRRT(ペプチド受容体放射性核種療法)」という治療法も選択肢の一つです。
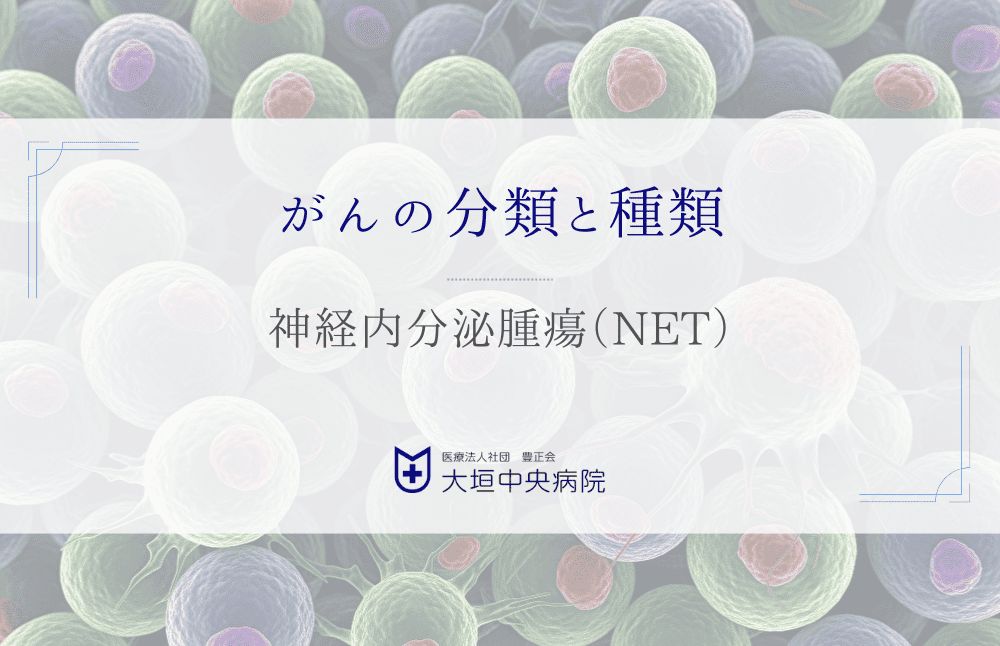
中皮腫 - アスベストが引き起こす胸膜・腹膜の悪性腫瘍
中皮腫は、胸腔(肺を覆う胸膜)、腹腔(内臓を覆う腹膜)、心膜(心臓を覆う心膜)といった、体の内腔を覆う「中皮細胞」から発生する悪性腫瘍です。
その発生には、過去に建材や断熱材として広く使用されたアスベスト(石綿)への曝露が強く関連していることが知られています。
アスベストを吸い込んでから数十年という非常に長い潜伏期間を経て発症するのが大きな特徴です。
中皮腫の発生原因
アスベスト(石綿)との強い関連
中皮腫の最大の原因はアスベストです。アスベストは極めて細い繊維状の鉱物で、吸い込むと肺の奥深くまで到達し、長期間体内に留まります。
この繊維が胸膜や腹膜の中皮細胞を慢性的に刺激し、遺伝子変異を引き起こすことで、がん化すると考えられています。
アスベストを取り扱う職業(建設業、造船業、自動車整備業など)に従事していた人に多く見られますが、その家族や工場の周辺住民など、直接的な職業曝露がない人にも発症することがあります。
長い潜伏期間
中皮腫は、アスベストを吸い込んでから発症するまでの潜伏期間が平均して40年から50年と非常に長いのが特徴です。そのため、過去にアスベスト曝露の経験がある高齢者に多く発症します。
アスベストの使用が原則禁止された現在でも、過去の曝露が原因で発症する患者は今後も続くと予測されています。
発生部位と種類
中皮腫は発生する部位によって名称が異なります。最も多いのが胸膜に発生する悪性胸膜中皮腫です。
- 悪性胸膜中皮腫
- 悪性腹膜中皮腫
- 悪性心膜中皮腫
このほか、精巣の鞘膜から発生する悪性精巣鞘膜中皮腫もまれに報告されます。
また、組織学的には上皮型、肉腫型、二相型の3つのタイプに分類され、この分類は治療方針や予後を予測する上で重要です。
中皮腫の主な組織型
| 組織型 | 発生頻度 | 予後の傾向 |
|---|---|---|
| 上皮型 | 約60-70% | 他の型に比べて比較的良好。 |
| 肉腫型 | 約10-20% | 進行が速く、治療抵抗性を示すことが多い。 |
| 二相型 | 約10-20% | 上皮型と肉腫型の両方の成分が混在。 |
典型的な症状と診断
症状
悪性胸膜中皮腫では、胸水(肺と胸壁の間に水がたまる状態)がたまることによる息切れや呼吸困難、持続する胸の痛み、咳などが主な症状です。
一方、悪性腹膜中皮腫では、腹水による腹部の膨満感、腹痛、便秘、食欲不振などが現れます。これらの症状は他の病気でも見られるため、診断が遅れることも少なくありません。
診断の確定まで
中皮腫が疑われる場合、まず胸部X線検査やCT検査などの画像検査で胸水や腹水、胸膜や腹膜の肥厚を確認します。診断を確定するためには、腫瘍細胞そのものを採取して顕微鏡で調べることが必要です。
胸水や腹水を注射器で抜いて細胞を調べる「細胞診」や、胸腔鏡や腹腔鏡という内視鏡を用いて直接腫瘍組織の一部を採取する「生検」を行い、病理組織学的診断で確定します。
集学的治療のアプローチ
中皮腫の治療は、病期(進行度)、組織型、患者の全身状態を総合的に評価して決定します。手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせた集学的治療が基本です。
薬物療法では、複数の抗がん剤を組み合わせる化学療法が標準治療の中心です。
近年では、体の免疫の仕組みを利用してがん細胞を攻撃する「免疫チェックポイント阻害薬」も重要な治療選択肢となり、治療成績の向上に貢献しています。
治療は長期にわたることが多く、症状を和らげる緩和ケアも並行して行うことが大切です。
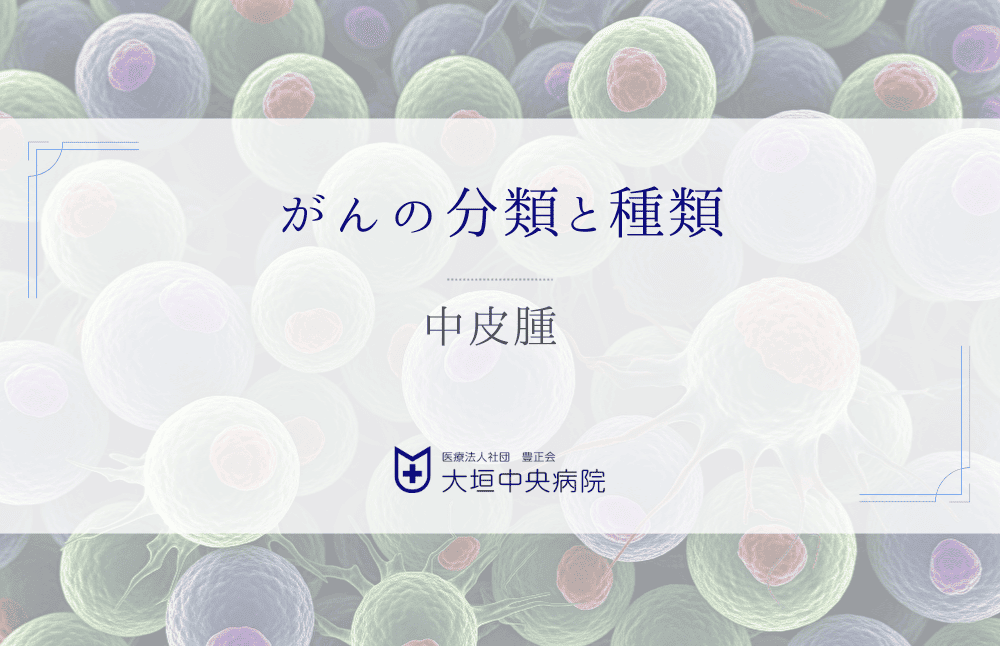
よくある質問
- 特殊な腫瘍は遺伝しますか?
-
今回解説した胚細胞腫瘍、神経内分泌腫瘍、中皮腫のほとんどは、遺伝的要因よりも後天的な要因で発生する「孤発性」のものです。
ただし、ごくまれに特定の遺伝性疾患が背景にある場合があります。例えば、一部の神経内分泌腫瘍は多発性内分泌腫瘍症(MEN)という遺伝性疾患の一部として発生することが知られています。
家族歴などで気になることがある場合は、主治医に相談することが大切です。
- 治療後の生活で気をつけることは何ですか?
-
治療後の体調は、受けた治療の種類や範囲によって大きく異なります。まずは無理をせず、体力の回復を最優先にしてください。
食事や運動については、自己判断せず、医師や看護師、管理栄養士の指導に従うことが重要です。また、治療後は定期的な通院と検査で再発の有無を確認します。
指定されたスケジュール通りに受診を続けることが、万が一の再発を早期に発見するために必要です。
- セカンドオピニオンは考えた方が良いでしょうか?
-
はい、セカンドオピニオンは患者の正当な権利であり、特に発生頻度の低い特殊な腫瘍の診断や治療においては、積極的に活用を検討する価値があります。
現在の主治医から提供された診断や治療方針について、別の医療機関の専門医の意見を聞くことで、病気への理解が深まったり、納得して治療を選択できたりする利点があります。
主治医にセカンドオピニオンを希望する旨を伝え、紹介状や検査データを提供してもらうのが一般的です。
- 専門医を見つけるにはどうすればよいですか?
-
特殊な腫瘍の診療経験が豊富な医師や医療機関を探すことは、治療成績にも影響する重要な点です。まずは現在かかっている医療機関の主治医に相談するのが第一歩です。
また、各学会のウェブサイトで専門医のリストを公開している場合や、がん診療連携拠点病院などに設置されている「がん相談支援センター」で情報提供を受けることもできます。
これらの資源を活用し、信頼できる医療チームを見つけることが治療への第一歩となります。
以上
参考文献
DUMOULIN, Daphne W., et al. Rare thoracic cancers: a comprehensive overview of diagnosis and management of small cell lung cancer, malignant pleural mesothelioma and thymic epithelial tumours. European Respiratory Review, 2023, 32.167.
FRANCESCHI, Enrico, et al. Rare primary central nervous system tumors in adults: an overview. Frontiers in Oncology, 2020, 10: 996.
MITRANOVICI, Melinda-Ildiko, et al. Diagnosis and management of dysgerminomas with a brief summary of primitive germ cell tumors. Diagnostics, 2022, 12.12: 3105.
AUST, Stefanie, et al. Detailed overview on rare malignant ovarian tumors. Bulletin du Cancer, 2020, 107.3: 385-390.
WILLIAMSON, Sean R.; ULBRIGHT, Thomas M. Germ cell tumors of the mediastinum. Pathology of the mediastinum, 2014, 146-68.
VIVEKANANDHAN, Sneha, et al. Immunotherapies in rare cancers. Molecular Cancer, 2023, 22.1: 23.
FRUMOVITZ, Michael; LEITAO JR, Mario M.; RAMALINGAM, Preetha. Diagnosis and Treatment of Rare Gynecologic Cancers-E-Book. Elsevier Health Sciences, 2022.
MCKENNEY, Jesse K.; HEEREMA-MCKENNEY, Amy; ROUSE, Robert V. Extragonadal germ cell tumors: a review with emphasis on pathologic features, clinical prognostic variables, and differential diagnostic considerations. Advances in anatomic pathology, 2007, 14.2: 69-92.
YOUNG, Robert H. Testicular tumors—some new and a few perennial problems. Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 2008, 132.4: 548-564.
CHRISTYANI, Grania, et al. An overview of advances in rare cancer diagnosis and treatment. International Journal of Molecular Sciences, 2024, 25.2: 1201.