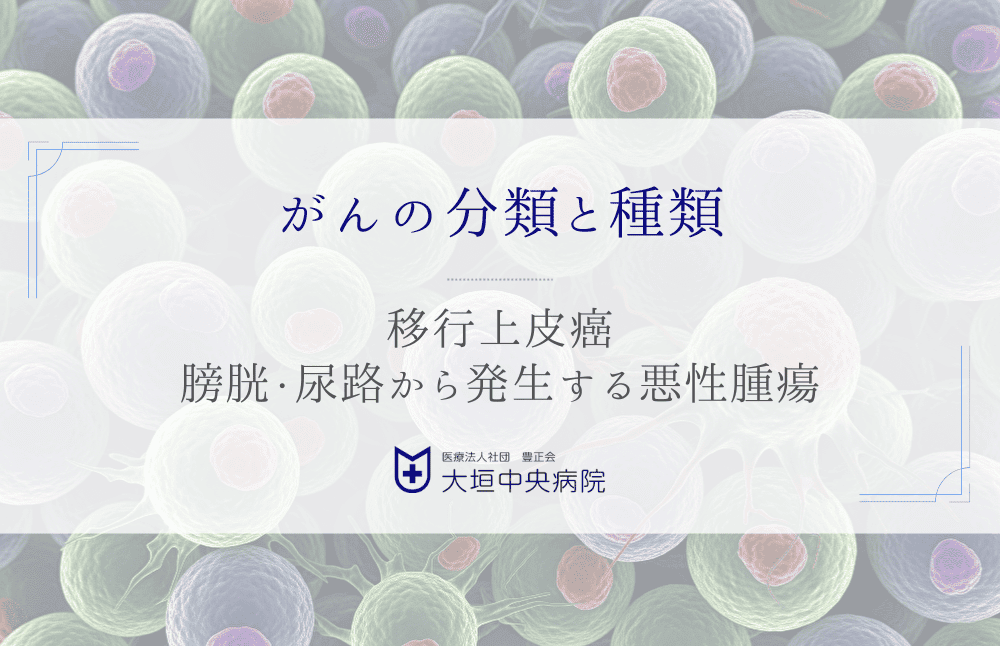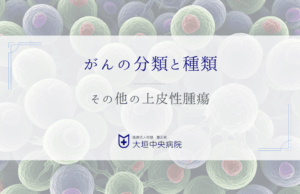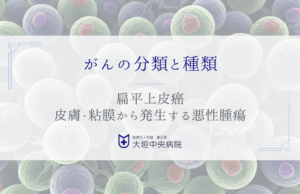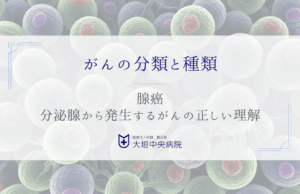移行上皮癌は、現在では「尿路上皮癌」という名称で知られ、私たちの尿路、特に膀胱に発生する悪性腫瘍です。
この癌は、尿を体外へ排出する通り道である腎盂や尿管にも生じることがあります。初期症状として最も多いのが、痛みを伴わない血尿です。
この記事では、移行上皮癌の基本的な知識から、その原因、症状、診断方法、そして筋層への浸潤の有無によって大きく変わる治療の選択肢まで、患者さんとご家族が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
移行上皮癌とは何か – 尿路上皮の悪性変化
私たちの体内で作られた尿は、腎臓の「腎盂」という部分に集められ、「尿管」を通り「膀胱」に溜められ、最終的に「尿道」から排出されます。この一連の尿の通り道を「尿路」と呼びます。
この尿路の内側は、「尿路上皮」という特殊な粘膜で覆われています。移行上皮癌、すなわち尿路上皮癌は、この尿路上皮の細胞が悪性化して発生する癌です。
尿路上皮の構造と癌の発生部位
尿路上皮は数層の細胞から成り、膀胱が尿で満たされた際には薄く伸び、空になると厚く縮むという伸縮性に富んだ性質を持っています。
この柔軟な組織が、常に尿という刺激にさらされることで、細胞に遺伝子変異が蓄積し、癌化することがあります。
発生頻度が最も高いのは膀胱で、尿路上皮癌全体の約95%を占めます。残りの約5%が腎盂や尿管に発生します。
尿路上皮癌の主な発生部位
| 発生部位 | 特徴 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 膀胱 | 尿を一時的に溜める袋状の臓器。最も発生しやすい。 | 約95% |
| 腎盂・尿管 | 腎臓と膀胱をつなぐ管状の臓器。膀胱癌との重複も多い。 | 約5% |
| 尿道 | 膀胱から体外へ尿を排出する管。発生は稀。 | 1%未満 |
癌の性質による分類
尿路上皮癌は、その後の治療方針を決定する上で極めて重要な、二つのタイプに大別します。一つは、癌が尿路上皮の表面、つまり粘膜内にとどまっている「筋層非浸潤癌」。
もう一つは、癌が粘膜を越えて膀胱の壁の深い部分、すなわち筋層にまで達している「筋層浸潤癌」です。この違いによって、治療の強度や手術の方法が大きく異なります。
移行上皮がんの原因 – 喫煙と職業性発がん物質の影響
移行上皮癌の発生には、特定の生活習慣や環境が深く関与していることが分かっています。その中でも、最も確実な原因として挙げられるのが喫煙です。
また、特定の化学物質を扱う職業に従事することも、リスクを高める要因となります。
最大の原因である喫煙
喫煙は、移行上皮癌(尿路上皮癌)の発生における最大の危険因子です。タバコの煙に含まれる多くの発がん物質は、肺から吸収されて血液中に入り、全身を巡ります。
最終的に腎臓で濾過されて尿中に排泄されるため、これらの発がん物質が長時間にわたって尿路の粘膜に接触し、細胞にダメージを与えます。
喫煙者は非喫煙者に比べて、膀胱癌になるリスクが2倍から4倍も高くなると報告されています。禁煙することで、そのリスクを時間とともに減少させることが可能です。
喫煙と発がんリスクの関係
| 要因 | リスクへの影響 | 解説 |
|---|---|---|
| 喫煙習慣 | リスクが2~4倍に増加 | タバコ煙中の発がん物質が尿中に排泄され、尿路上皮を刺激する。 |
| 禁煙 | リスクが徐々に低下 | 禁煙後10年以上でリスクは大幅に減少するが、非喫煙者レベルには戻らない。 |
職業性曝露と化学物質
特定の化学物質に長期間さらされる職業も、移行上皮癌の明確な原因となります。特に、染料やゴム、皮革、化学薬品などを製造する工場で働く人々は注意が必要です。
芳香族アミン類などの化学物質は、体内で代謝された後に尿中に排泄され、膀胱の粘膜に影響を与えます。過去にこれらの物質を扱っていた場合、曝露から数十年経ってから癌を発症することもあります。
見逃しやすい初期症状 – 血尿が示す重要なサイン
移行上皮癌の症状は、初期段階では非常に気づきにくいことがあります。しかし、体が発する重要なサインを見逃さないことが、早期発見と治療成功の鍵を握ります。
最も代表的な症状は血尿ですが、その現れ方には特徴があります。
痛みのない血尿(無症候性肉眼的血尿)
移行上皮癌の最も典型的で重要な初期症状は、排尿時の痛みなどを全く伴わない「無症候性肉眼的血尿」です。これは、目で見て明らかに尿が赤色や茶褐色、あるいはコーラのような色に見える状態を指します。
この血尿は、一度出たきりで自然に消えてしまうことが多く、「治った」と自己判断してしまうケースが少なくありません。
しかし、癌がなくなったわけではなく、症状が一時的に隠れているだけです。一度でも痛みのない血尿を認めた場合は、症状が消えても必ず泌尿器科を受診し、精密な検査を受けることが重要です。
血尿の種類と対応
| 血尿の種類 | 特徴 | 取るべき行動 |
|---|---|---|
| 肉眼的血尿 | 目で見て尿の色が赤いとわかる状態。 | 痛みの有無にかかわらず、直ちに泌尿器科を受診する。 |
| 顕微鏡的血尿 | 見た目は正常だが、検査で赤血球が検出される状態。 | 健康診断などで指摘された場合、精密検査を受ける。 |
その他の排尿に関する症状
血尿以外にも、膀胱の刺激症状として現れることがあります。これらは膀胱炎の症状と似ているため、特に女性では見過ごされがちです。
- 頻尿(トイレが近い)
- 排尿時痛(おしっこをする時に痛む)
- 残尿感(おしっこをしてもスッキリしない)
- 尿意切迫感(急に強い尿意を感じ、我慢が難しい)
これらの症状が抗生物質を服用しても改善しない場合は、癌の可能性を考えて専門的な検査を進める必要があります。
また、腎盂や尿管の癌が進行し、尿の流れが妨げられると、背中や脇腹に痛み(水腎症による疼痛)が生じることもあります。
診断の進め方 – 尿細胞診から内視鏡検査まで
血尿などの症状から移行上皮癌が疑われる場合、確定診断のためにいくつかの検査を段階的に行います。これらの検査は、癌の有無だけでなく、その悪性度や広がりを正確に把握するために重要です。
初期に行う検査
まず、体に負担の少ない検査から始めます。尿検査では、尿中の赤血球や白血球の有無を確認します。そして、尿路上皮癌の診断で特徴的なのが「尿細胞診」です。
これは、尿の中に剥がれ落ちた癌細胞がないかを顕微鏡で調べる検査です。悪性度の高い(顔つきの悪い)癌細胞ほど剥がれやすいため、この検査で陽性となれば癌の存在を強く疑います。
同時に、腹部超音波(エコー)検査を行い、膀胱内に腫瘍がないか、あるいは腎臓が腫れていないか(水腎症)などを確認します。
診断のための主な検査
- 尿検査・尿細胞診
- 腹部超音波(エコー)検査
- 膀胱鏡検査(内視鏡)
- CT検査・MRI検査
確定診断のための膀胱鏡検査
尿細胞診や画像検査で癌が疑われた場合、確定診断のために「膀胱鏡検査」を行います。これは、尿道から細い内視鏡(カメラ)を挿入し、膀胱や尿道の内部を直接観察する検査です。
医師はモニターを通して、腫瘍の有無、大きさ、形状、数、発生場所などを詳細に確認します。最近では、柔らかく細い軟性膀胱鏡が普及し、検査に伴う苦痛は大幅に軽減されています。
検査中に疑わしい部分が見つかれば、その組織の一部を採取(生検)し、病理検査で癌細胞の有無や悪性度を確定させます。
癌の広がりを調べる画像診断
膀胱癌の診断が確定したら、次はその癌がどの程度深く広がっているか(深達度)、また腎盂や尿管、リンパ節、他の臓器への転移がないかを調べるために、CT検査やMRI検査といった画像診断を行います。
これらの検査は、治療方針を決定する上で極めて重要な情報(ステージ)を提供します。
治療方針の決定 – 筋層浸潤の有無による分岐点
移行上皮癌の治療は、癌の進行度、すなわち「ステージ」に基づいて決定します。特に、癌が膀胱の壁の筋層にまで達しているかどうかが、治療法を大きく左右する最も重要な分岐点となります。
筋層非浸潤癌と筋層浸潤癌
診断の過程で得られた情報をもとに、癌を「筋層非浸潤癌」と「筋層浸潤癌」に分類します。筋層非浸潤癌は、癌が膀胱の表面の粘膜またはその下の結合組織にとどまっている比較的早期の癌です。
一方、筋層浸潤癌は、癌が膀胱の壁を構成する筋層にまで食い込んでいる進行した癌です。筋層には多くの血管やリンパ管が存在するため、筋層浸潤癌は転移を起こしやすい危険な状態と考えます。
癌の深達度による分類
| 分類 | 癌の深さ(深達度) | 主な治療方針 |
|---|---|---|
| 筋層非浸潤癌 | 粘膜内にとどまる (Ta, Tis) or 粘膜下層まで (T1) | 経尿道的手術 (TURBT) + 膀胱内注入療法 |
| 筋層浸潤癌 | 筋層以上に浸潤 (T2以上) | 膀胱全摘除術 + 全身化学療法 |
ステージ分類(TNM分類)
癌の進行度を客観的に示すために、国際的な基準であるTNM分類を用いてステージを決定します。
これは、T(原発腫瘍の深達度)、N(リンパ節転移の有無)、M(遠隔転移の有無)の3つの要素を組み合わせて評価するものです。
このステージ評価に基づき、患者さん一人ひとりの状態に合わせた治療計画を立てます。
手術治療の選択肢 – 膀胱温存から全摘術まで
移行上皮癌の治療の根幹をなすのが手術です。癌のステージに応じて、内視鏡を用いた膀胱を温存する手術から、膀胱を完全に取り除く手術まで、様々な選択肢があります。
筋層非浸潤癌に対する経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TURBT)
筋層非浸潤癌に対しては、「経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)」が標準的な治療法です。これは、腰椎麻酔または全身麻酔のもと、尿道から内視鏡を挿入し、先端の電気メスで癌を削り取る手術です。
お腹を切る必要がなく、体への負担が少ないのが特徴です。この手術は、癌を治療すると同時に、切除した組織を病理検査に出して、癌の深達度や悪性度を正確に診断するという重要な目的も担っています。
筋層浸潤癌に対する膀胱全摘除術
癌が筋層まで浸潤している場合、TURBTだけでは癌を取り除くことが困難であり、転移のリスクも高いため、「膀胱全摘除術」が標準治療となります。
これは、膀胱を周囲のリンパ節とともに完全に取り除く大がかりな手術です。男性では前立腺と精嚢、女性では子宮や卵巣、膣の一部を同時に切除することがあります。
膀胱を摘出すると尿を溜める場所がなくなるため、尿の出口を新たに作成する「尿路変向術」を同時に行います。
代表的な尿路変向術
| 尿路変向術の種類 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 回腸導管 | 小腸の一部を利用して導管を作り、腹壁にストーマ(排泄口)を作成する。 | 最も一般的で管理が比較的容易。パウチを腹部に装着する。 |
| 自然排尿型新膀胱 | 小腸で袋状の新膀胱を作成し、尿道につなぎ直す。 | ストーマが不要で見た目が変わらない。腹圧をかけて排尿する。 |
腎盂・尿管癌の手術
腎盂や尿管に癌ができた場合は、「腎尿管全摘除術」が標準的な手術です。これは、癌のある側の腎臓と尿管、そして尿管が膀胱につながる部分までを一体として切除する手術です。
尿路上皮はつながっているため、部分的な切除では再発のリスクが高く、このように広範囲に切除することが重要です。
薬物療法の役割 – 免疫療法と化学療法の使い分け
手術と並行して、あるいは手術が困難な場合に、薬物療法が重要な役割を果たします。
薬物療法には、癌細胞を直接攻撃する「化学療法」と、自身の免疫力を利用して癌と戦う「免疫療法」があり、病状に応じて使い分けます。
筋層非浸潤癌の再発予防(BCG膀胱内注入療法)
筋層非浸潤癌は、TURBTで腫瘍を切除しても、膀胱内に再発しやすいという特徴があります。特に悪性度が高い場合や、多発している場合には、再発予防を目的として「BCG膀胱内注入療法」を行います。
これは、ウシの結核菌を弱毒化したBCGという薬剤を、カテーテルを使って直接膀胱内に注入する治療法です。
BCGが膀胱の粘膜で免疫反応を強力に引き起こし、その力で目に見えない癌細胞を排除します。これは免疫療法の一種です。
進行癌に対する全身化学療法
筋層浸潤癌や転移のある進行癌に対しては、点滴で抗がん剤を投与する「全身化学療法」が中心となります。シスプラチンという薬剤を含む複数の抗がん剤を組み合わせる治療法が標準です。
この化学療法は、膀胱全摘除術の前に行い、癌を小さくして手術の成績を向上させる目的(術前化学療法)や、手術後に行い、再発を予防する目的(術後化学療法)、あるいは手術ができない転移性癌の進行を抑える目的で行います。
主な薬物療法の対象と目的
| 治療法 | 主な対象 | 目的 |
|---|---|---|
| BCG膀胱内注入療法 | 高リスク筋層非浸潤癌 | TURBT後の再発予防 |
| 全身化学療法 | 筋層浸潤癌、転移性癌 | 手術前後の補助、延命、症状緩和 |
| 免疫チェックポイント阻害薬 | 化学療法後の進行癌など | 延命、症状緩和 |
新たな選択肢としての免疫チェックポイント阻害薬
近年、進行性の尿路上皮癌の治療に「免疫チェックポイント阻害薬」という新しいタイプの免疫療法が登場し、治療の選択肢が広がりました。
癌細胞は、免疫細胞の攻撃にブレーキをかけることで生き延びています。この薬は、そのブレーキを解除し、免疫細胞が再び癌細胞を攻撃できるようにする働きを持ちます。
主に、化学療法が効かなくなった、あるいは副作用で続けられない進行癌の患者さんに使用します。
移行上皮癌(膀胱がん)の5年相対生存率(目安)
ステージI(筋層非浸潤): 90%以上
- ※早期発見できれば予後は非常に良好ですが、再発しやすいため定期検査が重要です。
ステージII(筋層浸潤・転移なし): 60〜70%前後
ステージIII(隣接臓器浸潤): 40〜50%前後
ステージIV(遠隔転移あり): 10〜20%未満
治療後の生活管理 – 再発がんの監視体制
移行上皮癌は、治療が終わった後も再発のリスクがあるため、長期にわたる定期的な検査と自己管理が非常に重要です。特に膀胱を温存した場合は、膀胱内の再発を入念に監視する必要があります。
定期的なフォローアップ検査
治療後の経過観察は、癌のステージや治療法によって異なりますが、一般的には定期的に泌尿器科を受診し、複数の検査を組み合わせて行います。
膀胱内再発のチェックには、膀胱鏡検査と尿細胞診が最も重要です。腎盂や尿管からの再発や、遠隔転移の有無を確認するために、定期的にCT検査も行います。
治療後の定期検査スケジュール(一例)
- 膀胱鏡検査・尿細胞診:治療後2年間は3~6ヶ月ごと、その後は1年ごと
- CT検査:6ヶ月~1年ごと
このスケジュールはあくまで一例であり、個々の患者さんのリスクに応じて医師が判断します。
指示された間隔で検査を受け続けることが、万が一の再発を早期に発見し、速やかに次の治療につなげるために大切です。
自己管理と生活上の注意点
日常生活においては、禁煙を継続することが最も重要です。喫煙は再発のリスクを高めるだけでなく、二次がん(別の種類の癌)の発生リスクも高めます。
また、水分を十分に摂取し、尿量を保つことも、尿路への刺激を減らす上で良いとされています。
そして何よりも、再び血尿が出た場合や、排尿に関する新たな症状が現れた場合には、次の予約を待たずに速やかに主治医に相談することが大切です。
よくある質問
- 血尿が出たら必ず癌なのでしょうか?
-
いいえ、必ずしも癌とは限りません。血尿の原因で最も多いのは膀胱炎や尿路結石、腎臓の病気などです。
しかし、特に痛みを伴わない血尿は移行上皮癌(尿路上皮癌)の重要なサインである可能性があるため、自己判断せずに必ず泌尿器科で詳しい検査を受けることが重要です。
原因を正確に診断し、適切な治療につなげます。
- 家族に膀胱癌の人がいると遺伝しますか?
-
尿路上皮癌の多くは、喫煙や化学物質への曝露といった後天的な原因で発生し、明確な遺伝性が認められるケースは稀です。
ただし、一部の遺伝性疾患(リンチ症候群など)では尿路上皮癌のリスクが高まることが知られています。
ご家族に癌の既往歴を持つ方が多いなど、心配な点があれば主治医に相談してください。
- 膀胱を全部取った後、排尿はどうなるのですか?
-
膀胱全摘除術の際には、尿の出口を作り直す「尿路変向術」を同時に行います。小腸を使ってお腹にストーマ(排泄口)を作り、そこにパウチを貼って尿を溜める「回腸導管」が一般的です。
また、条件が合えば、小腸で新しい膀胱(新膀胱)を作り、元の尿道につなぎ直して、これまで通り尿道から排尿する方法もあります。
どちらの方法にも長所と短所があるため、手術前に医師とよく相談して決定します。
尿路上皮から発生する癌には、移行上皮癌以外にも稀なタイプのものが存在します。
小細胞癌や未分化癌、神経内分泌腫瘍などは、発生頻度は低いものの、移行上皮癌とは異なる性質を持ち、診断や治療のアプローチも特有です。
これらの稀な上皮性腫瘍について理解を深めたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
参考文献
HO, Philip L.; WILLIAMS, Stephen B.; KAMAT, Ashish M. Immune therapies in non-muscle invasive bladder cancer. Current treatment options in oncology, 2015, 16: 1-19.
PFAIL, John L., et al. Immunotherapy in non-muscle-invasive bladder cancer: current status and future directions. World Journal of Urology, 2021, 39: 1319-1329.
DOYLE, Emma, et al. Urothelial cancer: a narrative review of the role of novel immunotherapeutic agents with particular reference to the management of non‐muscle‐invasive disease. BJU international, 2019, 123.6: 947-958.
BARONE, Biagio, et al. Immune checkpoint inhibitors as a neoadjuvant/adjuvant treatment of muscle-invasive bladder cancer: a systematic review. Cancers, 2022, 14.10: 2545.
PEYROTTES, Arthur, et al. Neoadjuvant immunotherapy for muscle-invasive bladder cancer. Medicina, 2021, 57.8: 769.
PANE, Katia, et al. New roadmaps for non-muscle-invasive bladder cancer with unfavorable prognosis. Frontiers in Chemistry, 2020, 8: 600.
FUNT, Samuel A.; ROSENBERG, Jonathan E. Systemic, perioperative management of muscle-invasive bladder cancer and future horizons. Nature reviews Clinical oncology, 2017, 14.4: 221-234.
LEE, Hyung Ho; HAM, Won Sik. Perioperative immunotherapy in muscle-invasive bladder cancer. Translational Cancer Research, 2020, 9.10: 6546.
VALENZA, Carmine, et al. Emerging treatment landscape of non-muscle invasive bladder cancer. Expert Opinion on Biological Therapy, 2022, 22.6: 717-734.
MORI, Keiichiro, et al. Impact of sex on outcomes after surgery for non-muscle-invasive and muscle-invasive bladder urothelial carcinoma: a systematic review and meta-analysis. World journal of urology, 2023, 41.4: 909-919.
上皮性腫瘍(癌腫)に戻る