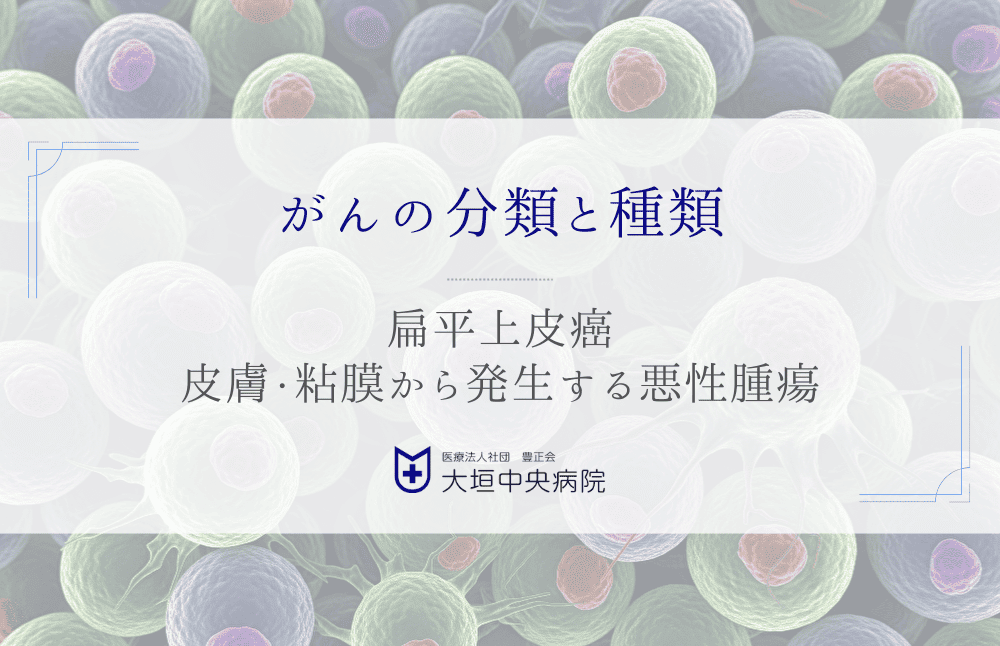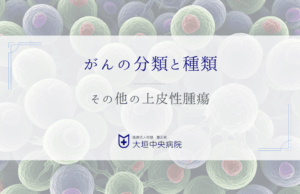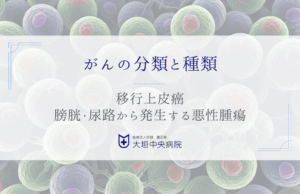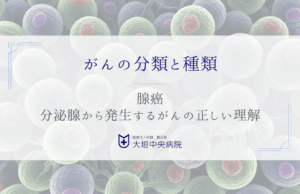「扁平上皮癌」という診断を受け、不安や多くの疑問を抱えているかもしれません。
このがんは、皮膚や体の様々な器官の表面を覆う「扁平上皮」という細胞から発生する悪性腫瘍です。発生する場所によって性質が大きく異なるため、正しい知識を持つことが治療への第一歩となります。
この記事では、扁平上皮癌の基礎から原因、症状、診断、そして治療法に至るまで、患者さんとご家族が知っておくべき情報を詳しく解説します。
扁平上皮癌とは何か – 発生部位と特徴
扁平上皮癌を理解するためには、まず、このがんが特定の「臓器」のがんではなく、細胞の「種類」に基づく分類名であることを知るのが重要です。
私たちの体を覆う皮膚や、口から食道、気管、子宮頸部といった管状の臓器の内壁は、「扁平上皮」と呼ばれる薄く平たい細胞でできています。
この細胞ががん化したものが、発生場所にかかわらず「扁平上皮癌」と呼ばれます。そのため、一口に扁平上皮癌といっても、その性質は発生部位によって大きく異なります。
扁平上皮細胞の役割とがん化
扁平上皮細胞は、外部の刺激や異物から体を守るバリアとしての重要な役割を担います。常に新しい細胞と入れ替わることで、その機能を維持しています。
しかし、紫外線やタバコの煙に含まれる化学物質などの長期間にわたる刺激で細胞の遺伝子に傷がつくと、細胞増殖のコントロールが失われ、がん化することがあります。
これが扁平上皮癌の始まりです。
主な発生部位とその特性
扁平上皮癌は、扁平上皮が存在する体のあらゆる部分に発生する可能性があります。特に発生頻度の高い部位と、それぞれの特徴を理解することが、疾患の全体像を掴む上で役立ちます。
皮膚に発生する扁平上皮癌
皮膚にできる扁平上皮癌は、日光(紫外線)に当たりやすい顔、頭部、首、手の甲などに好発します。
初期は赤みを帯びた湿疹や、治りにくいかさぶたのように見えることもあり、進行すると硬いしこりや潰瘍を形成します。皮膚がんの中では、基底細胞癌に次いで多く見られます。
肺に発生する扁平上皮癌
肺がんの一種である肺扁平上皮癌は、肺がん全体の約25~30%を占めます。主に肺の中心部、太い気管支に発生しやすいという特徴があります。
長年の喫煙習慣との関連が非常に強く、咳や血痰といった症状で発見されることが多いです。
その他の主な発生部位
食道、子宮頸部、そして口腔・咽頭・喉頭といった頭頸部も扁平上皮癌の好発部位です。食道がんでは、日本では約90%が扁平上皮癌です。
子宮頸がんもその多くが扁平上皮癌であり、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が主な原因として知られています。
発生部位による特徴の違い
| 発生部位 | 主な原因 | 特徴的な初期症状 |
|---|---|---|
| 皮膚 | 紫外線、慢性的な刺激 | 治りにくい赤み、しこり、潰瘍 |
| 肺 | 喫煙、大気汚染 | 長引く咳、血痰、胸の痛み |
| 子宮頸部 | ヒトパピローマウイルス(HPV) | 不正出血、おりものの異常 |
| 食道 | 喫煙、飲酒 | 食べ物のつかえ感、体重減少 |
| 頭頸部(口腔など) | 喫煙、飲酒 | 治らない口内炎、しこり |
扁平上皮がんの原因 – 紫外線と喫煙の影響
扁平上皮癌の発生には、生活習慣や環境に潜む様々な危険因子が深く関わっています。これらの原因を知ることは、がんの予防だけでなく、ご自身の状況を客観的に理解するためにも重要です。
特に「紫外線」と「喫煙」は、二大リスク因子として知られています。
がん発生の根本的な原因
がんの直接的な原因は、細胞の設計図であるDNAに傷がつくことです。扁平上皮細胞が、後述するような様々な発がん物質に長期間さらされると、DNAに異常が蓄積します。
その結果、細胞が無秩序に増殖を始め、がんとなります。
紫外線が皮膚に与える影響
皮膚扁平上皮癌の最大の原因は、太陽光に含まれる紫外線(UV)です。長年にわたり紫外線を浴び続けることで、皮膚の扁平上皮細胞のDNAが直接損傷を受けます。
特に、子供の頃に日焼けで水ぶくれを作った経験や、屋外での仕事、レジャーなどで日光を浴びる機会が多い人は、リスクが高まります。
喫煙が肺や食道に及ぼす危険性
喫煙は、肺扁平上皮癌の最も重要な原因です。タバコの煙には70種類以上の発がん性物質が含まれており、これらが気管支の粘膜を常に刺激し、がん化を引き起こします。
喫煙年数が長く、本数が多いほどリスクは高まります。また、食道がんや頭頸部がんにおいても、喫煙は飲酒と並ぶ主要な原因です。
主なリスク因子とその関連部位
| リスク因子 | 主な関連部位 | 概要 |
|---|---|---|
| 紫外線 | 皮膚 | 日光への長期的な曝露が細胞のDNAを傷つける。 |
| 喫煙 | 肺、食道、頭頸部 | タバコの煙に含まれる化学物質が粘膜を傷つける。 |
| ヒトパピローマウイルス(HPV) | 子宮頸部、中咽頭 | ウイルスの持続的な感染が細胞をがん化させる。 |
| 飲酒 | 食道、頭頸部 | 特に喫煙と合わさるとリスクが著しく増大する。 |
| 慢性的な炎症や傷跡 | 皮膚、口腔 | 長期間の刺激ががん化の引き金になることがある。 |
症状の見分け方 – 見逃してはいけない初期サイン
扁平上皮癌は、発生した部位によって様々な症状を示します。体の変化にいち早く気づき、早期に医療機関を受診することが、その後の治療結果に大きく影響します。
ここでは、見逃してはならない初期症状について、部位ごとに解説します。
皮膚に現れる初期症状
皮膚の扁平上皮癌は、見た目の変化として現れるため、比較的気づきやすいがんの一つです。しかし、湿疹やイボと見間違えることも少なくありません。
- 赤みを帯びた、表面がカサカサした斑点
- 数ヶ月以上治らない、じくじくしたびらんや潰瘍
- イボのように盛り上がり、硬くなるしこり
- 出血しやすい、かさぶたが取れやすいできもの
これらの変化が、特に日光の当たりやすい顔、耳、唇、手の甲に見られた場合は注意が必要です。
肺扁平上皮癌の警戒すべき症状
肺の扁平上皮癌は、風邪の症状と似ているため発見が遅れることがあります。特に喫煙者の方で、以下のような症状が2週間以上続く場合は、呼吸器内科の受診を検討してください。
肺がんの主な初期症状
| 症状 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 長引く咳 | 市販の薬を飲んでも改善しない、空咳や痰が絡む咳。 |
| 血痰 | 痰に血が混じる、あるいは錆び色の痰が出る。 |
| 胸の痛み・息切れ | 深呼吸や咳をした時の痛み、階段を上るだけで息が切れる。 |
| 声のかすれ(嗄声) | がんが声帯を調節する神経に影響を及ぼして起こる。 |
口腔・食道・子宮頸がんの初期症状
口腔内では「2週間以上治らない口内炎」が重要なサインです。粘膜が白くなったり(白板症)、赤くなったり(紅板症)する変化も前がん病変の可能性があります。
食道がんでは、熱いものがしみる、食べ物がつかえるといった嚥下時の違和感が初期症状として現れます。子宮頸がんでは、月経以外の出血(不正出血)や性交渉後の出血、普段と違うおりものなどが特徴です。
診断方法 – 組織検査から画像診断まで
気になる症状があって医療機関を受診すると、がんの有無、種類、進行度を正確に調べるために、いくつかの検査を行います。
診断を確定し、適切な治療方針を立てるためには、これらの検査結果を総合的に判断することが重要です。
確定診断に不可欠な組織検査(生検)
がんの診断を確定する上で最も重要な検査が「生検」です。これは、疑わしい部分の組織を少量採取し、顕微鏡で詳しく調べる病理組織診断です。
この検査によって、細胞が本当にがん細胞であるか、また、扁平上皮癌であるかといった「顔つき」を確定します。皮膚であれば一部を切り取り、肺や食道であれば内視鏡を使って組織を採取します。
がんの広がりを調べる画像診断
がんの診断が確定したら、次にがんがどのくらい広がっているか(ステージ)を評価するために画像診断を行います。これにより、治療方針が決まります。
主な画像診断検査
| 検査名 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| CT検査 | 腫瘍の大きさ、周囲臓器への広がり、リンパ節への転移の評価 | X線を使って体の断面を撮影する。詳細な形態を把握できる。 |
| MRI検査 | 特に頭頸部や骨盤内の詳細な評価 | 磁気を利用して撮影する。軟部組織の描出に優れる。 |
| PET-CT検査 | 全身への遠隔転移の有無を調べる | がん細胞がブドウ糖を多く取り込む性質を利用し、全身のがんの活動部位を検出する。 |
腫瘍マーカーの役割
血液検査で測定する腫瘍マーカーは、診断の補助や、治療効果の判定、再発のモニタリングに用いられます。扁平上皮癌では、SCC抗原やCYFRA21-1(シフラ)などが参考にされます。
ただし、腫瘍マーカーの値はがんでなくても上昇することがあり、逆にがんがあっても正常値のこともあるため、これだけでがんの有無を診断することはできません。
治療選択肢 – 手術・放射線・薬物療法の適応
扁平上皮癌の治療は、がんの発生部位、ステージ(進行度)、組織型、そして患者さん自身の全身状態や年齢、希望などを総合的に考慮して決定します。
治療の三大柱は「手術」「放射線治療」「薬物療法」であり、これらを単独、あるいは組み合わせて治療を進めます。
根治を目指す中心的な治療法 手術
がんが原発巣に限局している早期の段階では、手術によるがん組織の完全な切除が最も根治を期待できる治療法です。
がん細胞を残さないように、腫瘍とその周囲の正常な組織をある程度の範囲で一緒に切除します。リンパ節への転移の可能性がある場合は、周辺のリンパ節も同時に切除(リンパ節郭清)することがあります。
体を切らずにがんを叩く 放射線治療
放射線治療は、高エネルギーのX線などをがんに照射して、がん細胞を破壊する治療法です。手術が困難な部位のがんや、高齢などで手術が難しい場合に選択されます。
また、手術後の再発予防や、骨への転移による痛みを和らげる目的でも行います。
全身に広がるがん細胞と闘う 薬物療法
薬物療法は、抗がん剤や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬などを用いて、全身に散らばった可能性のあるがん細胞を攻撃する治療法です。
進行・再発した場合や、手術や放射線治療の効果を高めるために補助的に用いることがあります。
三大治療法の比較
| 治療法 | 適応 | 特徴 |
|---|---|---|
| 手術 | 早期の限局がんが中心 | 根治性が高いが、臓器の機能や形態が損なわれることがある。 |
| 放射線治療 | 手術困難例、術後補助、症状緩和 | 臓器の機能を温存しやすいが、治療期間が長く、副作用もある。 |
| 薬物療法 | 進行・再発がん、術前・術後補助 | 全身のがん細胞に効果が期待できるが、全身的な副作用が出やすい。 |
進行度による治療戦略 – ステージ別アプローチ
扁平上皮癌の治療方針を決定する上で最も重要な指標が「ステージ(病期)」です。
ステージは、がんの大きさ(T)、リンパ節への転移の有無(N)、他の臓器への遠隔転移の有無(M)を組み合わせたTNM分類によって、Ⅰ期(早期)からⅣ期(進行期)までに分類されます。
ステージに応じた適切な治療戦略を立てることが、より良い治療成績に繋がります。
早期ステージ(Ⅰ期・Ⅱ期)の治療
がんが原発巣にとどまっているか、ごく近くのリンパ節にわずかに広がっている程度の早期ステージでは、根治を目指した局所治療が中心となります。第一選択は手術で、がんを完全に取り除くことを目指します。
部位や状態によっては放射線治療が選択されることもあります。この段階で発見・治療できれば、生存率も高く、完治する可能性は十分にあります。
局所進行ステージ(Ⅲ期)の治療
がんが原発巣の周囲の組織や、広範囲のリンパ節にまで広がっているステージです。
この段階では、一つの治療法だけでは不十分なことが多く、手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせた「集学的治療」を行います。
例えば、手術の前に薬物療法でがんを小さくしたり、手術後に再発を防ぐ目的で放射線治療や薬物療法を追加したりします。
遠隔転移のあるステージ(Ⅳ期)の治療
がんが肺や肝臓、骨など、最初に発生した場所から離れた臓器に転移しているステージです。
この段階では、がんを完全に治すことは困難な場合が多く、治療の目的は、がんの進行を抑え、症状を和らげ、できるだけ長く、より良い生活の質(QOL)を維持することに置かれます。
薬物療法が治療の中心となり、免疫チェックポイント阻害薬などが有力な選択肢となります。
ステージ別の一般的な治療方針と生存率の目安
| ステージ | 主な治療方針 | 5年相対生存率の傾向 |
|---|---|---|
| Ⅰ期 | 手術または放射線治療(単独) | 高い |
| Ⅱ期・Ⅲ期 | 手術、放射線治療、薬物療法の組み合わせ | 中程度 |
| Ⅳ期 | 薬物療法が中心(症状緩和も目的) | 低い |
主な部位別の5年相対生存率(目安)
扁平上皮癌は発生部位によって予後が異なります。
皮膚: 早期発見できれば90%以上と非常に良好ですが、深部に及ぶとリスクが高まります。
肺(非小細胞肺癌):
- ステージI:80%前後
- ステージII:50〜60%前後
- ステージIII:20〜30%前後
- ステージIV:10%未満
食道:
- ステージI:80%前後
- ステージII:50〜60%前後
- ステージIII:30〜40%前後
- ステージIV:10〜20%未満
注:生存率はあくまで統計データであり、がんの部位や個人の状態によって大きく異なります。
がん予防のための生活習慣 – リスク軽減の実践法
扁平上皮癌のリスク因子には、日々の生活習慣が大きく関わっています。がんの発生を100%防ぐことはできませんが、リスクを減らすために今日から実践できることがあります。
ご自身の健康を守るために、生活習慣を見直してみましょう。
紫外線対策の徹底
皮膚扁平上皮癌の予防には、紫外線対策が最も効果的です。特に日差しの強い時間帯(午前10時~午後2時頃)の外出を避けたり、外出時には以下の対策を心がけたりすることが大切です。
- 日焼け止めの使用(SPF30、PA++以上を推奨)
- つばの広い帽子やサングラスの着用
- 長袖、長ズボンなど、肌の露出が少ない衣服の選択
禁煙の重要性
禁煙は、肺扁平上皮癌や食道がん、頭頸部がんの最も確実な予防法です。タバコをやめれば、その時点からがんのリスクは下がり始めます。
自力での禁煙が難しい場合は、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることも有効な手段です。受動喫煙もリスクを高めるため、周囲の人のためにも禁煙は重要です。
その他の予防策
節度ある飲酒を心がけること、バランスの取れた食事を摂ること、そして子宮頸がんの原因となるHPVの感染を防ぐHPVワクチンの接種(特に若年層)も、特定部位の扁平上皮癌の予防に繋がります。
また、定期的にがん検診を受けることで、万が一がんが発生しても早期に発見できます。
治療後の経過観察 – 再発がんの早期発見
がんの治療が無事に終了した後も、再発や新たな二次がんの発生がないかを確認するために、定期的な通院と検査(経過観察)が必要です。
治療後の生活を安心して送るためにも、経過観察は非常に重要な役割を果たします。
定期的な検査の目的と内容
経過観察の目的は、局所再発(元の場所での再発)、リンパ節転移、遠隔転移を早期に発見することです。
検査の頻度や内容は、がんの部位やステージによって異なりますが、一般的には問診、診察、血液検査(腫瘍マーカー)、CTなどの画像検査を組み合わせて行います。
経過観察スケジュールの例(肺がん術後)
| 期間 | 頻度 | 主な検査内容 |
|---|---|---|
| 術後~2年 | 3~6ヶ月ごと | 問診、診察、胸部CT、腫瘍マーカー |
| 術後3~5年 | 6~12ヶ月ごと | 問診、診察、胸部CT |
| 術後6年以降 | 年1回 | 問診、診察、胸部X線など |
注:これはあくまで一例であり、担当医の指示に従ってください。
セルフチェックと体調管理
定期検査と合わせて、ご自身で体調の変化に気を配ることも大切です。
治療した部位のしこりや痛み、長引く咳、原因不明の体重減少など、何か気になる症状が現れた場合は、次の予約を待たずに速やかに担当医に相談してください。
禁煙の継続やバランスの取れた食事、適度な運動など、健康的な生活を維持することも、再発予防に繋がります。
患者・家族が知るべき重要事項 – 医療機関選択のポイント
がんと診断されたとき、どの医療機関で治療を受けるかは、患者さんとご家族にとって非常に重要な決断です。
納得のいく治療を受けるためには、情報収集を行い、信頼できる医療チームを見つけることが大切です。
専門性と治療実績の確認
扁平上皮癌は発生部位が多岐にわたるため、治療にはそれぞれの分野の専門知識が必要です。
例えば、肺がんであれば呼吸器外科や呼吸器内科、皮膚がんであれば皮膚科や形成外科といった、その領域の専門医が在籍し、治療経験が豊富な病院を選ぶことが一つの目安になります。
病院のウェブサイトで診療科の紹介や治療実績を確認したり、がん診療連携拠点病院などの情報を参考にしたりするのも良いでしょう。
セカンドオピニオンの活用
担当医から提示された診断や治療方針について、他の専門医の意見を聞く「セカンドオピニオン」は、患者さんの権利です。
別の医師の意見を聞くことで、現在の診断や治療法への理解が深まったり、他の治療選択肢を知ることができたりします。
納得して治療に臨むために、セカンドオピニオンを積極的に活用することを検討してください。
チーム医療とサポート体制
がん治療は、医師だけでなく、看護師、薬剤師、放射線技師、ソーシャルワーカーなど、多くの専門職が関わる「チーム医療」で進められます。
また、治療に伴う身体的・精神的な苦痛を和らげる緩和ケアチームや、医療費や生活に関する相談ができるがん相談支援センターの有無も、病院を選ぶ上で重要なポイントです。
よくある質問
扁平上皮癌に関して、患者さんやご家族からよく寄せられる質問にお答えします。
- 扁平上皮癌は遺伝しますか?
-
ほとんどの扁平上皮癌は、紫外線や喫煙といった後天的な要因で発生するものであり、直接的に親から子へ遺伝することは稀です。
ただし、色素性乾皮症のように、遺伝的に皮膚がんを発症しやすい体質(遺伝性疾患)も存在します。
血縁者にがんになった人が多いなど、ご心配な点があれば担当医に相談してみましょう。
- 治療中の食事で気をつけることはありますか?
-
治療中は、副作用で食欲が低下したり、口内炎で食べにくくなったりすることがあります。基本的には、食べられるものを無理のない範囲で食べることが大切です。
特定の食品ががんに良い・悪いといった科学的根拠の乏しい情報に惑わされず、栄養バランスを考えた食事を心がけましょう。
食事に関する悩みは、管理栄養士に相談することもできます。
- 生存率の数字はどのように解釈すればよいですか?
-
生存率は、同じがんと診断された多くの人々のデータを集計した統計的な指標であり、個人の余命を予測するものではありません。
あくまで治療方針を考える上での参考情報の一つと捉えることが大切です。近年は新しい治療薬の登場により、治療成績は年々向上しています。
数字に一喜一憂せず、ご自身の治療に前向きに取り組むことが重要です。
尿路(腎盂、尿管、膀胱)に発生するがんに「移行上皮癌(尿路上皮癌)」があります。これは扁平上皮癌とは異なる種類の細胞から発生するがんで、血尿などの症状で発見されることが多いです。
特に膀胱に好発し、喫煙が大きなリスク因子であることが知られています。移行上皮癌について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
参考文献
ANDRUCHOW, Jennifer L., et al. Implications for clinical staging of metastatic cutaneous squamous carcinoma of the head and neck based on a multicenter study of treatment outcomes. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society, 2006, 106.5: 1078-1083.
QUE, Syril Keena T.; ZWALD, Fiona O.; SCHMULTS, Chrysalyne D. Cutaneous squamous cell carcinoma: Management of advanced and high-stage tumors. Journal of the American Academy of Dermatology, 2018, 78.2: 249-261.
CLAVEAU, J., et al. Multidisciplinary management of locally advanced and metastatic cutaneous squamous cell carcinoma. Current Oncology, 2020, 27.4: e399.
ODDONE, Nicolas, et al. Metastatic cutaneous squamous cell carcinoma of the head and neck: the Immunosuppression, Treatment, Extranodal spread, and Margin status (ITEM) prognostic score to predict outcome and the need to improve survival. Cancer, 2009, 115.9: 1883-1891.
LEEMAN, Jonathan E., et al. Patterns of treatment failure and postrecurrence outcomes among patients with locally advanced head and neck squamous cell carcinoma after chemoradiotherapy using modern radiation techniques. JAMA oncology, 2017, 3.11: 1487-1494.
MAUBEC, Eve. Update on the management of cutaneous squamous cell carcinoma. Acta Dermato-Venereologica, 2020, 100.11: 5753.
QUE, Syril Keena T.; ZWALD, Fiona O.; SCHMULTS, Chrysalyne D. Cutaneous squamous cell carcinoma: Incidence, risk factors, diagnosis, and staging. Journal of the American Academy of Dermatology, 2018, 78.2: 237-247.
SACCO, Assuntina G.; COHEN, Ezra E. Current treatment options for recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma. Journal of clinical oncology, 2015, 33.29: 3305-3313.
ARGIRIS, Athanassios, et al. Evidence-based treatment options in recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. Frontiers in oncology, 2017, 7: 72.
LUBOV, Joshua, et al. Prognostic factors of head and neck cutaneous squamous cell carcinoma: a systematic review. Journal of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 2021, 50.1: 54.
上皮性腫瘍(癌腫)に戻る