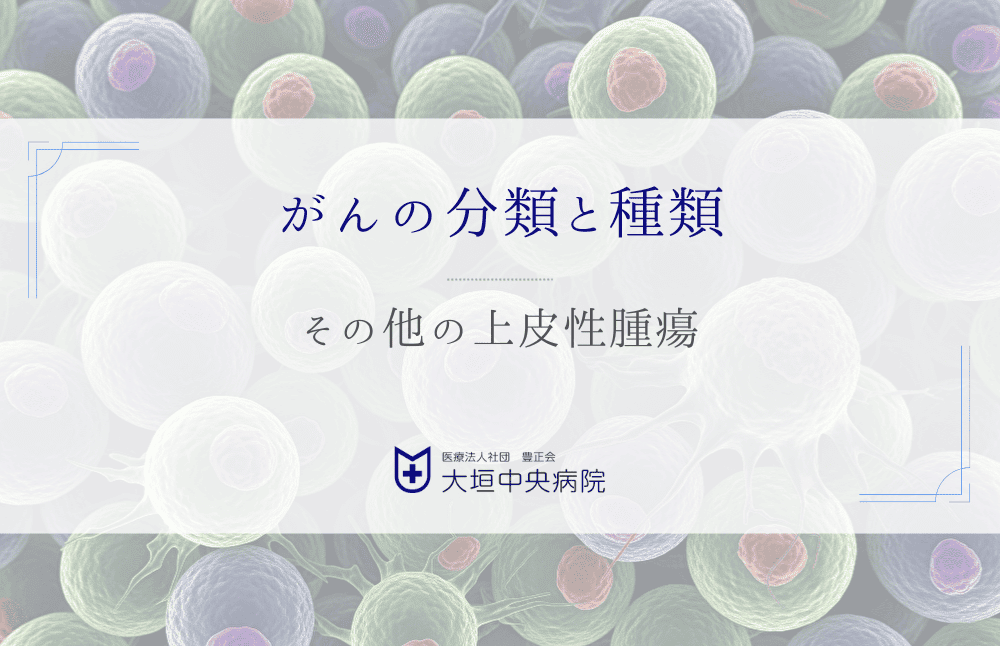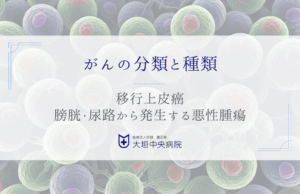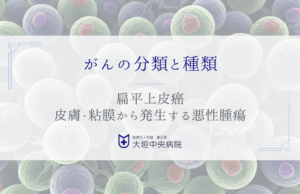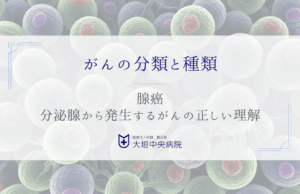がんと診断されたとき、多くの方が耳にするのは「腺癌」や「扁平上皮癌」といった比較的頻度の高い種類です。
しかし、がんの世界は非常に多様で、これらには分類されない「その他の上皮性腫瘍」と呼ばれる一群が存在します。
これらには小細胞癌、未分化癌、神経内分泌腫瘍などが含まれ、その多くが「希少がん」として扱われます。
これらの腫瘍は発生頻度が低く、進行が速い、あるいは診断が難しいといった特徴を持つため、患者さんやご家族は情報の少なさに戸惑うことがあるかもしれません。
この記事では、これらの特殊な腫瘍の全体像を捉え、その特徴、診断、治療法について、できる限り分かりやすく解説します。
その他の上皮性腫瘍とは何か – 特殊な組織型の特徴
私たちの体を構成する細胞の一つである「上皮細胞」から発生する悪性腫瘍を「上皮性腫瘍」、一般に「癌(がん)」と呼びます。
この上皮性腫瘍は、組織の形(組織型)によって、主に腺管構造をつくる「腺癌」や、重層扁平上皮に似た構造を示す「扁平上皮癌」などに分類します。
しかし、中にはこれらの典型的な分類に当てはまらない、特殊な性質を持つ腫瘍群が存在し、それらを総称して「その他の上皮性腫瘍」と呼ぶことがあります。
これらは発生頻度が低く、診断や治療に専門的な知識を要するため、しばしば「希少がん」として扱われます。
上皮性腫瘍の分類と「その他」の位置づけ
がんの分類は、治療方針を決定する上で非常に重要です。病理医が顕微鏡でがん組織を観察し(病理診断)、その顔つきから種類を特定します。
しかし、小細胞癌のように細胞が非常に小さい、あるいは未分化癌のように細胞が成熟した組織の特徴を全く示さない場合、一般的な分類が困難になります。
これらの腫瘍は、発生した臓器に関わらず、共通した生物学的な特徴や臨床的な経過を示すことがあります。
主な上皮性腫瘍の分類
| 分類 | 主な特徴 | 代表的な発生臓器 |
|---|---|---|
| 腺癌 | 分泌腺の細胞に似ており、腺管構造をつくる。 | 肺、胃、大腸、乳房、前立腺 |
| 扁平上皮癌 | 皮膚や粘膜の表面を覆う細胞に似ている。 | 肺、食道、子宮頸部、皮膚 |
| その他 | 上記に分類されない特殊な組織型を示す。 | 肺、甲状腺、皮膚、全身の様々な臓器 |
希少がんとしての側面
国立がん研究センターによると、「希少がん」とは「人口10万人あたりの年間発生数が6例未満の稀ながん」と定義されます。その他の上皮性腫瘍に分類されるものの多くは、この定義に当てはまります。
例えば、皮膚に発生するメルケル細胞がんや皮膚付属器がん(汗腺がんなど)、胸部に発生する胸腺腫なども、広い意味でこのカテゴリーに含まれる希少ながんです。
希少がんは症例数が少ないため、診断経験のある医師や治療法に関する情報が限られやすいという課題があります。
小細胞癌の実態 – 急速進行する悪性度の高いがん
小細胞癌は、「その他の上皮性腫瘍」の中でも特に悪性度が高く、進行が非常に速いことで知られるがんです。
最も多く発生するのは肺ですが、食道、膀胱、前立腺、子宮頸部など、全身のあらゆる臓器に発生する可能性があり、「肺外小細胞癌」と呼ばれます。
その名の通り、がん細胞が非常に小さいことが組織学的な特徴です。
小細胞癌の主な発生部位と症状
肺に発生する小細胞肺癌が全体の大多数を占めます。主な原因は喫煙と深く関連しています。
症状としては、持続する咳、血痰、胸の痛み、息切れなどが現れますが、進行が速いため、診断されたときには既に他の臓器へ転移していることも少なくありません。
また、ホルモンに似た物質を産生することがあり、本来のがんの症状とは異なる「腫瘍随伴症候群」と呼ばれる特有の症状(例えば、低ナトリウム血症による意識障害など)を引き起こすことがあります。
進行速度と転移のしやすさ
小細胞癌の最大の特徴は、その増殖スピードの速さです。がん細胞が分裂する周期が非常に短く、あっという間に大きくなります。
また、早い段階から血液やリンパの流れに乗って、脳、肝臓、骨、副腎など全身に転移しやすい性質を持っています。
そのため、診断時には手術が困難な「進展型」として見つかることが多く、治療は化学療法(抗がん剤)が中心となります。
小細胞癌の病期分類
| 病期 | 状態 | 主な治療方針 |
|---|---|---|
| 限局型 (LD) | がんが片側の胸の中にとどまっている状態。 | 化学療法と放射線治療の同時併用 |
| 進展型 (ED) | がんが反対側の胸や他の臓器に広がっている状態。 | 化学療法、免疫チェックポイント阻害薬 |
未分化癌の特徴 – 組織診断が困難な特殊ながん
未分化癌は、がん細胞が成熟した細胞の姿を失い、何の細胞から発生したのか起源を特定するのが非常に困難な、特殊ながんの一群です。
細胞の「分化」とは、細胞が特定の役割を持つように成熟していく過程を指しますが、「未分化」はその逆で、非常に原始的な状態にあることを意味します。
このため、極めて悪性度が高く、急速に進行する傾向があります。
「未分化」とは何を意味するのか
正常な細胞は、例えば胃の粘膜細胞なら消化液を出す、皮膚の細胞なら体を保護するといった、決まった役割を持っています。これは細胞が十分に「分化」している証拠です。
がん細胞は、この分化の度合いが低いほど、無秩序に増殖する性質が強くなります。
未分化癌は、この分化度が最も低い状態で、顕微鏡で見ても腺癌なのか扁平上皮癌なのか、あるいは肉腫など他のがんなのかさえ区別がつかないことがあります。
診断における課題
未分化癌の診断は、病理医にとっても挑戦的なものです。まず、腫瘍の一部を採取する「生検」を行い、組織を詳しく調べます。
しかし、前述の通り細胞の起源が分からないため、確定診断のために「免疫組織化学染色(免疫染色)」という特殊な検査を追加します。
これは、細胞が持つ特有のタンパク質(マーカー)を染め分けることで、細胞の正体を探る手がかりを得る検査です。この検査によって、他のがんとの鑑別を行います。
代表的な未分化癌
- 甲状腺未分化癌
- 膵未分化癌
- 胃未分化癌
甲状腺未分化癌とその他の未分化癌
未分化癌の代表例として、甲状腺未分化癌が挙げられます。これは甲状腺がんの中でも最も悪性度が高く、診断後の進行が極めて速いことで知られています。
首の急激な腫れや痛み、声のかすれ、呼吸困難などの症状で気づかれることが多いです。他の臓器に発生する未分化癌も、同様に進行が速く、予後が厳しい傾向にあります。
治療は、手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせた集学的なアプローチが必要です。
神経内分泌腫瘍の分類 – 機能性と非機能性の違い
神経内分泌腫瘍(Neuroendocrine Neoplasm: NEN)は、神経系の細胞と内分泌(ホルモン産生)系の細胞の両方の特徴を併せ持つ「神経内分泌細胞」から発生する腫瘍の総称です。
この細胞は全身の様々な臓器に存在するため、神経内分泌腫瘍も消化器(膵臓、消化管)や肺を中心に、全身どこにでも発生する可能性があります。
近年、診断技術の向上により発見されるケースが増えています。
機能性NETとホルモン過剰産生による症状
神経内分泌腫瘍の一部は、ホルモンを過剰に作り出す性質を持っており、これを「機能性」と呼びます。産生するホルモンの種類によって、体に様々な症状が現れます。
例えば、インスリンを過剰に産生すれば低血糖発作を、ガストリンなら難治性の胃潰瘍を、セロトニンなら下痢や顔面紅潮といった特徴的な症状(カルチノイド症候群)を引き起こします。
これらの症状が、がん発見のきっかけとなることもあります。
機能性NETによる代表的な症状
| 産生ホルモン | 関連する腫瘍名 | 主な症状 |
|---|---|---|
| インスリン | インスリノーマ | 低血糖症状(冷や汗、動悸、意識障害) |
| ガストリン | ガストリノーマ | 難治性の胃・十二指腸潰瘍 |
| セロトニンなど | カルチノイド | 皮膚紅潮、下痢、喘息様症状 |
非機能性NETの特徴
一方、ホルモンを産生しないか、産生しても症状として現れないタイプを「非機能性」と呼びます。
こちらは特有の症状がないため、腫瘍がかなり大きくなって腹痛や黄疸などの圧迫症状が出るまで、あるいは検診などで偶然発見されるまで気づかれないことが多く、診断時には進行しているケースも少なくありません。
神経内分泌腫瘍の多くはこの非機能性です。
関連する腫瘍
神経内分泌腫瘍は、その悪性度(顔つき)によって、進行の比較的緩やかな「神経内分泌腫瘍(NET)」と、増殖が速く悪性度の高い「神経内分泌癌(NEC)」に大きく分けられます。
小細胞癌も、この神経内分泌癌(NEC)の一種と位置づけられています。また、皮膚にできるメルケル細胞がんや、胸腺にできる胸腺腫の一部も、神経内分泌の性質を持つことが知られています。

診断の難しさ – 組織学的鑑別の重要性
これまで見てきたように、その他の上皮性腫瘍は種類が多様で、性質も様々です。そのため、正確な診断を下すことが治療の第一歩として極めて重要になります。
特に、顕微鏡で見ただけでは区別がつきにくい腫瘍同士を正確に見分ける「鑑別診断」が、治療方針を大きく左右します。
生検と病理診断の役割
がんの確定診断は、腫瘍の一部を針や内視鏡で採取する「生検」や、手術で切除した組織を調べる「病理診断」によって行います。
病理医は、この組織標本を顕微鏡で観察し、がん細胞の形状、配列、核の大きさなどから、がんの種類を特定します。
しかし、未分化癌のように特徴が乏しい場合や、小細胞癌と悪性リンパ腫のように細胞の見た目が似ている場合、鑑別は容易ではありません。
診断で重要となる観察ポイント
| 観察項目 | 小細胞癌での特徴 | 未分化癌での特徴 |
|---|---|---|
| 細胞の大きさ | 非常に小さい | 多様(大型のことが多い) |
| 核の形状 | 核クロマチンが繊細で微細顆粒状 | 異型性が強く、核小体が明瞭 |
| 細胞の配列 | シート状、リボン状など特徴的な配列 | 構造に乏しく、バラバラに増殖 |
免疫組織化学染色(免疫染色)の活用
鑑別診断において強力な武器となるのが、前述した「免疫染色」です。がん細胞が持つ特有のタンパク質を抗体で染め分けることで、その細胞の出自を明らかにします。
例えば、神経内分泌マーカー(シナプトフィジン、クロモグラニンAなど)が陽性になれば神経内分泌腫瘍を、サイトケラチンというマーカーの種類を見れば上皮性の起源を強く疑うことができます。
この検査により、より客観的で正確な診断が可能になります。
画像診断との組み合わせ
CT、MRI、PET-CTといった画像診断も、診断の補助や病気の広がり(病期)を決定するために重要です。
特に神経内分泌腫瘍では、ソマトスタチン受容体という特殊なタンパク質を目印にした「ソマトスタチン受容体シンチグラフィ」や「Ga-DOTATOC PET/CT」といった核医学検査が、転移巣の検出に非常に有用です。
治療戦略の特殊性 – 腫瘍型別のアプローチ
その他の上皮性腫瘍に対する治療は、画一的なものではありません。腫瘍の種類、悪性度、進行度、そして患者さん自身の体の状態を総合的に判断し、個別に治療戦略を立てる必要があります。
手術、放射線治療、薬物療法という3つの柱を、いかに効果的に組み合わせるかが鍵となります。
手術療法の適応と限界
がんが特定の場所にとどまっている「限局期」であれば、手術による完全切除が根治を目指すための基本の治療となります。
進行の緩やかな神経内分泌腫瘍(NET)や、一部の皮膚がん(例:乳房外パジェット病)などでは、手術が第一選択です。しかし、小細胞癌や未分化癌のように、診断時にすでに全身へ広がっていることが多い腫瘍では、手術の適応は限られます。
手術でがんを取りきれない、あるいは手術による体への負担が大きすぎると判断した場合は、他の治療法を選択します。
腫瘍型と手術の主な役割
- 神経内分泌腫瘍(NET): 根治を目指す中心的な治療
- 小細胞癌: 適応は非常に限定的
- 未分化癌: 周囲への広がりが強いため、完全切除が困難なことが多い
放射線治療の役割
放射線治療は、高エネルギーのX線などを照射してがん細胞を破壊する治療法です。小細胞肺癌の限局型では、化学療法と同時に行う「化学放射線療法」が標準的な治療として確立しています。
また、脳転移の予防(予防的全脳照射)や、骨転移による痛みを和らげる緩和的な目的でも、放射線治療は重要な役割を果たします。
化学療法(抗がん剤治療)の位置づけ
化学療法は、薬剤を点滴や内服で投与し、全身に散らばったがん細胞を攻撃する治療法です。
小細胞癌や未分化癌、進行した神経内分泌癌(NEC)のように、増殖が速く全身に広がりやすいがんに対しては、治療の中心となります。
使用する薬剤の組み合わせ(レジメン)は、がんの種類によって標準的なものが決まっています。
代表的な化学療法のレジメン
| がんの種類 | 代表的な薬剤の組み合わせ |
|---|---|
| 小細胞肺癌 | シスプラチン + イリノテカン / エトポシド |
| 神経内分泌癌 (NEC) | シスプラチン + イリノテカン / エトポシド |
| 甲状腺未分化癌 | ドセタキセル + ドキソルビシン など |
薬物療法の選択 – 分子標的薬と免疫療法の役割
近年の薬物療法の進歩は目覚ましく、従来の抗がん剤に加え、がん細胞の特定の弱点を狙う「分子標的薬」や、人間が本来持つ免疫の力を利用する「免疫チェックポイント阻害薬」が、これらの特殊ながんの治療にも大きな変化をもたらしています。
分子標的薬とは
分子標的薬は、がん細胞の増殖や生存に関わる特定の分子(タンパク質や遺伝子)だけを標的にして、その働きを妨げる薬です。
正常な細胞への影響が少ないため、従来の抗がん剤に比べて副作用が軽い傾向があります。
神経内分泌腫瘍では、腫瘍の増殖に関わるmTORという分子を阻害する薬(エベロリムス)や、血管が新しく作られるのを妨げる薬(スニチニブ)などが使われます。
甲状腺未分化癌では、BRAFという遺伝子に変異がある場合に、それを標的とする薬が有効なことがあります。
免疫チェックポイント阻害薬の登場
私たちの体には、がん細胞などの異物を攻撃する免疫の仕組みがありますが、がん細胞は免疫にブレーキをかけることで攻撃から逃れています。
免疫チェックポイント阻害薬は、このブレーキを解除し、免疫細胞が再びがんを攻撃できるようにする画期的な薬です。この治療は、特定のがん種に対して劇的な効果を示すことがあります。
メルケル細胞がんにおける免疫療法の成功
免疫チェックポイント阻害薬が特に有効な例として、希少な皮膚がんであるメルケル細胞がんが挙げられます。
進行・再発したメルケル細胞がんに対して、この薬は高い効果を示し、標準治療の一つと位置づけられています。
また、小細胞肺癌の進展型に対しても、化学療法と免疫チェックポイント阻害薬の併用が新たな標準治療となっています。
主な免疫チェックポイント阻害薬
| 薬剤名(一般名) | 標的分子 | 主な対象疾患(例) |
|---|---|---|
| ニボルマブ / ペムブロリズマブ | PD-1 | メルケル細胞がん、小細胞肺癌など |
| アテゾリズマブ / デュルバルマブ | PD-L1 | 小細胞肺癌など |
| イピリムマブ | CTLA-4 | 小細胞肺癌など |
予後と経過観察 – 各腫瘍型の生存率
病気の今後の見通し(予後)は、がんの種類、悪性度、そして診断されたときの進行度(病期、ステージ)によって大きく異なります。
治療を終えた後も、再発や転移がないかを確認するための定期的な経過観察がとても大切です。不安なことも多いと思いますが、主治医とよく相談しながら、一歩ずつ進んでいくことが重要です。
腫瘍型別の予後の違い
一般的に、細胞の増殖が速く、悪性度の高い腫瘍ほど予後は厳しくなる傾向があります。甲状腺未分化癌や小細胞癌は、進行が非常に速いため、厳しい予後が予測されます。
一方で、神経内分泌腫瘍(NET)の中でも悪性度の低い(高分化型と呼ばれる)タイプは、進行が非常に緩やかで、長期にわたって病気と付き合っていくことも可能です。
このように、同じ「その他の上皮性腫瘍」という括りの中でも、予後は千差万別です。
腫瘍の悪性度と一般的な予後
| 悪性度 | 代表的な腫瘍 | 一般的な経過 |
|---|---|---|
| 低い | 神経内分泌腫瘍 (NET G1/G2) | 進行は緩やか。長期生存も期待できる。 |
| 高い | 神経内分泌癌 (NEC)、小細胞癌、未分化癌 | 進行が速く、予後は厳しい傾向にある。 |
ステージ(病期)と生存率
どのようながんであっても、予後に最も大きく影響するのは、発見されたときのステージです。がんが原発臓器にとどまっている早期の段階で見つかれば、治療により根治する可能性は高まります。
一方で、他の臓器に転移している進行した状態で見つかると、治療はがんの進行を抑え、症状を和らげることが中心となり、長期的な生存は難しくなります。
だからこそ、体に異変を感じたときに、ためらわずに医療機関を受診することが大切です。
主な腫瘍型の5年相対生存率(目安)
希少がんのためデータは限られますが、代表的な傾向を示します。
小細胞肺癌(小細胞癌の代表)
- 限局型(ステージI-III一部):約20〜30%
- 進展型(ステージIV):約1〜2%
- ※進行が極めて速いですが、初期の抗がん剤治療が効きやすい特徴があります。
神経内分泌腫瘍(NET)
- 悪性度が低いタイプ(G1/G2)であれば、転移があっても10年生存率が60〜70%を超えることも珍しくありません。
未分化癌(甲状腺の例)
- 診断からの1年生存率は約20〜40%と非常に厳しいですが、分子標的薬の登場により改善が期待されています。
治療後の定期的な検査
治療によって目に見えるがんがなくなった後も、再発のリスクは残ります。
そのため、治療後も定期的に通院し、問診、診察、血液検査、CTなどの画像検査を受け、再発や転移の兆候がないかをチェックします。この経過観察の期間や頻度は、がんの種類やステージによって異なります。
不安な点や気になる症状があれば、定期検診を待たずに主治医に相談しましょう。
よくある質問
ここでは、その他の上皮性腫瘍と診断された患者さんやご家族からよく寄せられる質問にお答えします。
- 「その他の上皮性腫瘍」と診断されました。どこで詳しい情報を得られますか?
-
まずは、ご自身の病状を最もよく理解している主治医に相談することが基本です。
その上で、より客観的で信頼できる情報源として、国立がん研究センターが運営する「がん情報サービス」のウェブサイトをお勧めします。
各種のがんについての詳しい解説や、治療法、療養に関する情報が掲載されています。
また、診断や治療方針について他の医師の意見を聞きたい場合は、セカンドオピニオンを活用することも一つの方法です。
- Q. 希少がんの治療経験が豊富な病院を探すにはどうすればよいですか?
-
全国の「がん診療連携拠点病院」は、質の高いがん医療を提供する中心的な施設です。まずはこれらの病院に相談するのがよいでしょう。
希少がんに関しては、国立がん研究センター中央病院などに「希少がんセンター」が設置されており、専門的な診断や治療、相談に応じています。
主治医に相談し、紹介状を書いてもらうことも可能です。
- 免疫チェックポイント阻害薬は誰でも使えますか?
-
いいえ、誰でも使えるわけではありません。
免疫チェックポイント阻害薬が効果を示すかどうかは、がんの種類や、PD-L1というタンパク質の発現率、特定の遺伝子変異の有無などによって異なります。
また、間質性肺炎や甲状腺機能異常症といった特有の副作用があるため、患者さんの全身状態や合併症の有無などを考慮して、使用するかどうかを慎重に判断します。
参考文献
FILIPPINI, Daria Maria, et al. Rare Head and Neck Cancers and Pathological Diagnosis Challenges: A Comprehensive Literature Review. Diagnostics, 2024, 14.21: 2365.
TANG, Liansha, et al. The clinicopathological features and prognosis of primary pulmonary lymphoepithelioma-like carcinoma: A systematic review and meta-analysis. PloS One, 2020, 15.10: e0240729.
JONES, Machael A.; YOUNG, Robert H.; SCULLY, Robert E. A Clinicopathologic Analysis of 11 Cases with Review of the Literature. The American journal of surgical pathology, 1995, 19.7: 815-825.
JO, Vickie Y.; FLETCHER, Christopher DM. Myoepithelial neoplasms of soft tissue: an updated review of the clinicopathologic, immunophenotypic, and genetic features. Head and neck pathology, 2015, 9: 32-38.
LAVAREZE, Luccas, et al. Clinicopathological and survival profile of patients with salivary gland myoepithelial carcinoma: A systematic review. Journal of Oral Pathology & Medicine, 2023, 52.2: 101-108.
SEETHALA, Raja R.; BARNES, E. Leon; HUNT, Jennifer L. Epithelial-myoepithelial carcinoma: a review of the clinicopathologic spectrum and immunophenotypic characteristics in 61 tumors of the salivary glands and upper aerodigestive tract. The American journal of surgical pathology, 2007, 31.1: 44-57.
DIECI, Maria Vittoria, et al. Rare breast cancer subtypes: histological, molecular, and clinical peculiarities. The oncologist, 2014, 19.8: 805-813.
SU, Jiann-Sheng, et al. Clinicopathological characteristics in the differential diagnosis of hepatoid adenocarcinoma: a literature review. World Journal of Gastroenterology: WJG, 2013, 19.3: 321.
LAW, Joanna K., et al. A systematic review of solid-pseudopapillary neoplasms: are these rare lesions?. Pancreas, 2014, 43.3: 331-337.
NAMIKAWA, Tsutomu; HANAZAKI, Kazuhiro. Clinicopathological features and treatment outcomes of metastatic tumors in the stomach. Surgery today, 2014, 44: 1392-1399.
上皮性腫瘍(癌腫)に戻る