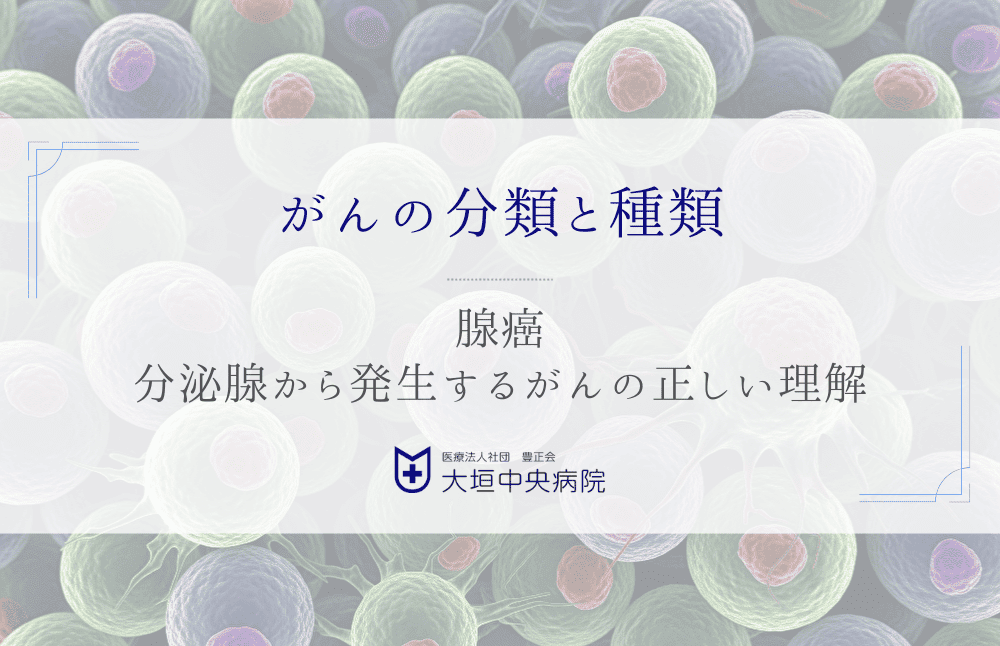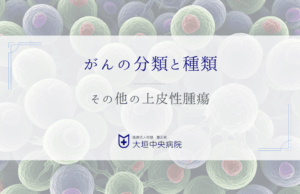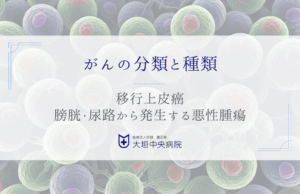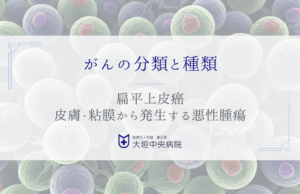「腺癌」という診断を受け、不安や疑問を抱えているあなたへ。
この記事は、腺癌という病気の基本的な知識から、原因、症状、検査、そして多様な治療の選択肢までを、一つひとつ丁寧に解説します。
特に肺や消化器に多く見られるこのがんは、遺伝子の解析が進み、治療法も大きく変化しています。
腺癌とは何か – 基本的な病気の理解
がんと一言でいっても、その種類は様々です。腺癌(せんがん)は、数あるがんの中でも特に発生頻度の高い種類の一つです。
私たちの体の中には、粘液や消化液などの液体を分泌する「腺細胞」という細胞があり、それらが集まって「腺組織」を形成しています。この腺組織から発生する悪性腫瘍を総称して「腺癌」と呼びます。
特定の臓器の名前ではなく、がん細胞の「顔つき」や「出身地」による分類名と理解すると分かりやすいでしょう。
上皮性悪性腫瘍の一種
私たちの体の表面や、臓器の内側を覆っている組織を「上皮」と呼びます。腺細胞もこの上皮の一種です。したがって、腺癌は「上皮性悪性腫瘍」という大きなグループに含まれます。
同じ上皮から発生するがんでも、皮膚や粘膜の表面を覆う扁平上皮細胞から発生するがんは「扁平上皮癌」と呼ばれ、腺癌とは区別します。
顕微鏡でがん細胞を観察した際に、細胞が腺のような管状の構造(腺管構造)を作ろうとしていたり、粘液を産生していたりすると、腺癌と診断されます。
腺癌と他のがんとの違い
がんの分類は、その発生起源によって決まります。腺癌が腺組織由来であるのに対し、例えば筋肉や骨、脂肪、血管などから発生するがんは「肉腫」と呼ばれます。
また、血液細胞から発生するがんは「白血病」や「悪性リンパ腫」です。このように、がんの出身地によって性質や治療法が大きく異なるため、正確な病理診断が治療の第一歩として極めて重要になります。
腺癌の主な特徴
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 発生起源 | 体の分泌機能を持つ「腺細胞」から発生する。 |
| 組織学的特徴 | 顕微鏡で見ると、腺管構造や粘液産生が認められる。 |
| 主な発生部位 | 肺、胃、大腸、乳房、前立腺など、腺組織が多い臓器に発生しやすい。 |
なぜ腺癌は発生するのか – リスク要因と原因
腺癌が発生する明確な原因は、一つの要因だけで説明できるものではなく、複数のリスク要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
発生する臓器によって主要な原因は異なりますが、遺伝子の異常が根本的な引き金となる点は共通しています。生活習慣や環境要因が、この遺伝子の異常を誘発することがあります。
遺伝子の変異が根本的な原因
私たちの体の細胞は、設計図である遺伝子の情報に基づいて正常に分裂・増殖しています。しかし、様々な要因によってこの遺伝子に傷がつき、変異が起こることがあります。
特に、細胞の増殖をコントロールする「がん遺伝子」や「がん抑制遺伝子」に異常が生じると、細胞は無秩序に増え続け、がん細胞へと変化します。
この遺伝子の変異の蓄積が、がん発生の根本的な原因です。
生活習慣との関連
特定の生活習慣は、遺伝子を傷つけ、腺癌のリスクを高めることが知られています。例えば、肺の腺癌では喫煙が大きなリスク要因ですが、非喫煙者にも多く発生することが特徴です。
胃の腺癌ではヘリコバクター・ピロリ菌の持続感染や塩分の多い食事、大腸の腺癌では高脂肪・低繊維の食生活や肥満が関連していると考えられています。
環境要因と職業性曝露
アスベスト(石綿)やラドンといった特定の物質に長期間さらされる環境は、肺の腺癌のリスクを高める原因となります。
また、大気汚染なども関連が指摘されており、自分では避けがたい環境要因もがんの発生に関わっています。これらの要因は、体内に慢性的な炎症を引き起こし、細胞ががん化する土壌を作ると考えられています。
臓器別の主なリスク要因
| 発生臓器 | 主なリスク要因・原因 |
|---|---|
| 肺 | 喫煙、受動喫煙、アスベスト曝露、大気汚染、遺伝的要因 |
| 胃 | ピロリ菌感染、高塩分食、喫煙、遺伝的要因 |
| 大腸 | 高脂肪・低繊維食、肥満、運動不足、飲酒、喫煙、遺伝的要因 |
腺癌の種類と発生部位 – 体のどこにできるのか
腺癌は、体内の腺組織が存在するあらゆる場所に発生する可能性があります。そのため、発生部位は非常に多岐にわたります。中でも、肺、胃、大腸、乳房、前立腺は腺癌の好発部位として知られています。
同じ腺癌という名前でも、発生した臓器によって性質や症状、治療法が大きく異なるため、どの臓器の腺癌であるかを正確に把握することが重要です。
肺腺癌
肺に発生するがん(肺癌)の中で最も多いタイプが腺癌で、全体の約半数を占めます。特に、肺の末梢部(肺野部)に発生しやすいのが特徴です。
かつて肺癌は喫煙者の男性に多い病気というイメージでしたが、肺腺癌は非喫煙者や女性にも多く見られます。初期には症状が出にくく、健康診断の胸部X線検査やCT検査で偶然発見されることも少なくありません。
消化器系の腺癌
胃や大腸、膵臓といった消化器にも腺癌は多く発生します。胃癌や大腸癌のほとんどは腺癌です。
これらの臓器は食物の通り道であり、常に様々な刺激にさらされているため、細胞ががん化しやすい環境にあると考えられます。
早期に発見できれば内視鏡による治療も可能ですが、進行するとリンパ節や肝臓などへ転移しやすくなります。
主な腺癌の発生部位
- 呼吸器系: 肺
- 消化器系: 胃、大腸、食道、膵臓、胆のう
- 生殖器系: 前立腺、子宮体部、卵巣
- その他: 乳房(乳腺)、甲状腺、唾液腺
気づくべき症状と早期発見の重要性
腺癌の症状は、発生した臓器やがんの進行度(ステージ)によって大きく異なります。特に初期の段階では自覚症状がほとんどないことが多く、それが発見を遅らせる一因となっています。
しかし、がんが進行するにつれて様々なサインが現れます。体の変化に注意を払い、気になる症状があれば早めに医療機関を受診することが、早期発見と治療成功の鍵を握ります。
臓器別の注意すべき症状
発生部位によって、特有の症状が現れます。例えば、肺腺癌では長引く咳や痰、血痰、胸の痛み、息切れなどが代表的な症状です。胃の腺癌であれば、胃の不快感や痛み、食欲不振、体重減少が見られます。
大腸の腺癌では、便に血が混じる、便秘と下痢を繰り返す、お腹が張るといった症状に注意が必要です。これらの症状は他の病気でも起こりうるため、自己判断せずに専門医の診察を受けることが大切です。
臓器ごとの主な初期症状
| 発生臓器 | 注意すべき症状の例 |
|---|---|
| 肺 | 2週間以上続く咳、血痰、胸痛、息切れ |
| 胃 | みぞおちの痛み、食欲不振、吐き気、黒い便 |
| 大腸 | 血便、便通異常(便秘・下痢)、腹痛、残便感 |
転移によって起こる症状
がんが進行し、元の場所から離れた臓器へ転移すると、その部位に応じた症状が現れます。例えば、肺腺癌が骨に転移すると、腰や背中などに強い痛みが起こります。
脳への転移では、頭痛や吐き気、めまい、手足の麻痺といった症状が出ることがあります。これらの症状は、がんが全身に広がっているサインであり、治療方針を決定する上で重要な情報となります。
診断方法と検査の流れ – 正確な診断のために
腺癌が疑われる場合、診断を確定し、がんの広がりや性質を詳しく調べるために様々な検査を行います。検査は、体に負担の少ないものから段階的に進めるのが一般的です。
最終的には、がん細胞そのものを採取して顕微鏡で調べる「病理診断」によって確定診断が下されます。この一連の検査は、最も効果的な治療法を選択するための重要な情報収集の期間です。
画像検査によるがんの探索
まず、がんの存在や位置、大きさを調べるために画像検査を行います。胸部X線検査やCT検査、MRI検査、超音波(エコー)検査などが用いられます。
PET-CT検査は、全身のがん細胞の活動を一度に調べることができるため、転移の有無を確認するのに役立ちます。これらの画像検査の結果を総合的に判断し、がんが疑われる部位を特定します。
確定診断のための組織検査
画像検査でがんが疑われた場合、診断を確定するために、その部分の組織や細胞を直接採取する検査が必要です。これを「生検」と呼びます。
肺であれば気管支鏡、胃や大腸であれば内視鏡を使って組織を採取します。採取した組織は病理医が顕微鏡で詳しく観察し、がん細胞の有無や種類(腺癌かどうかなど)を診断します。
この病理診断が、がんの診断における最終的な結論となります。
遺伝子検査の重要性
近年、腺癌の治療では遺伝子検査が極めて重要な役割を担っています。生検で採取したがん組織を用いて、がんの増殖に関わる特定の遺伝子変異(EGFR遺伝子変異など)の有無を調べます。
この検査結果によって、後述する「分子標的薬」という特定の薬が効くかどうかを予測できます。治療方針を決定する上で、遺伝子情報は今や不可欠なものとなっています。
主な診断検査の目的
| 検査の種類 | 主な目的 |
|---|---|
| CT/MRI検査 | がんの位置、大きさ、周囲への広がりを評価する。 |
| 生検(病理診断) | がん細胞を直接確認し、がんの種類(腺癌など)を確定させる。 |
| 遺伝子検査 | がん細胞の遺伝子変異を調べ、分子標的薬の効果を予測する。 |
がんのステージ分類と進行度の見方
がんの診断が確定すると、次に「ステージ(病期)」を決定します。ステージとは、がんがどのくらい進行しているかを示す世界共通の指標です。
がんの大きさ、リンパ節への転移の有無、他の臓器への遠隔転移の有無という3つの要素を組み合わせて総合的に判断し、治療方針を決定したり、今後の見通し(予後)を予測したりするための重要な基準となります。
TNM分類によるステージ決定
ステージの決定には、国際的に「TNM分類」が用いられます。
- T因子: 原発巣のがんの大きさや周囲への広がり
- N因子: 所属リンパ節(がんの近くにあるリンパ節)への転移の有無と範囲
- M因子: 遠隔転移(がんが発生した場所から離れた臓器への転移)の有無
これら3つの因子の評価を組み合わせて、ステージをⅠ期(早期)からⅣ期(進行期)の4段階に分類します。数字が大きくなるほど、がんが進行していることを意味します。
ステージ分類の概要
| ステージ | がんの進行度の目安 |
|---|---|
| Ⅰ期 | がんが原発臓器に限局しており、リンパ節転移がない早期の状態。 |
| Ⅱ期・Ⅲ期 | がんが周囲の組織に広がったり、近くのリンパ節に転移したりしている状態。 |
| Ⅳ期 | がんが他の臓器へ遠隔転移している進行した状態。 |
ステージと治療方針の関係
ステージは治療方針を決定する上で極めて重要です。一般的に、ステージⅠやⅡなどの早期がんであれば、手術による根治を目指します。
ステージⅢでは、手術と薬物療法(抗がん剤治療)、放射線療法を組み合わせた集学的治療を検討します。遠隔転移があるステージⅣの場合は、全身に効果が及ぶ薬物療法が治療の中心となります。
ただし、同じステージでも患者さんごとの状態やがんの性質によって、治療法は個別に判断します。
治療の選択肢 – 手術・薬物療法・放射線療法
腺癌の治療は、がんのステージ、発生した臓器、がん細胞の遺伝子情報、そして患者さん自身の全身状態や希望などを総合的に考慮して決定します。
治療の基本となるのは「手術」「薬物療法」「放射線療法」の3つで、これらを単独、あるいは組み合わせて行います。近年は薬物療法の進歩が著しく、治療の選択肢は大きく広がっています。
手術(外科療法)
がんが原発巣とその周辺にとどまっている早期のステージでは、がんを完全に取り除くことを目指す手術が最も有効な治療法です。
肺腺癌であればがんのある肺葉を切除し、胃や大腸の腺癌でもがんとその周囲のリンパ節を含めて切除します。
近年は、体への負担が少ない腹腔鏡下手術や胸腔鏡下手術といった低侵襲手術が積極的に行われています。
薬物療法(全身治療)
薬物療法は、薬剤を用いて全身のがん細胞を攻撃する治療法です。進行・再発した腺癌の治療の中心となるほか、手術後の再発予防(術後補助化学療法)としても行います。
薬物療法には、従来の「抗がん剤」、特定の分子を狙う「分子標的薬」、自己の免疫力を利用する「免疫チェックポイント阻害薬」など、作用の異なる複数の種類があります。
分子標的薬による個別化治療
分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わる特定の遺伝子変異(EGFRなど)やタンパク質だけを狙い撃ちにする薬です。
そのため、標的となる遺伝子変異を持つがんに対して高い効果が期待でき、正常な細胞への影響が少ないため副作用も従来の抗がん剤とは異なります。
治療前に行う遺伝子検査の結果に基づいて、効果が期待できる患者さんにのみ使用します。
免疫チェックポイント阻害薬
私たちの体には、がん細胞を異物として攻撃する免疫の仕組みが備わっています。しかし、がん細胞は免疫にブレーキをかけることで攻撃から逃れています。
免疫チェックポイント阻害薬は、このブレーキを解除し、再び免疫細胞ががんを攻撃できるようにする薬です。肺腺癌をはじめ、多くの腺癌でその有効性が示されています。
主な薬物療法の種類
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 細胞障害性抗がん剤 | 細胞分裂が活発な細胞(がん細胞)を攻撃する。正常細胞にも影響が及ぶ。 |
| 分子標的薬 | がん細胞の特定の遺伝子変異や分子を標的とする。個別化治療の代表。 |
| 免疫チェックポイント阻害薬 | がん細胞に対する自己の免疫力を高めることで効果を発揮する。 |
放射線療法
放射線療法は、高エネルギーのX線などをがん細胞に照射して破壊する局所治療です。手術が難しい場合や、手術後の再発予防、骨転移による痛みの緩和など、様々な目的で用いられます。
薬物療法と組み合わせて治療効果を高めることもあります。
がんと共に生きる – 治療中の生活と心のケア
がんの治療は、身体的な負担だけでなく、精神的、社会的な側面にも大きな影響を及ぼします。
治療を続けながら、いかに自分らしい生活を維持していくか、そして不安や落ち込みといった心のつらさにどう向き合うかが重要になります。
医療チームとよく相談しながら、様々なサポートを活用することが、治療を乗り越える力になります。
副作用との付き合い方
治療には副作用が伴うことがあります。抗がん剤による吐き気や脱毛、分子標的薬による皮疹や下痢、免疫療法による特有の副作用など、用いる薬によって症状は様々です。
どのような副作用が起こりうるか、そしてその対処法について、事前に医師や看護師、薬剤師から十分な説明を受けましょう。
副作用をコントロールする薬も進歩しており、症状を我慢せずに早めに相談することが大切です。
心のケアとサポート
がんと診断されたことによるショック、治療への不安、将来への心配など、心に大きな負担がかかるのは当然のことです。
一人で抱え込まず、家族や友人、そして医師や看護師、がん相談支援センターの相談員など、信頼できる人に気持ちを話してみましょう。
同じ病気を経験した患者さんの会(ピアサポート)に参加することも、孤独感を和らげ、有益な情報を得る機会になります。
相談できる窓口の例
| 相談窓口 | 主な役割 |
|---|---|
| 主治医・看護師 | 病状や治療、副作用に関する医学的な相談。 |
| がん相談支援センター | 病気のこと、治療や療養生活、医療費など、がんに関するあらゆる相談。 |
| ピアサポート | 同じがん体験者との交流を通じて、悩みや不安を分かち合う。 |
予後と再発予防 – 治療後の経過観察
治療が一通り終了した後も、再発や転移がないかを確認するために、定期的な経過観察が必要です。
予後(治療後の経過の見通し)は、がんの種類やステージ、治療の効果によって異なりますが、近年、新しい治療法の登場により、特に遺伝子変異を持つ腺癌などの生存率は向上しています。
再発のリスクを減らし、健やかな生活を送るために、治療後の生活習慣にも気を配ることが大切です。
生存率の考え方
生存率は、がんと診断された人のうち、一定期間後(通常は5年後)に生存している人の割合を示す統計データです。
これは多くの患者さんのデータの平均値であり、個々の患者さんの余命を示すものではありません。ステージやがんの性質によって大きく変動しますし、あくまで過去のデータに基づいた指標です。
数字に一喜一憂せず、ご自身の治療に集中することが重要です。
主な腺癌の5年相対生存率(目安)
腺癌は発生する臓器によって予後が異なりますが、代表的な部位のデータを示します。
- 肺腺癌:
- ステージI:80〜90%前後
- ステージII:60〜70%前後
- ステージIII:30〜40%前後
- ステージIV:10%未満(分子標的薬の適応があれば長期生存例も増加中)
- 胃癌(大部分が腺癌):
- ステージI:90%以上
- ステージII:60〜70%前後
- ステージIII:40〜50%前後
- ステージIV:10%未満
- 大腸癌(大部分が腺癌):
- ステージI〜II:80〜90%以上
- ステージIII:70〜80%前後
- ステージIV:20%前後
再発・転移のモニタリング
治療後は、定期的に通院し、問診や血液検査(腫瘍マーカー)、CTなどの画像検査を受けます。これにより、万が一再発や転移が起きた場合でも、早期に発見し、速やかに次の治療を開始することができます。
経過観察の頻度は、がんのステージや再発リスクに応じて決められます。
再発予防のために心がけたい生活習慣
- 禁煙を継続する
- バランスの取れた食事を摂る
- 適度な運動を習慣にする
- 体重を適切に管理する
よくある質問
- 腺癌は遺伝しますか?
-
すべての腺癌が遺伝するわけではありませんが、一部には家族内で発生しやすい「家族性腫瘍」や、特定の遺伝子変異が親から子へ受け継がれる「遺伝性腫瘍」が存在します。
例えば、大腸癌や乳癌の一部には遺伝的要因が強く関与していることが知られています。
血縁者に若くしてがんになった方や、複数のがんを経験した方がいる場合は、主治医に相談してみることをお勧めします。
- 治療の選択で迷っています。どうすればよいですか?
-
治療法を決める際には、主治医から病状や各治療法のメリット・デメリットについて十分な説明を受け、ご自身の価値観やライフスタイルも伝えた上で、一緒に考えていくことが大切です。
もし、他の医師の意見も聞いてみたい場合は、セカンドオピニオンを利用することも一つの方法です。納得して治療に臨むことが、前向きな気持ちを保つ上で重要になります。
- 分子標的薬や免疫療法の治療費は高額ですか?
-
これらの新しい薬は、従来の抗がん剤に比べて高額になる傾向があります。
しかし、日本には高額療養費制度があり、医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。
また、ご加入の民間保険や、勤務先の福利厚生なども確認してみましょう。医療費に関する心配事は、病院のがん相談支援センターやソーシャルワーカーに相談できます。
腺癌と同じく、体の表面や臓器の内側を覆う「上皮」から発生するがんに「扁平上皮癌」があります。
腺癌が分泌腺に由来するのに対し、扁平上皮癌は皮膚や口腔、食道、肺の気管支といった扁平上皮細胞から発生します。発生する場所や原因、がんの性質が腺癌とは異なるため、治療法も異なります。
がんについての理解をさらに深めるために、以下の記事もご覧ください。
参考文献
BARR KUMARAKULASINGHE, Nesaretnam; ZANWIJK, Nico van; SOO, Ross A. Molecular targeted therapy in the treatment of advanced stage non‐small cell lung cancer (NSCLC). Respirology, 2015, 20.3: 370-378.
SAITO, Motonobu, et al. Treatment of lung adenocarcinoma by molecular-targeted therapy and immunotherapy. Surgery today, 2018, 48: 1-8.
NAGANO, Tatsuya; TACHIHARA, Motoko; NISHIMURA, Yoshihiro. Molecular mechanisms and targeted therapies including immunotherapy for non-small cell lung cancer. Current cancer drug targets, 2019, 19.8: 595-630.
YUAN, Min, et al. The emerging treatment landscape of targeted therapy in non-small-cell lung cancer. Signal transduction and targeted therapy, 2019, 4.1: 61.
DE SCORDILLI, Marco, et al. Targeted therapy and immunotherapy in early-stage non-small cell lung cancer: current evidence and ongoing trials. International journal of molecular sciences, 2022, 23.13: 7222.
TO, Kenneth KW; FONG, Winnie; CHO, William CS. Immunotherapy in treating EGFR-mutant lung cancer: current challenges and new strategies. Frontiers in oncology, 2021, 11: 635007.
MINGUET, Joan; SMITH, Katherine H.; BRAMLAGE, Peter. Targeted therapies for treatment of non‐small cell lung cancer—recent advances and future perspectives. International journal of cancer, 2016, 138.11: 2549-2561.
RODAK, Olga, et al. Current landscape of non-small cell lung cancer: epidemiology, histological classification, targeted therapies, and immunotherapy. Cancers, 2021, 13.18: 4705.
MADEDDU, Clelia, et al. EGFR-mutated non-small cell lung cancer and resistance to immunotherapy: role of the tumor microenvironment. International journal of molecular sciences, 2022, 23.12: 6489.
上皮性腫瘍(癌腫)に戻る