「癌」という言葉を聞くと多くの方が不安を感じるでしょう。実は、癌の大部分は私たちの体の表面や内臓の表面を覆う「上皮」という組織から発生します。
これを上皮性腫瘍(癌腫)と呼び、全悪性腫瘍の約90%を占めます。癌腫は発生した臓器や組織の形(組織型)によって、性質や治療法が異なります。
この記事では、最も代表的な腺癌、扁平上皮癌、移行上皮癌を中心に、その特徴、原因、診断、治療の基本について詳しく解説します。
腺癌
腺癌は、体の分泌腺や臓器の内面を覆う腺細胞から発生する悪性腫瘍です。胃や大腸、肺、乳房、前立腺など、分泌機能を持つ多くの臓器で見られます。
腺癌は、正常な腺組織が持つ「何かを分泌する」という特徴を、程度の差はあれ受け継いでいることが多く、組織学的には腺のような構造(腺管構造)を形成しようとする傾向があります。
その多様な発生部位と性質から、癌腫の中でも非常に重要な位置を占めています。
腺癌の定義と特徴
腺癌を定義づける最も大きな特徴は、その発生起源が腺細胞である点です。腺細胞は、消化液、ホルモン、粘液など、体に必要な物質を産生し、分泌する役割を担っています。
癌化した腺細胞も、この名残として粘液を産生したり、管状の構造を作ったりすることがあります。この性質は、病理診断において癌の種類を特定する上で重要な手がかりとなります。
また、同じ臓器に発生した癌でも、腺癌と他の種類の癌とでは、進行の仕方や治療薬への反応性が異なるため、正確な組織型の診断が治療方針の決定に極めて重要です。
分化度による分類
腺癌は、その顔つきの悪性度を示す「分化度」によっても分類します。分化度とは、癌細胞がどれだけ正常な腺細胞の構造や機能に近いかを示す指標です。
高分化型は正常組織に近く、比較的おとなしい性質を持ちます。一方、低分化型は正常組織の面影がほとんどなく、増殖スピードが速く、転移しやすい傾向があります。
この分化度の評価は、治療後の経過を予測する上でも参考にします。
発生しやすい臓器
腺癌は、体内の広範な臓器に発生する可能性があります。特に消化器系に多く、胃癌や大腸癌の大部分は腺癌です。
また、肺癌においても腺癌は最も頻度の高い組織型であり、特に非喫煙者や女性の肺癌に多いことが知られています。その他、ホルモンの影響を受ける乳房や前立腺、子宮体部なども腺癌の好発部位です。
これらの臓器はすべて何らかの分泌機能を持つ腺組織を含んでおり、腺癌が発生する土壌があると言えます。
発生臓器別の主な症状
| 臓器 | 主な初期症状 | 特徴的な所見 |
|---|---|---|
| 胃 | みぞおちの不快感・痛み、食欲不振 | 進行すると貧血や黒色便が見られることがある |
| 大腸 | 血便、便通異常(便秘・下痢) | 早期は自覚症状がないことが多く、検診が重要 |
| 肺 | 長引く咳、血痰、胸痛 | 喫煙者に多いが、非喫煙者の腺癌も増加傾向にある |
診断と治療
腺癌の診断は、まず内視鏡検査やCT、MRIなどの画像診断で病変の場所や広がりを確認することから始まります。確定診断には、病変の一部を採取して顕微鏡で調べる生検(組織診)が必要です。
治療は、癌の進行度(ステージ)、発生した臓器、患者さん自身の全身状態などを総合的に考慮して決定します。早期であれば手術による切除が根治を目指す基本となります。
進行している場合には、手術に加えて化学療法(抗がん剤治療)や放射線療法を組み合わせます。
近年では、特定の遺伝子変異を持つ腺癌に対して、その変異を標的とする分子標的薬や、体の免疫力を利用して癌を攻撃する免疫チェックポイント阻害薬なども登場し、治療の選択肢は大きく広がっています。
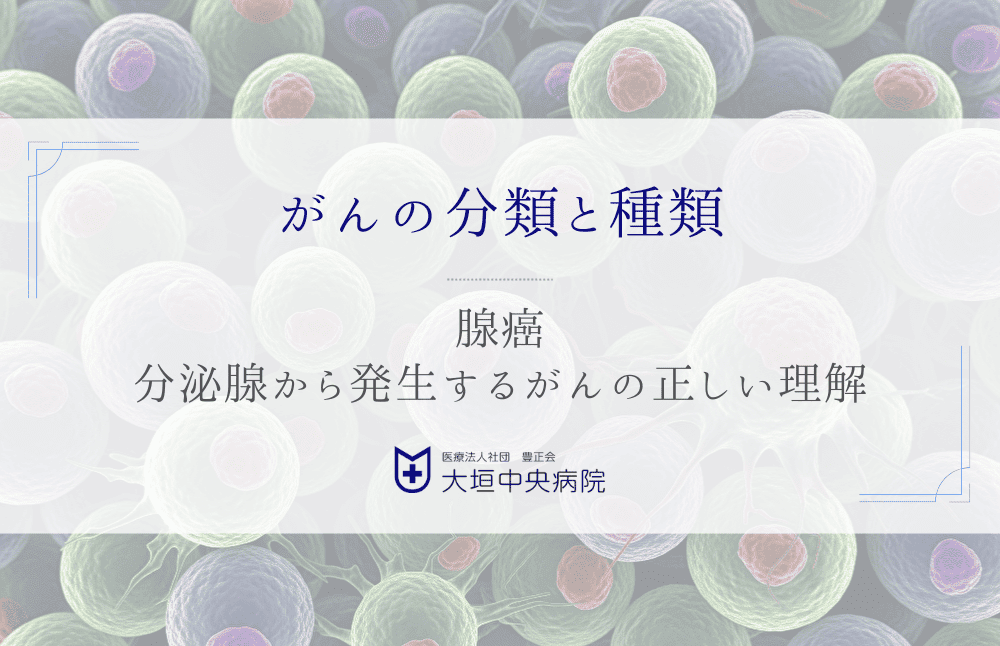
扁平上皮癌
扁平上皮癌は、私たちの体を覆う皮膚や、口腔、食道、気管、子宮頸部といった管腔臓器の粘膜を構成する「扁平上皮細胞」から発生する悪性腫瘍です。
この癌は、外界からの刺激に常にさらされる場所に発生しやすいという特徴があります。
例えば、皮膚では紫外線、肺や喉ではタバコの煙、子宮頸部ではヒトパピローマウイルス(HPV)の持続感染などが、発生の大きな要因となります。
原因が比較的はっきりしているものが多く、予防や早期発見が重要になる癌の一つです。
扁平上皮癌の概要と特徴
扁平上皮は、薄い細胞が何層にも重なった丈夫な構造をしており、外部の物理的・化学的な刺激から体を守るバリアの役割を果たしています。
扁平上皮癌の細胞は、この正常な扁平上皮の性質を受け継ぎ、細胞同士がしっかりと結合し、角化(ケラチンというタンパク質を作ること)する傾向があります。
この角化の程度は、病理診断で癌の悪性度を判断する材料の一つになります。
また、本来は扁平上皮でない気管支などに、喫煙などの慢性的な刺激が加わることで粘膜が扁平上皮に変化(扁平上皮化生)し、そこから癌が発生することもあります。
主な発生部位とリスク因子
扁平上皮癌は、体の様々な部位に発生します。皮膚にできるものは皮膚癌として、口腔や咽頭、喉頭にできるものは頭頸部癌として知られます。
食道癌や肺癌、子宮頸癌、肛門癌などにも扁平上皮癌が多く見られます。これらの発生には、それぞれ特有のリスク因子が深く関わっています。
主なリスク因子と関連部位
| リスク因子 | 主な発生部位 | 予防・早期発見のポイント |
|---|---|---|
| 喫煙 | 肺、口腔・咽頭・喉頭、食道 | 禁煙。定期的な歯科検診や内視鏡検査が有効。 |
| 紫外線 | 皮膚(特に顔や手などの露出部) | 日焼け対策。ほくろやシミの急な変化に注意する。 |
| ヒトパピローマウイルス(HPV) | 子宮頸部、中咽頭、肛門 | HPVワクチンの接種。子宮頸がん検診を受ける。 |
診断と治療の基本方針
扁平上皮癌の診断は、発生部位によって異なりますが、視診や触診で確認できることも少なくありません。
皮膚や口腔、子宮頸部などは直接観察しやすく、異常があれば組織を採取して確定診断します。肺や食道など体の内部にできた場合は、内視鏡や画像検査が中心となります。
治療の基本は、手術による切除と放射線療法です。扁平上皮癌は一般的に放射線に対する感受性が比較的高いため、放射線療法がよく効く場合があります。
特に頭頸部や食道など、手術で機能や形態を大きく損なう可能性がある部位では、放射線療法と化学療法を組み合わせる治療法も積極的に選択します。
進行・再発した場合には、化学療法や免疫チェックポイント阻害薬が治療の中心となります。
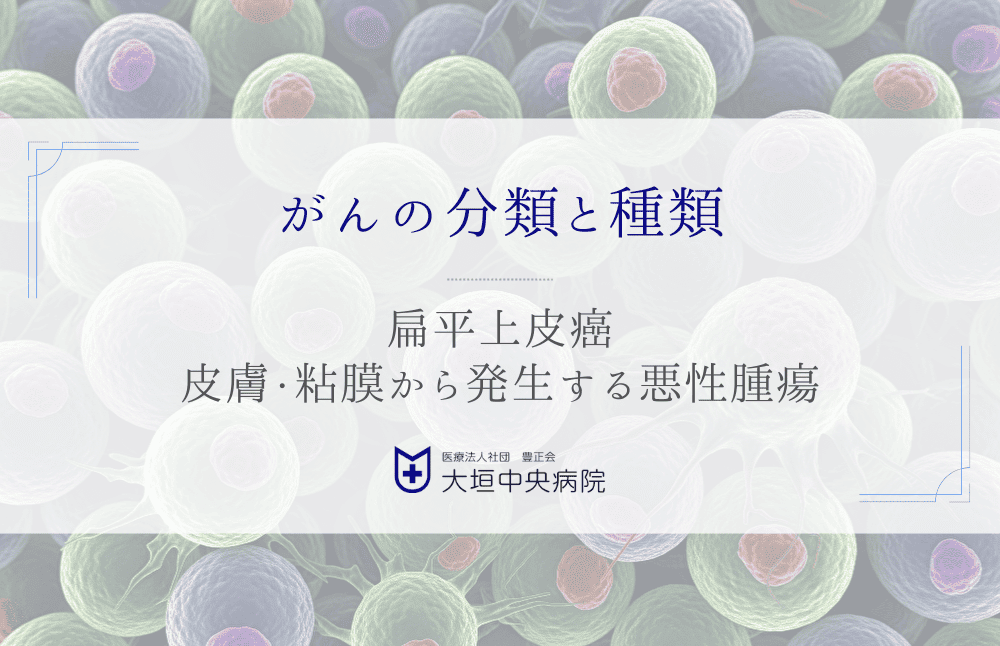
移行上皮癌
移行上皮癌は、腎臓で作られた尿が通る道すじである「尿路」の内側を覆う、特殊な上皮細胞から発生する悪性腫瘍です。尿路とは、具体的には腎盂、尿管、膀胱、尿道の一部を指します。
この癌は「尿路上皮癌」とも呼ばれ、そのほとんどは膀胱に発生します。移行上皮癌の最も重要で代表的なサインは「血尿」です。
特に、痛みなどの他の症状を伴わない血尿に気づいた場合は、速やかに専門医の診察を受けることが大切です。
移行上皮(尿路上皮)とは
移行上皮は、他の上皮組織とは異なるユニークな特徴を持っています。それは、尿の量に応じて伸び縮みできる高い伸縮性です。
膀胱に尿が溜まると移行上皮は薄く引き伸ばされ、排尿して膀胱が空になると厚く縮みます。この柔軟な性質が、尿を一時的に溜めておくという膀胱の機能を実現しています。
しかし、この上皮は尿に含まれる発癌物質に長時間さらされるため、癌が発生しやすい環境にあるとも言えます。
発生部位と特徴
移行上皮癌の約95%は膀胱に発生します。残りは腎盂や尿管に発生します。この癌の厄介な特徴の一つに、「多発性」があります。
これは、尿路の複数の場所に同時に、あるいは時間をずらして次々と癌が発生しやすい性質を指します。
そのため、一度治療しても、膀胱内の別の場所や、腎盂・尿管に新たな癌が見つかることがあり、治療後も長期にわたる定期的な検査が重要になります。
症状と診断
最大の警告サインは、目で見てわかる血尿(肉眼的血尿)です。
多くの場合、排尿時の痛みなどを伴わないため、「一度だけだったから」と放置してしまうケースが見られますが、これは非常に危険です。
血尿に気づいたら、必ず泌尿器科を受診してください。その他、頻尿や排尿時痛、残尿感といった症状が現れることもあります。
診断のためには、まず尿検査で尿に血や癌細胞が混じっていないか(尿細胞診)を調べます。そして、最も重要な検査が、尿道から内視鏡を挿入して膀胱内を直接観察する「膀胱鏡検査」です。
この検査で腫瘍が確認された場合、組織を採取して癌の確定診断と、癌の根の深さ(深達度)を評価します。
進行度と治療の概要
| 進行度(ステージ) | 癌の状態 | 主な治療法 |
|---|---|---|
| 表在性 | 癌が膀胱の表面(粘膜・粘膜下層)にとどまる | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)、BCG膀胱内注入療法 |
| 筋層浸潤性 | 癌が膀胱の壁の筋層まで達している | 膀胱全摘除術、全身化学療法、放射線療法 |
| 転移性 | リンパ節や他の臓器へ転移している | 全身化学療法、免疫チェックポイント阻害薬 |
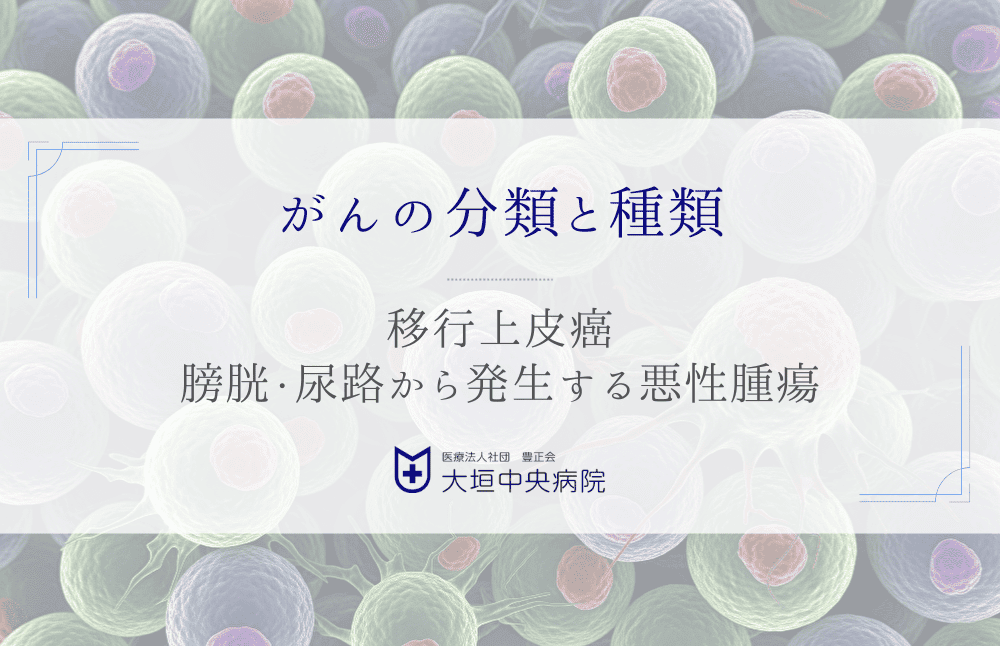
その他の上皮性腫瘍
これまで解説してきた腺癌、扁平上皮癌、移行上皮癌は、上皮性腫瘍の代表格ですが、その他にも様々な種類の上皮性腫瘍が存在します。
発生頻度は低いものの、それぞれが特有の性質を持ち、診断や治療において専門的な知識が必要です。ここでは、代表的なものをいくつか紹介します。
基底細胞癌
皮膚に発生する癌の中で最も頻度が高いのが基底細胞癌です。皮膚の最も深い層である基底層や、毛根を包む組織から発生します。主に高齢者の顔面など、長年にわたり紫外線を浴びてきた部位に見られます。
黒色から黒褐色の小さなほくろのように見えることが多く、ゆっくりと大きくなります。この癌の最大の特徴は、転移することが極めてまれであるという点です。
そのため、手術で完全に取り除くことができれば、治癒が期待できます。
腎細胞癌
腎細胞癌は、腎臓の本体である腎実質の尿細管上皮から発生する癌です。成人の腎臓にできる癌の約90%を占めます。
以前は症状が出にくく、進行した状態(血尿、腹部のしこり、痛み)で見つかることが多かったのですが、近年は健康診断などの超音波検査やCT検査で、症状のない早期の段階で偶然発見されるケースが増えています。
治療の基本は手術で、近年では薬物療法も大きく進歩しています。
肝細胞癌
肝臓を構成する主要な細胞である肝細胞から発生する癌です。日本の肝細胞癌の多くは、B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスの持続感染による慢性肝炎や肝硬変を背景として発生します。
アルコールの過剰摂取や、近年増加している非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)もリスク因子です。
肝臓の機能が低下している患者さんが多いため、治療法の選択には、癌の進行度だけでなく、肝臓の予備能力(肝予備能)を慎重に評価することが必要です。
まれな上皮性腫瘍の例
- メルケル細胞癌
- 内分泌腺の癌(甲状腺癌、副腎皮質癌など)
- 唾液腺癌
様々な上皮性腫瘍とその特徴
| 腫瘍名 | 主な発生部位 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 基底細胞癌 | 皮膚(特に顔面) | 転移はまれ。紫外線が主な原因。 |
| 腎細胞癌 | 腎臓 | 近年は無症状で発見されることが多い。 |
| 肝細胞癌 | 肝臓 | 肝炎ウイルスや肝硬変が背景にあることが多い。 |
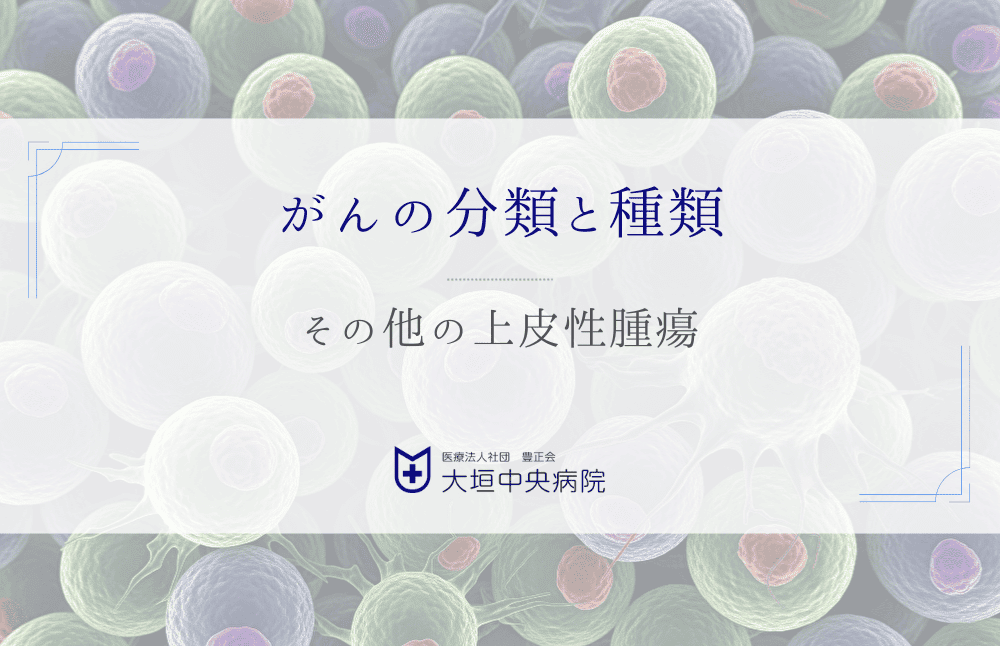
よくある質問
- 癌腫(がんしゅ)と肉腫(にくしゅ)の違いは何ですか?
-
癌腫と肉腫は、どちらも悪性腫瘍ですが、発生する組織が異なります。癌腫は、この記事で解説したように、体の表面や臓器の内側を覆う「上皮細胞」から発生する癌です。
全悪性腫瘍の約90%を占めます。一方、肉腫は骨や筋肉、脂肪、血管といった、体を支えたり結合したりする「非上皮性組織(間葉系組織)」から発生するまれな癌です。
発生起源が異なるため、性質や治療法も異なります。
- 癌の早期発見のために自分でできることはありますか?
-
早期発見には、国や自治体が推奨する「がん検診」を定期的に受けることが非常に重要です。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんには有効な検診方法があります。
また、普段から自分の体の変化に注意を払うことも大切です。
「いつもと違う」と感じる症状(例えば、長引く咳、血便や血尿、原因不明の体重減少、体表のしこりなど)があれば、放置せずに医療機関を受診してください。
- 癌の発生に遺伝は関係しますか?
-
癌の一部には、特定の遺伝子の変異が親から子へ受け継がれることで発生リスクが高くなる「遺伝性腫瘍」が存在します。しかし、これは癌全体の中では少数です。
多くの癌は、遺伝とは直接関係なく、加齢や、喫煙、食生活、感染症といった様々な環境的要因が長年にわたって積み重なることで発生します。
- 治療法はどのようにして決まるのですか?
-
治療法は、一つの要素だけで決まるわけではありません。まず、癌の種類(組織型)、進行度(ステージ)、癌細胞の遺伝子情報などを詳しく調べます。
それに加えて、患者さん自身の年齢、全身状態、他に持っている病気、そして何よりもご本人の価値観や治療に対する希望を考慮します。
これらの情報を基に、担当医をはじめとする医療チームが総合的に判断し、最も良いと考えられる治療方針を提案します。
この記事では、体の表面や内臓の「上皮」から発生する上皮性腫瘍(癌腫)について解説しました。
しかし、悪性腫瘍にはもう一つ、骨や筋肉、脂肪、血管といった結合組織から発生する「非上皮性腫瘍(肉腫)」という種類が存在します。
癌腫に比べて発生頻度は低いものの、その性質や治療法は大きく異なります。癌に対する理解をさらに深めるために、次は肉腫がどのような病気であるかを知ることも重要です。
以下の記事で、癌腫との違いや肉腫特有の特徴について詳しく学んでみましょう。
参考文献
CASSARINO, David S.; DERIENZO, Damian P.; BARR, Ronald J. Cutaneous squamous cell carcinoma: a comprehensive clinicopathologic classification: part two. Journal of cutaneous pathology, 2006, 33.4: 261-279.
COCUZ, Iuliu Gabriel, et al. Pathophysiology, Histopathology, and Differential Diagnostics of Basal Cell Carcinoma and Cutaneous Squamous Cell Carcinoma—An Update from the Pathologist’s Point of View. International Journal of Molecular Sciences, 2024, 25.4: 2220.
FRANCHI, Alessandro. Epithelial tumors. In: Pathology of sinonasal tumors and tumor-like lesions. Cham: Springer International Publishing, 2019. p. 85-145.
TRAVIS, William D. Update on small cell carcinoma and its differentiation from squamous cell carcinoma and other non-small cell carcinomas. Modern Pathology, 2012, 25: S18-S30.
MIYAI, Kosuke; ABU-FARSAKH, Hussam; RO, Jae Y. Other Types of Carcinoma. In: Urinary Bladder Pathology. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 83-96.
MANUNTA, Andrea, et al. Non‐transitional cell bladder carcinomas. BJU international, 2005, 95.4: 497-502.
SHOKEIR, A. A. Squamous cell carcinoma of the bladder: pathology, diagnosis and treatment. BJU international, 2004, 93.2: 216-220.
PANER, Gladell P., et al. Updates in the pathologic diagnosis and classification of epithelial neoplasms of urachal origin. Advances in Anatomic Pathology, 2016, 23.2: 71-83.
EICHHORN, John H.; YOUNG, Robert H. Transitional cell carcinoma of the ovary: a morphologic study of 100 cases with emphasis on differential diagnosis. The American journal of surgical pathology, 2004, 28.4: 453-463.
WRIGHT, Thomas C.; FERENCZY, Alex; KURMAN, Robert J. Carcinoma and other tumors of the cervix. In: Blaustein’s pathology of the female genital tract. New York, NY: Springer New York, 1994. p. 279-326.

