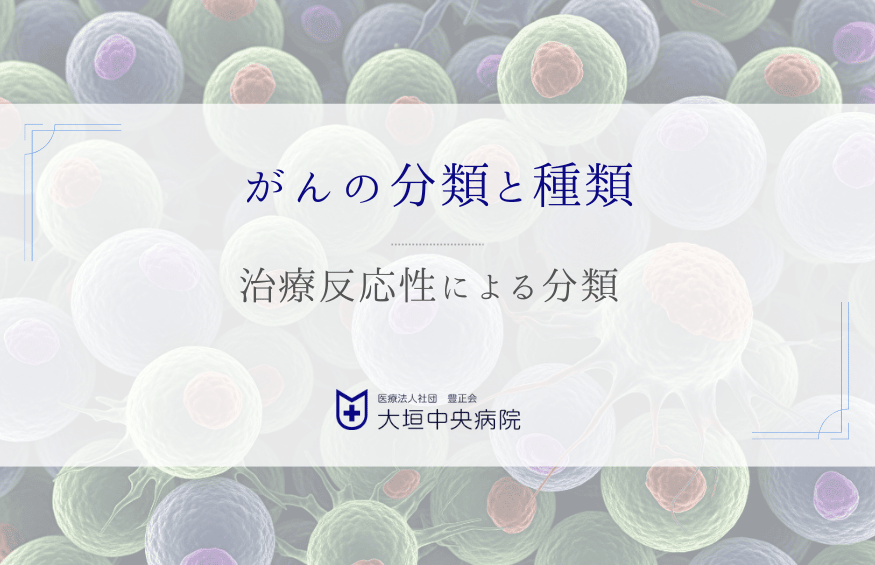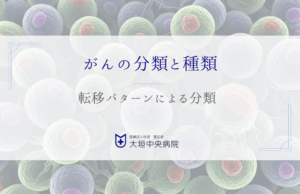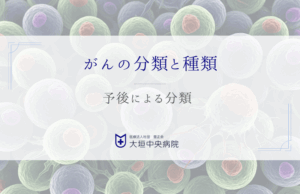がんの治療法は日々進歩していますが、同じ種類の「がん」と診断されても、同じ薬がすべての人に同じように効くわけではありません。この違いは、がん細胞が持つ「個性」に由来します。
この記事では、その個性を「薬への反応の仕方」で捉える「治療反応性による分類」について、詳しく解説します。
この分類法を理解することは、ご自身の状態を深く知り、納得のいく治療選択をする上で重要な知識となります。
なぜ治療効果に差が生まれるのか、そして、どのようにして自分に合った治療法を見つけていくのか、その考え方の基本を一緒に学んでいきましょう。
同じ臓器のがんでも、薬の効き目は人それぞれ
肺がん、胃がん、大腸がんなど、がんは発生した臓器や組織によって分類するのが一般的です。しかし、同じ臓器にできたがんであっても、治療薬の効果には大きな個人差が生じることが広く知られています。
ある人には劇的な効果を示した薬が、別の人にはほとんど効かない、あるいは強い副作用だけが現れてしまう。こうした事態は、がん治療において決して珍しくありません。
この個人差の背景には、一見同じに見えるがんでも、その内部に潜む細胞レベルの性質、つまり「がんの個性」が大きく異なっているという事実があります。
がん治療の画一性とその限界
従来のがん治療、特に化学療法では、「特定の臓器のがんには、この抗がん剤」というように、ある程度標準化された治療計画を立てていました。
この方法は多くのがん患者さんの治療に貢献してきましたが、一方で治療効果が出にくいケースや、効果判定が難しいケースも存在しました。
画一的なアプローチでは、個々のがんが持つ多様性に対応しきれないという限界が見えてきたのです。患者さん一人ひとりの「がんの種類」だけでなく、その「性質」を見極める必要性が高まっています。
肺がんにおける治療効果の個人差の例
| 患者さんの特徴 | Aさん | Bさん |
|---|---|---|
| がんの種類 | 肺腺がん | 肺腺がん |
| 使用した分子標的薬 | EGFR阻害薬 | EGFR阻害薬 |
| 治療効果 | 腫瘍が大幅に縮小 | 効果が見られなかった |
なぜ同じがんなのに治療効果が違うのか
この治療効果の違いを生む最大の要因は、がん細胞の遺伝子情報にあります。私たちの体の設計図である遺伝子は、細胞の増殖や死滅をコントロールしています。
がん細胞では、この遺伝子に異常(変異)が生じることで、無秩序な増殖が引き起こされます。
そして、この遺伝子変異のパターンが、患者さん一人ひとりで、さらには同じ患者さんの体内にあるがん細胞の中でも、多様性に富んでいるのです。
この遺伝子レベルの違いが、薬に対する「感受性」の差、つまり薬の効き目の違いとして現れます。
そこで注目される「治療反応性」という分類基準
このような背景から、がんを発生臓器だけで分類するのではなく、それぞれの「がんがどのような治療に反応する性質を持っているか」という観点で分類する考え方が重要視されるようになりました。
それが「治療反応性による分類」です。これは、がんの「戸籍(どこで生まれたか)」だけでなく、「性格(どんな性質か)」を見て、治療法を考えていこうというアプローチです。
この分類を用いることで、より精度の高い治療効果の予測が可能になります。
治療反応性とは何か
治療反応性とは、特定のがんが、特定の治療法(化学療法、分子標的薬、免疫療法など)に対して、どの程度効果を示すかという性質を指します。
例えば、「Aという薬によく反応する(感受性が高い)タイプ」や、「Bという薬には反応しにくい(耐性がある)タイプ」のように分類します。
この性質を治療開始前に把握することで、無駄な治療を避け、最初から効果が期待できる治療法を選択できる可能性が高まります。
従来の分類法との違い
従来の分類法が「形態学的な特徴(がん細胞の見た目)」や「発生臓器」を主軸にしていたのに対し、治療反応性による分類は「機能的な特徴(薬への反応)」を主軸とします。
これにより、異なる臓器に発生したがんでも、同じ遺伝子変異を持つ場合は同じ分子標的薬が効く、といった臓器横断的な治療の道が拓かれました。
従来の分類と治療反応性による分類の視点
| 分類項目 | 従来の分類(臓器別) | 治療反応性による分類 |
|---|---|---|
| 主な視点 | がんが発生した臓器・組織 | 治療薬への感受性・耐性 |
| 治療選択の根拠 | 臨床データに基づく標準治療 | がんの遺伝子情報・バイオマーカー |
| 目指すもの | 集団に対する有効性 | 個人に対する効果の最大化 |
治療薬への感受性で見る – がん細胞のタイプ分け
がん細胞を治療薬への感受性でタイプ分けすることは、個別化医療の根幹をなす考え方です。
がん細胞の増殖に関わる特定の分子(タンパク質や遺伝子)を「バイオマーカー」として測定し、そのバイオマーカーの状態に応じて薬の効きやすさを判断します。
このバイオマーカーの有無や量が、がん細胞のタイプを決める重要な手がかりとなります。
薬が「効く」タイプと「効きにくい」タイプ
例えば、ある種のがん細胞は、特定の「分子」を異常に多く作り出し、それをエネルギー源として増殖しています。この「分子」の働きをピンポイントで妨害するのが「分子標的薬」です。
この特定の「分子」を持つがん細胞は、その分子標的薬が「効く」タイプと言えます。一方で、その「分子」を持たないがん細胞には、同じ薬を使っても効果は期待できません。
これが薬の感受性による基本的なタイプ分けです。
感受性を決める要因 – バイオマーカーの役割
バイオマーカーは、治療効果を予測するための目印です。血液や組織の検査によって測定し、治療方針を決定するための客観的な指標として用います。
バイオマーカーには、特定の遺伝子変異やタンパク質の発現量など、さまざまな種類があります。
主なバイオマーカーの種類
- 遺伝子変異(例 EGFR、ALK、BRAF)
- 遺伝子の増幅(例 HER2)
- タンパク質の発現(例 PD-L1)
これらのバイオマーカーを調べることで、どの分子標的薬や免疫療法が効果的か、あるいは化学療法の効果判定をどのように行うべきか、といった具体的な治療戦略を立てることが可能になります。
バイオマーカーと対応する分子標的薬の例(肺がん)
| バイオマーカー(遺伝子異常) | 対応する分子標的薬の種類 | 主な作用 |
|---|---|---|
| EGFR遺伝子変異 | EGFRチロシンキナーゼ阻害薬 | がん細胞の増殖信号をブロック |
| ALK融合遺伝子 | ALK阻害薬 | 異常なタンパク質の働きを抑制 |
| ROS1融合遺伝子 | ROS1阻害薬 | がん細胞の増殖命令を止める |
治療方針決定の羅針盤 – 期待できる効果と副作用の予測
治療反応性による分類は、どの治療法を選ぶべきかという重要な判断を下す際の、まさに羅針盤のような役割を果たします。
単に効果があるかないかだけでなく、どの程度の治療効果が期待できるのか、そしてどのような副作用が起こりうるのかを、より高い精度で予測することを目指します。
これにより、患者さんと医療者が共に納得し、治療のゴールを共有した上で治療を開始できます。
治療効果の予測と個別化医療の実現
バイオマーカー検査の結果に基づいて治療法を選択することは、個別化医療の核心部分です。
例えば、「バイオマーカーAが陽性なので、分子標的薬Xの効果が70%の確率で期待できる」といった具体的な予測が可能になります。
これにより、闇雲に治療を試すのではなく、科学的根拠に基づいた戦略的な治療計画を立てることができます。これが個別化医療の大きな利点です。
治療反応性による治療選択の考え方
| バイオマーカーの状態 | 予測される治療反応性 | 推奨される治療方針の例 |
|---|---|---|
| 特定の遺伝子変異あり | 対応する分子標的薬への高い感受性 | 分子標的薬治療を第一選択とする |
| PD-L1高発現 | 免疫チェックポイント阻害薬への良好な反応 | 免疫療法を検討する |
| 特異的なバイオマーカーなし | 従来の化学療法への一定の反応 | 標準的な化学療法を基本とする |
副作用のリスクを事前に把握する
治療反応性の評価は、副作用の予測にも役立ちます。薬の効き方と副作用の現れ方は、関連している場合があるからです。
例えば、特定の遺伝子タイプを持つ人は、ある抗がん剤による皮膚障害が出やすい、といったことが分かっています。
こうした情報を事前に知ることで、副作用に対する予防策を講じたり、症状が出た際に迅速に対応したりすることが可能になり、治療の安全性を高めることにつながります。
「効かない治療」を避けるために- 癌治療における個別化の重要性
がん治療において最も避けたいことの一つは、効果が期待できない治療を長期間続けてしまうことです。これは患者さんの身体的な負担を増やすだけでなく、貴重な時間を失うことにもなりかねません。
治療反応性を見極め、個別化医療を実践することは、このような事態を防ぎ、治療の効率と質を向上させる上で極めて重要です。
患者さん一人ひとりに合わせた治療計画
個別化医療とは、集団の平均的なデータに頼るのではなく、「個」に焦点を当てる医療です。
がんの遺伝子情報、バイオマーカーの状態、さらには患者さんの年齢、体力、併存疾患、ライフスタイルなどを総合的に考慮して、その人にとって最も良いと考えられる治療計画を立てます。
このアプローチにより、治療効果を最大化し、副作用を最小限に抑えることを目指します。
個別化医療と従来の治療の比較(患者さんから見た視点)
| 項目 | 個別化医療 | 従来の標準治療 |
|---|---|---|
| 治療法の選択 | 自身の癌の性質に基づいて選択 | がんの種類や進行度に基づいて選択 |
| 治療効果の期待 | より高い効果が期待できる | 平均的な効果が期待できる |
| 副作用のリスク | 予測しやすく、対策を立てやすい | 個人差が大きく予測が難しい場合がある |
個別化医療がもたらすメリット
個別化医療は、患者さんにとって多くのメリットをもたらします。自分のがんの性質を深く理解できることは、治療への主体的な参加を促し、精神的な安心感にもつながります。
個別化医療の主な利点
- 治療効果の向上
- 重篤な副作用の回避
- 不要な医療費の削減
- 患者さんのQOL(生活の質)の維持・向上
薬剤耐性を持つがん細胞の存在 – 治療が効きにくくなる理由
治療を開始した当初は非常によく効いていた薬が、しばらくすると効果を示さなくなることがあります。これは「薬剤耐性」と呼ばれる現象で、がん治療における大きな課題の一つです。
生き残ったがん細胞が薬の攻撃を回避するすべを身につけ、性質を変化させることで発生します。この薬剤耐性の出現も、治療反応性が変化する一例と言えます。
治療中に発生する薬剤耐性
薬剤耐性は、治療の過程で新たながん細胞の遺伝子変異が起こることなどが原因で発生します。
薬によって多くのがん細胞が死滅しても、ごく一部の耐性を持つ細胞が生き残り、それらが再び増殖を始めることで、治療が効かない状態(再発・再燃)に至ります。
そのため、治療中も定期的な効果判定を行い、耐性の兆候を早期に捉えることが大切です。
薬剤耐性の主な種類
| 耐性の種類 | 概要 | 例 |
|---|---|---|
| 一次耐性 | 治療開始時から薬が効かない状態 | 標的となる遺伝子変異がない |
| 獲得耐性 | 治療中に薬が効かなくなる状態 | 新たな遺伝子変異の出現 |
耐性を獲得したがん細胞を克服するために
薬剤耐性が現れた場合でも、治療の選択肢がなくなるわけではありません。
耐性の原因となっている新たな遺伝子変異を特定し、それに対応する別の分子標的薬に切り替えたり、化学療法や免疫療法など、異なる作用を持つ治療法を組み合わせたりすることで、再び治療効果を得られる可能性があります。
耐性を克服するための研究や新しい臨床試験も活発に行われています。
自身のタイプを知るための遺伝子パネル検査という選択肢
自分のがんがどのような遺伝子変異を持ち、どの治療薬に反応する可能性があるのか。それを包括的に調べるための強力なツールが「がん遺伝子パネル検査」です。
この検査は、一度に多数(数十から数百)のがん関連遺伝子を同時に調べ、個々のがんの設計図を詳細に解析します。
遺伝子パネル検査で何がわかるのか
遺伝子パネル検査により、治療薬の選択に直結する遺伝子変異(ドライバー遺伝子変異)の有無や、治療効果を予測するバイオマーカーの情報などを得ることができます。
標準治療が終了した、あるいは終了が見込まれる患者さんなどが対象となり、次の治療法を探すための重要な手がかりを提供します。
また、結果によっては、まだ承認されていない薬を試す「臨床試験」に参加できる可能性も見つかることがあります。
がん遺伝子パネル検査の概要
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 検査対象 | がん組織や血液 |
| 解析内容 | 多数のがん関連遺伝子の変異、増幅、融合など |
| 主な目的 | 治療標的の探索、薬剤感受性の予測、臨床試験のマッチング |
保険適用と臨床試験への参加
一部のがん遺伝子パネル検査は、特定の条件を満たす場合に保険適用となります。検査を受けることができるかどうかは、主治医との相談が必要です。
検査の結果、有効な治療薬が見つからない場合もありますが、自分のgがんの性質を正確に知ることは、今後の治療方針を考える上で非常に有益な情報となります。
また、検査で見つかった遺伝子異常によっては、国内外で実施されている臨床試験への参加という道が開けることもあります。
治療反応性の理解が拓く、今後の癌治療の可能性
治療反応性という概念は、もはやがん治療において欠かせないものとなっています。この考え方が浸透することで、癌治療はより精密で、より患者さん本位のものへと進化を続けています。
将来的には、がんの種類を問わず、遺伝子情報に基づいて治療法が選択される時代がさらに本格化していくでしょう。
新しい治療薬の開発へ
治療反応性の研究は、新しい治療薬の開発にも直結します。薬剤耐性の原因となる遺伝子変異を解明することで、その耐性を克服する新薬の開発が進められています。
また、希少ながん種や、これまで有効な治療法が少なかった種類のがんに対しても、遺伝子変異を標的とした治療薬開発の光が当たっています。
免疫療法と治療反応性の関係
近年、がん治療の大きな柱となった免疫療法(特に免疫チェックポイント阻害薬)においても、治療反応性の予測は重要なテーマです。
PD-L1というタンパク質の発現率などがバイオマーカーとして用いられていますが、まだ予測精度は十分とは言えません。
現在、免疫ががんに応答する力をより正確に予測するための、新しいバイオマーカーの研究が進められており、今後の発展が期待されます。
治療反応性研究の今後の方向性
- リキッドバイオプシー(血液検査)によるリアルタイムな反応性モニタリング
- AI(人工知能)を活用した複雑なデータ解析と治療効果予測
- 個々の患者さんに合わせた治療薬の組み合わせ(コンビネーション療法)の最適化
よくある質問
- 治療反応性は、治療の途中で変わることがありますか?
-
はい、変わる可能性があります。治療を続けるうちに、がん細胞が薬剤耐性を獲得し、薬が効きにくくなることがあります。
これは、がん細胞内で新たな遺伝子変異が起こることなどが原因です。そのため、定期的に治療効果判定を行い、必要に応じて再度検査を行い、治療方針を見直すことが重要です。
- 遺伝子パネル検査は誰でも受けられますか?
-
現在、保険診療で遺伝子パネル検査を受けられるのは、主に「標準治療がない固形がん」や「局所進行または転移があり、標準治療が終了(または終了見込み)の固形がん」の患者さんなど、特定の条件を満たす場合に限られます。
自費診療で受けることも可能ですが、まずは主治医に、ご自身が検査の対象となるか、どのようなメリットや限界があるかを相談することが大切です。
- 検査をしても、治療に結びつくバイオマーカーが見つからない場合はどうなりますか?
-
遺伝子パネル検査を行っても、必ずしもすべての患者さんで治療薬の選択につながるような遺伝子変異が見つかるわけではありません。
その場合は、従来の化学療法や、緩和ケアなどを含めた標準的な治療を継続することが基本となります。
しかし、検査で得られた自分のがんの詳しい遺伝子情報は、将来新しい薬が登場した際に役立つ可能性があり、決して無駄にはなりません。
現時点ではパネル検査を受けても、実際に治療薬が見つかり使用できる患者さんは全体の1〜2割程度であるという厳しい現実もあります。その点も含めて、検査を受けるかどうかを検討することが大切です。
がんの分類には、今回解説した「治療反応性」の他にも、がんがどのように広がりやすいかという性質で分ける「転移パターンによる分類」という考え方もあります。
がんが最初に発生した場所から、体の他の部位へどのように移動していくか(転移)の傾向を理解することは、治療方針や予後の予測において非常に重要です。
特に、リンパ節転移や血行性転移、あるいは特定の臓器に転移しやすいがんの性質などを知ることで、より包括的な視点からご自身の状態を把握できます。
以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ合わせてお読みください。
参考文献
GONZALEZ DE CASTRO, D., et al. Personalized cancer medicine: molecular diagnostics, predictive biomarkers, and drug resistance. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 2013, 93.3: 252-259.
PAJIC, Marina, et al. Preclinical strategies to define predictive biomarkers for therapeutically relevant cancer subtypes. Human genetics, 2011, 130.1: 93-101.
DUFFY, Michael J.; O’DONOVAN, Norma; CROWN, John. Use of molecular markers for predicting therapy response in cancer patients. Cancer treatment reviews, 2011, 37.2: 151-159.
NALEJSKA, Ewelina; MĄCZYŃSKA, Ewa; LEWANDOWSKA, Marzena Anna. Prognostic and predictive biomarkers: tools in personalized oncology. Molecular diagnosis & therapy, 2014, 18.3: 273-284.
WANG, Richard C.; WANG, Zhixiang. Precision medicine: disease subtyping and tailored treatment. Cancers, 2023, 15.15: 3837.
WOLF, Denise M., et al. Redefining breast cancer subtypes to guide treatment prioritization and maximize response: Predictive biomarkers across 10 cancer therapies. Cancer cell, 2022, 40.6: 609-623. e6.
SHEN, John Paul. Artificial intelligence, molecular subtyping, biomarkers, and precision oncology. Emerging topics in life sciences, 2021, 5.6: 747-756.
DAI, Xiaofeng, et al. Cancer hallmarks, biomarkers and breast cancer molecular subtypes. Journal of cancer, 2016, 7.10: 1281.
LA THANGUE, Nicholas B.; KERR, David J. Predictive biomarkers: a paradigm shift towards personalized cancer medicine. Nature reviews Clinical oncology, 2011, 8.10: 587-596.
MALONE, Eoghan R., et al. Molecular profiling for precision cancer therapies. Genome medicine, 2020, 12.1: 8.
がんの臨床的分類に戻る