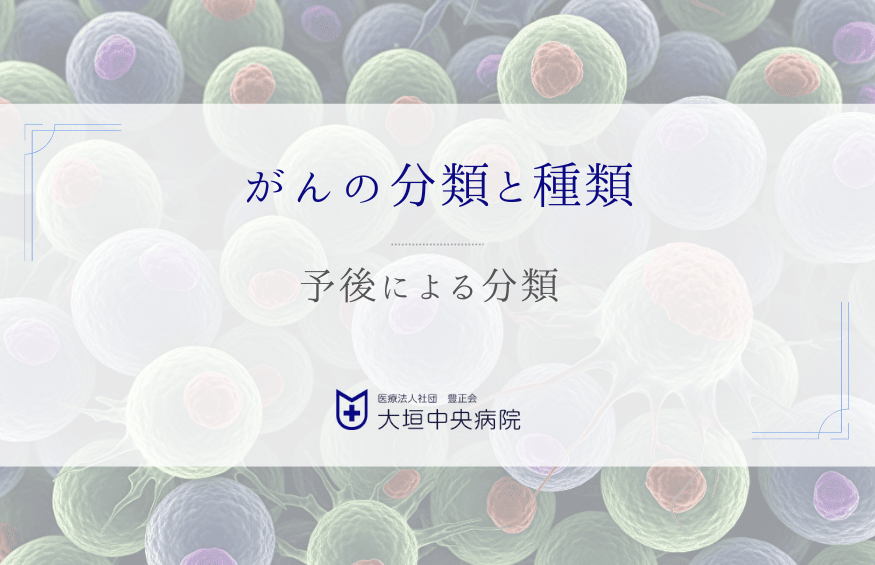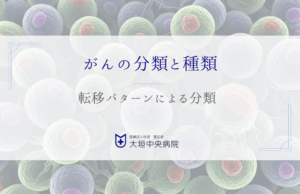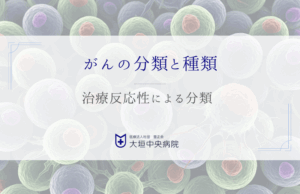がんと診断された時、多くの情報が一度に伝えられ、戸惑いを感じる方も少なくないでしょう。
特に「予後」という言葉は、ご自身の未来に関わる重要な情報でありながら、その本当の意味を正確に理解するのは簡単ではありません。
この記事では、がん治療の羅針盤ともいえる「予後による分類」について、その基本から治療方針との関わりまでを丁寧に解説します。
予後予測は、単に未来を言い当てるものではなく、あなたと医師が協力して、これから進むべき治療の道筋を考え、納得のいく選択をするための大切な情報です。
「予後」とは何か – 治療の道筋を示す言葉の本当の意味
「予後」という言葉を聞くと、漠然とした不安を感じるかもしれません。
しかし、医療における予後は、今後の病状の見通しを示す客観的な予測であり、治療計画を立てる上で非常に重要な役割を果たします。
この言葉の意味を正しく知り、どのように治療に活かしていくのかを理解することが、納得のいく医療への第一歩となります。
予後という言葉の正しい理解
予後とは、病気の経過や結末についての医学的な見通しを指します。これは占いのようなものではなく、これまで蓄積されてきた多くの患者さんの臨床データや統計に基づいた科学的な予測です。
具体的には、「治療によってがんが治る可能性はどのくらいか」「再発のリスクはどの程度か」「どのくらいの期間、病状が安定した状態でいられるか」といった見通しを示します。
医師はこれらの予後予測を基に、患者さん一人ひとりにとってどのような治療がより良い結果をもたらす可能性が高いかを判断します。
予後予測が治療方針にもたらす影響
予後予測は、治療方針を決定する際の重要な判断材料となります。例えば、予後が良いと予測される(治る可能性が高い、再発リスクが低い)場合は、身体への負担が少ない治療法を選択できる可能性があります。
一方で、予後が厳しいと予測される(進行が速い、再発リスクが高い)場合は、より強力な治療法を検討する必要があるかもしれません。
このように、予後予測は、治療の強さや種類、組み合わせを考える上で、医師と患者が共有すべき大切な情報です。
予後因子とは – 予測の根拠となる情報
予後を予測するためには、様々な情報が必要です。これらの予測の根拠となる個々の情報を「予後因子」と呼びます。
予後因子は、大きく分けて「患者さん自身の要因」と「がんの特性に関する要因」の2つに分類できます。
患者さん自身の要因
患者さん自身の状態も予後に影響を与えます。年齢や性別、全身の状態(Performance Status – PS)、合併している他の病気の有無などがこれにあたります。
同じ種類、同じステージのがんであっても、患者さんの体力や健康状態によって、治療の選択肢や治療への反応が異なるため、予後も変わってきます。
がんの特性に関する要因
がんそのものが持つ性質は、予後を大きく左右します。
がんの種類(組織型)、がんの広がり具合を示す病期(ステージ)、がん細胞の顔つきである悪性度(グレード)、特定の遺伝子変異の有無などが重要な予後因子です。
これらの情報を総合的に分析し、医師は予後を判断します。後の章で詳しく解説する「病期(ステージ)」や「悪性度」は、この中でも特に重要な予後因子です。
予後を左右する3つの鍵 – 病期(ステージ)、悪性度、遺伝子情報
がんの予後を予測し、適切な治療方針を立てるためには、がんの個性を多角的に評価することが重要です。
その中でも特に重要なのが、「病期(ステージ)」「悪性度(グレード)」「遺伝子情報」という3つの鍵です。
これらは、がんが今どのような状態にあるのか、そしてこれからどのように振る舞う可能性があるのかを教えてくれる、治療戦略における中心的な情報となります。
病期(ステージ)- がんの広がりを示す指標
病期(ステージ)は、がんが体の中でどのくらい広がっているかを示す分類です。
がんが最初に発生した場所(原発巣)にとどまっているのか、周囲のリンパ節に及んでいるのか、あるいは他の臓器にまで転移しているのかを評価します。
ステージは通常、ローマ数字(I, II, III, IV)で表され、数字が大きくなるほど、がんが進行していることを意味します。このステージ分類は、治療方針を決定する上で最も基本的な情報となります。
がんの進行度を示す「病期」の重要性
病期は、がんの進行度を客観的に示す共通言語です。医師は病期に基づいて、手術、放射線治療、薬物療法といった治療法を単独で、あるいは組み合わせて行う計画を立てます。
例えば、早期のがん(ステージIなど)では手術で取り除く治療が中心となることが多い一方、進行したがん(ステージIVなど)では全身に効果が及ぶ薬物療法が治療の中心となります。
患者さん自身がご自身の病期を理解することは、治療の全体像を把握する上で非常に大切です。
主な予後因子
| 因子カテゴリ | 主な因子 | 概要 |
|---|---|---|
| がんの特性 | 病期(ステージ) | がんの広がり。治療方針決定の基本となる。 |
| がんの特性 | 悪性度(グレード) | がん細胞の顔つき。増殖の速さや転移のしやすさを示す。 |
| 患者の要因 | 全身状態(PS) | 日常生活の制限度。治療への耐性を示す。 |
悪性度(グレード)- がん細胞の顔つき
悪性度(グレード)は、がん細胞の「顔つき」や「性質」を示す指標です。顕微鏡でがん組織を観察し、正常な細胞とどれくらい異なっているかで判断します。
悪性度が高い細胞ほど、正常な細胞とは似ていない形をしており、増殖するスピードが速く、転移しやすい性質を持つ傾向があります。
このため、悪性度は再発のリスクを予測する上で重要な予後因子となります。
悪性度の診断が示す再発リスク
悪性度は通常、「グレード1(G1)」から「グレード3(G3)」または「グレード4(G4)」のように分類します。
グレード1は正常細胞に近く、おとなしい性質(高分化型)であるのに対し、数字が大きくなるにつれて正常細胞との違いが大きくなり、攻撃的な性質(低分化型)を持つことを示します。
同じステージのがんであっても、悪性度が高い場合は再発リスクが高いと判断され、より積極的な治療を検討することがあります。
遺伝子情報 – 個別化医療への扉
近年、がん細胞の遺伝子情報を調べることで、さらに詳細な予後予測や治療方針の決定が可能になってきました。
特定のがん遺伝子の変異や、ある種のタンパク質の発現などを調べることで、薬の効果を予測したり、再発のリスクをより正確に評価したりします。
例えば、特定のがん遺伝子変異が見つかった場合、その遺伝子を標的とする分子標的薬という種類の薬が劇的な効果を示すことがあります。
がんの遺伝子情報は、画一的な治療から、患者さん一人ひとりの「がんの個性」に合わせた個別化医療を実現するための鍵となります。
がんの進行度を示す「ステージ分類」の基本
がんの治療方針を考える上で、まず基本となるのが「ステージ分類」です。これは、がんの進行度を客観的な基準で評価し、分類するものです。
世界中の医師が共通の認識でがんの状態を把握し、標準的な治療法を検討するために、国際的に広く用いられている「TNM分類」がその基盤となっています。
世界共通の指標「TNM分類」
TNM分類は、がんの広がりを3つの異なる側面から評価する方法です。それぞれのアルファベットが示す意味を理解することで、ご自身の診断内容をより深く把握できます。
TNM分類の各因子の意味
| 因子 | 評価する内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| T (Tumor) | 原発巣の大きさや広がり | がんが最初にできた場所での大きさや、周囲の組織への浸潤の程度。T1からT4のように数字が大きくなるほど進行している。 |
| N (Nodes) | 所属リンパ節への転移 | がん細胞が原発巣の近くにあるリンパ節に転移しているかどうか、またその個数や範囲。N0(転移なし)からN3のように分類する。 |
| M (Metastasis) | 遠隔転移の有無 | がん細胞が血液やリンパの流れに乗って、原発巣から離れた他の臓器(肺、肝臓、骨など)に転移しているかどうか。M0(転移なし)かM1(転移あり)で示す。 |
これらのT、N、Mの3つの因子をそれぞれ評価し、その組み合わせによって総合的なステージ(病期)が決定されます。
例えば、「T1N0M0」という診断は、「原発巣は小さいサイズで、リンパ節転移や遠隔転移はない」という状態を示し、多くの場合、早期のがんであるステージIに分類されます。
TNM分類からステージ(病期)が決まる流れ
TNM分類の評価が終わると、医師はその組み合わせを「UICC-TNM分類」や各がん種の「取扱い規約」といった基準に照らし合わせ、最終的なステージを決定します。
このステージは、治療方針を決定するための最も重要な情報の一つです。
ステージ分類の例(大腸がんの場合)
| ステージ | TNM分類の組み合わせ(一例) | 状態の概要 |
|---|---|---|
| I | T1 N0 M0, T2 N0 M0 | がんが腸の壁の浅い層にとどまっている。 |
| II | T3 N0 M0, T4 N0 M0 | がんが腸の壁の深い層に達しているが、リンパ節転移はない。 |
| III | Any T N1-2 M0 | リンパ節への転移があるが、遠隔転移はない。 |
| IV | Any T Any N M1 | 肝臓や肺など、他の臓F器への遠隔転移がある。 |
各がん種で異なるステージ分類の考え方
TNM分類は多くの固形がんで用いられる基本的な考え方ですが、ステージを決定するためのTNMの組み合わせ方は、がんの種類によって異なります。
例えば、同じTNMの評価でも、胃がんと肺がんとでは最終的なステージが異なる場合があります。これは、がんの性質や進行の仕方が臓器によって違うためです。
また、血液のがんのように、固形のしこりを作らないがんでは、TNM分類とは異なる独自の分類法を用います。
ご自身の診断について理解を深めるためには、担当の医師から、ご自身のがん種に特有の分類法について説明を受けることが重要です。
分類が導く治療戦略 – あなたに合った医療を選択するために
がんの分類は、単に状態を整理するためだけのものではありません。
その最大の目的は、一人ひとりの患者さんにとって、より効果が期待でき、かつ身体への負担とのバランスが取れた治療戦略を立てることにあります。
ステージや悪性度といった分類結果は、膨大な臨床研究の積み重ねから導き出された「標準治療」へとつながる道しるべです。
ステージ(病期)ごとの標準的な治療方針
がん治療の基本は、ステージ(病期)に応じた標準治療です。標準治療とは、現時点で最も効果が高いと科学的に証明されている治療法を指します。
ステージ分類によって、手術、放射線治療、薬物療法(抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など)をどのように用いるか、大まかな方針が決まります。
ステージと主な治療法の関係
| ステージ | がんの状態 | 主な治療方針 |
|---|---|---|
| I期・II期 | 早期がん・比較的早期 | 手術や放射線治療など、がんのある場所を局所的に治療することが中心。再発リスクに応じて術後に薬物療法を追加する場合がある。 |
| III期 | 局所進行がん | 手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせた集学的治療を行うことが多い。 |
| IV期 | 遠隔転移のある進行がん | 薬物療法など、全身に効果を及ぼす治療が中心となる。生活の質(QOL)を維持することも重要な目標。 |
予後因子を考慮した治療法の調整
標準治療はあくまで基本的な方針であり、実際の治療は、他の予後因子を考慮して個別に調整します。特に、がん細胞の悪性度や再発のリスクは、治療の強さを決める上で重要な判断材料となります。
悪性度が高い場合の治療の考え方
例えば、同じステージIIの診断であっても、悪性度(グレード)が高いがんは、低いがんに比べて増殖が速く、転移や再発を起こしやすい性質を持っています。
そのため、医師は再発リスクが高いと判断し、手術後に補助的に抗がん剤治療を行うことを提案するかもしれません。
このように、悪性度の診断は、標準治療の枠組みの中で、より個人に合わせた治療を選択するための重要な情報となります。
再発リスクに応じた治療の選択
再発のリスク評価には、悪性度だけでなく、がんの遺伝子情報なども用いられるようになっています。例えば、一部の乳がんでは、術後の組織を用いた遺伝子検査により、再発の可能性をスコア化します。
そのスコアが高い患者さんには化学療法を追加し、低い患者さんにはホルモン療法のみを行う、といった判断が可能です。
これにより、不要な治療を避け、本当に治療が必要な患者さんに適切な医療を提供することにつながります。
患者の希望と医師の説明を統合する
最終的な治療方針は、これらの医学的な情報だけで決まるものではありません。
医師からの十分な説明を受け、治療の目的、期待できる効果、そして起こりうる副作用について患者さん自身が理解することが重要です。
その上で、ご自身の年齢、体力、生活環境、そして人生で大切にしたいことなどを医師と共有し、共に治療方針を決定していきます。予後による分類は、その対話のための客観的な土台を提供するものなのです。
統計データとの向き合い方 – 予後予測は未来の決定ではない
予後の説明を受ける際、しばしば「生存率」という言葉が用いられます。
これは客観的なデータに基づいていますが、数字そのものが一人歩きしてしまい、大きな不安や誤解を生むこともあります。
統計データはあくまで過去の集団の傾向を示すものであり、あなた個人の未来を決定づけるものではありません。データとの正しい向き合い方を理解することが大切です。
生存率データの正しい解釈
生存率は、がんの予後を示す代表的な指標の一つですが、その意味を正しく理解する必要があります。
5年相対生存率とは何か
がん統計でよく使われるのが「5年相対生存率」です。
これは、あるがんと診断された人のうち、5年後に生存している人の割合が、日本人全体の5年後の生存率と比べてどのくらいかを示す数値です。
100%に近いほど治療で生命を脅かされる可能性が低いことを意味します。この指標は、がん以外の原因で亡くなる方の影響を取り除いて、純粋にそのがんによる生命への影響を評価するために用いられます。
生存率は集団のデータであることの理解
最も重要なことは、生存率はあなたと同じ病状を持つ多くの患者さんのデータを集計した「平均値」であるという点です。
例えば、5年生存率が70%と聞いて、「自分は30%の確率で5年以内に亡くなる」と考えるのは正確ではありません。
この70%という集団の中には、5年後も元気に過ごしている方がたくさんいますし、残念ながら再発を経験する方も含まれています。
あなたは集団の中の一人ですが、その集団の平均がそのままあなたの経過になるわけではありません。
生存率データを見る際の注意点
- 過去のデータであること(診断・治療技術は進歩している)
- 年齢や合併症などの個人差は反映されていない
- あくまで集団の傾向であり、個人の未来を予測するものではない
あくまで予測 – 個人の経過は様々
医師が示す予後は、これまでの経験とデータに基づく最善の「予測」です。しかし、人間の体は複雑であり、同じ診断、同じ治療を受けても、その後の経過は一人ひとり異なります。
予測よりもずっと長く元気に過ごされる方もいれば、予期せぬ経過をたどる方もいます。
予後予測は、治療の大きな方向性を決めるための参考情報と捉え、数字に一喜一憂しすぎないことが心の安定につながります。
データに惑わされず、前向きに治療と向き合う
統計データは冷静に受け止めつつも、それ以上に大切なのは、今ご自身が受けられる最善の治療に集中することです。
医療は日々進歩しており、過去のデータが作られた時代よりも新しい治療法が登場している可能性もあります。
予後予測は参考情報の一つとして心に留め、担当の医師を信頼し、ご自身の体の声に耳を傾けながら、一日一日を大切に過ごすことが重要です。
自分の癌を理解する – 医師との対話で確認すべきポイント
予後による分類を理解し、納得のいく治療を選択するためには、医師との対話が欠かせません。
診断や治療方針について、ただ説明を受けるだけでなく、積極的に質問し、ご自身の状況を正確に把握することが重要です。ここでは、医師との対話の際に確認しておきたいポイントを整理します。
診断内容の正確な把握
まずは、ご自身のがんがどのような状態なのかを正確に知ることが全ての基本です。以下の点について、具体的な説明を求めましょう。
自分の病期(ステージ)とTNM分類
ご自身のがんのステージと、その根拠となったTNM分類(T、N、Mがそれぞれ何であったか)を明確に確認しましょう。これにより、がんの広がり具合を具体的にイメージできます。
医師への確認事項リスト
- 私のがんの正確な病名(組織型)は何ですか?
- 私の病期(ステージ)とTNM分類を教えてください。
- がんの悪性度(グレード)はどのくらいですか?
- 治療の目的は何ですか?(根治を目指すのか、進行を抑えるのか)
悪性度(グレード)についての説明
ステージだけでなく、がん細胞の性質である悪性度(グレード)についても尋ねてみましょう。「悪性度は高いですか、低いですか?」と聞くだけでも、がんの勢いについての理解が深まります。
これが今後の再発リスクや治療法の選択にどう影響するのかも併せて確認すると良いでしょう。
治療方針に関する質問
次に、なぜその治療法が提案されているのか、その根拠を理解することが大切です。治療への納得感を高め、主体的に臨むために、以下の点を確認しましょう。
提示された治療法の根拠
「なぜ私のステージや悪性度に対して、この治療法が推奨されるのですか?」と質問することで、医師がどのような考えで治療方針を立てたのかを知ることができます。
標準治療に基づいているのか、何か特別な理由があるのかを確認しましょう。
治療による効果とリスクのバランス
| 確認すべき項目 | 質問の例 | 得られる理解 |
|---|---|---|
| 期待される効果 | 「この治療で、どのような効果が期待できますか?」 | 治療の目標(治癒、延命、症状緩和など)が明確になる。 |
| 副作用・リスク | 「どのような副作用が、どのくらいの確率で起こりますか?」 | 副作用への心構えと対策を立てられる。 |
| 他の選択肢 | 「他に考えられる治療法はありますか?その長所と短所は何ですか?」 | 提示された治療法を客観的に評価できる。 |
予後に関する説明の受け止め方
予後について尋ねることは、勇気がいるかもしれません。しかし、今後の見通しを知ることは、心の準備や人生設計をする上で助けになる場合もあります。
もし予後について聞きたい場合は、ご自身がどの程度の情報を求めているかを医師に伝えることが大切です。
「平均的なデータとして教えてほしい」「厳しい見通しであっても、正直に伝えてほしい」など、希望を伝えてみましょう。
そして、伝えられた情報はあくまで統計的な予測であることを忘れずに、冷静に受け止めるよう心がけましょう。
予後分類を知ることで拓ける、納得のいく治療への道
がんの予後による分類について理解を深めることは、単に医学知識を得る以上の意味を持ちます。
それは、患者さん自身が治療の主体となり、医師と対等なパートナーとして、共にがんに立ち向かうための基盤を築く作業です。
正しい情報に基づいた理解は、不安を軽減し、未来への一歩を踏み出す力を与えてくれます。
情報がもたらす心の準備
自分の状況を客観的に把握することは、これから起こりうる事態に対して心の準備をする助けとなります。
どのような治療が行われ、どのような経過をたどる可能性があるのか、大まかな見通しが立つことで、漠然とした不安が具体的な課題へと変わります。
治療に伴う生活の変化にも計画的に備えることができます。
治療への主体的な参加
予後分類や治療方針の根拠を理解すると、なぜ今この治療が必要なのか、その意味を自分自身で納得できます。これにより、治療への取り組み方が「受け身」から「主体的」なものへと変わります。
治療の目標を医師と共有し、同じ方向を向いて進んでいるという感覚は、困難な治療を乗り越える上での大きな支えとなります。
治療への向き合い方の変化
| 視点 | 情報がない状態 | 情報を理解した状態 |
|---|---|---|
| 医師との関係 | 一方的に指示を受ける | 相談し、共に決定するパートナー |
| 治療への姿勢 | 漠然とした不安の中で受動的になる | 目的を理解し、主体的に参加する |
| 将来への見通し | 不確実性への恐怖が強い | 見通しに基づいた心の準備ができる |
医師との信頼関係の構築
予後分類という共通の言語を持つことで、医師との対話はより深く、具体的なものになります。患者さんが自身の病状を理解しようと努める姿勢は、医師にも伝わります。
疑問点を率直に質問し、自身の希望を伝えることで、互いの理解が深まり、治療のパートナーとしての信頼関係が育まれます。
この信頼関係こそが、長期にわたるがん治療を乗り越えるための最も重要な土台となるのです。
予後分類を知ることは、決して怖いことばかりではありません。それは、あなた自身の治療の物語を、あなたが主役となって紡いでいくための、最初のページを開くことなのです。
よくある質問(Q&A)
このセクションでは、がんの予後による分類に関して、患者さんやご家族からよく寄せられる質問にお答えします。
- ステージIVと診断されたら、もう治療法はないのでしょうか?
-
いいえ、そのようなことはありません。ステージIVは、がんが最初にできた臓器から他の臓器へ遠隔転移している状態を指し、一般的に手術で完全に取り除くことは難しい場合が多いです。
しかし、治療法がないわけではありません。
近年の薬物療法の進歩は目覚ましく、新しい分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬などによって、がんの進行を長期間コントロールしたり、症状を和らげたりすることが可能になってきています。
ステージIVの治療の目標は、がんと共存しながら、いかに自分らしい生活を長く維持するか、という点に置かれます。
治療法は常に進歩していますので、希望を失わずに担当の医師とよく相談することが重要です。
- 5年生存率が低いと診断されました。希望は持てないのでしょうか?
-
5年生存率は、あくまで過去に診断された多くの患者さんの統計データであり、あなた個人の未来を予言するものではありません。
このデータには、様々な年齢や健康状態の人が含まれており、また、データが収集された時点よりも新しい、より効果的な治療法が現在では利用可能になっている場合も多くあります。
数字は一つの参考情報として冷静に受け止め、それに一喜一憂するのではなく、今あなたにとって最善の治療は何かを考え、それに集中することが大切です。
希望を持って治療に取り組む気持ちは、治療効果にも良い影響を与えると言われています。
- 予後について、医師にどこまで詳しく聞くべきですか?
-
これは患者さん個人の考え方によりますので、絶対的な正解はありません。
「平均的な余命など、厳しい情報も含めてすべて知りたい」という方もいれば、「数字は聞かずに、目の前の治療に集中したい」という方もいます。
大切なのは、ご自身がどうしたいのかを考え、その気持ちを正直に医師に伝えることです。医師は患者さんの気持ちを尊重します。
もし気持ちが決まらない場合は、「多くの患者さんは、この状況でどのような経過をたどることが多いですか?」といった形で、少し距離を置いた聞き方をしてみるのも一つの方法です。
ご家族と相談してみるのも良いでしょう。
予後の聞き方に関する考え方
タイプ 考え方 医師への伝え方の例 詳細把握型 全ての情報を知った上で、今後の人生設計を考えたい。 「統計的なデータも含め、予後について詳しく教えてください。」 治療集中型 詳細な数字を聞くと不安になるので、今は治療に集中したい。 「今は予後の数字よりも、治療のことだけを考えたいです。」 段階的把握型 まずは大まかな見通しを知り、心の準備ができたら詳しく聞きたい。 「まず、今後の見通しについて大まかに教えていただけますか?」
がんの治療法は、がん細胞そのものの特徴によっても大きく左右されます。
特に、薬物療法に対する反応性(効きやすさ)で分類する考え方は、近年の治療戦略においてますます重要になっています。
次の記事『治療反応性による分類 – あなたのがんに最適な薬を見つけるために』では、遺伝子変異やタンパク質の発現など、薬の効果を予測する指標に焦点を当て、個別化医療の最前線を詳しく解説します。
予後分類と合わせて理解することで、ご自身の治療について、より深く多角的な視点を持つことができるでしょう。
参考文献
SOBIN, Leslie H. TNM: evolution and relation to other prognostic factors. In: Seminars in surgical oncology. Hoboken: Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company, 2003. p. 3-7.
BURKE, Harry B. Outcome prediction and the future of the TNM staging system. Journal of the National Cancer Institute, 2004, 96.19: 1408-1409.
CHANSKY, Kari, et al. The International Association for the Study of Lung Cancer Staging Project: prognostic factors and pathologic TNM stage in surgically managed non-small cell lung cancer. Journal of thoracic oncology, 2009, 4.7: 792-801.
SOBIN, Leslie H. TNM: principles, history, and relation to other prognostic factors. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society, 2001, 91.S8: 1589-1592.
PARK, Y. H., et al. Clinical relevance of TNM staging system according to breast cancer subtypes. Annals of oncology, 2011, 22.7: 1554-1560.
VERONESI, Umberto, et al. Rethinking TNM: breast cancer TNM classification for treatment decision-making and research. The Breast, 2006, 15.1: 3-8.
GETTMAN, Matthew T., et al. Pathologic staging of renal cell carcinoma: significance of tumor classification with the 1997 TNM staging system. Cancer, 2001, 91.2: 354-361.
HORTOBAGYI, Gabriel N.; EDGE, Stephen B.; GIULIANO, Armando. New and important changes in the TNM staging system for breast cancer. Am Soc Clin Oncol Educ Book, 2018, 38: 457-467.
TAKES, Robert P., et al. Future of the TNM classification and staging system in head and neck cancer. Head & neck, 2010, 32.12: 1693-1711.
がんの臨床的分類に戻る