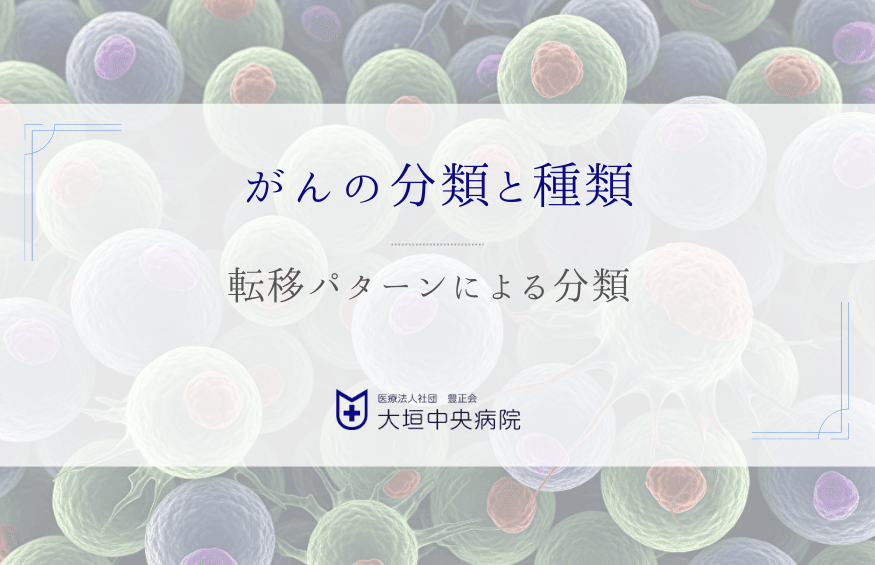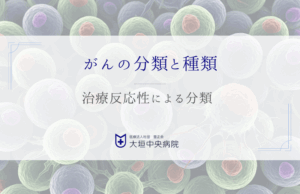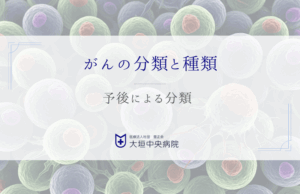「がんが転移する」と聞くと、多くの方が不安を感じるでしょう。しかし、がんの転移は無秩序に起こるわけではなく、一定の傾向やパターンが存在します。
この記事では、がんがどのように広がり、どこへ向かうのかという「転移パターン」に基づいた分類について詳しく解説します。
この知識は、ご自身の病状を深く理解し、医師と共に治療方針を考える上で大きな助けとなります。
がんの「個性」ともいえる転移の性質を知ることで、今後の見通しを立て、より納得して治療に臨むための第一歩を踏み出しましょう。
転移パターンによる分類とは何か – がんの個性を知る
がんの診断を受けると、多くの場合「ステージ」という言葉を耳にします。これは主に「TNM分類」という国際的な基準に基づいて決定します。
この分類は、がんの広がりを評価する上で非常に重要ですが、それだけががんの性質を示すものではありません。
がん細胞が最初に発生した場所(原発巣)から、どのようにして体の他の部分へ広がっていくか、その道筋や傾向にも特徴があります。この「転移の道筋」に注目した分類が、転移パターンによる分類です。
がんの種類によって、特定の臓器に転移しやすい、特定のルートを通りやすいといった「個性」があり、それを理解することが治療戦略を立てる上で役立ちます。
がんの広がりを示すTNM分類
がんの進行度を評価する世界共通の基準がTNM分類です。
これは、がんそのものの大きさ、リンパ節への転移の有無、そして他の臓器への遠隔転移の有無という3つの要素を組み合わせて、病状のステージを決定します。
- T (Tumor) – 原発巣のがんの大きさや周囲への広がり
- N (Node) – 所属リンパ節(がんの近くにあるリンパ節)への転移の有無と範囲
- M (Metastasis) – 体の他の臓器への遠隔転移の有無
これらの組み合わせから、がんはステージIからIVまでに分類され、数字が大きくなるほど進行していることを示します。
このステージ分類は、治療方針の決定や予後(治療後の経過の見通し)を予測する上で基本となる情報です。
がんの分類方法の比較
| 分類方法 | 主な目的 | 注目する点 |
|---|---|---|
| TNM分類(ステージ分類) | がんの進行度を評価する | がんの大きさ、リンパ節転移、遠隔転移 |
| 組織型分類 | がん細胞の顔つきを調べる | 顕微鏡で見た細胞の種類や形 |
| 転移パターンによる分類 | がんの広がり方の傾向を把握する | 転移のルート(リンパ行性、血行性など) |
転移のパターンを知る意義
TNM分類ががんの「現在地」を示す地図だとすれば、転移パターンはがんが進む「ルート」を示すものです。
例えば、ある種類のがんはリンパの流れに乗りやすく、また別のがんは血液に乗って遠くの臓器を目指しやすい、といった特徴があります。
このルートを予測できれば、転移が起こりやすい場所を重点的に検査したり、先回りして治療を行ったりするなど、より戦略的な対応が可能になります。
これは、ご自身の体のなかで何が起きているのかを理解し、今後の治療計画を立てる上で非常に重要な情報です。
リンパの流れに乗るがん細胞 – リンパ行性転移の基本
私たちの体には、血管の他にリンパ管という管が網の目のように張り巡らされています。リンパ管の中にはリンパ液が流れており、免疫機能などを担っています。
がん細胞が原発巣から剥がれ落ち、このリンパ管に入り込んでリンパの流れに乗り、別の場所で再び増殖することがあります。
これを「リンパ行性転移」と呼びます。リンパ管の途中には、関所のような役割を持つ「リンパ節」があり、転移はまずこのリンパ節で起こることが多いです。
リンパ節の役割と転移
リンパ節は、体内に侵入した細菌やウイルスを食い止めるフィルターの役割を持っています。
がん細胞もここでせき止められることがあり、そのため、原発巣の近くにあるリンパ節(所属リンパ節)は、がんが最初に転移する場所としてよく知られています。
手術の際に、このリンパ節を一緒に切除して転移の有無を調べるのは、がんの広がりを正確に把握するためです。
リンパ節に転移があるかどうかは、その後の治療方針や予後を左右する重要な判断材料となります。
リンパ行性転移しやすいがんの例
| がんの種類 | 特徴 | 最初の転移先となりやすいリンパ節 |
|---|---|---|
| 乳がん | 腋窩(わきの下)のリンパ節への転移が多い | 腋窩リンパ節 |
| 胃がん | 胃の周囲にある多数のリンパ節へ転移する | 胃周囲リンパ節 |
| 肺がん | 肺門部や縦隔(左右の肺の間)のリンパ節へ転移する | 肺門・縦隔リンパ節 |
センチネルリンパ節生検
かつては、転移の可能性のあるリンパ節を広範囲に切除する手術(リンパ節郭清)が一般的でした。しかし、この方法は腕や足のむくみ(リンパ浮腫)などの後遺症を引き起こすことがあります。
そこで近年、乳がんや悪性黒色腫などの治療で「センチネルリンパ節生検」という検査と考え方を取り入れることが増えました。
センチネルリンパ節とは「見張りリンパ節」とも呼ばれ、原発巣からのがん細胞が最初にたどり着くリンパ節のことです。このリンパ節を特定し、ごくわずかに切除して転移の有無を調べます。
もし、ここに転移がなければ、それより先のリンパ節にも転移している可能性は低いと判断し、不要なリンパ節の切除を避けることができます。
これにより、患者さんの体への負担を大きく減らすことが可能になります。
血液を通じて全身へ – 血行性転移の特徴と標的臓器
がん細胞はリンパ管だけでなく、血管に入り込んで血液の流れに乗って全身を旅することもあります。そして、体の遠く離れた臓器にたどり着き、そこで新たな塊(腫瘍)を作ります。
これを「血行性転移」と呼び、一般的に「遠隔転移」として知られる状態の多くがこれにあたります。血行性転移は、がんが原発巣から離れた場所に広がる主な経路であり、治療をより複雑にする要因の一つです。
しかし、どのがんがどの臓器に転移しやすいかという傾向、つまり「標的臓器」が存在することも分かっています。
がん細胞が血管に侵入するまで
原発巣で増殖したがん細胞は、まず周囲の組織に染み込むように広がっていきます(浸潤)。その過程で、毛細血管などの壁を壊して血管内に侵入します。
血流に乗ったがん細胞は、体の様々な場所へと運ばれますが、全ての細胞が転移に成功するわけではありません。多くは免疫細胞によって排除されたり、血流の圧力に耐えられなかったりします。
しかし、一部の生命力の強いがん細胞が、特定の臓器の細い血管に引っかかり、そこで血管の壁を再び破って組織の中に入り込み、増殖を始めます。これが血行性転移の始まりです。
標的臓器の存在
がんの種類によって、血行性転移しやすい臓器には一定の傾向があります。
これは、各臓器の血流量や、がん細胞がそこで生き延びて増殖しやすい環境(いわば「土壌」のようなもの)があるかどうかに関係していると考えられています。
例えば、肺は全身から血液が集まる場所であるため、様々ながんの転移先となりやすいです。肝臓も同様に血流が豊富なため、特に消化器系のがんの転移が多く見られます。
血行性転移の主な標的臓器と関連するがん
| 転移先(標的臓器) | 転移しやすい原発巣のがん | 主な症状 |
|---|---|---|
| 肺 | 乳がん、大腸がん、腎がんなど | 長引く咳、血痰、息切れ |
| 肝臓 | 胃がん、大腸がん、膵臓がんなど | 腹部の張り、黄疸、倦怠感 |
| 骨 | 乳がん、前立腺がん、肺がんなど | 痛み、骨折、高カルシウム血症 |
| 脳 | 肺がん、乳がん、悪性黒色腫など | 頭痛、吐き気、麻痺、けいれん |
腹腔・胸腔への広がり – 播種と呼ばれる転移のかたち
転移には、リンパや血液の流れに乗るものとは異なる特殊なタイプも存在します。その一つが「播種(はしゅ)」です。
これは、がん細胞が原発巣の表面から直接、腹腔(お腹の中の空間)や胸腔(胸の中の空間)に種をまくように散らばって広がる転移の様式を指します。
腹腔に広がった場合を「腹膜播種」、胸腔に広がった場合を「胸膜播種」と呼びます。このタイプの転移は、特に胃がんや卵巣がん、肺がんなどで見られ、治療が難しいケースの一つとされています。
腹膜播種とは
腹腔の内側は、腹膜という薄い膜で覆われています。胃がんや大腸がん、卵巣がんなどが進行し、臓器の最も外側の膜を突き破ると、がん細胞がお腹の中にこぼれ落ちることがあります。
これらの細胞が腹膜の表面に生着し、無数の小さな転移巣を作ります。これが腹膜播種です。進行すると、お腹に水が溜まる「腹水」の原因となったり、腸閉塞を引き起こしたりすることがあります。
播種が起こりやすい部位と関連するがん
| 播種の種類 | 広がる場所 | 関連する主な原発巣のがん |
|---|---|---|
| 腹膜播種 | 腹腔内 | 胃がん、卵巣がん、大腸がん、膵臓がん |
| 胸膜播種 | 胸腔内 | 肺がん、乳がん |
胸膜播種と胸水
同様に、肺がんなどが肺を覆っている胸膜を破ると、がん細胞が胸腔内に散らばり、胸膜播種を引き起こします。
胸膜の表面でがん細胞が増殖すると、炎症が起きて胸の中に水が溜まる「がん性胸膜炎(胸水)」という状態になります。胸水が大量に溜まると肺が圧迫され、息切れや呼吸困難の原因となります。
播種による転移は、手術で完全に取り除くことが難しく、多くの場合、薬物療法が治療の中心となります。
なぜ、播種は手術で取りきれないのか
「播種」は、その名の通り「種をまく」ようにがん細胞が広がります。
これをイメージしやすく言うと、お腹や胸の中に「細かい砂粒やゴマをバラバラとまき散らしたような状態」です。
塊(かたまり)として存在しているがんであれば手術で切り取ることができますが、砂粒のように無数に広がり、臓器の隙間に入り込んだがん細胞を、一つひとつメスで完全に取り除くことは物理的に不可能です。
無理に取ろうとすれば、広範囲の臓器を傷つけてしまうことになります。だからこそ、薬物療法が主役になります。
そのため、播種が見つかった場合、治療の主役は「手術」から「薬物療法(抗がん剤)」へと切り替わります。
薬であれば、血液に乗って全身を巡ったり、腹腔内に直接行き渡ったりすることで、目に見えない無数の小さな種(がん細胞)をまとめて攻撃することができるからです。
原発不明癌の謎を解く鍵 – 転移巣から元の場所を推測する
通常、がんは原発巣が見つかり、その後に転移巣が発見されます。
しかし、時には先に転移巣が見つかり、全身を詳しく検査しても、がんが最初にどこから発生したのか(原発巣)が特定できない場合があります。
これを「原発不明癌」と呼びます。がん全体の数パーセントを占めるとされ、治療方針を立てるのが難しい病気です。
しかし、このような状況でも、転移のパターンや転移したがん細胞の性質を詳しく調べることで、元の臓器を推測し、有効な治療法を探る手がかりを得ることができます。
転移巣の病理検査の重要性
原発不明癌の診断では、転移巣から採取した組織を顕微鏡で詳しく調べる「病理検査」が極めて重要です。がん細胞は、元の臓器の細胞の性質(顔つき)をある程度保っていることが多いからです。
例えば、肺に転移したがん細胞を調べて、それが明らかに消化管の細胞の特徴を持っていれば、原発巣は胃や大腸にある可能性が高いと推測できます。
さらに「免疫染色」という特殊な検査を行うことで、細胞がどのような種類のタンパク質を持っているかを調べ、より詳しく原発巣を絞り込んでいきます。
原発不明癌の原発巣推定に用いる主な検査
| 検査の種類 | 目的 | 分かることの例 |
|---|---|---|
| 病理組織検査 | 転移したがん細胞の顔つきを調べる | 腺がんか扁平上皮がんかなどの大まかな分類 |
| 免疫染色検査 | がん細胞が持つ特有のタンパク質を調べる | 肺がん由来か、消化器がん由来かなどの推定 |
| 遺伝子検査 | がん細胞の遺伝子変異を調べる | 特定の遺伝子変異に効く分子標的薬の適応 |
画像診断と腫瘍マーカー
病理検査と並行して、CTやPET-CTなどの高度な画像診断を行い、体内に隠れている可能性のある原発巣を探します。また、血液検査で「腫瘍マーカー」の値を調べることも有力な手がかりとなります。
腫瘍マーカーは、がん細胞が作り出す特殊な物質で、がんの種類によって特有のマーカーの値が高くなる傾向があります。
これらの情報を総合的に判断し、最も可能性の高い原発巣を推定し、そのがんに準じた治療を開始します。
原発不明癌の治療は、まさに転移パターンという手がかりを頼りに進める、謎解きのような側面を持っているのです。
転移ルートの予測が治療計画を変える – 手術・放射線・薬物療法の選択
がんの転移パターンを理解することは、診断だけでなく、具体的な治療計画を立てる上でも決定的に重要です。
がんがどのルートを通り、どこへ向かう可能性が高いかを予測することで、三大治療法である「手術」「放射線療法」「薬物療法」をどのように組み合わせるか、その戦略が変わってきます。
限局しているのか、リンパ節に留まっているのか、あるいはすでに遠隔転移しているのか。その状況に応じて、治療の目的や手段は大きく異なります。
治療法の選択と転移パターン
がんの治療は、その広がり具合によって大きく方針が異なります。
- 原発巣に限局している場合 – 手術や放射線療法による根治(完全に治すこと)を目指す局所治療が中心です。
- リンパ節転移がある場合 – 手術で原発巣とリンPA節を切除し、再発を防ぐために術後に薬物療法や放射線療法を追加することを検討します。
- 遠隔転移がある場合 – 基本的に全身にがん細胞が広がっていると考えられるため、薬物療法(抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など)による全身治療が主体となります。ただし、転移巣が少数で制御可能な場合は、放射線療法や手術を組み合わせることもあります。
転移の状況に応じた治療法の選択例
| がんの広がり | 主な治療目的 | 中心となる治療法 |
|---|---|---|
| 原発巣に限局(転移なし) | 根治 | 手術、放射線療法 |
| 所属リンパ節への転移 | 根治と再発予防 | 手術 + 薬物療法・放射線療法 |
| 遠隔臓器への転移 | 延命、症状緩和、QOL維持 | 薬物療法(全身治療) |
予後予測への活用
転移のパターンは、治療後の経過の見通しである「予後」を予測する上でも重要な因子です。
一般的に、転移がない場合に比べてリンパ節転移がある場合、さらに遠隔転移がある場合へと、段階的に予後は厳しくなる傾向があります。
しかし、近年は薬物療法の進歩が目覚ましく、遠隔転移があるステージIVのがんであっても、長期にわたってがんと共存しながら生活を送ることが可能になるケースも増えています。
転移のパターンとがんの性質を正確に把握し、一人ひとりに合った治療法を選択することが、より良い予後につながります。
定期検診と経過観察の重要性 – がんの転移を早期に捉えるために
がん治療において、転移や再発をできるだけ早い段階で発見することは、その後の治療の選択肢を広げ、より良い結果を得るために極めて重要です。
治療が終わった後も、医師の指示に従って定期的に検査を受ける「経過観察」を続けること、そして治療中においても、転移が出現していないかを確認するための検査は欠かせません。
転移のパターンを考慮に入れることで、リスクの高い部位を重点的に監視し、効率的かつ効果的な検査計画を立てることができます。
転移・再発を発見するための検査
転移や再発の有無を調べるためには、様々な検査を組み合わせて行います。どの検査を行うかは、原発巣のがんの種類、進行度、そして転移しやすい場所(標的臓器)などを考慮して決定します。
- 血液検査(腫瘍マーカー) – 特定のがんで上昇する値を定期的に測定し、変化を監視します。
- 画像検査 – CT、MRI、超音波(エコー)、PET-CTなどを用いて、全身の臓器を画像で確認します。
- 内視鏡検査 – 胃カメラや大腸カメラなどで、消化管内の再発を直接観察します。
主な画像検査とその特徴
| 画像検査 | 特徴 | 特に有用ながん・部位 |
|---|---|---|
| CT検査 | X線を用いて体の断面を撮影する。短時間で広範囲を調べられる。 | 肺、肝臓、リンパ節など全身のスクリーニング |
| MRI検査 | 磁気を利用して撮影する。放射線被ばくがなく、軟部組織の描出に優れる。 | 脳、骨盤内臓器(前立腺、子宮など)、骨 |
| PET-CT検査 | がん細胞がブドウ糖を多く取り込む性質を利用し、全身のがん細胞を検出する。 | 予期せぬ転移の発見、原発不明癌の探索 |
なぜ経過観察が必要なのか
手術で目に見えるがんをすべて取り除いたとしても、画像検査では捉えきれない微小ながん細胞が体の中に残っている可能性があります。
これらの細胞が時間をかけて再び増殖し、再発や転移として現れることがあります。経過観察は、この見えない敵が姿を現すのをいち早く捉えるための「見張り」です。
定期的な検査を面倒に感じることがあるかもしれませんが、これはご自身の体を守るための大切な取り組みです。不安な点や気になる症状があれば、ためらわずに担当医に相談しましょう。
個々のがんの特性を理解し、より良い治療選択につなげる
これまで見てきたように、がんは一つとして同じものはありません。発生した臓器、細胞の顔つき、そして転移のパターンなど、それぞれが独自の「個性」を持っています。
この個性を深く理解することこそが、数ある治療法の中からご自身にとってより良い選択をするための鍵となります。
医師から提示される治療方針の背景にある「なぜこの治療法なのか」という理由を、転移パターンという視点から理解することで、治療に対する納得感も深まるはずです。
ご自身の病状について主体的に学び、治療チームの一員として積極的に関わっていく姿勢が大切です。
個別化治療の時代へ
近年のがん治療は、すべての人に同じ治療を行う時代から、個々のがんの遺伝子情報や性質に基づいて治療法を選択する「個別化治療」や「プレシジョン・メディシン(精密医療)」へと移行しています。
転移パターンによる分類も、この大きな流れの一部と捉えることができます。例えば、特定の遺伝子変異を持つ肺がんは脳に転移しやすいといったデータも蓄積されつつあります。
こうした情報を基に、将来の転移リスクを予測し、予防的な治療を行う研究も進んでいます。転移の傾向を把握することは、未来の治療戦略を立てる上でも重要なのです。
医師との対話のために
ご自身の転移パターンやリスクについて理解を深めたら、ぜひその知識を担当医との対話に活かしてください。
「私の場合は、どこに転移する可能性が高いのでしょうか」「そのために、どのような検査を定期的に行うのですか」といった具体的な質問は、医師との相互理解を深め、信頼関係を築く上で役立ちます。
病状や治療について分からないこと、不安なことを明確に伝え、共に考え、納得のいく治療を選択していくことが、がんと向き合う上で何よりも重要です。
よくある質問(Q&A)
ここでは、がんの転移パターンに関して多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- 転移するともう治らないのでしょうか?
-
「転移=末期」というイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。近年、薬物療法や放射線療法の進歩により、転移があってもがんの進行を長期間コントロールできるケースが増えています。また、転移した腫瘍の数が少なく、場所も限られている「オリゴメタスターシス(少数転移)」という状態であれば、手術や放射線療法で転移巣を取り除くことで、根治を目指せる場合もあります。重要なのは、転移の状況を正確に把握し、諦めずに適切な治療法を探すことです。
- ステージIVと診断されました。どのような治療になりますか?
-
ステージIVは、がんが原発巣から離れた臓器に遠隔転移している状態を指します。
この場合、治療の主な目的は、がんの進行を抑え、症状を和らげ、生活の質(QOL)を維持しながら、できるだけ長くがんと共存することになります。
治療の中心は、抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬などを用いた全身に効果が及ぶ薬物療法です。
ただし、前述のオリゴメタスターシスのように、状況によっては局所的な治療を組み合わせることもあります。
治療方針はがんの種類や体の状態によって大きく異なるため、担当医とよく相談することが大切です。
- 原発巣と転移巣でがんの性質は変わりますか?
-
基本的には、転移巣のがん細胞は原発巣の性質を受け継いでいます。しかし、転移の過程や薬物治療の影響で、がん細胞の性質が変化(進化)することがあります。
例えば、最初は効果があった抗がん剤が、治療を続けるうちに効かなくなる「薬剤耐性」という現象も、がん細胞の性質変化の一例です。
そのため、再発や転移が起こった際に、再度、転移巣の組織を採取して病理検査や遺伝子検査を行い、その時点でのがんの性質を調べ、治療方針を見直すこともあります。
がんの分類には、今回解説した転移パターンの他にも、治療後の経過の見通しを示す「予後」に基づいた考え方があります。
予後良好ながん、予後不良ながんといった分類は、がんの悪性度や進行の速さと深く関連しており、治療強度を決定する際の重要な判断材料となります。
例えば、進行が緩やかで予後が良いとされるタイプのがんであれば、体への負担が少ない治療を選択できる可能性があります。
次の記事で詳しく学んでいきましょう。
参考文献
WONG, Sunny Y.; HYNES, Richard O. Lymphatic or hematogenous dissemination: how does a metastatic tumor cell decide?. Cell cycle, 2006, 5.8: 812-817.
PRASANNA, Thiru, et al. The survival outcome of patients with metastatic colorectal cancer based on the site of metastases and the impact of molecular markers and site of primary cancer on metastatic pattern. Acta Oncologica, 2018, 57.11: 1438-1444.
SOLÁ, Montserrat, et al. Prognostic value of hematogenous dissemination and biological profile of the tumor in early breast cancer patients: a prospective observational study. BMC cancer, 2011, 11.1: 252.
STACKER, Steven A.; BALDWIN, Megan E.; ACHEN, Marc G. The role of tumor lymphangiogenesis in metastatic spread. The FASEB Journal, 2002, 16.9: 922-934.
SPARRER, D., et al. Primary and secondary metastatic dissemination: multiple routes to cancer-related death. Molecular Cancer, 2025, 24.1: 203.
BUDCZIES, Jan, et al. The landscape of metastatic progression patterns across major human cancers. Oncotarget, 2014, 6.1: 570.
ATHANASSIADOU, Pauline; GRAPSA, Dimitra. Bone marrow micrometastases in different solid tumors: pathogenesis and importance. Surgical Oncology, 2008, 17.3: 153-164.
LEONG, Stanley PL, et al. Patterns of metastasis in human solid cancers. Cancer Metastasis And The Lymphovascular System: Basis For Rational Therapy, 2007, 209-221.
VAN TRAPPEN, Philippe O.; PEPPER, Michael S. Lymphatic dissemination of tumour cells and the formation of micrometastases. The Lancet Oncology, 2002, 3.1: 44-52.
ZHOU, Hengbo; LEI, Pin-ji; PADERA, Timothy P. Progression of metastasis through lymphatic system. Cells, 2021, 10.3: 627.
がんの臨床的分類に戻る