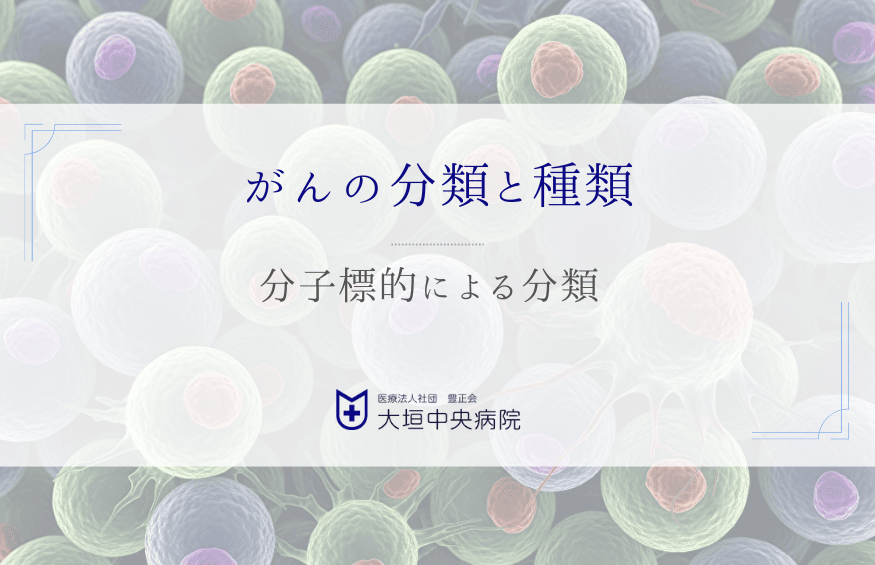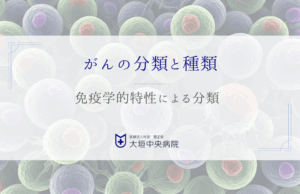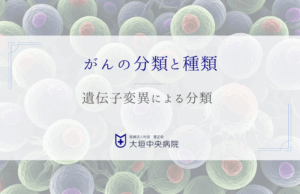がんの治療法は、これまで手術、放射線治療、化学療法が中心でした。
しかし近年、がん研究の進歩により、がん細胞の特性を遺伝子レベルで詳しく調べる「ゲノム医療」が登場し、治療の考え方が大きく変わりつつあります。
その中核をなすのが「分子標的による分類」です。これは、がん細胞だけが持つ特有の「目印」を見つけ出し、それを基にがんを分類する方法です。
この分類によって、一人ひとりの体質やがんの性質に合わせた「個別化医療」の実現が期待されています。この記事では、その基本から検査、治療への活用法までを分かりやすく解説します。
がん細胞が持つ特有の「目印」- 分子標的の基本
がん治療の世界では、「分子標的」という言葉が重要な意味を持ちます。これは、がん細胞の増殖や転移に深く関わる特定のタンパク質や遺伝子のことです。
正常な細胞にはない、あるいは働きが異常になっているため、がん細胞特有の「目印」となります。この目印を正確に見つけ出すことが、新しいがん治療の第一歩となります。
分子標的とは何か
私たちの体は約37兆個の細胞から成り立っており、それぞれの細胞は決められた役割を果たしながら増殖や死滅を繰り返しています。この細胞の秩序を保つために、細胞内では様々なタンパク質が働いています。
しかし、がん細胞では遺伝子に「変異」が起こることで、これらのタンパク質が異常に活性化し、細胞が無限に増殖するようになります。
この異常なタンパク質や、その原因となる遺伝子変異そのものが「分子標的」です。
遺伝子変異が「目印」を生み出す
遺伝子は体の設計図であり、タンパク質を作るための情報が記録されています。何らかの原因でこの設計図の一部に間違い(変異)が生じると、作られるタンパク質の形や働きが変わってしまいます。
がん細胞では、この遺伝子変異が積み重なることで、増殖のスイッチが常に入った状態になります。このスイッチの役割を果たす異常なタンパク質が、分子標的薬が狙う「目印」となるのです。
分子標的の具体例とその働き
| 分子標的の名称 | 主な関連がん種 | 細胞内での主な働き |
|---|---|---|
| EGFR | 肺がん、大腸がん | 細胞の増殖を促す信号を送る |
| HER2 | 乳がん、胃がん | 細胞増殖のアクセル役を担う |
| ALK | 肺がん | 異常な融合遺伝子として細胞増殖を活性化する |
遺伝子レベルでの分類は なぜ治療法を変えるのか
従来のがん分類は、がんが発生した「臓器」が基準でした。しかし、分子標的による分類は、がんの「遺伝子の特徴」という、より本質的な部分に着目します。
この視点の転換が、がん治療そのものを大きく変える力を持っています。
同じ臓器のがんであっても、遺伝子変異の種類が異なれば、全く違う性質のがんとして捉え、それぞれに適した治療法を選択する時代になっています。
臓器別の分類から遺伝子別の分類へ
例えば、同じ「肺がん」と診断されても、Aさんの肺がんは「EGFR遺伝子変異」が原因であり、Bさんの肺がんは「ALK融合遺伝子」が原因である場合があります。
臓器という視点では同じ病気ですが、遺伝子レベルで見ると全く異なる特性を持っています。そのため、AさんとBさんでは効果が期待できる治療薬も異なります。
このように、がんの根本原因である遺伝子変異に基づいて分類することで、より効果的な治療戦略を立てることが可能になります。
個別化医療の実現
分子標的による分類は、「個別化医療」の基盤です。患者さん一人ひとりのがんの遺伝子情報を詳しく調べることで、そのがんに特有の弱点を見つけ出します。
そして、その弱点をピンポイントで攻撃する治療薬を選択します。これは、まるで鍵と鍵穴のように、特定のがん細胞にだけ作用する薬を見つけ出す作業に似ています。
このアプローチにより、治療効果を高めると同時に、副作用を軽減することが期待できます。
従来分類と分子標的分類の比較
| 比較項目 | 従来の分類(臓器・組織型) | 分子標的による分類 |
|---|---|---|
| 基準 | がんが発生した臓器や細胞の見た目 | がん細胞の遺伝子変異やタンパク質の特徴 |
| 治療方針 | 臓器ごと、進行度ごとに標準化された治療 | 個々のがんの特性に合わせた治療(個別化医療) |
| 使用する薬剤 | 従来の抗がん剤(化学療法)が中心 | 分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など |
分子標的薬 – 特定の印を持つ細胞だけを狙う考え方
分子標的による分類が治療に直結するのは、「分子標的薬」という薬剤の存在があるからです。この薬は、がん細胞が持つ特有の「目印(分子標的)」だけを狙い撃ちにするように設計されています。
従来の抗がん剤が、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えていたのに対し、分子標的薬はより選択的に作用するのが大きな特徴です。
分子標的薬の作用点
分子標的薬は、がん細胞の増殖に必要な信号の伝達を妨害したり、がん細胞の生存に必要な物質の働きを阻害したりすることで効果を発揮します。
例えば、ある遺伝子変異によって異常なタンパク質が作られ、それががん細胞の増殖スイッチを押し続けている場合、分子標的薬はそのスイッチの働きをブロックします。
これにより、がん細胞は増殖できなくなり、やがて死滅に至ります。この働き方のため、特定の「目印」を持つがんにしか効果を示しません。
分子標的薬と従来の抗がん剤の違い
| 特徴 | 分子標的薬 | 従来の抗がん剤(化学療法) |
|---|---|---|
| 攻撃対象 | がん細胞の特定の分子(目印) | 細胞分裂が活発な細胞(がん・正常問わず) |
| 副作用 | 皮膚障害、下痢、高血圧など特有のもの | 吐き気、脱毛、骨髄抑制など全身性のもの |
| 必要な検査 | 対応する分子標的の有無を調べる検査が必須 | 特定の遺伝子検査は必須ではない |
分子標的薬の種類
分子標的薬は、その大きさや作用の仕方によって、主に「低分子化合物」と「抗体医薬品」の2種類に大別できます。低分子化合物は細胞の中に入り込んで、細胞内部の異常なタンパク質の働きを抑えます。
一方、抗体医薬品はサイズが大きく、細胞の表面にある目印に結合して、がん細胞の増殖信号を止めたり、免疫細胞ががんを攻撃する手助けをしたりします。
分子標的治療の主な特徴
- 特定のがん細胞に選択的に作用する
- 治療前に効果を予測するためのバイオマーカー検査を行う
- 従来の抗がん剤とは異なる副作用が現れることがある
- 薬剤耐性が生じることがある
あなたの癌にもあるかもしれない代表的な分子標的
分子標的は、さまざまながんで見つかっています。特に、肺がん、乳がん、大腸がんなどでは、特定の遺伝子変異に対する分子標的薬が開発され、治療成績の向上に大きく貢献しています。
ここでは、代表的ないくつかのがん種で見られる分子標的と、それに対する治療について紹介します。ご自身の状況と照らし合わせ、主治医と話す際の参考にしてください。
肺がんにおける分子標的
肺がんは、分子標的による分類が治療に大きく影響する代表的ながんです。特に非小細胞肺がんの一部では、EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子といった「ドライバー遺伝子」が見つかることがあります。
これらの遺伝子変異がある場合、それぞれに対応した分子標的薬が著しい効果を示すことが知られています。
肺がんで見られる主な遺伝子変異
| 遺伝子変異 | 日本人非小細胞肺がんにおける頻度(目安) | 治療 |
|---|---|---|
| EGFR | 約30-40% | EGFR阻害薬による治療 |
| ALK | 約5% | ALK阻害薬による治療 |
| ROS1 | 約1-2% | ROS1阻害薬による治療 |
乳がん・大腸がんにおける分子標的
乳がんでは「HER2(ハーツー)」というタンパク質が有名です。HER2が過剰に発生しているタイプの乳がんでは、HER2の働きを抑える分子標的薬が標準治療の一つになっています。
また、大腸がんでは、RAS遺伝子(KRAS、NRAS)やBRAF遺伝子の変異の有無を調べることが重要です。
これらの遺伝子変異があると、一部の分子標的薬の効果が期待できないことが分かっており、治療薬を選択する上で大切な情報となります。
乳がん・大腸がんの主なバイオマーカー
| がん種 | 代表的なバイオマーカー | 治療選択における意義 |
|---|---|---|
| 乳がん | HER2タンパク質 | 抗HER2薬の効果を予測する |
| 大腸がん | RAS遺伝子変異 | 抗EGFR抗体薬の効果がない可能性を示す |
| 大腸がん | BRAF遺伝子変異 | 予後予測や特定の分子標的薬選択に関わる |
これまでの分類方法 – 臓器や進行度との違い
分子標的による分類が注目される一方で、これまでのがんの分類方法が不要になったわけではありません。
がんが発生した臓器による分類や、がんの広がりを示す病期(ステージ)による分類も、治療方針を決定する上で依然として重要な役割を担っています。
新しい分類方法は、これらの伝統的な分類方法を補完し、より多角的な視点からがんを捉えるために用いられます。
臓器や組織型による分類
最も基本的な分類は、がんが最初に発生した臓器によるものです。例えば、肺にできれば「肺がん」、胃にできれば「胃がん」と呼びます。
さらに、顕微鏡でがん細胞の顔つき(組織型)を観察し、「腺がん」や「扁平上皮がん」などに細かく分類します。これらの情報は、がんの基本的な性質や進行のしやすさを把握する上で基礎となります。
病期(ステージ)による分類
がんの進行度合いを示すのが病期(ステージ)分類です。一般的に、がんの大きさ(T)、周辺のリンパ節への転移の有無(N)、他の臓器への遠隔転移の有無(M)の3つの要素を組み合わせて決定します。
ステージは通常I期からIV期に分けられ、数字が大きくなるほどがんが進行していることを意味します。手術が可能かどうかなど、大きな治療方針を決める際の重要な指標です。
TNM分類の概要
| 因子 | 評価する内容 | 意味合い |
|---|---|---|
| T (Tumor) | 原発巣の大きさと広がり | がん自体の大きさや周囲への浸潤の程度 |
| N (Node) | 所属リンパ節への転移の有無と広がり | がんがリンパ管を通ってどれだけ広がっているか |
| M (Metastasis) | 遠隔転移の有無 | 血液などを通じて他の臓器へ転移しているか |
自分のがんに適した治療法を見つけるための検査
自分のがんがどのような遺伝子の特徴を持っているかを知るためには、専門的な検査が必要です。
これらの検査は、がん組織の一部や血液を使って行い、治療の道筋を照らすための重要な情報を提供してくれます。
代表的な検査として、「コンパニオン診断」と「がん遺伝子パネル検査」があります。
治療薬の選択に直結するコンパニオン診断
コンパニオン診断は、特定の分子標的薬の効果が期待できるかどうかを調べるための検査です。ある分子標的薬を使用する前に、その薬が標的とする遺伝子変異やタンパク質が存在するかどうかを確認します。
この検査で陽性(目印がある)と判定された場合に、その薬の投与を検討します。多くの場合、特定の薬剤と一対一で対応しており、治療に際して保険適用を受けるための条件にもなっています。
多数の遺伝子を一度に調べるがん遺伝子パネル検査
がん遺伝子パネル検査は、一度の検査で数十から数百個のがん関連遺伝子を同時に調べることができる検査です。
標準治療が見つからない場合や、終了してしまった場合などに、新たな治療薬の候補を見つけ出す目的で行われます。
この検査によって、予期せぬ遺伝子変異が見つかり、臨床試験中の薬を含めた新しい治療の選択肢につながる可能性があります。これはゲノム医療の中核をなす検査です。
コンパニオン診断とがん遺伝子パネル検査の比較
| 項目 | コンパニオン診断 | がん遺伝子パネル検査 |
|---|---|---|
| 目的 | 特定の薬剤の効果予測 | 網羅的な遺伝子変異の検出と治療法探索 |
| 調べる遺伝子数 | 1つまたは少数 | 数十〜数百個 |
| 保険適用 | 対応する薬剤の使用を前提に適用 | 条件を満たせば適用(標準治療終了後など) |
検査から治療へ – 分子標的分類の活用法
遺伝子検査で有用な情報が得られた後、それをどのように実際の治療に結びつけていくかが重要です。検査結果は専門家によって分析され、その内容が主治医から患者さんへ丁寧に説明されます。
その上で、今後の治療方針を一緒に考えていくことになります。必ずしも全ての検査結果が治療に結びつくわけではありませんが、可能性を探る上で大きな一歩となります。
検査結果の解釈と治療方針の決定
がん遺伝子パネル検査の結果は、「エキスパートパネル」と呼ばれる、遺伝子やがん治療の専門家チームによって議論されます。
そして、検出された遺伝子変異の医学的な意味付けや、推奨される治療薬の候補などがレポートにまとめられます。
主治医は、このレポートを基に、患者さんの病状や体力、希望などを総合的に考慮しながら、最も良いと考えられる治療法を提案します。
遺伝子検査後の流れ
- 遺伝子変異が見つかり、対応する承認薬がある場合 → その薬剤での治療を検討
- 遺伝子変異が見つかり、臨床試験中の薬がある場合 → 臨床試験への参加を検討
- 治療に結びつく遺伝子変異が見つからなかった場合 → 他の治療法(化学療法など)を検討
遺伝子変異が見つからない場合
遺伝子パネル検査を行っても、残念ながら治療に結びつくような明確な遺伝子変異が見つからないこともあります。
しかし、それは決して治療の道が閉ざされたことを意味するわけではありません。その場合でも、従来の化学療法や放射線治療、あるいは免疫チェックポイント阻害薬など、別の角度からの治療アプローチがあります。
検査結果は、数ある選択肢の中から進むべき道を絞り込むための一つの情報であり、総合的な判断が大切です。
より納得してがんと向き合うための知識
ゲノム医療の進展により、がん治療はより複雑で専門的になっています。だからこそ、患者さん自身が治療の主体者として、基本的な知識を持ち、積極的に治療に参加する姿勢が大切になります。
医師からの説明をよく理解し、分からないことや不安なことは遠慮なく質問することで、より納得のいく治療選択につながります。
ゲノム医療時代に大切なこと
分子標的による分類やそれに基づく治療は、大きな期待が寄せられる一方で、限界や課題もあります。
例えば、効果的な分子標的薬が開発されていない遺伝子変異も多くありますし、治療を続けていくうちに、がん細胞が薬剤への耐性を獲得することもあります。
こうした現実も理解した上で、主治医と信頼関係を築き、二人三脚で治療を進めていくことが重要です。
主治医に確認したい質問の例
| 質問のカテゴリ | 具体的な質問例 | 質問の意図 |
|---|---|---|
| 検査について | 私のがんでは、どのような遺伝子検査が考えられますか | 自分に適した検査の種類やタイミングを知る |
| 治療について | もし遺伝子変異が見つかったら、治療法は変わりますか | 検査結果が治療計画にどう影響するかを把握する |
| 費用・副作用 | その治療の費用は保険適用されますか。副作用は | 経済的負担や生活への影響を具体的に知る |
遺伝情報との向き合い方
がんの遺伝子検査では、時に生まれつき持っている遺伝子の特徴(遺伝性腫瘍)が分かることがあります。
これは、ご自身だけでなく、血縁者にも関わる可能性のあるデリケートな情報です。このような情報とどう向き合うか、事前に心の準備をしておくことも大切です。
必要に応じて、遺伝カウンセリングなどのサポートを受けることもできます。
よくある質問
- 分子標的治療はすべてのがんに有効ですか?
-
いいえ、すべてのがんに有効というわけではありません。分子標的治療は、特定の「分子標的(目印)」を持つがん細胞に対して効果を発揮する治療法です。
そのため、治療の対象となる遺伝子変異などがなければ、効果は期待できません。治療前に遺伝子検査などを行い、薬の標的があるかどうかを確認することが重要です。
- 分子標的薬の副作用はどのようなものがありますか?
-
分子標的薬は、従来の抗がん剤とは異なる特有の副作用が出ることがあります。代表的なものとして、皮膚の発疹や乾燥、爪の異常、下痢、高血圧、疲労感などが挙げられます。
副作用の種類や程度は、使用する薬剤によって大きく異なります。
治療を開始する前に、どのような副作用が起こりうるか、またその対処法について主治医や看護師、薬剤師から十分な説明を受けてください。
- がん遺伝子パネル検査の結果はどのくらいで分かりますか?
-
検査を提出してから結果が返ってくるまでの期間は、検査の種類や医療機関によって異なりますが、一般的には数週間から1ヶ月程度かかることが多いです。
結果が出た後、専門家チーム(エキスパートパネル)での議論を経て、最終的なレポートが作成されます。詳しいスケジュールについては、検査を受ける医療機関に確認してください。
- 分子標的を探す検査や治療は保険適用されますか?
-
多くのコンパニオン診断や、特定の条件を満たした場合のがん遺伝子パネル検査は、公的医療保険の適用となっています。
また、保険適用されている分子標的薬による治療も、高額療養費制度の対象となります。ただし、検査や治療によっては自費診療となる場合もあります。
費用に関する詳細は、主治医や医療機関の相談窓口で事前に確認することが大切です。
この記事では、がん細胞の遺伝子的な特徴に基づく「分子標的による分類」を解説しました。がん治療の個別化は、別の側面からも進んでいます。
それは、患者さん自身の免疫が、がんをどのように認識しているかという「免疫学的特性」による分類です。この視点は、免疫チェックポイント阻害薬などの効果を予測する上で非常に重要です。
がん治療のもう一つの大きな柱である免疫とがんの関係について、次の記事で詳しく学んでみませんか。
参考文献
JÜRGENSMEIER, Juliane M.; EDER, Joseph P.; HERBST, Roy S. New strategies in personalized medicine for solid tumors: molecular markers and clinical trial designs. Clinical cancer research, 2014, 20.17: 4425-4435.
DIETEL, Manfred; SERS, Christine. Personalized medicine and development of targeted therapies: the upcoming challenge for diagnostic molecular pathology. A review. Virchows Archiv, 2006, 448.6: 744-755.
ROUKOS, Dimitrios H.; MURRAY, Samuel; BRIASOULIS, Evangelos. Molecular genetic tools shape a roadmap towards a more accurate prognostic prediction and personalized management of cancer. Cancer biology & therapy, 2007, 6.3: 308-312.
SCHMIDT, Keith T., et al. Precision oncology medicine: the clinical relevance of patient‐specific biomarkers used to optimize cancer treatment. The Journal of Clinical Pharmacology, 2016, 56.12: 1484-1499.
RIEDL, Jakob M., et al. Molecular diagnostics tailoring personalized cancer therapy—an oncologist’s view. Virchows Archiv, 2024, 484.2: 169-179.
WISTUBA, Ignacio I., et al. Methodological and practical challenges for personalized cancer therapies. Nature reviews Clinical oncology, 2011, 8.3: 135-141.
EL‐DEIRY, Wafik S., et al. The current state of molecular testing in the treatment of patients with solid tumors, 2019. CA: a cancer journal for clinicians, 2019, 69.4: 305-343.
SYN, Nicholas Li-Xun, et al. Evolving landscape of tumor molecular profiling for personalized cancer therapy: a comprehensive review. Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 2016, 12.8: 911-922.
SWANTON, C.; CALDAS, C. Molecular classification of solid tumours: towards pathway-driven therapeutics. British journal of cancer, 2009, 100.10: 1517-1522.
TSIMBERIDOU, Apostolia M., et al. Molecular tumour boards—current and future considerations for precision oncology. Nature Reviews Clinical Oncology, 2023, 20.12: 843-863.
がんの分子生物学的分類に戻る