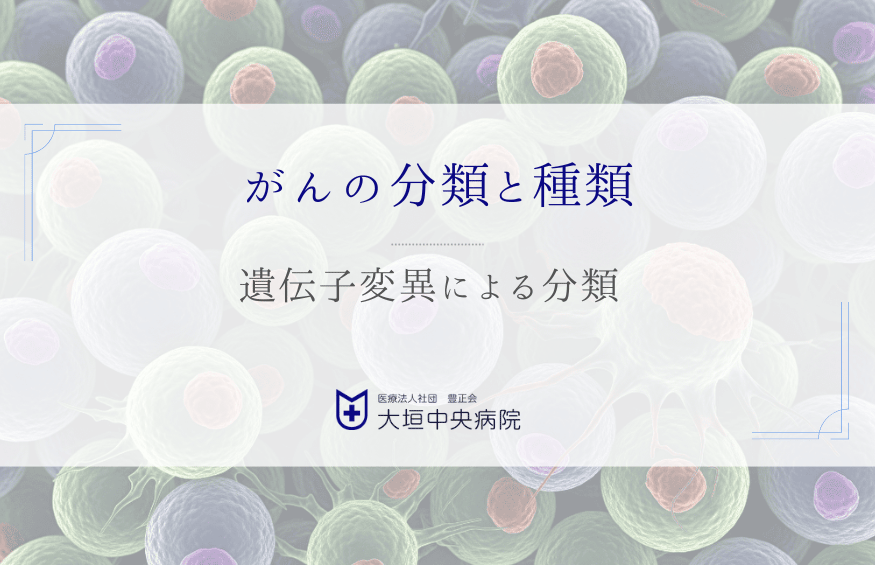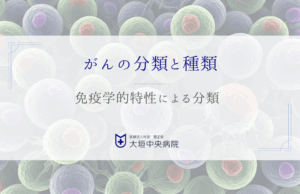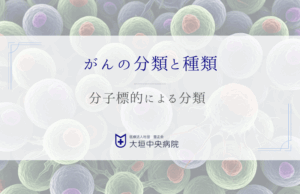がん治療は、すべての人に同じ治療法を適用する時代から、個々の患者さんの体質やがんの性質に合わせて治療法を選択する「個別化医療」の時代へと大きく変化しています。
その中心的な役割を担うのが、「遺伝子変異によるがんの分類」です。
この記事では、なぜ遺伝子の違いが重要なのか、どのような検査があり、治療にどう結びつくのかを、一つひとつ丁寧に解説します。
すべてのがんは同じではない – 個性を決める遺伝子の違い
「がん」と一括りにされがちですが、その性質は発生した臓器や組織の種類だけでなく、一人ひとりの患者さんで大きく異なります。この「がんの個性」を決定づけているのが、遺伝子の情報です。
近年のがん研究の進歩により、がん細胞が持つ特有の遺伝子変異を特定し、それに基づいてがんを分類するという考え方が治療の根幹を成すようになりました。
これにより、より効果の高い治療法を選択する道が開かれています。
がんの多様性 – 臓器だけでなく個人でも異なる
例えば同じ「肺がん」と診断されても、Aさんの肺がんとBさんの肺がんでは、その後の経過や薬の効き方が全く違うことがあります。
これは、がん細胞の増殖や転移に関わる遺伝子の働きが、AさんとBさんとで異なっているためです。
見た目や発生した場所が同じでも、その内部の設計図である遺伝子レベルで見ると、全く別のがんであると言えます。
同じ臓器のがんでも性質は千差万別
これまでのがん治療は、主にがんが発生した「臓器」や、顕微鏡で見たときの「顔つき(組織型)」によって分類し、治療方針を決定していました。
例えば、「胃がん」や「大腸がん」、「肺がんの腺がん」や「扁平上皮がん」といった分類です。この方法は今でも重要ですが、同じ分類のがんであっても、治療効果には個人差が大きいという課題がありました。
これまでのがん分類とゲノム医療時代の分類
がんのゲノム(全遺伝情報)を解析する技術が進んだことで、がんの性質を遺伝子レベルでより詳細に分類できるようになりました。これが「ゲノム医療」の考え方です。
臓器や組織型による分類と遺伝子変異による分類
| 分類方法 | 基準 | 特徴 |
|---|---|---|
| 臓器・組織型による分類 | がんが発生した臓器や細胞の形状 | 基本的な治療方針を決定する上で重要だが、個人差に対応しきれない場合がある。 |
| 遺伝子変異による分類 | がん細胞が持つ特有の遺伝子変異 | 個々のがんの特性に基づき、分子標的薬などの効果を予測し、治療法を選択する。 |
遺伝子情報に基づく個別化医療への転換
遺伝子変異に基づいてがんを分類することで、特定のがん細胞だけが持つ弱点を狙い撃ちする治療法、すなわち「個別化医療」が可能になります。
これは、がん治療が臓器別の考え方から、原因となる遺伝子異常に基づいた臓器横断的な考え方へとシフトしていることを意味します。
細胞の設計図に起きる変化 – 遺伝子変異とは何か
私たちの体は、約37兆個もの細胞から成り立っています。それぞれの細胞は「遺伝子」という設計図を持っており、この設計図に基づいて体を構成するタンパク質が作られ、生命活動が維持されています。
この設計図に何らかの変化が生じることを「遺伝子変異」と呼び、これががんの発生に深く関わっています。
私たちの体を作る遺伝子の役割
遺伝子はDNA(デオキシリボ核酸)という物質でできており、細胞の増殖や機能、そして死滅(アポトーシス)といった生命現象をコントロールする重要な情報が書き込まれています。
通常、細胞は体の状態に応じて適切に分裂・増殖しますが、このコントロールに異常が生じると、細胞は無秩序に増え続け、がん細胞へと変化します。
遺伝子変異が起こる理由
遺伝子変異は、生まれつき親から受け継いだもの(生殖細胞系列変異)もありますが、がんの多くは、生まれた後の様々な要因によって特定の細胞に後天的に生じるもの(体細胞変異)です。
遺伝子変異を引き起こす主な要因
- 加齢による自然な変化
- 喫煙や紫外線などの生活習慣・環境要因
- ウイルスや細菌への感染
- 細胞分裂の際のコピーミス
遺伝子変異の種類
遺伝子変異にはいくつかの種類があり、それぞれタンパク質の機能に与える影響が異なります。これらの変異が、がんの発生や増殖の引き金となります。
主な遺伝子変異の種類
| 変異の種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 点突然変異 | DNAの塩基が一つだけ別のものに置き換わる。 | EGFR遺伝子変異 |
| 欠失・挿入 | DNAの一部がなくなったり、新たに入り込んだりする。 | HER2遺伝子変異 |
| 融合 | 異なる遺伝子が一部で結合し、新しい機能を持つ。 | ALK融合遺伝子 |
ドライバー遺伝子とパッセンジャー遺伝子 – 変異の重要性を見極める
がん細胞の中では、数多くの遺伝子に変異が見つかります。しかし、すべての変異ががんの増殖に直接関わっているわけではありません。
がんの性質を理解し、治療法を考える上で、変異をその役割によって「ドライバー遺伝子変異」と「パッセンジャー遺伝子変異」に区別することが非常に重要です。
がんの増殖を直接引き起こすドライバー遺伝子
ドライバー遺伝子に起きた変異は、がんの発生や増殖、転移の直接的な原因となります。
車で言えば、アクセルを踏み込んだり、ブレーキを壊したりする役割を担うもので、がんの増殖を促進する中心的な存在です。
そのため、このドライバー遺伝子の働きを抑えることができれば、がんの増殖を強力に抑制できる可能性があります。
直接的な原因ではないパッセンジャー遺伝子
一方、パッセンジャー遺伝子変異は、がん細胞が増殖する過程で偶然生じた、がんの増殖には直接影響しない変異です。車で言えば、乗っているだけの同乗者のような存在です。
これらの変異は多数見つかりますが、治療の直接的な標的とはなりにくいです。
治療における標的としての重要性
個別化医療において、治療の標的となるのは主にドライバー遺伝子変異です。この変異を特定し、その働きをピンポイントで阻害する薬剤が「分子標的薬」です。
ドライバー遺伝子とパッセンジャー遺伝子の比較
| 項目 | ドライバー遺伝子変異 | パッセンジャー遺伝子変異 |
|---|---|---|
| がん増殖への関与 | 直接的な原因となる | 直接的な原因ではない |
| 治療の標的 | 主な標的となる | 通常、標的とならない |
| 変異の数 | 比較的少ない | 多数存在する |
なぜ遺伝子変異で癌を分類する必要があるのか
がん細胞の遺伝子変異を特定し、それに基づいて分類することは、現代のがん治療において不可欠な考え方となっています。
それは、個々の患者さんのがんの特性を深く理解し、より効果的で、かつ副作用の少ない治療法を選択するための、最も重要な情報となるからです。
個々の患者さんに合わせた治療選択 – 個別化医療の実現
遺伝子変異による分類の最大の目的は、「個別化医療」を実現することです。
薬が効きやすいタイプのがんか、効きにくいタイプのがんかを治療開始前に予測し、一人ひとりの患者さんに合った治療計画を立てることができます。
治療効果の予測と副作用の軽減
特定の遺伝子変異を持つがんには、その変異を標的とする分子標的薬が劇的な効果を示すことがあります。一方で、その遺伝子変異を持たないがんには、同じ薬を使っても全く効果がありません。
無駄な治療を避け、副作用のリスクを軽減するためにも、遺伝子情報に基づく分類は極めて重要です。
ゲノム医療がもたらす変化
遺伝子変異による分類は、「ゲノム医療」の中核をなすものです。ゲノム医療では、がんの発生場所(臓器)だけでなく、原因となっている遺伝子変異の種類に注目して治療法を考えます。
臓器横断的な治療の可能性
例えば、ある特定の遺伝子変異(例 NTRK融合遺伝子)が見つかった場合、それが肺がんであっても大腸がんであっても、同じ分子標的薬が有効である可能性があります。
これを「臓器横断的(Tumor-agnostic)治療」と呼び、ゲノム医療がもたらした大きな進歩の一つです。
肺がんや乳がんにおける遺伝子分類の重要性
| がん種 | 主なドライバー遺伝子変異 | 治療への影響 |
|---|---|---|
| 肺がん(非小細胞) | EGFR, ALK, ROS1, BRAFなど | 複数の分子標的薬が存在し、治療選択に遺伝子検査が必須。 |
| 乳がん | HER2, PIK3CA, BRCA1/2など | ホルモン療法や分子標的薬の選択、遺伝性腫瘍のリスク評価に重要。 |
分子標的薬 – 特定の遺伝子変異を狙い撃つ治療法
遺伝子変異による分類が治療に直結する最大の理由が、「分子標的薬」の存在です。
これは、がん細胞の増殖に関わる特定の分子(タンパク質や遺伝子)だけを狙い撃ちするように設計された薬剤で、個別化医療の主役と言える治療法です。
分子標的薬の働き方
がん細胞は、ドライバー遺伝子の変異によって異常なタンパク質を作り出し、それを「増殖せよ」という命令系統(シグナル伝達)のスイッチとして利用しています。
分子標的薬は、この異常なスイッチの部分に結合し、命令が伝わらないようにブロックすることで、がん細胞の増殖を止めます。
がん細胞の増殖シグナルを止める
鍵と鍵穴の関係に例えられます。がん細胞の異常なタンパク質が「鍵穴」だとすると、分子標的薬はぴったりとはまる「偽の鍵」のようなものです。
偽の鍵が鍵穴を塞いでしまうため、本来の鍵(増殖シグナル)が入ることができなくなり、増殖の命令がストップします。
従来の抗がん剤との違い
従来の抗がん剤(殺細胞性抗がん剤)は、がん細胞だけでなく、正常な細胞の中でも分裂が活発な細胞(髪の毛の細胞や粘膜の細胞など)にもダメージを与えてしまうため、脱毛や吐き気といった副作用が強く出ることがありました。
分子標的薬は、標的とする分子を持つがん細胞を中心に攻撃するため、正常な細胞への影響が比較的少なく、副作用の種類も異なります。
作用点と副作用の比較
| 項目 | 分子標的薬 | 従来の抗がん剤 |
|---|---|---|
| 作用点 | がん細胞の特定の分子 | 細胞分裂が活発な細胞全般 |
| 主な副作用 | 皮膚障害、下痢、高血圧など薬剤により様々 | 吐き気、脱毛、骨髄抑制など |
分子標的薬の対象となる主な固形がん
現在、多くの固形がんに対して分子標的薬が開発され、実際の治療で使われています。
特に肺がん、乳がん、大腸がんなどでは、治療方針を決定する上で遺伝子検査が標準的な診療の一部となっています。
主な固形がんと分子標的薬の例
| がん種 | 標的遺伝子/タンパク質 | 薬剤の種類 |
|---|---|---|
| 肺がん | EGFR, ALK, ROS1 | チロシンキナーゼ阻害薬 |
| 乳がん | HER2 | 抗HER2薬 |
| 大腸がん | EGFR, BRAF | 抗EGFR抗体薬、BRAF阻害薬 |
治療効果と耐性の問題
分子標的薬は高い効果を示すことがある一方で、治療を続けているうちにがん細胞が性質を変化させ、薬が効かなくなる「耐性」という問題が生じることがあります。
耐性が生じた場合、再度遺伝子検査を行い、新たな治療法を検討することになります。
自身のタイプを知る – がん遺伝子パネル検査の役割
自分のがんがどのような遺伝子変異を持っているのかを調べるための検査が、「がん遺伝子パネル検査」です。
この検査により、個々のがんの特性が明らかになり、個別化医療に向けた重要な情報を得ることができます。
がん遺伝子パネル検査とは
がん遺伝子パネル検査は、がんの組織や血液を用いて、がんの発生や増殖に関連する多数の遺伝子を一度に調べる検査です。
数十から数百の遺伝子を網羅的に解析し、治療薬の選択に役立つ可能性のある遺伝子変異を探します。
一度に多くの遺伝子を調べる検査
従来は、一つの遺伝子変異を調べるために一つの検査を行う必要がありました。
しかし、がん遺伝子パネル検査では、一度の検査で多数の遺伝子を同時に解析できるため、効率的に情報を得ることが可能です。
検査でわかること
この検査によって、治療法の選択に直結するドライバー遺伝子変異が見つかる可能性があります。また、遺伝性のがんに関連する情報が得られることもあります。
検査で得られる主な情報
- 分子標的薬の選択に役立つ遺伝子変異(バイオマーカー)の有無
- 一部の免疫チェックポイント阻害薬の効果予測に関する情報
- 臨床試験(治験)中の薬剤の対象となる可能性
- 遺伝性腫瘍に関連する遺伝子変異の可能性
保険適用となるがん遺伝子パネル検査
2019年6月から、一部のがん遺伝子パネル検査が保険適用となりました。
ただし、誰でも受けられるわけではなく、「標準治療がない固形がんの患者さん」や「局所進行もしくは転移があり、標準治療が終了した(または終了が見込まれる)固形がんの患者さん」などが対象となります。
主な保険適用の検査
| 検査名 | 対象検体 | 特徴 |
|---|---|---|
| OncoGuide NCCオンコパネル | がん組織と血液 | 日本で開発された検査。正常な細胞の遺伝子情報と比較する。 |
| FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル | がん組織 | コンパニオン診断の機能も併せ持つ。 |
コンパニオン診断との関係
がん遺伝子パネル検査と似た目的の検査に「コンパニオン診断」があります。
コンパニオン診断は、特定の分子標的薬を使用できるかどうかを判断するために、対応する特定の遺伝子変異の有無だけを調べる検査です。
パネル検査が網羅的に調べるのに対し、コンパニオン診断は1対1の関係で調べるという違いがあります。
変異が見つかっても治療に結びつかない場合の理解
がん遺伝子パネル検査を受けて遺伝子変異が見つかったとしても、それが必ずしもすぐに治療に結びつくとは限りません。
期待を持って検査を受けた結果、有効な治療法が見つからないという現実に直面することもあります。その理由を正しく理解しておくことは、今後の治療を考える上で大切です。
対応する薬剤がまだない遺伝子変異
検査でドライバー遺伝子変異が見つかったとしても、その変異を標的とする薬剤がまだ開発・承認されていない場合があります。
研究は世界中で進められていますが、すべての遺伝子変異に対して薬が存在するわけではないのが現状です。
VUS(意義不明のバリアント)とは何か
検査結果の中には、「VUS(Variant of Uncertain Significance)」、すなわち「臨床的意義が不明なバリアント」と報告される変異が含まれることがあります。
これは、遺伝子に変異があることはわかったものの、その変異ががんの性質や薬の効果にどのような影響を与えるのか、現時点の科学的知見では判断できない状態を指します。
今後の研究によって、その意義が明らかになる可能性があります。
臨床試験(治験)への参加という選択肢
標準治療として使える薬がなくても、見つかった遺伝子変異を対象とした新しい薬の臨床試験(治験)が国内外で行われている場合があります。
治験への参加は、新しい治療を受けられる可能性がある一方で、効果や安全性がまだ確立されていないという側面もあります。主治医や専門家とよく相談し、情報を集めて検討することが重要です。
遺伝子変異と治療薬の有無
| 検査結果 | 考えられる状況 | 次の選択肢 |
|---|---|---|
| 治療薬のある変異が見つかる | 対応する分子標的薬が保険適用されている。 | 分子標的薬による治療を開始する。 |
| 治療薬のない変異が見つかる | 変異はあるが、承認された薬剤がない。 | 臨床試験(治験)を探す、標準的な化学療法などを行う。 |
| VUS(意義不明) | 変異の臨床的な意味が不明。 | 経過観察、または他の治療法を検討する。 |
パネル検査の治療到達率について
現時点では、がん遺伝子パネル検査を受けて治療につながる遺伝子変異が見つかり、実際にその治療薬(治験含む)を使用できる患者さんは、全体の約10%〜20%程度といわれています。
多くの場合は「変異は見つかったが使える薬がない」あるいは「意義不明の変異(VUS)だった」という結果になる可能性があることを、あらかじめ知っておくことが大切です。
遺伝子情報と向き合い、納得して治療に臨むために
がん遺伝子パネル検査によって得られる情報は、非常に専門的で複雑です。その結果をどのように受け止め、今後の治療にどう活かしていくのか。
患者さん自身が情報を正しく理解し、医療者と協力しながら、納得のいく意思決定を行うことが何よりも大切になります。
検査結果の正しい理解
検査結果は、複数の専門家(エキスパートパネル)によって議論され、その内容が主治医に伝えられます。そして主治医から患者さんへ説明が行われます。
わからないことや不安なことがあれば、遠慮せずに質問し、自分が理解できるまで説明を求めましょう。
遺伝カウンセリングの重要性
検査結果によっては、遺伝性のがんの可能性が示唆されることがあります。このような遺伝情報は、ご本人だけでなく、ご家族にも関わるデリケートな問題です。
遺伝カウンセリングでは、臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーなどの専門家が、遺伝に関する医学的な情報提供や心理的なサポートを行い、意思決定を支援します。
セカンドオピニオンを活用する
主治医からの説明に加えて、別の医療機関の専門家の意見を聞く「セカンドオピニオン」も有効な手段です。
特にゲノム医療は日進月歩の分野であるため、異なる視点からの意見を聞くことで、治療選択の幅が広がったり、現在の治療方針への理解が深まったりすることがあります。
主な相談先
- 主治医・担当の医療チーム
- がんゲノム医療中核拠点病院・連携病院の相談窓口
- がん相談支援センター
- 遺伝カウンセリング外来
よくある質問
- がん遺伝子パネル検査の費用はどのくらいですか?
-
保険適用の場合、検査自体の費用は決められており、高額療養費制度の対象となります。自己負担額は年齢や所得によって異なりますが、数万円から十数万円程度になることが多いです。
ただし、検査前後の診察やカウンセリング費用などが別途必要になる場合があります。詳しくは病院の相談窓口で確認してください。
- 検査結果が出るまでどのくらいかかりますか?
-
検体を提出してから、専門家による検討(エキスパートパネル)を経て結果が主治医に報告されるまで、通常1ヶ月から2ヶ月程度かかります。
検査の種類や医療機関の状況によって期間は変動します。
- 見つかった遺伝子変異は子どもに遺伝しますか?
-
がんの多くは、生まれた後の環境要因などで生じる「体細胞変異」であり、これは遺伝しません。
しかし、がん遺伝子パネル検査の結果、生まれつき持っている可能性のある「生殖細胞系列変異」の疑いが指摘されることがあります。
その場合は、遺伝カウンセリングを受け、必要に応じて確定診断のための追加検査などを検討することになります。
- どの病院で検査を受けられますか?
-
保険適用のがん遺伝子パネル検査は、国が指定した「がんゲノム医療中核拠点病院」「がんゲノム医療拠点病院」「がんゲノム医療連携病院」で受けることができます。
これらの病院は全国に設置されています。まずは主治医に相談するか、がん相談支援センターなどで情報を得ることが第一歩です。
この記事では、がんを遺伝子変異によって分類し、個別化医療に繋げる考え方について解説しました。
遺伝子変異の中でも、特に治療の標的となる分子を見つけ出し、そこを狙い撃ちする「分子標的薬」は、現代のがん治療に欠かせない存在です。
次の記事『分子標的によるがんの分類』では、この分子標的薬がどのような仕組みで効くのか、どのような種類があるのか、そして、従来の抗がん剤とどう違うのかについて、さらに一歩踏み込んで詳しく解説しています。
参考文献
JÜRGENSMEIER, Juliane M.; EDER, Joseph P.; HERBST, Roy S. New strategies in personalized medicine for solid tumors: molecular markers and clinical trial designs. Clinical cancer research, 2014, 20.17: 4425-4435.
SWANTON, C.; CALDAS, C. Molecular classification of solid tumours: towards pathway-driven therapeutics. British journal of cancer, 2009, 100.10: 1517-1522.
SYN, Nicholas Li-Xun, et al. Evolving landscape of tumor molecular profiling for personalized cancer therapy: a comprehensive review. Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 2016, 12.8: 911-922.
GAMBARDELLA, Valentina, et al. Personalized medicine: recent progress in cancer therapy. Cancers, 2020, 12.4: 1009.
COYLE, Krysta Mila; BOUDREAU, Jeanette E.; MARCATO, Paola. Genetic mutations and epigenetic modifications: driving cancer and informing precision medicine. BioMed research international, 2017, 2017.1: 9620870.
DIENSTMANN, Rodrigo, et al. Genomic medicine frontier in human solid tumors: prospects and challenges. Journal of Clinical Oncology, 2013, 31.15: 1874-1884.
EL‐DEIRY, Wafik S., et al. The current state of molecular testing in the treatment of patients with solid tumors, 2019. CA: a cancer journal for clinicians, 2019, 69.4: 305-343.
ROUKOS, Dimitrios H.; MURRAY, Samuel; BRIASOULIS, Evangelos. Molecular genetic tools shape a roadmap towards a more accurate prognostic prediction and personalized management of cancer. Cancer biology & therapy, 2007, 6.3: 308-312.
DIENSTMANN, Rodrigo, et al. Consensus molecular subtypes and the evolution of precision medicine in colorectal cancer. Nature reviews cancer, 2017, 17.2: 79-92.
HENSING, Thomas, et al. A personalized treatment for lung cancer: molecular pathways, targeted therapies, and genomic characterization. Systems Analysis of Human Multigene Disorders, 2013, 85-117.
がんの分子生物学的分類に戻る