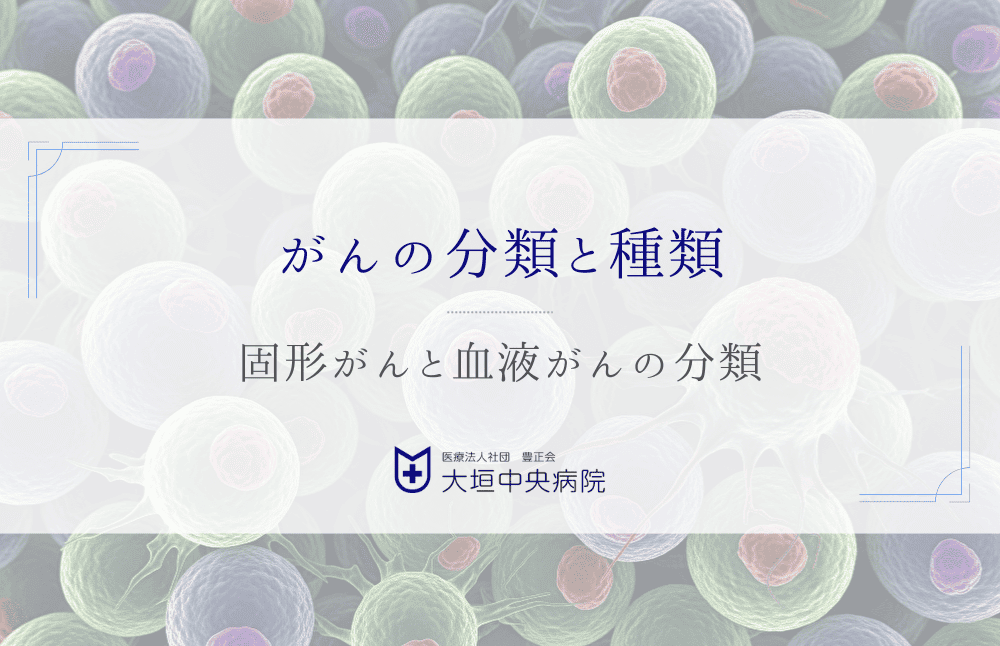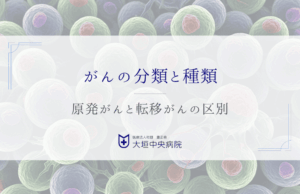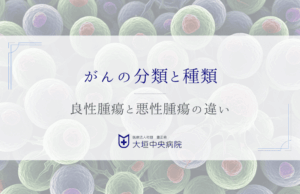「がん」と診断されたとき、多くの方が大きな不安を抱きます。しかし、「がん」は単一の病気ではなく、非常に多くの種類が存在します。
その中でも、がんを理解する上で最も基本的で重要な分類が「固形がん」と「血液がん」です。この二つの分類は、がんが発生する場所、性質、進行の仕方、そして治療の方法まで、あらゆる面で大きく異なります。
ご自身の、あるいはご家族の病状を正しく理解し、納得して治療に臨むためには、この根本的な違いを知ることが第一歩となります。
この記事では、がんという病気の全体像を掴むため、二大分類の基本的な知識から、具体的な種類、診断、治療法までを専門的な観点から分かりやすく解説します。
がんの基本分類 – 発生部位による二つの大きな区分
がんの分類は多岐にわたりますが、すべての基本となるのが「どこから発生したか」という視点です。
体内の細胞が異常に増殖して塊を作るタイプと、血液やリンパといった体液の中で増えるタイプに大別でき、これが固形がんと血液がんという二大分類の根幹をなします。
この発生部位の違いが、その後の診断や治療戦略を決定づける最も重要な要素となります。
固形がんと血液がんの定義
がんの分類を理解する上で、まず「固形」と「血液」という言葉が何を指すのかを明確にすることが重要です。これは物理的な形状と発生する組織の違いに基づいています。
物理的な「塊」の有無
固形がんは、その名の通り、特定の臓器や組織に細胞が密集して物理的な「塊(腫瘍)」を形成します。例えば、胃や肺、大腸といった臓器の壁にできるしこりがこれにあたります。
一方、血液がんは、骨髄などの造血組織で発生し、がん細胞が個々に血液やリンパ液に乗って全身を循環するため、特定の場所に限定された塊を作りません。
この「塊を作るか、作らないか」という点が、両者を区別する最も分かりやすい特徴です。
発生する組織の系統
細胞の起源という観点から見ると、固形がんは主に体の構造を形成する「組織細胞」から発生します。これには、臓器の表面を覆う上皮細胞や、骨・筋肉などを構成する非上皮細胞が含まれます。
対照的に、血液がんは血液細胞(赤血球、白血球、血小板)を作り出す「造血組織」から発生します。この発生起源の違いが、がん細胞の性質そのものを決定づけます。
がんの二大分類の基本
| 分類 | 主な特徴 | 発生部位の例 |
|---|---|---|
| 固形がん | 特定の場所に塊(腫瘍)を形成する | 肺、胃、大腸、乳房、皮膚など |
| 血液がん | 塊を形成せず、血液やリンパで全身に広がる | 骨髄、リンパ節 |
固形がんの特徴 – 臓器に塊を形成するがんの性質
固形がんは、特定の臓器や組織に根を張り、増殖して腫瘍という塊を形成するがんの総称です。この「局所性」という性質が、固形がんの診断から治療に至るまでのすべての段階で中心的な考え方となります。
腫瘍がどこにあり、どのくらいの大きさで、周囲にどの程度広がっているかを正確に把握することが、治療方針を立てる上で極めて重要です。
増殖と浸潤の仕方
固形がんの腫瘍は、ただ大きくなるだけではありません。周囲の正常な組織に染み込むように広がっていく「浸潤」という特徴を持ちます。
この浸潤の程度が、がんの進行度(ステージ)を決定する重要な要素の一つです。
局所での増殖
初期の固形がんは、発生した場所に留まって増殖します。この段階では、腫瘍は比較的小さく、その臓器内にとどまっています。
この時期に発見し、腫瘍を完全に取り除くことができれば、根治の可能性は非常に高くなります。
周囲組織への浸潤
がん細胞は増殖するにつれて、元の組織の境界を越えて、隣接する組織や臓器へと広がっていきます。例えば、胃がんが進行すると、胃の壁を突き破って隣の膵臓や大腸にまで達することがあります。
この浸潤が、手術でがんを取り除く範囲を決定する上で重要な情報となります。
転移という拡散パターン
固形がんのもう一つの重要な特徴が「転移」です。これは、がん細胞が発生した場所(原発巣)から剥がれ落ち、血液やリンパの流れに乗って体の他の場所に移動し、そこで新たに増殖を始める現象を指します。
転移が起こると、がんは局所の病気から全身の病気へと性質を変えます。
リンパ行性転移と血行性転移
転移の経路には主に二つあります。一つは、リンパ管を通って近くのリンパ節に移動する「リンパ行性転移」です。もう一つは、血管に入り込んで遠くの臓器に移動する「血行性転移」です。
例えば、大腸がんは肝臓へ、肺がんは脳や骨へ転移しやすいといったように、がんの種類によって転移しやすい臓器の傾向があります。
固形がんの進行プロセス
| 進行段階 | がん細胞の状態 | 主な治療方針 |
|---|---|---|
| 早期がん | 原発巣に限局し、小さい | 手術や放射線治療による局所治療が中心 |
| 進行がん | 周囲組織へ浸潤、リンパ節転移 | 手術に加え、化学療法などを組み合わせる |
| 遠隔転移がん | 血行性に遠くの臓器へ転移 | 化学療法や免疫療法などの全身治療が中心 |
血液がんの特徴 – 血液や造血器官に発生するがんの性質
血液がんは、固形がんとは対照的に、発生した時点から「全身の病気」としての性質を持ちます。これは、がん細胞が血液やリンパ液という全身を巡るシステムの中で発生し、増殖するためです。
そのため、特定の場所に限定した治療ではなく、全身に行き渡る治療法が主体となります。
全身性の疾患としての性質
血液がんのがん細胞は、骨髄という血液の工場で生まれ、血液に乗って体の隅々まで運ばれます。そのため、「早期発見」という概念が固形がんとは少し異なります。
発見されたときには、すでにがん細胞が全身に存在していると考えるのが基本です。
単一の腫瘍を形成しない
血液がんの代表である白血病では、がん化した白血球が骨髄内で異常に増え、正常な血液細胞の産生を妨げます。これらの細胞は血液中を循環しているため、手術で取り除くべき塊は存在しません。
この点が、治療戦略が化学療法中心となる根源的な理由です。
症状の現れ方
血液がんの症状は、正常な血液細胞が作れなくなることによって引き起こされます。赤血球が減れば貧血による動悸や息切れ、倦怠感が出現します。
白血球が減れば感染症にかかりやすくなり、血小板が減れば出血しやすくなる(鼻血、歯茎からの出血、あざ)といった症状が現れます。
これらの症状は全身に及ぶため、特定の臓器の不調として自覚されにくいこともあります。
血液がんの主な症状
| 正常な血液細胞の減少 | 代表的な症状 |
|---|---|
| 赤血球の減少(貧血) | めまい、立ちくらみ、動悸、息切れ、倦怠感 |
| 白血球の減少 | 発熱、感染症(肺炎、敗血症など) |
| 血小板の減少 | 鼻血、歯茎からの出血、皮下出血(あざ) |
固形がんの代表例 – 肺がん・胃がん・大腸がんなど主要な種類
固形がんは、発生した臓器の名前をつけて呼ばれることが一般的です。日本人に多い肺がん、胃がん、大腸がんをはじめ、乳がん、肝臓がんなど、非常に多くの種類が存在します。
ここでは、代表的な固形がんの種類と、その特徴について解説します。
癌腫と肉腫という大きな分類
固形がんは、さらに細胞の起源によって「癌腫」と「肉腫」に分けられます。これは専門的な分類ですが、がんの性質を理解する上で役立ちます。
癌腫 (Carcinoma)
臓器の表面や内側を覆う「上皮細胞」から発生するがんです。固形がんの約90%を占め、私たちが一般的に「がん」と呼ぶもののほとんどがこの癌腫にあたります。
肺がんや大腸がん、乳がんなどが代表例です。
肉腫 (Sarcoma)
骨、軟骨、筋肉、脂肪、血管といった、体を支える「非上皮性細胞(結合組織)」から発生するがんです。発生頻度は癌腫に比べて低いですが、若年層にも発生することがあります。
骨肉腫や平滑筋肉腫などがこれに含まれます。
主要な固形がんの種類と特徴
ここでは、日本で罹患数の多い代表的な固形がんについて、その特徴を簡単に紹介します。
- 肺がん
- 胃がん
- 大腸がん
- 乳がん
代表的な固形がん
| がんの種類 | 主なリスク因子 | 特徴的な症状 |
|---|---|---|
| 肺がん | 喫煙、受動喫煙 | 長引く咳、血痰、胸痛 |
| 胃がん | ピロリ菌感染、塩分の多い食事 | 胃の不快感、食欲不振、体重減少 |
| 大腸がん | 食生活の欧米化、運動不足 | 血便、便通異常(便秘・下痢) |
血液がんの代表例 – 白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫の違い
血液がんは、どの種類の血液細胞ががん化したかによって、主に「白血病」「悪性リンパ腫」「多発性骨髄腫」の三つに大別されます。
これらは同じ血液がんの仲間ですが、それぞれに異なる特徴と症状、治療法があります。
白血病
「血液のがん」と聞いて多くの方が思い浮かべるのが白血病でしょう。骨髄で血液細胞のもとになる「造血幹細胞」ががん化し、異常な血液細胞(白血病細胞)が無制限に増殖する病気です。
進行の速さによって「急性」と「慢性」に、がん化した細胞の系統によって「骨髄性」と「リンパ性」に分類されます。
急性白血病と慢性白血病
急性白血病は進行が非常に速く、診断されたら直ちに強力な化学療法による治療が必要です。
一方、慢性白血病は比較的ゆっくりと進行するため、すぐに治療を開始せず経過を観察することもあります。
悪性リンパ腫
白血球の一種である「リンパ球」ががん化する病気です。リンパ球は全身のリンパ節やリンパ組織に存在するため、首や脇の下、足の付け根などのリンパ節が腫れることで気づかれることが多いです。
多くの種類(病型)があり、それによって治療方針が大きく異なります。
多発性骨髄腫
リンパ球の一種である「形質細胞」ががん化し、骨髄の中で増殖する病気です。
がん化した形質細胞は、骨を溶かす物質や異常なタンパク質(Mタンパク)を産生するため、骨の痛みや骨折、腎機能障害、貧血といった特徴的な症状を引き起こします。
3大血液がんの比較
| 種類 | がん化する細胞 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 白血病 | 造血幹細胞 | 貧血、感染、出血傾向 |
| 悪性リンパ腫 | リンパ球 | リンパ節の腫れ、発熱、体重減少 |
| 多発性骨髄腫 | 形質細胞 | 骨の痛み、骨折、腎障害、貧血 |
診断方法の違い – 画像検査と血液検査の使い分け
がんの診断は、その種類によってアプローチが大きく異なります。固形がんは「形あるもの」を見つけるための画像検査が中心となり、血液がんは血液そのものの異常を調べる血液検査が診断の入り口となります。
適切な検査を組み合わせ、がんの確定診断と進行度(ステージ)の決定を行います。
固形がんの診断
固形がんの診断では、まず画像検査で腫瘍の場所、大きさ、広がりを評価し、最終的にその組織の一部を採取して顕微鏡で調べる「病理診断」で確定します。
画像検査の役割
CTやMRI、PET検査などの画像検査は、体の中を詳細に写し出し、腫瘍の位置や周囲への浸潤、遠隔転移の有無を調べるために重要です。
これらの情報をもとに、治療方針の要となるステージ分類を行います。
確定診断のための生検
画像検査でがんが疑われても、それだけでは確定診断にはなりません。
疑わしい部分の組織を少量採取(生検)し、病理医が顕微鏡でがん細胞の有無や顔つき(悪性度)を確認することで、初めて診断が確定します。この病理診断は、治療法を選択する上で最も重要な情報です。
血液がんの診断
血液がんの診断は、採血による血液検査から始まることがほとんどです。血液中の赤血球、白血球、血小板の数や形態に異常がないかを調べ、病気の最初の兆候を捉えます。
血液検査の重要性
血液検査は、体に負担の少ない簡単な検査でありながら、白血病などの血液がんの診断において極めて多くの情報を提供します。
がん細胞が血液中に現れている場合は、その存在を直接確認することもできます。
骨髄検査による確定診断
血液検査で異常が見つかり、白血病や多発性骨髄腫が疑われる場合には、確定診断のために骨髄検査を行います。
これは、血液の工場である骨髄の状態を直接調べる検査で、がん細胞の割合や種類、遺伝子異常などを詳しく分析し、正確な病名と治療方針を決定します。
治療アプローチの違い – 手術・放射線・化学療法の選択基準
がん治療の三大柱は「手術」「放射線治療」「化学療法」です。固形がんと血液がんでは、その病気の性質が根本的に異なるため、これらの治療法の位置づけや選択基準も大きく変わります。
近年ではこれらに加え、免疫療法なども重要な選択肢となっています。
固形がんの治療戦略
固形がんの治療は、がんが局所に留まっているか、全身に広がっているかによって大きく二分されます。
局所治療としての手術と放射線治療
がんが原発巣とその周辺に限局している場合、治療の基本はがんを物理的に取り除くことです。手術はがん組織を直接切除し、放射線治療は高エネルギーのX線などを照射してがん細胞を破壊します。
これらは「局所治療」と呼ばれ、根治を目指すための中心的な役割を担います。
全身治療としての化学療法と免疫療法
がんが転移して全身に広がっている場合や、手術後の再発を防ぐ目的で、全身に作用する薬物療法を行います。化学療法(抗がん剤)は、細胞分裂が活発ながん細胞を攻撃します。
また、近年進歩が著しい免疫療法は、自身の免疫力を高めてがんを攻撃する治療法で、特定の種類の固形がんに高い効果を示します。
血液がんの治療戦略
血液がんは本質的に全身の病気であるため、治療も全身に行き渡る方法が中心となります。
化学療法が治療の根幹
血液がん治療の根幹をなすのは化学療法です。複数の薬剤を組み合わせて点滴や内服で投与し、全身に潜むがん細胞を根絶することを目指します。
治療は長期間に及ぶことが多く、入院が必要な場合も少なくありません。
造血幹細胞移植
強力な化学療法を行っても再発のリスクが高い場合や、難治性の血液がんに対しては、造血幹細胞移植という強力な治療法を選択することがあります。
これは、大量の化学療法や全身への放射線治療でがん細胞を徹底的に叩いた後、健康な造血幹細胞を移植して正常な血液産生能力を回復させる治療です。
転移パターンの違い – 固形がんと血液がんで異なる拡散方法
がん細胞が最初に発生した場所から他の場所へ広がることを「転移」または「浸潤」と呼びますが、その様式は固形がんと血液がんで大きく異なります。
この拡散方法の違いを理解することは、がんの進行を予測し、適切な治療範囲を決定する上で重要です。
固形がんの転移経路
固形がんは、いくつかの明確な経路を通って体を移動します。
- リンパ行性転移
- 血行性転移
- 播種性転移
リンパ行性転移はリンパ管を、血行性転移は血管を介してがん細胞が広がります。播種は、がんが腹腔や胸腔内に直接散らばるように広がる特殊な転移形式です。
がんの種類によって、どの経路でどこに転移しやすいかという傾向(例えば、大腸がんは肝臓へ、肺がんは脳へ)があり、治療後の経過観察ではその点を考慮した検査計画を立てます。
血液がんの拡散
血液がんの場合、「転移」という言葉は通常使いません。
なぜなら、がん細胞は発生初期から血液やリンパ液に乗って全身を循環しており、特定の場所から別の場所へ「移動する」という概念とは異なるからです。
全身への浸潤
血液がんのがん細胞は、骨髄、リンパ節、脾臓といった造血・リンパ組織を中心に増殖しますが、血液の流れに乗ってあらゆる臓器に入り込む可能性があります。これを「浸潤」と呼びます。
例えば、白血病細胞が中枢神経(脳や脊髄)に浸潤することもあります。
拡散パターンの比較
| 項目 | 固形がん | 血液がん |
|---|---|---|
| 拡散の様式 | 転移(リンパ行性、血行性など) | 浸潤(全身循環) |
| 主な広がり方 | 段階的に広がる(局所→リンパ節→遠隔臓器) | 初期から全身に広がる |
予後の特徴 – それぞれの分類における生存率の傾向
「予後」とは、病気の経過や結末についての医学的な見通しのことを指し、しばしば「5年相対生存率」などの指標で示されます。
がんの予後は、がんの種類、進行度(ステージ)、治療の効果、そして患者さん自身の体力など、多くの要因によって左右されます。固形がんと血液がんでは、この予後を考える上での視点も異なります。
固形がんの予後とステージ
固形がんの予後は、診断された時点でのステージと強く関連します。
ステージは、がんの大きさ(T)、リンパ節転移の有無(N)、遠隔転移の有無(M)を組み合わせて決定され、早期であるほど予後は良好です。
早期発見の重要性
例えば、大腸がんや胃がんでは、がんが粘膜内にとどまる早期のステージIで発見されれば、5年生存率は90%を超えます。
しかし、遠隔転移のあるステージIVになると、その数値は大きく低下します。このため、がん検診などによる早期発見が極めて重要です。
血液がんの予後と病型
血液がんの予後は、固形がんのように単純なステージ分類で一括りにはできません。
むしろ、病気の「種類(病型)」や「染色体・遺伝子異常の有無」といった、がん細胞そのものの生物学的な性質が予後を大きく左右します。
病型と遺伝子変異の役割
例えば、同じ急性骨髄性白血病でも、特定の遺伝子変異を持つタイプは予後が良好である一方、別の変異を持つタイプは難治性であることが分かっています。
そのため、治療方針を決定する際には、これらの詳細な検査結果が非常に重要になります。
悪性リンパ腫も非常に多くの病型に分かれ、進行が緩やかで長い経過をたどるタイプから、急速に進行する悪性度の高いタイプまで様々です。
予後を左右する主な因子
| 分類 | 予後を決定する主要な因子 |
|---|---|
| 固形がん | 診断時の病期(ステージ) |
| 血液がん | 病型、染色体・遺伝子異常の種類 |
よくある質問
- 癌腫と肉腫はどちらも固形がんですか?
-
はい、どちらも固形がんに分類されます。違いは、がんが発生した細胞の種類にあります。
体の表面や臓器の内側を覆う上皮細胞から発生するのが「癌腫」(例:肺がん、胃がん)で、固形がんの大部分を占めます。
一方、骨や筋肉、脂肪といった体を支える結合組織から発生するのが「肉腫」(例:骨肉腫)です。発生頻度は肉腫の方が稀です。
- 悪性リンパ腫は固形がんのようにリンパ節が腫れるのに、なぜ血液がんに分類されるのですか?
-
良い質問です。悪性リンパ腫はリンパ節に塊(腫瘤)を作ることが多いため、一見すると固形がんのように見えます。
しかし、その本質は血液細胞の一種であるリンパ球ががん化したものであり、発生起源が造血組織にあるため血液がんに分類されます。
また、リンパ球はリンパ液に乗って全身を巡るため、病気は局所にとどまらず全身的な性質を持つという点も、血液がんに分類される理由です。
- がんのステージはどのように決まるのですか?
-
ステージは主に固形がんの進行度を示す指標で、以下の3つの要素を基に総合的に判断します。
- T因子: 原発巣の腫瘍の大きさや広がり
- N因子: 周囲のリンパ節への転移の有無と範囲
- M因子: 他の臓器への遠隔転移の有無
これらの組み合わせによって、早期のステージIから最も進行したステージIVまでに分類します。ステージは、治療方針を決定し、予後を予測するための非常に重要な情報です。
- 化学療法は固形がんにも血液がんにも使うのですか?
-
はい、どちらの治療にも用いますが、その位置づけが異なります。血液がんでは、全身に広がったがん細胞を叩くための根幹的な治療法です。
一方、固形がんでは、手術が難しい進行・転移がんに対する主要な治療として、あるいは手術後の再発予防(補助化学療法)として使います。
近年では、化学療法だけでなく、特定の分子を狙う分子標的薬や免疫療法など、薬物療法の選択肢は多様化しています。
参考文献
TAYLOR, Justin; XIAO, Wenbin; ABDEL-WAHAB, Omar. Diagnosis and classification of hematologic malignancies on the basis of genetics. Blood, The Journal of the American Society of Hematology, 2017, 130.4: 410-423.
SAHA, Sayan, et al. A Comprehensive Review on Unravelling the Complexity of Blood Cancer. blood, 6: 7.
KANSAL, Rina. Diagnosis and Molecular Pathology of Lymphoblastic Leukemias and Lymphomas in the Era of Genomics and Precision Medicine: Historical Evolution and Current Concepts—Part 1: Lymphoid Neoplasms. Lymphatics, 2023, 1.2: 55-76.
TIRINO, Virginia, et al. Cancer stem cells in solid tumors: an overview and new approaches for their isolation and characterization. The FASEB Journal, 2013, 27.1: 13-24.
CHAUDHARY, Ajay Kumar, et al. Matrix metalloproteinase and its drug targets therapy in solid and hematological malignancies: an overview. Mutation Research/Reviews in Mutation Research, 2013, 753.1: 7-23.
STORB, Rainer F., et al. Hematopoietic cell transplantation for benign hematological disorders and solid tumors. ASH Education Program Book, 2003, 2003.1: 372-397.
HSI, Eric D. Hematopathology E-Book: A Volume in the Series: Foundations in Diagnostic Pathology. Elsevier Health Sciences, 2017.
HARRIS, Timothy JR; MCCORMICK, Frank. The molecular pathology of cancer. Nature reviews Clinical oncology, 2010, 7.5: 251-265.
JAFFE, Elaine Sarkin (ed.). Pathology and genetics of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Iarc, 2001.
NAJAFI, Masoud, et al. The current knowledge concerning solid cancer and therapy. Journal of biochemical and molecular toxicology, 2021, 35.11: e22900.
がんの基本的分類に戻る