がんは、遺伝子の変異によって細胞が異常に増殖する病気ですが、その発生には生活習慣や環境、遺伝など様々な要因が関わっています。
その中でも、特定のウイルス、細菌、寄生虫といった病原体への感染が、一部のがんの重要な原因となることがわかっています。
世界のがん全体の約15-20%は、感染症が原因で発生すると推計されています。感染によって引き起こされる慢性的な炎症や、病原体が持つ遺伝子が人の細胞の性質を変化させることが、がん化の引き金となります。
この記事では、がんの発生に関わる代表的な感染症の種類、それによって引き起こされるがんのリスク、そして予防や対策について詳しく解説します。
ウイルス感染が引き金となるがん
私たちの身の回りには無数のウイルスが存在しますが、その中の一部は「がんウイルス」と呼ばれ、人の細胞に入り込んでがんを発生させる能力を持っています。
ウイルスが持つ遺伝子が細胞の遺伝子に組み込まれたり、ウイルスの増殖が細胞の分裂を異常に活発化させたりすることで、正常な細胞ががん細胞へと変化するのです。
代表的なものに、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスや、肝細胞がんを引き起こす肝炎ウイルスなどがあります。ここでは、がんと関連の深いウイルスについて解説します。
ヒトパピローマウイルス (HPV)
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、皮膚や粘膜に感染するごくありふれたウイルスで、100種類以上の型が存在します。
ほとんどの場合、感染しても免疫の働きによって自然に排除されますが、一部のハイリスク型のウイルスが持続的に感染すると、がんを引き起こすことがあります。
HPVと子宮頸がんの関係
子宮頸がんの95%以上は、ハイリスク型HPVの持続感染が原因であることが明らかになっています。特にHPV16型と18型は、子宮頸がんの原因の約60-70%を占めます。
HPVが子宮頸部の細胞に感染すると、ウイルスの作り出すたんぱく質が、細胞の異常な増殖を抑える働きを持つ遺伝子の機能を停止させます。
これにより、細胞は無秩序に増え続け、数年から数十年かけて「異形成」という前がん病変を経て、がんへと進行します。
子宮頸がんの他にも、中咽頭がん、肛門がん、腟がん、外陰がん、陰茎がんなどの原因にもなります。
ワクチンによる予防
HPV感染症は、ワクチンで予防できるがんの一つです。HPVワクチンは、特に感染リスクの高いHPV16型や18型などの感染を防ぐ効果が高く、性交渉を開始する前の年齢で接種することが最も効果的です。
ワクチン接種と、20歳以上での定期的な子宮頸がん検診を組み合わせることで、子宮頸がんの発生を大幅に減らすことが可能です。
検診によって前がん病変の段階で発見すれば、子宮を温存した形での治療も選択できます。
B型・C型肝炎ウイルス (HBV/HCV)
B型肝炎ウイルス(HBV)およびC型肝炎ウイルス(HCV)は、血液や体液を介して感染し、主に肝臓に炎症を引き起こすウイルスです。
これらのウイルスによる持続的な感染は、肝細胞がんの最大の原因となります。日本における肝細胞がんの約80%は、これら肝炎ウイルスの持続感染が背景にあると考えられています。
肝細胞がんへの移行
HBVやHCVに持続的に感染すると、肝臓で慢性的な炎症が続きます。この炎症は、肝細胞の破壊と再生を繰り返す状態を引き起こします。
この絶え間ない細胞の再生過程で遺伝子のコピーミス(変異)が起こりやすくなり、がん細胞が生まれるリスクが高まります。
特にC型肝炎は慢性化しやすく、慢性肝炎から肝硬変、そして肝細胞がんへと進行するケースが多く見られます。B型肝炎の場合は、肝硬変を経ずに直接肝細胞がんが発生することもあります。
治療と定期検診の重要性
近年、肝炎ウイルスの治療は大きく進歩しました。特にC型肝炎ウイルスに対しては、インターフェロンを使わない経口の抗ウイルス薬が登場し、多くの患者さんでウイルスを体内から排除できるようになりました。
B型肝炎ウイルスに対しても、ウイルスの増殖を抑える薬が開発されています。ウイルス量をコントロールすることで、肝硬変や肝細胞がんへの進行を抑制することが期待できます。
肝炎ウイルスのキャリア(体内にウイルスを持つ人)であるとわかった場合は、症状がなくても定期的に専門医の診察と画像検査、血液検査を受けることが、肝細胞がんの早期発見のためにとても重要です。
主な発がん性ウイルスとその特徴
| ウイルス名 | 関連する主ながん | 主な感染経路 |
|---|---|---|
| ヒトパピローマウイルス (HPV) | 子宮頸がん、中咽頭がん | 性的接触 |
| B型・C型肝炎ウイルス (HBV/HCV) | 肝細胞がん | 血液、体液 |
| EBウイルス (EBV) | バーキットリンパ腫、上咽頭がん | 唾液 |
EBウイルス (EBV)
EBウイルス(エプスタイン・バール・ウイルス)は、ヘルペスウイルス科に属するウイルスで、世界中の成人の90%以上が感染しているとされています。
多くは幼少期に唾液を介して感染し、症状が出ないか、出ても軽い風邪のような症状で済みます。思春期以降に初感染した場合は、伝染性単核球症という発熱や喉の痛みを伴う病気を引き起こすことがあります。
関連するがんの種類
一度感染すると生涯にわたって体内に潜伏し続けるEBウイルスですが、通常は免疫によって活動が抑えられています。
しかし、免疫の働きが低下した状態など、特定の条件下でウイルスの活動が活発になると、がんの発生に関与することがあります。
EBウイルスが関連する悪性腫瘍としては、アフリカの子どもに多い「バーキットリンパ腫」や、アジア、特に中国南部に多い「上咽頭がん」が知られています。
その他にも、胃がんの一部や、臓器移植後やHIV感染者に見られるリンパ増殖性疾患などもEBウイルスとの関連が指摘されています。
感染経路と発症リスク
主な感染経路は、ウイルスの含まれる唾液です。キスや飲み物の回し飲みなどで感染するため、「キス病」と呼ばれることもあります。ほとんどの人が感染しているウイルスであり、感染自体を防ぐことは困難です。
がんの発症には、ウイルスの他に、遺伝的な要因や環境要因、免疫状態などが複雑に関わっていると考えられており、EBウイルスに感染しているからといって、必ずしもがんになるわけではありません。
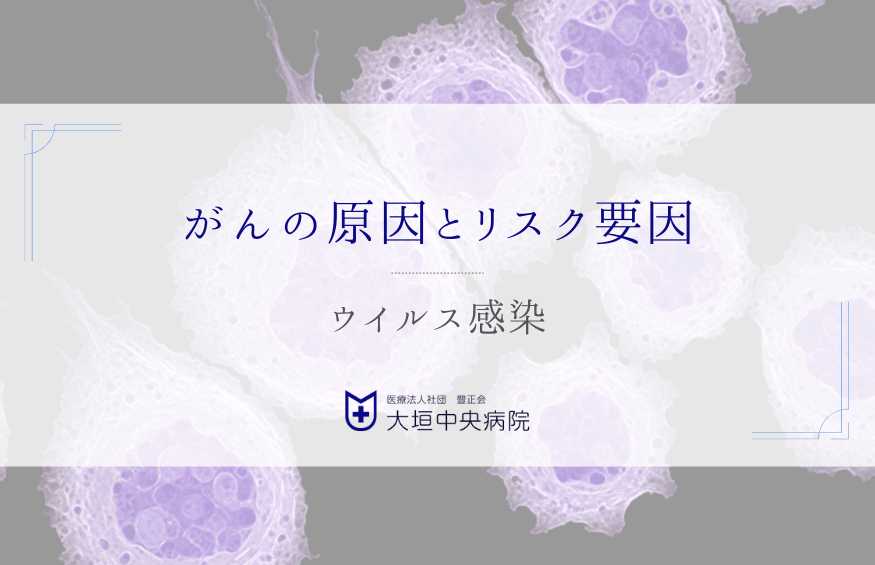
細菌感染が関与するがん
細菌感染もまた、特定のがんのリスクを高める要因となります。
ウイルスのように細菌が直接細胞のがん化を引き起こすケースは稀ですが、細菌が引き起こす長期間にわたる慢性的な炎症が、がんの発生しやすい環境を作り出すと考えられています。
炎症が続くと、組織を修復するために細胞分裂が活発になりますが、その過程でDNAに損傷が蓄積し、がん化につながる変異が起こりやすくなるのです。
ここでは、代表的なヘリコバクター・ピロリと胃がんの関係を中心に、細菌感染とがんについて解説します。
ヘリコバクター・ピロリ (ピロリ菌)
ヘリコバクター・ピロリ、通称ピロリ菌は、強い酸性の環境である胃の中に生息できる特殊な細菌です。主に幼少期に、衛生環境が整っていなかった時代の井戸水などを介して経口感染すると考えられています。
このピロリ菌の持続感染が、胃がんの発生における最も大きなリスク要因であることがわかっています。
胃がん発生のリスク
ピロリ菌に感染している人は、感染していない人と比較して胃がんになるリスクが5倍以上高いと報告されています。ピロリ菌は胃の粘膜にすみつき、持続的な炎症を引き起こします。
この炎症が長年にわたって続くと、胃の粘膜が萎縮する「萎縮性胃炎」という状態になります。
萎縮性胃炎がさらに進行すると、胃の粘膜が腸の粘膜のようになる「腸上皮化生」という変化が起こり、この腸上皮化生の一部から胃がんが発生すると考えられています。
除菌治療の効果
ピロリ菌の感染は、検査で診断でき、抗菌薬と胃酸の分泌を抑える薬を1週間服用する「除菌治療」によって取り除くことが可能です。
早期に除菌治療を行うことで、胃がんの発生リスクを約3分の1から3分の2程度まで低減できるとされています。特に、萎縮性胃炎が進行する前に除-菌することが、胃がん予防には効果的です。
ただし、除菌に成功した後も、胃がんのリスクが完全になくなるわけではありません。特に、すでに胃の粘膜の萎縮が進んでいる場合は、除菌後も定期的に胃の内視鏡検査を受けることが大切です。
がんリスクと関連する細菌
| 細菌名 | 関連する主ながん | リスク要因 |
|---|---|---|
| ヘリコバクター・ピロリ | 胃がん、MALTリンパ腫 | 慢性胃炎、胃粘膜の萎縮 |
| 特定の胆道内細菌 | 胆道がん | 慢性的な胆道の炎症 |
| 歯周病関連菌など | 大腸がん、食道がん | 慢性炎症、腸内環境の変化 |
その他の関連が疑われる細菌
ピロリ菌と胃がんの関係ほど明確ではありませんが、他の細菌とがんの関連性についても研究が進んでいます。
これらの多くは、細菌が引き起こす慢性的な炎症や、細菌が作り出す毒素などが、がんの発生に関与している可能性が考えられています。
胆道がんと特定の細菌
胆道がんの発生には、胆管内で持続する慢性的な炎症が関わっているとされています。
近年の研究で、胆管炎や胆石を持つ患者さんの胆汁から特定の細菌が検出されることが多く、これらの細菌感染が胆道がんのリスクを高める可能性が指摘されています。
細菌が産生する物質が胆道の上皮細胞を傷つけ、がん化を促進するのではないかと考えられていますが、まだ研究途上の段階です。
大腸がんと口腔内細菌
大腸がん組織から、フソバクテリウム・ヌクレアタムという口腔内に常在する歯周病の原因菌の一種が、正常な大腸組織よりも多く見つかるという報告があります。
この細菌が大腸がんの増殖や転移に関わっている可能性が示唆されており、口腔内の衛生状態と消化器系のがんとの関連について、活発な研究が行われています。
腸内細菌叢のバランスの乱れが、大腸がんを含む様々ながんの発生や進行に関与するという考え方も注目されています。

寄生虫感染によるがんのリスク
寄生虫の感染も、一部のがんの発生原因となります。寄生虫が人の体内に長期間すみつくことで、その組織に慢性的な炎症や物理的な刺激を与え続けます。
この持続的な刺激が細胞の遺伝子変異を誘発し、がんの発生につながると考えられています。衛生環境の改善により日本国内での感染は稀になったものもありますが、世界的には依然として重要な健康問題です。
ここでは、がんとの関連が知られている寄生虫について解説します。
日本住血吸虫
日本住血吸虫は、かつて日本の一部の地域(山梨県、広島県、佐賀県など)の河川に生息していた巻貝(ミヤイリガイ)を中間宿主とする寄生虫です。
汚染された水に皮膚が触れることで体内に侵入し、主に門脈という肝臓につながる血管内に寄生します。虫卵が肝臓や大腸の組織に詰まることで、強い炎症反応を引き起こします。
肝臓がんや大腸がんとの関連
日本住血吸虫の虫卵によって引き起こされる慢性的な炎症は、肝臓の線維化(肝硬変)や大腸のポリープ形成などを引き起こし、長期的には肝細胞がんや大腸がんのリスクを高めることが知られています。
特に、肝硬変に至った場合の肝細胞がんのリスクが指摘されています。過去の流行地では、現在でも高齢者を中心に既感染者が見られ、注意が必要です。
日本における現状
日本では、中間宿主であるミヤイリガイの駆除や河川改修などの公衆衛生活動が功を奏し、1978年以降は新規の患者発生はなく、2000年に日本住血吸虫病は終息したとされています。
しかし、過去に流行地で生活していた経験がある方で、原因不明の肝機能障害などがある場合は、この感染症の可能性を考慮することもあります。
肝吸虫
肝吸虫は、主に東南アジアや東アジアに分布する寄生虫で、コイ科の淡水魚を生で食べることによって感染します。
人の体内では、胆管(肝臓で作られた胆汁を十二指腸へ送る管)の中に寄生し、長期間にわたって生き続けます。日本でも、過去に輸入された淡水魚が原因で感染例が報告されたことがあります。
感染症予防のための基本的な対策
- 定期的な手洗い
- 安全な水の飲用
- 食品の十分な加熱調理
- 適切なワクチン接種
胆管がんのリスク
肝吸虫が胆管に寄生すると、その物理的な刺激や分泌物が原因で、胆管の上皮に慢性的な炎症が引き起こされます。
この長期間にわたる炎症が、胆管の細胞のがん化を促し、胆管がんの発生リスクを著しく高めることがわかっています。
世界保健機関(WHO)の専門機関である国際がん研究機関(IARC)は、肝吸虫を「ヒトに対して発がん性がある」(グループ1)と分類しています。
主な感染源と予防策
主な感染源は、肝吸虫の幼虫が寄生しているコイやフナ、モツゴなどの淡水魚を生、あるいは加熱が不十分な状態で食べることです。予防策として最も重要なのは、淡水魚を生食しないことです。
調理の際は、中心部まで十分に火を通すことが大切です。また、淡水魚を扱ったまな板や包丁などの調理器具は、熱湯で消毒し、他の食材への汚染を防ぐことも重要です。
これらの対策を徹底することで、肝吸虫の感染は確実に防ぐことができます。
がんとの関連が指摘される寄生虫
| 寄生虫名 | 関連する主ながん | 主な感染源 |
|---|---|---|
| 日本住血吸虫 | 肝細胞がん、大腸がん | 汚染された淡水(経皮感染) |
| 肝吸虫 | 胆管がん | コイ科の淡水魚の生食 |
| エジプト住血吸虫 | 膀胱がん | 汚染された淡水(経皮感染) |
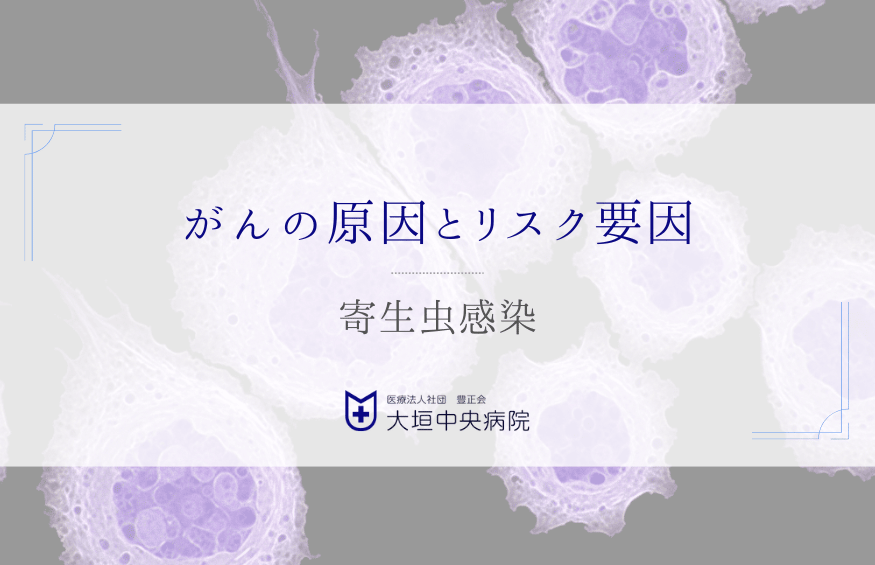
感染症とがん - よくあるご質問
- がんの原因となる感染症にかかったら、必ずがんになりますか?
-
いいえ、必ずがんになるわけではありません。例えば、ピロリ菌に感染した人のうち、胃がんになるのはごく一部です。
感染はあくまでがんのリスク要因の一つであり、発がんには遺伝的な要因や他の生活習慣(喫煙、食生活など)が複雑に関係します。
しかし、リスクを減らすために、原因となる感染症の治療や、定期的な検診を受けることがとても大切です。
- がんの原因となる感染症は、人から人へうつりますか?
-
原因となるウイルスや細菌などの病原体は、人から人へうつることがあります。例えば、肝炎ウイルスは血液、HPVは性的接触、ピロリ菌は経口で感染します。
しかし、がんそのものが感染症のようにうつることは絶対にありません。
重要なのは、病原体の感染経路を正しく理解し、適切な予防策(ワクチン接種、手洗い、安全な性交渉など)を講じることです。
- 感染症が原因のがんは予防できますか?
-
はい、一部のがんは予防が可能です。
ヒトパピローマウイルス(HPV)に対するHPVワクチンは子宮頸がんの予防に、B型肝炎ウイルス(HBV)に対するB型肝炎ワクチンは肝細胞がんの予防に高い効果があります。
また、ピロリ菌の除菌治療は胃がんのリスクを下げることがわかっています。感染経路を断つための衛生管理や、感染を早期に発見して治療することも、がんの予防につながります。
- 自分の体内にがんの原因となるウイルスや細菌がいるか調べる方法はありますか?
-
はい、調べる方法があります。B型・C型肝炎ウイルスは血液検査で、ヒトパピローマウイルスは子宮頸がん検診で細胞を採取して調べます。
ヘリコバクター・ピロリは、呼気検査、血液検査、便検査、あるいは胃の内視鏡検査の際に組織を採取して調べることができます。
気になる症状があったり、リスクを感じたりする場合は、かかりつけ医や専門の医療機関に相談することをお勧めします。
がんの発生には、今回解説した感染症以外にも、慢性炎症性疾患、免疫不全・免疫抑制状態、ホルモン・内分泌要因、放射線治療・化学療法、前がん病変など、医学的要因が関わっています。
ご自身の健康状態や家族の病歴を理解し、がん全体の要因について知識を深めることは、より適切な健康管理と予防行動につながります。
がんの医学的要因についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
参考文献
KUPER, Hannah; ADAMI, H.‐O.; TRICHOPOULOS, Dimitri. Infections as a major preventable cause of human cancer. Journal of internal medicine, 2001, 249.S741: 61-74.
ZUR HAUSEN, Harald. The search for infectious causes of human cancers: where and why. Virology, 2009, 392.1: 1-10.
HERRERA, Luis A., et al. Role of infectious diseases in human carcinogenesis. Environmental and molecular mutagenesis, 2005, 45.2‐3: 284-303.
ZUR HAUSEN, Harald. Infections causing human cancer. John Wiley & Sons, 2007.
MUELLER, Nancy. Infectious agents. In: Cancer prevention: the causes and prevention of cancer. Dordrecht: Springer Netherlands, 2000. p. 63-73.
MASROUR-ROUDSARI, Jila; EBRAHIMPOUR, Soheil. Causal role of infectious agents in cancer: an overview. Caspian journal of internal medicine, 2017, 8.3: 153.
DE FLORA, Silvio; LA MAESTRA, Sebastiano. Epidemiology of cancers of infectious origin and prevention strategies. Journal of preventive medicine and hygiene, 2015, 56.1: E15.
SAMARAS, Vassilis, et al. Chronic bacterial and parasitic infections and cancer: a review. The Journal of Infection in Developing Countries, 2010, 4.05: 267-281.
ZUR HAUSEN, Harald. The search for infectious causes of human cancers: where and why (Nobel lecture). Angewandte Chemie International Edition, 2009, 48.32: 5798-5808.
VAN TONG, Hoang, et al. Parasite infection, carcinogenesis and human malignancy. EBioMedicine, 2017, 15: 12-23.

