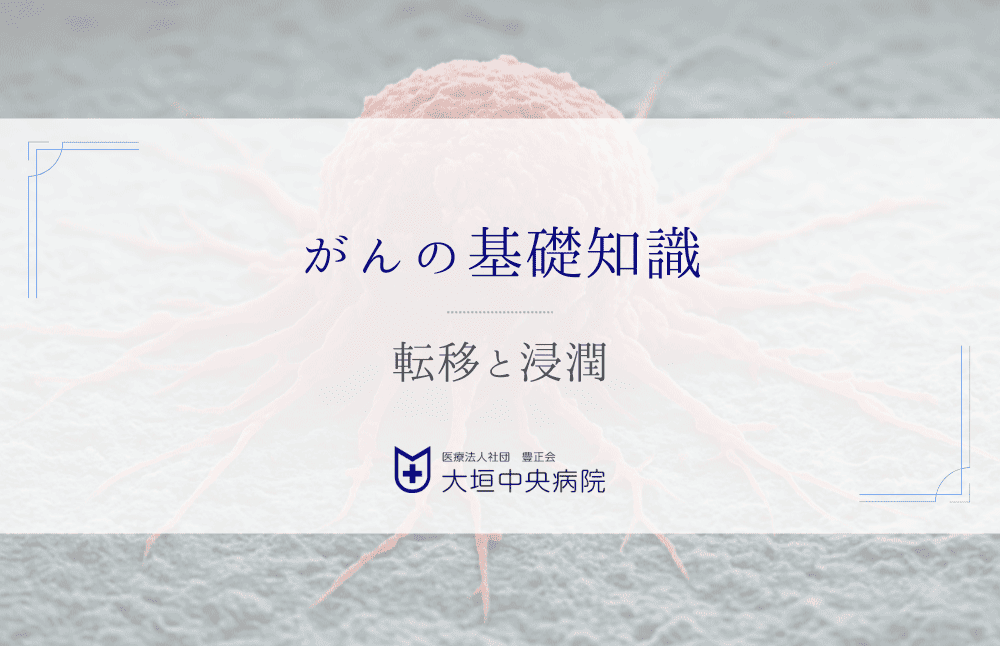がんと診断されたとき、多くの方が「転移」や「浸潤」という言葉を耳にします。
これらの言葉は、がんの進行度や今後の治療方針を考える上でとても重要ですが、その違いや意味を正確に理解するのは簡単ではありません。
この記事では、がんの転移と浸潤の基本的な知識を分かりやすく解説し、患者様ご自身が病気と向き合い、治療に臨むための一助となることを目指します。
がんの転移とは何か – 原発巣から他の臓器への広がり
がんと向き合う上で、「転移」という言葉は、病状の進行を示す重要な指標となります。
最初にがんが発生した場所(原発巣)から、がん細胞が血液やリンパ液の流れに乗って体の他の場所へ移動し、そこで新たに増殖を始める現象、それが転移です。
この遠隔地での広がりを理解することは、ご自身の状態を把握し、今後の治療方針を考える上で大切な第一歩となります。
原発巣と転移巣の関係
転移によってできた新しいがんの塊を「転移巣」と呼びます。例えば、大腸がんが肝臓に転移した場合、その転移巣は肝臓の細胞ではなく、大腸がんの性質を持ったがん細胞で構成されます。
したがって、この場合の治療は、肝臓がんの治療ではなく、大腸がんの治療法を基本として進めます。この原発巣の性質を維持するという特徴は、治療法選択の根幹をなす重要な考え方です。
原発巣と転移巣の基本的な違い
| 項目 | 原発巣のがん | 転移巣のがん |
|---|---|---|
| 発生場所 | がんが最初に発生した臓器 | 原発巣から移動した先の臓器 |
| がん細胞の性質 | 発生した臓器の細胞に由来する | 原発巣のがん細胞と同じ性質を持つ |
| 治療の基本方針 | 原発巣のがんの種類に基づく | 原発巣のがんの種類に基づく |
転移という現象が持つ意味
がんの転移が確認されるということは、がんが原発巣だけにとどまらず、全身に広がっている可能性を示唆します。
そのため、治療方針も局所的な治療だけでなく、全身に効果を及ぼす薬物療法などを組み合わせた、より包括的なアプローチが必要になることが多くなります。
浸潤のメカニズム – がん細胞が周囲の組織に侵入する過程
「浸潤」は、がんがその場で広がる最初の段階を示す言葉です。がん細胞が、発生した場所から周囲の正常な組織へとじわじわと染み込むように広がっていく様子を指します。
まるで木の根が地中に伸びていくように、がん細胞は組織の境界を破壊しながらその範囲を広げていきます。この局所的な広がりが、やがて転移へとつながる重要な段階となります。
がん細胞の増殖と広がり
がん細胞は、正常な細胞とは異なり、無秩序に増殖を続けます。増え続けたがん細胞は塊(腫瘍)を形成し、次第に周囲の組織を圧迫し始めます。
さらに、がん細胞は特殊な酵素を出して、組織と組織の間にある壁(基底膜)を溶かし、そこから内部へと侵入していきます。この一連の動きが浸潤です。
浸潤の進行度合い
浸潤がどのくらいの深さまで達しているかは、がんの進行度を判断する上で極めて重要です。浸潤が浅い段階であれば、がんは臓器の表面に近い部分にとどまっています。
しかし、浸潤が進むと、臓器の壁のより深い層へと達し、最終的には壁を突き破って隣の臓器にまで及ぶこともあります。
浸潤の段階的な広がり
| 浸潤の段階 | がん細胞の状態 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 早期 | 臓器の表面(粘膜内)にとどまる | この段階での発見と治療が理想的 |
| 進行期 | 臓器の壁の深い部分まで達する | 転移のリスクが高まり始める |
| 末期 | 臓器の壁を突き破り、隣接臓器に及ぶ | 局所的な進行が著しい状態 |
転移と浸潤の違いを理解する – 2つの進展様式の特徴
転移と浸潤は、どちらもがんが広がる現象ですが、その様式は根本的に異なります。浸潤は「局所的」な広がり、転移は「遠隔的」な広がりと理解すると分かりやすいでしょう。
この二つの違いを正しく知ることは、医師からの説明を理解し、ご自身の病状を正確に把握するために役立ちます。
場所で考える二つの違い
浸潤は、がんが発生した場所とそのすぐ隣の組織で起こる現象です。一方、転移は、がん細胞が血液やリンパの流れに乗って、原発巣から遠く離れた臓器で新たに増殖することを指します。
例えば、胃がんが胃の壁に深く食い込んでいくのが浸潤、胃がんのがん細胞が肝臓や肺に飛んでいくのが転移です。
がんの進行における両者の関係
浸潤は、転移が起こるための前提条件とも言えます。がん細胞は、まず周囲の組織に浸潤して血管やリンパ管に到達しなければ、血流やリンパ流に乗って遠くへ移動することができません。
つまり、浸潤が進むほど、転移のリスクは高まると考えられます。
浸潤と転移の比較
| 項目 | 浸潤 (Invasion) | 転移 (Metastasis) |
|---|---|---|
| 広がる範囲 | 局所的(がんの周囲) | 遠隔的(全身の様々な臓器) |
| 移動方法 | 組織へ染み込むように直接広がる | 血液やリンパ液の流れに乗って移動 |
| 関係性 | 転移が起こるための第一歩 | 浸潤が進行した結果として起こる |
がんの転移経路 – 血行性・リンパ行性・播種性の3つのルート
がん細胞が原発巣から他の臓器へと旅をする際には、主に3つのルートが存在します。どのルートを通りやすいかは、がんの種類や発生した場所によって異なります。
これらの転移の「通り道」を知ることで、なぜ特定のがんが特定の臓器に転移しやすいのかを理解する手がかりになります。
血行性転移 血の流れに乗って
がん細胞が、浸潤の過程で毛細血管などの血管内に侵入し、血液の流れに乗って全身へと運ばれるのが血行性転移です。
血液は全身の臓器を巡っているため、このルートは肺、肝臓、骨、脳など、様々な臓器への転移の原因となります。
リンパ行性転移 リンパの流れに乗って
私たちの体には、血管網と並行してリンパ管網が張り巡らされています。がん細胞がリンパ管に侵入し、リンパ液の流れに乗って移動するのがリンパ行性転移です。
リンパ液は、途中にある関所のような「リンパ節」を経由します。そのため、多くの場合、まず原発巣に最も近いリンパ節に転移し、そこからさらに遠くのリンパ節へと段階的に広がっていきます。
手術でがん組織と一緒に周囲のリンパ節を切除(郭清)するのは、このリンパ行性転移の可能性を考慮しているためです。
播種性転移 体の空間に種をまくように
胃や大腸など、お腹の中(腹腔)にある臓器にできたがんが、臓器の表面を覆う膜(漿膜)を突き破ると、がん細胞が腹腔内にパラパラと散らばることがあります。
これが種をまく様子に似ていることから「播種(はしゅ)」と呼ばれます。腹膜播種がその代表例で、広範囲にがんが広がるため、治療が難しい場合があります。
3種類の転移ルート概要
| 転移のルート | 移動の媒体 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 血行性転移 | 血液 | 肺・肝臓・骨など全身の臓器が標的となる |
| リンパ行性転移 | リンパ液 | まず近くのリンパ節へ転移することが多い |
| 播種性転移 | 腹腔・胸腔などの体腔液 | 腹膜や胸膜に種をまくように広がる |
転移しやすい臓器とその理由 – 肺・肝臓・骨・脳への転移
がんの種類によって、転移しやすい臓器にはある程度の傾向があります。これは、原発巣の臓器と血流の関係や、転移先の臓器の環境ががん細胞の増殖に適しているかどうかなどが関係しています。
ここでは、特に転移が多い肺、肝臓、骨、脳について、その理由と症状を解説します。
肺への転移とみられる症状
肺は、心臓から送り出された全身の血液が必ず通過するフィルターのような役割を持つ臓器です。そのため、血行性転移の標的になりやすい特徴があります。
初期の肺転移では症状がないことも多いですが、がんが大きくなると、持続する咳、血痰、息切れ、胸の痛みなどの症状が現れることがあります。
肝臓への転移とその原因
胃や大腸、膵臓など消化器系のがんは、肝臓に転移しやすい傾向があります。これは、これらの臓器を流れた血液が、栄養を運ぶ「門脈」という太い血管を通って、まず肝臓に集められるためです。
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、転移があっても初期には症状が出にくいですが、進行すると腹部の張り、黄疸、全身の倦怠感などの症状が現れます。
骨への転移で注意すべき症状
乳がんや前立腺がん、肺がんなどは骨に転移しやすいことで知られています。骨転移の主な症状は、持続的な痛みです。
また、骨がもろくなるため、軽い衝撃で骨折(病的骨折)を起こしたり、血液中のカルシウム濃度が高くなる「高カルシウム血症」という状態を引き起こしたりすることもあります。
主な原発巣と転移しやすい臓器
| 原発巣のがん | 転移しやすい主な臓器 |
|---|---|
| 大腸がん | 肝臓、肺、腹膜 |
| 乳がん | 骨、肺、肝臓、脳 |
| 肺がん | 脳、骨、肝臓、副腎 |
浸潤の深さが意味すること – ステージ分類との関係
がんの進行度を示す「ステージ(病期)」は、今後の治療方針を決定し、予後を予測する上で最も重要な情報の一つです。
このステージ分類において、浸潤の深さは「T因子」として評価され、ステージを決定する根幹をなす要素となります。
TNM分類におけるT因子
がんのステージは、国際的に用いられる「TNM分類」に基づいて決定します。
- T (Tumor) 原発巣の腫瘍の大きさと浸潤の深さ
- N (Node) 所属リンパ節への転移の有無と広がり
- M (Metastasis) 遠隔転移の有無
このうち、T因子はがんが臓器の壁のどの深さまで達しているかを示します。Tの数字が大きくなるほど、浸潤が深いことを意味し、ステージも高くなります。
T因子の一般的な分類例
| T因子 | 浸潤の深さの目安 |
|---|---|
| Tis (上皮内がん) | がんが粘膜の最も浅い層にとどまる |
| T1-T3 | 数字が大きくなるほど壁の深い層へ浸潤 |
| T4 | がんが臓器の壁を突き破り、周囲の組織や臓器に及ぶ |
ステージ進行と浸潤
浸潤が深くなりT因子が進行すると、がんは血管やリンパ管に到達しやすくなります。その結果、N因子(リンパ節転移)やM因子(遠隔転移)が陽性になる可能性が高まります。
このように、浸潤の深さは、がんの局所的な進行度だけでなく、全身への広がりやすさを示す重要なバロメーターと言えます。
転移・浸潤の検査方法 – 画像診断と病理検査の役割
転移や浸潤の有無、そしてその広がりを正確に評価するためには、様々な種類の検査を組み合わせて行います。体の内部を画像で見る「画像診断」と、採取した組織を顕微鏡で調べる「病理検査」がその二本柱です。
これらの検査結果を総合的に判断し、がんのステージを確定します。
画像で見る検査
画像診断は、体に大きな負担をかけることなく、がんの存在や広がりを視覚的に捉えることができます。
- CT検査 X線を使って体の断面を撮影し、ミリ単位でがんの大きさや位置、リンパ節への転移などを評価します。
- MRI検査 磁気を利用して体の内部を撮影します。特に脳や肝臓、骨盤内の臓器など、CTでは分かりにくい部分の評価に有用です。
- PET検査 がん細胞が正常細胞よりも多くのブドウ糖を取り込む性質を利用し、全身のがん細胞の活動を調べる検査です。予期せぬ転移の発見に役立ちます。
組織を調べる確定診断
画像診断でがんが疑われた場合、最終的な確定診断のために病理検査を行います。これは、がんが疑われる部分の組織の一部を採取し(生検)、顕微鏡でがん細胞の有無や顔つき(悪性度)を直接確認する検査です。
この検査によって、がんの種類が確定し、治療方針の決定に繋がります。
主な検査の役割分担
| 検査の種類 | 主な目的 | 分かることの例 |
|---|---|---|
| CT / MRI | がんの形、大きさ、位置の把握 | 浸潤の深さ、リンパ節の腫れ |
| PET | 全身のがん細胞の活動を調べる | 遠隔転移の有無、再発の発見 |
| 病理検査 | がんの確定診断、種類の特定 | がん細胞の有無、悪性度 |
転移・浸潤と予後の関係 – 治療選択への影響
転移や浸潤の有無は、がんの予後(今後の病状の見通し)と密接に関係し、治療法の選択に大きな影響を与えます。
一般的に、がんは原発巣にとどまっている早期の段階ほど予後が良く、転移が認められる進行した段階では、より慎重な経過観察と集学的な治療が必要となります。
生存率で見る予後
がんの予後を示す指標の一つに「5年相対生存率」があります。これは、あるがんと診断された人のうち、5年後に生存している人の割合を、日本人全体の5年後の生存率と比較した数値です。
この生存率は、がんのステージによって大きく異なります。ステージが進む、つまり転移や浸潤が広範囲に及ぶほど、生存率は低下する傾向にあります。
ただし、これはあくまで統計上のデータであり、個々の患者様の未来を決定するものではありません。
転移の有無による5年相対生存率の違い(全がん平均・目安)
- 限局(浸潤のみ・転移なし): 約90%以上
- がんが原発巣にとどまっている状態。
- 領域(近くのリンパ節転移あり): 約60〜70%
- 所属リンパ節への転移がある状態。
- 遠隔転移あり(ステージIV): 約10〜20%
- 肺や肝臓など、離れた臓器への転移がある状態。
※これは全てのがんを合わせた平均値であり、がんの種類によって大きく異なります(例:甲状腺がんは転移があっても予後が良い傾向があります)。
治療方針決定への影響
転移がなく、浸潤も浅いがんであれば、手術や放射線治療といった局所的な治療法で根治を目指せる可能性が高くなります。
一方、遠隔転移がある場合は、がんが全身に広がっている状態と考えられるため、化学療法や免疫療法といった全身に作用する薬物療法が治療の中心となります。
このように、転移と浸潤の評価は、治療のゴールと手段を決定する上で最も重要な情報となります。
転移・浸潤を防ぐための治療戦略 – 手術・薬物療法・放射線治療
がんの治療は、転移や浸潤の状況に応じて、様々な治療法を組み合わせて行います。
治療の目的は、がんを完全に取り除くこと(根治)、がんの進行を抑えること、そしてがんによる症状を和らげること(緩和)など、病状によって様々です。
ここでは、主な治療法である手術、薬物療法、放射線治療について解説します。
局所を治す手術と放射線療法
がんが原発巣とその周辺に限局している場合、その部分を物理的に取り除く、あるいは叩く治療が中心となります。
- 手術療法 がん組織とその周囲の正常組織の一部、そして転移の可能性があるリンパ節を一緒に切除します。根治を目指す上で基本となる治療法です。
- 放射線療法 高エネルギーのX線などをがん細胞に照射して破壊する治療法です。手術が難しい場合や、手術後の再発予防、骨転移による痛みの緩和など、様々な目的で用います。
全身に働きかける薬物療法
目に見えないレベルで全身に広がっている可能性のあるがん細胞や、実際に転移が確認されたがんに対しては、薬物による全身治療を行います。
化学療法と免疫療法の違い
化学療法は、細胞分裂が速いがん細胞を標的にする抗がん剤を用いて、がんの増殖を抑えたり破壊したりする治療です。
一方、免疫療法は、患者様自身が本来持っている免疫の力(免疫チェックポイント阻害薬など)を利用して、がんと戦う力を高める新しいアプローチの治療法です。
がんの種類や患者様の状態によって使い分けたり、組み合わせたりします。
再発を防ぐための補助療法
手術で目に見えるがんをすべて取り除いた後でも、画像には映らない微小ながん細胞が体内に残っている可能性があります。
これが将来の再発の原因となるため、手術後に行う薬物療法を「術後補助療法」と呼びます。これにより、再発のリスクを下げることが期待できます。
よくある質問
- ステージⅣと診断されたらもう治療法はないのでしょうか?
-
いいえ、そんなことはありません。ステージⅣは遠隔転移がある状態を指し、根治が難しい場合が多いのは事実ですが、治療法がなくなるわけではありません。
近年の薬物療法の進歩は目覚ましく、化学療法や免疫療法、分子標的薬などにより、がんの進行を長期間コントロールしたり、症状を和らげたりすることが可能になってきています。
治療の目標を「がんと共存する」ことに置き、QOL(生活の質)を維持しながら治療を続ける選択肢があります。
- 転移と再発はどう違うのですか?
-
転移は、最初の診断時に、原発巣とは別の場所にがんが見つかる状態を指すことが多いです。一方、再発は、手術や放射線治療などで一度は目に見えるがんがなくなった後、再びがんが出現することを言います。
再発には、元の場所の近くで起こる「局所再発」と、遠くの臓器で起こる「遠隔再発」があります。この遠隔再発は、実質的には転移と同じ状態です。
- 症状がなくても転移していることはありますか?
-
はい、十分にあり得ます。特に、肺や肝臓への転移は、かなり進行するまで自覚症状が現れないことが少なくありません。
そのため、がんの治療後は、自覚症状がなくても定期的に画像検査などを受け、転移や再発が起きていないかを確認することがとても重要です。
以上
参考文献
SRIHARIKRISHNAA, S.; SURESH, Padmanaban S.; PRASADA K, Shama. An introduction to fundamentals of cancer biology. In: Optical Polarimetric Modalities for Biomedical Research. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 307-330.
TARIN, David. Cell and tissue interactions in carcinogenesis and metastasis and their clinical significance. In: Seminars in cancer biology. Academic Press, 2011. p. 72-82.
FRANKS, Leonard Maurice; TEICH, Natalie M. (ed.). Introduction to the cellular and molecular biology of cancer. Oxford University Press, 1997.
MCKINNELL, Robert G. The biological basis of cancer. Cambridge University Press, 1998.
HEJMADI, Momna. Introduction to cancer biology. Bookboon, 2014.
TARIN, David. Understanding cancer: the molecular mechanisms, biology, pathology and clinical implications of malignant neoplasia. Springer Nature, 2023.
TOBIAS, Jeffrey S.; HOCHHAUSER, Daniel. Cancer and its management. John Wiley & Sons, 2009.
STEPHENS, Frederick O., et al. Basics of oncology. Dordrecht: Springer, 2009.
JAIN, Buddhi Prakash; PANDEY, Shweta (ed.). Understanding cancer: From basics to therapeutics. Academic Press, 2022.