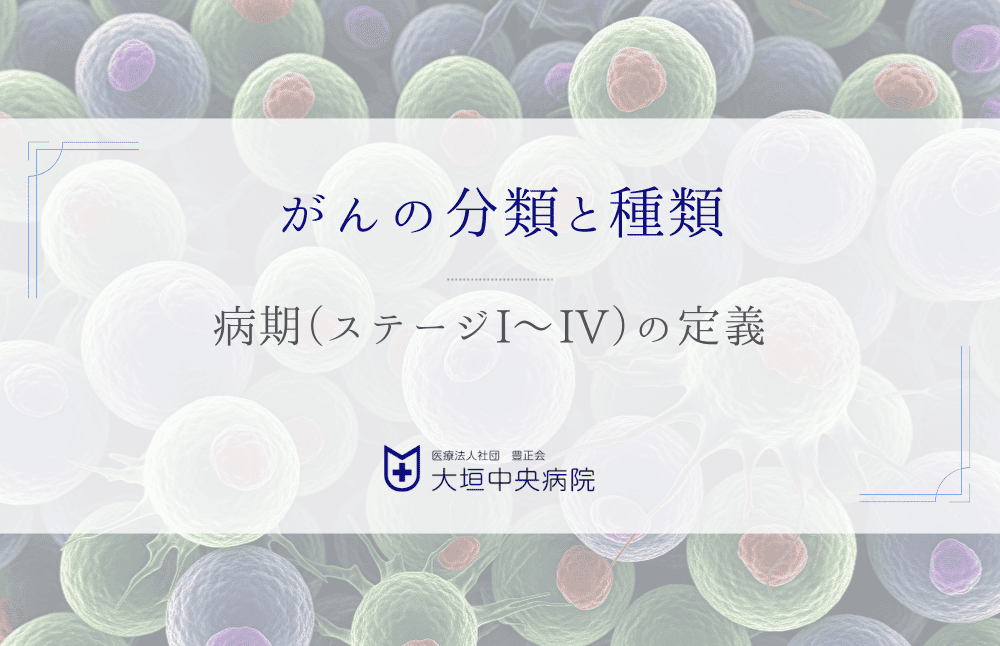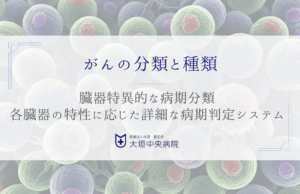がんと診断された時、多くの方が「ステージ」という言葉を耳にします。このステージは、病状の広がり、つまり進行度を客観的に示す重要な指標です。
ステージを知ることは、ご自身の体のなかで何が起きているのかを正しく理解し、医師と共に最善の治療方針を考えていくための第一歩となります。
この記事では、がんのステージが何を意味し、どのように決まるのか、そしてそれが治療や予後にどう関わるのかを、国際的な基準である「TNM分類」にも触れながら、一つひとつ丁寧に解説します。
正しい知識は、不安を和らげ、前向きに治療と向き合う力になります。
がんの病期(ステージ)とは何か
がんの診断において「病期」または「ステージ」という言葉は、がんが体の中でどのくらい広がっているかを示す「ものさし」の役割を果たします。
これは医師が病状を正確に把握し、適切な治療計画を立てるための基礎情報です。患者さん自身が病状を理解し、治療に主体的に関わるためにも、ステージの意味を知ることは非常に大切です。
病期分類が示すがんの進行度
ステージは、がんの進行度を数字やローマ数字(I, II, III, IV)で表したものです。数字が小さいほど早期のがんであり、大きくなるにつれて進行していることを示します。
この分類は、がんが最初に発生した場所(原発巣)から、どれだけ大きくなっているか、周囲の組織に浸潤しているか、近くのリンパ節や他の臓器(遠隔臓器)に転移しているか、といった複数の要素を総合的に評価して決定します。
進行度を客観的に示す指標
ステージ分類は、世界共通の基準に基づいて行われるため、誰が見ても同じように病状の進行度を理解できる客観的な指標です。
これにより、異なる医療機関であっても、一貫性のある評価と治療を提供することが可能になります。この共通の理解が、医療の質を保つ上で重要な役割を担っています。
ステージが持つ治療選択上の意味
診断されたステージは、その後の治療方針を決定する上で極めて重要な情報です。
例えば、がんが限られた場所にとどまっている早期のステージでは、手術や放射線治療といった局所的な治療で根治を目指すことが多くなります。
一方、がんが広範囲に広がっている進行したステージでは、薬物療法を中心とした全身的な治療が必要になるなど、ステージに応じて治療の目的や方法が大きく異なります。
ステージ概要
| ステージ | 進行度の目安 | 一般的な状態 |
|---|---|---|
| I期 | 早期 | がんが原発巣に限局している |
| II期・III期 | 局所進行 | がんが周囲の組織やリンパ節に広がっている |
| IV期 | 遠隔転移 | がんが他の臓器に転移している |
なぜがんにステージ分類が必要なのか
がんのステージ分類は、単に病状の進行度を示すだけではありません。医療チームが最適な治療を提供し、患者さんが今後の見通しを立てる上で、いくつかの重要な役割を果たしています。
この客観的な分類があるからこそ、標準的で質の高い医療が実現します。
治療方針決定の共通言語
ステージは、医師や看護師、薬剤師など、がん治療に関わる全ての医療スタッフが、患者さんの状態を正確に共有するための「共通言語」です。
例えば「肺癌のステージIIIA」と聞けば、医療従事者はがんのおおよその広がりや、考えられる治療の選択肢を即座にイメージできます。
この共通認識のもとで治療方針を議論することで、チームとして一貫した医療を提供できるのです。
予後を予測するための客観的指標
ステージは、治療後の経過、すなわち「予後」を予測するための統計的なデータに基づいた指標でもあります。
過去に同じステージと診断された多くの患者さんの治療結果を分析することで、今後の病状の見通しや、治療の効果についてある程度の予測を立てることが可能です。
もちろん、予後は個人差が大きいものですが、ステージ分類は将来を考える上での一つの目安となります。
医師と患者が病状を共有する大切さ
ステージという客観的な指標を用いることで、医師は患者さんやご家族に対して、現在の病状を具体的かつ分かりやすく説明できます。
専門的で複雑な病状も、ステージという共通の言葉で表現することで、患者さん自身が自分の状態を理解し、納得して治療に臨む助けになります。
- 治療方針の決定
- 予後の予測
- 臨床試験の対象分け
- 治療効果の評価
ステージI – 早期がんの特徴と定義
ステージIは、がんの分類の中で最も早期の段階を示します。この段階で発見されると、多くの場合、根治を目指した治療が可能であり、良好な予後が期待できます。
ステージIがどのような状態を指すのか、その定義と特徴を詳しく見ていきましょう。
がんが原発巣にとどまる状態
ステージIの最も重要な特徴は、がんが最初に発生した臓器(原発巣)の中にとどまっていることです。がん細胞はまだ周囲の組織に深く浸潤しておらず、その広がりは限定的です。
大きさも比較的小さなものが多く、この段階での治療は、がんを完全に取り除くことを主な目的とします。
リンパ節転移がないことの重要性
がん細胞は、リンパ管を通ってリンパ節にたどり着き、そこで増殖することがあります。
これをリンパ節転移と呼び、がんが広がり始める兆候の一つです。ステージIでは、基本的にこのリンパ節への転移が認められません。
リンパ節に転移がないことは、がんがまだ局所にとどまっている強力な証拠であり、治療成績が良好である大きな理由の一つです。
ステージIにおける治療と予後
ステージIのがんに対する治療は、手術による切除が第一選択となることが多いです。がんの種類や発生した場所によっては、放射線治療や内視鏡治療も選択肢となります。
この段階で適切な治療を行えば、多くのがんで高い生存率が期待できます。早期発見、早期治療がいかに重要であるかを示すステージと言えます。
ステージIの一般的な特徴
| 評価項目 | 状態 | 意味 |
|---|---|---|
| がんの大きさ・広がり | 比較的小さく、限局的 | 原発巣内にとどまっている |
| リンパ節転移 | なし | がんの広がりが限定的である証拠 |
| 遠隔転移 | なし | 他の臓器への転移はない |
ステージII・III – 局所進行がんの判定基準
ステージIIとステージIIIは、がんが原発巣を越えて周囲の組織や近くのリンパ節へと広がり始めた「局所進行がん」と呼ばれる状態です。
早期がん(ステージI)と遠隔転移がある進行がん(ステージIV)の中間に位置します。この段階では、より集学的な治療が必要となることが多くなります。
ステージIIの定義 がんの広がりとリンパ節への影響
ステージIIは、ステージIよりもがんが大きくなっているか、原発巣のある臓器の壁に深く浸潤している状態を指します。
がんの種類によっては、原発巣に最も近いリンパ節に少数の転移が認められる場合もステージIIに分類されることがあります。
まだがんは原発臓器の周辺にとどまっていますが、局所での進行が見られる段階です。
ステージIIIの定義 より広範囲なリンパ節転移
ステージIIIは、ステージIIよりもさらにがんが進行し、リンパ節への転移がより広範囲に及んでいる状態です。転移しているリンパ節の数や場所が、ステージを決定する重要な要素となります。
また、がんが原発臓器を越えて、隣接する重要な組織や臓器にまで及んでいる場合もステージIIIと診断されます。手術だけではがんを取り除くことが難しくなるケースも増えてきます。
手術の適応と治療法の組み合わせ
ステージIIやIIIでは、手術が可能であっても、術後に再発のリスクを減らす目的で化学療法(抗がん剤治療)や放射線治療を組み合わせる「集学的治療」を行うことが一般的です。
また、手術の前に薬物療法を行い、がんを小さくしてから手術に臨むこともあります。治療方針は、がんの種類、進行度、そして患者さん自身の体力などを総合的に判断して決定します。
ステージIIとIIIの比較
| ステージ | がんの広がり | リンパ節転移の状態 |
|---|---|---|
| II期 | 原発巣の壁への深い浸潤、または近傍リンパ節への軽度な転移 | なし、またはごく少数 |
| III期 | 隣接臓器への浸潤、または広範囲なリンパ節転移 | 多数または広範囲 |
ステージIV – 遠隔転移の意味と診断
ステージIVは、がんの病期分類の中で最も進行した段階です。このステージは、がんが最初に発生した場所から離れた他の臓器にまで広がっている状態、すなわち「遠隔転移」が認められることを意味します。
治療の目的や考え方も、早期がんとは大きく異なります。
遠隔転移とは何か
遠隔転移とは、がん細胞が血液やリンパの流れに乗って全身を巡り、原発巣から離れた臓器(例えば、肺がんが脳や骨に転移する、大腸がんが肝臓に転移するなど)に生着して、そこで新たな腫瘍を形成することです。
この状態になると、がんは局所的な病気ではなく、全身に影響を及ぼす病気として捉える必要があります。
ステージIVと診断された場合の治療目標
ステージIVのがんでは、がんを完全に体からなくすこと(根治)が困難な場合が多くなります。
そのため、治療の主な目標は、がんの進行をできるだけ抑え、症状を和らげ、生活の質(QOL)を維持しながら、がんと共存していくことに置かれます。
もちろん、近年の治療法の進歩により、ステージIVであっても長期にわたり良好な状態を保つことができる患者さんも増えています。
全身治療の重要性
遠隔転移がある場合、目に見える転移巣だけでなく、画像検査では捉えきれない微小ながん細胞が全身に散らばっている可能性があります。
そのため、手術や放射線治療のような局所的な治療だけでは不十分であり、抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬といった、全身に効果を及ぼす薬物療法が治療の中心となります。
がんの種類と主な遠隔転移部位
| がんの種類 | 転移しやすい部位 |
|---|---|
| 肺癌 | 脳、骨、肝臓、副腎 |
| 大腸癌 | 肝臓、肺、腹膜 |
| 乳がん | 骨、肺、肝臓、脳 |
| 胃がん | 肝臓、腹膜、リンパ節 |
TNM分類で読み解く病期の仕組み
がんのステージは、医師の主観で決まるものではなく、「TNM分類」という国際的に標準化された基準に基づいて客観的に評価されます。
このTNM分類は、3つの異なる要素を評価し、それらを組み合わせることで最終的なステージを決定します。この仕組みを理解することで、ご自身の病状をより深く知ることができます。
T因子 原発腫瘍の大きさと広がり
TはTumor(腫瘍)の頭文字で、最初にがんが発生した場所(原発巣)の腫瘍そのものの状態を示します。
具体的には、腫瘍の大きさや、原発臓器の壁のどの深さまでがんが達しているか(浸潤の深さ)、周囲の組織への広がりの程度を評価します。
Tの後ろに続く数字(T1, T2, T3, T4など)が大きくなるほど、腫瘍が大きく、広がりが高度であることを意味します。
N因子 所属リンパ節への転移の有無と範囲
NはNode(リンパ節)の頭文字で、原発巣の近くにある所属リンパ節への転移の状態を示します。
リンパ節転移がないか(N0)、転移があるか、ある場合はどの範囲のリンパ節まで、いくつ転移しているか(N1, N2, N3など)を評価します。
数字が大きくなるほど、リンパ節転移が広範囲に及んでいることを示します。
M因子 遠隔転移の有無
MはMetastasis(転移)の頭文字で、原発巣から離れた臓器への遠隔転移があるかどうかを示します。評価はシンプルで、遠隔転移がない場合はM0、ある場合はM1と分類します。
M1と評価された時点で、がんの種類にかかわらず、ステージは原則としてIV期となります。
TNM因子の概要
| 因子 | 評価項目 | 意味 |
|---|---|---|
| T (Tumor) | 原発腫瘍の大きさと広がり | T1〜T4で評価。数字が大きいほど進行。 |
| N (Node) | 所属リンパ節への転移 | N0〜N3で評価。数字が大きいほど広範囲。 |
| M (Metastasis) | 遠隔転移 | M0 (なし) か M1 (あり) で評価。 |
TNMの組み合わせとステージ決定
最終的なステージは、これらT・N・Mの3つの因子の評価結果を、がんの種類ごとに定められた対照表に当てはめて決定します。
例えば、同じT1N0M0という評価でも、がんの種類によってステージIと決まることもあれば、他のステージになることもあります。
この詳細な分類により、個々の患者さんの病状に合わせた、より適切な治療方針の選択が可能になります。
がんの種類によって異なるステージの基準
TNM分類は全てのがんに共通する評価の枠組みですが、その具体的な基準はがんが発生した臓器(がんの種類)によって大きく異なります。
臓器の解剖学的な構造や、がんの進行の仕方の特徴がそれぞれ違うためです。ここでは代表的ながんを例に、ステージ基準の違いを見てみましょう。
肺癌における特有の分類基準
肺癌のTNM分類は非常に細かく規定されています。T因子は腫瘍の大きさに加え、気管支への浸潤の程度や、胸水(きょうすい)の有無なども評価対象となります。
N因子も、転移したリンパ節の位置によって細かく分類されます。例えば、同じ肺の中のリンパ節への転移(N1)と、左右の肺の間(縦隔)のリンパ節への転移(N2)では、ステージが大きく変わります。
これらの複雑な要素を組み合わせて、肺癌の進行度を正確に評価します。
大腸癌のステージ分類とその特徴
大腸癌のステージ分類で特に重要なのは、がんが大腸の壁のどの深さまで達しているかという「深達度」です。これがT因子を決定する最も大きな要素となります。
大腸の壁はいくつかの層でできており、がんが粘膜内にとどまっている早期のものから、壁を突き破って外に出ているものまで、深達度によってTの評価が変わります。
リンパ節転移の個数も予後に大きく影響するため、N因子の評価で重視されます。
肺癌と大腸癌のステージI基準比較例
| がんの種類 | ステージIと判定されるTNMの組み合わせ例 |
|---|---|
| 肺癌 | T1a-c N0 M0 (腫瘍が3cm以下で転移なし) など |
| 大腸癌 | T1 N0 M0, T2 N0 M0 (がんが固有筋層までで転移なし) など |
他のがん種での分類の違い
他のがん、例えば乳がんでは腫瘍の大きさに加えてホルモン受容体の有無やHER2というタンパク質の発現状態などもステージ分類や治療方針決定に加味されます。
胃がんでは大腸がんと同様に壁の深達度が重要視されます。このように、がんの種類ごとに独自の評価基準が設けられており、それぞれの特性に合わせた精密な分類が行われています。
病期診断に用いられる検査方法
がんのステージを正確に決定するためには、体の内部を詳しく調べるさまざまな検査が必要です。
これらの検査によって、がんの大きさ、広がり、リンパ節や他の臓器への転移の有無を詳細に評価し、TNM分類を確定します。
ここでは、病期診断に用いられる主な検査を紹介します。
画像診断 CT、MRI、PET検査の役割
画像診断は、ステージ診断の中心となる検査です。CT(コンピュータ断層撮影)検査は、X線を使って体の断面画像を撮影し、腫瘍の大きさや位置、リンパ節の腫れなどを広範囲に調べます。
MRI(磁気共鳴画像)検査は、磁気を利用して体の内部を撮影する検査で、特に骨盤内や脳など、軟部組織の描出に優れています。
PET(陽電子放出断層撮影)検査は、がん細胞が正常細胞よりも多くのブドウ糖を取り込む性質を利用して、全身のがん細胞の活動を調べる検査で、予期せぬ遠隔転移の発見に役立つことがあります。
- CT検査 (全身の広がりを把握)
- MRI検査 (特定の部位を詳細に観察)
- PET検査 (全身のがん細胞の活動を評価)
内視鏡検査と生検による確定診断
胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査は、消化管の内部を直接観察し、がんの表面的な広がりを確認します。
同時に、疑わしい組織の一部を採取する「生検」を行い、顕微鏡で調べることで、がん細胞の存在を確定(確定診断)し、その性質(顔つき)を調べます。
これはステージ診断の前提となる最も重要な検査です。
腫瘍マーカーの補助的役割
腫瘍マーカーは、がん細胞が作り出す特殊な物質で、血液検査で測定します。この数値が高い場合、がんの存在が示唆されます。
ただし、腫瘍マーカーは早期がんでは上昇しないことも多く、また、がん以外の原因で数値が上がることもあるため、これだけで診断やステージ決定はできません。
主に、治療効果の判定や再発のモニタリングの補助として用いられます。
ステージ分類が決める治療方針の選択
診断されたステージは、その後の治療法を決定する上で最も重要な道しるべとなります。
がんの進行度に応じて、治療の目的(根治を目指すのか、延命や症状緩和を目指すのか)や、用いられる治療法(手術、放射線治療、薬物療法など)が大きく変わってきます。
早期がん(ステージI)における根治を目指す治療
ステージIのようにがんが原発巣に限局している場合、治療の第一目標はがんを完全に取り除き、治癒させること(根治)にあります。
このため、がんを物理的に除去する手術や、高エネルギーのX線でがん細胞を破壊する放射線治療といった「局所療法」が治療の中心となります。
がんの種類によっては、体への負担が少ない内視鏡による切除も可能です。
局所進行がん(ステージII・III)における集学的治療
ステージIIやIIIのがんでは、局所療法だけでは再発のリスクが高いことがあります。そのため、手術、放射線治療、薬物療法(抗がん剤など)を組み合わせた「集学的治療」が行われます。
例えば、手術前に薬物療法でがんを小さくしたり、手術後に目に見えない微小ながん細胞を叩くために薬物療法を追加したりします。複数の治療法を組み合わせることで、根治の可能性を高めます。
進行がん(ステージIV)における全身治療
ステージIVでは、がんが全身に広がっているため、薬物療法などの「全身治療」が主体となります。
抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬などを使い、がんの増殖を抑えたり、症状を緩和したりすることで、QOL(生活の質)を維持しながら、できるだけ長くがんと共存することを目指します。
特定の状況下では、症状緩和のために手術や放射線治療を行うこともあります。
ステージ別治療方針の一般例
| ステージ | 主な治療法 | 治療の目的 |
|---|---|---|
| I期 | 手術、放射線治療、内視鏡治療 | 根治 |
| II期・III期 | 手術・放射線・薬物療法の組み合わせ | 根治、再発予防 |
| IV期 | 薬物療法(全身治療)、症状緩和のための局所療法 | 延命、QOLの維持・向上 |
病期と予後の関係を知る
「予後」とは、病気の経過や結末についての医学的な見通しのことです。がんのステージは、この予後を予測するための重要な情報の一つです。
一般的に、ステージが進むほど予後は慎重に見る必要がありますが、これはあくまで統計的な傾向であり、個々の患者さんの未来を決定づけるものではありません。
5年相対生存率の意味と解釈
がんの予後を示す指標として、「5年相対生存率」がよく用いられます。
これは、あるがんと診断された人のうち、5年後に生存している人の割合が、日本人全体の5年後の生存率と比べてどのくらいかを示す数値です。
例えば、5年相対生存率が90%であれば、そのがんと診断された人の5年後の生存率が、一般の日本人全体のそれと比べて90%であることを意味します。
これは治療の効果を測る上での一つの目安となります。
ステージ進行と生存率の関連性
多くのがんにおいて、ステージと5年相対生存率には明確な相関関係が見られます。一般的に、ステージIで診断された場合の生存率は高く、ステージが進むにつれて生存率は低下する傾向にあります。
これは、ステージが進むほど、がんが広範囲に広がり、治療が難しくなるためです。
しかし、これは多数の患者さんのデータを集計した平均値であり、個々の患者さんにそのまま当てはまるわけではないことを理解することが重要です。
ステージ別5年相対生存率の一般的な傾向
【全がん協加盟施設の生存率データに基づく目安】 がんの種類によって大きく異なりますが、全がん(全部位)を平均した5年相対生存率の一般的な傾向は以下の通りです。
- ステージI: 90%前後(早期発見なら非常に良好)
- ステージII: 70〜80%前後
- ステージIII: 40〜60%前後
- ステージIV: 10〜20%前後(ただし、がん種や分子標的薬の適応により長期生存も増加中)
※これはあくまで全てのがんを合わせた平均値です。例えば甲状腺がんや乳がんはこれより高く、膵臓がんはこれより低くなる傾向があります。
予後を左右する他の要因
予後はステージだけで決まるわけではありません。
がん細胞の性質(悪性度)、患者さん自身の年齢や全身状態、持病の有無、そして治療がどのくらい効果を発揮するかなど、さまざまな要因が複雑に絡み合って決まります。
同じステージであっても、これらの要因によって予後は大きく変わる可能性があります。
- がんの組織型や悪性度
- 患者さんの年齢や全身状態(PS)
- 治療への反応性
- 遺伝子変異の有無
よくある質問(FAQ)
がんのステージに関して、患者さんやご家族からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。ご自身の状況を理解する一助としてください。
- ステージは一度決まったら変わりませんか?
-
診断時に決定されたステージ(臨床病期)は、治療方針を決定するための初期評価であり、基本的には変わりません。これは、治療前の状態を記録として残しておくためです。
しかし、治療の経過によってがんの状態は変化します。
- 治療後の再発・進行による変化
-
例えば、手術後に再発したり、遠隔転移が出現したりした場合、病状は進行したことになります。
この場合、最初のステージ分類とは別に、「再発」や「進行」という言葉で現在の状態を評価し、それに応じた新たな治療方針を立てます。
最初の診断ステージが後から変更されることはありません。
- 同じステージなら予後は同じですか?
-
同じステージと診断されても、その後の経過(予後)が全ての患者さんで同じになるわけではありません。ステージは非常に重要な指標ですが、予後を決定する唯一の要因ではないためです。
- 個人差と多様な要因
-
前述の通り、予後にはがん細胞の性質、患者さんの全身状態、治療への反応性など、多くの要因が影響します。また、同じステージIIIであっても、TNM分類の組み合わせは様々です。
これらの違いが、個々の患者さんの予後の差となって現れます。ステージはあくまで統計的な見通しを示すものであり、一人ひとりの未来を保証するものでも、限定するものでもありません。
- ステージ0とは何ですか?
-
ステージ0は、TNM分類が適用される通常のがん(浸潤がん)とは少し異なる特殊な状態を指します。これは「上皮内がん」や「非浸潤がん」とも呼ばれます。
上皮内がん(非浸潤がん)の説明
がん細胞が、臓器の表面を覆う上皮という層の中にとどまっており、その下の基底膜という境界を越えていない状態です。
この段階では、がん細胞が血管やリンパ管に入り込んで転移する可能性は極めて低いと考えられています。そのため、適切に治療すれば、ほぼ100%治癒が期待できるとされています。
厳密にはTNM分類の「TisN0M0」に相当し、ステージIよりもさらに早期の段階と位置づけられます。
この記事では、ステージ分類の全体像を解説しましたが、がんの種類によって基準は細かく異なります。
例えば、肺がんや大腸がん、乳がんなど、それぞれの臓器の特性に応じた詳細な分類が存在します。
ご自身のがん種に特化したステージ分類についてさらに詳しく知りたい方は、次の記事「臓器特異的な病期分類」もぜひご覧ください。
より具体的な情報が、あなたの疑問や不安の解消につながるかもしれません。
参考文献
WU, Jiayuan, et al. Association between tumor-stroma ratio and prognosis in solid tumor patients: a systematic review and meta-analysis. Oncotarget, 2016, 7.42: 68954.
BURKE, Harry B. Outcome prediction and the future of the TNM staging system. Journal of the National Cancer Institute, 2004, 96.19: 1408-1409.
LEA, Dordi, et al. Accuracy of TNM staging in colorectal cancer: a review of current culprits, the modern role of morphology and stepping-stones for improvements in the molecular era. Scandinavian journal of gastroenterology, 2014, 49.10: 1153-1163.
CHIANG, Chi Leung, et al. Prognostic factors for overall survival in nasopharyngeal cancer and implication for TNM staging by UICC: A systematic review of the literature. Frontiers in oncology, 2021, 11: 703995.
ZHANG, Qiong-wen, et al. Prognostic significance of tumor-associated macrophages in solid tumor: a meta-analysis of the literature. PloS one, 2012, 7.12: e50946.
WOODARD, Gavitt A.; JONES, Kirk D.; JABLONS, David M. Lung cancer staging and prognosis. Lung cancer: treatment and research, 2016, 47-75.
SEXTON, Rachel E., et al. Gastric cancer: a comprehensive review of current and future treatment strategies. Cancer and Metastasis Reviews, 2020, 39.4: 1179-1203.
KOGA, Kenji, et al. A review of 79 thymomas: modification of staging system and reappraisal of conventional division into invasive and non‐invasive thymoma. Pathology international, 1994, 44.5: 359-367.
HUANG, Chih-Yang, et al. A review on the effects of current chemotherapy drugs and natural agents in treating non–small cell lung cancer. Biomedicine, 2017, 7.4: 23.
TRIKHA, Mohit, et al. Targeted anti-interleukin-6 monoclonal antibody therapy for cancer: a review of the rationale and clinical evidence. Clinical cancer research, 2003, 9.13: 4653-4665.