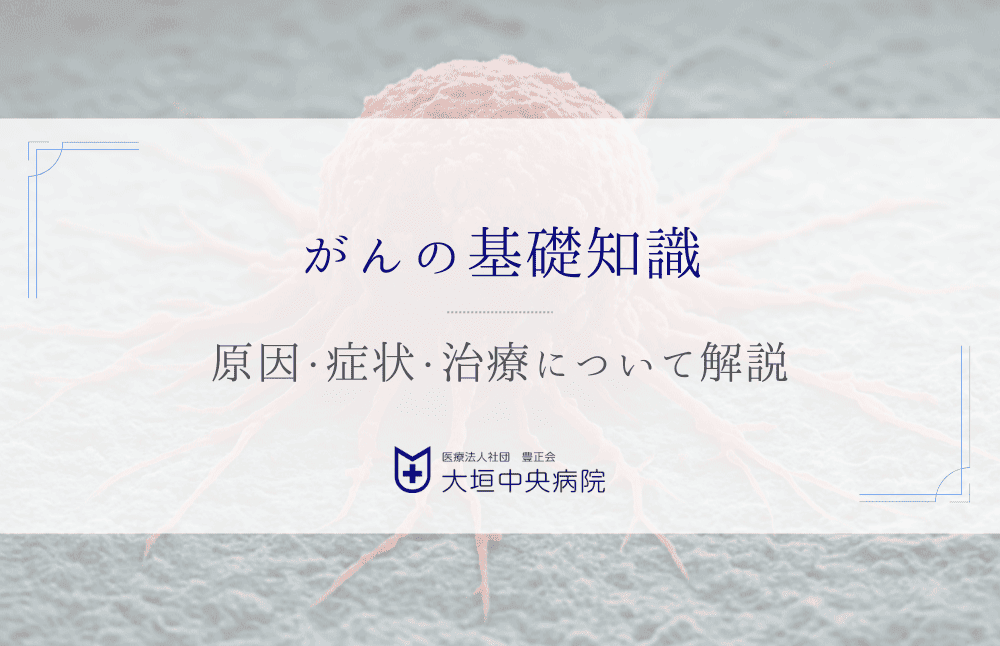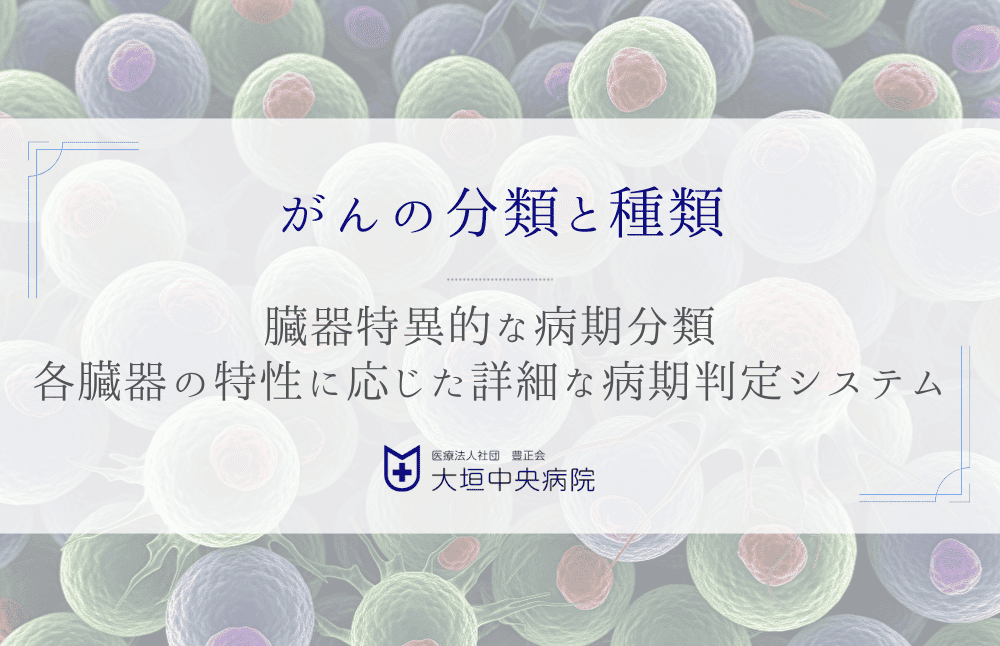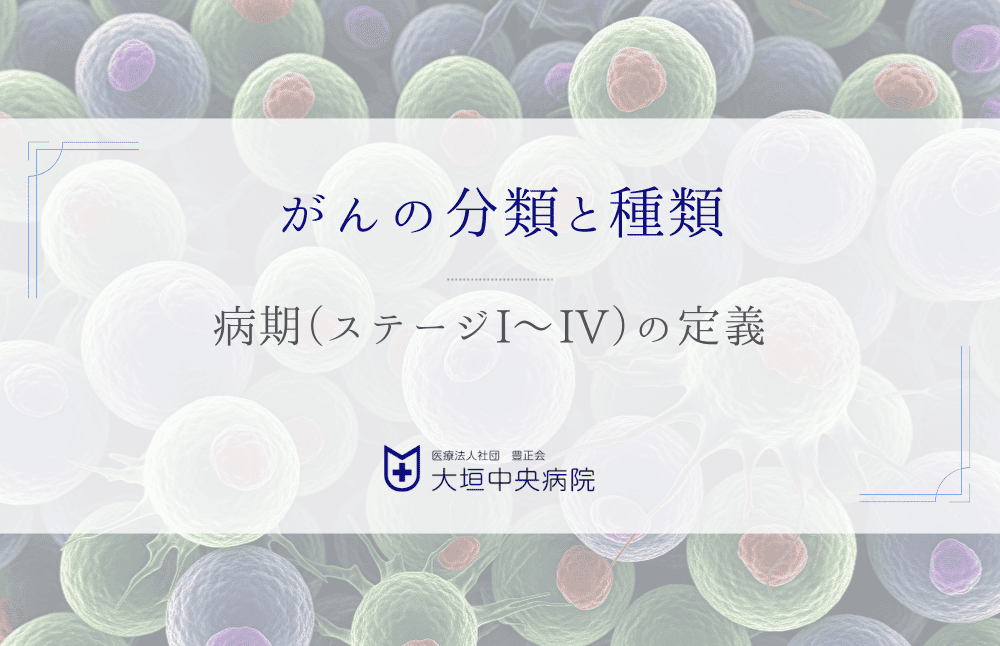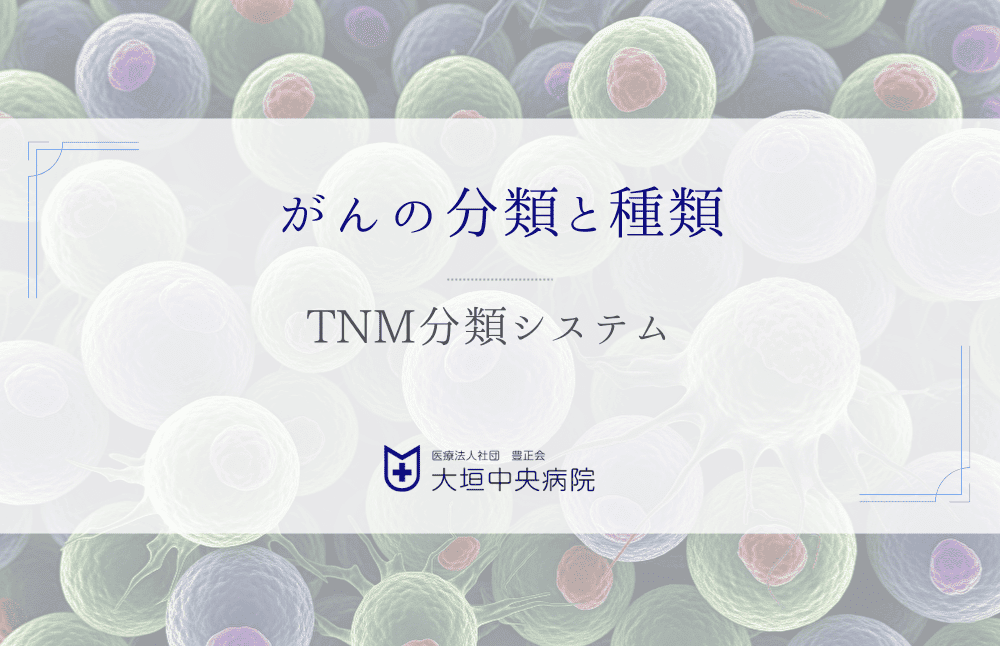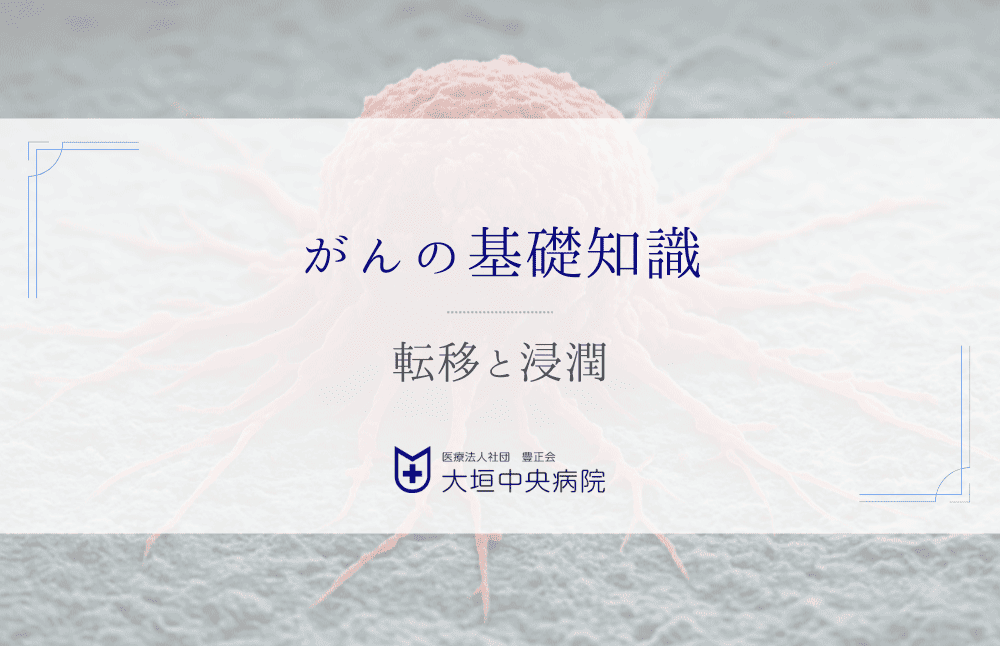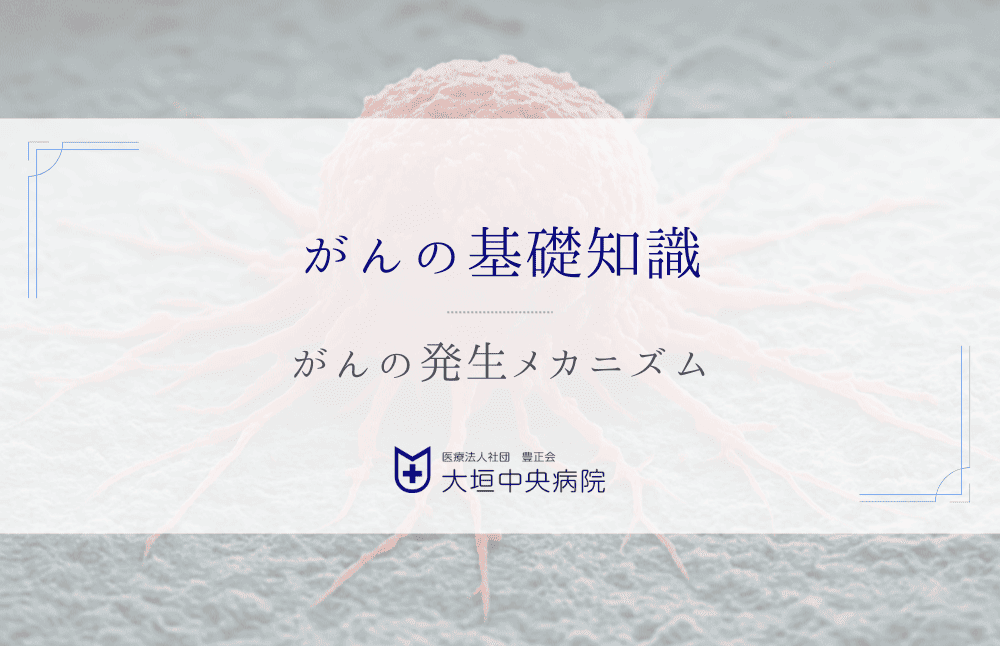がんと診断されたとき、あるいはご家族ががんと診断されたとき、多くの方が大きな不安と衝撃を受けることでしょう。
テレビやインターネットには情報が溢れていますが、その中には不正確なものや、かえって不安を煽るものも少なくありません。しかし、いたずらに恐れる必要はありません。
がんという病気を正しく理解し、その性質を知ることは、ご自身や大切な人の命を守り、納得のいく治療を選択するための重要な第一歩です。
この記事では、がんとは一体どのような病気なのか、その最も基本的な知識について、専門的な観点から分かりやすく解説します。正しい情報を、これからの戦いに挑む力に変えていきましょう。
がんとは何か
「がん」という言葉を聞くと、多くの人が死に直結する恐ろしい病というイメージを持つかもしれません。しかし、がんの正体は、私たちの体を作る細胞の異常から始まる病気です。
ここでは、がんという病気の本質を理解するために、その定義や種類、そして「良性」との違いについて詳しく見ていきます。基本を学ぶことで、がんに対する漠然とした恐怖が、具体的な知識へと変わるはずです。
がんの定義
私たちの体は約37兆個もの細胞から成り立っています。これらの細胞は、体の各部分で決められた役割を担いながら、秩序正しく分裂、増殖し、やがては古くなって死んでいきます。
この精巧な生命活動をコントロールしているのが、細胞の核の中にある「遺伝子」です。がんは、この遺伝子に何らかの原因で傷がつき、その結果、細胞が異常な性質を持って無秩序に増え続ける状態になったものを指します。
専門的には「悪性新生物」と呼び、私たちの体に発生する「できもの(腫瘍)」の一種です。しかし、すべての腫瘍ががん(悪性)というわけではありません。
悪性新生物と良性新生物
腫瘍には、がんである「悪性新生物」と、がんでない「良性新生物(良性腫瘍)」があります。両者は増殖の仕方に大きな違いがあり、体への影響も全く異なります。
その違いを正しく知ることは、がんという病気を理解する上でとても重要です。一般的に、良性腫瘍は増殖が緩やかで、周りの組織を押しのけるように大きくなりますが、他の場所に広がることはありません。
一方で悪性腫瘍、すなわちがんは、周囲の組織に染み込むように広がり、体のあちこちに飛び火する性質を持ちます。
良性腫瘍と悪性腫瘍(がん)の比較
| 特徴 | 良性新生物(良性腫瘍) | 悪性新生物(がん) |
|---|---|---|
| 増殖の速さ | 比較的ゆっくり | 一般的に速い |
| 周囲への影響 | 組織を圧迫するが、破壊はしない | 組織を破壊しながら広がる(浸潤) |
| 他の臓器への広がり | ない(転移しない) | ある(転移する) |
がんの種類
がんは、発生した体の部位や、がん細胞が由来する組織の種類によって分類します。
この分類は、がんの性質や治療方針を決定する上で非常に重要です。大きく分けると、「癌腫」「肉腫」「造血器腫瘍」の3つに分類できます。
組織の由来によるがんの分類
体の表面や内臓の表面を覆う「上皮細胞」から発生するがんを「癌腫」と呼びます。肺がん、胃がん、乳がん、大腸がんなど、私たちがよく耳にするがんの多くがこの癌腫に含まれます。
一方で、骨、筋肉、脂肪、血管といった、体を支える組織(非上皮性細胞)から発生するがんを「肉腫」と呼びます。発生頻度は癌腫に比べて低いのが特徴です。
そして、血液やリンパ組織から発生するのが「造血器腫瘍」で、白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などがこれにあたります。
代表的ながんの分類例
| 分類 | 由来する細胞 | 代表的ながん |
|---|---|---|
| 癌腫 (Carcinoma) | 上皮細胞(臓器の表面や内側を覆う細胞) | 胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、肝臓がん |
| 肉腫 (Sarcoma) | 非上皮性細胞(骨、軟骨、筋肉、脂肪、血管など) | 骨肉腫、軟部肉腫、平滑筋肉腫 |
| 造血器腫瘍 | 血液やリンパ組織の細胞 | 白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 |

正常細胞とがん細胞の違い
私たちの体を健康に維持している正常な細胞と、病気を引き起こすがん細胞。両者はもともと同じ細胞から始まりますが、その性質は全く異なります。
がん細胞は、正常細胞が持つべきいくつかの重要なルールを破ることで、その悪性度を高めていきます。この違いを細胞レベルで理解することで、がん治療が何を目指しているのかをより深く知ることができます。
細胞増殖の制御
正常な細胞は、体からの指令に従って必要なときだけ分裂・増殖し、不必要なときには増殖を停止します。例えば、怪我をしたときに皮膚が再生するのは、この制御機能が正しく働いているからです。
しかし、がん細胞はこの制御を無視します。体からの「増殖停止」のサインを無視し、自分勝手に、そして無限に増え続けるという特徴を持っています。
この無秩序な増殖が、がん組織が塊(腫瘍)を形成し、大きくなっていく原因です。
アポトーシスからの回避
正常な細胞には、古くなったり、遺伝子に異常が生じたりした場合に、自ら死を選ぶようにプログラムされた仕組みがあります。これを「アポトーシス(プログラム細胞死)」と呼びます。
この仕組みは、体に不利益な細胞が増えないようにするための重要な安全装置です。しかし、がん細胞はこのアポトーシスから逃れる能力を獲得しています。
本来であれば死ぬべき異常な細胞が死なずに生き残り、増え続けることで、がんは勢力を拡大していくのです。
細胞の形状と機能
正常な細胞は、それぞれが特定の形と機能を持ち、自分の役割を果たすために成熟していきます。これを「分化」と呼びます。例えば、肝臓の細胞は肝臓の、神経の細胞は神経の役割を専門的に担っています。
しかし、がん細胞は増殖を繰り返すうちに、この分化の能力を失っていきます。正常な細胞とは似ても似つかない形(異型性)になり、本来の細胞としての機能を失った「未熟」な状態になるのです。
これを「未分化」と呼び、一般的に未分化な細胞ほど悪性度が高い傾向があります。
正常細胞とがん細胞の主な性質の違い
| 性質 | 正常細胞 | がん細胞 |
|---|---|---|
| 増殖 | 制御されている(必要な時だけ増殖) | 制御不能(無秩序に増殖) |
| 寿命 | 有限(分裂回数に限界がある) | 不死(無限に増殖できる) |
| 機能 | 分化し、特定の機能を持つ | 未分化で、本来の機能を失う |
寿命の違い
正常な細胞の分裂回数には限界があります。これは染色体の末端にある「テロメア」という構造が、細胞分裂のたびに短くなるためです。
テロメアがある一定の長さまで短くなると、細胞はそれ以上分裂できなくなり、やがて寿命を迎えます。この仕組みが、細胞の無限増殖を防いでいます。
ところが、がん細胞の多くは「テロメラーゼ」という酵素を活性化させることで、短くなったテロメアを修復し、無限に分裂し続ける能力、いわゆる「不死」の性質を獲得しています。
この不死性が、がんが永続的に増え続ける根源となっています。

がんの発生原因
なぜ、がんという病気が発生するのでしょうか。その根本には遺伝子の変異がありますが、その変異を引き起こす原因は一つではありません。
私たちの生活習慣から、ウイルスや細菌への感染、あるいは生まれ持った体質まで、様々な要因が複雑に関与し合って、がんの発生につながります。
ここでは、がんを引き起こす要因について、内的なものと外的なものに分けて解説します。
遺伝子の変異
がんの発生は、すべて細胞の設計図である遺伝子に傷がつくこと、すなわち「変異」から始まります。
一つの細胞ががん細胞に変化するためには、一つの遺伝子変異だけでは不十分で、複数の遺伝子に次々と変異が積み重なることが必要です。
この変異が蓄積するのに、多くの場合、数年から数十年という長い年月がかかります。そのため、がんは高齢になるほど発症しやすくなるのです。
がんの発生に直接関わる遺伝子として、特に重要なのが「がん遺伝子」と「がん抑制遺伝子」です。
がん遺伝子とがん抑制遺伝子
私たちの体には、細胞の増殖を促進するアクセルのような役割を持つ「がん原遺伝子」と、増殖を抑えるブレーキ役の「がん抑制遺伝子」があります。
がん原遺伝子は、変異することで細胞の増殖を異常に活発化させる「がん遺伝子」に変化します。これは、車のアクセルが踏みっぱなしになった状態に例えられます。
一方、がん抑制遺伝子は、変異することでそのブレーキ機能が失われ、細胞増殖を止められなくなります。これは、ブレーキが壊れた車のような状態です。
がんの発生には、このようなアクセルとブレーキの両方の異常が関わっていることが多いのです。
遺伝子の役割と変異による影響
| 遺伝子の種類 | 正常な状態での役割 | 変異が起きた場合の影響 |
|---|---|---|
| がん原遺伝子 | 細胞の増殖を適切にコントロールする(アクセル) | 変異すると「がん遺伝子」となり、細胞増殖を過剰に促進する |
| がん抑制遺伝子 | 細胞の増殖を抑制したり、傷ついたDNAを修復したりする(ブレーキ) | 変異すると機能が失われ、細胞増驚の抑制が効かなくなる |
がんの発生要因
遺伝子に変異を引き起こす要因は、大きく「内的要因」と「外的要因」に分けられます。
内的要因は、年齢のように避けることが難しいものですが、外的要因の多くは生活習慣の見直しによってリスクを下げることが可能です。
内的要因
最も大きな内的要因は「加齢」です。年齢を重ねるにつれて、細胞分裂の際のコピーミスや、様々な外的要因にさらされる機会が増え、遺伝子の変異が蓄積しやすくなります。
また、親から受け継いだ特定の遺伝子変異により、特定のがんになりやすい体質(遺伝性腫瘍)も内的要因に含まれます。ただし、遺伝性のがんはがん全体の5%程度であり、ほとんどのがんは遺伝と直接関係なく発生します。
外的要因
外的要因は、私たちの生活環境や習慣に起因するもので、がん発生の要因の多くを占めます。これらのリスクを理解し、避ける努力をすることが、がんの予防につながります。
主な外的リスク要因
- 喫煙
- 過度な飲酒
- 偏った食生活(塩分の過剰摂取、野菜・果物不足など)
- 運動不足と肥満
- ウイルスや細菌への感染(ヒトパピローマウイルス、ピロリ菌など)
がんの種類と関連する主なリスク要因
| がんの種類 | 主なリスク要因(外的要因) |
|---|---|
| 肺がん | 喫煙(受動喫煙含む)、アスベスト |
| 胃がん | ピロリ菌感染、塩分の多い食事、喫煙 |
| 大腸がん | 加工肉・赤肉の摂取、肥満、飲酒、喫煙 |
| 肝臓がん | B型・C型肝炎ウイルス感染、飲酒、肥満 |
| 子宮頸がん | ヒトパピローマウイルス(HPV)感染 |

転移と浸潤
がんが恐れられる最大の理由は、その場にとどまらず、体のあちこちに広がっていく性質を持つからです。この「広がり」には、「浸潤(しんじゅん)」と「転移(てんい)」という2つの重要な様式があります。
これらは、がんが進行し、治療を困難にする主な原因です。この二つの現象の違いと、その経路を理解することは、がんの進行度を把握し、治療方針を考える上で欠かせません。
浸潤とは
浸潤とは、がん細胞が周囲の正常な組織の中に、まるで水が染み込むようにじわじわと広がっていく現象です。がん細胞は、増殖する過程で周囲の組織を破壊しながら、その領域を拡大していきます。
正常な細胞との境界が不明瞭になるため、手術でがんを取り除く際には、目に見えるがんの塊だけでなく、浸潤している可能性のある周辺の正常な組織も一緒に切除することが重要になります。
この浸潤の広がり具合は、がんの進行度を判断する上での重要な指標の一つです。
転移とは
転移とは、最初に発生した場所(原発巣)からがん細胞が剥がれ落ち、血液やリンパの流れに乗って体の別の場所に移動し、そこで再び増殖を始める現象です。
この移動先で新たながんの塊を作ったものを「転移巣」と呼びます。例えば、肺にできたがんが脳に転移した場合、脳にできたがんも元の肺がんと同じ性質を持つため、「肺がんの脳転移」と診断します。
転移はがんが全身に広がった状態を示すため、治療は手術などの局所的な治療だけでなく、抗がん剤などの全身に効果が及ぶ治療法が中心となります。
浸潤と転移の違い
| 項目 | 浸潤 | 転移 |
|---|---|---|
| 広がり方 | 連続的に周囲の組織へ染み込むように広がる | 非連続的に、離れた臓器へ飛び火するように広がる |
| 移動手段 | 直接的な増殖 | 血管やリンパ管などを介して移動する |
転移の経路
がん細胞が体を旅するための主なルートは、「血行性転移」「リンパ行性転移」「播種」の3つです。
血行性転移
がん細胞が、浸潤の過程で近くにある毛細血管に入り込み、血液の流れに乗って全身に運ばれる経路です。血液は体の隅々まで巡っているため、血行性転移は脳、肺、肝臓、骨など、様々な臓器に起こる可能性があります。
原発巣から離れた場所に転移巣(遠隔転移)を作る主な経路です。
リンパ行性転移
がん細胞がリンパ管に入り込み、リンパ液の流れに乗って運ばれる経路です。リンパ液は、最終的に血管に合流しますが、その途中で関所のような役割を果たす「リンパ節」を通過します。がん細胞はまず、原発巣に最も近いリンパ節にたどり着き、そこで増殖します(リンパ節転移)。そこからさらに、次のリンパ節へと順々に広がっていく傾向があります。
播種(はしゅ)
胃がんや大腸がんなどが進行して臓器の壁を突き破ると、がん細胞がお腹の中(腹腔)に種をまくように散らばることがあります。これを「腹膜播種」と呼びます。
同様に、肺がんなどが胸の中(胸腔)に広がると「胸膜播種」となります。播種は、広範囲にがんが散らばるため、治療が難しいとされています。
転移の主な3つの経路
| 経路の名称 | 移動の媒体 | 主な転移先 |
|---|---|---|
| 血行性転移 | 血液 | 肺、肝臓、脳、骨など全身の臓器 |
| リンパ行性転移 | リンパ液 | リンパ節 |
| 播種 | 体腔(腹腔、胸腔など)内の液体 | 腹膜、胸膜など |

よくある質問
がんについて学ぶ中で、様々な疑問が浮かんでくることでしょう。ここでは、患者さんやご家族から特によく寄せられる質問に対して、Q&A形式でお答えします。
正しい知識を持つことで、不確かな情報に惑わされることなく、前向きに病気と向き合う一助となることを願っています。
- がんは遺伝しますか?
-
すべてのがんが遺伝するわけではありません。がんの多くは、生活習慣などの環境要因と加齢が主な原因で、遺伝とは直接関係のない「散発性のがん」です。
しかし、がん全体の約5%は、特定の遺伝子の変異が親から子へ受け継がれることで、がんになりやすい体質が遺伝する「遺伝性腫瘍」であると考えられています。
血縁者の中に若くしてがんになった方や、特定のがん(乳がん、卵巣がん、大腸がんなど)になった方が複数いる場合は、遺伝カウンセリングについて主治医に相談することも一つの選択肢です。
- ストレスはがんの原因になりますか?
-
現時点では、ストレスが直接的にがんを引き起こすという明確な科学的根拠はありません。
しかし、過度なストレスは、免疫機能の低下を招いたり、喫煙や過度の飲酒、不健康な食生活といった、がんのリスクを高める行動につながったりすることがあります。
ストレスを上手に管理し、心身ともに健康的な生活を送ることは、がん予防の観点からも重要と言えるでしょう。
- がんは誰でもなる可能性がありますか?
-
はい、その通りです。がんは特別な病気ではなく、誰でも生涯のうちにかかる可能性のある病気です。現在の日本では、生涯のうちに2人に1人が何らかのがんにかかると統計上推計されています。
特に、がんは加齢とともにリスクが高まるため、高齢化社会の進展に伴い、がん患者さんの数は増加傾向にあります。
だからこそ、すべての人にとって、がんの正しい知識を持ち、予防や早期発見に努めることが大切なのです。
- 早期発見にはどのような検査がありますか?
-
がんを早期に発見するためには、定期的に「がん検診」を受けることが非常に有効です。
国が推奨する5大がん(胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がん)には、それぞれ科学的に効果が証明された検診方法があります。
例えば、胃がんならバリウム検査や内視鏡検査、大腸がんなら便潜血検査などです。これらの検診で「要精密検査」と判定された場合は、必ず専門の医療機関でより詳しい検査を受けてください。
また、体に何らかの異変を感じた際には、検診の時期を待たずに速やかに医療機関を受診することも、早期発見につながる重要な行動です。
以上
この記事では、がんの基本的な知識について幅広く解説しました。
がんの本質をさらに深く理解するためには、私たちの体を構成する「正常細胞」と、病気を引き起こす「がん細胞」の決定的な違いを知ることが重要です。
なぜがん細胞は無限に増え続け、正常な機能を失ってしまうのか。その根本的な性質の違いを学ぶことで、がん治療がどのような目的で行われるのか、その戦略が見えてきます。
次の記事で、細胞レベルの世界をのぞき、がんという病気の核心に迫ってみましょう。

参考文献
PERLIKOS, Fotis; HARRINGTON, Kevin J.; SYRIGOS, Konstantinos N. Key molecular mechanisms in lung cancer invasion and metastasis: a comprehensive review. Critical reviews in oncology/hematology, 2013, 87.1: 1-11.
MALKI, Ahmed, et al. Molecular mechanisms of colon cancer progression and metastasis: recent insights and advancements. International journal of molecular sciences, 2020, 22.1: 130.
HASSANPOUR, Seyed Hossein; DEHGHANI, Mohammadamin. Review of cancer from perspective of molecular. Journal of cancer research and practice, 2017, 4.4: 127-129.
MAREEL, Marc; LEROY, Ancy. Clinical, cellular, and molecular aspects of cancer invasion. Physiological reviews, 2003, 83.2: 337-376.
TESTA, Ugo; CASTELLI, Germana; PELOSI, Elvira. Cellular and molecular mechanisms underlying prostate cancer development: therapeutic implications. Medicines, 2019, 6.3: 82.
BERTRAM, John S. The molecular biology of cancer. Molecular aspects of medicine, 2000, 21.6: 167-223.
MAEKAWA, Shigekatsu; TAKATA, Ryo; OBARA, Wataru. Molecular mechanisms of prostate cancer development in the precision medicine era: a comprehensive review. Cancers, 2024, 16.3: 523.
AZMI, Asfar S.; BAO, Bin; SARKAR, Fazlul H. Exosomes in cancer development, metastasis, and drug resistance: a comprehensive review. Cancer and Metastasis Reviews, 2013, 32: 623-642.
BOGENRIEDER, Thomas; HERLYN, Meenhard. Axis of evil: molecular mechanisms of cancer metastasis. Oncogene, 2003, 22.42: 6524-6536.
IMRAN, Aman, et al. Role of molecular biology in cancer treatment: a review article. Iranian journal of public health, 2017, 46.11: 1475.