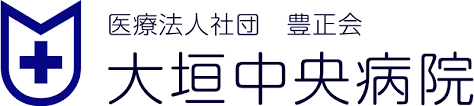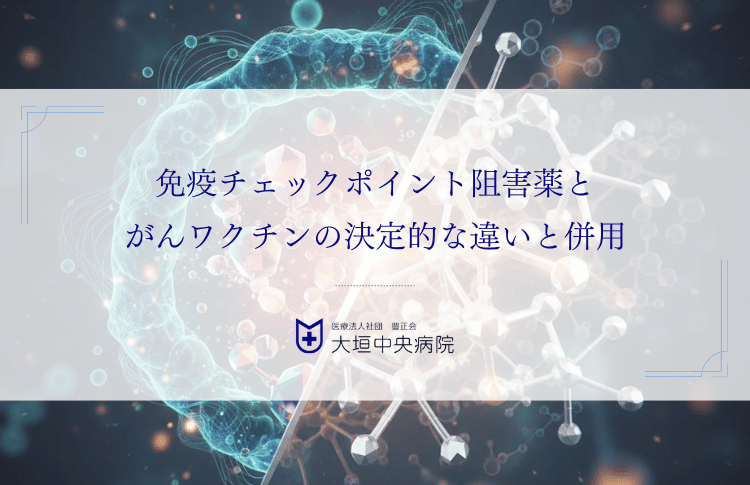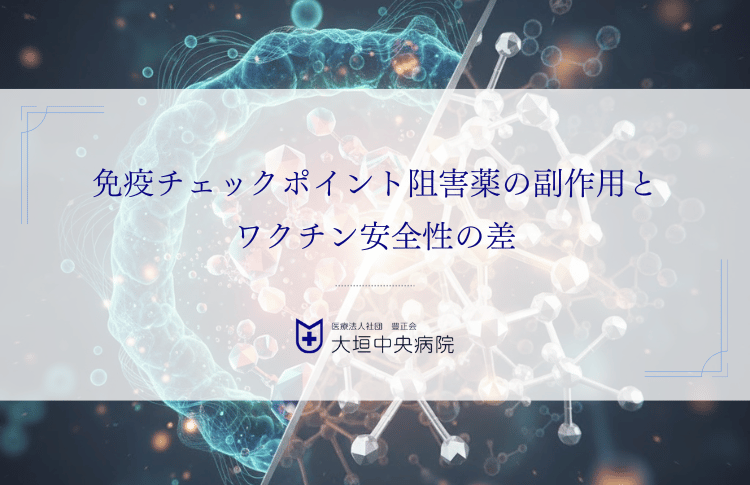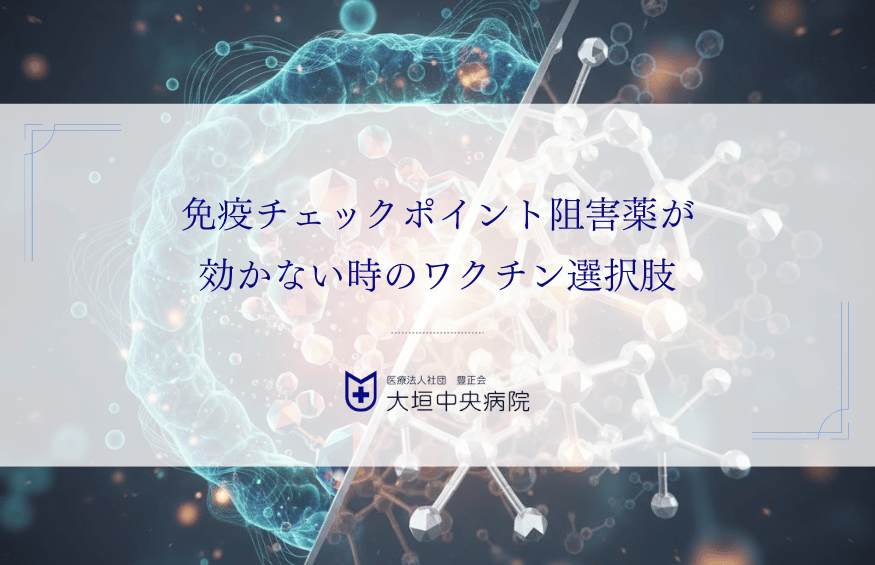がん治療の常識が今、大きな転換点を迎えています。従来の「手術」「抗がん剤」「放射線」に加え、第4の柱として確立された免疫療法。
その中でも特に注目を集めるのが、ノーベル賞を受賞した「免疫チェックポイント阻害薬」と、患者ごとのがん抗原を標的とする「がんワクチン」です。
これらは同じ免疫療法でありながら、その作用点は「ブレーキを外す」か「アクセルを踏む」かという正反対の性質を持ちます。
本記事では、これら二つの決定的な違いを生物学的な視点から紐解き、なぜ今、両者の併用療法が進行がん治療の突破口として期待を集めているのか、その科学的根拠と臨床的な意義を徹底解説します。
単独では超えられなかった治療の壁を、二つの力の融合がどのように乗り越えようとしているのか、その全貌に迫ります。
免疫チェックポイント阻害薬とがんワクチンの決定的な違い
免疫チェックポイント阻害薬はがん細胞による免疫逃避(ブレーキ)を解除することで既存の免疫細胞を再活性化させるのに対し、がんワクチンは特定の抗原を目印として新たな攻撃部隊を育成・動員する(アクセル)という点で、根本的なアプローチが異なります。
攻撃対象を特定するか否かのアプローチ
免疫チェックポイント阻害薬(ICI)とがんワクチンを比較した際、最も本質的な違いは「何を目印に攻撃するか」という点にあります。
オプジーボやキイトルーダに代表される免疫チェックポイント阻害薬は、特定の「がん抗原」を標的にするわけではありません。
これらは、がん細胞が免疫細胞(T細胞)にかけている「ブレーキ」そのものを標的とします。具体的には、PD-1やPD-L1といった分子の結合を阻害することで、T細胞が本来持っている攻撃力を回復させます。
つまり、攻撃対象がどのがん細胞であるかに関わらず、免疫システム全体の抑制を解くことで、結果的にがんへの攻撃を誘発するという広範囲な戦略をとります。
一方で、がんワクチンは極めて特異的なアプローチを採用します。
がんワクチンは、がん細胞特有の目印である「がん抗原(ネオアンチゲンなど)」を体内に投与し、免疫の司令塔である樹状細胞に「これが敵である」と明確に教育します。
教育された樹状細胞は、その情報を細胞傷害性T細胞(キラーT細胞)に伝え、特定の目印を持つがん細胞だけを狙い撃ちするように指令を出します。
このため、がんワクチンは「指名手配書」を配るようなものであり、狙った相手をピンポイントで排除するための高度な選択性を持っています。
アプローチと作用点の比較
| 比較項目 | 免疫チェックポイント阻害薬 | がんワクチン |
|---|---|---|
| 基本的な役割 | 免疫のブレーキ解除(抑制の排除) | 免疫のアクセル(攻撃部隊の育成) |
| 標的とするもの | 免疫細胞またはがん細胞上の受容体(PD-1など) | がん細胞特有のタンパク質(がん抗原) |
| 攻撃の特異性 | 非特異的(全身の免疫活性化) | 特異的(特定のがん細胞のみ攻撃) |
免疫細胞への作用機序と活性化のタイミング
作用するタイミングと場所も大きく異なります。免疫チェックポイント阻害薬が効果を発揮するのは、すでにがん組織の中にT細胞が入り込んでいるものの、がん細胞によって無力化されている段階です。
つまり、「現場には到着しているが、手足を縛られている警察官」の縄を解くのがこの薬の役割です。
したがって、もともとがん組織にT細胞が少ない場合、ブレーキを外しても攻撃する主体がいないため、効果が得られにくいという特性があります。
それに対し、がんワクチンは免疫応答の最初期段階に作用します。
リンパ節などの免疫組織において、まだがん細胞を認識していないナイーブT細胞に対し、がんの情報を教え込み、強力なエフェクターT細胞へと分化・増殖させます。
そして、訓練されたT細胞の大軍を血流に乗せてがん組織へと送り込みます。いわば「新たな特殊部隊を基地で育成し、現場へ派遣する」役割を担います。
この違いゆえに、がんワクチンは免疫細胞が不足している状況でも、新たに攻撃部隊を作り出す力を持っています。
持続的な免疫記憶の形成における相違点
治療効果の持続性、すなわち「免疫記憶」の形成においても両者には違いが見られます。
免疫チェックポイント阻害薬は、投与されている間、およびその効果が残存している期間において免疫抑制を解除し続けます。
一部の患者では長期的な寛解が得られますが、これは体内の既存のT細胞が疲弊せずに戦い続けられた結果です。
がんワクチンは、その設計思想そのものが「記憶の形成」に重点を置いています。ワクチンによって誘導されたT細胞の一部は「メモリーT細胞」として体内に長期間留まります。
その結果、もしがん細胞が一度消滅した後に再発したり、転移したりした場合でも、メモリーT細胞が即座に反応し、迅速に攻撃を再開することが可能です。
感染症のワクチンと同様に、がんに対する長期的な監視システムを体内に構築するという点で、がんワクチンは予防的な側面も併せ持っています。
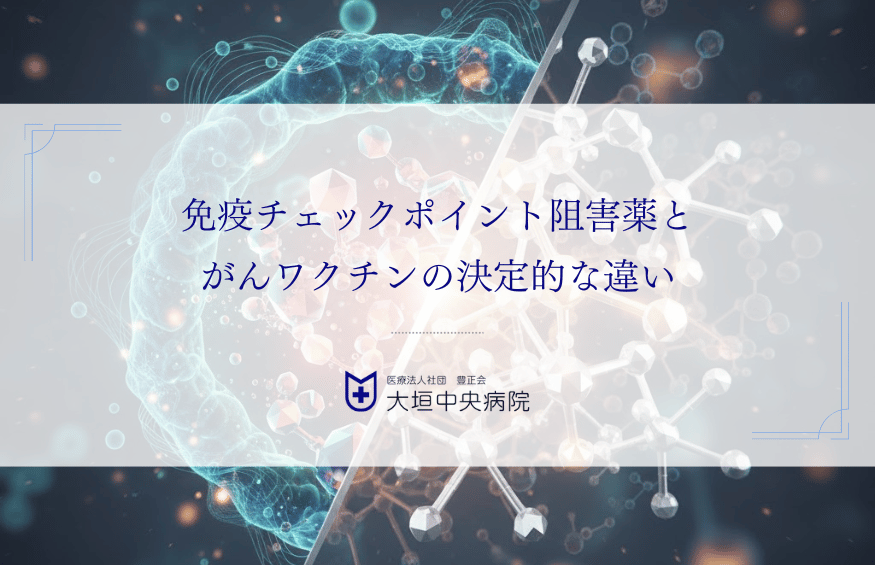
オプジーボなどの阻害薬とがんワクチンを使い分ける判断基準
治療方針の決定には、がんの組織型だけでなく、「免疫環境が燃えているか(Hot)冷めているか(Cold)」という腫瘍の微小環境の状態と、PD-L1発現率などのバイオマーカー分析が重要な判断材料となります。
がん細胞表面のPD-L1発現率による適合性
オプジーボやキイトルーダなどの免疫チェックポイント阻害薬を使用する際、最も基本的な指標となるのが、がん細胞表面における「PD-L1」というタンパク質の発現率です。
PD-L1は、T細胞のPD-1と結合してブレーキをかけるための「スイッチ」のような存在です。
病理検査を行い、がん細胞の多くがPD-L1を出している場合(陽性率が高い場合)、それは「免疫細胞が攻撃に来ているが、がん細胞がPD-L1を使って必死に防御している」状態を意味します。
この場合、阻害薬を使ってその結合をブロックすれば、劇的な効果が期待できます。
逆に、PD-L1の発現率が低い、あるいは陰性の場合、阻害薬単独では効果が薄い可能性があります。ここでがんワクチンの出番となります。
PD-L1が低いということは、そもそも免疫細胞による攻撃圧力が弱く、がん細胞が防御策を講じる必要を感じていない可能性があります。
このようなケースでは、まずワクチンを使って免疫細胞を強制的に動員し、攻撃を開始させることが優先されます。
腫瘍遺伝子変異量(TMB)と治療反応性の関係
次に重要な指標が「腫瘍遺伝子変異量(TMB:Tumor Mutational Burden)」です。これは、がん細胞の遺伝子にどれだけ多くの傷(変異)が入っているかを示す数値です。
変異が多いがん細胞は、正常な細胞とは異なる異常なタンパク質(ネオアンチゲン)を多く作り出します。
これらは免疫細胞にとって「異物」として認識しやすいため、TMBが高い(TMB-High)がんは、本来免疫原性が高く、免疫チェックポイント阻害薬が効きやすい傾向にあります。
一方で、遺伝子変異が少ない(TMB-Low)がんは、正常細胞との見分けがつきにくく、免疫細胞に見過ごされがちです。
この場合、免疫系ががんを敵と認識できていないため、阻害薬でブレーキを外しても攻撃が始まりません。
こうした患者に対しては、がんワクチンを用いて特定の微細な変異や抗原を標的として提示し、免疫系に「これが敵だ」と教育する必要があります。
つまり、TMBの高低は、阻害薬単独でいくか、ワクチンを主軸あるいは併用するかを決める大きな分かれ道となります。
患者固有のHLA型と抗原提示の重要性
がんワクチンの利用を検討する上で避けて通れないのが、患者の白血球の型である「HLA(ヒト白血球抗原)」です。
がんワクチンに含まれる抗原ペプチドは、このHLAという「お皿」に乗って提示されることで初めて免疫細胞に認識されます。
HLAの型は人によって異なり、特定のHLA型にしか適合しないワクチンも数多く存在します。
免疫チェックポイント阻害薬はHLA型に関わらず使用できますが、ワクチンは「鍵と鍵穴」の関係のように、患者のHLA型とワクチンのタイプが合致しなければ効果を発揮しません。
したがって、HLA検査を行い、適合するペプチドや抗原が存在するかを確認することは、ワクチンを選択する際の絶対条件です。
また、がん細胞側がこのHLA分子を隠してしまう(消失させる)ことで免疫から逃れるケースもあり、その場合はワクチンの効果が減弱するため、別の戦略を練る必要があります。
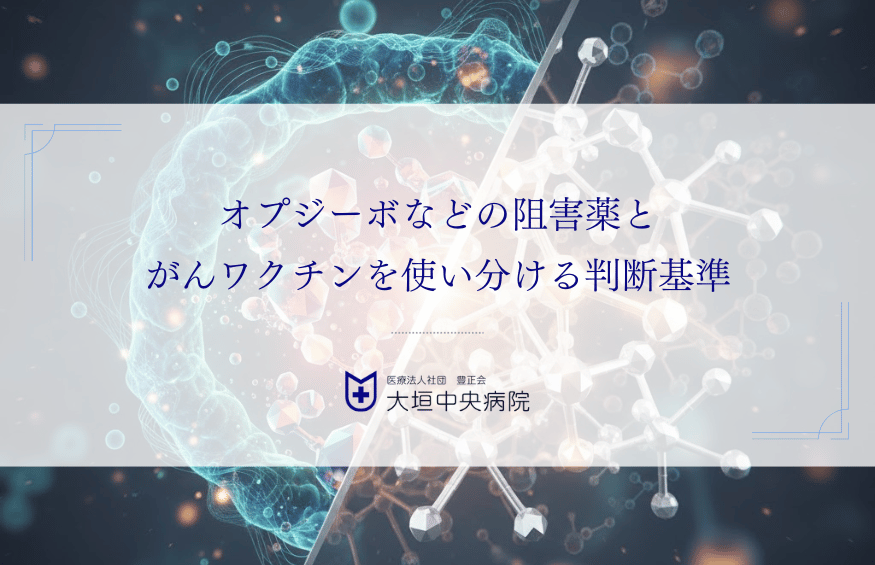
免疫チェックポイント阻害薬が効かない時のワクチン選択肢
免疫チェックポイント阻害薬が無効となる主な原因は腫瘍内への免疫細胞の浸潤不足であり、がんワクチンはこの「Cold Tumor」を「Hot Tumor」へと転換させる呼び水としての役割を果たします。
免疫細胞が浸潤していないコールド腫瘍への対策
がん組織は、免疫細胞の浸潤度合いによって「Hot Tumor(熱い腫瘍)」と「Cold Tumor(冷たい腫瘍)」に分類されます。免疫チェックポイント阻害薬が劇的に効くのは、主にHot Tumorです。
ここには既に多くのT細胞が集まっており、ブレーキさえ外せば戦える状態にあるからです。
しかし、多くのがん患者、特に膵臓がんや大腸がんの一部などは、T細胞ががん組織の中にほとんど入り込んでいないCold Tumorの状態にあります。
この状態では、いくら高価な阻害薬を使っても、攻撃する兵隊がいないため効果は限定的です。
ここでがんワクチンが重要な選択肢となります。ワクチンを投与すると、体内のリンパ節で強力に誘導されたT細胞が血流に乗ってがん組織へ移動します。
このT細胞の流入によって、がん組織内で炎症反応が引き起こされ、Coldな環境がHotな環境へと変わるきっかけが生まれます。
つまり、ワクチンは阻害薬が効くための下地を作る「プライミング(呼び水)」としての機能を果たし、これまで治療法がなかった症例に希望をもたらします。
阻害薬の効果を妨げる主な要因
- 腫瘍内へのリンパ球浸潤が著しく少ない(Cold Tumor)
- がん細胞がPD-L1を発現しておらず標的にならない
- T細胞が疲弊しきっており再活性化できない
- がん細胞が抗原提示分子(HLA)を隠している
獲得耐性が生じた後の次なる治療戦略
当初は免疫チェックポイント阻害薬が効いていたにもかかわらず、途中から効かなくなってしまう「獲得耐性」も大きな課題です。
これは、がん細胞が生き残るために進化し、新たな変異を起こして抗原の形を変えたり、別の免疫抑制ルートを使ったりすることで発生します。一度耐性がついてしまうと、同じ薬を使い続けても効果は望めません。
この局面において、がんワクチンを用いたアプローチは、免疫系に「新しい敵の特徴」を再教育する手段となります。
特に、患者のがん組織を採取し、その時点での遺伝子変異に合わせたオーダーメイドのがんワクチン(ネオアンチゲンワクチン)を作成すれば、変異して逃げようとするがん細胞を再び捕捉することが可能です。
耐性ができたからといって諦めるのではなく、変化した敵に合わせて武器(T細胞の認識能力)をアップデートするという戦略が、ワクチンによって可能になります。
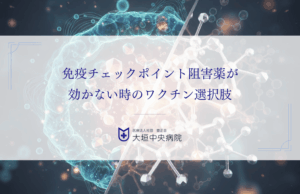
免疫療法のアクセルとブレーキの役割を知り併用効果を狙う
アクセル(ワクチン)とブレーキ解除(阻害薬)を同時に行う併用療法は、単剤治療の限界を補完し合い、特異的な攻撃力の最大化と免疫抑制環境の克服を同時に実現します。
ブレーキ解除とアクセル全開の相乗効果
自動車の運転を想像すると分かりやすいでしょう。サイドブレーキを引いたままアクセルを踏んでも車は進みません(ワクチンの単独効果の限界)。
逆に、坂道でブレーキを外すだけでは、エンジンがかかっていなければ車は勢いよく動きません(阻害薬の単独効果の限界)。
併用療法は、「がんワクチンというアクセルでエンジンを全開にし、同時に免疫チェックポイント阻害薬でブレーキを完全に解除する」という戦略です。
この組み合わせにより、ワクチンによって誘導された数多くの特異的T細胞が、阻害薬の助けを借りてがん細胞による妨害を受けることなく、スムーズに攻撃を実行できるようになります。
臨床試験においても、それぞれの単独療法では反応しなかった患者群に対し、併用することで奏効率が向上するデータが蓄積されつつあります。
併用療法における役割分担
| 治療法 | 役割(比喩) | 具体的な作用 |
|---|---|---|
| がんワクチン | アクセルを踏む | 攻撃部隊(T細胞)の数を増やし、がんへの誘導を行う |
| チェックポイント阻害薬 | ブレーキを外す | T細胞の疲弊を防ぎ、攻撃能力を維持・回復させる |
| 併用療法 | スポーツ走行 | 多数の精鋭部隊が、妨害を受けずにフルパワーで攻撃する |
特異的T細胞の誘導による攻撃力の最大化
併用療法の真価は、攻撃の「質」と「量」の両立にあります。免疫チェックポイント阻害薬単独では、体内に元々あるT細胞しか活用できません。
その中には、がんとは関係のないT細胞も多く含まれており、効率的とは言えない側面があります。
しかし、がんワクチンを併用することで、がん細胞だけを狙う「特異的T細胞」の比率を爆発的に高めることができます。
こうして増やされた精鋭部隊は、阻害薬の効果によってPD-1/PD-L1経路による無力化を免れます。
その結果として、質の高いT細胞が大量に、かつ活性化された状態でがん組織に到達するため、腫瘍を縮小させる力が最大化されます。
これは、単に薬を二つ混ぜるという足し算ではなく、生物学的な理にかなった掛け算の効果を生み出します。
腫瘍微小環境の改善と免疫抑制の克服
がん細胞は、自らを守るために周囲に「免疫抑制細胞(TregやMDSCなど)」を集め、攻撃しにくい環境(腫瘍微小環境)を作り上げています。
この環境下では、T細胞が入ってきてもすぐに元気をなくしてしまいます。併用療法は、この劣悪な環境を改善する力も持っています。
ワクチンによる強力な抗原刺激は、インターフェロンガンマなどの炎症性サイトカインの放出を促します。この作用を通して、腫瘍微小環境が免疫抑制的な状態から、免疫活性化状態へとシフトします。
さらに阻害薬が加わることで、T細胞だけでなく、NK細胞やマクロファージといった他の免疫細胞も活性化し、がんを取り巻く環境全体を「がん排除」の方向へと塗り替えていくのです。

阻害薬とワクチンの併用療法で拓く進行がん治療の可能性
標準治療が奏功しなかった進行がんや再発がんにおいて、併用療法は長期的な生存期間の延長と、微小残存病変の根絶による治癒を目指す新たな選択肢となります。
標準治療抵抗性の固形がんに対するアプローチ
ステージ4の進行がんや、抗がん剤治療後に増大した固形がんにおいては、残された治療手段が限られています。
こうした「標準治療抵抗性」のがんに対し、免疫チェックポイント阻害薬とがんワクチンの併用は、新たな希望の光となりつつあります。
特に、これまで免疫療法が効きにくいとされてきたタイプのがん種においても、併用によって腫瘍の縮小が確認される事例が出てきました。
重要なのは、この併用療法が全身治療であるという点です。手術や放射線が局所的な治療であるのに対し、活性化された免疫細胞は血流に乗って全身を巡ります。
そのため、画像診断では見つけられないような微細な転移巣に対しても攻撃が及びます。
進行がんにおいては、目に見える大きな腫瘍を叩くだけでなく、全身に散らばったがん細胞をいかに抑え込むかが生命予後を左右するため、この全身的な作用は極めて大きな意味を持ちます。
術後補助療法としての再発予防効果への期待
進行がんの治療だけでなく、手術後の再発予防(術後補助療法)としての可能性も注目されています。
手術で肉眼的にがんを取り切ったとしても、微小ながん細胞が体内に残存している可能性はゼロではありません。これらが時間をかけて増殖し、再発を引き起こします。
術後の体内は、がん細胞の総量が減っており、免疫システムが優位に立ちやすい状況です。
このタイミングでワクチンと阻害薬を併用し、徹底的な掃討作戦を行うことで、微小残存病変(MRD)を根絶できる可能性が高まります。
現在、メラノーマや肺がんなどを対象に、術後の併用療法が再発率をどれだけ下げるかを検証する臨床試験が世界中で進行しており、「がんを治し切る」ための最後の一手として期待されています。

免疫チェックポイント阻害薬の副作用とワクチン安全性の差
免疫チェックポイント阻害薬は全身の免疫過剰による自己免疫疾患様の副作用リスクがありますが、がんワクチンは局所反応が主であり、併用時はそれぞれの副作用特性を理解した管理が必要です。
全身性の自己免疫反応と局所的な炎症反応
両者の副作用は、その作用機序の違いを反映して大きく異なります。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫のブレーキを全身で外してしまうため、正常な細胞まで攻撃してしまうリスクがあります。
これが「免疫関連有害事象(irAE)」です。皮膚の発疹、下痢(大腸炎)、甲状腺機能障害、間質性肺炎など、全身のあらゆる臓器で炎症が起きる可能性があります。
対照的に、がんワクチンは特定の標的だけを攻撃させるため、副作用は限定的です。最も多いのは、注射した部位の赤み、腫れ、痛みといった局所反応です。
また、免疫が活性化する過程で一時的な発熱や倦怠感が見られることもありますが、これらはインフルエンザワクチンなどと同様の反応であり、多くの場合数日で軽快します。
がんワクチン単独で、生命に関わるような重篤な副作用が起きる頻度は、阻害薬や抗がん剤に比べて極めて低いと言えます。
主な副作用の比較
| カテゴリー | 免疫チェックポイント阻害薬 | がんワクチン |
|---|---|---|
| 主な症状 | 間質性肺炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害など | 注射部位の疼痛・発赤、発熱、倦怠感 |
| 発生の範囲 | 全身の臓器に及ぶ可能性あり | 主に局所的、または一過性の全身反応 |
| 管理の難易度 | 専門医による早期発見とステロイド等の治療が必要 | 解熱鎮痛剤などで比較的容易にコントロール可能 |
重篤な免疫関連有害事象(irAE)のリスク管理
併用療法を行う場合、特に注意すべきは免疫チェックポイント阻害薬由来のirAEです。
ワクチンによって免疫系が強く刺激されている状態でブレーキを外すため、理論上は免疫反応がより激しくなり、副作用の頻度や程度が増す可能性も懸念されます。
しかし、現在の多くの臨床データでは、併用によって副作用が管理不能なほど激増するという証拠は示されておらず、適切なモニタリング下であれば安全に実施可能とされています。
重要なのは、患者自身が「いつもと違う」と感じた些細な変化を医師に伝えることです。息切れ、長引く下痢、強い疲労感などはirAEの初期症状である可能性があります。
併用療法を受ける際は、がんワクチンの安全性の高さに油断することなく、阻害薬による全身反応のリスクを常に頭に入れ、医療チームと緊密に連携して体調管理を行うことが大切です。

複合免疫療法としての阻害薬とワクチンにかかる費用総額
併用療法は高額な薬剤費と個別製造コストが重なるため、総額は数百万単位となることが多く、保険診療と自由診療の組み合わせや資金計画の立案が重要です。
薬剤費と製造コストが積み重なる経済的負担
免疫チェックポイント阻害薬とがんワクチンの併用は、経済的な負担が大きくなる傾向にあります。まず、オプジーボやキイトルーダなどの阻害薬は、薬価自体が高額です。
保険適用内であれば高額療養費制度を利用して月々の支払いに上限を設けることができますが、適応外のがん種に使用する場合は全額自己負担となり、年間で数百万円から一千万円近くかかることも珍しくありません。
ここにがんワクチンの費用が加わります。がんワクチンの多くは、現時点では自由診療(保険適用外)として提供されています。
特に、患者一人ひとりの細胞や遺伝子に合わせて製造する「自家がんワクチン」や「ネオアンチゲンワクチン」は、大量生産ができず、個別製造のコストがかさみます。
これらが合算されるため、治療を開始する前に総額の見積もりを取り、経済的な実現可能性を慎重に検討する必要があります。
コストを構成する主な要因
- 免疫チェックポイント阻害薬の薬剤費(数週間に一度の投与が必要)
- がんワクチンの製造費(細胞培養や遺伝子解析の技術料を含む)
- 投与ごとの手技料および検査費(免疫反応のモニタリング)
- 副作用対策のための投薬や入院費
自由診療枠での治療計画と資金計画の立て方
現在、日本においてこの併用療法を保険診療のみで完結させることは難しく、多くの場合は「混合診療」の禁止規定との兼ね合いから、全額自由診療となるか、あるいは先進医療制度を利用する形になります。
自由診療のクリニックで治療を受ける場合、価格設定は医療機関によって異なります。
治療計画を立てる際は、単に「1クールいくら」という目先の費用だけでなく、治療が長期化した場合の維持費や、万が一副作用が出た際の処置費用まで含めて考えることが大切です。
医療ローンや民間の医療保険(自由診療対応型のがん保険)を活用できる場合もあるため、病院の相談窓口やファイナンシャルプランナーに相談し、無理のない資金計画を立てた上で治療に臨むことが、治療を継続させるための鍵となります。
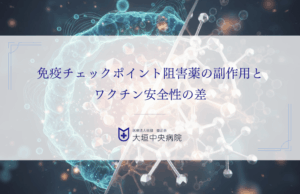
よくある質問
- 併用療法を行えばどんながんでも治るのでしょうか?
-
残念ながら、すべてのがんが完治するわけではありません。免疫療法は効果がある人には劇的に効きますが、全く効果が見られないケースも存在します。
がんの種類、遺伝子のタイプ、免疫の状態によって効果は大きく異なります。
しかし、単独療法では効果がなかった患者さんでも、併用によって腫瘍の縮小や病勢のコントロールが可能になる事例は増えています。
- ワクチンと阻害薬は同時に打つのですか?順番がありますか?
-
治療プロトコル(計画)によりますが、多くの場合、まずワクチンを数回投与して免疫系を「プライミング(予熱)」し、T細胞を増やしてから阻害薬を投与する、あるいは同時期に並行して投与を開始するケースが一般的です。
免疫のサイクルを考慮し、最も効果が出やすいタイミングを医師が判断してスケジュールを組みます。
- 二つの治療を合わせると副作用は2倍になりますか?
-
副作用が単純に2倍になるわけではありません。がんワクチンの副作用は局所的なものが多く、阻害薬の全身的な副作用とは質が異なります。
ただし、免疫機能が強力に活性化されるため、通常よりも慎重な経過観察が必要です。多くの臨床試験において、併用療法の安全性は許容範囲内であると報告されています。
- 高齢でもこの併用療法を受けることはできますか?
-
年齢だけで制限されることはありません。免疫療法は抗がん剤に比べて体力への負担が比較的少ないため、高齢の患者さんでも受けられるケースが多いです。
ただし、基礎疾患(自己免疫疾患や重篤な心疾患など)がある場合はリスクが高まるため、全身状態を詳しく検査した上で医師が判断します。
- mRNAワクチンとペプチドワクチンの違いは何ですか?
-
どちらもがん抗原を免疫に教えるためのツールですが、伝達手段が異なります。ペプチドワクチンは抗原の断片(タンパク質)そのものを投与します。
一方、mRNAワクチンは抗原の設計図(遺伝情報)を投与し、体内の細胞に抗原を作らせて提示させます。
mRNAワクチンの方が、より強力かつ多様な免疫反応を引き出せる可能性があり、現在急速に開発が進んでいます。

参考文献
ZANOTTA, Serena, et al. Enhancing dendritic cell cancer vaccination: the synergy of immune checkpoint inhibitors in combined therapies. International Journal of Molecular Sciences, 2024, 25.14: 7509.
ZANOTTA, Serena, et al. Enhancing dendritic cell cancer vaccination: the synergy of immune checkpoint inhibitors in combined therapies. International Journal of Molecular Sciences, 2024, 25.14: 7509.
CHYUAN, I.-Tsu; CHU, Ching-Liang; HSU, Ping-Ning. Targeting the tumor microenvironment for improving therapeutic effectiveness in cancer immunotherapy: focusing on immune checkpoint inhibitors and combination therapies. Cancers, 2021, 13.6: 1188.
BUTTERFIELD, Lisa H.; NAJJAR, Yana G. Immunotherapy combination approaches: mechanisms, biomarkers and clinical observations. Nature Reviews Immunology, 2024, 24.6: 399-416.
NEW, Jacob, et al. Immune checkpoint inhibitors and vaccination: assessing safety, efficacy, and synergistic potential. Vaccines, 2024, 12.11: 1270.
ZHAO, Jing, et al. Safety and efficacy of therapeutic cancer vaccines alone or in combination with immune checkpoint inhibitors in cancer treatment. Frontiers in pharmacology, 2019, 10: 1184.
VARAYATHU, Hrishi, et al. Combination strategies to augment immune check point inhibitors efficacy-implications for translational research. Frontiers in oncology, 2021, 11: 559161.
PALMER, Adam C., et al. Predictable clinical benefits without evidence of synergy in trials of combination therapies with immune-checkpoint inhibitors. Clinical Cancer Research, 2022, 28.2: 368-377.
KLEPONIS, Jennifer; SKELTON, Richard; ZHENG, Lei. Fueling the engine and releasing the break: combinational therapy of cancer vaccines and immune checkpoint inhibitors. Cancer biology & medicine, 2015, 12.3: 201-208.
HE, Mengying, et al. Immune checkpoint inhibitor‐based strategies for synergistic cancer therapy. Advanced Healthcare Materials, 2021, 10.9: 2002104.