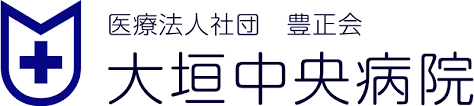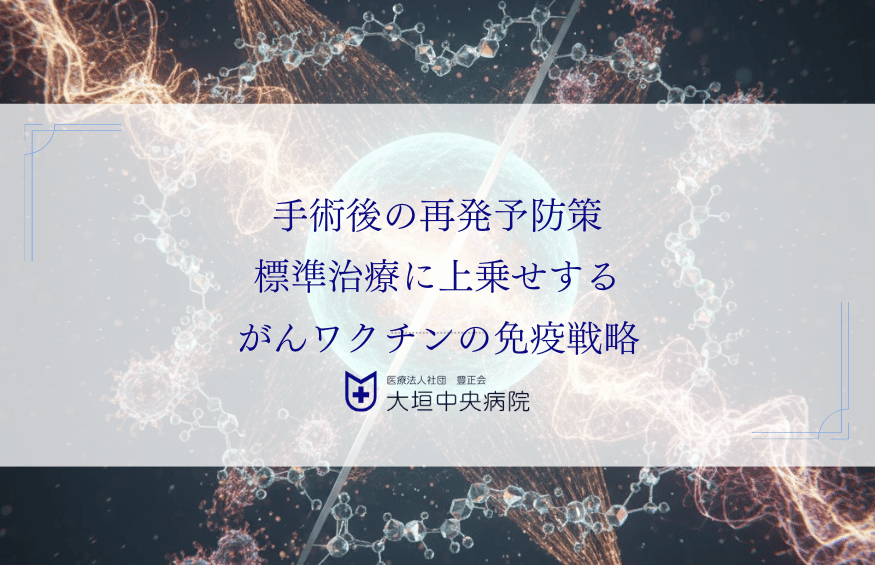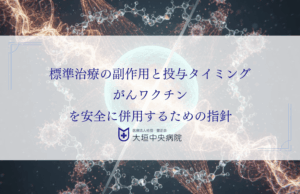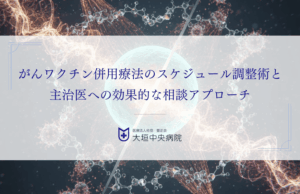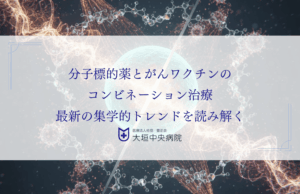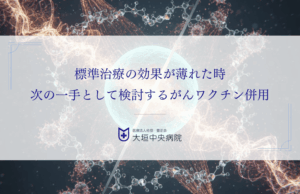手術を無事に終えた安堵の一方で、多くの患者様が抱える「再発への不安」。
目に見えるがんは取り除けましたが、画像検査では捉えきれない微細ながん細胞が体内に潜んでいる可能性は否定できません。
標準治療に免疫の力を上乗せする「がんワクチン」は、この見えない敵に対する追加の防衛策として機能します。
ご自身の免疫細胞を教育し、再発リスクを抑え込むための攻めの戦略について、その根拠と具体的な活用法を詳しく解説します。
手術だけでは届かない微小がん細胞への対策
手術は目に見える固形のがんを取り除く強力な手段ですが、肉眼や画像検査では確認できないレベルの微細ながん細胞が体内に残存している可能性があり、これらを標的とするために全身的な対策が必要です。
手術の成功は治療の大きな山場を越えたことを意味しますが、それは「目に見える敵」がいなくなった状態に過ぎません。
血液やリンパ液の流れに乗って体のどこかに潜んでいるかもしれない微細ながん細胞、いわゆる「微小転移」に対しては、局所的な治療である手術だけではアプローチが届かない領域が存在します。
そのため、全身をパトロールする免疫の力を利用し、残存する可能性のある細胞を叩く戦略が重要になります。
画像検査の限界と微小転移のリスク
CTやMRI、PET検査などの画像診断技術は日々進歩していますが、それでも発見できるがんの大きさには物理的な限界があります。
一般的に、画像検査で確認できるのは5ミリメートルから1センチメートル程度の大きさになってからです。
しかし、がん細胞の大きさはわずか0.01ミリメートルから0.02ミリメートル程度であり、1センチメートルの塊になるには数億個から10億個ものがん細胞が集まる必要があります。
つまり、「画像上は異常なし」という診断であっても、それは数億個以下のがん細胞の集団が存在しないことを保証するものではありません。
手術で原発巣(元々のがん)を完全に取りきったとしても、手術の時点で既に微細ながん細胞が血管やリンパ管を通って他の臓器に移動している可能性があります。
これが再発や転移の正体です。この「見えないリスク」に対して先手を打つことが、再発予防において極めて重要な考え方となります。
局所治療と全身治療の役割分担
がん治療には、患部を直接狙う「局所治療」と、体全体に作用する「全身治療」の二つのアプローチがあります。
手術や放射線治療は局所治療の代表であり、そこに存在するがん塊を物理的に排除したり焼き切ったりする力は非常に強力です。
一方で、すでに散らばってしまったかもしれない細胞に対しては、全身に行き渡る治療法が必要となります。
抗がん剤治療(化学療法)は全身治療の代表ですが、これに加えて、自身の免疫細胞を活性化させて全身を巡回させるがんワクチン療法も全身治療の一つに位置づけられます。
局所治療で本丸を落とし、全身治療で残党を掃討するという役割分担を理解することで、なぜ手術後の追加治療が必要なのかが明確になります。
標準治療が終わったからといって治療を終了するのではなく、この時期こそが微細な細胞を叩く好機と捉える視点が大切です。
手術とワクチンの役割比較
| 比較項目 | 手術(局所治療) | がんワクチン(全身治療) |
|---|---|---|
| 治療の対象 | 目に見える固形のがん(原発巣や限定的な転移) | 目に見えない微小ながん細胞、全身の転移 |
| 主な目的 | がん細胞の物理的な除去、腫瘍量の劇的な削減 | 残存細胞の排除、免疫記憶による長期的な監視 |
| アプローチ | メスによる切除 | 免疫細胞への教育による特異的な攻撃 |
標準治療の間隙を埋める上乗せ効果
標準治療は多くの臨床試験を経て確立された、現時点で推奨される治療法ですが、すべての微小がんを根絶できるわけではありません。
特に抗がん剤は、活発に分裂する細胞を攻撃する性質を持つため、休眠状態にあるようながん細胞(がん幹細胞など)に対しては効果が及びにくいという側面があります。
ここで免疫療法の出番となります。がんワクチンは、がん細胞特有の目印(抗原)を免疫細胞に覚え込ませることで、抗がん剤とは異なるルートでがん細胞を攻撃します。
標準治療で数を減らした後に、異なる作用機序を持つワクチン治療を「上乗せ」することで、治療の網の目から漏れたがん細胞を捕捉する確率を高めることを目指します。
標準治療を否定するのではなく、その効果を補完し、より強固な再発予防体制を築くための戦略的な選択肢となります。
標準治療と免疫療法の決定的な違いと相互補完
標準治療である抗がん剤や放射線治療ががん細胞を直接攻撃する「外部からの介入」であるのに対し、がんワクチンは患者自身の免疫力を高めて間接的にがんを攻撃する「内部からの反撃」であり、両者を組み合わせることで治療の死角を減らすことができます。
標準治療は、がん細胞が増殖するスピードを利用して攻撃を仕掛けますが、同時に正常な細胞にも一定のダメージを与えることは避けられません。
一方、がんワクチンは特定の目印を持つ細胞だけを狙い撃ちにするよう免疫系を誘導するため、体への負担を抑えつつ、標準治療とは全く異なる角度から再発リスクにアプローチします。
無差別攻撃と標的攻撃の違い
一般的な抗がん剤(細胞障害性抗がん剤)は、細胞分裂が活発な細胞を攻撃するように設計されています。
これはがん細胞の大きな特徴の一つですが、髪の毛の細胞や消化管の粘膜、骨髄細胞など、正常な細胞でも分裂が活発なものは攻撃の対象となってしまいます。
これが脱毛や吐き気、白血球減少などの副作用の原因となります。
治療法ごとの特徴と比較
| 治療法 | 攻撃の主体 | 正常細胞への影響 |
|---|---|---|
| 抗がん剤(化学療法) | 薬剤が直接攻撃 | 分裂の速い正常細胞も影響を受ける(副作用あり) |
| 放射線治療 | 放射線(X線など) | 照射野に含まれる正常組織に影響が出る可能性 |
| がんワクチン | 自身の免疫細胞 | 特定の目印を狙うため、正常細胞への影響は軽微 |
対照的に、がんワクチンは「がん細胞だけが持っている目印(抗原)」を免疫細胞に提示し、その目印を持つ細胞だけを攻撃するよう指令を出します。
警察犬に犯人のにおいを覚えさせて追跡させるようなものです。この特異性により、正常な細胞への誤爆を避けながら、がん細胞だけをピンポイントで排除することを目指します。
標準治療が広範囲爆撃だとすれば、がんワクチンはスナイパーによる狙撃のような性質を持っています。
免疫抑制からの回復を促す
手術や抗がん剤治療を受けた直後の体は、侵襲や薬剤の影響で一時的に免疫力が低下していることが少なくありません。がん細胞はこの免疫の隙を突いて増殖しようとします。
そのため、がん細胞自体も免疫細胞のブレーキを踏ませるような物質を出し、攻撃を逃れようとする性質を持っています。
がんワクチン治療は、低下したり抑制されたりしている免疫システムに「敵はこれだ」という明確な情報を与え、攻撃のスイッチを入れ直す役割を果たします。
単に免疫力を上げるだけでなく、戦うべき相手を明確に指示することで、ぼんやりとしていた免疫細胞を精鋭部隊へと変えていきます。
標準治療でがんの総量を減らし、その後にワクチンで免疫監視体制を再構築するという流れは、理にかなった連携プレーと言えます。
長期的な記憶による監視体制
薬の効果は基本的に投与されている期間に限られますが、免疫療法の最大の特徴は「免疫記憶」にあります。
一度がん細胞の特徴を覚えた免疫細胞(メモリーT細胞など)は、体内に長期間留まり、監視を続けます。
もし数ヶ月後、数年後に再び微小ながん細胞が活動を開始しようとしても、記憶を持った免疫細胞が即座に反応し、増殖を未然に防ぐことが期待されます。
この長期的な監視能力こそが、再発予防においてがんワクチンに期待される大きな役割です。
毎日のように薬を飲み続けるのとは異なり、自身の体に備わった防御システムを強化し、持続的な警戒態勢を敷くことで、再発への不安を軽減する心の支えにもなり得ます。
がん細胞を特定し攻撃する免疫の働き
がんワクチンは、樹状細胞などの司令塔役となる細胞にがんの情報を与え、攻撃実行部隊であるT細胞を活性化させることで、がん細胞を特異的に排除する一連の免疫反応を引き起こします。
私たちの体には、本来ウイルスや細菌などの異物を排除する免疫システムが備わっていますが、がんは自分の細胞が変化したものであるため、免疫システムが「異物」として認識しにくいという厄介な性質があります。
がんワクチンはこの認識を助け、免疫細胞に「これは攻撃すべき敵である」と教え込むための教育ツールとして機能します。主な登場人物とその役割は以下の通りです。
免疫戦略における主な登場人物
- 樹状細胞(司令塔):がんの情報を収集し、攻撃部隊に標的を伝達する
- 細胞傷害性T細胞(攻撃部隊):指令に基づき、がん細胞を捜索し破壊する
- ヘルパーT細胞(支援部隊):免疫反応全体を統括・活性化し、攻撃を支援する
- がん抗原(目印):がん細胞の表面に特異的に現れるタンパク質の断片
- MHCクラスI分子(提示皿):がん細胞が自身の正体を免疫細胞に示すための土台
司令塔となる樹状細胞の役割
免疫システムの中で、敵の情報を収集し、攻撃部隊に指令を出す極めて重要な役割を担っているのが「樹状細胞」です。
樹状細胞は体中をパトロールしており、がん細胞の死骸などを取り込むと、その表面にある特徴的なタンパク質(抗原)を分析します。
そして、その情報をリンパ節などで待機しているリンパ球(T細胞)に伝えます。
がんワクチン治療の多くは、この樹状細胞をいかに効率よく働かせるかに重点を置いています。
体外で培養した樹状細胞にがんの目印を取り込ませてから体に戻したり、あるいは体内の樹状細胞に直接届くように抗原となる物質(ペプチドなど)を注射したりします。
司令塔が正確な情報を持てば持つほど、攻撃部隊の精度は向上します。
攻撃部隊となる細胞傷害性T細胞
樹状細胞から「この目印を持つ細胞を攻撃せよ」という指令を受け取るのが、細胞傷害性T細胞(CTL)と呼ばれるリンパ球です。
指令を受けたCTLは活性化し、分裂して数を増やしながら、血流に乗って全身を巡ります。
そして、教えられた目印を持つがん細胞を見つけ出すと、パーフォリンやグランザイムといった物質を放出して細胞膜に穴を開け、がん細胞を破壊します。
この一連の流れにおいて、がんワクチンはCTLに対する「手配書」のような役割を果たします。
手配書がなければ、CTLは目の前にがん細胞がいても素通りしてしまうことがありますが、明確な手配書があれば、隠れているがん細胞を見つけ出して攻撃することが可能になります。
この攻撃力の強さと正確さが、がんワクチンの真骨頂です。
がん特有の目印「がん抗原」
免疫細胞ががん細胞を見分けるための目印となるのが「がん抗原」です。正常な細胞にはほとんど存在せず、がん細胞にだけ多く発現しているタンパク質が理想的な抗原となります。
例えば「WT1」や「CEA」、「MAGE」といった様々な抗原が見つかっており、がんの種類によって発現しやすい抗原が異なります。
がんワクチン治療では、患者様のがん細胞がどのような抗原を持っているかを調べ、それに合わせたワクチンを使用することが大切です。
また、一つだけでなく複数の抗原をターゲットにすることで、がん細胞の逃げ道を塞ぐ戦略もとられます。自分のがんに合った抗原を見つけることが、治療成功の鍵となります。
再発予防における治療開始のタイミング
がん細胞の総量が最も少ない手術直後や術後化学療法の終了直後こそが、がんワクチンの効果を最大限に引き出せる「好機」であり、微小残存病変に対して圧倒的な数的優位を持って戦うことが可能です。
免疫療法には「腫瘍量(がん細胞の数)が少ないほど効果が出やすい」という明確な鉄則があります。
目に見える再発をしてからでは、がん細胞の数は数十億個、数千億個にも達し、増殖の勢いも強いため、免疫の力だけで抑え込むことが難しくなります。
敵が少数で、まだ組織化されていない段階で叩くことが、勝利への近道です。
微小残存病変(MRD)という概念
手術で肉眼的にがんを取り除いたとしても、顕微鏡レベルでしか見えないがん細胞が残っている状態を「微小残存病変(MRD: Minimal Residual Disease)」と呼びます。
この段階では、がん細胞はまだ血管網を十分に構築しておらず、免疫による攻撃に対して脆弱な状態にあります。
腫瘍量と免疫療法の効果の関係
| 時期 | がん細胞の量(腫瘍量) | ワクチンの期待度 |
|---|---|---|
| 手術直後・術後化学療法後 | 極めて少ない(微小残存病変) | 高い(免疫細胞が優勢に立ちやすい) |
| 経過観察中の早期発見 | 少ない(画像で確認できる程度) | 中程度(早期介入が必要) |
| 進行・再発時 | 多い(全身に広がっている) | 単独では難しい(他の治療との併用が必要) |
この時期にワクチンを投与することで、免疫細胞は少数のがん細胞を効率的に処理することができます。
逆に、再発が確認できる大きさまで成長してしまうと、がん細胞は自らを守るための微細環境を作り上げ、免疫細胞を寄せ付けないようにしたり、無力化したりする術を獲得してしまいます。
したがって、画像検査で「異常なし」と言われている時期こそが、実は治療のゴールデンタイムなのです。
免疫再構築の期間を活用する
手術や抗がん剤治療による身体的ストレスから回復する過程で、免疫システムも再構築されます。
この回復期にがんワクチンによる「教育」を行うことで、新しく作られる免疫細胞たちに最初からがんに対する攻撃能力を持たせることができます。
白紙の状態に近い免疫系に、正しい情報をインプットするイメージです。
また、術後補助化学療法(抗がん剤)を行う場合、抗がん剤とワクチンのタイミングをどう調整するかは専門的な判断が必要です。
抗がん剤の種類によっては免疫細胞を極端に減らしてしまうため、同時併用よりも、化学療法の休薬期間や終了後にワクチンを開始する「シーケンシャル(順次)療法」が選択されることもあります。
個々の治療スケジュールに合わせて、免疫が最も反応しやすい時期を見極めることが大切です。
再発・転移が見つかってからでは遅いのか
もちろん、再発が見つかってからでも免疫療法を行う意義はありますが、予防的な投与に比べるとハードルは上がります。
再発時にはがんの勢いが強く、免疫抑制の壁も厚くなっているため、チェックポイント阻害剤などの強力な薬剤との併用が必要になることが多いです。
「再発したら考えよう」という先送りは、最も有利な戦いの場を放棄することになりかねません。
標準治療が終わった段階で、体の中に残っているかもしれない火種を完全に消し去るためのアクションを起こすことが、将来の安心につながります。
予防に勝る治療はないという原則は、がん治療においても同様です。
患者様が選択可能ながんワクチンの種類
現在利用可能な主ながんワクチンには、人工的に合成した目印を使用する「ペプチドワクチン」や、患者自身の細胞を加工する「樹状細胞ワクチン」などがあり、それぞれに特性や適合するタイプが異なります。
どのがんワクチンも「免疫を教育する」という目的は同じですが、その手段や材料、手間に違いがあります。
自身の病状や体力、そしてがんの性質に合わせて、どのタイプが適しているかを検討する必要があります。
手軽に始められるペプチドワクチン
ペプチドワクチンは、がん抗原(がんの目印となるタンパク質)の断片である「ペプチド」を人工的に合成し、これを皮下に注射する治療法です。
樹状細胞がこのペプチドを取り込み、T細胞に提示することで免疫反応を誘導します。比較的安価で、製剤化されているためすぐに治療を開始できる利点があります。
代表的なものに「WT1ペプチドワクチン」などがあります。ただし、ペプチドワクチンは患者の白血球の型(HLA型)とワクチンの型が合致していないと効果を発揮しません。
鍵と鍵穴の関係のように、型が合って初めて免疫スイッチが入る仕組みです。そのため、事前の血液検査で適合性を確認することが必須となります。
オーダーメイドの樹状細胞ワクチン
樹状細胞ワクチンは、患者自身の血液から「単球」という細胞を取り出し、体外で培養して樹状細胞へと成長させ、そこにがんの目印を取り込ませてから再び体内に戻す治療法です。
まさに自分の細胞を使ったオーダーメイド医療であり、免疫の司令塔を直接強化するため、理論的に高い効果が期待されます。
このワクチンの強みは、人工のペプチドだけでなく、手術で摘出した自身のがん組織(腫瘍ライセート)を目印として使用できる点にあります。
自分のがんそのものを使うため、単一の抗原だけでなく、その人のがんが持つ無数の抗原情報を樹状細胞に教え込むことが可能になります。
ただし、細胞培養のための採血(成分採血)が必要であり、高度な培養施設を要するため費用が高額になる傾向があります。
主なワクチンのタイプ比較
| 種類 | 特徴とメリット | 考慮すべき点 |
|---|---|---|
| ペプチドワクチン | 人工合成で品質が安定、注射のみで簡便 | HLA型の適合が必要 |
| 樹状細胞ワクチン(人工抗原) | 自身の細胞を強化、高い誘導能力 | 成分採血(アフェレーシス)が必要 |
| 樹状細胞ワクチン(自家組織) | 自分のがん組織を使用、多数の抗原を標的 | 手術検体の確保・保存が必要 |
その他の新しいワクチン技術
近年では、コロナワクチンで有名になったmRNA技術を応用したがんワクチンの開発も進んでいます。
これはがん抗原の設計図となるmRNAを投与し、体内で抗原を作らせて免疫を誘導するものです。また、複数のがん抗原を一度に刺激できるカクテルワクチンなども研究・臨床応用されています。
重要なのは、どのワクチンが「優れているか」という単純な比較ではなく、どのアプローチが「現在の自分の状況に合っているか」です。
例えば、手術検体が保存されているなら自家がん組織を使った樹状細胞ワクチンが選択肢に入りますし、そうでなければ汎用性の高いペプチドワクチンや、人工抗原を用いた樹状細胞ワクチンが候補になります。
標準治療との相乗効果を高める要因
化学療法や放射線治療によってがん細胞が破壊される際に放出される抗原が、ワクチンの効果を増幅させる「免疫原性細胞死(ICD)」という現象を引き起こし、標準治療とワクチンの併用は単なる足し算以上の相乗効果を生み出すことが期待されます。
かつては、抗がん剤は免疫を弱めるためワクチンとの相性が悪いと考えられていました。
しかし、現代の免疫学では、適切なタイミングでの併用がむしろ免疫反応を強く惹起することがわかってきています。
がん細胞の「悲鳴」を利用する
抗がん剤や放射線によってがん細胞がダメージを受けると、細胞が死ぬ過程で様々な物質を放出します。これを「免疫原性細胞死(ICD)」と呼びます。
この時、がん細胞の中に隠れていた抗原がばら撒かれ、同時に「危険信号」が周囲の免疫細胞に送られます。
相乗効果を生み出す主な要因
- 免疫原性細胞死(ICD):標準治療によるがん細胞の破壊が、新たな抗原提示を促す
- バリケードの破壊:腫瘍周囲の環境が変化し、免疫細胞が浸透しやすくなる
- 抗原性の向上:薬剤の影響でがん細胞が目印を出しやすくなる場合がある
- 抑制の解除:特定の治療が、がんによる免疫抑制状態を緩和する
この状況下でがんワクチンを使用すると、ワクチンによって活性化された免疫細胞が、ばら撒かれた抗原を目印にして、生き残っているがん細胞をより効率的に発見できるようになります。
つまり、標準治療ががん細胞の隠れ蓑を剥がし、ワクチンがその隙を突いて攻撃するという連携が成立するのです。
この「アブスコパル効果」に似た全身的な免疫活性化を意図的に狙うのが併用療法の醍醐味です。
腫瘍微小環境の変化
がん細胞の周囲には、免疫細胞の侵入を阻むバリケード(腫瘍微小環境)が築かれています。標準治療はこのバリケードを一時的に破壊したり、構造を変化させたりする効果があります。
堅牢な城壁が崩れたタイミングで、ワクチンによって訓練されたT細胞部隊を送り込むことで、通常では到達しにくいがんの中心部まで攻撃の手を伸ばすことが可能になります。
また、特定の分子標的薬などは、がん細胞の表面にある抗原の発現量を増やしたり、免疫細胞のブレーキを解除したりする作用を持つものもあります。
主治医と相談しながら、どの薬剤を使っている時期にワクチンを開始するのが最も効果的か、戦略的に計画を立てることが求められます。
免疫チェックポイント阻害剤との関係
近年標準治療として定着しつつある「免疫チェックポイント阻害剤(オプジーボやキイトルーダなど)」は、がん細胞がかけた免疫へのブレーキを外す薬です。
一方、がんワクチンはアクセルを踏む(攻撃部隊を増やす)治療です。
理論上、ブレーキを外しながらアクセルを踏むこの組み合わせは非常に強力です。
標準治療としてチェックポイント阻害剤が適応となる場合、そこにがんワクチンを上乗せすることで、解除されたブレーキの効果を最大限に活かし、爆発的な攻撃力を生み出す可能性があります。
自分の受けている治療が免疫にどう作用するかを知ることで、ワクチンの活かし方も見えてきます。
治療を受けるための適合条件と検査
がんワクチン治療を効果的に行うためには、HLA検査による遺伝子型の確認や免疫機能の評価が必須であり、自身の体質や免疫状態に合致した治療戦略を立てることが成功への第一歩です。
どんなに優れた薬でも、体に合っていなければ効果は期待できません。特に免疫療法は、個人の遺伝的な背景や、その時の体のコンディションに大きく左右される治療法です。
そのため、治療開始前の「事前評価」が極めて重要になります。
治療開始前に確認すべき主な項目
| 検査・確認項目 | 内容と目的 |
|---|---|
| HLA検査 | 白血球の型を調べ、適合するペプチドや抗原を選定する |
| 免疫機能検査 | リンパ球数やその比率を調べ、免疫の予備能力を評価する |
| 抗原発現解析 | 手術検体を用い、がん細胞がターゲットとなる抗原を持っているか確認する |
| 一般血液検査 | 貧血や栄養状態、肝腎機能など、治療に耐えうる全身状態か見る |
HLA検査(白血球の型)の重要性
HLA(ヒト白血球抗原)は、いわば白血球の血液型のようなものです。がん抗原ペプチドは、このHLAというお皿に乗せられて初めてT細胞に認識されます。
日本人の約6割は「HLA-A24」という型を持っていますが、「HLA-A2」など他の型の人もいます。
多くのペプチドワクチンは、特定のHLA型(例えばA24型の人専用)に合わせて設計されています。
もし型が合わないワクチンを打っても、免疫細胞は情報を・受け取ることができず、効果は全く出ません。
まずは血液検査で自分のHLA型を知り、適応するワクチンがあるかどうかを確認することがスタートラインです。樹状細胞ワクチンにおいても、使用する抗原とHLAの適合性は重要です。
免疫機能と全身状態のチェック
ワクチンは自身の免疫力を使って戦うため、基礎的な免疫力が極端に低下していると十分な効果が得られません。
血液中のリンパ球数や、栄養状態(アルブミン値など)をチェックし、戦える体であるかを確認します。
もし栄養状態が悪ければ、まずは栄養療法で体の土台を整えることが優先される場合もあります。
また、活動度(パフォーマンスステータス)も指標になります。寝たきりの状態よりも、ある程度日常生活が送れる元気な状態の方が、免疫システムも正常に反応しやすい傾向にあります。
再発予防の段階であれば、通常は全身状態が良いことが多いため、ワクチンの適応としては好条件であると言えます。
がん抗原の発現確認
自分の持っていたがん細胞が、ワクチンのターゲットとなる抗原(WT1やCEAなど)を実際に持っているかどうかも重要な要素です。
手術で摘出した組織が保存されていれば、「免疫染色」という検査で抗原の有無を調べることができます。
ターゲットとなる目印を持っていないがんに、その目印を狙うワクチンを打っても意味がありません。敵の特徴を正確に把握し、その特徴に合った武器を選ぶこと。
これが個別化医療の基本であり、無駄な治療を避けるためにも必要な手順です。
Q&A
手術後の再発予防としてがんワクチンを検討されている方から寄せられることの多い疑問について、医学的な観点からお答えします。
- 副作用はどのようなものがありますか?
-
自身の免疫細胞を活性化させる治療であるため、抗がん剤のような激しい副作用(脱毛、激しい嘔吐、骨髄抑制など)はほとんどありません。
多く見られるのは、注射部位の赤み、腫れ、痒みです。これらは免疫が正常に反応している証拠でもあります。
インフルエンザワクチンのように一過性の発熱や倦怠感が出ることがありますが、通常は数日で治まります。体に優しい治療として、働きながら通院される方も多くいらっしゃいます。
- 抗がん剤治療中ですが併用は可能ですか?
-
基本的には可能ですし、むしろ相乗効果が期待できる場合もあります。
ただし、抗がん剤の種類や量によっては免疫細胞が一時的に減少し、ワクチンの効果が出にくくなる時期があります。
そのため、抗がん剤投与の休薬期間を狙ったり、抗がん剤のコースが終了した直後に開始したりするなど、主治医と連携して適切なスケジュールを組むことが大切です。
決して独断で判断せず、双方の医師と相談してください。
- どのがんでも効果はありますか?
-
がんワクチンは原理的に、固形がん(胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、膵臓がんなど)を含む幅広いがん種に対応可能です。
重要なのは「がんの種類」よりも「ターゲットとなる抗原を持っているか」や「HLA型が合っているか」です。
ただし、血液のがん(白血病など)の一部では治療法が異なる場合があります。ご自身の病状に適応があるかどうかは、事前の医療相談や検査で確認する必要があります。
- いつまで続ける必要がありますか?
-
再発予防の場合、一般的には1クール(5回から10回程度、医療機関やワクチンの種類による)を数ヶ月かけて行い、免疫の基礎を作ります。
その後は、免疫記憶を維持するために数ヶ月に1回程度のメンテナンス投与を行う長期的なプランが提案されることが多いです。
再発のリスクが高い期間(術後2年から3年など)は警戒レベルを高く保つことが推奨されますが、個々のリスクやライフスタイルに合わせて計画されます。
参考文献
WANG, Tingting, et al. A cancer vaccine-mediated postoperative immunotherapy for recurrent and metastatic tumors. Nature communications, 2018, 9.1: 1532.
MICHALCZYK, Kaja; MISIEK, Marcin; CHUDECKA-GŁAZ, Anita. Can adjuvant HPV vaccination be helpful in the prevention of persistent/recurrent cervical dysplasia after surgical treatment?—a literature review. Cancers, 2022, 14.18: 4352.
DI DONATO, Violante, et al. Adjuvant HPV vaccination to prevent recurrent cervical dysplasia after surgical treatment: a meta-analysis. Vaccines, 2021, 9.5: 410.
LE, Quoc-Viet, et al. In situ nanoadjuvant-assembled tumor vaccine for preventing long-term recurrence. ACS nano, 2019, 13.7: 7442-7462.
KUANG, Ming, et al. Phase II randomized trial of autologous formalin-fixed tumor vaccine for postsurgical recurrence of hepatocellular carcinoma. Clinical cancer research, 2004, 10.5: 1574-1579.
HSUEH, Eddy C., et al. Prolonged survival after complete resection of disseminated melanoma and active immunotherapy with a therapeutic cancer vaccine. Journal of clinical oncology, 2002, 20.23: 4549-4554.
MITTENDORF, Elizabeth A., et al. Efficacy and safety analysis of nelipepimut-S vaccine to prevent breast cancer recurrence: a randomized, multicenter, phase III clinical trial. Clinical Cancer Research, 2019, 25.14: 4248-4254.
ZENGA, Joseph, et al. Salvage of recurrence after surgery and adjuvant therapy: a multi-institutional study. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 2019, 161.1: 74-81.
GHELARDI, Alessandro, et al. Surgical treatment of vulvar HSIL: adjuvant HPV vaccine reduces recurrent disease. Vaccines, 2021, 9.2: 83.
GRINSHTEIN, Natalie, et al. Neoadjuvant vaccination provides superior protection against tumor relapse following surgery compared with adjuvant vaccination. Cancer research, 2009, 69.9: 3979-3985.