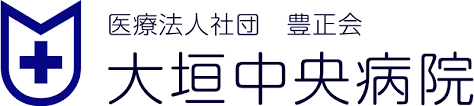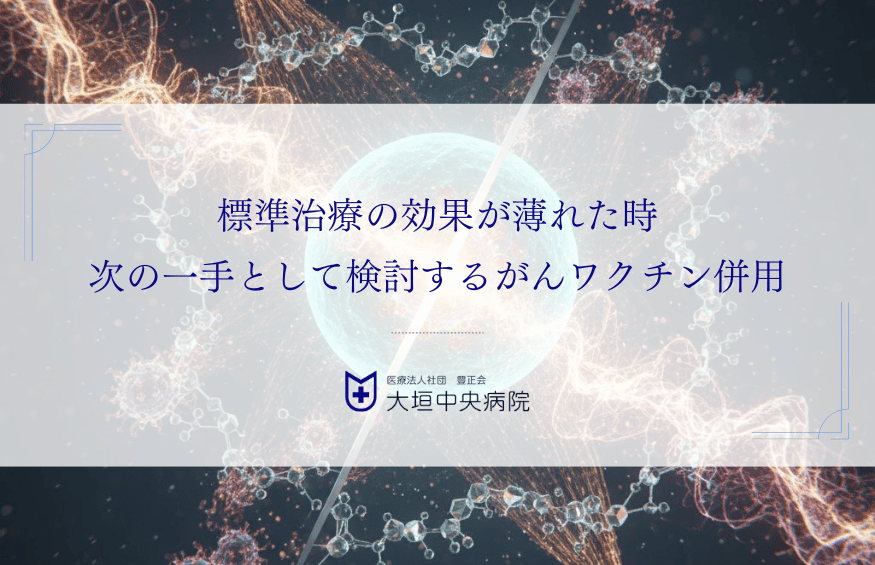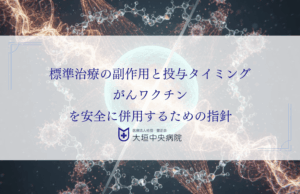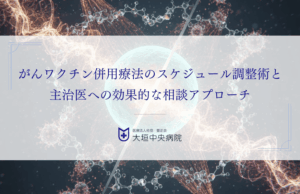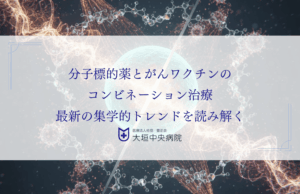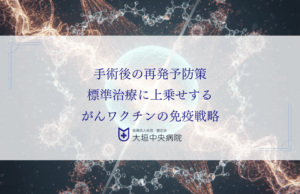がん治療において「標準治療」とは、現時点で科学的根拠に基づき推奨される第一選択の治療法を指します。
しかし、がん細胞は賢く、時間とともに薬剤への耐性を獲得し、治療効果が薄れてしまうことがあります。
医師から「使える薬がなくなった」「緩和ケアへ移行しましょう」と提案された時、多くの患者様は絶望感に襲われるかもしれません。
しかし、医療技術は日々進歩しており、標準治療の枠を超えた新たな選択肢が存在します。
特に注目すべきは、自身の免疫力を再教育する「がんワクチン」と、既存の治療薬や他の免疫療法を組み合わせる「併用療法」です。
単独では突破できなかった壁を、複数の治療法を掛け合わせることで乗り越えようとするこのアプローチは、進行がんに対する有力な「次の一手」となり得ます。
本記事では、標準治療後の選択肢としてのがんワクチン併用療法の理論と実際について、詳しく解説します。
標準治療の限界とがん細胞の薬剤耐性について
標準治療の効果減弱は、がん細胞の生存戦略による必然的な現象であり、次の対策を練るための起点となります。
薬剤耐性が生じる背景を理解し、標準治療終了後の選択肢を正しく認識することは、納得のいく治療選択を行うための第一歩です。
がん細胞が薬に慣れてしまう理由
がん細胞は、正常な細胞とは異なり、遺伝子が不安定で常に変化し続けています。抗がん剤や分子標的薬を使用すると、最初は多くのがん細胞が死滅し、腫瘍が縮小します。
しかし、数億個、数兆個というがん細胞の中には、最初からその薬剤に対して抵抗力を持つ「耐性細胞」がごくわずかに潜んでいることがあります。
あるいは、薬剤による攻撃を受ける中で、生き残るために新たな遺伝子変異を起こし、薬の作用を無効化する能力を獲得する細胞も現れます。
例えば、細胞内に入ってきた薬をポンプのように外へ汲み出してしまう機能を持ったり、薬が標的とするタンパク質の形を変えて結合できないようにしたりします。
このようにして、薬剤耐性を獲得した一部のがん細胞が再び増殖を始めると、これまで効いていた薬が効かなくなり、「再発」や「増悪」といった状態に陥ります。
これは治療の失敗というよりも、生物学的な生存本能による適応現象といえます。
標準治療終了と言われた時の心構え
主治医から「標準治療の終了」を告げられることは、患者様にとって非常に重い事実です。
しかし、これは「治療の手立てが全くなごくなった」という意味ではなく、「保険診療のガイドライン上で、統計的に有効性が証明された薬剤を使い切った」という意味に過ぎません。
標準治療は、大規模な臨床試験で多くの人に効果があると証明された治療ですが、あくまで「平均的な正解」です。
個々の患者様の体質やがんの性質に合わせた個別化医療の領域には、まだ選択肢が残されています。
標準治療と自由診療における治療の目的の違い
| 比較項目 | 標準治療(保険診療) | 自由診療(先端医療など) |
|---|---|---|
| 治療の根拠 | 大規模な臨床試験で統計的有意差が証明されたエビデンスに基づく。 | 基礎研究や小規模試験での理論的有効性に基づく個別化医療。 |
| 対象となる患者 | ガイドラインで定められた一定の基準を満たす集団。 | 標準治療不応例や、体力的に標準治療が難しい個々の症例。 |
| 主な目的 | 腫瘍の縮小、生存期間の延長(全体平均としての効果)。 | QOLの維持、個別のがん特性に合わせた治療、長期共存。 |
この段階で重要になるのは、焦って根拠のない民間療法に飛びつくのではなく、科学的な理論に基づいた「次の一手」を冷静に検討することです。
緩和ケアは苦痛を取り除くために大切ですが、それと並行して、がんに対する積極的な治療を継続する道を探ることは可能です。
その一つの有力な候補が、免疫の力を利用した治療法です。
緩和ケアのみという選択肢以外の道
標準治療が終わると、病院によっては積極的な治療を提供できず、緩和ケア病棟への転院や在宅医療を勧められることが一般的です。
しかし、体力(パフォーマンスステータス)が維持されており、臓器の機能が保たれている場合、自由診療を含めた先端的な治療に挑戦する余地があります。
特に、身体への負担が比較的少ないがんワクチン療法などの免疫療法は、抗がん剤治療で疲弊した体でも取り組みやすい選択肢の一つです。
また、標準治療では「がんを小さくすること」が主眼に置かれますが、次の一手では「がんの進行を抑え、生活の質(QOL)を保ちながら共存する」ことへと目標をシフトさせる場合もあります。
完全に治すことが難しくても、進行を遅らせ、自分らしい時間を長く過ごすための戦略として、併用療法を検討する価値は大いにあります。
第4の治療法としてのがんワクチン療法の基礎知識
がんワクチン療法は、患者様自身の免疫システムにがんの特徴を記憶させ、ピンポイントで攻撃させる特異的免疫療法です。
従来の治療法とは異なる作用機序を持つため、副作用を抑えつつ、これまでの治療で制御できなかったがん細胞に対しても効果を発揮する可能性があります。
自身の免疫力を活用する仕組み
私たちの体には、本来がん細胞を異物として認識し、排除する免疫機能が備わっています。その主役となるのが「キラーT細胞(細胞傷害性T細胞)」と呼ばれるリンパ球です。
しかし、がん細胞は巧妙に正体を隠したり、免疫細胞の攻撃を抑制したりするため、通常の免疫力だけでは増殖を抑えきれなくなります。
がん免疫療法に関わる主要な細胞と役割
- 樹状細胞は、がんの目印を取り込み、T細胞に攻撃指令を出す重要な司令塔です。
- キラーT細胞は、樹状細胞の指令を受け、実際にがん細胞を攻撃する実行部隊として働きます。
- ヘルパーT細胞は、他の免疫細胞を活性化させ、攻撃力を高める支援部隊の役割を担います。
- NK細胞は、目印の有無に関わらず、異常な細胞をいち早く見つけて攻撃する巡回部隊です。
がんワクチン療法は、がん細胞特有の目印(抗原)を人工的に合成したり、患者様自身のがん組織から抽出したりして体内に入れます。
これを、免疫の司令塔である「樹状細胞」が取り込み、がんの目印をキラーT細胞に提示します。目印を覚えたキラーT細胞は、全身を巡ってがん細胞だけを正確に捜索し、攻撃を開始します。
つまり、がんワクチンは直接がんを殺す薬ではなく、自身の免疫細胞を「対がん戦闘モード」に教育し、活性化させるためのスイッチといえます。
予防ワクチンと治療ワクチンの違い
一般的に「ワクチン」と聞くと、インフルエンザやコロナウイルスのように、感染症にかからないための「予防接種」をイメージされる方が多いでしょう。
これらは、まだ体内に病原体が入っていない状態で、あらかじめ抗体を作らせておくものです。
一方、がんワクチンは「治療ワクチン」と呼ばれ、すでに体内に存在しているがん細胞を攻撃するために投与されます。
治療用ワクチンでは、即効性のある強い免疫反応を引き起こす必要があります。
その結果、単に抗原を注射するだけでなく、免疫反応を強めるためのアジュバント(免疫賦活剤)を混ぜたり、患者様の血液から採取した樹状細胞を体外で培養・加工して戻したりするなど、高度な技術が用いられます。
予防ではなく、今あるがんとの戦いを有利に進めるための援軍を送るイメージです。
特異的免疫療法のメリット
免疫療法には、大きく分けて「非特異的免疫療法」と「特異的免疫療法」があります。
古くからあるキノコ由来の成分やサイトカイン療法などは、全身の免疫を底上げする非特異的なもので、攻撃の矛先が定まりにくいという課題がありました。
対して、がんワクチンは特定の目印を標的にする「特異的免疫療法」に分類されます。
この特異性により、正常な細胞を傷つけることなく、がん細胞だけをピンポイントで攻撃することが可能になります。
そのため、従来の抗がん剤に見られるような脱毛や激しい吐き気、骨髄抑制といった重篤な副作用が少なく、体への負担が軽いのが大きな特徴です。
高齢の方や体力が低下している方でも治療を継続しやすく、日常生活を送りながら通院治療が可能である点は、QOLを重視する上で非常に重要な要素となります。
なぜ単独ではなく併用療法が推奨されるのか
併用療法が推奨される理由は、がんが構築する免疫抑制環境を打破し、多角的な攻撃で薬剤耐性を防ぐ必要があるからです。
ワクチンによる攻撃力の強化と、他の薬剤による防御壁の破壊を組み合わせることで、単独療法では得られない治療効果を目指します。
免疫抑制環境を打破する必要性
がん細胞が増殖して塊(腫瘍)を作ると、その周囲には「がん微小環境」と呼ばれる独特のエリアが形成されます。
この環境内では、免疫細胞の働きを強制的に止める物質が放出されていたり、免疫を抑制する細胞(制御性T細胞など)が呼び寄せられていたりします。
いわば、がんは自分を守るための強力なバリアを張っている状態です。
単独療法と併用療法の考え方の比較
| 項目 | 単独療法(ワクチンのみ) | 併用療法(ワクチン+α) |
|---|---|---|
| 作用の方向性 | 免疫細胞を増やし、攻撃力を高める(アクセルのみ)。 | 攻撃力を高めつつ、がんの防御機能を削ぐ(アクセル+ブレーキ解除)。 |
| がん微小環境への影響 | 抑制環境が強い場合、効果が出にくい。 | 抑制環境を改善し、免疫細胞が活動しやすい場を作る。 |
| 耐性への対応 | 標的となる目印が消えると効かなくなるリスクがある。 | 複数のメカニズムで攻撃するため、耐性が生じにくい。 |
がんワクチンによって強力なキラーT細胞を育てて送り込んでも、このバリアに阻まれてしまえば、がん細胞に到達する前に無力化されてしまいます。
これが、ワクチン単独療法の限界と言われる所以です。
この状況を打開するためには、ワクチンの力で攻撃部隊を増やすと同時に、バリアを破壊したり、免疫抑制を解除したりする別の治療法を組み合わせることが必要になります。
がん微小環境(TME)へのアプローチ
併用療法では、役割分担が重要です。がんワクチンは「アクセル」として免疫細胞を活性化させますが、それだけでは不十分です。
例えば、低用量の抗がん剤や放射線治療、あるいは特定の分子標的薬を併用することで、がん微小環境の構造を変化させることが可能です。
その結果、免疫細胞が腫瘍の内部へ浸透しやすい環境を整えます。
また、血管新生阻害薬などを併用してがんへの血流環境を正常化し、免疫細胞が戦場(腫瘍)へスムーズに移動できるようにする戦略もとられます。
単一の攻撃ではなく、環境そのものを「免疫が働きやすい状態」に変えることが、併用療法の大きな目的の一つです。
多角的な攻撃でがんを追い詰める戦略
がんは単一の細胞集団ではなく、多様な性質を持つ細胞の集まりです。ある攻撃には弱くても、別の攻撃には強い細胞が混在しています。
ワクチン療法で特定の目印を持つがん細胞を攻撃しても、その目印を持たない「抗原欠失変異株」が生き残ってしまう可能性があります。
そこで、作用機序の異なる治療を組み合わせることで、逃げ道を防ぎます。
例えば、ワクチンで特定の目印を持つ細胞を叩きつつ、他の薬剤で細胞分裂そのものを阻害したり、別の経路で免疫を活性化させたりします。
このように多角的に攻めることで、がん細胞が薬剤耐性を獲得する隙を与えず、治療効果の持続を目指すのが併用療法の強みです。
免疫チェックポイント阻害薬との相乗効果
がんワクチンと免疫チェックポイント阻害薬の併用は、免疫の「アクセル」と「ブレーキ解除」を同時に行うことで、強力な抗腫瘍効果を生み出します。
この理論的な整合性の高さは、現在の免疫療法における最も重要な戦略の一つとして位置づけられています。
ブレーキを解除しアクセルを踏む関係
免疫細胞には、自分自身の正常な細胞を過剰に攻撃しないよう、暴走を防ぐためのブレーキ機能(免疫チェックポイント)が備わっています。
がん細胞はこの機能を悪用し、免疫細胞にあるブレーキボタン(PD-1など)を押して、攻撃を止めさせてしまいます。
免疫チェックポイント阻害薬は、このブレーキボタンにカバーをかけ、がん細胞がボタンを押せないようにする薬です。
ワクチンと免疫チェックポイント阻害薬の役割分担
| 治療法 | 役割のイメージ | 具体的な作用 |
|---|---|---|
| がんワクチン | アクセルを踏む(攻撃命令と増員) | がんの目印を提示し、特異的なキラーT細胞を教育・増殖させ、がん組織へ誘導する。 |
| 免疫チェックポイント阻害薬 | ブレーキを外す(妨害の排除) | がん細胞による免疫抑制シグナル(PD-1/PD-L1結合など)を遮断し、T細胞の無力化を防ぐ。 |
| 併用効果 | フルスピードで突進 | 活性化した大量のT細胞が、抑制を受けることなくがん細胞を破壊し続ける。 |
これを車に例えると、がんワクチンはエンジンの回転数を上げて車を加速させる「アクセル」の役割を果たします。一方、がん細胞は必死に「ブレーキ」を踏んで車を止めようとします。
ワクチン単独では、いくらアクセルを踏んでもブレーキがかかったままなので車(攻撃)は進みません。そこで、免疫チェックポイント阻害薬を使ってブレーキを強制的に解除します。
アクセル全開の状態でブレーキが外れるため、免疫細胞は猛烈な勢いでがん細胞を攻撃できるようになります。
オプジーボやキイトルーダとの併用事例
代表的な免疫チェックポイント阻害薬には、ニボルマブ(製品名:オプジーボ)やペムブロリズマブ(製品名:キイトルーダ)などがあります。
これらはすでに多くの標準治療で使用されていますが、単剤での奏効率(がんが縮小する割合)は20〜30%程度に留まることも少なくありません。
これは、そもそも攻撃を担当するキラーT細胞の数が不足している患者様では、ブレーキを外しても攻撃力が足りないためです。
そこで、がんワクチンを併用します。ワクチンによって質の高いキラーT細胞を体内で大量に誘導(教育・増殖)し、攻撃の準備を整えた上で、チェックポイント阻害薬を使います。
こうすることで、「兵隊の数を増やす」ことと「兵隊の足かせを外す」ことが同時に行われ、これまでの治療で反応しなかった症例でも効果が期待できるようになります。
奏効率の向上を目指す科学的根拠
近年の臨床研究において、ワクチンとチェックポイント阻害薬の併用が、それぞれの単独療法よりも高い抗腫瘍効果を示すデータが蓄積されつつあります。
特に、「冷たい腫瘍(Cold Tumor)」と呼ばれる、免疫細胞がほとんど浸透していないタイプのがんに対して、ワクチンが呼び水となって免疫細胞を誘導し、「熱い腫瘍(Hot Tumor)」へと変化させる効果が確認されています。
熱い腫瘍に変えることができれば、チェックポイント阻害薬の効果も飛躍的に高まります。
標準治療でチェックポイント阻害薬の効果が不十分だった場合でも、ワクチンを加えることで再び効果を発揮する可能性があるため、次の一手として非常に論理的な選択肢といえます。
抗がん剤や放射線治療との併用による免疫原性細胞死
抗がん剤や放射線治療との併用は、がん細胞を破壊することで新たな抗原を放出させ、免疫系に認識させる「免疫原性細胞死」を引き起こします。
これにより、体内にあるがんそのものを新たなワクチンとして利用し、免疫療法の効果を増幅させることが可能です。
がん細胞を壊して免疫に認識させる
がんワクチンが効くためには、免疫細胞ががんの目印(抗原)を認識する必要があります。しかし、がん細胞の中には目印を隠しているものもあります。
ここで役立つのが、抗がん剤や放射線治療です。これらの治療によってがん細胞が破壊されると、細胞内部に隠されていた様々なタンパク質や抗原がばら撒かれます。
この現象は「免疫原性細胞死(ICD:Immunogenic Cell Death)」と呼ばれます。
ばら撒かれた抗原を樹状細胞が取り込むことで、ワクチンに含まれていなかった未知のがん抗原までも免疫システムが学習することになります。
つまり、がんを壊すこと自体が、体内での新たなワクチン接種のような効果を生み出すのです。これにより、人工的なワクチンと、自身の体内から供給されるワクチンのダブル効果が期待できます。
併用により期待される効果の流れ
- 抗がん剤や放射線でがん細胞の一部を破壊し、崩壊させます。
- 壊れたがん細胞から、多様ながん抗原が周囲に放出されます。
- 樹状細胞が放出された抗原を取り込み、T細胞に新たな敵として教えます。
- ワクチンで元々強化されていた免疫に加え、新たな抗原を標的とする免疫も加わり、攻撃の幅が広がります。
アブスコパル効果の可能性
放射線治療との併用において特に興味深い現象が「アブスコパル効果」です。
これは、ある一箇所のがん病変に放射線を照射した際、照射していない離れた場所にある転移巣までもが縮小するという現象です。
局所の放射線治療によって免疫原性細胞死が起こり、活性化した全身の免疫細胞が他の場所のがんも攻撃した結果と考えられています。
がんワクチンを併用することで、このアブスコパル効果が起こる確率を高めることが期待されています。
放射線で局所のがんを叩き、そこで生じた免疫反応をワクチンで増幅させ、全身に散らばる微小な転移がんを叩く。
この全身的な治療効果は、進行がんのコントロールにおいて極めて重要な戦略となります。
従来の治療薬を低用量で活用する工夫
標準治療で使用される抗がん剤は「最大耐用量」といって、副作用が出るギリギリの量を使うことが一般的ですが、ワクチンの併用相手として使う場合は、あえて量を減らすことがあります。
これを「メトロノミック療法」や低用量化学療法と呼ぶこともあります。
目的はがんを直接殺し尽くすことではなく、免疫を抑制する細胞(制御性T細胞など)を選択的に減らしたり、がん細胞の表面に目印をより多く出させたりすることです。
低用量であれば、骨髄抑制などの副作用で免疫細胞自体が減ってしまうリスクを抑えながら、免疫療法の効果を底上げする「免疫調整薬」としての役割を引き出すことができます。
標準治療で体力的に抗がん剤が続けられなくなった方でも、この方法であれば治療を継続できる可能性があります。
個別化医療としてのネオアンチゲンワクチン
個別化医療の極みであるネオアンチゲンワクチンは、患者様固有の遺伝子変異を標的とすることで、高い特異性と安全性を両立させます。
自身の細胞情報に基づいた完全オーダーメイドの治療は、標準治療後の有力な選択肢となります。
遺伝子解析によるオーダーメイド治療
従来のがんワクチンは、多くの患者様に共通して発現している「共通抗原(WT1など)」を使用していました。
これは多くの人に使える反面、個々のがん細胞への適合性は完璧ではありませんでした。
一方、ネオアンチゲン(新生抗原)とは、患者様のがん細胞の遺伝子変異によって生じた、その人だけのオリジナルの抗原です。
共通抗原ワクチンとネオアンチゲンワクチンの比較
| 比較項目 | 共通抗原ワクチン(WT1など) | ネオアンチゲンワクチン |
|---|---|---|
| ターゲット | 多くのがん患者に共通する目印。 | 個人の遺伝子変異由来の固有の目印。 |
| 製造方法 | 既製品(すぐに開始可能)。 | 完全オーダーメイド(解析・製造に数週間〜数ヶ月)。 |
| 特異性・効果 | 広範囲に使えるが、反応には個人差がある。 | がん細胞への特異性が極めて高く、強い免疫反応が期待できる。 |
ネオアンチゲンワクチン療法では、まず患者様のがん組織と正常な血液の遺伝子を次世代シーケンサーで解析し、比較します。
そこで見つかった遺伝子変異の中から、免疫細胞が特に強く反応しそうな変異(ネオアンチゲン)をAI解析などで予測し、それを元に完全にオーダーメイドのワクチンを製造します。
自分のがんだけが持つ特徴を狙い撃ちにするため、理論的に非常に強力な治療法です。
正常細胞を攻撃しない高い特異性
共通抗原は、わずかながら正常な細胞にも存在している場合があり、理論上は副作用のリスクがゼロではありません。
しかし、ネオアンチゲンは正常な細胞には絶対に存在しない、がん細胞特有の変異タンパク質です。
そのため、免疫細胞が正常細胞を誤って攻撃するリスクが極めて低く、高い安全性が確保されています。
この高い特異性により、強力な免疫反応を引き起こしても、自己免疫疾患のような副作用が起こりにくいという利点があります。
したがって、標準治療後の弱った体であっても、安全性を保ちながら最大限の攻撃力を引き出すことができる、理想的なターゲットといえます。
樹状細胞ワクチンとの組み合わせ
ネオアンチゲンは単独で投与されることもありますが、患者様の血液から採取した樹状細胞と組み合わせることで、さらに効果を高めることができます。樹状細胞にネオアンチゲンを取り込ませてから体内に戻すことで、確実のがんの情報をT細胞に伝達させることができます。
この手法は手間と時間がかかりますが、患者様自身の細胞と、自身のがん情報を掛け合わせるため、体内での拒絶反応などが少なく、非常に理にかなった治療法です。
標準治療の効果が薄れた後、残された時間を有意義に使うための、質と精度の高い医療として検討されるべき選択肢です。
治療を開始するための準備と医療機関の選び方
治療開始にあたっては、自由診療と治験の違いを理解し、セカンドオピニオンを活用して信頼できる専門機関を選ぶことが重要です。
費用や期間を含めた具体的な計画を立てることで、安心して治療に臨むことができます。
自由診療と臨床試験の区別
まず理解しておくべきは、多くのがんワクチン療法は現在、健康保険が適用されない「自由診療」であるという点です。全額自己負担となるため、経済的な計画が必要です。
一方で、大学病院やがんセンターなどでは、新しいワクチンの効果を確かめる「治験(臨床試験)」が行われている場合があります。
治験の条件に合致すれば、治療費の負担が軽減されることもあります。
情報を探す際は、国立がん研究センターの「がん情報サービス」などで公的な臨床試験情報を検索すると同時に、自由診療を行っているクリニックの情報も収集する必要があります。
自由診療のクリニックを選ぶ際は、免疫療法を専門とし、細胞加工施設(CPC)を併設しているか、提携しているかなど、ハード面とソフト面の充実度を確認することが大切です。
セカンドオピニオンの効果的な活用法
現在治療を受けている主治医に内緒で別の治療を始めることは推奨されません。これまでの治療経過や画像データ、血液検査の結果などは、次の治療戦略を立てる上で貴重な情報源です。
勇気を出して「免疫療法について話を聞いてみたいので、紹介状やデータをお願いしたい」と伝え、セカンドオピニオンとして免疫療法の専門医を受診しましょう。
初診時に準備しておくとスムーズなもの
- 診療情報提供書(紹介状)には、これまでの治療経過、使用した薬剤、病理診断結果などが記載されています。
- 画像データは、CT、MRI、PET検査などのCD-ROMデータが有用で、経過がわかる過去のものもあると理想的です。
- 直近の血液検査の結果用紙は、現在の体の状態や免疫機能の目安を知るために必要です。
- 現在服用しているすべての薬がわかるお薬手帳も持参しましょう。
良心的な医師であれば、標準治療後の選択肢を探す患者様の気持ちを尊重し、必要な資料を提供してくれます。
また、併用療法を行う場合、標準治療(例えば維持療法中の抗がん剤など)と並行して行うこともあるため、主治医と免疫療法医の連携が取れることが理想的です。
治療費と期間の目安を把握する
自由診療の場合、治療費は医療機関によって大きく異なりますが、一般的には1クール(5〜6回の投与)で150万円〜300万円程度かかることが多いです。
ネオアンチゲンワクチンの場合、遺伝子解析費用やオーダーメイド製造費用が加算されるため、さらに高額になる傾向があります。
また、治療期間は数ヶ月に及ぶことが多く、採血や投与のために定期的な通院が必要です。自宅からの通いやすさや、緊急時の対応体制なども含めて検討しましょう。
初診時には、治療の総額、追加費用の有無、期待される効果とリスクについて、納得いくまで説明を受けることが重要です。
見積書を提示してもらい、家族と十分に話し合ってから決定することをお勧めします。
Q&A
- 副作用はどの程度ありますか?
-
一般的にがんワクチン療法は重篤な副作用が少ない治療法です。最も多く見られるのは、注射部位の赤み、腫れ、痒み、または一過性の発熱や倦怠感です。
これらは免疫が活性化している証拠でもあり、通常は数日で治まります。
ただし、免疫チェックポイント阻害薬を併用する場合は、間質性肺炎や大腸炎、甲状腺機能障害などの免疫関連有害事象(irAE)が現れる可能性があるため、専門医による慎重な管理が必要です。
- 治療を開始するタイミングはいつが良いですか?
-
免疫療法は、免疫細胞がまだ元気なうちに開始する方が高い効果が期待できます。
そのため、「標準治療が完全に終わってから」や「末期になってから」と考えるのではなく、標準治療の効果に陰りが見え始めた段階、あるいは副作用で標準治療の継続が難しくなった段階で、早めに相談することが望ましいです。
早期に検討を開始することで、残された体力を有効に活用し、治療の選択肢を広げることができます。
- どのがんでも受けられますか?
-
がんワクチン療法は、固形がん(胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、膵臓がんなど)を中心に、幅広いがん種で実施されています。
ただし、一部の血液がん(白血病など)では適応が異なる場合や、特定の自己免疫疾患をお持ちの方には慎重な判断が求められる場合があります。
また、ネオアンチゲンワクチンの場合は、遺伝子解析の結果、標的となる変異が見つからない場合もあります。
まずは受診して適応の有無を確認することが必要です。
- 現在抗がん剤治療中ですが併用は可能ですか?
-
はい、可能です。むしろ、記事内で解説したように、抗がん剤や放射線治療と併用することで相乗効果が期待できるケースが多くあります。
ただし、抗がん剤の種類や量によっては一時的に免疫機能が低下することもあるため、ワクチンの投与スケジュール(抗がん剤投与の休薬期間に打つなど)を調整する必要があります。
主治医と連携しながら計画を立てることが重要です。
- 通院頻度はどれくらいですか?
-
治療の種類やプロトコルによりますが、一般的には2週間に1回程度のペースで、計5回から6回を1クールとして実施する医療機関が多いです。
1回の治療時間は、ワクチンの皮内注射のみであれば短時間で終わりますが、樹状細胞ワクチンの成分採血(アフェレーシス)を行う日や、点滴を併用する場合は数時間を要することもあります。
体調に合わせて無理のないスケジュールを組むことが可能です。
参考文献
ZHAO, Jing, et al. Safety and efficacy of therapeutic cancer vaccines alone or in combination with immune checkpoint inhibitors in cancer treatment. Frontiers in pharmacology, 2019, 10: 1184.
C. AZOURY, Said; M. STRAUGHAN, David; SHUKLA, Vivek. Immune checkpoint inhibitors for cancer therapy: clinical efficacy and safety. Current cancer drug targets, 2015, 15.6: 452-462.
MOUGEL, Alice; TERME, Magali; TANCHOT, Corinne. Therapeutic cancer vaccine and combinations with antiangiogenic therapies and immune checkpoint blockade. Frontiers in immunology, 2019, 10: 467.
WU, Yingcheng, et al. The clinical value of combination of immune checkpoint inhibitors in cancer patients: a meta‐analysis of efficacy and safety. International Journal of Cancer, 2017, 141.12: 2562-2570.
LIAO, Juan-Yan; ZHANG, Shuang. Safety and efficacy of personalized cancer vaccines in combination with immune checkpoint inhibitors in cancer treatment. Frontiers in Oncology, 2021, 11: 663264.
KLEPONIS, Jennifer; SKELTON, Richard; ZHENG, Lei. Fueling the engine and releasing the break: combinational therapy of cancer vaccines and immune checkpoint inhibitors. Cancer biology & medicine, 2015, 12.3: 201-208.
ZANOTTA, Serena, et al. Enhancing dendritic cell cancer vaccination: the synergy of immune checkpoint inhibitors in combined therapies. International Journal of Molecular Sciences, 2024, 25.14: 7509.
LAI, Xiulan; FRIEDMAN, Avner. Combination therapy of cancer with cancer vaccine and immune checkpoint inhibitors: A mathematical model. PLoS One, 2017, 12.5: e0178479.
CHYUAN, I.-Tsu; CHU, Ching-Liang; HSU, Ping-Ning. Targeting the tumor microenvironment for improving therapeutic effectiveness in cancer immunotherapy: focusing on immune checkpoint inhibitors and combination therapies. Cancers, 2021, 13.6: 1188.
KYI, Chrisann; POSTOW, Michael A. Immune checkpoint inhibitor combinations in solid tumors: opportunities and challenges. Immunotherapy, 2016, 8.7: 821-837.